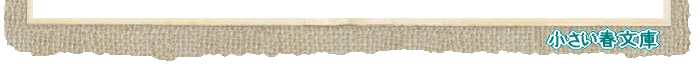ハヤテは食べることが大好きで、とても人懐っこい体の大きなシェパード。
* * * * * * * * * * * * * * *
ともだち
はだい悠
* * * * * * * * * * * * * * *
ハヤテは食べることが大好きで、とても人懐っこい体の大きなシェパード。
それに、まだ、誰にも認められていないが、とっても賢い犬。
この家に来たときは、ぬいぐるみのように小さく可愛かったので、家族全員から宝物のように大切され、疲れて眠くなるまで遊んでもらえた。でも今は、邪魔者扱い、少々もてあまし気味、一日中家から離れた檻のような小屋の中でひとりぼっち、誰も遊んでくれない。
とにかく、ハヤテは食べることが好きなので、みるみる大きくなって、一年あまりで、現在の大きさになった。立ちあがると大人の女性の背丈ほどにもなるので、家の者も、相手にするのがなんとなく面倒になったわけだ。
ハヤテがみんなから煙たがれるようになってから、もう二年近くになる。家の者が、ハヤテに会いにくるのは、朝と夕方の二回。ドッグフードを持ってくるときだけ、それも、挨拶程度に無愛想に、ヨウとか、オイとか、と声をかけてくれるだけで、ハヤテが食べてる間にすぐ居なくなってしまう。ハヤテは食べることに夢中でそのことに気づかない。だから、相手にしてもらったという気持ちはしない。
ハヤテはよく食べて大きいだけじゃなく、よく吠えるので、家のものは、とにかく扱いに困っていた。
やたらと吠えるわけではない。家に誰かが訪ねてきたときに、それを知らせるときと、見知らぬものを家の周囲に発見したとき、それに、遠く離れた、まだ見ぬ犬と吠え合って情報交換するときだけ。
でも、なにせ、体に合わせるように声も大きい。低音で窓ガラスを振るわせるくらいに迫力がある。だから、家のものは近所に迷惑がかかっているのではないかと気が気でならなかった。
そんなわけで、ハヤテの一日は、ほとんどがふて寝しているか、力なく横たわっているか、寂しさに耐え切れずにクゥクゥとうなっているだけだった。
クゥクゥと、うなると不思議と寂しさがまぎれることに、ハヤテは気づいていた。
ある日。親戚の女の子がふたりやってきた。家の者が、
「ハヤテ、トモダチが遊びにきたよ。」
と言って紹介してくれた。女の子達は十歳のマキと八歳のユキの姉妹。
ハヤテは檻から出された。
うれしそうに走る回るハヤテに、女の子達はさっそく命令を下した。
「ハヤテ、とまれ。」
「ストップ、ストップ。ステイ、ステイ。」
「おすわり、おすわり。」
と、女の子達は,日本語と英語で交互に我先を争うように叫んだ。
それは、もし、ハヤテが自分たちの言うことを聞いてくれたら、ハヤテを自分たちが引き取って、可愛がってあげても良いようなことを、家の者と事前に話し合っていたからだった。
だが、ハヤテは女の子達の命令に従うような気配はまったく見せなかった。あいかわらず女の子達の周りを走り回ったり、命令と関係なく臥せってみたり、じゃれて飛びつこうとしたりするだけだった。
それでも、女の子達は、くり返しくり返し命令を下した。
たまに、ハヤテが言うことを聞くと、女の子達は満足したように、頬を緩めるが、またすぐ、言うことを聞かなくなるので、いらだち始めた。
ハヤテにとって、自由に伸び伸びて走り回れるだけじゃなく、遊んでもらえるのも二年ぶりだったので、とにかくうれしくてうれしくてたまらなかった。ハヤテにとって、女の子の命令を聞く聞かないは二の次だった。それは遊びの一部に過ぎなかった。
だが、女の子達は、そうではなかった。真剣だった。いくら、調教の仕方が、テレビで見ただけのにわか仕立ての、稚拙で、的を得なかったものであったとはいえ、プライドがいたく傷つけられたような気がした。
女の子達は、相変わらず服従の意思を見せないハヤテに対して、ついに怒り出した。
「ストップ、ステイ、ステイ、ストップ。」
「とまれ、とまれ、ふせ、ふせ、ハヤテ、ふせ。」
「ハヤテ、ストップ、ハヤテ、ストップ、だめ、ちがうったら、なんどいったらわかるの。」
と矢継ぎ早に、ハヤテも混乱するくらいに命令を出し続けた。
二人の女の子はだんだん興奮してきてよく判らなくなってきていたのだ。そして、ついに、ハヤテを手でぶつようになった。
体を、ときには顔を。
だが、ハヤテは少しも変わらなかった。小さな女の子に怒鳴られたり,ぶたれたりしても少しも苦にならなかったからだけではなく。マキとユキが苛立ち大きな声で叫んでも、ハヤテにとっては、それは、雰囲気がさらにいちだんと、にぎやかになったような気がして、それも、自分がとった行動のせいで、そうなったとなれば、なおさらやめるわけにはいかなかったからだ。しかも、女の子の小さな手でぶたれたぐらいは、体の大きなハヤテにとっては強く触られたようなもので、それに、顔をぶたれたのも、なでられたような気がして、かえって気持ち良いくらいだったからだ。
三十分後、相変わらず自由にあっちこっちと走り回り、飛びつき、意味もなく伏せ、時たま指示に従うだけのハヤテに、マキとユキは「これで最後」と、言わんぱかりに、強く大きい声で命令を下した。
「ハヤテ、ストップ、良い、これがステイで、これがシッダウンよ。シッダウン、違うってば、ストップ、ステイ、うん、もう、ストップ、もう、止め、もう、おわり、ハウス、ハウス。」
「だめ、もう、あきらめよう。」
そう言ったきり、二人はハヤテに目をくれることもなく、家の中に入って行ってしまった。
残されたハヤテは何が起こったか判らずキョトンとするだけだった。
翌朝、二人の女の子は自分たちの家に帰るために、ドアをあけて出てきた。そして、ハヤテには、まったく目もくれずに車に乗り込もうとした。
昨夜、家の中でこんな話し合いがされたことを、ハヤテは知らない。
「ねえ、どうだった、ハヤテ、言うことを聞いた?」
すると、姉のマキが笑いをこらえながら言った。
「だめ、全然だめ.ちっとも言うこと聞いてくれない。あれじぁ仲良くなれない。」
妹のユキがそれに付け加えるように言った。
「ハヤテってさ、もしかしたらあんまり賢くないんじゃないの。」
家の者が答える。
「警察犬にもなるシェパードだからね。そんなことないと思うけど。」
「もしかして、バカ犬だったりして。」
マキがそう言うと、みんな笑顔になった。
目の前を通り過ぎる女の子達を見て、ハヤテは二人がこれからどこに行くのかなんとなく判った。
家の者がハヤテに言った。
「ハヤテ、ともだちが帰るよ。」
突然のように、寂しさや悲しさが体のあっちこっちから沸き起こってくるのを感じたハヤテは、全身から搾り取るやうな声で、ウオッウオッウオッウオッと、叫んだ。
車に乗り込んだミキが言った。
「と、も、だ、ち? 、、、、友達じゃないよ。」
マキが言った。
「ウオッウオッ、変な声、ちゃんと吠えられないのかしら。」
二人を乗せて走り出した車はあっというまに、ハヤテに目の前から消えてしまった。