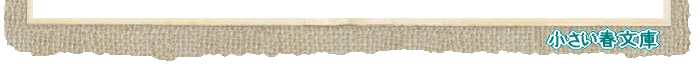はだい悠
* * * * * * * * * * *
もう一ヶ月近くになるだろうか。
人通りの少ない一本の道をへだてて、家の前にある集合住宅の広場から聞こえてくる、子供たちの遊び声を、康夫と清子が話題にするようになったのは。
十年前に一人息子を交通事故で亡くしてから、夫婦の会話は、年を追うごとに徐々に少なくなってきてはいたが、さらに、三ヶ月前、康夫の肝臓にガンが見つかってからは、まったくと言って良いほど、会話らしい会話はしなくなり、家の中は一日中沈んだ雰囲気になっていた。特に夕暮れ時の凍りつくような侘しさなは絶えがたいものがあった。
康夫は、平均寿命にはあと十年足りないが、七十年生きたのだからもう十分と思う反面、どうしても死への不安と寂しさは隠しきれなかった。
医者は、まだ中期だから、治療と療養次第で残りの人生を十分楽しく送ることができるから、心配ないと言ってくれたが、それが本当かどうか、それに中期なんてあまり聞いたことがない、もしかしたら本当は、と思うと、晴れ晴れとした気分になることは決してなかった。
妻の清子は、他人の苦しみを自分のことのように感じる傾向が強いため、どうしても夫のことを気にかけるあまり、自分から積極的に何事もなかったかのように話しかけることはできなかった。それで、家の中はますます沈んだものになっていくしか、仕方がなかったのである。
ところが、今からちょうど二ヶ月前あたりから、あの元気な子供たちのはしゃぎ声や叫び声が聞こえてくるようになってからは、その様相は徐々にではあったが変化して行った。
最初は二人とも話題にしなかった。でも、そのことをとても意識していることはお互いにわかっていた。
ある日の午後。清子が、なにげなく、しかも昨日までの話しの続きのように、うれしそうな表情で、最初に言った。
「今日は、とくに賑やかね。あれは、おにごっこ、そうよ、おにごっこよ」
「そうだ、あのはしゃぎかた、まちがいなくおにごっこだ。子供のころよく遊んだもんだよ」
と、康夫は天井のほうに目をやりながら笑みをうかべて言った。
その広場は、青い金網と植え込みで囲われており、さらに二人の家のまえには高いブロック塀がさえぎるため、家の中からはその様子を見ることはほとんどできない。だが、広場を取り囲むようにして立ち並ぶ四階建ての三棟のコンクリートの壁に反響するせいか、衰えかけている二人の耳でもはっきりと聞き取ることができた。まるで目の前で遊んでいるかのように。
とりわけ一人の女の子の、体全体からほとばしるような、強く、大きく、のびのぴとした声が印象的でいつまでも二人の耳に残っていた。
そのことを清子がまっさきに話題にした。
「なんて大きな声の女の子なんでしょう。まだ小さいはずなのに」
康夫がそれにすぐ反応して言った。
「ユイやカズの小さいときと比べてどうだろう、五歳ぐらいかな?」
「いえ、あの感じは、まだ三歳か、四歳じゃない。なんにでも好奇心があるって感じでしょう。なんて楽しそうなんでしょう。ほんとうに元気だこと」
「今、ちょうど、遊びに目覚めている感じだね」
「一番可愛いざかりね」
「あんなに元気に、大きい声を出せるなんて、きっと生きてることが楽しくて楽しくてしょうがないんだろうね。なんだかこっちまで元気になってくるような気がするよ」
「将来が楽しみね。あんなにはっきりと声が出るなら、歌手か、アナウンサーか。それともわたしたちのよう先生になるのも良いんじゃない。きっと生徒に慕われるわ」
「あんなに元気だと、いるだけで周りが明るくなってほんとうに助かるんだよね。とても貴重な存在なんだよね」
「いるだけで十分なのよね」
「とにかく楽しみだね。あっ、ところで、今日の夕ご飯はなんだろう」
「えっ、あっ、そう、久しぶりにあなたの大好きなてんぷらにしようと思っているの」
「なんだか気持の良い空腹がしてね。どういうわけか最近、以前のように食欲が出てきてるんだよ。不思議なことに」
こんなぐあいに、子供たちのことを話題にしたあとは、会話は続くのだった。
そんなある日の午後。二人がいつものように、それとなく広場の様子に耳を傾けていると、清子がうれしそうな表情で話しかけた。
「ねえ、いま、聞いた。あの子ミクちゃんって言うんだね」
「えっ、ミキじゃない、わたしにはミキと聞こえたよ」
「いえ、ミクです。きっと未来と書いてミクと読むのね」
「違うね、美しい希と書いてミキと読むんだよ」
と、結婚以来喧嘩らしい喧嘩をしたことがない康夫だったが、このときばかりはむきになった。清子が続ける。
「夕べ、あなたがお風呂に入っているとき、子供たちが花火大会をやっていたわ。みんな楽しそうだった。ワイワイ、キャアキャアって。ミクちゃんなんてとくにね。星空に届きそうなくらいに大声を出して喜んでいたわ。」
「子供のころってあれで十分なんだよ。なにもお金をかけた大げさなものじゃなくても良いんだよ。わたしも思いだすよ、、家族みんなで集まってやった花火大会、こじんまりとしたものだったけどね。とても楽しかった。良い思い出だよ」
清子がさらに続けて言う。
「わたしね、今日、ついに見たの、ミクちゃんを。住宅の横を通りかかったら、広場の様子が賑やかだったから、なんとなくそっちのほうに目をやりながらゆっくりと歩いていたら、ミクちゃんのあの元気な声が聞こえてきたの、それで急いでその声のするほうを見ると、小さな女の子がいたの、目の前のおかあさんらしき人に必死になにかを訴えながらね。声はミクちゃんだから、あの子がミクちゃんなのよ。髪を両耳の上でチョコンとゆわえて、顔はまん丸でぽっちゃりして、太陽と言うより、お月さんのような、とってもおだやかな笑顔をしてたわ。」
そして、こんなこともあった。
いつもと違う様子に二人は耳をそばだてている。康夫が驚いたように言う。
「なにが起こっているんだろう。おかえり、おかえりって、なんども言ってるようだが。こんどはバイバイって言っている」
清子は、立ちあがって外の様子を見ようとする。だが見ることはできないので、すぐあきらめ、聞き耳を立てるように小首をかしげた。そして楽しそうに笑みを浮かべて言った。
「あの子、ミキちゃんね、道を通る子供たちに、子供と言うより小学生のお兄ちゃんたちにね、声をかけているのよ。バイバイ、バイバイって、なんども、返ってくるまでね。いや、返って来ても、また言ってる。ミキちゃんにとって遊びなのね、声をかけることがきっと楽しくて楽しくてしょうがないのね。おにいちゃんたちも迷惑そうにしているけど、ちゃんと返しているから、たぶん、照れているのよね、ほんとうはきっと嬉しいのね。あっ、ずっと言ってるもんだから、おにいちゃんたち逃げるようにして走って帰って行っちゃった。それでもまだ言っている。ほんとうに天真爛漫ね」
「天衣は無縫か」
康夫が言い終わっても、二人の顔からは、にこやかな笑みはなかなか消えなかった。
そして、今日も、子供たちが元気に遊ぶ声が聞こえてくる。清子がうれしそうに話しかける。
「ねえ、聞いた、いま、もういいかいって言ったよね。ミキちゃん。かくれんぼをやっているのね。もう誰もやらなくなって、すたれたのかと思った。最近全然見ていなかったからね。まだ続いていたんだ。子供のころよく遊んだものね」
「よく遊んだよ。色んな遊びがあったからね。かんけり、いしけり、おしくらまんじゅう、うまとび、はないちもんめ、それから、、、、じんとり、たからとり、めんこ、ビーだま、ベえごま、わたしなんか女の子がよくやる、おはじきや、おてだまや、あやとりもやっていたからね」
と、康夫が生き生きと話した。清子が話題を変える。
「そういえば、あの娘、ミキちゃん。昼前泣いていたっけ。ビィェビィェってね。最近あういう泣き方をする子をみたことがなかったから、とても懐かしく感じて、なんかほっとした感じだった。それにしても、昔よく見た、道路に座り込んで足をばたばたさせて泣いている子や、母親に取りすがって泣いている子なんて、近頃ほんとうに見たことないね。どうしてかしらね」
康夫が思い出に浸るようにゆっくりと話し始める。
「わたしはよく泣かされてたっけ。兄弟にいじめられてね。子供のころはよく感情を爆発させていたもんで声を張り上げて、思いっきり泣いたもんだよ。顔をぐしゃぐしゃにして、ギャアギャアってね。そのあと、母親や兄弟みんなになだめられたりして、もとに戻るんだけどね。妙に懐かしいね」
そのとき、清子がなにげなく話題を変えた。
「あれはいつでしたっけ」
「なにが?」
「検査」
「なんの?」
「精密検査」
「わたしのガンの検査だろう。そんなに気を使ってくれなくても。こんどの月曜日が検査で、結果がわかるのは火曜日。そんなに気を病むことはないさ。もうどんな結果がでようが、覚悟はできているさ。もうなにが起ころうが、最後まであの子のように元気に生き抜いてやろうと思っている」
精密検査の日。家に帰ってきた康夫は珍しく、清子が夕食の準備をする食堂に入り、なにげなく清子にたずねた。
「最近、あの娘の声を聞いてないような気がするんだけど」
「天気が悪かったから、それに、もしかしたら、夏休みだから親戚やどっかに行ってんじゃないの」
「今日はカレーですか。これは昔のカレーじゃないですか.新婚当時によく食べた。なつかしいなあ。最後の晩餐ってことですか」
「そんな意味じゃないですよ。昔を思い出してね。たぶん好きじゃないかと思って」
「正直に言うと、リョウ子さんが、よく作ってくれた今風のカレー、あれはあれでおいしいんだけど、でもほんとうは、このように豚肉やジャガイモが入ったカレーが、いちばん好きなんだ」
「やっぱり、そうだったでしょう」
「なんか昔に戻ったような気がする、なにもかも若々しく美しく夢と希望に満ちていた昔にね」
「わたしはこんなにも変わってしまったけどね」
「ちっとも変わってやしないさ」
「気持はね、でも顔はこんなに見る影もなくなって」
「そんなことないよ。わたしはいつも思ってるんだ。いまは年寄りメイクしているだけなんだって。頭の中では、いつも若くて美しいあなたの笑顔を思い描いているよ」
「そう言ってくれると、とても嬉しい。わたしもこれからはそうします」
名前を呼ばれて診察室に入ろうとしたとき、康夫は,日頃お世話になっている看護婦長とすれ違ったが、彼女が涙ぐんでるのを見ていやな予感がした。きっと、わたしのの検査結果を見て、余命なん日もないと判って、同情の気持から思わずそうなったに違いないと思った。
医師はほんの一瞬じっと見たあと、少し笑みを浮かべて言った。
「いやあ、不思議です。こんなこともあるんですかね。なんども確認したんですが、病巣が進行しているどころか、良くなっているようにも見えるんですよ。この前の写真と比べてみても、誤診なんかじゃなかったことがわかるんですが。結論を言いましょう。率直に言って、もう大丈夫です。とにかくいまの状態を続けて行けば、なにも問題はありません。おそらく平均寿命はもとより、死ぬまで健康に生きられますよ」
康夫は思わず付き添ってきた清子を見た。二人は青春の輝きを取り戻したかのような晴れやかな表情で、お互いのひとみの中に希望の光を確認しあった。そして康夫はにこやかな表情で医師に言った。
「いや、さきほど看護婦長さんが涙ぐんでるのを見たもので、てっきりわたしのことかと思い、もうだめなのかと思っていました」
医師が急に表情を曇らせて言った。
「そうでしたか。それはですね、、、、ちょうど、今朝方、たいへん悲しい出来事があったものですから。いろいろな患者さんがおりましてね。あなたのように奇跡的に回復なさるかたもいれば、突然発病して、どんな手当の甲斐もなく、亡くなられる方も居るんですよ。ほんとうに残念で悲しいことです。わたしたちもできるかぎりのことはしたんですが、どうにもなりませんでした。進歩している現代医学と言われても、まだまだわからないことがあるんです。なんとか助けてあげたかったんですが、まだ三歳になったばかりですから、ほんとうに悔しいです。良く取り上げられます、急性の白血病というやつです。なにしろ進行が早すぎました。彼女たちは助けてあげようと必死でしたから、それで」
「あっ、それは、たいへんお気の毒なことでした」
康夫と清子が挨拶してかえろうとしたとき、さきほどの看護婦長がドアから入ってきて言った。
「亡くなられたお嬢さんのおかあさんが、先生にということで、おみえなってます」
「わたしがこんなに元気になったのは、きっとあの娘のおかげだな。きょうかえったらさっそくあの娘の顔を見に行こう」
と、康夫は穏やかな表情で独り言のように言いながら清子のほうを見ると、清子は暗い表情でささやくように言った。
「いまの人、ミキちゃんのおかあさんよ。広場でいつも遊んでいる、声の大きい、あのミキちゃんの」
二人は青春の輝きが消えうせた表情でじっと見つめあった。そして、ついさきほどお互いの瞳の中に確認しあったばかりの希望の光が鉛色の陰に覆われていくのをハッキリとみてとった。
「あんなに良い子でしたから、きっと天国に召されて、ずっと、元気に、おにごっこやかくれんぼをしながら遊んでいると思いますよ。永遠にね」
「みなさんがそう言ってくれて、励ましてくれて、とても、なんてお礼をいったら良いか、でも、いまは、とてもつらくて、 」
康夫と清子はよろめきながらもなんとか二人で支え会いあって診察室を出た。
次のような言葉を耳に残しながら。
「ミキはどこにも行ってないんです。でもどこにもいないんです」
そして康夫はつぶやくように言った。
「きっと、連れ戻されたんだね、、、、あんな娘だったら、だれもが傍に置きたいからね、、、、」