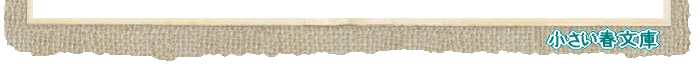青い精霊の森から(1部)
はだい悠
* * *
遥か昔、私たちの祖先は森の中で人間になろうとしていた。
だが、彼らを取り囲む自然は常に厳しいものであった。
しかし、かといって、それほど耐え切れないものではなかっ
たはずだ。
原始の生命力を持ってすれば、風雨や、暑さ寒さにはそれな
りに対処できたはずだ。
ときおり、猛獣などに襲われることもあったろうが、結果的
に誰かが犠牲になればそれで済むことだったろう。
そのうち何度かくり返しているうちに、知恵もついて戦うこ
とも出来たはずだ。
また、まれには、突然の自然災害に遭遇することもあったろ
うが、その場を逃れて別のところに移れば、それで解決するこ
とだったに違いない。
それらのことはとてつもない恐怖であったに違いないが、今
日、我われが考えるほど悲劇的なことではなかったはずだ。
時間の経過とともにある程度は忘れ去られるようなものだっ
たに違いない。
それよりも周囲の自然からは、食べ物などではるかに多くの
恩恵を受けていたはずで、むしろ感謝の気持ちを捧げるべき対
象となっていたに違いない。
そしてなん世代もかけて色んなことを身に付けながら、我わ
れの祖先は人間性を育み、精霊の力を借りて徐々に人間になっ
ていったに違いない。
このとき、育まれていった人間性とは、身近なもの同士が、
お互いに相手の声や動作をよりどころにして、いっしょに狩を
したり、物を作ったり、食べ物を食べたり、遊んだりすること
から生まれてきたものに違いなく、それは単なる仲間のことを
考え、そして思いやるということだけではなく、相手の話し方
の違いや、表情の微妙な変化から、複雑で豊かな相手の気持ち
を理解できるようになったに違いない。
そのことは身近なもの同士を、さらに近づけさせて、より信
頼しあうようにさせ、ますます穏やかで親密な関係にさせて行
ったに違いない。
そしてそれは、まだあまり顔見知りでない多くの人たちと仲
良くやっていくことに役立つものであったに違いない。
ということは、精霊とは、穏やかで創造的で平和的なものだ
ったということになるが。
現在、われわれの周りには、かつて我われの祖先を養い育て
たような自然はない。
あるのは人間を威圧するような高層ビルや巨大建築物、高速
で人や物を運搬する車や飛行機、瞬時に世界中の誰とでも顔を
合わせることもなく話が出来る通信機器、自分とは直接関係の
ない出来事を知ることが出来るテレビなどのマスメディア、そ
してその結果として洪水のように押し寄せる膨大な量の情報と
商品、それにめまぐるしく移り変わる流行の数々、さらには、
そこから外れたら、誰であってもまともな生活がおぼつかなく
なるような緻密で効率の良い巨大な社会システムである。
その中でほとんどの人間は適応して生きている。
こざっぱりとした服装でわき目も降らずに舗道を歩き、こじ
んまりとした表情で行列を作っては電車に乗り、物分りがよさ
そうな表情で見知らぬ人たちと話しをしては、顔色も変えずに
世界中の悲惨な出来事を知識のように受け入れ、何事にも要領
がよく、規則正しさや礼儀正しさに誇りとプライドを持ちなが
らである。
それこそまさに現代の精霊の成せる業ではないのか。
では、その精霊とは。
うなりを上げる巨大重機の鋼鉄の精霊であり、
膨大なエネルギーを生み出す爆発の精霊であり、
新幹線やジェット機のスピードの精霊であり、
通信機器によって人と人とが無限につながる連鎖の精霊であ
り、
溢れるように押し寄せる商品や情報による波動の精霊であり
、
移り変わる流行による加速度の精霊であり、
テレビなどの視覚情報による膨張する空間の精霊であり、
そしてすべての人と人、物と物とを分けよう分けようとする
分離の精霊である。
だが、これはあくまでも社会に適応して生きているものたち
にとっては精霊となるであろうが、何らかの理由で、適応でき
ないもの、たとえば、人より不器用であったり要領が悪かった
りするもの、それに偏った性格が災いして、周りの人と協調す
ることが出来ないものにとっては、果たして己をよき方向へと
導くような精霊となることができるだろうか。
その結果、おそらく彼らは、理屈には合わない破壊や暴力、
そして陰鬱な悪へと駆り立てられるだけだろう。
しかし、もしこれが、周囲の大人たちが望むように行動でき
ない重大の若者ならどうだろう。
これは、それまで子供としてはふさわしくないような過酷な
体験をしたために、社会や大人たちに対して反感を抱いている
若者のことだけを言っているのではない。
それまでは周囲の大人たちのいうことを素直に聞いて、社会
や自分のことをほとんど意識しないで生きてきたのだったが、
なにかのきっかけで、社会や自分のことを強く意識するように
なった若者にも言えることなのだ。
そのきっかけとなるのは人によってさまざまであるが、決し
て特別なことではない、ほとんどが日常的なことである。
自分の性格や肉体のことが急に気になり始め、それを他人と
比較するようになったために、友達だけでなく家族とも、それ
までのような関係を保てなくなったり、さらには自分が眼だな
いからではなく逆に目立つことが気になったり、勉強がが出来
ないからではなく、むしろ勉強が出来すぎることが気になった
り、大人に反抗的ではなく、今まであまりにも従順で良い子で
あることに気がついたりすることによってである。
また、どの若者がそうなるかはあらかじめ予測は出来ない、
ある者にとっては必然的であるが、あるものにとっては偶然的
であったりして、宿命的というべきか、あるいはちょっとよそ
見しているうちに、皆からそれてしまったというべきか。
そして彼らは皆いちように希望や目標を持てないでいる。
しかも決して表には現さないが、漠然と自分に自信がもてな
いということで不安でいっぱいである。
このとき現代の精霊は確実に悪霊となって彼らに襲い掛かる
に違いない。
そうなるとなんら防御の手段を持っていない若者たちは、例
外なく地獄の季節を走り抜けなければならないだろう。
繁華街から少し外れたところに人の出入りがないビルがある
。その二階の一室に髪を金色に染めた二人の少年が眠っている
。カギをこじ開け無断で住んでいるのだ。部屋の中にはベッド
の代わりとなるダンボール以外は何もない。
東の窓には、隣のビルの壁が立ちふさがり、北の窓には高速
道路の高架が覗いており、車の音がひと塊の騒音となってかす
かに響いている。
二人は着ていたTシャツを下に敷き、上半身は裸ではある。
外は六月の強い日差しが照っているが、彼らの表情は眠りの精
に征服されたかのように涼しげで穏やかである。やや赤みがか
った透き通るような肌は、どんな悪条件のなかでも行き続ける
植物のようにみずみずしく、薄暗く殺風景な部屋のなかでは、
黄金のような輝きを放っている。
それは、彼らが、いまを、どのような悪意に満ちた考えを持
って生きていようが、それらさえも無意味にしてしまいそうな
勢いで、肉体だけはひたむきに成熟していきながら、日々その
外見を変化させている。
その肉体の純粋な営みを思うと、彼らの多少の犯罪にも眼をつ
ぶりたくなる。
普段二人は、夕方になると起き出し、繁華街に出かけ、仲間
と合流してたむろし、彷徨いながら遊び暴れ、戦っては逃げま
わり、そして、必要に応じてエサを採取し、ときにはエモノを
狩り、やがて太陽が昇り、町が昼間の賑わいを見せ始めるころ
、へとへとに疲れた体を休めるために、再びここに戻ってるの
である。
二人はお互いをショウとトキュウと呼び合った。
ショウは翔平のショウであるが、トキュウはショウが名づけ
たもので、久作のキュウに”ト”を付けたのであるが、その意味
するところは久作には判らなかった。でも悪気はなさそうだっ
たのでまったく気にはならなかった。年齢についてはお互いに
中学生ではないことを感じてはいたが、正確には知らなかった
。というよりもお互いに知ろうとはしなかった。
だからそれ以外のことは何も知らなかった。なぜなら二人に
とっては、過去はそこの抜けたスニーカーのように不恰好で無
意味なものであり、今現在、関わっていることだけが、カッコ
よく、意味があり、生きているすべてだったからである。
二ヶ月前、トキュウは学校に行くのを止めた。
簡単に言えば面白くなくなったからであったが、本当の理由は
、周囲の仲間がなにを考えているのか突然判らなくなったから
である。しかし、学校が面白くないからといって、自分の家が
面白いというわけではなかった。同じころ同様に、家も面白く
なくなった。
トキュウの家は特別に貧しくもなく豊かでもなく平穏であり
きたりだった。家族もそれ以前と少しも変らなかった。だから
何らかの具体的な不満を感じたわけではなかった。
でも、なぜか、それまでのように気軽に接することが出来な
くなっていた。そこでトキュウはなんとなく家にいずらくなっ
た。そして頻繁に町に出るようになった。
町にはトキュウ同じような年ころの男女が昼よるとなく溢れ
ていた。トキュウの足は自然と彼ら若者が出入りしそうな場所
に向かっていた。彼らと同じ種であることを本能的に嗅ぎ取っ
ていたからである。
町はいつも賑やかである。おびただしい人間と、おびただし
い人工の光と音に溢れ、華やかである。そして人間を圧倒し、
挑発し、変容させる。
若者は様ざまである。自分の肉体を進んで傷つけたり染めた
りするもの、広場や路上でダンスやスポーツに夢中になるもの
、漫画や音楽に子供のように熱中するもの、異性だけでもなく
同姓にも特別の興味を示すもの、分不相応な大金を持って遊び
ほうけているもの、熱帯地方の鳥や魚のように化粧し着飾るも
の、みんな風景の一部となって熱烈に、そしてみんな夢見るよ
うに自分を主張していた。
トキュウにとって、彼らはみな自由でのびのびと生きている
ように見えた。ちょっぴりうらやましさを感じるほど立った。
だがどのひとつにもなれなかった。なぜなら、それらはみんな
以前からあったものであり、人に知られているものであり、そ
して古臭いものだったからである。自分が彼らと同じことをや
ることは、真似である屈辱的なことだと感じていたからである
。
そういう彼らの姿は確かにトキュウの眼には映ったが、決し
て心には映らなかった。このことは町の華やかな風景にもいえ
ることである。写真のように眼には映るが決して心には映らな
かった。
人はだれでも夢見ることができなければ心は凍結するしかな
い。
トキュウにとって学校や家族だけではなく、町もわからない
ものになった。そしてトキュウにとって、世界は徐々に不透明
とを増していき、混沌となった。
しかし、トキュウは町に行くのを止めなかった。なぜなら、
ほかにいく場所がどこにもなかったから。それにこのまま家に
閉じこもることは、自分がこの世界から抹殺されてしまうよう
な気がしたからである。そう感じさせたのは、ひとつの肉体と
してのひとつの純粋な生命体としてのトキュウのプライドであ
った。
トキュウま戸惑いながらも、惰性で遊び、無感情に人とすれ
違い、孤独にそして不安げに町をさまよった。その姿はまさに
、群れからはぐれてしまった小型草食動物のそれであり、その
戸惑いや無感情は、いつ大型の肉食動物に襲われるかもしれな
いという、不安と心細さと同じものである。
来る日の来る日もトキュウは、町に出かけ群集にまぎれ、習
慣のように遊び反射的にさまよった。しかし町を少しも変らな
かった。
《町は自分から意味を見い出すものだけしか受け入れない》
ということを、まだ独りで生きていく知恵もない動物のような
トキュウに気づくはずもなかった。群集のなかの無名な一人に
過ぎないトキュウは、一本の街路樹や、一個の舗道の敷石や、
一個の広告塔と同じように、町の風景を構成する一要素に限り
なく近づきつつあった。
まだ喧騒の続くある日の夜更け、普段気にも留めなかった光
景がふと眼に入り、トキュウは足を止めた。駅舎の壁が低い窓
のように切り抜かれ、そこからホーム上に居る人々の足元が映
画のスクリーンを見ているかのように見えるのである。かがん
でも膝までしか見えなかったが、トキュウの眼はなぜか釘付け
となった。音もなく電車が入ってきた、ドアが開き、寂しそう
に四本の脚しかなかったホームは、急に様ざまな足取りで溢れ
、賑やかになった。急ぐ女の足取り、だらしない男の足取り、
弾むような足取り、疲れたような足取り。トキュウは人々の足
取りを見ながら、人々の表情を見ているような気がしていた。
ドアが閉まると電車は出て行った。そしてホームはふたたび静
かになった。トキュウは舗道にかかんだまま次の電車の様子を
好奇心の強い子供のように無心に眺め続けた。そして五つめの
電車がホームから出て行ったとき、後ろのほうから声をかける
ものがいた。
「おい、何やってんだこんなところで?」
振り向くと制服に身を包んだひとりの若い警察官が見下ろすよ
うに立っていた。
トキュウは別に歩行者のじゃまをしているわけでもないと思
い無視することにした。しかし警察官を立ち去らなかった。
「おい、おまえ、ノゾキやってたろう」
「ちがうよ」
「さっきからずっとなに見てた? お前まだ学生だろう。とん
でもない奴だな。子供のくせに、こんな夜更けに出歩いている
んじゃないよ」
その乱暴な言い方に、トキュウは押しつぶされそうになった
。警察官はなおも続けた。
「おい、ヘンタイ、へんたい野郎、ちょっと交番に来るか?」
トキュウは激しく恐れ動揺した。そしてその場を離れた。その
姿はまるで、せっかくたどり着いた水場から、肉食動物に脅さ
れてすごすご逃げ出す草食動物と少しも変らなかった。歩きな
がらトキュウは、
《何も悪いことはしてない》
と思うと、動いていた時計が止まってしまったような気配とと
もに、悔しさがこみ上げてきて涙が溢れそうになった。しかし
一時間もするとトキュウの心は平静さを取り戻した。
町をさまよっているうちに、夜の色鮮やかな光の群れが、深
くえぐられた心の傷を覆い隠してくれたようだった。
町は恐れもしなければ動揺もしない、建物も車も舗道も硬い
、もし町から人間を除けば、それは無機物の塊に過ぎない。そ
の町のなかで人間はさまざまだ。高速で移動しているもの、機
械のように歩くもの、地べたに座り込むもの、亀のように歩く
ものがいる。進んで善を行うものもいれば進んで悪を行うもの
もいる。騙すものもいれば騙されるものもいる。命令するもの
もいれば命令されるものもいる。電車や映画館で隣同士になっ
ても、おたがいどんな人間かわからない。アパートの隣室に殺
人犯が住んでいようと気づかない。判らなくても気づかなくて
も人々は住み分けるように共存することができる。町のなかで
は、風は季節によって時刻によってさまざまな方向から吹くよ
うに、たとえ同じところに居合わせても、人々の感じ方はさま
ざまであり、人々の思いは無限に反射し衝突し、そして交錯す
る。そして人々は自分と同じ種の人間を本能的に嗅ぎだし、群
れ集い、交感しあい、所有し合い、いっしょに意味を見出し夢
を見る。
トキュウにはまだ仲間も大切にしている物もなかった。持ち
物といえば、いまだ日々成長を続けている生まれたままのよう
なつややかな肉体だけだった。実際トキュウの体には傷はなか
った。そもそもトキュウには今まで大きな怪我や病気の経験は
なかった。それだけではなく、ほんとうの飢えや渇きの経験も
なく、身をよじるような苦痛や快楽を味わったことがまったく
といっていいほどなかった。それに思い出すほどの友達との喧
嘩や遊びなどの体験の記憶もなかった。だからある意味ではト
キュウの心は、肉体同様、まだ喜怒哀楽も知らず生まれたまま
のように何の傷もなく純粋であるともいえるのである。
しかしそれは、人並みに夢の見方も知らないことであり、ま
だ人との付き合い方も知らないことであり、そのまま社会に出
ることは、まだよちよち歩きしかできない幼な子のように、非
常に危なっかしいことである。
このようにトキュウがこれまで平穏無事に過ごしてこれたのは
単なる偶然ではなく、日々の生活にあまり変化を望まない、温
厚な人々のなかだけで育ってきたからである。
トキュウはいつもポケットにお金を入れて、闇雲に欲望を満
足させようとして町をと迷い歩いているわけではなかった。毎
日どうにか工面だ来たのは、たいていは最低限の欲望を満たす
程度のものでしかなかった。
それでもトキュウは、なぜかそれほど苦痛ではなかった。
しかし、それも日増しに難しくなってきていて、だんだん
慢性的な空腹状態に陥っていた。
ある夜トキュウは同世代の若者にまぎれてゲームセンターで
遊んだあと、外に出て歩き出すと、耐え難い空腹を感じた。
眼の前にあふれるほどの食糧をウィンドーから覗かせている
スーパーマーケットが現われた。それに眼を奪われながらトキ
ュウは、ポケットに入れている手の指先に千円札の感触を感じ
た。
トキュウに店に入った。
閉店まじかの客もまばらの店内を、商品の群れの中を、うろ
ついた。何しろ始めてはいる店だったので。
そしてパン売り場を見つけると、菓子パン二つ手に取り、こ
んどはレジをもとめてきょろきょろ周囲を見まわして歩いた。
そしてレジの場所を見つけそちらに向かおうとしたとき、いき
なり腕をつかまれ、周囲からは見えない商品の棚の影にひきづ
られて、その勢いで倒された。戸惑いながら見上げると、底に
は店の店員である若い大人の男が立っていた。その男はトキュ
ウの
前に立ちふさがるようにして言った。
「何しにきた。取るつもりだったのだろう。もう許さないぞ、
お前らのせいでどんなに大変だか判るか?」
店員は大声ではなかったが、激しい怒りを顔に表していた。ト
キュウは戸惑いながら男を見た。
「なんだその眼は、この泥棒やろう。お前らクズはみんな同じ
眼をしているな。キツネみたいにいやらしい眼をしてさ、どう
せ金なんか持ってないんだろう」
トキュウは急いでポケットに手をいれ先ほどの札をつかむと、
それを勢いよく出して店員に見せながら言った。
「金なら在るよ、ほら!」
しかし、それは金ではなかった。二つに折られた何かの割引券
だった。店員はこぞとばかりに怒りを込めたまなざしで睨みな
がら言った。
「このうそつき野郎、どうせこんなこったろう、お前らの考え
ることはみんな判ってんだ。やっぱり盗むつもりだったんだな
、正直にいえよ!」
そういいながら店員はトキュウの脚をけった。そしてさらに興
奮して言った。
「お前ら見たいクズは警察に突き出しても良いんだけど、それ
じゃ面白くないな、お前らは何もされても文句は言えないんだ
ぞ、いいか、昔はお前らみたいなのはみんな手を切り落とされ
たんだぞ」
そう言いながら店員は前よりも強くけった。
「いいか、もう二度と来るなよ。今度きたらどうなるか判って
るんだろうな」
そういい終わると店員はじっとトキュウを睨み続けた。戸惑い
の表情を見せながらトキュウは何も言い返すことができなかっ
た。
そして追い出されるように店を出た。
トキュウの頭は混乱していた。あまりにも店員の男が一方的
だったので、何が起きたのかよく理解できなかったからだ。大
きな悔しさや憤りよりも、自分はいったい何か悪いことをした
んだろうかという思いでいっぱいだった。
店員の顔を思い浮かべるたびにトキュウは、なぜあの男はあ
んなに激しく怒るのだろうかと不思議な気持ちでいっぱいだっ
た。
トキュウは繁華街のメインストリートを臨める公園に向かっ
た。
舗道沿いの階段を数段昇ると、視野が開けた。周囲は植え込
みとまばらな樹木でかこまれていた。
トキュウは階段を上がったところで、空腹を満たすかのよう
に思いっきり水を飲んだ。
公園は大たい三つの部分からなっていた。多くの人々が出入
り口のように利用する階段部分と、その階段を降りきったとこ
ろから始まる平らな広場の部分、そして、これは大部分を占め
ているのだが、高い樹木が寄り密になっている森林部分。
階段は下りで扇型になっていた。そしてその先の広場の周囲
には所々にベンチがおいてあり、ほぼ真ん中のステージのよう
に高くなっているところには花壇になっており、花が植えられ
ていた。
トキュウは人ごみに飽きると、よくここに来て休んだ。いつ
も色んな人たちが時間に関係なく、入れ替わり立ち代りやって
きてはみんな好き勝手にやりたいことをやっていた。
トキュウにとってはここにきても友達に会えるわけでもなく
、これといって楽しいことがあるわけでもなかったが、いつも
のびのびとした雰囲気を感じることが出来て気に入っていた。
トキュウは広場に面した階段の真ん中辺に腰を下ろした。そ
して横になり星の見えない空にぼんやりと眼をやった。もう先
ほどの事は忘れてしまったかのように何にも頭には浮かんでこ
なかった。
またしても町の色鮮やかな光の群れがトキュウの心の傷を覆
い隠してくれたのだろうか? それともトキュウの若くて未熟
な心があまりにも柔軟でやわらかすぎるために、針のような言
葉にも傷つくことはなく、いったんは受容しながらも、やがて
は何事もなかったかのように、それを通過させて、どこかの道
端に捨て去ってしまったのだろうか?
真夜中に近づいても公園に集まってくる人々の数はそれほど
変らなかった。
突然入り口のほうで奇声が上がり、弾んだような話し声が響
くと、ダンスのステップを踏むように軽快な足取りで、若い男
がが一人二人と通り過ぎていった。トキュウは彼らを見て反射
的に緊張した。なぜなら、彼らはみな自分と同年代の若者たち
であったからだ。
そして彼らが自分から離れていくにしたがって、その緊張も
徐々に和らいでいき、やがて彼らが自分から遠くはなれてベン
チに陣取るのを見てようやく、もとの自分に戻っていった。
少し落ちつくとトキュウは、いつものびのびとした雰囲気を
感じるようになっていた。そして周囲を見まわすと老若男女さ
まざまな人たちがここに集まって来ているのが判った。トキュ
ウに最も近いのはトキュウの斜め後ろに座っている少女たちの
集団だった。
その若い女たちは自分たちの美意識や流行を極限まだ極めて
いるようだった。
ほとんどが肌もあらわに、熱帯地方の魚や鳥のような配色で
、可能な限り原色の衣服を身につけ、顔は限りなく黒に近く、
眼や口は緑や白で縁取られ、髪の毛は銀色の光沢を放ち、耳や
鼻や口元にはピアスがつけられ、色鮮やかなアクセサリーは手
や首だけでなく、体中いたるところにつけられぶら下がってい
た。それはまるでどこか遠い世界に住む自立した少数民族のよ
うであった。
もし初めて彼女たちを眼にする人が顔の部分だけを見たとし
たら、きっと白と黒が反対になっている写真のネガを見ている
ような気がするだろう。いったい何が彼女たちの美意識を反転
させているのだろうか?
その少女たちにせよ、軽快なステップでトキュウの傍を通り
過ぎていった若い男にせよ、トキュウは、日頃から自分とはま
ったく違う世界にすむ若者たちのように感じていたので、出来
るならあまり近づきたくないと思っていた。いったい何がそう
させているのか?
彼女たちの話し声はだんだん大きくなり、トキュウにはまる
で口げんかをしているかのように聞こえてきた。すると一人の
女が群れから離れて歩き出した。そしてトキュウの前のほうの
階段に腰を下ろすと、はき捨てるように独り言を言い始めた。
「ああ、むかつく、なんであいつらに英語かわかるんだよ。ふ
ん、進行形の意味も判らないくせに。あたしにはってもダメ、
これはこういう意味だとか、これは文法的にどうだとか、そん
なことばっかりすぐ頭に浮かんでくるんだから。ああ、つまら
ない。今日はこのまま帰ろうかな?」
もう一人の女が群れを離れ、トキュウの前にいる女に歩み寄り
ながら言った。
「ねえ、ミュウ、あんた暗いよ、どうするの? 行かないの?
みんなカラオケにいくんだけど、おいてくよ」
「アタイは、今日いい、もう帰る」
そう言いながらミュウと呼ばれた女はコツコツという高い音を
立てながら、トキュウの横を通り過ぎ、階段をあがっていった
。ほどなくその音も聞こえなくなった。そして気がつくと他の
女たちも見えなくなっていた。
トキュウにとってミュウが撒き散らした強い臭気が初めて嗅
ぐ匂いのように印象に残った。
公園内に若者たちだけが目立つようになったころ、トキュウ
は、あちこちにたむろする若者たちを中心に話しかけている身
なりのかなりきちんとした大人たちに気づいた。その大人たち
はひとりの女性を含む三人だった。トキュウは急に沈んだ気持
ちになった。以前、繁華街で会ったことがある、あの例のやつ
らに違いないと思ったからである。
あの例の奴らとは、深夜繁華街にたむろする若者たちに、自
分たちから進んで話しかけては、それがまるで自分たちの使命
であるかのように若者たちの悩み事を聞いてあげたり、相談に
乗ってあげたりする大人たちのことである。
しかしトキュウにとって彼らと話をすることは、なぜか気が
重く、とても煩わしいことであった。というのも、彼らのなれ
なれしい余裕のある態度や物分りの良さそうな笑みを浮かべた
冷静な態度は、なんか自分見下されているような気がして、眼
には見えない圧迫感のようなものを感じていたからである。
しかも、彼らのその物分りの良さそうな笑みもトキュウにと
っては、彼らの自信と優越を誇示するものとしてしか受け取る
ことができなかった。
それでしつこすぎる彼らに対して余計なお世話と反撥心を覚
えるのも時間の問題だった。
やがてその大人たちはトキュウのところにやってきた。そし
てそのうちの一人の男が
「ちょっと、すいません」
と丁寧にトキュウに挨拶をすると一枚の写真を示しながら言っ
た。
「この子、見たことがないですか? 実は私たちの娘なんです
。この辺で見かけたことがあると聞いたもんですから」
トキュウは写真に写る一人の制服姿の少女にぼんやりと眼をや
りながら言った。
「、、、、ないっす」
「ないですか」
「こんな真面目そうな子、この辺にはいないっすよ」
「そうですか」
トキュウにとってはほとんど関心がないことだったが、写真か
らではどうにも少女のイメージがつかめないような気がして、
つい次の言葉が口から出てしまった。
「写真はこれ一枚だけですか?」
「今はこれだけなんですよ。これでも最も新しいものなんです
よ。そうですよね、、、だいぶ変っているかも、、ありがとう
ございました」
そう言って大人たちはトキュウから離れて行った。
トキュウはあの例の奴らでなくて良かったと思った。
しばらくすると先ほどの男がトキュウのところにやってきて
言った。
「この写真あなたにあげますから持って行ってください。私た
ちはこれで帰らなければなりません。時間がないものですから
。もし見かけることがありましたら電話ください。裏に番号書
いてありますから。よろしくお願いします」
そう言い終ると男はゆっくりとした足取りでトキュウから離れ
て行った。
トキュウは《なんで俺が》と不満そうにつぶやきながら渡さ
れた写真にもう一度眼をやったあと、無造作にズボンのポケッ
トに入れた。
時計は十二時をまわっていた。
そしてトキュウは抑えていた空腹感にふたたび悩まされ始め
た。とりあえず家に帰るしかないのかなと思った。《でもお金
がない、歩いて帰れば時間がかかって遅くなる。でも家のもの
はたぶん寝ていて、だれとも顔をあわせなくても済むに違いな
い、それで良いのだ》とトキュウは思った。
そしてトキュウは通りに向かって歩き出した。
舗道に面した階段をおり始めてとき、先ほど公園内で見かけ
たのと同じような服装をした少女たちが、夜の町の華やかな風
景をひとつの絵のなかの背景のようにしてたむろしているのに
気づいた。彼女たちのところを通り過ぎるとき、トキュウはさ
っきと同じ連中だと思った。なぜなら、ミュウと呼ばれる少女
が撒き散らしていたのと同じ香気を感じたからである。
その後もトキュウにっては変り映えのしない日々が続いた。
ある日の午後、トキュウが地下鉄のホームから地上に通じる
エスカレーターに乗っていたとき、後ろから歩いてきたスーツ
を着た若い見知らぬ女が、トキュウの右の手を強くたたいた払
いのけた。トキュウの両手が左右の手すりにおいてあったから
である。そしてその女はさも当然のごとくに無言のままトキュ
ウを追い越してエレベーターを昇って行った。トキュウは一瞬
呆然とした。いったい何が起こったか判らなかったからである
。でもすぐに状況が理解できた。そしてそれと同時に激しい怒
りが爆発するかのように沸き起こってきた。
《許さない、何がっても絶対に許さない》
という気持ちになった。舗道に出ると真っ先にさっきの女を探
した。しかし見つけることはできなかった。
町は生暖かく、まだ午後の強い陽射しが差し込んでいた。ト
キュウの怒りはなかなか収まらなかった。汗のようにへばりつ
く不快さは耐え難いものがあった。そして
《まあ、いいさ、もしまた同じようなことがあったら、今度は
思いっきり後ろからケリを食らわせてやる》
と思うと徐々に気持ちが和らぐのを感じた。
その怒りもほとんど消えかかってきたころ、トキュウは異質
な光景に出会った。頭髪を金色に染めた一人の若者が背の高い
独りの男に腕を捕まれてスーパーマーケットの建物の後ろのほ
うに連れて行かれるのを目にしたのだ。その背の高い男とはこ
のあいだの店員であることからして、トキュウは一瞬にして今
何が起こっているのか、またこれから何が起ころうとしている
のかを悟った。
《あの男はこのあいだ俺を泥棒扱いにした奴だ。どんな理由が
あろうと俺はあいつを許さない》
そう思うとトキュウは怒りと憤りで気持ちがとてつもなく大き
くなっていくのを感じた。
トキュウは気づかれぬように二人を追った。二人が日陰に入
り建物の角を曲がったときにはトキュウは二人のすぐ後ろにま
で近づいていた。そして二人が地下に通じる階段をおり始めた
とき、トキュウは早足でその店員の背後に迫り、踊り場のとこ
ろで、思いっきり体当たりを食らわした。するとその店員は手
摺りを越えて落下し何かくずれるような音が響いた。トキュウ
は叫ぶように言った。
「いまだ、逃げろ、いいから逃げろ!」
二人はまるで前々から打ち合わせていたかのように走った。振
り返りもせず全力で走った。角をまかり道路を横切り、ふたた
び角を曲がると、ようやく後ろを振り返りながらゆっくりと歩
き出した。
トキュウが激しく息を切らしながら言った。
「はあ、はあ、もういいだろう、ざまあみろってんだ。いい気
持ちだ。はあ、はあ、あいつはとんでもない奴だぞ。人を泥棒
扱いして苛めるんだぞ。お前も今頃何をされていたがわかんな
いぞ、何にも悪いことしてないのにさ、なあ、そうだろう、は
あ、はあ」
もう一人の若者はまだ声にならないようだった。
「少し休もう」
そういいながらときゅうは舗道沿いの小さな緑地帯に誘った。
そして木陰に身を潜めるように座った。二人は生暖かい空気と
奇妙な静寂に身をゆだねた。やがて吹き出る汗も、乱れて呼吸
も徐々に収まっていった。そして二人は初めて顔を見合わせた
。トキュウが助けたその若者は顔をゆがませながら言った。
「おまえもやるな、びっくりしたぞ」
「なあに、たいしたことないさ」
「大丈夫かな?」
「どってことないさ、もとはといえばあいつがみんな悪いんだ
から」
「そうだよな、たいした額でもないのにさ。しつこいよ。俺は
ショウヘイ、君は?」
「キュウイチ」
二人は話しながらお互いをじっくりと観察した。
トキュウはショウヘイのことを、自分より体が大きく、眉毛
も太く整った顔立ちをしているので、少し自分より年上かなと
思った。ショウヘイはトキュウのことをこれといった特徴ある
顔立ちには見えなかったが、思ったほどめちゃくちゃなことを
やるような人間には見えなかった。
トキュウ急激に喉の渇きをを覚えた。
「ショウヘイ喉が渇いただろう」
「ああ、そうだな」
「云いか、まってろ、今もってきてやるからや」
そう言いながらトキュウは立ち上がると一人で歩き出した。道
路を横切り角を曲がって適当な店を探した。
そのときが近づくに従って、トキュウは気持ちが高ぶり緊張
した。しかし五感は鋭くなり、集中力は増し気持ちは充実して
いた。まるで普段の十倍もの速さで頭が回転しているような感
じだった。それはかつて経験したことがないような、限りなく
無意識に近い攻撃的な気持ちだった。そしてキツネのような狡
猾さすばしっこさで、生まれて初めての盗みを完璧に成し遂げ
たのだった。
悠然と戻ってきたトキュウはショウヘイに缶ジュースを渡し
た。
「さあ飲んでくれ、お金は良いよ、どうせ只なんだから」
「サンキュウ」
「ああ、あんまり冷えてないな、まだ入れたばっかしだな」
「お前、ずいぶん慣れてるみたいだな」
「まあな、これで生きてるようなもんだからな」
トキュウは嘘をついた。しかし自分では嘘という意識はまった
くなかった。むしろ話すたびに誇らしい気持ちになり自分を大
きく感じた。
町は夕暮れが近づいていた。
それまでぼんやりと風景に眼をやっていたショウヘイがトキ
ュウを見ながら言った。
「とこに寝ている?」
「うんと、いえ、いや、たまにだけどね、ほとんどはこんなと
ころかな」
「俺は、良いとこ知ってるぞ。空き家なんだけど、なにもない
んだけど、でも、なにをやろうが自由だから、俺んとこ来ない
か?」
「うん」
それを最後に二人の会話は途切れた。そしてしばらくのあいだ
疾走する車群に眼をやっていたが、ショウヘイが不安そうな表
情で言った。
「お前、喧嘩やるか?」
「けんか?」
「そうか、まあ、良いや、どうしてもむかつく奴がいるんだよ
。でも一人じゃ、、、、あいつらはいつも二三人なんだよ。ど
うだいキュウイチ、力を貸してくれるかい?」
「いいとも、どこだい」
「まだ良い。夜だ。夜をまとう。どうも昼間は元気が出ない。
ああ、今夜は面白くなるぞ。ところでキュウイチ、お前どこか
で見たことがあるぞ」
「そりゃあ、どこかでは見たことがあるだろうな、あっちこっ
ち歩いているから」
「お前、フンスイ広場にいなかったか?」
「フンスイ広場? なんだそれは?」
「電波塔の隣にある公園の広場のことだよ」
「ええ、あそこにフンスイなんてないぞ、なんでそう言うんだ
?」
「判らない、みんながそう言うんで、、、、まあ、良いじゃな
いか、何でも」
「そうだな、フンスイのないフンスイ広場か、変なの!」
二人の会話が途切れた。
しばらくするとショウヘイが突然犬のように「ウォ、ウォ」
と叫んだ。トキュウが驚いて訊いた。
「おい、なにがあったんだ?」
「いや、何にも、自分にもわからないんだ。なんか無性に叫び
たくなるんだよ。今頃になるとね」
「変なの!」
ふたたび会話が途切れた。
あとはそこまで来ている夜を待つだけだった。
ネオンサインは輝き町は夜になった。
二人は沸き起こる精気に促されるように動き出した。二人
になってトキュウは人が変ったように大胆になっていた。それ
までトキュウは周囲にあまり眼もくれず機械のように単調なリ
ズムで歩いていたのだったが、その夜からは、夜の街の光景に
じっくりと目をやりながら、通りにあるすべてのものは自分の
持ち物であるかのように、手で触れたり、ときには脚でけった
りしながら、ゆっくりと歩いたり、また相手に合わせるかのよ
うに小走りになったり、そしてときには人目を気にせずに、い
たるところに座ったり腰をかけたりしては、あたかも自分の庭
に居るかのように振舞った。
二人はほとんどの通りをぶらついた。そしてまだ歩いていな
い通りに差し掛かったとき、ショウは先に行こうとしたトキュ
ウに言った。
「この通りは止めよう、なんか好きじゃない、あれ、ヤーボー
がいるんだよ」
「ヤーボーって?」
「おい、そんな大きい声で言うなよ、聞こえるじゃないか、お
前マジで知んねえのかよ。ちょっと頭のおかしい大人のことだ
よ」
トキュウは良く判らなかったが、ただならぬショウの気配を
察して従うことにした。
それから二人はゲームセンターに行き子供のように遊んだ。
二人は今日知り合ったと思えないくらい意気投合した。
やがて金がなくなると、二人は外に出た。しばらく歩いたあ
と、周囲に繁華街の全貌が眺められる舗道に腰をおろした。も
はや二人の若者にとってお気に入りの場所はたとえそれがどん
な所でも、たちどころに居心地の良い場所となった。二人が眼
を奪われるのはまったく示し合わせたかのように同じ年頃の若
者たちだった。
このときの二人にとって、眼の前を通り過ぎるさまざまな人
々も、町の賑やかや風景と同じように単なる背景に過ぎなかっ
た。
トキュウは反対側の舗道に眼を向けながら言った。
「奴らか?」
「いや、違う」
しばらくしてショウが鋭く言った。
「いた、奴らで、ほらあそこの電話ボックスの隣に、アッ、こ
っちを見た、気がついたかな? 今日こそは決着つけないとな
! 目障りでしょうがない!」
トキュウはショウに促されるようにその方向に眼をやった。そ
してすぐにそれらしき若者たちの姿を捉えた。トキュウの眼は
くぎ付けとなり一瞬にして気持ちが高ぶった。トキュウは激し
く反発しながらも激しく惹かれていた。つまりトキュウは武者
震いの予兆を感じていた。そして不安そうに言った。
「奴らは何人だ?」
「三人は居るな、なあにたいしたことないさ」
そう言うショウには自信と落ち着きが感じられた。トキュウを
勇気を得た。
二人は立ち上がると、その三人の若者たちから遠ざかるよう
に歩いた。そして急いで道路を横断して気づかれないように彼
らの背後にまわると、ゴミ箱の陰に身を潜めた。
「奴らは気づいてないな、みてろ、ひびるぞ」
そう言うとショウは、ゴミ箱から空き缶をひとつ取り出し、彼
らに向かって投げた。空き缶を音を立てて彼らの足元に転がっ
て言った。そのとき黄色いティーシャツを着た一人が、その音
に気づき、缶が転がってきた方向に何気なく眼をやった。そし
て突然のように出現したショウとトキュウを眼にした。しかし
その若者は何事もなかったかのような顔をして、他の二人にな
にやら話しかけ始めた。
トキュウとショウは苛立った。そこでトキュウはゴミ箱から
ビニールのゴミ袋を取り出し、三人に向かって思いっきり投げ
つけた。ゴミ袋は三人の前に転がって息、今度ははっきりと三
人の目に留まった。対峙の瞬間を思うと、トキュウの緊張は急
激に高まっていった。しかし三人は、トキュウたちに目をくれ
ようともせず、ゆっくりと立ち上がり、トキュウたちから離れ
るように歩き始めた。その姿を見てトキュウは感情を爆発させ
た。
「オラ、逃げるのかよ、オラ、オラ」
そのとき三人は突然逃げるように走り出した。トキュウは小
走りで追いかけながらさらに吼えるようよ叫んだ。ショウも叫
んだ。通り過ぎる人々は、その様子にありふれた出来事のよう
にほとんど関心を示さなかった。二人は傍若無人に叫んだ。ト
キュウは叫ぶたびにだんだん声が大きくなっていった。なぜな
ら自分の叫び声に身をゆだねていると自分の力強さを感じると
ともに、自分が自分でなくなっていくような心地よさを感じて
いたからである。
二人の眼を逃げる三人の姿を追い続けた。やがてその三人は
人ごみに消えていった。二人は自分たちの目の届く範囲のもの
はすべて自分たちのもののように感じていた。
ショウが勝ち誇ったように言った。
「なんで逃げるんだよ、つまんないな」
「あぁ」
トキュウは快感にしがみついていたのでそれ以上答えられなか
った。
二人は歩き出した。トキュウが訊ねるように言った。
「やつらはいったい何をしたんだい?」
「うっ、何でむかつくかってこと? それはだな、いつだった
かゲームセンターで遊んでいたんだよ、そしてたら、、、こっ
ちはいっしょうけんめいやっていたのに、、、奴らときたら、
こっちを見てさ、ニヤニヤしてるんだよ、、、なんかバカにさ
れてるみたいでよ、腹がたって、腹がたって、『てめえ、何が
おかしいんだ』って言ってやりたかったけど、なにせ、こっち
は一人、奴らは三人出しさあ、まあな一回だけならまだしも、
これがまたよく会うんだよな、そのたびにニヤニヤされたんじ
ゃ、ほんとにむかつく、俺のいったいどこかおかしいって言う
んだよ、、なあ、、それよりさ、お前のことトキュウって呼ん
で良いかな?」
「いいけど、なんで?」
「なんでって、そのほうが良いだろう。トキュウ、トキュウだ
よ、なんか速そうじゃないか。なあ、それより腹減らないか?
」
「ああ、腹減った」
「いいか、まってろ、今度は俺が持ってくるから」
そういうとショウは一人でどこかへ走って行った。
トキュウは舗道をはずれビルの壁にもたれかかるようにして
腰を下ろした。
三十分後、ショウが走って戻ってきた。そして手に持ってい
た弁当をトキュウに渡しながら行った。
「どうだ、すごいだろう、うまそうだろう」
「うん、うまそうだ」
二人は並んで弁当を食べ初めた。
「ついてたな今日は」
「金持ってたの?」
「ある訳ないじゃん」
「やったのか?、よくこんな大物を。お前もなかなかやるなあ
」
「なあ、トキュウ、その玉子焼きどうだ?」
「どうって、なにが?」
「味だよ、ちょっと甘くないか」
「普通じゃないか、うん、ちょっと甘いか」
「俺、、、、前さ、、、、料理人目指して、、、、働いていた
ころ、、、よく、、、先輩たちに言われたんだよ。お、お前に
は向いてないってさ、、、、お前の舌はどうかしてるってさ、
、、、あ、あれだよ、味音痴ってやつだよ、、、、、それで止
めたんだけどな、、、、まあ、それだけじゃないけど、、お、
俺はあんまり細かいこと得意じゃないみたいなんだ。どうだい
これからカラオケにでも行かないか?」
「カラオケ? いいよ、つまんないよ」
「どうして?」
「好きじゃないんだよ」
「歌ってれば、楽しくなってくるって!」
「いきたくないよ」
「お前、もしかして、、、そうか、お前ほんとうは音痴なんだ
ろう。そうか、トキュウは音痴なのか。俺は味音痴で、お前は
ほんとうの音痴、あっはっはっはっ、、、、」
「笑うなよ、だいいち金がないじゃないか」
「そうだなあ、そうだ、そうだ」
トキュウとショウが別々に孤独であったときには決して思い
浮かびもしなかったような言葉が、このときなぜかあまりにも
自然に次から次へと口を付いて出るようになっていたことに、
二人はまったく気づいていなかった。 弁当を食べ終わると二
人はふたたびさ迷い始めた。
二人の足取りも軽やかで表情も生き生きとしていた。それは
飢えから癒されたというよりも、きっと二人を結び付けたに違
いないお互いの孤独がどこかへ跡形もなく吹き飛んでしまった
からである。
二人は繁華街をはすれて人通りの少ない通りに入ろうとして
いた。曲がり角に差し掛かったとき、トキュウがいきなり窓ガ
ラスに貼られていたポスターを指差しながら言った。
「俺、これを見るとなんかイライラしてくる。暴れたくなるっ
ていうか、、、なあ、ショウ、お前はどうだ。なにが『犯罪の
ない明るい町』だよ」
それは見るものすべてが、自分に向かって微笑みかけている
のではないか錯覚してしまいかねないほどの明るく清潔感に溢
れた美しい笑顔の少女の防犯ポスターだった。
ショウが怪訝そうな顔をして答えた。
「俺はよく判らないな? 可愛いと思うけどな」
「うん、可愛いさ、でも、なんていうのかな、うわぁ、たまら
ない、ショウいいか、逃げる用意をしろ、この窓ガラス叩き割
ってやるから!」
「おい、トキュウ、待てよ、ここは交番だぞ、ヤバイよ」
「判ってるよそれくらい、おっ、人はいない、今だな、ショウ
、お前は先に行ってろ」
そう言いながらトキュウは、舗道に刺さっている車よけの金
属の棒を引き抜くと、今度はそれを窓ガラスめがけて投げつけ
た。投げると同時に二人は走った。背後にガラスの激しく割れ
る音を聞きながら全力で走った。
最初の角を曲がる前にトキュウは後ろ振り向いた。そしてゆ
っくりと走りながらその角を曲がると前を走っているショウに
叫ぶように話しかけた。
「大丈夫だよ、もう大丈夫。ああ、すっきりした。なんで気持
ちがいいんだろう。ハァ、ハァ」
ショウは立ち止まって、ゆっくり歩いて来るトキュウに言った
。
「やっぱりお前はトキュウだよ、いきなり、なんかやりだすん
だから、ハァ、ハァ」
トキュウは笑いをこらえながら答えた。
「ああ、不思議だ、なんてこんなに気持ちがいいんだろう」
二人はふたたびゆっくりと歩き出した。
ときおり後ろを振り返っていたショウが心配そうに言った。
「やばくないかな?」
「なんで?」
「途中ですれ違った奴、俺たちの顔覚えてないかな?」
「大丈夫だよ。だれも、俺たちには関心ないよ」
「うん、そうだな。大人が俺たちに関心ある訳ないよな。アッ
! マジ、ヤバイヨ! あの交番に監視カメラ付いてなかった
か?」
「ついてても、そんなに判らないって!」
「アッ、そうだ! いい考えがある。トキュウ、お前も、俺み
たいに髪を染めろ。髪を染めて、ピアスをしろよ! なんか今
のままだと、見てると頭が痛くなるよ、なんか窮屈そうでさ、
なあ、そうしようよ、そうすればマジで判らなくなるって!」
「うん、それていい、決めたぞ」
そう言うとトキュウは、夜空に青空を見たような気分になっ
た。
いつしか二人はふたたび人ごみに分け入っていた。
何気なく後ろを見ていたショウが独り言のように言った。
「やつら似てるな。俺たちをつけてるのかな?」
その声に振り返ったトキュウは、二時間前に追い払ったはずか
の三人組を人ごみに発見して激しく動揺した。そして三人の姿
を見据えながら言った。
「奴ら仕返しする気かな?」
「判らない。よし、こっちへ行こう。もしついて来たら、奴ら
はやる気だ」
二人は賑やかな通りを離れた。そしてしばらく決して振り返
ることなく歩いた。
トキュウにとって初めて歩く場所だった。大きな川があり、
アーチ型の鉄橋があった。人通りは少なかったが、たくさんの
車が鈍い夜の光を受けてひっきりなしに疾走していた。二人は
橋を渡った。そして渡りきって川沿いに歩こうとしたとき、示
し合わせたかのように初めて後ろを振り返った。先ほどの三人
の姿が見えた。橋を渡り始めたところだった。ショウが確信し
たように言った。
「奴らやる気だな。この先に音楽ホールがあるんだ。あそこは
広いところだ、あそこで待ち伏せよう。奴らマジでやる気なら
、こっちだってな、なあ、トキュウ。あっ、そうだ、お前これ
持ってろ、おれは、いい、もう一本持ってるから。他にもいっ
ぱいあるんだ」
そう言ってショウはトキュウに一本のナイフを渡した。そして
もう一本を自分のポケットから取り出すと、慣れた手つきで扱
いながら言った。
「よく見てろよ。こうやるんだ!」
トキュウはショウの真似をした。初めて手にしたので最初は
ぎこちなかったが、何度もくり返しているうちにどうにか様に
なるようになった。それと同時に徐々に緊張と興奮が高まって
行った。
二人はゲートをくぐり、広場を通り、音楽ホールに通じる階
段を昇りきり、三人が現れるのを立って待った。
ショウが言った。
「トキュウ、もしかしたらお前、俺たちみたいなのと付き合う
の初めてじゃないか?」
「うん、そうだ。今までは何を考えているのか判んねえやつば
っかりでさ」
「そうか、でもな、どうも初めてのようには見えないけどなあ
」
しかしトキュウはショウの言う意味も判らないくらい不安で
いっぱいだった。
やがて建物の影から三人が現われ、周囲のようすに目を配り
ながらゲートに通り掛かった。トキュウの眼には彼らはみなそ
れぞれに手に何かを持っているように見えたので、トキュウの
緊張と興奮は頂点に達した。そしてトキュウは身震いするほど
に全身の力を振り絞り威嚇するように叫んだ。
「おら、なにやってんだ。こそこそするんじゃねえぞ」
その声に周囲の建物に反射し、薄暗い広場に響き渡った。ショ
ウもつられるように叫んだ。三人は驚いたように立ち止まると
、お互いに顔を見合わせた。そしてゆっくりと歩いて最も近い
街路樹の陰に固まった。何か相談しているみたいに。
トキュウがつぶやくように言った。
「なんだ、どうしたんだよ」
「よし、様子を見てくる」
そう言うとショウはゲートに向かって歩いた。そしてゲートに
着くと立ち止まった。しばらくすると三人のうちの一人がショ
ウの方に向かって歩き出した。そしてショウとその若者がなに
やら話し始めた。やがて二人は分かれた。トキュウのところに
戻ってきたショウは言った。
「奴ら、いっしょにやりたいんだって、俺たちと、どうだい、
賛成かい?、反対かい?」
「ショウがかまわないなら、俺はいいよ、賛成さ」
それを聞いてショウは三人に向かって手を振りながらオーイと
叫んだ。トキュウそれまでに高まっていた緊張と興奮がどこか
へ吹き飛んでしまったかのように感じた。
三人がやってきた。先頭を歩いてきたものが手に持っていた
紙袋を
「これを取ってくれ」
といってトキュウに差し出した。トキュウは受け取るとショウ
といっしょに中を覗いた。そこには缶コーヒーとハンバーガー
が二つずつ、それに銀色のネックレスとナイフとストップウォ
ッチが入っていた。ショウは
「この型の奴はまだ持ってない」
と言ってナイフを取った。トキュウはネックレスを取った。そ
して残りは三人に返した。
五人はお互いに名乗りあった。
三人とも髪を染めピアスをしていたが、それぞれ特徴があっ
た。
ゲンキはだれよりも背が低く、顔も幼く、いちばん年下のよ
うに見えた。
タイヨウは体は大きかったがまだ大人の顔には成っていなか
った。
サンドは痩せていてだれよりも機敏そうだった。
五人は誰一人として、それそれの名前を不思議がるものはい
なかった。みんな素直に受け入れた。トキュウにはもはや微塵
の敵意もなかった。
それよりも、まだ知り合ったばかりだというのに、何年も付
き合ってきた友達のような親近感を彼らに覚えた。それはトキ
ュウの体の中に爆発的に起こってきたので、とにかく何でもい
いから彼らと話し合って親しくなりたいと言う気持ちにさせる
ものだった。トキュウは世界が急に膨らんだような気がして、
かつて体験したことがないくらい陽気になった。それは何が起
きても怖くない、自分には何でもできるように高揚した気分だ
った。
五人を近づけたのは、同じようなことを感じ、同じようなこ
とを考え、同じようなことに興味を示すという同種の匂いをお
互いに嗅ぎ取ったからであった。しかし、ではそれはいったい
なんであるかは、まだだれも具体的には気づいていなかった。
トキュウがタイヨウに話しかけた。
「あそこの公園の広場で会ったよな」
タイヨウはニヤニヤ笑いながら首をかしげた。
トキュウはさらに続けた。
「電波等の隣の公園だよ」
「フンスイ広場、フンスイ広場」
とゲンキが独り言のように言うと、トキュウが同調するように
答えた。
「そうそう、フンスイ広場だよ」
するとサンドがトキュウに答えるように言った。
「フンスイ広場なら、よく行ってたから、会ったかもな」
ゲンキがふたたび独り言のように言った。
「ある、ある」
トキュウがさらに続けた。
「ダンスやってたろう」
サンドが答えた。
「俺達はダンスなんてやならいからさあ、なあ、タイヨウ、お
前がダンスだってよ」
それを聞きながらタイヨウはニヤニヤしながら首を振った。シ
ョウがたずねた。
「みんなは何が得意なんだ?」
するとサンドが人差し指を折り曲げて笑いながら答えた。
「何って? これかな。金がなくで生きていけるから」
「どっ、ど、こででも寝れるからなあ」
とタイヨウがニヤニヤしながら初めてしゃべった。
するとゲンキが勢いよく言った。
「やっちゃうよ、なんでもやっちゃうよ」
それを聞いてみんながニヤついた。
サンドが言った。
「けど、トキュウほどじゃないよ。すごいんだってなトキュウ
は、ショウが言ってたよ」
ショウがさえぎるように言った。
「そうだ、凄いんだよトキュウは、半端じゃないんだから。怖
い者なしって感じだ。すぐにパアッとやっちゃうんだ、なあ、
なあ!」
「まあな」
とトキュウは反射的に答えた。
サンドが突然、車が疾走する通りを見ながら言った。
「おい、ハナだぞ、ハナ! 短い花びらだな」
それを聞いて他の者もみないっせいにその方向に眼を向けた。
水銀灯に照らされた人気ない通りを二人の若い女が歩いてい
た。サンドとゲンキは勢いよく立ち上がった。そのとき顔だけ
はどんな姿勢になっても終始女たちに向けられていた。それは
まるでエモノを付けねらう肉食動物のようだった。ショウも立
ち上がると弾むように言った。
「さあ、おもしろいことになりそうだぞ」
「よし、行くぞ、後をつけるぞ」
トキュウはみんなと会わせることに沸き起こる快感を覚えてい
た。
五人は二人の若い女の後をつけた。これから何かが起こりそ
うな予感にだれもが興奮を隠さなかった。
ショウが言った。
「いったいどこへ行くんだろう? 公園のほうに行かないかな
」
するとトキュウがすぐ同調するように答えた。
「そうだな、そうしないかな」」
トキュウは頭に浮かぶことをすべて言葉にすることはとにかく
心地よいことであった。
二人は相変わらず人気ない通りを歩いていた。五人は距離を
徐々に縮めていった。そして数メートルほどになったとき、二
人の女は不穏な気配を感じ取ったのか、後ろを振り返った。
ショウが大きく両手を揺らしながら言った。
「アッ、気づきやがった。チクショウ、残念だな」
だが、そう言うショウの表情は少しも残念そうではなかっ
た。むしろ楽しそうだった。他の者も何かゲームに夢中になっ
ているかのようににこやか立った。
距離がさらに縮まったころ、若い女たちは繁華街を臨める通
りに入っていた。
五人は幾分早足になった女たちをさらに追跡したが、やがて
繁華街で人ごみに巻き込まれるようになると、追跡を止めた。
それはだれかが言い出したわけではなく、自然とそうなったの
であった。というのも人気ない場所であれほど五人の目をひき
つけていた女たちの姿も、見慣れた華やかな風景の元では、何
の興味も引かない、ありふれた存在になったからであった。
繁華街では五人はまるでひとつの生き物のように行動した
。かたまって歩くときもあれば離れて歩くときもあり、意味
もなく走ることもあれば立ち止まって話しこんでみたり、と
きには舗道いっぱいに広がって歩いてみたりと、自由自在に
その形を変えた。そして道路を横切るときも、決して失踪す
る車にひるむことなく堂々と歩いた。彼らにとって最早足を
踏み出す
場所はどこでも道であり、自分たちの行動が、通り過ぎる車
や人間によって妨げられないことはとてつもない快感だった
。彼らの奔放な行動は夜が更けても衰えることはなかった。
だか、それでもいくらかは疲れを感じたのか、それともひ
とまず飽きたのか、五人は休息するかのように、人ごみを離
れて、裏通りを臨める歩道にいっせいに腰を下ろした。
しばらくするとゲンキとタイヨウが小さな声だ話し始めた
。そして立ち上がると二人は別々になって、色んな店先に並
んでいる自動販売機の下を覗いたり手を差し入れたりし始め
た。それは手分けして何かを探しているようにも見えた。彼
らの行動は、見渡す限りのすべての自動販売機にじっくりと
時間をかけて及んだ。
やがて二人は帰ってきた。そしてメインストリートから少
し外れたところにある自販機の前に立った。そこは飲み屋の
店先だった。
サンドがショウとトキュウに行った。
「俺たちも行こう、飲もうぜ」
トキュウはこのとき二人が探していたのはお金だとわかっ
た。
ゲンキとタイヨウに近づきながらサンドが声をかけた。
「どうだ、あったか?」
ゲンキが答えた。
「三人分しかないんだ」
「良いよ、わけて飲もうよ」
五人は自販機の前に立って時間をかけて飲み物を選んだ。
そして店先でふざけあいながらまわし飲みした。トキュウも
勧められたが、なぜか、
「そんなに乾いてない」
と言って断った。
五人の傍若無人ぶりは、飲み屋の店先を占有しそうな勢い
だった。
ちょうどそのとき二人の大人が店から出てきた。そしてそ
のことに気づかないタイヨウとゲンキが彼らの歩行を妨げた
。するとそのうちの一人が突然怒り出し二人に向かって激し
くののしり始めた。
「バカやろう、邪魔すんじゃない、ガキの癖に、こんな夜遅
くまでうろつきやがって、きたねえ格好して、お前らドブネズ
ミとおんなじだよ。オラ、どけ、どけ、ガキは家帰ってクソし
て寝ろ」
そう言い終ると男は、タイヨウとゲンキを両手で乱暴に押し
のけ、もう一人の男と舗道に歩き出した。あまりにも突然だっ
たので、タイヨウとゲンキだけではなく、他の三人もこれと言
った反応を示すことができなかった。しかしトキュウは、仲間
が侮辱されたことを自分が侮辱されたかのように感じた。そし
てそれまで満ち足りていたものが急に失ったかのような気がし
て、それをふたたび取り戻すためなら、どんな手段を使っても
かまわないような気がした。
舗道に出た二人の男は右と左に分かれ、おぼつかない足取り
で歩き出した。一人も表通りのほうへ、もう一人は裏通りのほ
うへ、裏通りに向かった男はトキュウたちをののしった男だっ
た。
サンドがその男にじっと眼を注ぎながら言った。
「このままで済むと思うのか」
「ああ、そうだ、そうだ」
とタイヨウが同調した。そしてトキュウが言った。
「やるしかないな」
トキュウはみんなが同じ気持ちでいることを感じていた。そし
てささやくように言った。
「よし、つけるぞ」
その声で五人はいっせいに歩き出し裏通りへ向かう男をつけ始
めた。その男の足取りは思った以上におぼつかなかった。
その男が裏通りに入ると五人はその距離をすぐ背後にまで縮
めた。付けねらう五人の目はどれも不安げであるだけでなく、
どことなく寂しげでもあった。そして周囲にまったく人気がな
いことを確認すると、傷ついた獲物を狩るリカオンのように、
その男を取り囲み、打ち倒し、組み伏せ、あっけなく金を奪う
ことに成功した。
五人にとって初めてであるにもかかわらず、しかも何の打ち
合わせもしないのに、それがいとも簡単に成功したのは、みん
な自分の役割を本能的に心得ていて、それを見事に果たしたか
らに違いなかった。みんな失われたものを取り戻したかのよう
に満足そうに笑みを浮かべていた。なかにも喜びのあまり奇声
を発するものもいた。
五人はふたたび繁華街の人ごみにまぎれた。みんな奪った金
で何でもできるような気がしていた。疾走する車よりも速く膨
らんでいった欲望の風船は、ビルの高みよりも高く掲げられ、
どんな夜の光よりも色鮮やかに輝いていた。
まず五人はゲームセンターに行き、子供のようにふざけあい
、飛びまわり、手当たり次第に遊んだ。やがてみんな同じよう
に疲れ、同じように飽きた。そしてまだ残っている金でカラオ
ケに行こうということになった。しかしトキュウはどうしても
行く気になれなかった。そこで、二時間後に再び公園の広場で
会おうということにして仲間と別れた。
トキュウは公園に向かっていた。一人になったトキュウは、
どこか体の一部を失ったかのような心細さを感じ、これからど
うしてよいか判らない激しい不安に襲われていた。それは昨日
まで孤独に町をさまよっていたときにはまったく感じたことの
ないものだった。
歩きながらトキュウは激しくのどの渇きを覚えた。
公園につくと水を思いっきり飲んだ。飲みながらトキュウは
だいぶ前から何も飲んでいなかったことに気づいた。だが、そ
れがいつからだったから思い出せなかった。そして正門の階段
を昇りながら、今日起こったことはすべて夢のなかの出来事の
ような気がした。階段を昇りきって広場を眼にしたとき昨日ま
での一人ぼっちの自分を感じた。
水銀灯に照らされた広場はいつもと様子が違っていた。普段
はみんなバラバラなのだが、広場に面した階段の中央にひと塊
になっていた。その数はおよそ十数名、男もいるが女もいる。
でもほとんどはトキュウと同じ年頃の若者だった。
その群れにだんだん近づくにつれてトキュウは、その若者た
ちの前に立っている二人の大人の男の姿が眼に入ってきた。そ
の二人は若者たちになにやら話しこんでいる様子だった。トキ
ュウは若者たちの後ろに席を取るといっしんに聞き耳を立てた
。若者たちの興奮ぶりからして、話し合いはかなり前から始ま
っていたようで、トキュウにとって最初何を話しているのかま
ったく見当がつかなかった。そのうち断片的ではあったが徐々
に意味が取れるようになってきた。
二人の大人は、二十台半ばと四十前後の男だった。若者たち
と話しているのは主にその年上の男で、若い男のほうは自分か
ら進んではあまり喋ろうとしなかった。二人とも大都市の夜更
けにはふさわしくないくらい身なりも話し方もきちんとしてい
て、その上表情や仕草もかなり理性的で、だれが見ても酔っ払
いや怪しい人物でないことは判った。
若者たちにとって父親のような男が話し続けていた。
「いや、どんな親だって自分の子供のことを思わない親はい
ません。親だけじゃないです。学校の先生だって、魚屋のお
じさんだって、バスの運転手さんだって、みんな君たちのこ
とを心配していますよ。ほんとうよ、みんな疑りぶかいなあ、
ところでみんなのご両親は何をやっているの?」
「しらねえよ、最近会ってないからな」
とその大人の眼の前に居た若者が仕方なさそうに答えた。
「親は親、子供は子供」
ともう一人の若者が言うと、他の若者たちがお互いに顔を見
合わせたりして、少しざわついた。
大人の男がさらに話し続けた。
「また言うようだけど、このままで良いとは、私にはどうし
ても思えないんだよ。学生だったら、ちゃんと学校に行った
ほうが良いだろうし、仕事をしているんだったら、真面目に
勤めたほうが良いと思うんだよ。
「つまんねえんだよ」
とトキュウの眼の前で若者がつぶやくように言った。大人の
男はその若い男に眼をやりながら言った。
「つまらないって、何がつまらないんだろう?」
その若者が答えた。
「何がって、学校に決まってるんじゃん。楽しくないからし
ょうがないじゃん」
すると大人の男がゆっくりと話し始めた。
「イヤそういうものじゃないと思うよ。たしかに今はつまら
ないかもしれない、辛いかもしれない、でも、それは将来絶
対に役に立つことだからね。仕事だってそうだよ、今は大変
かもしれない、苦しいかもしれない、でも今のうちに色んな
ことを身につけていれば、大人になったときに楽になるし有
利だってことだからね」
そのとき突然別の若者がさえぎるように言った。
「楽しいことやって何が悪いんだよ、大人には関係ないだろ
う」
大人の男が冷静に答えた。
「悪いとは言ってないよ。その楽しいことをやりながら、勉
強するものはもっと勉強して、働いているものはもっと真面
目に働くって言うのはいちばん良いことじゃないかな。まあ、
みんなにはそれそれ事情があると思うけど、でも今のままで
社会に通用すると思う? それが心配なんだよ。親からもら
った大事な体をそんなに傷つけてさ何が楽しいんだろう。あ
あ、それにどうみてもそんな化粧は変だと思うよ。服装だっ
て決して美しくない、どっちかというと、、、、、」
そう言いかけながら首を傾げる大人の男に対して、写真のネ
ガのような、体には熱帯地方の鳥のように着飾った若い女た
ちは、なにやら顔を見合わせながらお互いにぶつぶつ言い始
めた。そしてそのうちの一人が激しく抗議するように言った。
「何にも判ってないね。それはあんたの考えでしょう。あた
したちには、あたしたちの考えがあるのよ。あたしたちは自
分で美しいと思っていればそれで良いのよ」
「そうだよ、そうだよ」
と他の女たちもいっせいに抗議した。
大人の男は少し顔に笑みを浮かべながら言った。
「そうかな、とても美しいとは思えないけど、グロテスクっ
て言うか、気持ち悪いって言うか」
若い女たちがバラバラに答え始めた。
「美しいよ」
「何、グロテスクって?」
「あんたのほうこそ気持ち悪いよ」
大人の男がさらに言った。
「いったい何が目的なのか、ちっとも判らないんだよ。それ
じゃ男の子にだってもてないだろう?」
ふたたび若い女たちがバラバラに答え始めた。
「もてるよ、可愛いって言ってくれるよ」
「このあいだ、逃げられちゃった」
「大人には関係ないよ」
「良いじゃない、自分が良いなら」
さらに大人の男が言った。
「でも、いつまでもそんな格好はできないだろう」
若い女の誰かが小さな声で言った。
「それはいつかは止めるかもしれないけど、、、、」
すると別の若い女がさえぎるように言った。
「ちょっと待ってよ。どうしてあたしたちの格好がそんなに
良くないって決め付けるのよ。だって判らないじゃない、そ
のうちにあたしたちの方が美しいって言われるようになるか
もしれないじゃん」
「そうだよ、そうだよ」
と他のすべての女たちが同調するように言った。その女はさ
らに話し続けた。
「ねえ、可笑しいと思わない、大人たちの服装って、男も女
も、昔からちっとも変らないじゃん、みんな同じようじゃん、
古臭くって、ダサくって」
それを聞いて他のすべての女たちは、子供のような仕草で無
邪気に笑った。そしてその女は、ざわつきが収まるのを待っ
て最後に締めくくるように言った。
「あたしたち誰がなんと言おうと止めないわよ」
大人の男は軽く頷きながらふたたび話し始めた。
「ところでみんなはどうやって生活しているのかな? ちゃ
んと働いているようには見えないんだけど。親からもらって
いるの?
」
仕方なさそうに一人の女が答えた。
「ちゃんとやってるよ、バイトだけど」
「バイトだけじゃこんな格好して夜まで遊んでられないんじ
ゃないの?」
「ときどき親からもらう」
「そうだろうね。かわいそうだね。みんなのご両親は。今ま
で苦労して大切に育ててきたのに、こんな風になってしまう
なんて、泣くに泣けないね。ところでみんなのご両親はみん
なが何をやっているのか知っているのかな?」
男も女もみんなバラバラに言い始めた。
「苦労してるわけないだろう」
「あいつらが泣く訳ないよ」
「かわいそうなのはこっちだよ」
「大切だと笑わせるなよ」
「知ってるんじゃないの」
大人の男はすべての若者に訊ねるように言った。
「ご両親は何にも言わないの?」
「いわないよ」
「言える訳ないよ」
大人の男は少し表情を硬くして言った。
「どうでしょう、皆さん、もう少し真面目にやってみようと
いう気はないですかね。もう少しご自分の将来を考えてみて
はいかがですか?」
すると一人の少女が吐きすてるように言った。
「真面目に、真面目にって、だからさあ、真面目にやったか
らってどうなるの? 大人ってさ、サラリーマンにしても、
先生にしても、真面目そうな顔をして歩いているけど、ちっ
とも楽しそうな顔をしてないじゃん、なんかいつもつまらな
さそうな顔してるじゃん、ときどき本当に苦しそうにしてい
る奴もいるじゃん、いったいどうしたのって言いたくなるの
よね。それにさあ、あんたたちもちっとも楽しそうじゃない
じゃん、ほんとうは人生を楽しんでないんじゃない?」
そしてふたたび男も女もバラバラに話し始めた。
「毎日同じことをやってさ何が楽しいの?」
「なんでさ、何も悪いことをやってないのに大人に怒られな
ければいけないの?」
「そう、大人はなんでみな偉そうにしているの?」
それを聞いて大人の男は一瞬戸惑いの表情を見せたが、すぐ
にもとの冷静な表情に戻り、丁寧に話し始めた。
「皆さん、いいかな、人生と言うものは、そんなに楽しいこ
とばかりじゃないんだよ。むしろくるしいこしのほうがおお
いかもしれない、もしよかったらみなさんのお父さんやお母
さんに訊いてみたらどうですか」
「なんで親に話しを聞かなきゃいけないんだよ」
と一人の若い男が言うとふたたびざわついた。すると大人の
男は語気を強めて言った。
「わたしたちは本当に皆さんのことが心配なのです。なぜな
ら都会には色んな誘惑が溢れていますからね。このままだと
皆さんがきっと悪い道に入ってしまうんじゃないかと思って
いるんですよ」
「なんだ悪い道って?」
と少年の声で誰かが言うと、大人の男はゆっくりと答えるよ
うに言った。
「たとえばですね、面白くないからと言って、薬に手を出し
たり、お金がないからといって万引きしたり、ちょっとぜい
たくをしたいからといって風俗につとめたりとか、、、、、」
「やってないわよ」
と誰かが言うと若者たちはざわめいた。そのとき一人の少女
がひときわ大きな声で言った。
「ねえ、おじさん、別にあたしはやっているわけじゃないけ
ど、風俗やってて何が悪いの? 本人がいいと思っているな
らそれでいいじゃない。それよりさあ、風俗に行くのはたい
ていあんたみたいなオヤジだよ。親父が行くから風俗がある
んじゃない、ほんとうにいやらしいのはあんたのようなオヤ
ジたちだよ」
それを聞いてふたたびざわついた。
大人の男は少しも表情を変えずにふたたび話し始めた。
「まあ、たしかにそういう面もないとは言えません。おそら
く皆さんの中にはそういうことをしている人はいないんでし
ょう。しかし、問題なのはこのような環境のなかに居ると、
犯罪に手を染めると言うか、巻き込まれると言う可能性があ
ると言うことなんです。そうなったらそれこそ人生で台無し
です。いくら本人がいいといっても大人としても見過ごす訳
には行かないのです」
「ならないって」
「いいじゃないか自分の人生なんだから。何をやろうが自由
じゃないか」
「余計なお世話だよ」
「あんたには関係ないよ」
とあちこちから男女を問わず声が出てふたたびざわついた。
そのときだった、トキュウは肩をたたかれた。見るとショウ
たちが到着していた。トキュウがショウに言った。
「早かったな!」
「行く途中で他のグループともめてな、生意気な奴らだった
から、ちょっとのめしたかったけど、逃げられてね、面白く
ないから止めて帰ってきた。何やってんだ?」
「よく判らない」
ショウと三人は他の若者のように座った。
トキュウの耳にふたたび大人の男の声が入ってきた。
「ところで皆さんの将来の夢は何かな、何になりたいのかな?
あなたは?」
「歌手」
「あなたは?」
「ダンサー」
「あなたは?」
「あたしはデザイナー」
「あなたは?」
「あたしはとりあえず海外旅行」
「あなたは?」
「俺は留学」
「あなたは?」
「レーサー」
「あなたは?」
「おれはディージェイ」
次々と話される若者たちの答えを聞きながらトキュウは戸惑
い焦った。なぜなら、将来何になるかなどと、今まで一度も
考えたことがなく、自分は夢と言えるものを持っていなかっ
たことに気づいたからだった。
トキュウは話題が変ることだけを必死に願っていた。
大人の男はふたたび話し始めた。
「そうか皆さんは大きな夢を持っているんだね。いいことだ。
ところで私が皆さんにこうして話しているのは、ほんとうに
皆さんの力になってあげたいと考えているからなんです。こ
れから皆さんは、そうさっきのような夢を実現するためには、
さまざまな困難や問題に突き当たると思うんだよね。そこで
もしよかったら、今後皆さんの相談に乗ってあげようと考え
ているんですよ」
そのとき誰かがさえぎるように言った。
「ほんとうかよ、口先だけじゃないの!」
「言うだけなら何でもいえるからな!」
大人の男が答えた。
「いや、そんなことは決してありません」
「大人はみんな同じだからなあ」
「調子いいんじゃないの?」
大人の男が答えた。
「約束しますよ」
「本当に、本当に行ってもいいのか?、いつでも良いのか?」
大人の男が答えた。
「ああ、良いですよ」
「それじゃ、おじさんの家教えてよ」
大人の男が答えた。
「良いですよ。家ではないんだけど、連絡先をですね、、」
そういって大人の男は、もう一人の若い男と何やら小声で話
し始めた。それが終わると若い大人は、名詞のようなカード
を眼の前に居る若い女たちから順番に配り始めた。その様子
に眼を配りながら先ほどからの大人の男が言った。
「じゃ今日はこれでおしまいにしましょう。もしよかったら
明日またここでお会いしましょう、今度はもっとゆっくり話
しましょうね」
二人の大人の男がいなくなると広場に集まっていた若者た
ちはバラバラになった。トキュウたち五人は再びひとつの生
き物のようにまとまって町をうろついた。夜明けが徐々に近
づくに従って繁華街には人影が少なくなっていったが、五人
の奔放さは少しも衰えることはなかった。やがて朝が来ると
五人は二つに分かれた。トキュウはショウといっしょにショ
ウがねぐらにしている空き家に行って眠った。
その日の夕方に起き出した二人は、夜になると他の三人と
合流した。そして前夜のように、じゃれあって走り、ふざけ
あっては走り、遊んでは跳びまわりながら再び傍若無人に町
をさまよった。
夜更けに五人は偶然のように公園に立ち寄った。
公園の広場では前夜のような話し合いが行われていた。
トキュウたちも参加することにした。
五人は他の若者たちにまぎれるようにして座った。
いつのまにかトキュウに耳にはピアスがつけられ、髪も金
色に染められていて、他の少年たちとは区別がつかないくら
いに、昨日までとき別人のようになっていた。
二人の大人の男の様子も、集まってきていた若者たちの様
子も、前の晩とそれほど変わっていなかったので、トキュウ
はすぐにその場の雰囲気になじんだ。
年上の大人は自信に満ちた表情で若者たちに話しかけてい
た。
「、、、、へえ、昨日から家に帰ってないの」
「いつものことだよ」
「でも家に帰ったほうが楽じゃないか?」
「そんなことない、ジャマ」
「何がジャマなの?」
「家族だよ」
「好きじゃないの?」
「そんなことないけどさ、とにかくジャマ」
「お母さんがいろいろとやってくれるんでしょう」
「やってくれるけど、なんかそれがイヤなの、窮屈で」
「あたしは嫌いだよ、うるさいのは」
「面白くないよね、なんか、宇宙人といるみたいなの」
それを聞いて少女たちの中心に笑い声が起こった。そして大
人の男は少し笑みを浮かべて言った。
「私たちから見れば皆さんが宇宙人に見えるけどね」
それを聞いて再び笑い声が起こった。大人の男がさらに続け
た。
「ところで、みんなはこうやって夜遅くまで町に居るけどテ
レビなんか見ないの?」
「ときどきみるくらい」
「あたしたちは町のほうが楽しいから」
大人の男が言った。
「家に帰ってゆっくり見てた方が楽しいんじゃない?」
「みんなおんなじたからね」
「ドラマとか歌番組とか、いま流行っているものはあんまり
見ないから」
「わあ、古臭い、テレビって遅れているのよ、なんてったっ
て、あたしたちのほうが断然新しいんだから。今流行ってい
るものを見たかったら、町に来て私たちを見ればいいんだよ」
「そうだよ、町には毎日のようにさ新しいことが起こってい
るんだから、家なんかに帰ってられないわよね、ねえ」
「ねえ」
「そうよ」
と他の少女たちも同調した。
「へえ、そうなの、ちっともしらなかった」
と大人の男はやや驚きの表情で行った。そして再び自信に満
ちた表情で話し始めた。
「ええと、では、今日も沢山集まってくれたようなので、こ
こでちょっと話題を変えましょう。いいですね。皆さんはや
はり少しは気になっていたんですね。口では私たちのいうこ
とに反対みたいなことばっかり言ってましたが、心の奥底で
は、やはりこのままではいけないという気持ちを持っている
んですね。正直言って、もう皆さんはここに集まってくれな
いんじゃないかと思っていました。でも今日こうして来てく
れたことに私たちは大変嬉しく思っています。それで、私た
ちはますます皆さんの力になってあげたいと思っています。
もしかしたら皆さんは見た眼以上にしっかりした人たちじゃ
ないかという気がしてきました。どうで小、、、、、ところ
で皆さんは学校にも行かず定職にもつかないでいるようなの
ですが、しかしこれは皆さんが根っからの怠け者だからそう
しているのだとは、とても思えないのですよ。皆さんがいう
ように、ほんとうに学校がつまらないから、楽しくないから
行かないんだと思うのですよ。仕事だって、ほんとうに、真
面目にやったってしょうがないと思わせるような仕事しかな
いから定職に就かないでいると思うんですよ。もしも学校の
先生がだれにも判るように丁寧に時間をかけて教えてくれた
ら、きっと皆さんは喜んで勉強するようになるだろうし、仕
事だってもう少しやりがいのあるような楽しいものだったら、
きっと皆さんは定職について真面目に勤めるはずだと思うん
ですよ。でもそうなっていないのは、この社会のどこかに何
か原因があるんでしょうね。それでは皆さんはどこに原因が
あり、そしてそれはいったいなんだと思いますか? そうで
すよ、大人ですよ、私たち大人にすべての原因があるんです
よ。私たち大人が悪いから、しっかりしてないから、こうい
うことになるんですよ。このようなことは何も学校や職業の
ことだけではないんです。犯罪が多いことや、ホームレスが
町に溢れていることや、多くの若者たちが将来に夢や希望を
もてないでいるのも、みんなわたしたち大人が今まで創って
きた社会が悪いからこういうことになっているんですよ。で
はそんな大人の中で誰がいちばん悪いと思いますか? そう
ですね、政治家ですね。悪い政治家が悪い政治をやっている
から、こんな社会になっているんですよ。皆さんは知ってい
ますか? この国に住んでいて、普通に生活している限り、
だれでも幸せになれる権利を持っているということを。とこ
ろが実際は違います。多くの人は相変わらず不満を感じてい
ます。毎日のように辛いことや悲しいことがいたるところで
ももっと決め細やかで血の通ったシステムや制度を作ってく
れれば、たとえばさっき言った例でいますと、学校で時間を
かけて丁寧に教えるためには、もっと先生の数を増やすとか、
仕事をやりがいのあるものにするためには、いきなり若者た
ちを激しい競争社会さらして挫折させたりしないで、まずは
先輩である大人たちが丁寧に指導していきながら、時間をか
けて若者たちを育成するようにするとか、そうすれば若者た
ちは将来に夢や希望が持てるようになり、犯罪もホームレス
もなくなり幸せに感じる人間がどんどん増えてくるでしょう
ね。ところで皆さんはこんなことを疑問に思ったことはあり
ませんか? なぜこの世の中には貧乏の人や金持ちの人がい
るんだろうかって。みんな笑まれたときは同じ人間のはずが、
なんか不平等ではないか、どっか不公平ではないかって。こ
のようなことは皆さんの身近にありますよね。だれもがいい
学校に行きたいと思うのに、いける人といけない人がいると
か、大人の世界にだってありますね世、会社に一生努められ
る人もいれば、首になってホームレスにする人もいる。それ
から、社会全体がどんなに豊かになっても、満足にものを食
べきちんとしたところに住めない人たちがいまだに居るんで
す。なんか変だと思いませんか? このような問題は皆さん
が生まれるずっと前からあったんです。ところがいっこうに
解決してないんです。なぜだと思いますか? そうです、政
治をやる政治家が悪いからなんです」
そのとき、それまではほとんど黙って聞くだけであった少年
たちのなかから不満そうな声が掛かった。
「なんだよ、つまんないなあ」
それに触発されるように方々から声が上がった。
「なに言いたいのかサッパリ判らないよ」
「ちっとも面白くないじゃん」
「ああ、頭が痛くなりそうだよ」
「なんか違うんじゃねえの?」
「やっぱり大人は大人だよ」
すると大人の男は余裕の笑みを浮かべながら言った。
「どこが判らないのかな? 皆さんに判るようにできるだけ
簡単な言葉で話しているつもりなんだけどな」
「そうじゃないんだよ。理屈っぽいっていうか、まどろっこ
しいっていうか」
「アッ、そうか、判りました。でも、とりあえず最後まで聞
いてくれないかな。まだ途中だったから。あれ、どこまで話
したっけ、アッ、そうだ、政治をやる政治家が悪いというと
ころまでだったね。それではその悪い政治家を選ぶのは誰か
ということになるんですが? そうです、それは私たち普通
の大人です。だれでもない、私たち大人が悪い政治家を選ぶ
から、悪い政治ばっかり行われていて、社会がちっともよく
ならないのです。いちばん悪いのは私たち大人なんですね。
そこで皆さんにはそういう悪い大人にはなって欲しくないん
です。なにせ皆さんはこの国の将来を背負っている若者です
からね。皆さんにはぜひ真剣に将来のことを考えて行動する
ような立派な大人になってもらいたいんです。そのためにで
すね、、、、」
そのとき再び若者たちのあいだから声が上がった。
「いいじゃないか、政治がよかろうが悪かろうが、俺たちに
は関係ないよ」
大人の男が毅然と答えた。
「いや、あります。大いに関係あります。皆さんが本当にし
っかりしないとこの国は絶対によくならないのです。このこ
とは何も私たちの国に限ったことではないのです。何十億と
住んでいるこの地球は今とうなっているか皆さんはわかりま
すか? どんどん環境が悪くなるばかりじゃないですか。果
たしてこれで良いのでしょうか?アッ、では、ここで、彼に
話してもらいましょう。この件に関しては私よりも彼のほう
が詳しいですから」
そういいながら年上の男が正面から退くともう一人の大人、
それまでは目立たないようにわきの方に立っていた若い方の
大人がみんなの前に出てきてゆっくりと話し始めた。
「ええ、たぶん、皆さんはテレビや新聞でもうご存知かと思
いますが、今私たちの地球は大変な問題を抱えていますね。
たとえば、人間が自分たちの生活のためだといって、石油や
石炭などの化石燃料をどんどん燃やしたために、空気中に二
酸化炭素の量が増えていき、地球に温度がだんだん上がって
来ているんです。このまま行くとどうなると思います。そう
です、取り返しの付かないことになるんです。南極や北極の
氷がどんどん解けて域、水没する国が出てきたり、異常気象
が起こって旱魃や水害が激しくなったり、そうなると当然取
れる作物も取れなくなるでしょう。しかも気温が上がるわけ
ですから、動物や植物の生態系もどんどん変っていき、今ま
でに発生しなかったような伝染病も発生するようになるでし
ょう。もう今までのように好き勝手に化石燃料を使うことは
許されないのです。そのほかにもまで問題はあります。たと
えば世界のあるところでは人口が爆発的な勢いで増えていま
す。このままではいずれ食糧不足に陥って、億単位の餓死者
が出てしまうでしょう。戦争だっていまだに世界のいたると
ころで起こっています。いったいいつになったらこんな悲惨
なことがなくなるのでしょうか。これらの問題を解決するの
はすべて政治次第なのです。ですから、私たちは、私たち大
人だけではなく、将来大人になる皆さんも、自分たちさえよ
ければそれで良いんだというような考えを捨てて、もっと広
い視野を持って、世界の人々のことや、地球環境のことを考
えて行動するようになることが大切なのです。そうすれば自
然と政治もよくなり、さっきいったようなさまざまな問題も
解決して、だれもが望むような理想的な社会が実現するでし
ょう」
そういい終わると若い男はもとに位置に戻った。すると年上
の男が再び前に出てきて話し始めた。
「どうですか、判りやすかったでしょう。これで大いに関係
あるということが理解できたと思います。でも、これだけで
はないのですよ。さっきも少し話しましたが、皆さんには、
だれもが幸せになれる権利があるんですよ。それを悪政に踏
みにじられてもいいのですかね」
先ほどとは別の少年が不満そうに言った。
「なぁ、わかんねえんだよ、あんたたちの話は、何がなんだ
か、地球とか、環境とかいったって、なんか大きすぎて俺た
ちにはサッパリわかんねえんだよ。なに、ケンリがどうした
って、ケンリ、ケンリって、あんたらはそう言ってれば、幸
せになれるかもしれないけど、俺たちには、なぜそうなるの
かサッパリわからねえんだよ」
大人の男が少し首を傾げながら言った。
「ですから、よい政治家を選んで、よい政治を行うことによ
って、そのためには皆さんが、、、、」
広場はだんだん落ち着きのないものになってきていた。トキ
ュウの耳はその大人の男の声をはっきりと聞き取れなくなっ
ていた。
誰かがひとり言のように、しかしみんなに聞こえるように
言った。
「なんか俺たち幸せじゃないみたいだな」
すると大人の男が全員に訊ねるように言った。
「では皆さんは今幸せなんですか?」
誰かが言った。
「とうぜんさ、決まってるじゃない、なあ、毎日楽しいこと
をやって楽しんでいるというのに、なんたって自由だもんな、
それよりさ、あんたのほうが幸せじゃないんじゃないの、俺
にはそう見えるけどね。どうするの、俺たちにかまっている
場合じゃないんじゃないの?」
誰かが同調するよすに言った。
「そうだよ、あんたは他の古臭い大人とどう違うんだよ。な
んか堅苦しそうで、変り映えのしない格好でさ、どう見たっ
て自由って感じはしないね」
大人の男は少し戸惑いの表情を見せたが、すぐにもとの冷静
な表情に戻って話し始めた。
「いいですか、自由というものは、そんなものではないでし
ょう。楽しいからといってやりたいことをやるのが自由なん
ですか?、もしそれで他人に迷惑をかけたら、どうするんで
すが、そんなものは自由ではないでしょう。自由というもの
には責任が伴うものなのですよ。やりたいことをやって自分
さえ楽しければ良いというのはわがままというものです。も
う少し考えて行動しましょう。もう子供じゃないんだから」
誰かが吐き捨てるように言った。
「またかよ、いちいち面倒くさいな、いったい考えたってな
んになるんだよ。なんかむかついてきた。いったい俺たちの
なかに考えて行動してうまく行った奴なんか居るのかよ。い
たら見てみたいよ、とにかく俺たちはやるしかないんだよ」
そのとき少女たちのなかから声が掛かった。
「なぜ楽しいことやっちゃいけないの?」
大人の男は少し間を置いて答えた。
「いけないとき言ってないですよ」
「いってるよ、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけな
いって、大人はすぐ言うけど、それとどこが違うの?」
「イヤ、そういうことではなくて、もう少し他の人のことや
自分の将来のことをじっくり考えて行動して欲しいと言って
るんですよ。」
「しょうがないじゃない先のこと考えたって。だれだって今
がいちばん大切なんじゃないか、今が楽しければそれでいい
じゃない」
「そうだよ、楽しくって気持ちがよければ最高じゃん」
大人の男は戸惑いの表情見せながら言った。
「そうかな、そういう刹那主義はよくないですね。自分のこ
とをますますダメにするだけですよ。いや自分のことをだめ
にするだけではなく、世間にも迷惑を欠けることになります
からね。もう少し自分を大切にしましょうよ。もうそろそろ
自分を大切にしてご両親を安心させるようなまともなことを
やりましょうよ。その格好はどう見ても自分を大切にしてい
るようには見えませんよ。」
「ああ、やだな、そうやって大人はすぐ見かけで判断するん
だからね。どうして私たちが自分のこと大切にしてないって
言い切れるのよ」
大人の男は冷静な表情で言った。
「いや、私は決して見かけだけで判断はしてませんよ」
「してるよ。もしかして自分のこといちばん正しいと思って
るんじゃないの? なんかえらそうにしてさ、むかつく」
「ほんとむかつく、あんたは私たちのことを本当はダメな奴
らって思ってるんでしょう」
「それから絶対に悪いことやってるって思っているよ」
「いやそんなことはないですよ」
「じゃう私たちがますますダメになるってどういうこと」」
「いやそれはですね、このまま行けば皆さんは世間からます
ます相手にされなくなるだろうと言うことを言ったです。な
ぜなら皆さんの格好を見て、変っているとか、まともじゃな
いとかって思っている人はまだまだ沢山いますからね」
「居るいる、このあいだなんか、あたし万引きするように思
われたのよ。後ろに疲れてさ、アッたまにきた。大人ってほ
んとうに見かけで判断するわよ」
それを聞いて大人の男は少し苦笑いを浮かべながら言った。
「私は決してしませんけどね。ところで皆さんはそういう格
好いつまで続けるつもりですか?」
「そんなのわかんねえよ」
「やれるまでやるわ」
「あたしは一生やるわ」
「でも、それじゃ、周りから変な人間と思われて、仕事にも
つけず結婚もできなかったらどうするの?」
「そんなこと知らないよ」
「どうやって生活していくつもり?」
「そのときはそのときだよ。好きでもないことことをやって
長生きしたってしょうがないじゃない」
「そうだよ」
「好きなことをやって生きるのがいちばんじゃない」
「楽しいこともね」
「気持ちいいこともね」
トキュウは大人の男が何を言っているのか最初からほとん
ど理解できていなかった。それでほかの者たちのように不満
や反感は少しも感じなかった。しかし気持ちの上ではなにが
あっても少年たちに同調したかった。
そのとき誰かが言った。
「なぜ迷惑かけちゃいけないんだよ?」
その声で広場一瞬静かになった。そして大人の男が今までよ
りも真剣な表情で話し始めた。
「それは良くないことだからです。あなただって迷惑かけら
れたらいやでしょう。そういうことですよ」
「そのときはやるしかないじゃん」
「ではあなたはなぜ迷惑かけたいですか?」
「楽しいからじゃい。とにかく俺は迷惑かけたいんだよ」
「どうしましょう。他の人たちはどう思いますか? やっぱ
り同じ考えですか?」
先ほどとは別の若者が言った。
「あんたの言うことよくわかんねえよ。なんか違うんだよな、
あんたとおれたちとは。とにかく俺たちは今を楽しく自由に
生きたいだけなんだよ。それだけ、それ以外何も考えていな
いよ、それで良いじゃない、ほんと、ああ、めんどうくさい」
大人の男が言った。
「いや、わたしの言っていることはそんなに難しいことでは
ないと思っています。皆さんはもう少し考えて行動したらど
うですかって言っているだけなんです」
「子供じゃないんだからってか、やっぱり違うな、あんたと
俺たちは、だいいち、あんたは俺たちに考えろ考えろってい
ってるけど、それじゃまるで俺たちバカ見たいじゃん」
誰かが言った。
「やめろ、考えるなんて、やめろ」
「もううんざりだよ。政治の話しをしたってしょうがないよ。
たしかに悪いかもしれないけど、だからどうだっていうの?
俺たちにどうしろって言うの? ちゃんと働けって言うの?
真面目に学校に行けって言うの? 今が楽しければそれで
いいじゃん、先のことなんか知らねえよ」
それを聞いて若者たちはいっせいざわついた。しかし大人の
男はそれを無視するかのように冷静な表情で話し始めた。
「では、皆さん、ここで少し話題を変えましょう。皆さんは、
もし死んだらどうなると思いますか?」
それを聞いて若者たちは静かになった。大人の男は話し続け
る。
「皆さんは人間が死んだらどうなるか考えたことないですか
?」
少し間を置いて若者たちは次々と答え始めた。
「しらねえよ、そんなこと、墓場に行くんじゃないか」
「消えてなくなるんだよ」
大人の男は少し笑みを浮かべて言った。
「そうですか、では皆さんは、天国とか地獄とかいう言葉を
知っていますか? あっ、知っていますか、当然ですか、そ
うですね。でも言葉は言っているが、そこが実際どういうこ
ところかはよく知らない、そういうことですね。では答えま
しょう。天国は生きているときに良いことをした人たちが死
んでから行くところで、地獄とはその逆で、生きているとき
に悪いことをした人たちが死んでから行くところです。それ
では皆さん、死んだあと、天国に行きたいですか?、それと
も地獄に行きたいですか? もちろん天国ですよね、それで
は話しは簡単です。皆さんは悪いことをしなければいいので
す。もちろん皆さんが今日までにやってきたことはあまり問
題にはなりません。これからどういきるかが問題なのです。
私たち人間は、それぞれ生まれも育ちも容姿も性格も能力も
趣味もみんな違います。そして人それぞれ色んな事情を抱え
ながら生きているのです。とくに皆さんは大人たちが作った
この社会で、若者にとってはあまりにも悪すぎる環境の元で、
好奇心をくすぐるようなさまざまに誘惑にさらされながら、
半ば仕方なく生きています。しかしそれにもかかわらず大人
たちは、この悪すぎる環境を改善しようなどとは少しも考え
てきませんでした。なぜならおとなたちは本気で若者のこと
など考えたことなどなかったからです。ですから、これまで
の皆さんの過ちは多少多めに見てあげなくてはならないでし
ょう。しかしこれからはそうはいきません。仮に大人たちに
大部分の非はあったとしても、皆さんがまだ未成年だという
理由で許される訳にはいかないでしょう。悪いことは悪いの
です。それは罪です。悪いことをやったら罰せられなければ
ならないのです。もし皆さんがこれから悪いことをやったら、
罰せられるだけではなく、天国にもいけないでしょう。です
から、皆さんは今までにやってきたことを心から反省して、
これからは他人に迷惑をかけるようなことはしないで、人に
役立つようなことをしながら、誠実に生きることなのです。
そうすれば皆さんはきっと天国に行けるでしょう。ところで
天国ってどんなところだと思いますか?」
そのとき突然、広場全体にけたたましいエンジン音が鳴り
響いた。そしてまもなく、大人の男の背後の林の中から白い
煙が立ち昇った。その爆音は大人の男の話し声を完全にかき
消した。若者たちはざわつき、なにが起こったのかと立ち上
がるものもいて、もう誰も大人の男の話に耳を傾けるものは
いなかった。大人の男も自分から話を中断して、若者たちと
同じように爆音がする林のほうに眼を向けた。木立の奥から
はときおりうなるように響く激しいエンジン音が聞こえてく
るだけであった。それはあたかも都市の他のすべての騒音を
葬り去るかのようであった。
やがて木立の間から一人の男が乗ったバイクが現われた。
そしてみんなの注目を浴びながら、広場をゆっくりと二周し
たあと、中央の丸くステージのような高い所に置かれてある
花壇の花々を蹴散らしながら、巧みなハンドルさばきで、そ
の中心部に悠然と乗り上げた。そしてしばらくのあいだ爆音
を響かせていた。そのあいだほとんどの若者たちは、そのオ
ートバイは長いあいだ木立の中に放置されていたもので、ハ
ンドルは曲がり、主なカバーやマフラーはなく、だれにも見
向きもされないくらいさび付いた、あの骸骨のようなオート
バイであることに気づいた。
ほとんどの若者たちはもう動かないものと決め付けていた
だけに、なにか奇跡が起こったかのように驚き呆然と見てい
た。
それまでトキュウは、大人の男たちの話しや、それに対す
る若者たちの反応に、ほとんど共感できるものがなかったの
で、なにかモヤモヤとしたものを感じていたが、疾風のよう
にそのオートバイが出現して花々を蹴散らして乗り上げたと
きには、初めて他の若者たちに同調するかのよう思わず声を
上げた。そして一瞬のうちに自分の世界が広場の世界と一致
したかのように感じてそれまで感じたことのないような興奮
を覚えた。
オートバイに乗った男はサングラスをかけていた。長めの
髪の毛は少しも乱れる気配を見せていなかった。黒いズボン
とシャツは金属のような光沢を放っていた。表情は夜のせい
もあっていっさい読み取れなかったが、少し笑みを浮かべて
いるようにも見えた。
やがて男はエンジンを止めてオートバイから降りた。そし
てオートバイに寄りかかるようにして広場の若者たちと向か
い合った。若者たちのだれもが何か言葉を着たい品からも、
必死にその男の正体を探り当てようとしていた。しかし初対
面では何にも推し量ることはできなかった。年齢も同じ年頃
のようにも見えたが、はるか年上にも見えた。そして二人の
大人の男はいつのまにか広場から姿が見えなくなっていたこ
とには誰も気づいていなかった。
トキュウにとってその期待は狂おしいものとなった。
バイクの男はひととおり若者たちに眼をやった。日焼けし
たその表情からは、たしかに誰も年齢を推し量ることはでき
そうになかった。バイクの男は少し口元を笑みのように緩め
て言った。
「みんなどうした、さえない顔をして、なんだちっとも輝い
てないじゃないか! 良くまあ、あんな退屈な奴らと付き合
えるな! なあ、いままで通りやりたいことやろうよ、楽し
くさ、いったい誰に遠慮するんだい、大人か、笑っちゃうよ。
だれがなんと言おうと、好きなことをやるのがいちばんじゃ
ないか、なあ、そうだろう、どうしたんだい、元気がないな
、、、、」
そのときひとりの若者が言った。
「ほんとうに良いの、 好きなことをやっても?」
バイクの男がすぐさま答えた。
「当然じゃない、人間なんだから。やりたいと思ったらなん
でもやっても良いんだよ。みんなどうしたって言うんだよ。
なにをそんなに驚いたような顔をしているんだよ」
他の若者が言った。
「でも大人はすぐ怒るじゃない」
バイクの男は両手を広げていった。
「へえ、こりゃあたまげた、じゃ、みんなは大人に怒られる
から、やりたいことをやってこなかったって言うのかい、そ
うじゃないだろう、やってきたろう、大人に怒られたって止
めなかったろう、それはみんながほんとうにやりたいことだ
ったからだよ。いいかい、俺たちは人間だ、生まれたときか
ら自由なんだ。何でもできるんだ、それとも大人が怖いのか
な?」
誰かが言った。
「怖かないよ。でも大人はいうよ、他人に迷惑をかけるよう
なことはするなって」
バイクの男が言った。
「どうしたんだい、ちっとも本音を言わないじゃない」、ほ
んとうはやりたいことをやりたいと思っているくせに、大人
なんて、なんといおうと関係ないさ、アッ、そうか、さっき
の奴らに頭をやられたな、ああ、良いことがはびこっている
ってほんとうにやりすらいよ。いいかい俺たちは自由なんだ、
何でもできるんだから」
誰かが言った。
「でもやりたいことをやるの自由じゃないって言ってたけど」
バイクの男が言った。
「なんだよ、どうしたんだよ、急におとなしくなっちゃって、
あんなに遣り合ってたくせに、大人に見方すんのかよ。ああ、
やっぱりな、さっきの奴らに相当頭やられてるな、だめだ大
人の話しなんて聞いちゃ、大人なんてたいしたことないんだ、
大人なんて信用してないんだろう、みんな眼を覚まそう、今
までどおりやろうよ、いいかい俺たちは自由なんだ、なんで
もできるんだ」
誰かが言った。
「でも規則があるじゃないか」
バイクの男は今度ははっきりと笑みを浮かべて言った。
「これはたまげた、そこまでいうか、そこまでやられたいた
とはな、じゃあ、みんなに聞くけど、その規則はいったい誰
が作ったんだい、みんなはその規則を一度でも守るって宣言
したことあるかい、勝手に大人たちが作ったんじゃないか、
そんな規則に従う必要なんかないよ。いいかい我われは自由
なんだ、何でもできるんだ、規則なんてくそくらえだ。なに、
芝生に入るな! だと、なに、バイクで公園に入るな!
だと、ああ、だからどうしたというんだい、何が恐ろしいこ
とでも起こるっていうのかい、今まさに入っているのに、何
にも起こらないじゃないか、規則なんてどうってことないん
だよ」
誰かが言った。
「でも悪いことをすると、、、、」
バイクの男が少し苛立ちながら答えた。
「ああ、おしまいだ完全にやられている。今まであんなに大
人たちにバカにしてさ、やりたいことをやってきたのに、昨
日までのみんなはいったいどこに言ってしまったんだよ。い
いかい俺たちは自由なんだよ、何でもできるんだよ。ほんと
はみんなウズウズしてるんだろう、なんか面白いことやりた
くって、誰がなんといおうと舗道に寝そべってみたいと思っ
てんだろう。たまには道路の右側をでも思いっきり走って見
たいと思ってんだろう、賑やかな交差点でも花火でもしてみ
たいと思ってんだろう、誰でも学校の窓ガラスを思いっきり
割ってみたいて思ってんだろう。このなかにはさあの鉄塔に
昇ってみたいと思っている奴だっているだろう。俺はさ、さ
っきの大人みたいに頭が痛くなるようにことは言わないよ、
でもその代わりに言いたい、良いかい、決してよいことはす
るなよって、なあ、みんな、今までどおりにやりたいことを
やろうよ、楽しいよ。いいかい俺たちは自由なんだ、何でも
できるんだから、さあ元気を出して、まずは拍手だ。次は声
を出そう。ヤア、イェ、ヤア、イェ」
バイクの男はその掛け声を上げるたびに右手のこぶしを頭
上高く上げた。トキュウも思わず拍手をして声を上げた。初
めは少なかった拍手も掛け声もすぐに若者たち全体に広まっ
ていった。その広がりには開放されたときのような喜びと興
奮が伴っていた。トキュウは何か夢見ているような、かつて
味わったことのないような世界の広がりを感じていた。バイ
クの男は再びバイクにまたがった。そしてすべての注意を集
めるかのようにエンジン音を高らかに響かせた。やがて高め
られた緊張を解きほぐすかのようにゆっくりとエンジン音を
低くすると、思いっきり笑みを浮かべながら言った。
「いいかい、くり返すが、俺はさっきの大人みたいに頭が痛
くなるようなことは言わないよ。でも、その代わりに言いた
い、良いか決して良いことはするなよ。それからさ、そのう
ちに面白いこと見せてやる。あのいちばん賑やかや交差点で
面白いことが起こるから、見に来いよ、アバヨ」
そういい終わるとそのバイクの男は勢いよくバイクを発進さ
せ、花を蹴散らしながらステージのような花壇から跳ぶよう
に降りた。そして悠然と公園の入り口に通じる階段を昇ると
そのまま深夜の町に消えた行った。
うなるようなエンジン音が遠ざかるにつれて若者たちは、
それぞれのグループの仲間に問いかけるように話し始めた。
「いったい誰だ、あいつは?」
「親父なのか若いのかぜんぜん判らなかった」
「しかし、よく動いたな、あのバイク、廃車かと思ってた」
・・・・・・・・・・・
「なんかずいぶんカッコつけてたな」
「うんだな、でも運転うまかったな」
「いったい何しに来たんだ、あいつは俺たちの敵か?、それ
ても味方か?」
「わかんねえな」
・・・・・・・・・・・
「ねえ、ちょっとやばくない」
「そんなことないわよ、あたしはすっごく気になる」
「へえ、びっくり、古いのか新しいのか全然わかんない」
「でもなんか楽しいことが起こりそう」
「ほんと、なんか面白いことこれから起こりそう」
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
タイヨウがニヤニヤしながら独り言のように言った。
「なんだろうな良いことって?」
トキュウが思わず言った。
「うん、なんだろうな良いことって、わかんねえな」
ゲンキが言った。
「あれじゃない、道路に落ちいてるゴミを拾うとか、空き缶
を拾うとか、環境にいいことをやるとか、そういうことじゃ
ないの」
サンドが言った。
「そうだよ、そういうことだよ、俺たち小学生のころやった
よ。近所の川に行って、検査して、表を作って、汚染がどう
のこうのって、そういうことじゃない」
ショウが言った。
「そうかなあ、でも、そんな子供みたいなこといまさら誰も
やんないよ。いいこと、いいことね? おれはさっぱりわか
らねえ」
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
そして若者たちの群れは徐々にそれぞれのグループに別れ
て行った。
太陽にはすでにビルの陰に傾きかけているが、トキュウと
ショウは相変わらす穏かな表情で眠っている。
バイクの男が、その内にこの町のいちばん賑やかな交差点
で何か面白いことが起こると予告したのは今からちょうど二
週間前であった。
その日トキュウと仲間四人はひと通り町をさまよったあと、
真夜中近く、百メートルほど先にその交差点を臨める舗道に
腰をおろして休んでいた。
背後のビルの上方には電波等の赤い光が点滅していた。人
通りも少なく車の流れも弱く、幾分静かであった。そして十
二時を過ぎたころ、その交差点のほうで、バリッ、バリッ、
バァッ、バァッと爆発的な排気音が響いた。そのときまで半
信半疑たった五人は、ついにその時が来たかという思いでお
互いに顔を見合わせた。そしていっせいに立ち上がりその交
差点のほうに向かって全力で走った。
2部に続く