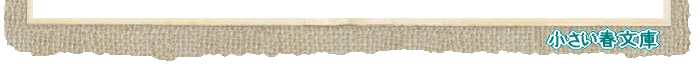今までミリサは、人間や動物、そして花や木だけが生きていると感じてきた。でも今は、雲や山や崖や谷や滝も生きているような気がした。
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
涙が涸れる
マーシャル センフィールド
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
ほとんど知らない人と話さないミリサが、道すがら仲良くなったリャマの子供と別れて寂しそうに歩いているのを見て、サラは思わず話しかけた。
「ねえ、元気になろうよ」
「私は元気よ」
「、、、、そういうことじゃなくって」
「、、、、判ってるよ」
とミリサは少し怒ったように答えた。
旅を続けなければならない限り、別れはいつものことなので、ミリサは、本当はサラが何かもっと別なことを言っているような気がしたからだ。
でもすぐに、本当の姉妹のように接してくれるサラにちょっとでも腹を立てことを後悔した。
そして、サラの思うとおり、もう子供じゃないんだから、いつまでも悲しい思い出に打ちひしがれていては、いけないんだと思った。
でも、どうすればそこから抜け出すことが出来るのか、全然わからないでいた。
ミリサは小さいときから、父と母の三人で、山を越え、川を渡り、草原を踏み分け、高地を横切り、町から村へ、村から町へと、砂糖と糸と、針と、飾り櫛と、そして腹薬を売り歩いていた。
その行商の旅は、春に始まり、秋に終わるようになっていた。
十歳のとき、近道をして断崖の小道を歩いているとき、母が濡れた岩に足を滑らした。谷に滑り落ちようといる母を、父は必死で助けようとしたが、二人ともそのまま霧の立ち込めた深い谷底へと滑り落ちていき、やがて姿が見えなくなってしまった。
ミリサは二日間眠ることも食べることもせずに、その場所にうずくまりただ泣いていた。そして偶然通りかかったサラ親子に発見された。
サラの両親は優しかった。ミリサを実の子供のように扱ってくれたので、ミリサは安心して付いて行くことが出来た。ミリサは、サラと同じように甘えることは出来なかった。でも決して自分が除け者にされているようには感じなかった。ミリサと同じ年頃のサラにとっても、ミリサが仲間に加わったことは、突然新しい姉妹が出来たようで、とても喜ばしいことだった。
だから四人はこの日まで、本当の家族のように助け合い励ましあいながら一緒に旅を続けることが出来た。
そしてその間ミリサは何があろうとも、絶望の淵から自分を救い出してくれたサラ親子に、ずっと感謝の気持ちを持ち続けていた。
変に会話が途切れたことに気まずさを感じていたミリサが、今度は先に話しかけた。
「ねえ、いつもと違う道なんだけど、どこへ行くの?」
「アウヤンテプイ」
「、、、、ア、ウ、ヤ、ン、テプイ。なにそれ?」
「平らな山。神様がたくさん住んでいるところ」
「たくさんの神様?」
「そう、お父さんが子供の頃一度見たことがあるんだって。みんなも一度は見ておいたほうがいいって。とにかくものすごく大きな大きな滝があるんだって」
それから三日後、密林を抜け、険しい崖をよじ登り、岩だらけの山道を歩きながらようやく、アウヤンテプイの全景が眺められる所にたどり着いた。
歩きにくい坂道を下って、少し上りきったとき、途切れた木の先に、その全貌を現した。
後ろを歩いていたミリサはみんなから促されるようにして前に進み出た。
そそり立つ崖は見上げても見上げても高く、その先を沸き起こる雲に隠していた。その雲と崖のあいだからリャマの乳のような真っ白い水が帯のような塊となって、下へ下へと、誇らしげにゆっくりと時を刻むように流れ落ちていた。
そしてその穏やか過ぎる流れはやがて、霧となって拡がり、その姿を失っていた。
ミリサは声もなくただ見上げるだけだった。とても不思議な気がしていた。
「アウヤンテプイ」とサラの言うように、たくさんの神様の山という意味なら、雲に隠れたがけの上にたくさんの神様が住んでいるということになるのだったが、ミリサはちっともそうは思わなかった。いや感じなかった。
今までミリサは、人間や動物、そして花や木だけが生きていると感じてきた。でも今は、雲や山や崖や谷や滝も生きているような気がした。そして自分を取り巻くすべてのものが何か巨大な生命力みたいなものに包みまているように感じた。
みんなみんな自分と同じように生きているんだ、と思うと、ミリサは生きていることがとても不思議なことのような気がしてきた。そして今までにあった色んなことが次から次へと甦ってきた。
突然葦の草むらからのあいだから広がった大きな大きなチチカカの湖を見たときの驚き。
朝日を浴びて銀色から金色に変っていく故里の壮大な山を見たときの美しさ。
山肌に描かれた巨大な鳥の絵を見たときの奇妙さ。
空いっぱいに星を見ながら眠るときの幸福感。
密林で突然猛獣とであったときの恐怖。
賑やかな町で買い物をしたときの楽しさ。
藁で作られたつり橋をサラの両親に助けられて渡ったときの充実感。
毎年通るたびに同じ花が咲き同じ鳥が飛んでいる草原を見たときの喜び。
サラたちとの出会いから始まったたくさんの楽しかったこと。
旅で出会い仲良くなった人や動物たちと別れなければならないときの寂しさ。
そして目の前で父と母を失ったときの悲しみと絶望感。
そのとき、表情も崩さず感嘆の声も上げることなくじっと見上げるミリサの眼から突然のように涙が溢れ、頬を暖かく伝わった。
父と母を深い谷底に見失ったとき、ミリサはどんなにサラたちから慰められても、泣くことを止めることは出来なかった。何日たっても些細な事で泣く幼な子のようにメソメソと涙を流していた。そしてそれが、月が三度丸くなるまで続いたある日、突然のように、ミリサは泣くことを止めた。どんなに泣いても両親が戻ってくるわけでないということ、それに自分のためを思ってくれるサラたちを落胆させるだけではなく余計な心配をかけるということに気づいたからだった。
それ以来ミリサはどんなに悲しいことや寂しいことがあっても、まるで涙が涸れたかのような泣くことは決してなかった。
助けを求めて逃れてきたサルの子供が、結局は捕まって殺されて食べられてしまったときも、
眠っているときに石の下に隠れていた毒虫に刺されて死ぬほど痛かったときも、
石を投げて戦っている男たちの群れに巻き込まれて怖かったときも。
ミリサは涙拭おうとはせず溢れるままにした。
やがて四人は来た道を戻り始めた。
ミリサは先を歩いているサラに追いつき、並んで歩きながら話しかけた。
「ねえ、マリアって優しそうで良い名前ね。どんな意味なの?」
「妹のこと?」
「うん」
「最近町で流行っている名前なんだって。もともとは大きな家に住んで馬に乗っている人たちが使っていたんだって。最高に美しいい名前なんだって」
「ふうん。いつまでお婆ちゃんの所にいるの?」
「私たちのように、いくつもの山を越えて歩けるようになるまでだって、いつかお母さんが言ってた」
「今度の旅では色んなことがいっぱいあったよね、そのこと話して上げるんでしょう。」
「うん。そうだ、ミリサが話してあげたら」
「私がマリアに話してあげても良いの?」
「良いよ。だって、マリアは、私たち二人の妹じゃない」
「サラ、ありがとう」