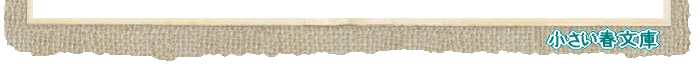青い精霊の森から(4部)
はだい悠
* * *
サイスがバイクとともに川に消えた日から、十日たっても、
二十日立ってもサイスはトキュウたちの前に姿を現さなかっ
た。しかしあえてそのことを口にするものはいなかった。
季節はすでに夏の盛りを過ぎていたが、街の雰囲気に目立
った変化はなかった。トキュウの仲間たちも以前と変わりな
く集まった。
トキュウたちは、深夜、繁華街の通りにたむろしていた。
話題が途切れたときケイタが心配そうに言った。
「警察が捜しているんだって、発炎筒を投げた人間を」
「どうして判るんだい?」
「聞いてあるいてんだって、目撃者を探して」
「わかるわけないよ、だれもおぼえないよ、おれたちのこと
を。俺たちに関心のある人間がいれば別だけれどね」
「こっちから言わない限り大丈夫さ、そんなやついないよな」
「ああ、いない、いない」
そのときあるグループが通りの反対側を通りかかった。今
までずっと気になっていたが、まだなんとも決着がついてい
なかった。相手は五人、こっちは八人、トキュウたちはコッ
ソリと後をつけた。
三つ目の通りに差しかかったとき敵は気づいて早足になっ
た。トキュウたちも早足になり追った。やがて敵は走り出し
た。トキュウたちも走って追った。最初は何の緊張感もなく、
相手が逃げるならこっちは追いかけるぞといった程度の遊び
のような軽い気持ちであった。だが、追いかけているうちに
じょじょに興奮してきて激しく敵対心を抱くようになった。
敵が信号を無視して道路を横切ると、トキュウたちも、大
胆にも車が走っている道路に飛び出し、その通行を妨害しな
がら、特別に黒光りのする車の群れのあいだ縫うようにして
渡った。敵はバラバラになった。トキュウとショウは一人に
狙いを絞って、通りからとおりへと、草食動物を付けねらう
肉食動物のように、執拗に不適に、しかしその反面ときおり
余裕の笑みを浮かべながら追いかけた。そしてついに薄暗い
袋小路に追い詰めた。しかし敵はスキを見てあっさりと逃げ
てしまった。それはもともとトキュウたちは捕まえてどうし
ようというわけでもなかったのに、それに比べて敵は逃げる
ことに必死だったからだ。二人は満足したのかそれ以上追い
かけなかった。
ショウが少し息を切らしながら言った。
「なぜ、あんなに逃げるんだろう?」
「俺たちが怖いんだろう、近くで見たら思ったより小さかっ
たな」
「まだ、中学生みたいだったな」
そう言いながら二人がその場を離れようとしたとき、大人の
男たちが黒い影のように道を塞いでいるのに気づいた。ショ
ウが、トキュウにも判るくらいに一瞬体をびくっとさせた。
そしてつぶやくように言った。
「ああ、まずった、とんでもないことになっちまった。ここ
はあの通りから入り込んだところじゃないか、ヤーボーだよ。
いいか、トキュウ、知らない振りをするんだぞ」
そして二人が大人の男たちのあいだを通り抜けようとしたが、
大人の男たちは通せんぼをして通してくれなかった。その中
の一人が言った。
「なあ、よくみかけるんだけどさ、まずいんだよな」
もう一人の男が言った。
「あんまり舐めたまねすねなよ。けじめをつけてくれないと
な」
二人は大人の男たちに押し戻され五六歩下がった。そのとき
ショウがささやくような小さな声で言った。
「あれだ、ナイフだ、ナイフを使って切り抜けるんだ」
ショウがポケットからナイフを出した。トキュウもつられる
ようにナイフを出した。
そしてショウは
「いまだ、いくぞ」
とトキュウに声を掛けながら、前に進み出ると思いっきりナ
イフを振りまわした。そして大人の男たちがひるんだスキに
そのあいだをすり抜けて走り出した。しかしトキュウはショ
ウにタイミングを合わせることができなかったため、その場
に取り残されてしまった。トキュウは手にナイフを持ったま
ま大人の男たちと対峙した。だが、なぜかショウのようにナ
イフを振りまわすことはできなかった。大人の男たちがだん
だん近づいてきた。先頭の男が手で顔をかばうようにして
「やれるものならなったみろ」
と言いながらトキュウの目の前にせまったきた。トキュウは
ナイフをその男の正面に持っていくだけでどうしても振りま
わすことはできなかった。そのうちにトキュウは一瞬のスキ
をつかれて腕をつかまれてしまい、なんなくナイフを取り上
げられたてしまった。そしてときゅうは腹部を蹴り上げられ
その場に倒れた。苦痛に身を捩じらせていると、なおも集ま
ってきた男たちから、体のいたるところを蹴られた。恐怖と
激痛のなかで気を失いそうになった。
気がつくと男たちの話し声が聞こえてきた。
「ナイフなんか持ちやがって、刺す度胸もないくせに」
「手ごたえないなあ、なんでこのガキ抵抗しないんだ」
「こいつ息してるか?」
「だいじょうぶだ、気を失っているだけだよ、ちょっと手加
減したからな」
「まったく目障りなやつらだ」
「ああ、でもな、こいつら見てると、ときどきほっとすると
きがあるんだよな、そう思わないか」
「そうだな、こいつらが揉め事を起こせば起こすほど、警察
の目を俺たちに向かなくなるもんな」
「こいつらがバカをやればやるほど俺たちはのんびりできる
ってもんだな」
「ああ、そうだな、もしこいつらがいなかったら、俺たちが
一番下ってことになって、俺たちが代わりにやってたかもし
れないな」
「なあに、要するにこういうバカな殴られ屋がこの世の中に
は必要だってことだよ」
「ああ、ほんとにすっきりしたぜ、なんせ久しぶりだもんな、
生の人間をぶっ飛ばしたのは」
「おい、こいつ前にも見たことがあるぞ、もしかしたらあの
野郎の仲間じゃないか?」
「あの野郎って?」
「バイクでビルの屋上から川に飛び込んだやつだよ」
「ああ、ガキどもをけしかけて騒ぎを起こしたってやつか」
「そうだ、最近のわけの判らない事件はみんなあいつの仕業
だっていう噂だよ」
そのときトキュウの頭を靴で踏みつけながら言う者がいた。
「おい、起きろ、死んだ振りをしてるんじゃないだろうな。
カスめ、お前らは社会のカスなんだよ。お前らがどんなにい
きがったって、この町は何にも変わらないんだよ。いいか人
にはそれぞれ役割ってもんがあるんだよ、お前らはずっうと
こうやってドブネズミみたいに這いずりまわってればいいん
だよ。いいか社会に役立つ人間になろうなんて夢にも思うん
じゃないぞ。そういうことはなお前たちよりずっと頭のいい
やつが代わりにやるから、お前たちは死ぬまで悪いことをや
って半端に生きればいいんだよ、そしてみんなから忌み嫌わ
れ、石を投げられ、クズといわれ、最後はもがいて苦しんで
のたれ死ぬんだよ。それでおしまいさ」
そのとき携帯電話がなってトキュウの頭から靴がどけられた。
「ああ、オレだ、今目障りなねずみを一匹始末したところだ。
なんか変な野郎でな、いきがってるくせにぜんぜんと手ごた
えがないんだ。・・・・ああ、だいじょうぶさ、急所ははず
しておいたから、男でも体でわからせるのが一番だ。・・・・
その件なんだけど、あとで警察に挨拶に行くよ。・・・・そ
れで何とかなるだろう。・・・・そうなんだよ、そんなこと
言われたって、こっちの知ったこっちゃないよな、予想まで
やってるわけじゃないから。・・・・あっ、うん、そういう
ときはな、頭を押さえつけて、テーブルなんかもちあげて、
それで頭をつぶすぞって脅かすのが一番きくんだ。・・・・
そうだよ、田舎もんのくせにこういうとこに来て飲む奴が悪
いんだよ。・・・・そうだよ、金持ってるからそういう眼に
会うんだよ。みんな金もってる奴が悪いのさ、あっはっは、
じゃ、すぐ行くよ」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
トキュウは男たちの足音がしなくなると薄目を開けて様子
を覗った。そして誰もいないことを確かめると起きて歩き出
した。しかし自分の体とは思えないくらい重く普通に歩くこ
とはできなかった。それでもどうにか前に進むことはできた。
それは一刻も早く繁華街から抜け出したかったからた。トキ
ュウはできるだけ人通りの少ない裏通りを選んだ歩いた。途
中小さな公園の水道で血と泥を洗い落とし体を冷やした。そ
して夜明け前にビルの空き部屋にたどり着くことができた。
そこはつい最近までショウと寝泊りしていたところだった。
なぜミュウのマンションではなく、そこを選んだかというと、
トキュウは自分の体を治すことよりも、痛めつけられた自分
の惨めな姿を仲間にさえ見られたくないと思ったからだった。
部屋に入ったトキュウは崩れるように倒れると敷いてあっ
たダンボールの上に身を横たえた。いったん体を休めるとも
ううごかすことができないほどに全身がいたんだ。
最初の二日間は、喉の渇きを癒すために夜中に一度だけ人
目を避けて外に出るときに体を動かすだけで、後はじっと身
動きもせず体を横たえて体力が回復するのを待つだけだった。
五日目の夕暮れ、トキュウは夢を見た。夢には、先日、そ
れを見て思わず吐き気を催したあるアパートの郵便受けシー
ルが出てきた。そしてそれはどんどん広がっていく充足した
穏かな感情を伴いながら、やがてそのひとつひとつがほんの
一瞬に過ぎなかったが、トキュウにとってはそれがなんであ
るかはっきりと判る連続するさまざまな映像へと変化して行
った。そしてそのシールは自分が小さいときに貼ったものだ
と判った。そしてそのアパートは自分が小さいときに住んで
いたところだと判った。
夢から覚め、トキュウはどうしようもない心細さに襲われ
ていると、ドアが開いてショウとミュウが入ってきた。ショ
ウが驚きの表情で言った。
「なんだ、やっぱりここに居たのか! なんでもっと早く気
づかなかったんだろう。どうした?」
「うん、うまく逃げられなかった。捕まってボコボコさ」
「オレはてっきり、逃げたとばかり思っていた。あとで行っ
たら居なかったしさ」
「まあ、いいさ、オレが悪いんだ。あのときナイフを振りま
していりゃあ良かったんだ」
「なに! ナイフを使わなかったのか? なぜ?」
「なぜって、どうしても手が動かなかったんだよ。たぶん使
い慣れていなかったからじゃないか」
「それでどうなんだ? 顔のほうは、まあ、何とか、でも体
のほうは?」
「うん、だんだん良くなって来ている」
「もしかして何にも食べてないんじゃないか」
「まあな」
「お前なんでそんなに我慢強いんだ。オレだったら」
そのときミュウがさえぎるように言った。
「歩ける? いや、歩けなくてもいい、手伝うから、あたし
んちに行こう」
トキュウは仲間たちに助けられてミュウのマンションに移
った。
そこへつくとトキュウはまず体を洗い、手当てを受け、そ
してミュウのベットに横たわった。
トキュウにとって退屈さはそれほど変らなかったが,食べ
物を十分に取ることができたので体力はみるみる回復して行
った。
三日目の夕方、ミュウがとにかく食べなくてはいけないと
いってテーブルの上にコンビニの袋を置いて外に出て行った。
トキュウはさっそく手当たり次第に食べ始めた。そして生野
菜の入ったパックをあけて食べていると、そのなかに長さ五
ミリほどの小さな青虫を発見した。死んでいるのかまったく
動かなかった。トキュウはその部分だけを残して食べた。す
べてを食べつくして満足感に浸りながらぼんやりとテーブル
の上に眼をやっていると、その上を先ほどの小さな青虫が一
秒間に体を何度もくねらせながら、移動しているのを見た。
それはまさに全力疾走で何かから逃げている姿だった。その
瞬間トキュウの眼をくぎ付けとなり、髪の毛は逆立ち、全身
に電気が走ったような気がした。二三秒後、トキュウは我に
かえると
「なんなんだ、これは、なんでオレがこんなのにびびりゃな
ければいけないんだよ」
と叫んで、ティッシュペーパーでそのあまりにも小さな生き
物を包み込むと思いっきり握りつぶした。だが、しばらくは
心臓がドキドキして興奮は収まらなかった。
深夜トキュウは自分で体を洗うことを思いついた。それは
どれほど体が動くか試すためだった。全身の隅々まで時間を
かけて洗った後、部屋に戻り何気なく鏡を見た。顔の腫れは
ほどんどひいていたが、どことなく弱々しそうで自分の顔で
はないような気がした。まだ完全には回復してないからだと
思った。そしてバスタオル一枚腰に巻いてベットに横たわっ
た。
しばらくしてミュウが仲間を連れて賑やかに帰ってきた。
「まだ寝てるみたい」
その声はマイだった。
トキュウは寝たふりをしていた。まで以前の自分に戻って
ないように思えたので、なんとなく顔を合わせる気になれな
かった。
みんなトキュウの存在を忘れたかのようにはしゃぎ騒いだ。
「ああ、こぼして、汚れるじゃない」
「いいよ、どうせ出て行くんだから」
「でも、あんまり汚すとお金取られるよ」
「取れるものならって見ろって、こっちにだって言い分はあ
るんだから」
「そうよね」
「ねえ、なんで出て行かなくちゃなんないの?」
「うるさくしたからよ、周りから文句が来てね」
「どうせならもっと騒ごうよ、音楽でもがんがん掛けてさ」
「今日はやめよう、そのうちにね」
「ねえ、新しい部屋見つかった?」
「まだ、むずかしくって」
「お金、またいっぱい掛かるもんね」
「あたし、たのんであげようか」
「だれに?」
「あたしの知ってる人に」
「でも、あんたの知ってる人ってなんとなくヤバそうね」
「そんなことないよ、やさしそうな人たちよ」
「いいわ、なんとかなるもんさ」
「ねえ、ケイタっていたよね、あの子最近見ないね」
「あたし大人の男の人たちと話しているのを見たことがある」
「ねえ、ゲンキ、あんた友達でしょう」
「知らないよ」
「なんかヤーボーとつながっているっていう噂だよ」
「止めよう、人がだれと付き合おうが、あたしたちとは関係
ないよ」
「ねえ、やっば、音楽掛けて騒ごうよ」
「ダメだって場、寝てる人がいるでしょう」
その声はサクの声だった。
「ああ、なんかつまらない」
「ねえ、あたしいま、お金貯めてんのよ」
「どうして?」
「あたし留学するから。ダンスの勉強するために」
「そうなの、あたしは英会話学校に行こうと思ってる」
「今でもよく外人と話してるじゃない」
「うん、もっともっとうまくなりたいから」
「ねえ、歌手の学校ってあるかしら」
「あるわよ、でもお金いっぱい掛かるみたいね」
「なんでもお金が掛かるのね」
「ねえ、あんたはデザインの学校に行くっていってたけど、
いつから行くの?」
「まだね、もうちょっとあそんでから」
「ねえ、ショウ、あんたこのあいだ、男の人と女の人に会っ
てたけど、あれお父さんとお母さんなの?」
「違う、あとの半分は合ってるけど」
「お母さんはほんとうなんだ」
「でも、やさしそうで真面目そうな男の人だったじゃない」
「だからなんだって言うんだよ。うるさいんだよ、お前は」
「だって、その方がいいじゃない、お母さんが幸せになって」
「何がいいんだ、お前は何にもわかっちゃいない、おい行こ
う、女なんかと話していたったしょうがない」
そのショウの声は興奮していた。そして玄関から出て行く何
人かの足音が聞こえてきた。
「なに、あんなに怒ってんだろう。バッカじゃない、男なん
てもういいよ。ああ、つまらない、最近おもしろいことない
もんね。サイス、どうしたのかしら、この町が変わると思っ
たけどね」
「海のほうで死体が発見されたって聞いたけどね。あれ、ほ
んとかな」
「あれは別人よ、そんな簡単に死ぬわけないじゃない」
「そうだよ、またぱぁっと現れるよ」
「ねえ、だれの話ししてんの? サイスって、だれ?」
「ええ、アンビだ、バイクに乗った男の人よ、モチが裸で乗
ったり、発炎筒を投げたりして、みんなで騒いだじゃない」
「ああ、あれ、楽しかったけど、なんか夢見たいね」
「夢なんかじゃない、ほんとうにあったんだよ」
「もう、どうでもいいよ、それより外に出よって、ここで騒
げないなら町に出ようって」
「そうね」
「みんな先にいってて、あたし後から行くから」
その声はミュウだった。
賑やかな話し声が玄関のドアの閉まる音で途切れると、部
屋の静寂が引き立った。
ミュウの声が響いた。
「ねえ、トキュウ起きてるよね」
「うん」
カーテンが開けられミュウが顔を覗かせた。
「あれ、ずいぶんすっきりした顔してるじゃない、風呂に入
ったの?」
「どのくらい体を動かせるかと思って」
「それで」
「ほとんどだいじょうぶみたい」
「良かったじゃない、ああ、あたしもシャワー浴びよっと」
そう言うとミュウは部屋からいなくなった。しばらくする飛
ばすタオル一枚体にないて戻ってきた。そして、部屋のあっ
ちこっちを動きまわりながら話し始めた。
「みんな、おかしい、やっぱり変、聞いているだんだん腹が
立ってきた。ねえ、そう思わない?」
「ショウのこと?」
「まあ、あれは色んな事情があるような気がするけど、そう
じゃなくって、モチやレイのことだよ。だって、どう見たっ
て、デザイナーやだんさーにはなれないよ。いまさら甘いよ、
絶対に無理ね。それからマイやサク、歌手世、どうして歌手
になれるのよ、歌が好きとうまいとは別のことなのよ。それ
も判らないんじゃ絶対に無理ね。それに咲く、サクは確かに
私より英語ができるの、どこで勉強した代わらないけど、た
ぶんいつも外人と遊んでいるからだろうね。でも、そこがち
ょっと悔しいのよ。どう見たってあたしのほうがいっぱい勉
強しているのに、できないって言うのはね。あっ、あたしね、
昔刃物図国勉強ができたのよ、学校でトップになったことも
あったのよ。信じられない、ほんとうよ、ああ、イヤだ、そ
んなこともうどうでもいいことよね。たしかサクの話だった
よね。でも英会話を勉強したからってサクに何ができるって
言うの、モチやレイやサクやみんなそうだけど、社会や政治
のこと何にも知らないのよ。とくにマイやサクはあまりにも
何にも知らないのでびっくりするときがあるくらいよ、よく
今まで生きてこれたなあって、これからどうするんだって、
ときどき、もしかしたら何にも考えてないんじゃないかと思
ってぞっとするときがあるくらいなんだから。でも不思議よ
ね、社会のことが知らないからって、自分のことが知らない
かっていうとそうでもなくて、マイもサクも自分のことバカ
で何にも知らないこと、ちゃんと知ってるのよね。あたしだ
ったら絶望して死んじゃうけどね。それでもみんな夢は持っ
ているのよね。そこがおもしろいっていうか、笑っちゃうと
いうか。みんな大人が悪いのよ。夢を語れなんていうから、
大人は夢を持っている子が良い子みたいな言い方をするでし
ょう。でも、誰もがなりたいものになれるって紋じゃないわ
、夢を実現できるなんて本のわずかよ。それに子供の言う夢
なんて、あれは本心じゃないわ、こういうことをいえば大人
が喜ぶことを知っているから言ってるだけよ。本当はいい子
でもなんでもない、子供は大人が思う以上に計算高く残酷で
いつもとんでもないことを考えているのよ。あたしなんてよ
く言い子っていわれてた、それでいちおう皆の前では良い子
を装っていたけど、陰では小さな生き物を殺したり苛めたり
してたわ。ふつう子犬や個ねって誰が見ても可愛いものでし
ょう。でも、あたしの場合最初は可愛い可愛いと思っている
んだけども、急になぜか腹が立ってきて、憎たらしくなって
くるの、カワイ子ぶるんじゃないって、感じかしら。それで
つねったりたたいたり泣き叫ぶまで苛めてしまうの。ほんと
のこと言うとね、ときどき人間の赤ちゃんにも思うときがあ
るの。もしこんなこと大人が聞いたらなんて悪い子と思うん
でしょうね。大人ってこんなとき、これは絶対に教育が悪い
からだって言うんでしょうね。関係ないのにね。とにかく大
人って何にも判っちゃいないのよ。だからすぐレールを敷き
たがるんだよ。子供は何にも知らないから、おだてられると
すぐそれに乗っかって走るのよ。レールはそんなに曲がって
もいないしでこぼこもしていないからきっとらくだと思うの
ね。それにその上を走ると大人たちも嬉しがるからね。とん
でもない地獄よ。あたしたちってそんなに単純ではないわよ。
レールっていったん走り出したら後はもう大人たちが決めた
終点まで行くしかないのよ。その間とに書くわ見目を振らず
ロボットみたいに毎日毎日同じことをやって、前に進むしか
ないのよ。途中で止めるなんて絶対に許されないのよ。なぜ
ならそれはすべての大人たちがすばらしいと思っている価値
観に反することだからなのよ。あたしだって当時は本気でそ
う思っていた。だから大人たちが仕掛けた罠にまんまとはま
ったという感じね。それからそこでは人よりできるだけ前方
に居ることが良いこととされているの、だから前のほうにい
たものが、後ろのほうに下がってくることは、敗北者になっ
てしまったような気になるの、あたしなんかいつも先頭のほ
うに居たので、下がらないように、下がらないようにって、
大変だった。毎日とても苦しかったわ。下がったときが夢に
出てくるくらい恐怖だったわ。ああ、なんでそんな思いをし
なくちゃなんないの、たかが詰め込みの勉強ぐらいで。なん
て息苦しい生活だったんでしょう。なんで大人たちはそんな
ことを子供に押し付けるんだろう。大人ってなんて勝手なん
だろうね。誰だってそんな生活から逃げ出したくなるよね。
そう思うよね。トキュウだって何かから逃げ出したかったん
でしょう。良いの別に言わなくたって。あたし、あるとき思
ったの、大人たちの思い通りになってたまるかって、だって
そのまま行ったらあたしおかしくなるの眼に見えていたもん、
そこであたし考えたの、大人たちの言いなりにならないよう
にするためにはどうしたらいいんだろうかって、そしたら、
気づいたの、大人たちに頼らなければ良いんだって、つまり
親に頼らず自分ひとりで生きれば良いんだってね。これなら
大人たちにあうだこうだって言われなくて済むってね。そこ
であたし家を出たの、誰にも縛られずにやりたいことをやっ
て生きるためにね。あたしね自由のためなら何でもできるの
よ、普通みんながこれは悪いことだからといってやらないこ
とでもね。だってあたしがおかしくなるよりましでしょう。
もう良い子なんてバイバイね。というより、サイスがいうよ
うにもともとあたしたちが何をやろうが自由なんだよね。そ
れにさあたしたちが自由にやることで、あたしを苦しめた大
人たちに復讐できると思うとなんとなく愉快じゃん、大人た
ちはすぐこれはいいことこれは悪いことといって、押し付け
るじゃん、でも、ほんとうはやってみないと判らないんだよ
ね。やってみて初めてどこが悪いんだろうかって思うときも
あるし、たいしたことないじゃんって思うときもあるからね。
それなのに大人たちって、あたしたちがやることを何かとん
でもないことをやっているかのように、騒いだり問題にした
り悩んだりするよね。あたしなんか大人たちが眼を丸くして
なんでこんなことをしているんだっていって本当にこまった
ような顔をするのを何度も見たことがあるわよ。そのときは
ほんとうに良い気分だった。ざまあ見ろって感じね。だって
あんなにあたしを苦しめたんだから、そのくらいの罰受ける
の当然だよ。トキュウだって大人たちに不満があるからこん
なことをやっているんでしょう」
さらにミュウがベットに腰をかけて話し続けた。
「最近なんか変なの、みんなバラバラっていうか、やっぱ中
心になるひとがいないからかしら。サイスがいたときはみん
なまとまりがあったよね。なんか目標みたいな物に向かって
さ、何にも言われなくてもさ、みんな自分から進んでついて
いったよね。ねえ、トキュウ、あんたサイスの代わりやらな
い?」
「それは無理だよ。オレはあんな世間をびっくりさせるよう
なことはできないよ。だいいちオレはバイクに乗れないし、
あんなにかっこよくないし、度胸もないし、それにあまり強
くもないし」
「バイクに乗れなくたって良いのよ、今までどおりで良いの
よ」
「それじゃ誰もついてこないよ。大声で脅したり、万引きや
っても絶対捕まらないっていう自信はあるけど、でもほかに
とりえは何にもないからな」
「そんなことなわよ、そういうことじゃないんだよね、ヘッ
ドって、なんていうか」
「オレよりショウのほうがいいと思うよ。オレより顔は大人
びているし、体も大きいし、それに比べてオレは」
「外見がどうのこうのじゃないのよ、なんていうのかな」
「それにオレにはまだ知らないことがいっぱいあるし」
「知らないことって?」
「社会のこととか、大人のこととか、どう付き合えばいいん
だとか」
「付き合うって、だれと?」
「うん、いろいろと、たとえば女の子とどう付き合えばいい
んだとか」
「なんだ、そんなこと心配してるの、簡単じゃない」
「簡単じゃないよ」
「簡単よ、今までどおりで良いのよ、なんの問題もないわよ」
「そういうことじゃなくって」
「なにが、どういうことよ」
「うーん、オレは、オレはサイスみたいなことはできないっ
てこと、女、女の子をバイクに乗っけたりしてさ」
「ああ、そう、そういうことを心配してたの」
「それならなおさら簡単よ、練習すれば良いのよ」
「練習、どうして?」
「あたしと、そう、あたしとね」
ミュウが自分のバスタオルをはずしてべっとに上がってき
た。そしてトキュウのバスタオルを剥ぎ取りながら言った。
「私たち女にはよく判んないんだけど、
男たちにとってはいつも何か特別な意味がある見たいね。
こんなに判りやすくて単純なことなのにね。
正直言って、
私の男の人の考えていること、
よくわからないわ。
突然乱暴になったり、
大人しくなったりすんだから。
それに男の人って、
とても理解できないことをやったり、
やってくれないと言ったりするからね。
こんなことにどういう意味があるんだろうって、
思うようなことをね。
でもやってくれって言われればやってあげるけどね。
そんなにイヤでもないからね。
私にとってほんとうにイヤなことは、
そんなことじゃないのよ。
どんなに理解できなくても、
ほとんどの男の人は最後は、
ひとりの人間に戻るのね。
男としてわからなくても、
人間としてわかれば、
それでほっとした気分になるのね。
でもなかには、
人間に戻れない男がいるのよ。
ずっとプラスチックのおもちゃみたいな顔してさ、
張り合いがないって言うか、
とてもがっかりした気分になるのね。
もしかして何にも考えていないんじゃないかと思って、
ぞっとするときもあるのよ。
でもこれはマイたちに感じるものとは、
別のものなのよね。
マイたちのときは、
なんか寂しいっていうか、
どっか悲しい気持ちが含まれているんだけどね。
でもこの場合はとにかく暗いって言うか、
冷たいっていうか、
とても沈んだ気持ちになるのよね。
トキュウってとっても判りやすい。
なんかとても自然って感じね。
初めは何でも仕方ないのよ。
余計なところに力が入ったりしてね。
でも何度も練習すれば、
その内にもっと楽にできるようになるわよ。
ねえ、今度は電気を消してやってみよう」
トキュウは久しぶりに繁華街に出た。風景は光り輝き、雑
踏はめまぐるしく、仲間たちは生き生きとし、トキュウはじ
ょじょに気持ちが高まっていくなかで、町全体が以前と変わ
りなく自分を歓迎しているかのように感じた。
その仲間たちのなかにトキュウは見かけない顔を見かけた。
ショウがさっそく紹介にかかった。
「こいつらはゲンとダイだ。これが噂のトキュウだ。なんだ
その顔は、もっと強そうな男だと思ったのか、見かけで強い
か弱いかわかんないぞ。喧嘩ちゅうのはな、実際にやってみ
ないと判んないだからな。なんセ、十人のヤーボーとやりあ
ったんだからな」
それ聞いてもゲンとダイはまだ不思議そうな顔をしていたが、
トキュウたちは誰が言い出したわけでもないのに自然と歩き
出した。歩きながらゲンとダイがタイヨウをからかいだした。
そしてお互いにたたきあったり、首を絞めあったりしながら
ふざけあっていたが、そのうちゲンがトキュウに近寄ってき
て話しかけた。
「テヌキはやるんか?」
「テヌキって?」
「万引きのことだよ」
「ああ、毎日さ」
「捕まったことないんか?」
「ないさ、そんなへまならないよ」
「じゃ、狩は?」
「しょっちゅう」
「今まで、どの位?」
「数え切れないくらい」
「オレさ、人をさして院から出てきたばかりなんだ。最近、
なんか、みんな迫力ねえやつばかりでさ、組むきしないんだ。
トキュウ、お前人を刺したことあるんか?」
「ああ、あるさ、二度ばかりな」
「そりゃあ、そうだろうな、ヤーボーとやりあったんだから
な。そのくらいの度胸はあるだろうな。なんかみんな根性の
ねえやつばっかりだよ。ハナはどうだい?」
「ハナって?」
「ハナは女って決まってるだろう。知らんのか」
「もちろん知ってるさ、それで?」
「だから、何人やったんだよ」
「やったって?」
「レイプだよ、レイプ」
「ああ、数え切れないな」
「手当たり次第ってか」
「まあ、そんなもんだな」
そこへダイがやってきてトキュウの顔をのぞきこみながら話
しかけた。
「あのさ、ショウから聞いたんだけど、お前切れるとおっか
ないんだってな、すげえ迫力なんだってな、一度見てみたい
もんだよ」
そのとき繁華街から外れた交差点を渡り始めると、ミュウた
ちが反対側からやってきた。近寄ってくる
まミュウが立ち止まりトキュウにはなしかけた。
「ねえ、今日、集まる?」
「たぶん、十二時ごろかな」
「わかった、あとでね」
それだけですれ違うとダイがトキュウに話しかけた。
「あれはお前の彼女か?」
「違う、友達だよ、仲間かな」
「集まるってなんのことだ?」
「ああ、あれは公園の広場に集まるってことだ」
「集まって何やるんだ?」
「なにって、いろいろと。とにかく暇になったら集まるんだ」
「あんまり楽しそうじゃないな。オレはもっとおもしろいと
こ知ってるぞ。駅の反対側の暗い路地があるところだ。神社
があってな、女を連れ込むにはちょうどいい林があるところ
だ。もしオレが頭だったら、そっちで遊ぶな」
いつのまにかトキュウたちは繁華街から遠く離れた歩道を歩
いていた。通りには切れ目なく車が走り続けていた。ゲンが
近寄ってきてトキュウにタバコを勧めた。
「あれは頭が痛くなるから吸わないんだ」
とトキュウは断った。
「初めはみんなそうなんだよな」
と言いながらゲンはひとりで吸い始めた。
しばらくして角曲がると不意に見慣れない若者たちのグル
ープとすれ違った。歩みを止めたトキュウたちは、気持ちの
高ぶりを感じながら振り返りその姿を眼で追った。その数は
五人だった。ダイがゲンキに言った。
「知ってるのか?」
「うっ、いや、はじめて見るやつらだ」
「なんかお前のことじろじろ見てたぞ」
「いや、見たことない」
「どこへ行くんだろう?」
「きっと中心だな」
「なんでみんな同じような服着てんだ?」
「あんなのにうろちょろされたんじゃ、目障りだな」
「トキュウ、追わないのか?」
「町を取らないのか?」
五人の後姿にじっと眼をやっていたトキュウが答えた。
「ああ、うん、そうだな、じゃ戻るか」
トキュウたちは五人の後をつけた。次第に距離を縮めなが
ら執拗に追った。繁華街に入った。どんなに人ごみで混雑し
ていても、トキュウたちにとっては五人の姿しか眼に入らな
かった。やがてすぐ背後にまで迫ったとき、五人は気づき立
ち止まり振り返った。トキュウたちの緊張は急激に高まった。
五人のなかの一人が言った。
「なんでついて来るんだ?」
「お前らが勝手に前を歩いてんだろう」
「もうついてくるなよ」
「違うんじゃないの、似合わないんだよ、その服は」
「お前らに関係ねえだろう」
「あるんだよ。目障りなんだよ」
このとき二つの集団の緊張は頂点に達した。
「ぐだぐたぬかすんじゃねえよ」
とトキュウが、突然人が変ったように怒りの表情で大声を上
げると、五人に向かって歩き始めた。と同時に他のものたち
もトキュウを追い抜く勢いで突進した。すると五人は取り囲
んでいた群集のあいだから散り散りになって逃げて行った。
トキュウたちは人ごみを縫って追いかけたが、五十メートル
ほどですぐ止めた。みんなこれ以上必要がないと思ったから
だ。
トキュウたちは再び集まった。ゲンがトキュウに近寄って
きた。
「あれじゃだれだってビビルよな」
「喧嘩は最初で決まっちゃうんだ」
「こんなに簡単に決まるとは思ってなかったよ」
「これじゃ、ほんとに取れるぞ」
トキュウたちは人ごみのなかを悠然と歩きだした。やや興
奮が収まりかけたころ、トキュウはビルの隙間の星の見えな
い空に眼をやりながら、ふと、あることに気づいた。自分が
どんなに怒りに身を負かせ我を忘れたかのように行動してい
ても、自分は決して自分より強そうな相手の前では切れない
ということに。
十二時が近づくと、トキュウたちはだれが言い出したわけ
でもないのに、自然と公園のほうに向かって歩き始めた。や
がて公園につくとみんな思い思いに広場に向かって階段に腰
を下ろした。途中姿が見えなくなっていたゲンが後からやっ
てくると、手に持っていた二本の缶ビールをトキュウたちに
勧めた。そこでみんなで少しずつまわし飲みをた。トキュウ
はジュースのように勢いよく飲んだ。冷たさのなかにたとえ
ようもない苦味を感じた。
ゲンキが言った。
「なんだタイヨウ、初めて飲むみたいな顔して」
「初めてじゃないよ、あんまり冷えてねえなあと思って」
「そりゅあ仕方ないさ、ずっと手で持ってきたんだから。ど
うだ気持ちいいだろう。オレはさ、もっと気持ちよくなるも
の知ってるけど、そのうちにな」
トキュウはだんだん頭がボォッとしてきて、周囲の様子が
判らないらい気持ちよくなってた。やがてじょじょに普段の
感覚が戻ってくると、みんなの話し声が耳に入ってくるよう
になった。
ゲンの声だった。
「へえ、そうだったの。オレが居ないあいだに色んなことが
あったって聞いたけど、みんなお前たちだったのか。すげえ
なあ、いったい誰がやれって言ったんだ、トキュウ?」
「いや、トキュウじゃない、サイスってやつがいて、そいつ
が全部命令したんだ」
「サイス? だれでそいつは?」
「急に現われたんだよ。あるときみんなでここにこうして座
って居ると、あの林からバイクに乗って出てきたんだよ。そ
れが運転がうまいんだ。天才だな」
ダイが言った。
「ふん、バイクに乗るのか、いったいそいつはどこに居るん
だ?」
「ビルの屋上から川に飛び込んで、それっきりさ」
「死んだのか?」
「判らない、百メートルは飛んだからな」
「名前はなんていうんだ? ほんとうの名前だよ」
「知らない」
「年は?顔は? 顔はどんな顔をしてるんだ?」
「年はわからない。いつもサングラスしてたから。大人にも
見えたし若くも見えた。いやあ、とにかくうまかったな、あ
んなぼろバイクでさ、よくあんなことができたよな。ぽんぽ
ん飛ぶんだぜ、パトカーからパトカー、ビルからビルへとな」
「そうなんだ、サイスがどんなに交通違反しようとも、結局
警察は捕まえることができなかったもんな、いつもえらそう
にしてるくせに、あんなに無能だとは思わなかったよ」
「あれも凄かったぜ、裸の女の子を前に乗せてさ、繁華街を
走りまわったんだぜ」
「いうこともよかったぜ、大人とはまったく反対なんだ。俺
たちは自由なんだから何でもできるんだって、やりたいこと
は何でもやれってな、それからいつも最後に言ってたよ、決
して良いことをするなってな」
そのときサンドが後ろを見ながら言った。
「あのモチって子さ、裸でバイクに乗ったのは」
いつのまにかミュウたちがやってきて、トキュウたちの後ろ
のほうに座っていた。
そのモチが言った。
「あたしがなんだって、あっ、タバコ飲んでる、ビールもの
だ」
「よく買えたわね。あっ、買うわけないか」
ゲンは女の子たちのいうことを無視するかのように話し始め
た。
「当たり前じゃないか、買ってまで飲むもんじゃないよ。オ
レはさ、万引きではだれにも負けないよ。あれはとにかく度
胸だから堂々としてれば良いのさ、コソコソするからかえっ
て眼だって捕まったりするのさ。オレの最高は店先からバイ
クをかっぱらったことさ。客のような顔をして行ってさエン
ジンを掛けてそのまま乗ってきたんだよ。あとはそれを乗り
捨てさ」
少女たちの誰かが言った。
「ねえ、どうして大人の真似なんかするん? そんなに早く
あんなだらしない大人になりたいん?」
「いいじゃない、なにをやったって、あたしたちってやりた
いことをやる人たちじゃない。だいじょうぶさ、ビールを飲
んだぐらいで、つまらない大人になんかならないから」
サンドが少女たちの話を無視するかのように話し始めた。
「とにかくサイスのやることは人間離れしてるんだ。やつが
命令することなんか、なんでこういうことするんだって、最
初は意味がよく判らないんだけど、実際やってみるとそれが
結構楽しいんだよね。よく燃やしたな」
ゲンが言った
「いいことするなか、どんどん悪いことをやれってことだな。
さすがだな、それこそほんとうのリーダーってもんだな。で
も、オレに言わせりゃ、ちょっと甘いな。やっば、町を取ら
なくちゃ、もっと仲間をふやして、結束してさ、どっちがが
強いか決着をつけてさ、名前を広めるんだよ。そうすれば金
だって自然に集まってくるしさ、それからさ。どうせ悪いこ
とをやるんだったら、少年院に行く覚悟でもっそ激しくやら
なくっちゃね。自由でなんでもてきるんだっていうのはちょ
っと腰が引けてるって感じだな、悪をやるときはもっと徹底
しないと、オレから見るとリーダーとしても少し物足りない
な。なあ、トキュウ、お前だったらそんな半端なことしない
よな、なんせ手当たり次第だもんな」
「ああ、まあな」
「それでさ、おもしろい遊びやってみないか、ここで何にも
しないでボォッとして立ってつまらないじゃないか。あのさ、
この公園の林の向こうは、あんまり人が通らない道路だよね。
そこでさ、最初に通った女をやっちゃうてのはどうだい」
「ババアでもか」
「そうだよ」
「子供でもか」
「子供は今時間通らないだろう」
「よし、やってみようじゃないか」
「やろう、やろう」
トキュウと若者たちはいっせいに立ち上がると、広場を横
切り林の奥へと入っていった。暗い林を抜けると水銀灯に照
らされた目当ての道路が現れた。トキュウたちはそれぞれ木
や植え込みの陰に身を潜ませた。しかし、人どころか車さえ
通る気配はなかった。
三十分後にようやく一台の車が通った。サンドが沈黙を破
った。
「通る訳ないよ、こんな時間に」
「女だけじゃない、だれだって通らないよ」
「だからいいんじゃないか」
「それもそうだな」
「もし通ったら、最初はだれがいい」
「それはやっぱり、トキュウだろうな」
「そうだ、トキュウだ」
何事もなくそれから三十分経過したときだった。ダイが突
然声を上げた。
「おっ、静かにしろ、誰か来た。若い女だ。制服だ」
「女子高生みたいだぞ」
「なんでこんな時間に、普通の子だぞ」
「きまりだからなあ、しかたがないなあ」
「さあ、トキュウ、お前からだぞ」
「ひとりでだいじょうぶか?」
「だいじょうぶさ」
「もし暴れて手に負えなかったら、手伝ってやるよ」
「まかせとけ」
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
トキュウは気づかれぬように背後にまわり後をつけた。そ
して足を速めて追いつくと、後ろから首に腕を掛け、そのま
ま引きづるようにして林の中へと連れ込んだ。少女は最初驚
いたように小さく悲鳴を上げたが、なぜかそのあとは抵抗ら
しい抵抗はしなかった。トキュウはそのことに何の不思議も
感じなかった。自分の持っている力が少女を無抵抗にさせて
いると思っていた。トキュウは周囲に群がる仲間を意識しな
がら、正当な行為のように最後まで自然に成し遂げた。
そしてトキュウが少女から離れるとき初めて少女の顔を見
た。すると一瞬その眼はくぎ付けとなった。薄暗くはあった
が少女が誰であるかはっきりと判ったからだ。それは間違い
なくあの写真に映っていた少女だった。
そのとき周囲が突然騒がしくなった。道路のほうや林のな
かからも複数の人間の声や足音が聞こえて来た。誰かが
「ヤバイ、逃げろ」
と小さく叫ぶと、みんないっせいに駆け出した。若者たちは
できるだけ林の奥の暗いほうへと向かって走った。 やがて
広い道路に出た。舗道に人影はまったくなく、反対側には夜
空に黒いシルエットとなって高層ビルが聳え立っていた。ト
キュウたちは猛スピードで走りぬける車の間を縫って道路を
横切った。あちこちでクラクションが鳴らされたが無事渡り
終えるとようやくゆっくりと歩き出した。
そしてすぐにゲンがトキュウに近寄ってきた話しかけた。
「やるじゃないか、さすがだな、ビデオ見てるみたいだった
ぞ」
「ああ、まあな」
とトキュウはややぶっきらぼうに答えた。ダイも近寄ってき
た話しかけた。
「うますぎるな、相当やってるな」
「ぜんぜん、抵抗させないもんな」
「なんかコツがあるみたいだな」
仲間たちが次から次へと話しかけてきたが、トキュウの頭
にはほとんど入ってこなかった。地響きを立て風を起こして
走る巨大なトラックの群れに眼をやりながらトキュウは、な
ぜあの写真の少女があそこを歩いていたのかと不思議な気持
ちになっていた。
トキュウたちは点滅する電波塔を目印にしながら再び繁華
街へと向かった。やがて少しも衰えることのない華やかな光
の群れがトキュウたちを包み込んだ。そしてやや人通りの少
なくなった通りを舗道いっぱいに広がって歩いた。歩きなが
らトキュウたちは、誰かがかわるがわる運んでくる飲み物や
食べ物で空腹や渇きを癒した。見そして、みんなで有り金出
し合ってゲームセンターで遊んだあと、この町でもっとも賑
やかな通りに入ろうとしたとき、前方に気になる若者たちの
一群を発見した。しかし止まることなく進んでその距離が五
六メートルに迫ったとき、その若者たちはみんな青いTシャ
ツを身につけていて、人数も二十名ほどだとわかった。そし
てそのなかには、数時間前にトキュウたちが暴力的に追い払
ったものたちもいることが判った。しかしもう手遅れだった。
両方の若者たちにとって、一瞬のうちに高まった緊張と興奮
は、不安と恐怖のなかで一瞬のうちに開放するしかなかった。
若者たちは周囲の人ごみを忘れたかのように激しく衝突した。
しかし、トキュウたちは九人、数には勝てなかった。じりじ
りと後退し、だんだんバラバラになり、やがて一人一人ちり
ぢりに逃げるしかなかった。
衝突はあまりにも突然だったため、最初トキュウはみんな
と同じように激しく興奮して立ちむかったが、そのうちにな
ぜか不思議なほど冷静に状況を把握しながら行動することが
できるようになった。そのためほとんどダメージを受けるこ
となく逃げることができた。
トキュウはまず繁華街を取り巻く通りを歩きながらバラバ
ラになった仲間を探し始めた。やがて一人二人と見つけるこ
とができた。しかしタイヨウとゲンキとコウイチはどうして
も見つけることができなかった。
トキュウたちは電波塔の下に腰をおろした。しばらくはだ
れも何も話さなかった。繁華街のほうから聞こえてくる救急
車のサイレンの音がやがて聞こえなくなったころ、サンドが
沈黙を破った。
「タイヨウが刺されたかもしれない。あいつ弱そうなくせに、
めちゃ暴れるんだから、逃げれば良いのにさ、やつらもマジ
だからな、タイヨウに脅しが効かなかったんだろうな」
「ゲンキ、五六人にかこまれていたもんな、あれじゃ助けよ
うがないもんな」
「コウイチもやられたみたいだ」
「なんだ、やられたのはみんな弱そうなやつばかりじゃない
か、だらしねえな」
「ちがうよ、やつらが弱そうなやつばかりを狙って攻撃して
きたんだよ。だれだって強そうな奴とやりたくないよ」
「数だよ、向こうの数が多すぎるよ」
「オレさ、ケイタ見たよ。昔からのダチが居たみたいなんだ。
でもオレはイヤだな、あういう連中、強いかもしれないが、
大先輩みたいなのがいて、みんなを集めて説教があったり、
礼儀がうるさかったり、決まりみたいなのがあったり、それ
に自分では使えない金が掛かるみたいなんだ。コウイチもこ
っのほが気楽で良いって言ってた。」
「それが自由ってことだよ。俺たちに規則なんて必要ないの
さ」
「やつらいつの間に人数を増やしたんだろう。オレは全員の
顔を知っているけど、強そうなやつなんか一人もいないじゃ
ないか、なんで急に勢いづいたんだろう、カッコつけやがっ
て」
とショウが少し悔しそうに言うと、ゲンがすかさず言った。
「俺たちも仲間を増やせば良いじゃないか、このままやられ
っ放しでいいわけないだろう、眼には眼、歯には歯だよ」
「やつらがナイフをちらつかせるなら、こっちだってやるし
かないだろう、持ってるものは使わないとな、やられたらや
り返すのさ、だれか持ってないやつはいるか、オレが今度も
って来てやるから」
「でもさ、俺たちはやる気あるけど、トキュウはどうなんだ。
さっきから何も言わないけど」
「もちろんやるさ、やられたらやり返すさ、オレ一人だって
やるさ。でもな、向こうの人数が多すぎるよ」
「少ないときにやるんだよ、やつらが集まってないときに」
「やみうちだな、それもおもしろいな」
サンドがやや苛立ちながら言った。
「関係ないよ、どんなに人数が多くたって、それならこっち
は車で突っ込めばいいんだよ、けちらしてやるよ」
「サンド、お前免許持ってるのか?」
「関係ねえよ、免許なんて」
「車はどうするんだ?」
「そこら辺に転がってるじゃないか」
ダイが言った。
「そうだよ、人数なんて関係ないよ。さっきはいきなりだっ
たからあんなになっちゃったけど、問題は度胸だよ、こっち
がどれだけマジかってことを見せればいいんだよ。マジでや
るぞってな、やつら同じ色のシャツなんか着てまとまってい
るように見えるけど、わかんねえぞ、根性のない奴らに限っ
てあういうことをしたがるんだ。案外いざとなったら、びく
びくかもな」
ショウが言った。
「そうさ、なにも恐れることはないさ、へいきだよ、だって
こっちにはみんなを勇気付けるあれがあるじゃないか」
ショウは余裕の笑みを浮かべながら話しつづけた。
「あれだよ、トキュウが切れるときに発する叫び声のことだ
よ。あれを効くとオレは頭も体も全部熱くなって、もうどう
なってもいいやという気分になるからな、それはもう怖いも
のないって感じだもんな」
「オレもさ、あれを聞くと全身に力がわいてくるって感じだ
もんな」
「ようし、やってやろうじゃないか、やつらが百人になろう
が、千人になろうが、関係ねえぞ」
ダイが言った。
「それからさ、どうせやるなら、みんなが見てる繁華街で堂
々とやろうじゃないか。あのスクランブル交差点がいいな、
あそこだと車も通るし人もどんどん集まってくるから、目立
つぞ、とにかく大騒ぎになるだろうな」
ゲンが言った。
「オレさ、ワルいのちょっと知ってるから、うまく行けば俺
たちの仲間になってくれるかもしれない」
トキュウが冷静に言った。
「大丈夫さ、きっとうまく行くさ、もう、さっきみたいなへ
まはやらないよ。絶対にやられたことはやり返すさ、眼には
眼、歯には歯だよ」
「そうだ、そうだ」
と周囲からだれとはなく声が上がった。それを聞いてもう誰
も自分たちの決意を疑うものはいなかった。みんな自信と勇
気に満たされていた。
トキュウたちは今夜十時再びこの場所に集まることを決め
た。そしてそれぞれの目的のためにバラバラに別れた。
トキュウとショウは以前寝泊りしていた無人のビルに向か
った。やがてそのビルに到着すると、ショウは外に放置され
ていた錆付いた椅子を部屋に持ち込み、それを踏み台にして
換気口のふたをナイフでこじ開けると、中から両手代の銀色
の袋を取り出した。そして床に腰を下ろすと袋を開けながら
言った。
「こんなところに隠しているとは思わなかったろう。よかっ
た、なんともなくて、オレの宝物だからな、とうとう役に立
つときが来たな、これをみんなに配ってと。人から奪ったも
のもあるけど、ほとんど店からてただいたものなんだ」
トキュウはそれを聴きながらダンボールの上に横たわって眼
を閉じた。そのうちショウも黙って横たわった。
やがてトキュウは寝苦しさを感じながら目覚めた。その原
因は外からの騒音だった。激しく地面を打ちたたく振動音が
絶え間なく続いていた。暑さも余計に気になりもう眠ること
ができなくなっていた。トキュウは激しくイラつき怒りを覚
えた。そして起き上がるとその音のする方へとビルの中を歩
いていった。すると二階の通路の窓から道路工事をしている
のが眼に入ってきた。泥とアスファルトにまみれた五六人の
大人が強い夏の陽射しを受けながらもくもくと作業をしてい
た。みんな顔を赤レンガのように高潮させ眼もどことなくう
つろであった。トキュウは窓を開け
「うるさいんだよ、眠れないじゃないか」
と怒鳴った。すると一人の作業員がトキュウに弱々しい視線
を向けて
「どうも吸いません」
といって頭を下げた。するとその隣に居た別の作業員が手を
休め舗道の木を見上げながら言った。
「これはなんという木だ」
「サルスベリだ」
「ああ、このクソ暑いのにサルスベリとは」
トキュウは窓を閉めると部屋に戻った。するとショウが話
しかけてきた。
「何かあったのか?」
「いや、道路工事があまりにもうるさいんで怒鳴りつけてや
った。そしたら、そしたらだよ、変なんだ。いい年をしたオ
ヤジがあれに謝るんだよ」
「怖そうに見えたんだよ」
「そうかな、汚ねえ格好してさ、今にもぶっ倒れそうな顔し
てさ、笑っちゃうよな、オレに誤るんだから。ああ、なんで
あうやってまで働かなきゃいけないんだろうな、オレはイヤ
だね、こんな暑いにも仕事をするなんて」
それっきり二人は何も話さなくなった。
夕方二人は静かな気配のなかでふたたび目覚めた。もう外
は薄暗くなっていた。二人は周囲を気にしながら外に出て公
園に向かった。公園に着くと二人はいつものように水道で顔
を洗った。街灯の光を受けてひときわ光り輝く水しぶきを撒
き散らしながら、トキュウは予想以上に水が冷たくなってい
るのに気づいた。そして思わず口走った。
「なんで、こんなに急に冷たくなったんだい」
「もう夏も終わったってことだよ」
「こんなに突然かよ。それでこれからどうなるんだよ」
「秋が来て、寒くなって、冬が来るんだよ」
「いいよ、このままで、秋なんて来なくたって」
「しょうがないさ、季節だから」
二人はどうしようもなく空腹を感じたのでミュウのマンシ
ョンに行った。部屋にはミュウがひとりで居た。二人を見て
ミュウが怒ったように言った。
「どこにいってたの捨てられた子犬たちが待ってるよ。そこ
のカーテンの後ろよ」
ショウがカーテンを開けると顔を腫らして力なくベットに
横たわっているゲンキとコウイチがいた。ミュウがさらに言
った。
「ねえ、どうして助けなかったの?」
トキュウが答えた。
「いきなりだったから、それに人数も多かったから、逃げる
だけで精いっぱいだったんだよ」
「じゃ、どうしてほっといたの、ビルの隙間に隠れていたの
よ」
「探したさ、でも見つからなかったんだよ」
そのとき玄関のドアが開いてモチとレイとマイが入ってき
た。そしてその後ろには顔と腕を包帯で巻いたタイヨウがつ
いてきていた。モチが言った。
「町をうろついていたのよ。トキュウにあいたいって言うけ
ど、判んないじゃない、どこにいるか、で、ひとまず連れて
きたの。ああ、よかった」
仲間の顔を見てタイヨウはほっとしたように笑みを浮かべ
て言った。
「病院を抜け出してきたよ。うるさいんだよ、家族はどこに
居るんだって、関係ねえさ、だから逃げてきたよ」
ミュウが言った。
「こんなに仲間がやられて、これからいったいどうするんだ
ろうね」
トキュウが答えた。
「とりあえず腹が減ってるんだけど」
「ああ、判った、さあ、みんなで冷蔵庫にあるもの全部持っ
てきて」
まもなくテーブルの上は飲み物や食べ物でいっぱいになっ
た。トキュウたちはさっそく食べにかかった。
モチが言った。
「あたしデザイナーになるの止めようかな。今日さ働きなが
らデザイナーになれるっていう会社に入った友達とケータイ
で話したの、そしたらその娘が言うには、デザイナーの勉強
なんかぜんぜんできないんだって、朝から晩までこき使われ
て、毎日が同じことの繰り返しなんだって、それでイヤにな
って止めたいっていてるから、あたしも、止めようかなって」
「でも、モチは学校に行くんだろう」
「そうだけどさ、お金が掛かるでしょう。遊んでばかりいる
からあんまりたまっていないのよね。それよりほんとのこと
いうと、あたし、なんか急に子供が欲しくなったのよね」
「子供?」
「赤ちゃんよ、最近電車なんかで見かけると、わっ、可愛い
って思うときがあるのよ。このままさらっちゃおうかなって
思うときがあるのよ、ねえ、そんなときない?」
「ちょっとね」
マイが突然ように立ち上がりながら言った。
「あたし帰る。約束があるの、今日なの、お金を返してくれ
るって約束した日は」
「あら、マイ、まだあんなこと信じてたの。バカみたい、返
ってくる訳ないじゃん、あんたはだまされたのよ」
「まあ、いいじゃない、マイが信じているなら。でも、あん
まり期待しないほうがいいよ」
マイが出て行くとミュウがトキュウたちに勢いよく話しか
けた。
「ねえ、このままやられっ放しで良いの、なんにもしないの
?」
トキュウが食べながら答えた。
「そんなことないさ、今夜やり返すさ、倍にしてな、みんな
で決めたんだ。逃げ隠れしないでどうどうとやろってな。そ
れも人前で目立つようにできるだけ派手になって、それであ
のスクランブル交差点がちょうどいいや、ということになっ
たんだ。あそこで騒ぎを起こせば、文句なしに人が集まって
くる、そうすればやつらだって、なんだと思ってやってくる
だろう、そこだよ」
ミュウが言った。
「そうこなくっちゃね、あそこならきっと野次馬がうじゃう
じゃ集まってくるね、久しぶりに大騒ぎができるじゃん。そ
れで、どうやって騒ぎを起こすの?」
「うん、まだ決めてないんだ」
ミュウが不適な笑みをうかべて言った。
「あたし、まだ、あのときの発炎筒を持ってるの。それに花
火をつけて、爆竹も良いね、それからなんかに火をつけて燃
やそうよ。音と光と煙、完璧だね。ますます人が集まってき
て大騒ぎだね。さあて、なにを燃やそうかしら、これがいい、
ふるすぎてやくたたずのでんわき、時代遅れのCDプレーヤ
ー、それに目覚まし時計、なんでこんなもの買っちゃたんだ
ろう。真面目に起きようなんて思ってたのかしら。笑っちゃ
うね。それからこんなものはもういらない、色んな契約書が
あるけど。ええと、これもいらない、初めは可愛いと思って
たけど、ときどき無性に腹が立ってぶち壊したくなるときが
あるの、このロボット犬、まだまだあるわ、もうぬいぐるみ
なんていらないね、これも燃やそう」
モチが言った。
「ねえ、ミュウ、これはどう、ワープロって言うんだっけ」
「あんたが持つていくなら、いいわよ、燃やしても」
レイが言った」
「ねえ、電子レンジはどうする」
「だれがそんな重いものもって行くのよ、あんたが。そんな
の持っていったら目立っちゃって変に思われるよ。捨てても
でいいんだけど、あんまり使わないから。デモね、ぬいぐる
みやプレーヤーならもって歩いていても変じゃないけど、で
も電子レンジはねえ、おもしろいけどね。それでさ、やつら
に勝つ自信はあるのかしら」
とミュウがトキュウの方を見ながら言った。トキュウが答え
た。
「色いろ作戦があるからね。それに助っ人が来るみたいなん
だ」
「やるのは何時ごろ?」
「そうだな、十一時ごろかな」
「判った、それまでに騒ぎを起こせば良いのね。ああ、わく
わくする、また町中が大騒ぎになるのね。おもしろくないオ
ヤジどもがまたバタバタするのね。ざまあみろだよね。でも
今夜は何かもっととんでもないことが起こりそうな気がする。
あたしたちは確実に前に進んでいるね」
「十一時、ねえ、そのまえにカラオケに行けるね」
「あたしは踊りたい」
やがて少女たちははしゃぎながら部屋を出て行った。
それまでもくもく食べていたゲンキが満足そうな笑みを浮
かべながら言った。
「今日、絶対にサイスが来るような気がするよ。とんでもな
いことってそのことだよ」
「へえ、来て、どうするんだろう
「みんなをあっと言わすんだよ、大騒ぎになってさ」
ショウがさえぎるように言った。
「来なくたって良いさ、やることはもう決まったんだから、
怖気づいたんなら別だけど」
「そんなことないさ、やられたからにはやり返すだけさ」
「タイヨウはちょっと無理だろうな」
そのときショウが銀色の袋からナイフを取り出しながら言っ
た。
「見てみろ、いいだろう、いざとなったらこれで戦うんだ。
もう舐めなれることはないよ」
ゲンキとコウイチが眼を輝かせながらナイフを手にとって見
た。トキュウが言った。
「今夜十時にあの電波塔の下に集まるんだ。そしてゆっくり
とあのスクランブル交差点にって、やつらが現れるのを待つ
んだ。それからだな俺たちの本当の力を見せるのは。それま
では目立たないようにバラバラになっていたほうがいいかも
しれない」
トキュウの言葉にみんな納得したようだった。
そしてトキュウたちはタイヨウひとりをミュウのマンショ
ンに残してそれぞれ別々に町に入っていった。
トキュウは一人で夜の街を歩いていた。そしてあるスーパ
ーマーケットのまえを通りかかったとき、かつて自分とトラ
ブルを起こしたあの店員がまだいるかどうか、なぜかとても
気になった。トキュウにとって、その店員とのトラブルは決
してイヤな思い出ではなかった。むしろその店員に親近感を
覚えるような、懐かしさを感じるような思い出であった。
トキュウはなかに入った。そしてひととおり店内を歩いた
がその店員の姿を見つけることはできなかった。やがて閉店
を告げる音楽が流れてきた。トキュウはなんとなく居心地の
悪さを感じながら急いで外に出た。
すると大音響になかで突然眼の前にポツンと立ち尽くす身
長後六十センチの女の子の姿が飛び込んできた。大音響はそ
の小さな女の子の泣き声だった。女の子は泣くことだけに全
精力を注いでいるためか、そこから動こうとする気配はまっ
たくなかった。その鳴き声は、街路樹の葉を揺らし、窓ガラ
スを響かせ、町のすべての騒音をかき消しながらビルとビル
のあいだにこだまする雷鳴のようにとどろき渡った。
その小さな女の子の十メートル前方には母親らしい女性が
ときおり後ろを振り返りながらゆっくりと歩いていた。それ
を見てトキュウは、その女の子は自分の欲しかったものが買
ってもらえなかったので泣いているんだと思った。そしてな
ぜか自分も泣きたい気持ちになった。それは、それが何かは
ハッキリしないが、遠い昔の出来事に懐かしさを覚えたから
だった。
トキュウはさらに一人で夜の街を歩き続けた。
そしてふとビルの間から電波塔を眼にしたとき、自分には
目的があることに気づいた。
トキュウは電波塔の方向に歩みを進めた。そしてしばらく
すると心臓が急にどきどきするのを感じた。やがて、電波塔
について仲間の姿を眼にしたとき、それは自然と感じなくな
っていた。
約束の十時までに全員の顔がそろった。
ショウはさっそくまだナイフを持ってないものに自分のナ
イフを選ばせた。
サンドがトキュウに近づいてきていった。
「ダメだった、適当な車が見つからなかった」
するとゲンも近づいてきて言った。
「話はしたんだけど、みんな乗り気じゃなくって」
トキュウが言った。
「これで十分さ、俺たちだけでやれるさ」
トキュウたちは町の中心街へとつながるスクランブル交差
点へと向かった。その交差点が眼の前に迫ったときトキュウ
たちは、ミュウたちがひと騒動起こすときまで一人一人分か
れて潜伏することを決め、バラバラになった。
トキュウは交差点から五十メートルほど離れた植え込みの
陰に腰を下ろした。そしてときおり交差点のほうに鋭い視線
を投げかけがら、かつてないくらいじっくりと通り過ぎる人
々を観察した。しばらくするとまたあの心臓のドキドキを感
じた。トキュウは大きく深呼吸すると
「こんなときに、どういうことだこれは」
と呟きながら、げんこつで自分の胸を激しくたたいた。しか
しいくら時間が経ってもどきどきはおさまりそうになかった。
トキュウがうなだれて得体の知れない不安を感じ始めてい
たとき、交差点のほうから車が次々と急停車する音が聞こえ
てきた。すばやく顔を上げてみると、交差点はもうもうと立
ち込める煙に包まれ、続いて連続する爆竹音のなかを四方八
方に花火の火の玉が飛び散り始めていた。
トキュウは立ち上がると人ごみにまぎれながら交差点に向
かって歩いた。トキュウがついたとき、交差点には、普段な
ら通り過ぎていたに違いない人々が群集となって、その周囲
に立ち止まっていた。
発炎筒が三本交差点の真ん中あたりで、まだかすかに煙を
上げて燃えていた。そしてひとつの信号機の支柱が根本から
炎を上げて燃えていた。
騒然とした雰囲気になってはいたが、集まってきていた人
々はみな不思議にも満足そうな笑みを浮かべながら、絶えず
何か面白いことを期待するかのような好奇の眼差しを周囲に
投げかけていた。
トキュウはこれはきっとミュウたちの仕業に違いないと思
うと急に力が沸いてくるような気がした。そしてトキュウは
群衆の中に昨夜の青いシャツを着たやつらがぽつぽつと現わ
れ始めたのを発見して、すべてが予想通りだと思った。その
うち青いシャツ者たちが一箇所に集まりだすと、トキュウた
ちも群集のなかに仲間を発見しあいながら、その反対側に集
まった。まもなくパトカーで警官が現れると、発炎筒は片付
けられ、くすぶり続ける支柱の炎も消され始めた。
やがて、交通が正常に戻り、警察官の姿も見えなくなり、
群集もその数をじょじょに減らして行ったとき、トキュウた
ちと青いシャツの若者たちが、その交差点をはさんで対峙す
るようにくっきりと現れた。この瞬間から状況は衝突に向か
って歩み始めた。
爆発的に高まっていく興奮のなかで、若者たちの仲間以外
の者に対する異常なほどの敵対心は、怒りと恐をははらみな
がら激しい闘争心へと変化していった。
もはや衝突の回避など、だれの頭にも浮かぶはずはなかっ
た。なぜなら、ひとつの生命体として原始的でむきだしのプ
ライドを頼りに生きている若者たちにとって、衝突を避けよ
うなどと考えることは、そのまま自分たちの弱さと敗北を意
味することになるからである。
トキュウは冷静に敵の人数を把握していた。自分たちのほ
うが少なかったが少しも不利な感じはしなかった。なぜなら
昨夜とは違い、みんな心の準備ができている上に、みんなポ
ケットにナイフを忍ばせているので、昨夜のように一方的
にやられることはないと確信したからである。
あとはきっかけを待つだけだった。信号が車を止めると、
人々はいっせいに横断歩道を渡り始めた。それにまぎれるよ
うに対峙する若者たちもゆっくりと交差点に歩み出る。そし
て彼らの距離が数メートルにまで近づくと、いったんそこで
立ち止まり、お互いに相手の悪口を言いたい放題に言い、と
きには激しくののしり挑発しあう。そして信号が変ると再び
もとの舗道まで戻り、次の対決を待つ。このようなことが二
度三度とくり返されたが、これといったきっかけもなく、な
かなか衝突には至らなかった。そんなときトキュウは思った。
もし今度接近したとき自分がいつものあの叫び声を上げれば、
確実に衝突に発展するだろうと。
それは、それを発するトキュウだけではなく、それを耳に
する仲間たちも、それによって全身に力が沸き起こってくる
とともに、どうなってもいいという気持ちにさせる叫びであ
る。
周囲には不穏そうな空気を感じてか、再び野次馬が集まり
だした。
トキュウはこれから先に起こり得ることはすべて自分次第
のような気がしてきた。激しく衝突し何人かがタイヨウのよ
うに傷つき苦しむ光景が眼の前に浮かんできた。
信号が車を止めた。
若者たちはまた接近し始めた。輝ける夜の光に照らされる
人の群れと車の群れ、そして眼の前に立ちはだかる敵と、そ
の敵を打ち倒そうとする仲間たち、すべての条件が整ってい
ることを感じながら、興奮が頂点に達しようとしていたとき、
トキュウはふと、
《どうなってもいい》
なんてことはない、自分たちは決して
《どうなってもいい》
ようなものではないような気がしてきた。そして、もし、い
ま自分が感情を爆発させれば、なんか取り返しのつかないこ
とが起こりみんながバラバラになるような気がした。
青信号で走り出した車が若者たちのあいだに入り込んでき
た。二つのグループは仕方なさそうに別れた。
舗道に戻ったトキュウが仲間に言った。
「なあ、みんな、今日は止めよう」
「ええ」
「なぜだよ、いまさら」
「やつらの数が多いからかよ」
「いやそういうことじゃない」
「じゃ、なぜだよ」
「もし、今ここで止めたら、やつらに、ビビッて逃げたと
思われるよ」
「バカにされるよ、女みたいって」
「これじゃ負けと同じだよ」
「戦わないで負けるのかよ、悔しいなあ」
「やつらぜんぜん強くないって」
「あんなやつらのさばらせていいのかよ」
「そうだけど、でもなにも今日じゃなくてもいいじゃないか、
チャンスは来るよ、また」
「さっぱりわからないよ、せっかく準備したのに、なぜ今日
じゃダメなんだ、これじゃ舐められるだけだよ」
「とにかく今日は止めよう」
そういってトキュウは交差点に背を向けて歩き出した。
トキュウの後を、最初はぶつぶつ言いながらついてきた仲
間たちも、その内に一人二人と離れていき、最後はショウと
途中から追いついてきたミュウだけとなっていた。トキュウ
はこれで良いのだと思いながら、何も喋ることなく歩き続け
た。そして公園につくと三人は広場を前にして階段のなかほ
どにトキュウを挟んで並んで座った。
だれも自分から進んで話そうとはせず三人のあいだにしば
らく気まずい沈黙が続いた。そしてようやくショウが話し始
めた。
「俺たちさ、数が少なくたって決してやつらには負けないよ。
みんなやつらによりやる気があるからさ」
トキュウが答えた。
「オレだって負けないと思う、いや、絶対に勝つよ。でも、
きっとタイヨウみたいに傷つくものがいっぱいでるよ」
「今度は、そう簡単にはやられないって。こっちだって全員
ナイフ持ってんだから」
「うん、それは、そうなんだけど」
「ああ、判った。そんなに心配なら、場所を変えてやればい
い、人が居ないところに呼び出すとか、そうすれば棒でもバ
ットでも何でも使えるぞ、いや、闇討ちでもいいさ、人数が
少なくなっているときを狙ってな、そうすればやられないっ
て、そうしないと、このままじゃ収まりがつかないよ」
「いや、そうじゃなくて、あのままぶつかれば、こっちだけ
じゃなく、あっちにも傷つくものがいっぱい出るっていうか」
「そりゃあ、仕方ないさ、喧嘩だもん、タイヨウがやられた
んだよ、仕返ししなくっちゃ」
「うん、そうなんだけどさ、でもさ、そもそも、いったいな
ぜやつらと喧嘩しなくちゃならないんだい」
「だって昨日あんな眼に合わされて黙っていられるわけない
だろう。男ならやり返さなくっちゃ。それにやつらに勝てば、
やつらをこの町から追い出せるじゃないか」
「なんで、やつらをこの町から追いださなきゃなんねんだ」
「そりゃあ、目障りだからだよ、邪魔臭いからだよ」
「でも、仲良くやってもいいじゃないか、俺たちだって最初
は二人だったじゃないか、そのうちにゲンキやサンドやコウ
イチやゲンが入ってきてうまくやってるじゃないか」
ショウが首を振りながら言った。
「やつらと仲良くだと、そんな甘いこと言ってると、こっち
が奴らに追い出されるよ。やつらは俺たちを追い出そうとし
てるんだよ。オレは向こうの何人か知ってるけど、そいつら
強くもねえくせに口だけは一人前で、いつも偉そうにしてい
るだけなんだよ。でも、実際は根性なしで、せこくて、きた
ねえやつらなんだ。話しの判るような相手じゃないよ、あん
なやつらと仲良くなんかできねえよ」
「でも、喧嘩にかっても、あっちにもこっちにもけが人がい
っぱい出て、苦しむものがいっぱい出てきたら、それほど意
味があることのようには思えないんだけど、かえってなんか
みんなバラバラになりそうな気がするけど」
「そんなことないよ、かえってみんな団結するよ。しょうが
ないじゃないか、男のプライドを掛けた喧嘩なんだから」
ショウがうなだれて言った。
「ああ、もう、おしまいだ、今までいったい何をやってきた
んだろう、俺たちは自由だ、なんでもできるんだって、皆で
いっしょに、大人たちがびっくりするようなことをやってき
たじゃないか、これからはもっともっとでかいことをやって
さ、世間を驚かすことができるかもしれないのに、もし、や
つらに負けたら、俺たちはこの町に居られなくなるんだよ、
自由でなくなるんだよ、何にも判っちゃいないよ」
ミュウが同調するように言った。
「そうよ、やつらをのさばらせたら何にもできなくなるのよ。
ああ、これからどんどん楽しいことが起こって、どんなにか
大人たちの苦しむ顔が見られる思ったのに、これじゃ今まで
やってきたことが何の意味もなくなっちゃうよ」
トキュウが苦しそうに答えた。
「でも、それはオレがいなくたってできるじゃないか」
「そんなことないよ、だれか引っ張るものが、頭が必要なん
だよ」
「それおかしいよ、自由な俺たちにそんな頭なんか必要ない
よ。みんなで話し合ってやればいいじゃないか。それにオレ
にはみんなを引っ張っていくような力はないよ。オレはほん
とうに何にも知らないんだよ。色んなことやってきたように
言うけど、ほんとは何にもしちゃいないんだよ。それに本当
はあまり強くもないし、格好もよくないし、女の子の前で泣
いたりするし、そんなオレにいったい何ができるって言うん
だい」
ミュウがあきれたように言った。
「まだそういうことを言ってるの、大きいとか小さいとか、
格好いいとか悪いとか、頭っていうのは外見じゃないって、
前にも言ったでしょう。なんていうか、、、、じゃ、いった
い他にだれができるって言うの? ほかにふさわしい人がい
ると思う」
トキュウはしばらく黙ったあとゆっくり言った。
「オレはもう嘘言うのイヤなんだよ」
「ウソ、ウソって何が?」
「じゃ言うけど、オレは人を刺したとかレイプしたって言う
けど、ほんとは何もやってないんだよ」
「それじゃ昨日はなぜあんなにうまく行ったんだ」
「あれか、オレにもよく判らない、今でも不思議なんだ」
「そんなウソ、だれでもつくさ、そういうウソはついていい
んだよ。みんな判ってるさ、ウソだって、はったりだって、
でも、どんなに見え見えだって、大きくついたほうが勝ちな
んだ、それでいいんだよ。問題なのはどうしても許せないウ
ソをつくやつなんだ。オレは勉強ができないけど、そういう
ことにはものすごく敏感なんだ」
「どんなウソでも、やっぱりウソはよくないよ」
「また子供みたいなこと言ってるよ、笑っちゃうよ」
「だってまだ子供じゃないか」
「まったく、もう。そうさ、オレたちウソつきはトキュウと
は育ちが違うからな、トキュウのように親から可愛がられて
育った者には俺たちの気持ちわかんねえだろうな」
「なぜオレがかわいがられて育ったって、見てもいないのに
判るんだよ」
「なんとなくそういう気がしたんだよ」
ミュウが苛立って言った。
「ほんとうにところトキュウはどうしたいの?」
「とにかくオレは、喧嘩しなくたってうまくやっていけそう
な気がするんだ」
「ダメだ、やつらを甘く見ている。やつらはそんな人間じゃ
ないんだ。やつらには命令とか掟とか制裁とかはあるけど、
自由なんてないのさ。サイスが言うように、思ったとおりに、
感じたとおりに、やりたいように行動するなんてこと、まっ
たくないのさ」
「もし、そうだったら仕方がない、ほかのところに行くさ」
「はあ、そんなヤワな考えじゃ、どこへ行ったって通用しな
いよ、だれもついてこないよ」
そういってショウは話すことを止めた。しかしトキュウがう
つむいたまま何も答えないので再び話し始めた。
「やっぱりそうだったのか、いいことをやろってんだ。大人
たちのいうことを聞いて良い子になろってんだ。いいさ、俺
たちと別れて独りだけ良い子になればいいさ」
ミュウが怒ったように言った。
「もう、いいわ。ああ、気に入らないことをもうどんどんぶ
ち壊してさ、これからどんない楽しいことが待っているかっ
て期待してたのに、これじゃあたしが今までやってきたこと
が何の意味もなくなってしまったじゃない。あたしバカみた
い。トキュウってほんとに何にも判っていないんだから」
そういい残してミュウはどこかへ立ち去って行ってしまった。
ミュウの最後のほうは泣き声になっていたようにトキュウに
は聞こえた。トキュウとショウはその後何も話すことなく別
れた。
久しぶりに両親の元にもどったトキュウは家に引きこもっ
た。だから町に出てふたたびかつての仲間たちと会うことは
なかった。
ショウたちと別れて二ヶ月が過ぎたある秋の日の午後。突
然警察から呼び出しを受けたトキュウは、その四角い灰色の
部屋で中年の刑事から取調べを受けようとしていた。刑事は
不安そうにうつむき加減のトキュウに鋭い視線を投げかけな
がらゆっくりと話し始めた。
「名前は橋本久作だな」
「は、はい」
「ふう、それで年はいくつなんだ」
「十六」
「へえ、まだ十六なんだ。今日はなんで呼ばれたかだいたい
判るね」
トキュウは黙ったまま不思議そうに首をかしげた。それを見
ながら刑事は言葉を続けた。
「最近の連続放火事件だけど、君はどのくらい関わってんだ」
トキュウは首を振りながら答えた。
「ぜんぜん、いつのことですか?」
「ここ二ヶ月のあいだのことだよ」
「この二ヶ月ぼくは家に引きこもっていて外に出たことはあ
りません。両親に聞けば判ります」
「本当に知らないのか?」
「はい、だってそんなことが起こっていたことも知らないく
らいですから」
「ほんとうか、ウソをついちゃいけないよ。じゃ、先月十六
日、公園の裏でホームレスが殺された事件、君は何か知って
るよね」
「いいえ、ほんとうに何も知りません」
とトキュウは懸命に真剣な表情を作りながら言った。その様
子にじっと眼をやっていた刑事は幾分表情を和らげながら言
った。
「長年の勘で言わしてもらうけど、どうも君は何かを隠して
いるような気がするんだけど、、、、まあ、いいか、ところ
で君は、最近テレビを見てるか?」
「あんまり」
「ニュースも?」
「見てないです」
「じゃ、事件のことは何にも知らないんだ。あんなに世間を
騒がせている事件を知らないんなんて」
トキュウは初めてその刑事の顔を見ながら落ち着いた表情で
ゆっくりといった。
「事件って、どんな事件ですか?」
すると刑事は少し苛立って言った。
「殺人事件だよ。訳のわからない殺人事件だよ。こんな事件
が起こるなんて本当に考えられないよ。いったい最近の若者
はなにを考えているんだろうね。大友翔平、知ってるな、ま
た知らないなんて言うなよ、調べはちゃんとついているんだ
からな、この男だよ」
そういって刑事は一枚の写真を出してトキュウに見せた。写
真に写っている男の髪の毛は黒く、しかも短く、耳にもピア
スはついていなかったが、トキュウはそれがショウだとすぐ
に判った。そして頷きながら言った。
「はい、知ってます。よくいっしょに遊んでました」
「じゃ、森嶋美由紀って知ってるな」
「モリシマミユキですか、知らないですね」
「おい、ダメ、ダメ、とぽけちゃ、もしかして任意だからっ
て甘く見てない、答えたくないことは答えなくてもいいなん
て思っていたら大間違いだよ。そのうちに判ることだからね、
今のうちに正直に話していたほうがいいよ。この女だよ」
そういって刑事はもう一枚の写真を出して見せた。トキュウ
はそれを見たとたん心臓か壊れるかと思うくらいドキッとし
た。そこに写っていたのは、トキュウがかつて、くしゃくし
ゃになるまでポケットに入れて持ち歩いていた写真の中の少
女であり、公園の裏で襲ってレイプした少女でもあったから
である。これがどんな問題をはらんでいるのだろうかと、ト
キュウは激しく動揺し不安になった。しかしできるだけ平静
さを装いながらじっくり見た。そして首をかしげながら言っ
た。
「どこかで見たことがあるような気が、、、、」
それを見て刑事はあきれたように笑みを浮かべて言った。
「いいかい、ウソをついちゃいけないよ、何度も言うようだ
けれど、調べはちゃんとついているんだからね。正直に答え
たほうがいいよ」
トキュウはなおも首をかしげながら知らない振りをした。刑
事は急に厳しい表情になり言葉を続けた。
「いいかい、見た人が居るんだよ、君たちのこと詳しく知っ
ている人なんだけどね。その人の話によると、君が大友翔平
といっしょにこの森嶋美由紀のマンションに出入りしていた
そうじゃないか、よく夜中に騒いでいたそうじゃないか、周
りに迷惑掛けて、なんか若さに任せて相当破廉恥なことをや
っていたそうじゃないか」
「そんなことないです、その僕たちを知っている人ってだれ
ですか?」
「そんなこといえないよ。そんなこと聞く前にまずは正直に
話すことだよ」
そう言いながら刑事は、それまでじっとトキュウに向けてい
た目をそらして、ふと天井を見上げた。そして突然うなづき
ながら言った。
「はあん、そうか、そうか、もしかしたら化粧で判んないか。
そのころは元の顔が判らないくらいすごい化粧してたそうだ
からな。あそこだよ、裏にドブ川が流れているマンションだ
よ。たしか仲間からはミュウと呼ばれていたみたいだな」
それを聞いてトキュウは激しく動揺し混乱た。刑事はさらに
続けた。
「この大友翔平と森嶋美由紀が人を殺したんだよ。地方から
出てきて立派な人間になるために一生懸命勉強していた学生
を殺したんだよ。何の罪もないのに、殴ったり蹴ったりして、
最後は二人で絞め殺したんだよ、残酷なやり方だよな。テレ
ビで見たらだれだって激しい怒りを覚えるよな、あのふてぶ
しい態度、あれは自分たちのやったことぜんぜん悪いと思っ
てない態度だよな。奴らは人間じゃない。けだものだ。あっ、
そうか、まだテレビで二人を見てなかったっけ。殺された学
生というのはな、日本の将来を背負ってたつような優秀な青
年だったんだぞ。親御さんも大変期待していたみたいだな。
ところがこの二人のために、親子四人の幸せそうな家庭だけ
ではなく、一家の将来の夢や希望までも全部ぶち壊されてし
まったんだからな。ほんとうに悔しいだろうな、さぞや無念
だろうな。幸せそうな家庭が壊されるってどんなことか、お
前たちのような人間にはわからないだろう。いったいこんな
ことがあって良いのだろうか、真面目で優秀な人間がクズ見
たいなのに生命を奪われるなんて」
このかんトキュウは、できるだけ平静さを装いながらも、ミ
ュウと写真の少女が同一人物であることを理解できなくて、
混乱は続いていた。しかしその一方で、もし同一人物である
ならば、かつて自分の周りで起きた様ざまな不可解な出来事
はすべて辻つまがあうような気がした。そして言った。
「ほんとうにこの二人がやったんですか?」
刑事は無愛想に答えた。
「そうだよ」
「何かの間違いじゃないですか」
「間違い、本人たちがやったって言ってるんだらか間違いな
いよ。ところで二人はどんな人間だったんだ? 君はだいぶ
年下のようだから、苛められたり、イヤなこと押し付けられ
たりしたんだろう、どうなんだ?」
トキュウはまた別の動揺を覚えながら、少し間を置いてから
言った。
「いいえ、とてもいい人たちでした」
「なにか変ったところはなかったか、突然暴れだすとか、残
酷なことを平気でやるとか」
「いや、そんなとこは見たことないです」
「そうだろうな、だいぶ年が離れてるから判んないかもしれ
ないな」
トキュウが驚いたように顔を上げていった。
「二人の年齢はいくつなんですか」
「なに、君は年も知らないで付き合っていたのか。だいたい
判るだろう、テレビに出ているんだから、二人とも二十歳だ
よ」
「えっ、ぜんぜん判らなかった。一つか二つ上だと思ってた。
その刑事はじっとトキュウに眼をやりながら言った。
「なにかあるだろう。いつもどんなことやって遊んでたんだ?
まあ、話したくないんなら、話さなくてもいいんだけど、で
も、いずれは判ることなんだよな。実は今度の事件でどうし
ても判らないことがあるんだ。動機のことなんだけどね、あ
の二人どう見ても正直に言ってるようには見えないんだ。こ
れまでの調べによるとだね、三人はだね、知り合ったその日
にはもう被害者のマンションで暮らし始めてるんだよ、一日
二日は仲良くやっていたみたいなんだけど、ところが三日目
になって、何があったかわからないけど、突然大友と森嶋の
二人は犯行に及ぶんだ。女の話しだと急にむかついてきたと
いうし、男の話しだと殺したくなったから殺したということ
たけど、こんなの動機にはならないだろう、なんか他にある
だろう、お前だってそう思うだろう。とりあえず今は、それ
を必死で捜査しているんだけど、これだと言うものがまだつ
かめていないんだよ。警察としてはいちおう金目当てでやっ
たんだろうとにらんでいるんだけどね。なぜなら、やつらが
逃走中に捕まったのは強盗未遂だからね。一銭も持ってなか
ったそうだ。ふう、まあ、このようなわけで、君にもぜひ協
力して欲しいってことだよ。ところで最近はいつあったんだ
?」
「二ヶ月前に別れて、それ以来ずっと会ってないです」
「二ヶ月前というと、八月末か、九月初めだな」
「大体その頃です」
「なんで別れたんだ」
「やりたいことって言うか、考え方が二人と会わなくなって」
「ふうん、ウソはついてないみたいだな。やつら九月十月は
地方を放浪していたみたいだからな。それから、なぜか、突
然この町に戻ってきて、事件を起こしたということになって
るみたいだからな」
そう言って刑事はいったんトキュウから眼を離したが、すぐ
にトキュウのほうに向き直り話し続けた。
「それからまだ他にも判らないことがあるんだな、ふつう逮
捕されたらどんな極悪人だって、多少おとなしくなるもんだ
よ。少しは罪を軽くしようと思ってな、ましてやまだ二十歳
の若者なんだからな、大人しくなって反省の色を浮かべて、
ウソでも悪いことしました、とかって、反省じみた言葉を言
うもんだよな、それが赤い血が流れている人間ってもんだろ
う。ところがこの男と女は似たもの同士で、反省するどころ
か、開き直ってあの通りマスコミの前で暴言をはくは悪態を
つくはで、あの態度は取調室でも変らないんだ。男は殺した
いから殺したんだ、ほかに理由なんて何もないって、その一
点張りなんだ。反省してなんになる反省するくらいなら初め
からやらないよ、なんてうそぶいているそうだ。それでも多
少は反省の気持ちがあるんだろうと聞くと、まったくないと、
なぜなら、オレはウソをつきたくないと、殺したときの気持
ちを正直に言って何が悪い、それで十分じゃないかと言って
るそうだ。たしかにそれはウソかもしないけど、ウソ以前の
問題なんだよな。それからこんなことも言ってるそうだ。反
省していい人になって頭を下げるくらいなら、反省しないで
悪人のまま嫌われていたほうがいいって、まったくどうしよ
うもない野郎だ。今日あたりなんかこんなことも言ってるそ
うだ。オレは自由なんだ、なんでもできるんだ、思ったこと、
感じたことをやって何が悪いって、まったくふざけた野郎だ
よな。頭がおかしくなったんじゃないのか、自由だからと言
って人間を殺す自由なんてあるわけないだろう。なんか聞く
ところによると、この二人の両親は社会的地位のあるきちん
とした人たちだそうじゃないか、だから、なおさら、なんで
あういうことをやったのか判らないんだよな。それにしても、
子供を殺された親御さんはほんとうに可哀想だよな、地元で
は頭のいい真面目な青年として大変評判がよかったそうだ。
親御さんも鼻高々だったそうだ。さぞや小さい頃から可愛が
られてダイ度に大事に育てられてきたんだろうな。それが身
を結び見事一流大学に進学し、これからどんなにすばらしい
人生が待ち受けていたかもしれないのに、それをこの二人が
全部奪い去ってしまったんだからな。それを思うとどうして
も許せない気持ちになるんだ。だから、君には何があったか
隠さずにはなして欲しいんだ。どんな悪いことをやってたん
だ。たぶん君は奴らに命令されてイヤイヤやってたんだろう
けど、そういうことはこっちだって判ってるさ、だから、正
直に話してくれないかな」
もうほとんど平静さを取り戻していたトキュウは、なにか
を思い出すかのように眼を閉じうつむいた。しかしあまりよ
く思い出すことができなかった。なぜなら、今のトキュウに
とって、まだわずか数ヶ月前とはいえ、ショウやミュウやサ
イスたちとの出来事は、すでに夢の中の出来事のように曖昧
で漠然としたもののようにしか感じられなくなっていたから
である。それでもトキュウは、今ここでなにを話すのが一番
ふさわしいのかを本能的に感じ取りゆっくり丁寧に語り始め
た。
「ほんとうに二人はいい人たちでした。美由紀さんは腹が減
ったるときなど好きなだけ食べさせてくれました。病気のと
きには泊めたりもしてくれました。翔さんもいい人でした。
仲間思いのやさしい人でした」
「本当に何もなかったんだな。まあ、いずれはわかることだ
けどな。噂では色んな悪いことをしてるみたいだけどな、で
も今はとにかく動機の解明が急がれるみたいでな、そのほか
のことは後まわしになってるみたいなんだ。とにかく最近は
これでもこれでも勝って言うぐらいに次々と変な事件が起こ
っているんだよな、経済が発展しているんだから、人並みに
真面目に働けば、だれだってどんどん幸せになれるっていう
のに、なんで好き好んで悪いことをやりたがるんだろうね、
まあ、世の中の人全員が幸せになったら、私たちの仕事もな
くなるけどね、まあ、それはそれで良いんだろうけどね。今
日はこれでいいだろう。今後も協力頼むね。それから君はも
うあういう連中とつきあうのは止めたほがいいよ、君はそん
なタイプじゃないみたいだから、真面目にやったほうがいい
よ、あっ、それから最後にもうひとつ、君は岩本幸成ってし
ってるかな、あれだよ、ビルの屋上から川にバイクでダイブ
したバカな男だよ」
トキュウは刑事の顔をシッカリ見て答えた。
「そんな男見たことも聞いたこともありません」
「なんか君が岩本といっしょに居るところを見たって言う人
がいるんだけどね」
「たぶん人違いだと思います」
「岩本が色んなくだらない事件の首謀者みたいなんだけど、
今となっては、生きているのか死んでいるのかもわからない
しな、でもあういう犯罪は岩本独りでできるものではないか
らな、きっと協力者がいたんだろうけど、もしかしたら別に
首謀者がいたりしてな。まあ、私の独り言だ、聞き流してい
いよ。それよりこんな悪党をかっこいいなどと思って、もう
あまり変な事件を起こすんじゃないぞ。警察だって仕事とは
いえ大変なんだからな、どんなくだらない事件だって、今や
っていることを中断しなくちゃいけないんだからな、でも、
それは後まわしになるだけで、結局あとで何倍も労力が掛か
るんだからな。忙しいだけじゃないんだ、色いろと神経を使
うんだよ。あうまで毎日マスコミに騒がれ世間の注目を集め
ていたら、ちょっとでも警察の対応がまずかったりすると今
度はこっちに世間の不満や怒りの矛先が向かいかねないんだ
からね。いいかい、君もゆっくりテレビでニュースを見たほ
がいいよ。今、世間はどうなっているか、どんなにどんなに
この事件に関心を持っているか、まあ関心というより、あれ
は熱狂だな、もう他のニュースなんてどうでもいいって感じ
だもんな。上から下までこの事件で持ちきりだからな。私だ
って自分が刑事であることを忘れてついチャンネルをあっち
こっちにまわして何回も見てしまうもんな。やっぱりあれだ
な、なんだかんだ言っても、みんなは堕ちていく人間って言
うか、悪党ってのはどんな顔をしているか、ほんとうは見て
みたいんだよな、、、、、」
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
刑事の話が終わりに近づくに従ってトキュウはだんだん心
臓がドキドキしてくるのを感じた。だがトキュウはできるだ
け冷静さを装いながら刑事に軽く会釈して部屋を出た。そし
て、トキュウは決して後ろを振り向くこともせず何事もなか
ったかのように一歩一歩着実に外に向かって歩みを進めた。
やがて警察署を出て雑踏になかを歩いているうちに次第に
そのドキドキも収まっていた。そしてトキュウは、なんだ警
察もたいしたことないな、と思った。と同時に、自分はなぜ
あんな父親のような大人を相手に、しかも威圧的な刑事を相
手に冷静にたいおうできたんだろうと不思議な気がした。
これといった目的もなく歩いていたトキュウは、偶然にも
家電量販店の前を通りかかった。展示されているすべてのテ
レビからは正午前のニュースが流れていた。
トキュウは吸い込まれるように店に入った。眼の前には音
の出ないテレビが上下左右に広がった。すべての画面から一
人のニュースキャスターの姿が消えると、大勢のマスコミに
囲まれ、刑事にはさまれて連行される二人の若者の姿が、す
べての画面に現れた。髪も染めず、ピアスもつけず、化粧も
せず、何にも装わないごく普通の若い男女だった。しかし彼
らは紛れもなくショウとミュウだった。険しい表情で正面に
向かって何かを叫んでいるショウの顔が大きく映し出された。
そのときトキュウはとっさに自分に向かって叫ばれているよ
うな気がした。
“裏切り者”
と。すると再び心臓がドキドキしはじめた。トキュウは急い
で外に出て歩きだした。
歩きながらトキュウは、知らず知らずのうちに人通りの少
ない通りを選んでいた。やがて前方に自分が住んでいる町へ
と通じる歩道橋を眼にしながら歩いていると、突然背後から
声を掛けられた。
「トキュウ、トキュウじゃない」
トキュウが振りかえると一人の少女が近づいてきた。ドラッ
グストアのなかからトキュウの姿を発見したようだった。マ
イは化粧も服装も以前と少しも変っていなかった。そして驚
いたように立ちつくすトキュウに向かって言った。
「やっぱりトキュウね。なにどうしたのそんなにびっくりし
たような顔して、久しぶりね。なにをしていたの? ねえ、
歩こう、あたしもこっちにいくの、ねえ、いったいみんなど
うしたの? 急に居なくなっちゃって。あたしね、ミュウの
マンションになんとも言ったの、でもいつ行ってもいないの
ね、そのうちに見たこともない人が出てきてさ、ミュウはど
こかに引っ越したみたいなのね。ねえ、男の子たちは急に居
なくなったみたいだけど、今どうしてる?」
「判らない」
「判らないって、仲間だったんでしょう。あっ、もちろん、
あれは知ってるよね。サンドが盗んだ車を乗りまわしている
うちに、パトカーに追いかけられて、トラックと正面衝突し
て死んだこと」
「ああ、そのことは知っている」
そう答えたあとトキュウはまた心臓がドキドキするのを感じ
た。
「どうしてあんなことしたんだろう?」
トキュウに何も答えずただ首を振った。そして話題を変える
ように言った。
「いつかお金を返してもらうんだって出かけていったよね。
あの約束どうだったの?」
「あれね、どうなったと思う、みんなあたしのことバカにし
てたでしょう、だまされたんだってね、でも、ちゃんと約束
の時間に来て返してくれたのよ。ねえ、もう一度みんなと集
まって遊ばない」
「うん、そうだね、そのうちにね」
「ねえ、トキュウ、あんた寒くない、そんなTシャツ一枚で、
もうじき冬なのよ」
「まだ、秋だよ。ところでさ、マイって年はいくつなの?」
「あたし?! ヒミツ。そんなことよりミュウ、今どこに居
るか知らない?」
「知らない」
「それじゃ、あたしこっちに行くから、また後でね」
とマイは笑みを浮かへて言うと、幼な子のように手を振りな
がら横道に歩いていった。
だがトキュウは、もう二度と会えないよう気がした。
(完)