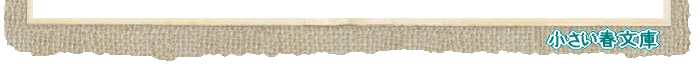それは、その衝撃音が、すべてのものに森の妖精の悲鳴のようにも思えたからあった。
* * * * * * * * * * * * * * *
木漏れ日
はだい悠
* * * * * * * * * * * * * * *
市立図書館は森のように緑豊かな町の北側にあった。
交通量の激しい主要道路沿いではあったが、道路からは五十メートルほど奥に入った所にあるためいつも郊外のような静けさが保たれていた。
そこへは、車で来る人たちのための駐車場付きの広い道か、それとも徒歩で来る人たちのための小道を通って行くことが出来た。
舗道から望むその小道は、幅は二メートルほどで、モミジや、カエデや、ユリの木や、榛の木などの様ざまな樹木の間を縫うようにゆるやかなエス字形をしていた。
だから、そこをを通る大抵の人たちは、
春には新緑の下、その木漏れ日や野鳥の声に包まれて、
夏には、セミ時雨のもと、虫取り網を持った子供たちとすれ違いながら、
そして秋には、木々の色鮮やかな紅葉の下を、踏みしめる落ち葉の音を聞きながら、歩くことができるのである。
でも、それだけではなく、そのときどきの幸運に恵まれた者は、
市街ではきわめて珍しいウグイスやホトトギスなどの鳴き声を耳にすることも、
また梢を飛び跳ねるリスの姿を眼にすることも、
さらには、どこから紛れ込んできたのか判らないが、黒いウサギの姿も眼にするということもできるのである。
初夏の陽射しが眩しい土曜日の午後。
町の東側にあるショッピングモールのドアが開き、満ち足りた笑顔の二人の少女が、手を広げ踊るようにして出てきた。
舗道を吹き抜けるそよ風を感じたからだった。
二人はそのまま歩き始めたが、すぐに一方の少女が驚いたように歩みを止めた。
「あっ、私、図書館に行く予定だったんだ」
「えっ、いまから?」
「うん」
「なんで黙ってたの?」
「黙っていたわけじゃなくって、忘れていたっていうか、、、、だってユカちゃんがあまりにも楽しそうにしていたんで、なんか私もつられてっていうか、ついつい楽しくなっちゃって、それで、、、、」
「ミナちゃんって、そういうところがあるから、人に合わせるっていうか、、、、ちょっと合わせ過ぎなのよ。もっと早く言ってくれれば、、、、どうしよう、、、、子供会の清掃ボランティアは三時からよ、その前に私たち五年生は三十分前に集まって準備しなくちゃならないのよ」
「、そうだよね、、、、ごめんね。本は今日までに返さなくちゃいけないし、、、、子供会が終わってからだと間に合わないし、、、、、、どうしよう」
「いいわ、私、先に行っている。ミヤちゃんは図書館に行ってから来て」
「ほんとにゴメンね」
「とりあえず急ごう」
「ねえ、どうして六年生じゃなくって、私たち五年生が準備をやるの?」
「よく判らない、前からの決まりみたい」
「それじゃ私走っていくから、出来るだけ早く行くようにするから」
「みんなに言っておく、ミナちゃん少し遅れるって、じゃあ、またね」
「またね」
丁字路の分かれ道に来て二人はそう言い残しながらお互いに離れるように歩き出した。
図書館への道のりは、だいぶ後戻りになるので子供会へは二十分ほど遅れることになるだろうか。
ミヤはそう思いながら自然と小走りになっていた。
七分後、ミナは、四車線の広い道路を挟んでその反対側に図書館へと通じる小道が見えるのところについた。
他にも車で来る人たちのための広い道があったが、ミナはその小道を歩くことが好きで、いつもそこを通ることにしていた。
あと百メートルほど行けば、信号があるのだが、時間の節約を考え、そこを渡ることにした。
通り過ぎる車はそれほど多くはなかったが、ほとんどの車はスピードを落とさなかったので、注意が必要だった。
ミナは、急いではいたが、まずは中央分離帯まで、それから反対側の舗道へと、二段階で渡ることにした。
ミナがそのように慎重になったのは、より安全のためということもあったが、渡るには相応しくない所を渡るという後ろめたさや、そのことで車のドライバーに少し迷惑が掛かるので、申し訳ないという気持ちがあったからあった。
眼の前を車が通り過ぎ、完全に安全が確認されると、ミナは中央分離帯まで小走りで渡った。
そこに着くと今度は反対側車線を見た。
逆光でまぶしかったが五十メートルほど先に一台の車がかなりのスピードやってくるのが見えた。
この車をやり過ごし、それからもう一度確認して、それから渡ろうとミナは考えた。
ミナは何気なくこれから通るであろう新緑の下の細い小道に眼をやったあと小さな深呼吸をしながら自分の足元に眼を落とした。
そのとき三メートルほど斜め前でゆっくりと走ってきて止まる車の陰が視界に入ってきた。
ミナは、私のために止まってくれたんだ思うと、そのことに驚きながらも、頭を少し上げてドライバーに眼をやった後、さらに頭を低く下げて、道路を小走りで渡り始めた。
そしてその車の前を通り過ぎたとき、ミナは激しい衝撃を受けた。
意識が薄れていくのを感じながらミナは思った。
「いったいどうしたんだろう?私のために止まってくれたんだから、それで嬉しくなって、でも迷惑が掛かるから早く渡らなければいけないと思って、それでお礼のつもりで頭を下げて急いで渡っただけなのに、、、あの運転手さん、あんなに暖かい笑顔で私のほうを見てくれたから、それでとても嬉しくなって、なんか気持ちがボワッとして、、、、、、」
響き渡るその予期せぬ衝撃音に、
小道を歩く者の顔は不安げに曇り、
黒ウサギは頭をもたげ、
リスは立ち止まり、
鳥はさえずるのを止め、
木漏れ日は消え、
そして木の葉はさざめくのを止めた。
それは、その衝撃音が、すべてのものに森の妖精の悲鳴のようにも思えたからあった。