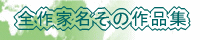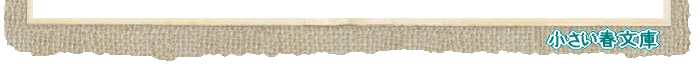はだい悠
はじめに
《 》内はこの小説の主人公タイガーとその周囲の動物たちの<鳴き声>と<思い>です。
「 」内はタイガーの耳に聞こえてくる周囲の動物の鳴き声や騒音、そして人間の会話です。
「ブゥーン、ブゥーン、ゴォー、ゴォー、ブゥ、ブゥ」
「うわぉ、空がこんなに青かったなんて、なんて気持が良いんだろう」
「ほんとうね、なんせ久しぶりの天気だもんね。風はないし」
「こんな日は部屋でくすぶってなんかいられないわよね。うわぁ、ネコ!」
「なにしてんの? ミャーオ!」
《ミャーオー》
「あら、返事したわよ。ノラかしら」
「信号、赤になるわよ、急ぐわよ」
「バタ、バタ、バタ、バタ」
「ペタ、ペタ、ペタ、ペタ」
「あっ、マミちゃん、ママから離れちゃだめ、そんなに走っちゃころんで痛い痛いするわよ」
「ネコちゃんが、ネコちゃんが。ねえ、名前なんて言うの? ミャー」
《ミャーオー》
「だめ、触っちゃ、汚いんだから。かまれて病気を移されたらどうするの。さあ、お手てを拭いて。バァイバァイしていきましょう」
「バァイバァイ」
「あら、こんにちは。お出かけですか?」
「ええ、ちょっと、お買い物に?」
「こんにちは、マミちゃん、ほんとうに可愛いわねえ」
「マミちゃん、こんにちはって、挨拶して」
「コンニチハ」
・・・・・・・
《フンだ、なにがキタナイだ。
なにがビョウキだ。早く行っちまえ。
アタタカイのは良いなあ。
キモチ良いなあ。
天気が良いからなあ。
それにしても腹減ったなあ。
ずいぶんなにも食ってないからなあ。
とにかく、どっかで食い物を見つけないと》
「さあ、みんないらっしゃい。こっちにきて食べなさい。さあ、そんなところに隠れてないで、怖がらなくても良いのよ、何にもしないからね。そこの植え込みのトラちゃんも、こっちにきて食べなさい」
《見たことないやつらだなあ。
なにをされるか判らないからな。
食いたいけどなあ》
「ここの猫たちはエサを与えられているみたいね。でも、まだ手術はほとんど済んでない見たいね。可愛いとか、かわいそうだからと言ってエサを与えるだけじゃ何の解決にもならないことを判っているのかしらね?」
「そうよね。どうかしら、うまくいくかしら」
「そうね、ここは公園の中でもわりと人通りが少ない静かな場所だから、きっとうまく良くと思うわ」
《なんだあれは、なんか変だぞ。
まあ、他をあたってみるか》
「なかなか寄って来ないわねえ。やっぱり警戒してんのかしら。ねえ、慣れるまで捕獲オリは隠しておいたほうが良いんじゃない」
「だいじょうぶだと思うわ。ここの猫たちは、たぶんオリを見るのは初めてだと思うから」
「いったいどうして最後まで面倒見ないのかしら。捨てるなんてほんとうに無責任よね。最初に飼った人間さえしっかりしていたら。わざわざ税金や寄付金を使って、ネコだって嫌がる不妊手術をすることもないのにねえ」
「さあ、みんなこっちに来てたぺなさい。そんなに怖がらないで、そうそう良い子ね。これもみんなのためを思って考えてやっているんだからね。わたしたちだってほんとうはこんな可愛そうなことはしたくはないのよ」
「ウーウー、フー」
「ギャー、ウー」
「アッ、だめ、喧嘩しないの。そんなに欲張らないの。ちゃんとみんなに平等に行き渡るだけあるからね。さあ、あなたたちも遠慮しないで前に来て食べて良いのよ」
「やっぱり、ネコは猫よね。捨てられるとだんだん野生に戻っていくのかしら。この中にボス見たいのがいるのかしら。サルみたいに強い弱いの順位があって」
「いるんじゃないかしら」
「あの落ちついたクロトラかしら。目が鋭いシロも強そうね。それともあの体も大きく強そうなクロブチかしら。見かけ倒しってこともあるからね。ミケはどことなく気が弱そうだから、あれは違うわね。猫たちの間でも、人間みたいに、なんとなく気が合わないとか、好きとか嫌いとかあるのかしら。挨拶の仕方が悪いから、気に入らないなんてことあるのかしらねえ」
「まあ、そこまでわねえ」
「そういえばネコ同士の挨拶って、どんなことするのかしら?」
「あら、あそこにいたトラちゃんの姿が見えないわ。どこへ行ったのかしら。まさかわたしたちの言ってること、判ったのかしら?」
「まさか、ネコに人間の言葉が判るとは思うないわ」
《なんか変だなあ、なんかイヤな感じだなあ。
オッ、この匂い、食い物の匂いだ。
近くなってきたぞ。
やっぱり、みんないるな。
なんだこのイヤな雰囲気は。
みんな怖がって隠れているぞ》
「やめないか!」
「やめません!」
「やめなさい!、、、、ふん強情なババアだ。あんたがエサをやるから、ネコがどんどん集まってくるんじゃないか。周りのものがどんなに迷惑しているのか判らないのか」
「お腹をすかせているのにほっとけというんですか。お宅は動物に対して哀れみの心を持ってないみたいですね」
「持ってるよ。それとこれとは話が違うんだよ。ネコはネズミをとって食って、生きていきゃあ良いんだよ」
「無理ですよ。ここの猫たちはネズミなんか取ったことないんですからね」
「それは、あんたがそうやって、エサをやって甘やかしているからじゃないか。ほっとけば、ネコは本能ってものがあるから、教えなくてもネズミをとって食うもんだよ」
「むちゃくちゃですよ。だいいちここには、すべての猫たちが生きていけるだけのネズミなんていませんよ。わたしは、いまだに一匹のネズミも見たことないんですからね」
「まったくもう、あう言えばこうだ。ネズミが少なければ少ないで、ネコはねずみを求めて他へ移って行くもんだよ。話しにもならない。ネコも堕落したもんだよ。エサをくれるなら誰でもかまわないんだ。プライドって云うものがないのかよ。 おいババア、この辺あんまりうろつくと転んで足でも折るぞ、気をつけろ!」
「さあ、クソジジィがいなくなったから、みんな出て来て食べなさい。お前たちはほんとうに可愛いねえ、なんて可愛いんだろう」
《なんかいつもと違う感じだなあ。
もう少し居たいけど、まあ、良いか。
あそこに在るのはあんまり好きなものじゃないから、ほかをあたってみるか。
ネズミってあのことだな。
小さいくせにすばしっこい奴。
あれを捕まえて食うとなると、大変だな。
まだやったことがないからな。
ダラクって何だよ。
プライドって何だよ》
「パァー、パァー、キキィー、バカヤロウ、もたもたしてると死ぬぞ。クソネコ! ブゥ-ン」
《だいじょうぶか? カシコソウ》
《あっ、タイガー、なんとか》
《見かけないチビどもだな、どこから来たんだ?》
《ゴウゴウと音がするハシの下にいたんで、どうしても付いて来るというもんで、まだ、なんにも知らないみたいで、、、、》
《おいカシコソウ、なんだあの渡り方。
見てられなかったぞ。
お前、チビどもにちゃんと教えたのか?》
《あっ、カタミミ、まだ、、、、》
《しょうがないなあ。
なら、オレが教えてやる。
よいか、チビども、道をわたるときはだな、こうやって見て、次にこうやって見て、それから渡るんだよ。
判ったか、判ったなら、さっそくやってみろ。
そうだそうだ。
良いか絶対に忘れるなよ》
《みんなはもう何か食ったか?》
《いや、まだなんにも》
《そうか。
アッ、そっちは今日はだめかもしれない。
なんか様子が変なんだ。
クソババアとか、クソジジィとかいうのが居てさ。
こっちに行こう。
なあ、カタミミ、お前このあいだ、他のオスネコと一緒に一匹のメスネコをとりかこでん何かやっていたな》
《タイガー、あれは違いますよ。
あれは、オスはオレだけで、あとはみんなメスだったんですから》
《そうだったのか、それにしても激しい争いだったなあ。
おいそっちじゃない、こっちだ。
おお、みんな居るぞ。
コワソウもヨワソウも居るぞ。
コワソウはさっきあっちで食ってたじゃないか、もう、こっちに来ているのか、すばやいなあ》
《もう我慢できない、さあ、みんな行くぞ。
タイガーは行かないんですか》
《いや、オレは行かない、そんなに腹へってないんだ。
さあ、チビども、いって思いっきり食ってこい》
《カタミミはあんなにニンゲンが嫌いなのに、でも食う時は別なんだよな。
ニンゲンに飼われていたネコは、よく判らない。
ああ、みんなといっしょに行けばよかったかなあ。
なんで行かなかったんだろう。
こんなに腹が減っているのに。
まあ、ひと眠りでもするか。
おい、どうしてこんなに早く戻ってきたんだ》
《いや、ちょっと遅かったみたいで、もうないということらしいんで、、、、》
《そうか、それじゃ仕方がないな。
よし、それならみんなに良い事を教えよう。
遅くなって食えなくて困ったとき、でも絶対に食える方法だ。
さっき食えなかったほかのみんなもこっちに来て聞くように。
良いか、よく見ろ、ニンゲンがベンチに居るだろう。
ベントウを食っているだろう。
それをもらうんだ。
でも、誰でも良いっていう訳じゃない。
オトコよりオンナだ。
とくにオーエルだ。
おい、マヌケ、お前はあれが得意だったな、みんなにそれを教えてやれ》
《よぉっし、それでは良いか、みんな良く聞けよ。
まず、ベンチに坐っているオーエルの後ろから静かに近づくんだ。
そして、お腹なんかすいてないような顔をして、
前に歩いていって背を向けたまま坐るんだ。
それから、しばらくしたら、なにげなく振り向いて、
ゆっくりと近づいて行って、
オーエルの脚に腰を軽くこすりつけるんだ。
そのとき、気持良さそうにミャーオと鳴くことを絶対に忘れないように。
それからよく聞けよ、ここからが最も大事なところなんだ。
腰をこすりつけたあと、最後に尻尾を巻きつけるようにして、
やさしくやさしくその脚をなでるんだ。
そうすればいちころよ。
オーエルたちは、お前たちより気持良さそうな声を上げて自分の食べ物を
どんどん分けてくれるというわけだ 》
《みんな判ったか。
でも、これはあれだぞ。
みんないっせいにやってはだめだぞ。
それから、これはほんとうに困ったときだけにやるように。
よし行こう》
《なあ、マヌケ、お前はどうしてそんなに得意なんだ》
《いやあ、それはオレにも良く判らないんだ。
うん、どういうわけか、オレがずっとニンゲンに近づいていくと、ニンゲンはマヌケ、マヌケと言って楽しそうな顔をして、なでたり食い物をくれたりするんで、それで、ついニンゲンが好きになって安心して近づいていくうちに色んなことを覚えるようになったというか、得意というか、、、、》
《おい、みんな、マヌケのやり方をよく見て真似るんだぞ。
さあてと、オレはほかを当たってみるか、、、、》
・・・・・・・・
「わたしだってほんとうは反対さ、でも、しょうがないじゃない、あの娘が好きなら。もう心配するのは止めよう。気持ちよく帰れなくなりそうだから。せっかくの娘の晴れの日だというのに」
「アッ、やっぱり残り物を持ってくれば良かったわ。もったいないと思ったんだよね。残念ねえ。持ってくればネコに上げられたのに。野良猫かしら?」
「さあ、そろそろ行こう。汽車の時間に間に合わなくなる」
《やっぱり、つい止まってしまうな、なんかくれそうな気がするからなあ。
ああ、行っちゃった。
それに比べて、メガネをかけて黙っているこのニンゲン、なぜなんにも感じないのかな。
寝ているんだろうが、起きているんだろうか。
オレの嫌いな花の匂いがするけど、生きているんだろうか、死んでいるんだろうか。
いつだったか、こんなニンゲンにひどい目に会わされたことがあったな。
サラリーマンという奴だ。
道ですれ違うとき、なんにも感じないので安心していたら、いきなり腰を蹴り上げられた。
オレはどれほどぶっ飛んだか。
今もあのときの息の匂いが忘れなれない。
それに、そのとき蹴られた腰がときどきいたむことがある。
ほんとうに何を思っているか判らない人間だ。
あんまり近づきたくない、やさしいニンゲンなのか、恐ろしいニンゲンなのかさっぱり判らない、早く離れよう。
ああ、この感じ、このなんとなく緩んだ感じ。このどうでも良いやあという雰囲気、これがガクセイという奴らだな。
ここは安心だから、ひと休みでもするか、、、、》
「ところでさあ、就職する会社決まった?」
「いや。正直言って、いま何もやってないんだ」
「どうするの」
「どうもしないさ。べつに慌てて就職しなくたって。アルバイトだってちゃんと食べていけるんだからさ。ちがう話しをしようよ。せっかく久しぶりに会ったんだから。天気もこんなに良いんだしさ」
「でも、これは君の人生にとって、ものすごく大事なことじゃないか、そうは思わない」
「もういいよ、僕のことなんか。君はもう決まったんだから、それで良いじゃないか」
「そうもいかないよ。なあ、友達なら心配するのは当たり前じゃないか」
「僕にはどうもしっくり行かないんだよ。その就職するとか、会社に入るとかいうやつ。なんかイメージが暗いんだよ、ふる臭いんだよ。世の中が高度情報化社会になろうとしているときに、満員電車に乗って会社に行って、決められた時間に仕事をするというのはなんか嫌なんだよ。他にやりようがあるような気がするんだよ。たとえばパソコンを使ってさ、自宅で好きなときに好きな時間だけ仕事をするとかね。おそらくこれは近い将来主流になると思うよ。そういう仕事ならやっても良いけど。今のシステムじゃ嫌だね。働く気がしないね。まだ自由で、給料のほうもそれほど変わらないアルバイトのほうが良いよ。まさか君が公務員になるなんて夢にも思わなかったよ。公務員になってなにしたいの。公務員って公僕だよ」
「公務員だってりっばな仕事だよ。国民のために働くんだから」
「まあ、立派じゃないなんて言ってないけど。でも、だって、君は昨年の今頃なんて言ってたと思う。国のためとか会社のためとか言って、組織の中で歯車のように働くのは嫌だって言ってたじゃないか。もっと自由な立場で痛いって。個人が組織の中に埋没しないような、個人が何よりも尊重されるようなところで働きたいって言ってたじゃないか。ところが、四年になったとたん、他の学生のように、眼の色を変えてあっちこっちと走りまわった挙句、そのうちにあっさりと決めてしまったんだよね。君の考えに僕は大賛成だったので、なんか裏切られたというか、ほんと、ついて行けないという感じだったよ」
「まあ、良いじゃないか、時間が立てば人間の考えは変わるもんだよ。君はちょっと過去にこだわりすぎたよ。だいいち、個人個人って、個人が大切かもしれないが、国だって会社だって大切だと思うよ。いや、一番大切なことかもしれないよ。だって、国のない人間なんて世界のどこを探したって居ないじゃないか。誰もがどこかの国に属しているんだよ。居たとしてもそれは惨めなものじゃない、難民とか呼ばれてさ。会社だってそうだよ。会社が在るから、人々が集まって、生きるために協力して色んな仕事をやっているんじゃないか。だから、まず国が在って、次に会社や家族があって、そして、最後に個人があって社会が成り立っているんじゃないか。これは世界のどこでも変わらないと思うよ」
「嫌、僕はどうしてもそんな考えには賛成出来ない。まず個人があるんだよ。個人が社会の基本であり原点なんだよ。個人が最初に在るからこそ、君のように色んなことを考えて自由に言えるんだよ。もし個人がなかったら考えなんてなんにも言えなくなるんだよ。とにかく、まず個人。個人が二人集まって夫婦ができ、子供が生まれて家族ができ、家族が集まって社会ができ国家になるというわけだ。だから、何よりも基本となる個人から出発して物事を考えるべきだと思うよ」
「そうかなあ。これじゃいつまでたっても平行線だな」
「だから、もう止めようよ。こんな話しはつまらない。以前のように音楽とか女の子の話しをしようよ。ネコは良いなあ、チョウチョなんか追っかけたりしてさ。悩みなんてないんだろうな」
《おっとっと、どうしたんだろう、オレは。
チョウチョなんか追っかけたりして。
食おうとしたんだな。
腹が減ってるからなあ。
まずいのは判っているのになあ。
ついつい捕まえようとしてしまったなあ》
「ネコに知能指数って在るかなあ?」
「ある訳ないじゃない。どうやって、はかることが出来るんだ。文字を読めも書けもしないネコが、どうして解答用紙に答えが書けるんだ」
「そうだよな、ネコに知能指数があったら人間なんかに飼われてなんかいないよな」
《なんとなくにぎやかというか、うるさいというか、この緩んだ感じが良いなあ。
のんびりして、みんなオーエルから食い物もらったかなあ。
あれ、どうしてツヨソウが一緒にいるんだろう。
まあ、良いかオレは他を探そう。
どうしたんだろう、このうきうきとした感じ。
このベンチの人間は何者だろう。
一人は会社員のようだが、もう一人はホームレスのようだ。
なんとなくのんびりとした雰囲気だ。
どれ、またひと休みでもするか》
「ほんとうにすみませんね。こっちからお願いして、わざわざこんな所までおいでいただいて、本来なら喫茶店とかでお話するのが良いんでしょうけど、なにせ他人には絶対聞かれたくないような大事な内容なものですから。
どうですか、こうやって見渡してみても、近くにいるのはネコぐらいで人に聞かれる心配なんてまったくないでしょう。それに天気もいいことだし、自然も美しいし、なんとも申し分ないですよね。
それではさっそくですが本題に入らせていただきます。先ほどもチラッとお話ししましたが、実は、わたしは真理というか、ある革命的な勉強方法を発見したんですよ。それでその方法を実行するためには、どうしてもある装置が必要なんですよ。それでお宅の会社にぜひその装置を開発してもらいたいと思いまして、この話しを持ちかけた訳ですよ。アッ、そうですね。その勉強方法ですね。それは英語の勉強方法ですよ。いや正確に言うと英会話のとくに聞き取りの勉強方法といったほうが良いかもしれませんね。
ところでお宅は英語得意ですか、、、、そうでしょうね。顔に出てますよ。英語の読み書きは問題ないが、聞いたり離したりするのはちょっと苦手だなあって。わたしなんかどっちも苦手ですけどね。いや正確に言うと苦手だったと、言うべきかな。
それはそうと、お宅は有名大学を出られて、今の会社に入られたと思うんですが、どうです、大学を出るまで何年間英語を勉強しましたが、十年でしょう。それなのにどうして英会話ができないんでしょうね。いや、これは、あなただけに言える事ではなくて高等教育を受けた誰にも言える事で、日本の教育全体の問題なんです。今盛んに問題にされていますよね。学校での英語の勉強方法は間違っているんではないかってね。わたしの個人的な体験を話させていただきますと、わたしは中学までは何とか付いていけました。でも高校になると覚える英単語の数がべらぼうに多くなるだけじゃなく、文法もますます難しくなるし、ほとんどついていけなくなりました。
実はいまだにそうなんですが、似たようなつづりとか似たような発音の単語の区別がどうしてもつかなかったですね。とくに抽象的なものを表すのに多かったですけどね。そのうえ発音記号はどうだとか、アクセントの位置がどうだとか、ということになるとほとんどパニック状態に近いものがありましたね。もうそうなると英語の勉強なんて苦痛以外の何物でもないですからね。テストの点数も十点とか二十点でますます嫌いになっていきましたよ。そんな体験しかありませんから、私に英会話が出来るなんて、はなから無理だとあきらめていましたね。
それはそうですよね。はっきり言って、わたしたちが日本語を話せるのは、なんにも知らない赤ん坊のときからずっと、英語とは比較にならないくらい豊富な日本語体験をしているおかげですからね。それはアルファベットや文法以前の問題ですからね。だから、英語の実際の体験がいかに大切かということはあえて言うまでもないのですがね。英語の実際の体験、つまり、生きた英語の体験とは、簡単に言うと、音その物の体験、つまり、、、、音体験、、、、」
「あのう、青野さんとおっしゃいましたっけ。お言葉ですが、それは、いまや常識となっているんじゃないですか。だから、いま外国人から直接教わる英会話学校がブームになっているんじゃないですか。実は、わたしはいま、週に二度ほど通っているんですよ」
「ええ、ごもっともです。それをおっしゃられるとわたしには返す言葉もございません。たしかにその通りなんです。なにしろ英会話を身につけるのに一番良いのは、イギリスやアメリカにいって、実際にそこで生活してみることですから。そしてその次に良いのは、あなたのように英語を話す外国人から直接教わることだということは、だけにも反論する余地のないことだと思いますから。たしかにその通りです。その通りなんですが、でも、お金がかかりますよね。それもけっこうな大金が。それに、度胸って云うか、勇気も必要ですよね。気後れって云うか、恥ずかしさって云うか、そんなものを意に返さないようなね。ども、そこなんですよ。わたしたちの世代には、どうしてもそんな気持にはなれないんですよ。この年になってなにをいまさらって云う気持が大きいんですよ。
でも、そうは思っていても、その一方では、夢のようなことも考えているんですよ。ひそかに勉強してある日突然、英語が話せるようになっているところを女房や子供に見せてびっくりさせてやろうってね。まあ、人生の終わりが見えた中年のささやかな野望といったもんでしょうかね。いや、あなたにはもう察しがついていると思われますが、実は、わたしも英会話の勉強を始めたんですよ。実際の英語体験が必要だと気づいたすぐ後にね。その勉強方法がほんとうに正しいかどうかぜひ確かめたいということもあってね。ただし、あなたのようにお金がかからない方法でね。それに、家族には絶対にばれないような方法でね。知れると、それ三日坊主だとか、また病気が始まっただとか、うるさいですからね。その方法とは、NHKでやっているラジオの英会話を聞き始めたということなんですよ。まあ、予想通りといえば予想通りなんですが、始めたころは、聞き取れるのはところどころの単語と、ちょっとしたフレーズぐらいで、文や会話全体となるとまったくのお手上げ状態でした。それでもわたしはくり返し聞けば何とかなるだろうという気がして、それに、くり返し聞けば、それまでほとんどと言っていいほどなかった英語の実体験の埋め合わせなるに違いないと思いましたので、さっそく、ディスカウントショップに行って、二千円のラジカセと、安いもんですね、たったの二千円ですよ、それに百円のテープを買いました。そのおかげで、たしかに前よりは聞き取れるようになりました。でも何度繰り返しても判らないところは判らない、やはり聞き取れないんですよ。全体の流れや意味のつながりから云って、おそらくこういう単語だろうとか、文法や時制の上から行って。たぶんこういう単語だろうと推測し、頭に思い浮かべながら意識を集中し耳を済まして聞くんですが、やっぱりどうしても聞き取れないんですね。そこでわたしはついにテキストを買い求めました。見ると、ごくありふれた日常会話のどうってことのない内容で、覚える気になれば五分もあれば十分なくらいで、なぜいままでこんな簡単なことが聞き取れなかったんだろうと思うと情けなくなるくらいでしたね。ええ、まあ、ですから、それで完璧なはずだったんですがね、だって、テキストが目の前にありますからね。ところがどういう訳かしっくり来ないんですよ。なんとなく目の前にモヤがかかっているような感じで、思うように聞き取れないんですよ。なんど繰り返してもですよ。単語や文を全部覚え意味も充分に理解してもですよ。なにかが引っかかっている感じで、どうしてもスムーズに聞き取れない。それは意識を集中して聞こうとすればするほどますます聞き取れなくなるという感じでしたね。なにが目に見えない障害が立ちふさがっているという感じで、やっぱり自分にはこの方法は無理なのかなあと思いましたね。まあ、最初の挫折というやつだったんでしょうか、たったの二千円ですからね。そんなに甘くはないぞということだったんでしょうね。まあ、それでもなんとか繰り替え聞くことは続けました。安いとはいえせっかく買ったんですからねえ。ところがしばらくすると、あるとき突然、それまでわからなかったフレーズや分が聞き取れるようになったんですよ。それはどことなく気持に余裕があり、なんとかして聞き取ろうという特別の強い意識が働いているときに起こるようでした。つまり、自然の音を聞くように、素直な気持でいるときに起こるようでした。わたしはそれなりに成果をあげていることが判ったので、その後もどうにかくり返し聞くことは続けました。といっても、まあ、昨日聞き取れたことが、今日になると聞き取れないという二歩前進一歩後退という感じでしたけどね。そのうち、しばらくして、ふと、あることに思いあたりました。もしかして、話された言葉を聞き取ることと文字や文法を覚え文を作り意味を理解することとは、まったくちがう脳の働きではないかという、つまり、ええと、今村さんでしたよね、今村さんはこ存知ですよね。脳はその場所によって任されている役割が違うってことを。それなんですよ。つまり、言葉を、音と言い換えてもいいですけどね。その言葉を聞き分けることを任されている脳と、文字を覚えたりすることを任されている脳とはまったくちがうということ。まあ、具体的にはそれがどこなのかは脳を研究する専門官に任せることにして、今はそれほど重要なことでは在りませんから。
そのようにですね、違うという事がはっきりすると、それまでなんか変だなあって思っていたことが、すべで納得が出来るようになったんですよ。たとえば、先ほどお話ししたように、テキストを見ないで聞き取ろうとするときの変な感じ、いわば、なんとか聞き取ろうとして、意識を集中すればするほど、ますます聞き取れなくなるという感じなんかはまさにそうですよね。聞き取ろうとすること、それはいわば、突き詰めれば、意味を理解しようとすることですからね。ところが実際は聞き取ることが出来ない。そこでテキストを読むことによって記憶され、それと同時に、意味がわかっている単語や文に頼らざるを得なくなる。つまり、音として耳から入ってくる言葉から直接的に理解するのではなく、耳は一応傾けてはいるが、そのじつ、音としてスピーカーから流れてくる英語に一致させるかのように、記憶している文の単語を順番に思い浮かべては、それで聞き取りに成功しているかのように思い込むのである。それが先ほどお話しした目の前にモヤがかかっているような感じだったのでしょうね。わたしたちが小さい時から話している日本語の場合はこんなことはありえませんよね。音から直接的に理解していますよね。音として入ってくる言葉を聞く振りをしながら、頭の中では文字を思い浮かべては、意味を日本語で理解しようとする。はっきり言って、遠まわりですよね。これでは聞こえてくる英語は雑音としてしか受け取れませんね。なぜこんなことが起こるんでしょうね。わたしはこれは簡単に言ってしまうと、聞きなれていないからだと思うんですよ。
学校では、まったくと言っていいほど、本物の英語を聞くことはなかったですから、それは無理のないことかもしれませんが。まあ、日本の英語教育の最大の欠陥でしょうね。ですから、わたしがテキストを買ってきて、それを見てなんとなく安心したのも、そういう教育に毒されていたからなのでしょうね。今では目からうろこが落ちたって感じですよね。ところで今村さんは、今まさにこうしてお話ししているときに、頭の中でわたしが言っていることを反復していませんか。かすかに、そうでしょうね。反復しているでしょう。まあ、詳しいことはわたしにも判りませんが、これが聞き取るということじゃないでしょう。またこのように自然に頭に思い浮かべるように反復できるってことは、今のわたしにはまだ確かなことはいえませんが、もしかしたら、これが、言葉を理解するための必要条件になっているかもしれませんよ。それからですね、このように反復できれば、話を聞いていて、もし突然、意味がはっきりしない言葉が出てきても、全体の意味の流れから推し量ったりして、その大体の意味を理解できるので、慣れている日本語の会話はそれほど苦になりませんよね。
とにかく、これが出来るのは、まさに聞きなれているからなのでしょう。それではここでですね、もう一度、聞きなれていない、と云うことをさらにもう少し詳しく言うと、それは、単語や文法を覚えることを任せられている脳に比べて、音としての言葉を聞き取ることを任せられている脳は、まったくと言って良いほど使われてこなかったということなんです、。そしてですね、その聞き取る脳というのは、覚える脳が個人によって生まれつきその能力が決まっていたり、なにかを覚えれば覚えるほど、その能力があるといわれたりするのとはちがって、先ほどもチラッとお話ししましたね、くり返し聞いたことがそれなりの成果があったと、その様にですね、くり返し聞くことによって、つまり、同じ刺激をくり返し受けることによって、その能力は目覚めたかまっていくもののようです。というより、訓練のように聞く体験を重ねることによってしか、その能力は働き始めず、かつ体験しいてるときだけしか働かず、その能力は高まらないといったほうが良いかもしれません。もうこれで十分に納得いただけますね。先ほどわたしがちょっと言いかけましたが、英語の実際の体験、生きた英語体験、つまり、音体験というものが、英会話を身につけるためにいかに大切かということが、もうこれでお判りいただけたような気がします。
これだったんですよ。わたしが最初にお話しした、わたしが発見した真理というのは、、、、
ところで、こんな話しを聞いたことはありませんか。わたしはテレビニュースで見たんですが。昔話をする九官鳥なんですよ。そうですよ、昔話をですよ。カラスやオウムなど色んな鳥が片言をしゃべるのは知っていましたが、長く話すのは初めてですよ。考えられないですよね。果たしてその九官鳥は意味を理解しているんでしょうか、いや、そうは思えないですね。それから覚えようとして覚えたんでしょうか、いや、それも違うでしょうね。不思議ですよね、文字も文法も知ってるわけじゃないのに。ましてや発音記号やアクセントの位置だって知らないでしょうし。いやあ、とにかくすごいですね。しゃべれるってことは五十音を聞き分けられるってことですからね。おそらく、英語で話し掛けていたら、その九官鳥は英語でしゃべれるようになっていたでしょうね。いやあ、ほんとうに驚きですよね。鳥にそんな能力が在ったなんて。でも、わたしはこう思うんですよ。飼い主がなんども同じ事をくり返しくり返し話して聞かせたからしゃべれるようになったんだって。つまり、鳥にもなんども同じ事をくり返し聞かせることによって、その能力が目覚め高まっていくという人間の言葉を聞き分ける力があったと云うことですよ。そうですよね。
今村さんもお気づきになったでしょうが、わたしたち人間にもそれと同じ能力、いやいや、脳みそは鳥よりはるかに大きいですから、きっと、それ以上の能力を発揮できることはは違いないですよね。鳥に出来て人間に出来ないはずはありませんからね。だから、わたしたち日本人が、わたしたちにも鳥と同じ様な能力が備わっていることを信じて、本物の英語をくり返し聞いていれば、そのうちに、外国人と同じ様にしゃべれる様になるはずですよね。そうなれば、もう、ああ、聴き取れないなどと言って頭を抱えるようなこともなくなるだろうし、英会話コンプレックスからも開放されるようになるでしょうね。
そうですね、ええと、ここで、ちょっと話しはわき道にそれますが、今村さんは自転車に乗れますよね。ええ、それじゃ、なぜ乗れるか判りますか」
「なぜ、なぜ乗れるんでしょうかね。判らないです、考えたこともないですから」
「そうでしょう、私だってそうですから。いや、誰だって、そうですよ。なぜ乗れるかなんて考えることは、人間はなぜ歩けるかって考える事と同じぐらいナンセンスなことかも知れませんからね。だって、そう聞かれたら誰だって、歩けるから歩けるとしか答えようがないでしょうからね。同じ様に自転車だって乗れるから乗れるとしか答えようがないでしょうね。仮にあるとしても、せいぜい体が覚えているくらいでしょうか。いわば、それは呼吸と同じくらいに自然なことであり、ほとんど無意識のうちにやれるってことなんでしょうね。でも、最初はそうじゃなかったはずですよ。みんな悪戦苦闘をしたはずです。なんとか乗ろうとして、バランスをとることに一生懸命で、しかし、なんども転んでは擦り傷を作り、痛い思いをし、そのたびに止めようと思ったり、自分には無理なんじゃないかと絶望的な気持になったり、でも、しばらくすると、再び勇気を沸いてきて練習を始めると云うことを繰り返しているうちに、ある日突然のように、乗れるようになったはずです。ところが今ではそんな苦労も忘れて、あたかもオギャアと生まれたときから乗っているかのように思っているんですよね。ところで、このことは、わたしたちが日本語をしゃべっている事とどこかにていませんか。先程の、なぜ自転車に乗れるかっていう質問を、なぜ日本語をしゃべれるかという質問に置き換えたら、そっくり同じじゃないですか。もし、今わたしたちが、なぜ日本語をしゃべれるのかって聞かれたら、おそらく、たいていの人はこう答えるでしょうね。しゃべれるからしゃべれるとか、日本に生まれたからしゃべれるとか、あたかも自然に身についたかのようにいうでしょうね。でも、言葉を身につけたのだって、自転車に乗れるようになったのと同じだと思いますよ。ほとんどの人は赤ん坊のときのことなので、忘れているだけで、意欲と努力とくり返しの練習が必要だったと思いますよ。たとえば、赤ん坊は生きることに一生懸命で、とにかく周囲の状況に耳を傾けることがまず意欲の現れであり、また多くの愛情を受け入れ、より多くの欲求を満たすために、周囲とコミュニケーションをはかろうとして言葉を発することは努力であり、そして、そのなかで、親や兄弟たちの語り掛けを何度も耳にすることや、その片言の言い間違いを直されることは、くり返しの練習であったはずである。そのおかげでわたしたちは今では無意識のうちに自転車に乗れるのと同じ様に、自然にまるで、この世に生まれたときから話せるかのようになっているのである。アッ、そうそう、また話題を変えて申し訳ないんですが、ここで一つ質問しても良いですか、もしあなたがですね、いま一輪車に乗ることを義務付けられたとしたら、さあ、どうしますか」
「まあ、とりあえず、一輪車を買ってきて練習ということでしょうか」
「そうですよね。間違っても一輪車に乗れるための本など買い求めたりしませんよね。仮にそんな本があったらの話しですが。わたしもまずは練習でしょうね。実は、わたしの小学生の娘は乗れるんですよ。確か、二年生のとき一週間ぐらいで乗れるようになったんですよ。なんか聞くところによると、乗れるようになるためには、その人の年齢に比例した時間がかかるそうで、そうなるとわたしの場合、少なく見ても四十日ぐらいかかるってことでしょうか。それから運動というのは小脳というやつが、頭の中のね、その小脳が関わっているみたいですね。しかし、ほんとうは小脳の話しなんてどうでも良いなですよね。大事な働きをしていることは判りますが、いまさらそれを知ったからといって、そのおかげで早く乗れるようになるわけじゃないですからね。とにかく今のわたしには、真面目に熱心に、そしてより多くの体験をすることが大切だとわかっていますから、ひたすら練習でしょうね。それも、たとえ転んで多少痛い思いをしようが、、より早く身につくようにと、足をペダルに縛り付けたりして、体に覚えこませるように繰り返し繰り返し練習に励むんでしょうね。ところで、今村さんはもう気付いていると思いますが、これは英語を聞き分けるためにくれ返しくり返し聞いていることとそっくりではありませんか。運動と聴覚とは多少の違いはあると思いますが、先程の自転車に乗れるようになったことと、日本語を話せるようになったことの例からも判るように、もうほとんど同じと見て良いでしょうね。ですから、当然、英会話を身につける上で本物の英語をなんどもくり返し聞くことは、間違いなく効果があると云うことを、きっとあなたに賛成していただけると思います」
「なんだか判った様な判らない様な、そう思えば思えないこともないのですけど、まるで、宗教の勧誘を受けているみたいですよ。ところで、その方法を始めて半年ということですが、効果は出ているんですか」
「ええ、まあ、出ていると言えば、出て、いや、出ていますよ」
「なんか変ですね。自信なさそうですね。青野さんのお話しだと、文字や文法を覚えることはなんの役にも立たないことのように聞こえるんですが、ということはですよ、いま学校では無駄なことをやっているということですか。わたしにはどうしてもそうは思えませんね。文字や文法というのは、語学の基本中の基本ですから充分に役にたっていると思いますよ」
「いや、役に立たないというのは、英会話のとき、その外国人がしゃべる英語を聞き取る能力の向上には、まあ、ほとんど役に立たないだろうということなんです。その他のとき、たとえば、本をよんだり手紙を書いたり翻訳したりするときには、充分過ぎるくらいに役立っていると思いますよ。だって文字や文法、つまり、単語や構文を覚えることは、人間に生まれつき備わっている素晴らしい能力の一つですから、わたしは意味もなく否定しようとは思いません。それはそれでどんどん活用していくべきだと思います。知識を広めたり、研究や学問を発展させるためには、絶対に必要なことだと思います。しかし、そのことはすべての人に当てはまるでしょうか、それは、そうことに携わる本の一握りの優秀な人たちにだけ必要なのではないでしょうか。わたしたち普通の人にとっては、そうですね、外国に旅行に行ったときにそれほど困らない程度に日常会話ができ、洋画を見たときには、字幕スーパーを見なくてもストーリーが判ればそれで充分なんです。ところが、今のわたしたちはそれさえも出来ないんです。何年間も学校で勉強してきたというのに。わたしたちはよっぽどバカなんでしょうか。それとも、学校教育が悪いんでしょうか。でも、わたしは、わたしたち普通の日本人がそんなにバカとはどうしても思えないので、やはり、学校で教える勉強方法のどこかに欠陥があると思わざるを得ないのです。たしかにですよ、頭のいい人たちは、人並み以上に単語や構文を覚える能力があり、英会話のときも、聞きながら同時に頭の中には文字であらわされた文を思いうかべて、それからすばやく意味を理解するんでしょう。そして、しゃべるときも同様に、まず最初にしゃべりたいことを文字であらわされた文を頭の中で作り、それらを思い浮かべながら、なぞるようにしゃべるんでしょうね。でも、わたしにはその方法はゆがんでいるというか、遠まわりをしているというか、あまり良い方法だとはとても思えないんです。言葉が本来持っている機能や役割に反しているような気がするのです。 さっきわたしが、少しあいまいな答え方をしたので、なんか自身がないように見えたんでしょうけど、それは効果がないからではなく、いや、効果はほんの徐々にではあるんですが、たしかに出ているんですよ。そうではなくて、その効果が出ていることを、あなたのような他の人に、いや他の人だけでなくわたし自身にもはっきりと判るようにね、どうすれば示すことができるんだろうかと、ふと思ったからです。文や構文を覚えるときは、これとこれを覚えたんだぞと自分にもはっきりと判りますからね。そして、その成果をペーパーテストでもって、はっきりと確かめることができますからね。ところが聞き取るということは、わたし自身の内部の問題ですから、つまり、生きた感覚のことですから、現実になにかを聞くことによってしか、しかもその聞いているときだけしか、その効果を確かめることができませんからね、それから今でも相変わらずこんなことがあるんですよ。以前に聞き取れたことが、何日か後に再びそれを聞いても、すぐに同じ様に聞き取れないということが、、、、それでちょっと言いよどんだのですよ」
「やっぱりそれは覚えることを無視して、聞くことばかりに偏りすぎているからじゃないですか」
「いや、はっきり言いますが、それは違いますね。覚えることは覚えるんです。文や意味を覚えるということはとても簡単なことなんです。なぜなら、物を覚えるということに深さなんてありませんからね。それはもう機械的にあっさりと一度覚えるだけで充分なんです。今問題にしているのはそう云うことじゃなくてですね、、、その再び聞いたときに聞き取れないというのは、その音の流れはどうにか追って行けるんですが、その内容というか、雰囲気というか、そう言うものがつかめないので入っていけないというか、しっくりとしない感じなんですよ。ですから、しばらくしてちょっとしたきっかけで、たとえば、単語やフレーズが聞き取れたり、文の全体の内容を思い出したりすると、そのあとは以前の同じ様に聞き取れるようになるんですよ」
「それは記憶しているからこそ、できることじゃないですか。それならやっぱり覚えることは重要だということになりませんか」
「ええ、記憶、つまり覚えることが重要だということは、確かにその通りなんですが、でもそれは、文字であらわされた文章の記憶ではなく、全体の内容の雰囲気、とくに音で表された感覚的な記憶、つまり、簡単に言ってしまうと音の記憶ですか。ですから、後で再び以前のように聞き取れなかったというのは、その音の記憶が良くできていなかったと言う事になります。よく音の記憶ができていなかったということは、よく音を聞き分けることができなかったということですから、つまり、よく音に慣れていない、またはなじんでいなかったということです。ということは、まだまだくり返し聞くことがたりなかったということですよ。それよりもですね。わたしはむしろ、どうしてもテキストに頼りがちになるのが我ながら心配ですね。聞き取るということが苦痛なのか、それとも不安なのかわかりませんが、まずとにもかくにもくり返し聞くことを自分に課していながら、最初からテキストに目をやりその内容を覚えて、少しでも楽に聞き取ろうという安易な方法に頼りがちになるんですよ。なんど聞いてもどうしても判らないときだけ見ればいいものをその方法こそが集中力が出て最も良い訓練になると自分では思っているのですが、どうしても辛抱できないんでしょうね。文章を記憶すれば、それで理解したと思い込む長い間の癖からどうしても抜け出せないんでしょうか。あれ、いつのまにか、また繰り返し聞くことが大切だということになっちゃいましたけど、アッ、そうそう、先程わたしは、この半年の間、わたしの聞き取り能力がどのくらい上達したかを示すのはほとんど不可能の様なことを言いましたが、でも、それは客観的にと言いますか、つまりどんな人にも納得できるような形では、ということでして、実際にわたし自身の内部では、この間いろんな変化が起こっておりまして、改めて色んなことに気づいたり、言葉と云うものに関して深く考えさせられるような様々な発見がたくさんあったんですよ。改めて気づいたことといえば、たとえば、冠詞がありますね、アとか、ザとか、聞き始めたときは最初言ってないんじゃないかとか、省略しているんじゃないかとか思っていましたよ。だって、ぜんぜん聞き取りなかったですからね。ところがそのうちに慣れてきて、なんとか聞き取れるようになると、ちゃんと言っていることが判りましたね。かすかにではあるが微妙なタイミングで、たしかに発音されているんですよ。決して省略なんかされていなかったんですね。それはまるで冠詞が本来持っている意味的な重要性からというよりも、表現の語調を整えて言い易いようにするために発音されているかのようなんですよ。それから、わたし自身の内部の変化としては、たとえば、単に聞き取りやすくなったというだけどゃなく、聞いている最中になんとも懐かしいものを耳にしている様な、そんな感情的なものを感じるようになってきたんですよ。それこそまさにくり返し聞くことによって、音に慣れてきて徐々に身にいてきたという証拠なんでしょうか。日本語に置いては、わたしたちはもう日常的に経験していることなんですけどね。それからこんなこともありましたよ。英語では複数や三人称にはエスをつけたり、過去形にはイィディをつけたりしますが、今までは決まりごとなんだからと機械的に知識として覚えてきましたが、なぜそうするかの本来の感情的な意味や、感覚的な広がりとか雰囲気といったものが、からだの内側から接しているかのように、なんとなく判るようになってきたんですよ。たとえば三人称のとき、動詞にエスを付けるとき、そうするとによって、それは私達ではなく私達から区別されはなれたものと云うことを感じさせるようになっているんですよね。それから、複数を表すとき、エスを付けることによって、なんとなく簡単でないような、ごちゃごちゃしたような勢いが在るような雰囲気を感じさせるようにできているんですよね。それから過去形だって、イィディを付けることによって、今現在でないもの、なんとなく重そうな時間の広がりを感じさせるようにできているんですよね。発声に関する発見としては、アクセントや発音が正確であるというよりも、リズムや抑揚が大切だということでしょうか、だってリズム感があまり必要でないとされる日本語でさえも、アクセントや発音が多少違っていても、理解できないとはないが、リズムや抑揚がぎこちなかったりずれていたりすると、意味がまったく通じなかったりすることが在りますからね。英語の場合、リズムや抑揚を重要視するあまりですね、日本語では考えられないような文の区切りや省略の仕方や言いまわしがあるので、戸惑うくらいですよ。でも、そもそも日本語で身についたやり方が英語に通用すると思っていたのが間違いなんですけどね。英語にはなんか日本語とは違う独特の法則みたいのがありますね。それは、おそらく、日本語にだってあるんでしょうけど。英語だからこうなるんだというなんか有無を言わせないものがありますね。でもかといって、でたらめで乱雑かというと決してそうではなく、無理がないというか、自然というか、こうなるからこうなるんだという合理的で必然的なものがありますね。そして、それは、わたしたちが頭の中で安易に考えたような理屈ではなく、感覚的というか、身についた肉体的というか、そんなものを含めたものの中からわき起こってきたというか、そんな理屈なんですよね。たとえば文ですが、これは見た目は単なる単語の配列ですけど、わたしたちは文法として主語の次は述語とか、助動詞の位置はこことか、この場合の前置詞はこれであるとか、まるで文が作られる以前からその文法は存在している法則であるかのように覚えこんであり、また実際にも文章を書いたり理解したりするときには、それを厳密に当てはめたりしているんです。でも、現実には、これはたぶん、日本語においても同じなんでしょうけど、後から頭の中で考え出され付け加えられた理屈なんですよね。ですからわたしは、そもそも最初は、しゃべる者と単語があり、そして次に単語の配列があると考えたいですね。そこでは単語はどのように配列されるかによって、その単語自身は、おのずと色々な役割をその文の中で負わされるようになるんですよ。英語の場合はとくに、単語の順番が重要視されるみたいですね。なぜなら、これはなんどもくり返し聞いているうちに肌で感じるように判ってきたんですが、しゃべるものは単語だけでなく、その配列の仕方に感情的な意味や意志を付け加えたり込めたりしているみたいです。そのことがはなつれる内容に奥行きや深みや生き生きとした感じを与えているんでしょうけど。そしてこのことは前にも触れましたが、しゃべる者の内部から自然と沸き起こってきたように、無理なくしかも非情に合理的で必然的でさえあるんですよね。ときどきなるほどと、なんて絶妙なんだろうと感じさせる表現が在りますからね。もし英語を日本語のような配列で意味を持たせようとしたら、きっと助詞のようなものが必要になったり、前置詞が後ろについたりするようになったりするんでしょうね。そうしたほうがしゃべりやすく聞きやすいという理由でね。このような事は日本語の場合にも充分に当てはまりますよね。たとえばわかりやすい例で言えば、鉛筆を数えるとき、わたしたちは、いっぽん、にほん、さんぼんと、助数詞の部分を、ぽん、ほん、ぼんとそれぞりに言い換えますよね。はたしてこのときわたしたちは言い換えていると云うことを意識しているでしょうか。これは誰かに教えられて出来るようになったのではないですよね。ほんとうに自然ですよね。わたしたちはなぜそうするのか判らないけど、とにかくそうせざるを得ないんですよね。しかし、かといって、それは決して思いつきや気まぐれで言ってるのでもないですよね。でも、よくよく注意してみると、前の数の部分の言い方と関連していることからして、そこにはなんか法則のようなものがありますよね。わたしはそれは、少し前に述べたように、ことばをしゃべるときに、しゃべるものを支配しているというか、その体内に流れているというか、それと似たような必然性や合理性の働きによるものだと思います。そこでわたしは今まで述べてきたこのようなですね、英語にも日本語にも、いやすべての言語にも当てはまるような合理性をですね、わたしたちが頭の中で考えるような合理性とは区別してですね、それとは違う合理性、つまり、わたしたちの肉体の中に生まれつき備わっている所の合理性と考えてはどうでしょうか。今これを仮に内的合理性とよびましょう。そうですね、このことをもっと判りやすく説明するのに何か言い方法がないでしょうか、アッ、そうそうこんな話しはどうでしょうか。音楽についてですが、その前に、ニ、三、質問しても良いですが。今村さんは音楽が好きですか、よく聞きますか」
「ええ、好きですよ。聞くのも、歌うのも」
「そうですか。わたしも好きですけど。ところで、クラシックはどうですか」
「ええ、聞きますよ、たまにですけど」
「うん、これはちょうど良い、実はわたしもそうなんですけど。クラシックってなんか変ですよね。わたしにはこんな体験があるんですよ。中学のとき、音楽の時間に始めたレコードで聞いたんですけど、なんか大げさで騒々しく、雑音みたいな感じで良く判らなかったです。でもその後なんどか耳にしながら年を経ていくうちに、だんだんじわっとしみるように判るようになって来たんですよ。これはなんでしょうね。簡単に言えば、聞きなれて親しみやすくなったという事なんでしょうけど、やはりくり返し聞く事の効果が音楽にも当てはまるという事なんでしょうか。不思議ですよね。こんな事もありませんでしたか。子供の頃、歌詞の意味も良くわからない大人の歌を覚えてうたっていたことが。どうして意味も判らない言葉のつながりを覚えられたんでしょうね。まあ、考えられる事は、これはたぶん、まず覚えやすいメロディを先に覚えて、その流れのなかで、その流れに従わせるかのようにして自然と歌詞を覚えたんでしょうけど、まだ良く判りませんね。あっ、本当はこんな話しじゃなかったですよね。だいぶわき道にそれましたね。話しを元に戻しましょう。ところで今村さんは音楽に理論があることご存知ですよね」
「ええ、詳しい事は知りませんが、でもあるんでしょうね」
「そうなんですよ。わたしも詳しいことは知りませんが、在るんですよ、たしかに。一般にはあまり知られていませんがね。これからあげる例は音楽の基礎みたいなもので、理論というほどのものではないんですが、簡単で判りやすいので上げますが。音階というものが在りますね。ドレミファソラシドと。その始めのドから終わりのドまでは一オクターブなんですが、音の周波数は機械で計ったようにちょうど倍になります。たとえば、いま仮に、始めのドを四百ヘルツだとしたら、その次のドは八百ヘルツというふうに。これはこの後も一オクターブ上がるごとに同じことが言えます。つまり次の一オクターブ上のドは千六百ヘルツ、そしてその次は三千二百というふうに。とにかく倍、倍になるんです。それからその一オクターブの間には十個のそれぞれ周波数が違う音があってそれらの音の周波数には、確か高校の数学で習いましたね、あの等比級数という法則を当てはめる事ができるんですよ。それから和音なんですが、それぞれ周波数が違う音が組み合わさってできているんですが、もしその音の組み合わせがでたらめだと、その和音の感じは不快で落ち着きのないものになるが、もしその組み合わせがなんとなく理屈に当てはまりそうだと、その和音の感じは、聞いて気持の良い調和の取れたものになるという具合にですね、その組み合わせというものが、なんともびっくりするくらいに絶妙で、まるで計算され尽くしたかのように法則的なんですね。そこには美しすぎるくらいの合理性が働いていると云うことを、誰もがきっと納得するに違いありませんね。これはまさに数学であり科学ですよね。音楽というのは数学や科学とはまったく正反対である感性の産物と考えられているのに、裏ではひそかに通じ合っているなんて不思議ですよね。しかし、わたしたちが歌を歌ったり聞いたりするときに、そんな周波数がどうだこうだとか、和音がどうのこうのとか、質面倒くさい理屈なで意識しているでしょうか。いやまったく意識していませんよね。というより、そんな事を知らなくたって、わたしたちは十分に音楽を楽しむ事ができるんですよ。なぜなら、そういう合理的なことを感じたり理解したりする能力がわたしたちの肉体には生まれつき備わっているからです。もう今村さんはわかりましたね。こういうことだったんですよ。わたしが先程言った内的合理性というのは。これで十二分に納得いただけるんではないでしょうか。ところで、こういうことは音楽だけに限らず、他でもいえますよね。たとえば、動作とか運動のときにも。わたしたちが行為として何か新しいことをやろうとするとき、最初はたいていぎこちないですよね。でも、そのうちにだんだん慣れてくると、体からは余分な力は抜けて動きがスムーズになってきますよね。とくにスポーツの場合はそれがハッキリとでますよね。練習してうまくなっていくにしたがって、動きはますます無理のないものなっていきますよね。そして無駄な動きが完全になくなって、それがあまりにも自然で理にかなっているように見えるときは、美しいと形容されるほどですよね。これなんかも、わたしたちが意識してやっていることでなく、わたしたちの内的合理性のおかげなんですよね。時間もだいぶたちましたので、もうそろそろ本題に入らないといけないのですが、まだちょっと言いたりない気がするのでもう少し話させてください。このようにわたしはこの半年のあいだ、単に英語をくり返し聞くという事から、こんなにも色んな事に気付き、また色んなことを発見しました。そのなかでもとくに、たった今お話ししましたように、人間の誰にも備わっている内的合理性に従って行動する事の大切さですか、つまり、人間はある程度自分の思い通りに自由に伸び伸びと行動する事が非常に大切であると云うことを知りました。この事は言い換えれば、自分の感覚や気分を信じろということで在ります。つまり、人間は何かをやるときはありのままの自分というものにもっと自信を持って自然にやれという事なんです。わたしはこの事を重要な成果と考えて、ということは、わたしのやってきたことは決して間違いではなかったということですから、今後もいままでのやり方を続けていくつもりです。前にも少し話しましたが、すでにうまく行きそうだという手ごたえは感じていましたから、最近では、ほんとうに英語を聞く事が楽しみなんですよ。時折驚くようなわくわくする事もありますよ。テキストの文を目で追うだけで、音が頭の中で響くようになるんですよ。英語の独特のリズムや抑揚をもってね。ですから聞く事はまるで躍動感にあふれた生き物を相手にしているような感じなんですよ。こんな事は昔学校で英語を勉強していたときには決して味わえなかった事ですよ。わたしが思うには、学校の勉強は、音楽にたとえれば、実際に演奏された音を聞くことなくその楽譜を一生懸命覚えているようなものだと思います。そうですね、もっと判りやすい例にたとえれば、こんなのはどうでしょう。英語という言語を生きている人間にたとえるんですよ。英語を感情や表情や大きさや形を持った具体的に生きている人間とすれば、学校での勉強は、その人間の骸骨について勉強しているようなものではないでしょうか。ここには骨は何本在るとか、ここの骨はこういう構造をしているとか、といった具合に、まったく生命のないものを相手にしているようなものではないでしょうか。それはそうですよね。あえて言うまでのことではないんですが、わたしたち日本人が日本語を覚えたっていうのは、まだ何も知らない赤ん坊のときから、愛情を注ぐ両親や兄弟など、周囲の表情や感情に満ちあふれた人間のいうことをくり返し耳にしながら、その言うことを真似したり、ときにはその微妙な言いまわしや間違いを言い直したりするという豊富な日本語体験のおかげなんですよ。ですから、とにかくそれは、見るだけでも聞くだけでもない、人間の全部の感覚を通して、その全体の生き生きとして雰囲気のなかで、言葉というものを身につけてきたんですから、英語を覚えるのにそれと同じ様な体験をするというのも当たり前であり、必要不可欠なことなんですよね。
ところで、今ふと思いついたんですが、なぜ九官鳥が長い昔話を話せるのか良かったような気がします。それはこういうことではないでしょうか。わたしたちは、日本語の歌だけでなく英語の歌でも、その歌詞の意味が判らなくても覚えて歌ううことができますが、それは前にも話したように、まずその歌の持つ雰囲気ですね、リズムとか調子とか、そういうものに自分をあわせるかのようにするとともに、メロディは覚えやすいので覚えながらその流れのなかで、その流れに従わせるかのようにして自然と歌詞もいっしょに覚えていったということなんですけど。九官鳥もその雰囲気やメロディに当たるものを、なんども繰り返して聞かせる飼い主の中に感じ取っていたのではないでしょうか。たとえば、わたしたち人間が話しているとき、その相手の表情や語調から言葉の意味以上の色んなことを感じてるように、その九官鳥も飼い主がしゃべっているときに、その動作や表情やロ調の中に、人間にも識別できないような微妙な違いを感じ取っていたので、それで覚えられたんではないでしょうか。
もう、すぐ話しがわき道にそれてしまいますね。これまでの話しからすると、すべてが順調にいっているように見えるかもしれませんが、実はちょっと問題があるんですよ。というのも、それはわたしがこの方法を始めたときからずっと解決されずに続いていたことなんんですけどね。それはですね。テープの英語にも慣れ、聞き取りもだいぶ上達したに違いないと自分では思っているんですが、にもかかわらず、テキストの新しい章に入るとき、どうしても最初にその文章の部分を見て、単語の意味を覚え大体の内容をつかんでから聞いているんですよ。そうするのは実は楽だからなんですけどね。何も知らずに始めて聞くのとは、判る量がぜんぜん違いますからね。とにかく聞くことが大切だ大切だといっておきながら、現実は昔のように文字に頼っているありさまなんですよ。まず最初は予備知識なしに聞くことが、意識を集中させて耳を鍛えるという意味で、大変に重要だということは充分すぎるくらいにわかっているのですが、情けないことに我慢できないんですね。聞き取れないという苛立ちのために。そもそも聞き取れないということがいまだに文字に頼る様るさせている最大の理由なんですけどね。聞き取れないのでなんとか聞き取ろうとするから、なんか変に緊張して帰って聞き取れなくなる。そこで今の葉なんだろうと思っていたりすると、そのあいだにテープはどんどん先に行ってしまい、ますます聞き取れない部分が増えていって、そのまま意味も内容もわからずに最後は混乱状態で終わってしまうという悪循環に陥ってしまうということがね。まあ、仕方がないというば仕方がないことかもしれませんね。まだ初めて半年ですから、こんなに早く身についたとしたら、この年で、二、三日の練習で一輪車に乗れるようなものですからね。ですから、たしかに聞き取れないというのは現実なのですから、それを潔く認めて、混乱して先に進めならくらいなら、あらかじめその内容を知っておくのも、今の段階では必要なことかもしれませんね。とにかく、完璧に身につくまでは仕方がないことかもしれませんね。
わたしが試みていることは、自転車に一度乗れるようになれば一生乗り続けることが出来るように、一度身につけたことは決して忘れることがないような方法です。ご存知のように学校での英語の勉強は主に単語や構文を暗記することですが、これはある程度時間をかければ誰でもできます。しかし、その反面、時間が経つにつれて、それは徐々に忘れ去られてしまうということもまた事実なんですよ。その点、わたしの方法はそんなことはまずないでしょう。では、わたしの方法に欠点がないかというと、そうでもありません。わたしの方法はごく稀には、ものすごい短時間で身に付けることが出来るような人がいる一方で、どんなにがんばっても一生身につけることが出来ない人が出るかも知れません。なぜなら、どんなに努力しても、結局一輪車に乗ることが出来ない人がいるようにね。
このようにいろんなことがありますが、今のところ、わたしはどうしても聞き取れないときには、とくに長い文のときですが、、そのときは、そこだけテープを巻き戻して、なんどもくり返し聞くようにしているんですよ。それでも正直いって、ときには聞くことが本当に嫌で嫌でたまらなくなるときがあるんですよ。まるで体の芯から英語に対して拒絶反応を起こしているような感じでね。まあ、それはおそらく、わたしがそれだけ生きた英語体験に接しているということなんでしょうけど。というのもわたしの方法というのは、日本語のリズムや発声のやり方から出来るだけ離れて、英語のそれを、まだ何も知らない赤ん坊のような気持で信頼して、耳に聞こえることだけを頼りに、耳に聞こえるようにありのままに受け入れることですから。これは、言い換えれば、日本語の持つ雰囲気や世界を捨て、英語のそれに身も心も委ねてしまうことですからね。もう少し大げさに言うと、日本人をやめて外国人になろうとしていることですからね。
前に確かこんなことを話しましたね。英語を聞きながら、それからほんの少し遅れるようにして頭の中で反復出来るようになったことは英語が身についてきた証拠だって。まさにその通りなんですが、実は、その反復が出来るというのは、決して発音やアクセントをきちんと聞き分けられるようになったからではなく、ましてや、単語の正確な知識や記憶のおかげでもないんですよね。それこそまさに英語のリズムが体全体に染み付いたかのように、身も心も英語が作り出す雰囲気や世界に完全にのめりこんでいるということが、最終的には重要な役割を果たしているみたいですね。
それにしても聞くって不思議ですね。文法的におかしいと思っていても、聞いてみるとちっとも変じゃない、言葉って聞いて感じが良ければそれで良いのかも知れませんね。とにかくわたしは色々なことにめけずに、真面目に聞き続けているよけですよ。まあ、余談になりますが、フランスは英語によって文化が侵略されるといって、英語を使うのを止めようとしていますが、日本ではそのような心配はまったくないと思います。なぜなら、いまのような頭を使うだけの教育を続けているかぎり体から沸き起こるような拒絶反応は起こりませんからね。ああ、ようやくこれで今日の本題に入れそうです。ここまで来るのにだいぶ時間がかかりましたけど。先程も言いましたが、聞き取れないときテープ巻き戻して聞くというのは、それはそれで良いんですが、でも、よくよく考えてみますと。もう少し効率のいい方法は果たしてないんでしょうか。この先端技術の発達した時代にですよ。巻き戻して聞くというのはそれなりに大変なんですよ。感できちんと決められたところに止めないといけないのでけっこう神経を使うんですよ。それもなんどもくり返しですから。そうなるとむしろ操作のほうに神経が行ってしまって、聞くことに集中できなくなるんですよ。なんとなく時間の無駄をやっているような気がします。
そこで、こう考えるのは当然じゃないでしょうか。もしそんなわずらわしい操作をしなくても、希望するあいだはずっと、できるなら半永久的にくり返し聞くことが出来たら、どんにすばらしいだろうかってね。そうなれば操作に煩わされたり、この決められた時間内に聞き取らなければいけないと自分にプレッシャーをかけて、変に焦ったり緊張したりすることもなくなるので、安心してリラックスして聞けるようになるはずです。そのことは同時にまた、聞こえてくる英語に対しても、本当に無理なく自然に集中できるということですから、落ちついて英語の作り出す雰囲気に身も心もゆだねることが出来るようになり、効果が比べ物にならないくらいあがることは絶対に間違いないことでしょうね。
そこなんですよ。今村さんにお願いしたいのは。あなたの会社にぜひこのような装置を作ってもらいたいんですよ。文は長くてもせいぜい四、五秒ですから、その四、五秒のあいだ、ほうっておいても半永久的に繰り返されるような装置をですね。そんなに難しいことはないと思いますよ。あなたのような専門家にとっては。もしそれが実現すれば、これからどんなに効率よく勉強することができるようになることか。わたしが試みている方法にとって、それは完璧な装置ですよ。まさに鬼に金棒でしょうね。
ところでこのことは私だけのことではなく、すべての人々に当てはまると思います。もし、この装置が売り出されたら間違いなく日本の英語教育に貢献するでしょうし、間違いなくヒット商品になるでしょうね。いや、これは何も日本の英語教育に限ったことじゃないでしょう。すべての国のすべての言語に当てはまることだと思います。ですから間違いなく世界的大ヒット商品になるでしょうね。そうなれば、あなたの会社はどんどん発展するでしょうし、もう、あなただってそれはもう、、、、それにあれですよね。アイディアにも知的所有権とかいうものが発生するんでしょう。そうすれば家族はなんと思うでしょうか、もうわたしに今までのような態度は取れないでしょうね」
「ちょっと良いでしょう。青野さんのお話しは、なんか魔法の話しを聞いているような、そんな気がするのです。わたしには、あなたが試みている方法がそんなに良い方法だとはどうしても思えないのですが。やはり英語を話す外国の人とじかに接して学ぶ方法がすぐれているように見えるのですが」
「いや、もっともです。前にも言いましたが、あなたのおっしゃるとおりです。返す言葉もありません。わたしのやっていることは、音声だけで、そしてその音声を通してのみ英語の作り出す雰囲気を感じながら英語の世界に入っていき、そして英語を身につけようとすることですが、今村さんが英会話教室でやっていることは、その音声だけじゃなく、実際の外国人の身振りや表情や態度から、微妙に変化する意思や感情を読み取りながらですね、それこそまさに具体的体験に裏付けられた言葉、生きた体験ですよね。そうして英語が作り出す雰囲気を感じながら、英語の世界に入っていき、そして、英語を身につけようとすることですから。間違いなくあなたの方法はわたしの方法よりすぐれていると思います。上達も早いでしょう。それはたしかにそうなんですが、前にも少し触れましたが、これはあくまでもわたしのような人間、つまり、英会話を勉強したいが、表立ってするのはなにをいまさらって感じでなんとなく恥ずかしい、ましてや、どことなくコンプレックスを感じていて、外国人と面と向かって習うのは気後れするというか、とにかく嫌だという、そういう中年のためにだけ考え出されたような方法なのです。ですから、もしお金が在って、外国人の前に出ても、冷静でいられる人は、あなたのように英語教室に行って学べば良いんですよ。わたしのような人間は老若男女を問わず、日本には数え切れないほどいると思います。ですから、もしあなたの会社によって開発された装置が世の中に売り出されて、わたしの勉強方法が知られるようになり、本当に効果があるということが噂にでも上るようなことになれば、彼らはきっといっせいに飛びつくでしょうね。それよりもですね、英会話教室に行くほどの大金もなく、従来通りの勉強を続けている中学生や高校生に、まず真っ先に使ってもらいたいですね。そうすれば、これらをあわせた需要は相当な数になるでしょうね」
「くり返し聞くことに本当に効果があるんでしょうか」
「ありますよ、間違いなく。それよりも、今まで、どう見ても効率が良いとは思えないあの面倒くさいラジカセで、それもわずか十回ぐらい聞くだけで、大体聞き取れたんですから、それを新しい装置によって、十回どころか百回二百回と何の操作もすることなくくり返し聞くことが出来るようになれば、その効果はかなりのものになるでしょうね。おそらく、わたしのように頭の悪い人間でも、そこまで繰り返せばどんなに長い文でも間違いなく聞き取れるようになるでしょうね。
とにかく何の操作をすることもなく、くり返し聞けるということはとても良い事なんです。極端な話し、その間はべつに聞こうとしなくても良いんです、なにか他のことを考えていても良いんです。たとえば単語の意味や文法を確認したり、というのも、かえってそのほうが集中できるはずだからです。なぜなら他になにをしようが音声だけはずっと半永久的に流れていますから、いつでも聞けるという安心感からリラックスできますからね。そこでもし百回二百回といわず、千回二千回と聞いたらどうでしょう。そうなれば覚えられるだけじゃなく、英語のリズムが体の心までしみこむでしょうね。それこそもう身も心も外国人ですよね。それがわたしの狙いでもあるんですがね。あっ、そうそう、場合によってはわたしの方法が、あなたのように英会話教室に行くよりすぐれているかもしれませんよ。なぜなら、聞き取れないからといって先生に対してなんどもくり返し言ってくれるように頼めませんからね。とにかくわたしたちは日本人であろうが外国人であろうがみんな同じ人間です、そこまで同じ言葉をなんども聞けば判らないはずないんです、覚えられないはずはないんです」
「判りました。では、なぜそんなに良い方法なのに今まで広まなかったんでしょう」
「なぜ、なぜなんでしょうね、わたしにも、、、、でも、たぶん、英語に自信のある人たちが勘違いをしたからじゃないでしょうか。この場合は英語教育に携わっている人たちのことですが。つまり中学や高校の先生に始まり進学塾や大学の先生、さらにそういう先生たちを管理する地方や国の役人を含めたすべての人たちのことなんですがね。彼らはみんな学校で教科書を使って先生に教えられたから、それに自分たちも努力し真面目に一生懸命に勉強したから、それで英語が得意になり話せるようになったと思っている人たちなんですよね。中にはみんなより特別に頭がいいから英会話ができると思っている人もいるでしょうが。でも、本当は違うんですよね。彼らの勘違いなんですよ。英語が得意だからテストの点数が良いとかいうのは、それは彼らが覚えることが好きで一生懸命勉強したからでしょうが、彼らが人並み以上に外国人と話せるようになったのは、本当は彼らが普通の人たちより、より多くの生きた英語体験を経験したおかげなんです。だも実際は、彼らは、自分たちの努力や頭のよさのおかげだけではなく、教育制度や先生のおかげでそうなっていると思っているのです。そのように彼らは英語教育に関しては、自信と自負心にあふれていますから、そのような自分を作った教育制度を疑うようなことはありえないでしょうね。ましてや自分たちの立場を危うくするような新しい方法なんて夢にも思いつかないでしょうね。そもそも本に書くことができるような内容を人に教えようなんて考えは傲慢ですよね。そんなものは自分で買って読めば済むことですから。本に書くことができないようなことを教えるのが大切なんですから。いまの学校で間違った方法で英語を学ばせること、つまり、英語の生きた体験の少ない先生が、読んで聞かせたり、実際に英語を聞いたこともない生徒に読ませることは害悪以上のなにものでもないでしょうね。もしわたしの方法が有効だと認められれば、全国の何十万という英語教育に携わっている人たちは青ざめるでしょうね。それくらい革命的なことだと思いますよ。
では、その装置についてもう少し詳しく言いますと、普段は普通の再生装置と変わらないのですが、切り替えスイッチがあり、それをたとえばくり返しという方に切れかえると、そのときから、そうですね、区切りの良いところとか、一つの文は時間にして二、三秒から、四、五秒でしょうから、その部分がなんの操作も加えない限りは、半永久的に繰り返されるというわけです。そしてそのうちにもう充分にはっきりと聞き取れるようになったと思ったら、なにか先程のスイッチとは違う簡単なボタンみたいなものを手で触れると、次の部分に自動的に移って、ふたたび繰り返しが始まるというようなものなんです。ところでこんなネーミングはいかがでしょうか、千回君とか、オウム君とか、先生殺しなんて云うのも良いでしょうね、、、、、、」
《おっと、こんなところで眠っている場合じゃないんだ。
早く食い物を見つけないと。
向こうから歩いてくるニンゲン、カイシャイン、オヤジ、おっ、あのオバサンなら鳴いて近寄って行けば何かくれそうだな。
あっ、だめだ、後ろからショウガクセイがいっぱい来た。
あいつらに捕まったらなにされるかわかんねえからなあ。
しょうがないハヤシに行こう。
走ろう。
それにしてもうるさいやつらだ。
やっぱりハヤシは良いなあ。
静かで、でも食い物がないからなあ。
おいおいそこの茂みに隠れているのは誰なんだ。
なんだ、オトナシイとウレイじゃないか。
そんな所でなにしているんだい?》
《うるさい、あっちに行って、お願いだからこっちに来ないで》
《どうしたんだなにをそんなに怖がっているんだ、ウレイは?》
《ウレイの生まれたばかりの子供がみんないなくなったんだよ。
後に変な匂いを残してさ、ああ、気持が悪い、嫌だいやだ、怖い怖い》
《変な匂いって?》
《もう良いから、あっちへ行ってよ。わたしたちは隠れていたいんだから》
《いったいどうしたっていうんだよ。
ウレイとオトナシイは、なにをあんなに怖がっているんだろう。
やけにカラスが集まっているな。
なにをあんなに騒いでいるんだろう》
「カァー、カァー、カァー、カァー」
「ピーポー、ピーポー、ピーホー、ピーポー」
《こんどはニンゲンがいっぱい集まって何かをしているぞ》
「ねえ、聞いた。猫の子が、脚をきられた猫の子が、血だらけで、袋に入れられて、ゴミ箱から発見されたんだって。怖いわねえ」
「まあ、可愛そうに、いったい誰がそんなことを。それで、死んじゃったの」
「いや、まだ生きていたみたいなの」
「ああ、それでさっき、急いで病院に連れて行ったのね。何かと思ったわ」
「みなさんのなかに、みなさんのなかに、子猫が捨てられたところを見た人はいませんか。いませんか。ご協力お願いします」
「わたしたちは今来たばかりだからねえ」
「ねえ、マスコミが来てるわよ。早いわねえ。どこのテレビ局かしら。何か聞かれるかもしれないねえ」
《食い物はないけど、このハヤシのなかを歩いていこう。
なんか落ちてないかなあ。
なんか食いてえなあ》
「バサ、バサ、バサ、バサ」
《このう、なにをしやがるんだ。
危ないじゃないか。
カラスの野郎》
《めざわりなんだよ、ネコめ。
あんまりこの辺うろつくんじゃないよ》
《かってだろう。
おい、降りて来い、やるならやろうじゃないか》
《まあ、そういきがるなって。
とにかく早く離れたほうが身のためだぞ》
《ふん、えらそうに何様だと思ってんだ。
あっ、そうか、てぇことはだ、この辺に食い物を隠してあるってことか。
当たりだろう。
見そこなうな。
オレたちは、お前らみたいに横取りまでして食おうとは思っていないよ。
お前らは本当に卑しいからな。
お前ら、人間に嫌われているの知っているか。
ごみを食い散らかしてさ。
お前らのためにこっちは本当に迷惑してるんだ》
《なにを言うか、お前らネコもおんなじじゃないか》
《お前らカラスほどひどくはないさ。
なにせお前らはやりたい放題だからな。
ニンゲンが言ってたぞ。
カラスが一番悪いって。
早くどうにかしなければって。
判るか、それがどういう意味か》
《なまいき言うな。
人間に食い物をもらうような、お前らだめネコに、そんなこといえるのか。
だめネコめ》
《なんだと、やろうてんのか》
《ほお、どうしようてんだ。
お前、飛べるのか、さあ、飛んでみい。
ネコも人間も同じようなもんだよ。
地面をはいつくばってさ、いったい何をやろうといてるんだか》
《はいつくばってんじゃないよ。
歩いてんだよ。
走ってんだよ。
満足に歩けもしないくせに。
お前ら の不格好な歩き方といったら、笑いもんだな。
おい、降りてきて歩いてみい》
《おっと、その手に乗るか。
降りたとたんに飛び掛ってくるんだろう。
こっちもそう簡単にはやられはしないけどな。
断っておくが、オレたちには仲間がいっぱい居るからその気になれば、お前ら猫はひとたまりもないぞ。
お前らは本当に油断のならない怪しいやつらだからなだな。
お前らが、オレたちの子供を狙ったことは決して忘れないぞ》
《お前らこそ怪しいもんだよ。
ウレイの子供が居なくなったのはお前らがやったんだろう。
卑しいカラスめ》
《やってないよ。
でも仮にそうだったとしても、オレたちは何にも悪くはない。
悪いのはすぐ見つかるようなところに子供を生んでお前らの仲間が悪いんだ。
だめネコめ》
《この悪党め、お前らは人間にやられちまえば良いんだ》
《ニンゲン、ニンゲンって、お前らはそんなにニンゲンが好きなのか。
お前らは本当にバカネコだな。
お前らは何にもしらねえんだな》
《また、えらそうに。
じゃあ、お前らはいったい何を知ってんだよ。
言ってみろ》
《ふん、お前らばかネコに言ったってしょうがないよ。
でもおれたちカラスは、お前らのように人間は信じない。
判るか。
もう良い、あっちへ行け。
この辺うろうろされると本当に困るんだよ、ばかネコよ》
《うるせえ、言われなくても行くよ。
誰がこんな所を、良いか、今度脅かしたらただじゃおかねえからな。
ふん、臆病者のカラスめ、たいしたことないな》
「キーン、コーン、カーン、キーン、コーン、カーン」
《ああ、暗くなってきた。
今日はもうだめかな、なにか食いたいなあ。
良い匂いだ。
なんて良い匂いなんだ。
たまらない、でも、あの人間たちは、いくら待っても何にもくれないからなあ》
「いらっしゃいませ、焼きそばはいかがですか。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。どうもありがとうございました」
《そうだ、あそこに行こう、あそこに行けばきっと、、、、
ハシを渡ってと。
走って渡ろう。
おっと、これは食い物じゃないや。
走れ、走れ。
さあ、ドーロだ。
クルマは、クルマはと。
よしいまだ、走って渡ろう。
ふう、路地だ。
人間はと。
居ないな。
確かここだったな、安心して歩いていたらいきなり蹴飛ばされたのは。
だいじょうぶだと思っていたのにな。
確か光る靴のカイシャインだったな。
あの時は痛かったなあ。
今でもときどき痛むんだ。
気をつけないとな。
あっ、ニンゲンが来る。
だいじょうぶかな、なんとなく嫌な感じだ。
あっ、そうだ、ヘイをいこう。
よいしょっと、ヘイを歩いて、ヘイを歩いてっと。
なんだよ、見るなよ。
だいじょうぶみたいだな。
あっ、そうだ、ちょっと近道だから、ヤネを歩いていこう。
よいしょっと。
ヤネを歩いて、ヤネを歩いてっと。
よいしょっと。
また、ヘイを歩いてっと。
くらくなってきたな、気をつけないとな、、、、》
「カチン、カチン、コロ、コロ、コロ」
「おっ、惜しい、今度はどうだ」
「カチン、カチン、コロ、コロ、コロ」
「あっ、惜しいなあ、もうちょっとだったのに、なかなか当たらないなあ。ほおら」
「カチン、カチン、コロ、コロ、コロ」
「ああ、まただめだ、ちくしょう」
《なにやってんだ?
ゴウゴウとするドーロに居るチュウガクセイたちは。
下に石を投げているんだな。
なにが居るのかな。
あっ、ネコだ。小さいネコだ。
それにしてもチビだな。
どうして逃げないんだろう?
周りは、ヘイと、トビラと、イシガキか。
あのチビにはちょっと高いかな。
どうしてあの大きなイシに隠れないんだろう?
さあ、早くこのヘイを渡ろう。
見つかったら、今度はこっちがやられるぞ。
どれ、いない、チュウガクセイがいない、もうだいじょうぶだ。
あのチビあそこで何やってるんだろう?
まあ、降りてみるか。
よいしょっと。
ほんとうにチビだな。
何もたもたしてんだろう?
ふう、どうだ。
なんだ、こいつ、オレを無視してやがる。
小さいくせに。
おい、チビ、ここで何やってんだ?》
《なにって、なにって、なあに?》
《こいつ、どこ見てんだ。オレはタイガーって言うんだけど、お前ここで何やってんだ?》
《わからない、わからない、タイガーは?》
《なんだ、こいつ変なやつだな。
他に仲間はいないのか?》
《いたんだけど、いなくなっちゃった。
どこへ行ったのか、わからない》
《なあ、チビ、お前ちょっとぐらい挨拶したらどうだ》
《アイサツってなあに?》
《アイサツっていうのはだな、こうやって、うっ、なっ、なんだお前、お前はオレが見えないのか。
そうか、そうだったのか。
眼が見えないんじゃな、それじゃここから出られるわけないよな。
おい、いつからここにいるんだ?》
《わからない、なんにもわからない》
《お前ずいぶんやせているな、なんにも食ってないんじゃないの?》
《ちゃんと食ってるさ、変な事言うなよ》
《そうかい、そうかい、わかったよ。
お前チビの癖になかなかだな。
それじゃ、またな。
よいしょっと、あいつもう少し大きければここに上がれて外に出られるのな。
あっ、路地だ。
良い匂い、良い匂い。
ニンゲンがいっぱいいる。
ここはだいじょうぶだな。
降りて下を歩こう。
よいしょっと。
あかるいな、あかるいな。
オバサン、オジサン、小さいスカート、大きなスカート。
おっ、ジテンシャ、危ないな、なんだこのオヤジは。
ここだ、ここだ。
おや、どうしたんだろう、どうしたんだろう。
くらいなあ、くらいなあ。
いないのかなあ、いないのかなあ、、、、、》
「あら、久しぶり。やっぱりトラちゃんだったのね。あまりにも寂しい声で鳴いているので、てっきり誰かと思ったわ。そうなの、昨日引っ越したばかりなの。あと一日早かったら会えたのにね。いっしょに連れてってもらえばよかったのに。ねえ、元気だった。あら、やせた見たいね。お腹すいているのかしら。ちょっと待ってね。さあ、こっちにはいってきて食べなさい。まあ、やっぱりお腹がすいていたのね」
「こんにちは、、、、あら、どこのネコ」
「はい、いらっしゃい。お隣さんが、、、、この辺にすんでいる野良みたいなんだけど、お隣の娘さんがほんとうに可愛がっていて、よくあまり物をもらって食べていたわよね。でも、昨日引っ越したでしょう、知らなかったわよね、ねぇ、トラちゃん」
「あっ、そうなの。商売のほうはうまく行ってたのかしら? お隣さん」
「いってたんじゃない、少なくともウチよりはね」
「今日はこれとこれちょうだい。それでどこへいったの?」
「なんか故里のほうで良い仕事が見つかったって言ってたわ。もう一度家族四人で力をあわせて頑張るんだって、張り切っていたわ」
「あれ見た、あれここの公園でしょう。ネコが脚を切られて捨てられていたっていうのは。ひどいわねえ」
「そうなの、怖いわねえ。いまもやっていたわよ。かわいそうに。どんな人がやったのかしら。トラちゃんも気をつけてよ。またニュースでやっているわ。ねえ、トラちゃん、テレビ見て、あのネコ知らない。まあ、かわいそうに」
《あっ、カワイイだ。
ニンゲンに一番可愛がられていたカワイイがどうして》
「でも、良かったわよ。 いま、殺到しているんだって、飼い主になりたいって言う人が」
「そうみたいね。ほんとうによかったわね。ありがとうございました。さあ、どんどん食べなさい、遠慮しなくていいのよ。これからもお腹がすいたときにはいつでも来るのよ。いらっしゃいませ」
《ああ、くった、くった、どこか静かなところで休もう。
いつものここが良い、たしかにこのドアなんだよなあ。
あかないかなあ、どうしてあかないんだろう。
ああ、眠い、眠い。
白いアシ、やわらかいテ、暖かいヒザ、ああ、眠い、、、》
「ギギィーギィー、ゴト、ゴト」
《あっ、なんだ、違うのか。
いないんだ、やっぱりいないんだ。
クニ、カゾク、ガンバル。
ああ、気持が悪い。
食いすぎたな。
草でもくわないとな。
そうだ、コウエンに戻ろう。
ああ、気持が悪い。 人間のいないところを行こう。
暗いなあ。
暗いなあ。
静かだなあ、静かだなあ。
よいしょっと、ああ、邪魔だなあ、なんだこの箱は。
よいしょっと。あれ、なんだあいつは、ブチデブではないか。
隠れるようにしてじっとしている。
よいしょっと》
「トン、トン、ドサ」
《わあ、なんだ、びっくりしたなもう。
なんだタイガーじゃないか、びっくりさせるなよ》
《なあに、いつものことじゃないか、どうしたってんだよ》
《いや、まあな》
《こんな薄暗いとこで何やってんだ?
なんか良い食い物でもあるのか、それとも毛のふさふさしたメスネコでも待っているのか?》
《違うよ、なんでもないよ。
お前こそ何やってんだ?》
《これからコウエンに戻るところだ。
どうだい、お前んとこの仲間は、どうしてる?》
《うん、まあまあだ。
タイガー、お前まだ何にも知らないのか?!》
《なんのことだ》
《すごい、すごいやつがうろうろしているんだ。
なんかケンキュウジョの裏のゴミ箱のような匂いのするやつだそうだ。
犬のように大きくて、ものすごく強くて、ネコの子まで食っちまうんだそうだ》
《お前、そいつを見たのか?》
《いや、まだ見てない。
もう怖くい怖くて。
みんなもうどっかに行ってしまっていないんだ。
お前んとこには、まだ来てないのか》
《どうなんだろう、わからない。
あっ、コウエンにどうだ、お前も一緒に来るか? ブチデブ》
《オレは、、、、オレはこっちに行く。
しばらくどこかに行こうと思っているんだ。
タイガー、お前たちも気をつけろよ》
《うん、わかった。
そんなにすごい奴がいるのか。
ああ、気持が悪い、早く草を食べないとな》
「ガサ、ゴソ、ガサ、ゴソ」
《わあ、びっくりしたなもう。
なんだイヌじゃないか。
いきなり出て来て脅かすなよ。
くるなよ、それ以上こっちに来るなよ》
《そう怒こるなって。
お前たちネコはすぐそうして怒こる。
お前たちネコはほんとうにいいよなあ。
たとえ周りにニンゲンがいても、怒りたいときには怒り、鳴きたいときには鳴き、喧嘩をしたいときには喧嘩をして、まったくやりたいほうだいだもんな。
オレたちにはそんなニンゲンに迷惑をかけるよすなことは恐れ多くてとてもできやしないよ。
それだけじゃない、お前たちは気分に任せてニンゲンをにらみつけたり、ときにはひっかいたりするんだからな。
もしオレたちがそんなことをしてみろ、たちまちホケンジョだぞ》
《なんだよ、そのホケンジョっていうのは?》
《うん、いや、オレにもよくわからないんだ。
でも、とっても怖いとこみたいだ。
よくニンゲンが、オレたちを見ながらホケンジョ、ホケンジョって言うんだが、そのときのニンゲンって、とても冷たくて怖くって、体ががくがく震えるくらいなんだ。
お前たちはそんなことはないだろう。
だからだオレたちは普段からニンゲンの気に障ることがないようにって、すごく注意して動きまわっているんだ。
たとえば、オレたちイヌは、決してニンゲンに噛み付いたり、たてついたりしません、ほんとうはおとなしくて可愛いんです、というような顔をしてさ、ちょっと怖そうなニンゲンとすれ違うときなんか、けっこう気を使うんだぞ。
何もないのに地面などかぐまねなどしてさ。
なるべく目立たないように目立たないようにしてるんだぞ。
そうでなくてもオレたちは体が大きくて目に付くんだからな。
それに比べてお前たちは、ニンゲンがいようがいまいが、平気でヤネにあがったりヘイを歩いたり、ニワに入ったり、小さくてすばしっこいことを良い事に、高いところでも狭いところでも自由自在に動きまわって、逃げたり隠れたりほんとうにうらやましいよ》
《そうかい、お前たちはそんなにおとなしいのか。
ウサギがいっぱい死んだのは、お前たちがやったんではないのか?!》
《なっ、なんてこと言うんだ、オレたちがそんなことやるわけないだろう》
《いくらウサギがショウガクセイに可愛がられているからってさ、なにも、、、
とにかくオレたちじゃないよ。
あれはニンゲンに飼われているイヌがそそのかされてやったんだよ。
だいいち、オレたちがカギを開けられるわけないだろう。
何を言ってるんだよ》
《そうか、わかったよ、わかったよ。
そうむきになるな。
そうか、お前たちイヌは、オレたち猫より体が大きいから良い事ばかりあるんじゃなかったのか。
そうか、それほど自由じゃなかったのか。
そうだろうな、そんなものつけられているからな》
《あっ、これか、これはクビワっていうんだ。
でも、これも役に立つときが在るんだよ。
これをつけているとなぜかニンゲンは、これがないイヌよりやさしくしてくれるんだよ。
飼われていたときのようにね》
《そうか、お前はニンゲンに飼われていたのか。
今度カワイイもニンゲンに飼われるみたいだな、、、、
なあ、イヌよ。
飼われるってそんなに良いのか》
《うっ、いや、わからない、もう忘れたよ》
《それでなんで捨てられたんだ》
《いや、オレは捨てられたんじゃないよ!》
《飼われたり、捨てられたり。
食い物をくれるのはニンゲン、ネコのアシを切るのもニンゲン、ニンゲンって一体なんなんだ。
良い奴なのか悪い奴なのか。
なあ、イヌよ、お前ニンゲンのことどう思う、好きか嫌いか?》
《いや、ちょっと待って、オレはニンゲンのこと考えたことないんだ》
《そうか、じゃあなあ。
ああ、もう気持は悪くないや。
草は食わんでもいいか。
いつものようにあのモノオキでひと休みでもしようっと、、、、》
「タツ、タッ、タッ、タッ、バタ、バタ、バタ、バタ、バタ」
「おい、林に入るぞ。リョウ早くしろ。木か茂みに隠れるぞ。おい、トシ、待て、小屋がある。あそこに隠れよう。ようし、誰にも見られなかったぞ。確かこの辺だよな、テレビに映っていたのは」
「そうだそうだ。あのゴミ箱だ。あのゴミ箱に足を切られたネコが捨てられていたんだ。ケイ、もしかしたらこの辺に血だらけの足が落ちているかもしれないぞ」
「おっ、なんだこの動いてる奴は」
「わあ、おどかすなよ、ケイ」
「それにしてもすげえことやるなあ、誰だよいったい。なんで切ったんだろう。ナイフかな、ハサミかな」
「良いもの持ってきたぞ。缶ビールだ」
「プシュウ」
「あっ、うっ、うっ、おい、リョウ、お前も飲め」
「うつ、うっねああ、にげえなあ」
「なんだ、お前は初めてなのか」
「リョウ、オレにも飲ませろ。あっ、あっ、ふう、喉が乾いていたからうめえやあ」
「お前ら、ナイフ持ってきたろうな。なにが起こるかわかんねえからな。そのときには、やられる前にやっちまうんだ」
「あっ、なんか顔がボォッとしてきた。体も熱くなってきたぞ」
「オレもだ。なんか気持ちよくなってきたぞ」
「あした、テストがあるんだって」
「いやな事言うなよ。どうせ勉強したってかわんねえんだから」
「うだそうだ。担任なんか、オレができないのは当たり前だと思ってんだから。お前なんか勉強できなくたって良いんだって云うような顔してさ。そうだよ、出来ないよ、オレたちは出来ないさ。良いこでもないよ、優等生でもないよ。いまさら良いこでなくたって良いよ。優等生じゃなくたって良いよ。その通りだよ。出来ない子だよ。駄目な子だよ。なんか文句があっかよ。それならいっそうのことほんとうに悪い子になってやろうじゃないか。悪いことやってやろうじゃないか。なあ、みんなもそう思うだろう。さあ、オレたちは今日から悪いやつだ。悪いことやってやろうじゃないか」
「おい、誰か来るぞ。静かにしろ。おまわりだ」
「二人で警戒してんだな、あんな事件が在ったからな」
「見ろよ、ピストルもってるぜ。本物のピストルだぜ。触ってみたいな」
「取っちゃおうか、襲ってさ。こっちは三人だぜ。ナイフも在るしさ」
「ナイフがあったってだめだよ。奴らは柔道やってるから強いぜ」
「後ろからいきなり棒かなんかで殴ったら」
「棒か、、、、ここはなんだ、物置か、、、、」
「わあ、びっくりした」
「なにやってんだよ、大きな声出して、聞こえたらどうするんだよ」
「何かないかなと思って探していたら、ネコがいた。びっくりさせやがって。良い物があった、棒だ、二本ある。ほら、これで後ろから、、、、」
「おい、危ないよ。こんなところで降りまわすなよ」
「おっ、やるか、こい。やあ、なんか、ぱあっと、暴れたい気分だな」
「静かにしろ。なんだあれは。ほら、池のほう、気持悪いなあ」
「なんだ、行きそうなババアじゃないか。脅かすなよ」
「なんで、あんな所よろよろと歩いてんだよ。池に落ちて死んじまうぞ」
「おい、こっちこっち、男と女が来るぞ」
「オヤジがずいぶん若い女をつれてるな。林に入ってきたぞ。なにをやろうてんだ。襲っちゃおうか」
「やっちゃおか。よし、オレとリョウは後ろから棒でオヤジを襲うから、トシは女をナイフで脅かせ、騒がれないようにな。よし、行くぞ」
「クソオヤジ待ってろ」
「ザブン、、、、」
「な、なんだ、いまの音は」
「ババァか、ババァが落ちたのか」
「いないぞ、やっぱり落ちたんだ」
「行ってみるか、、、、くそう、ババァなんか死ねば良いんだ」
「くそったれ」
「あっ、やっぱり落ちてる。おい、トシ、お前、飛び込め、元水泳部」
「ザブン、、、、」
「つかまえて、手を伸ばして、リョウ、お前も引っ張れよ。よし、上げろ。ヨイショ、ヨイショ。ああ、重いな、ヨイショ、ヨイショ。ああ、やっとあがった。ふう」
「おい、そこで何やってんだ?」
「あっ、おまわりさん、池に落ちたおばあさんを助けたんです」
「ええ、そうか、それで、だいじょうぶか? おばあさんは」
「たぶん、だいじょうぶだと思います」
「よくやった。よくやった。まずは救急車だ。それから本署へ連絡だ」
「ところで、みんなは中学生?」
「はい、そうです」
「こんなところで何をやってたんだ?」
「はい、偶然通りかかったんです。そしたら、ザブンと音がして、走ってきてみたら、おばあさんが池に落ちていたんです」
「とりあえず、住所と名前を教えてくれないか?」
「風邪を引くとたいへんだし、すぐ着替えたほうが良いね、アルコールの匂いがするから、酔っ払ってたんだな、、、、」
「ピーポー、ピーポー、ピーポー」
《ほんとうにニンゲンってうるさいな。
ゆっくり休ませてくれよ。
もうだいじょうぶだろうな。
ああ、また眠くなってきた。
ここ、ベンチの下で眠ろう、、、、》
・・・・・・・・