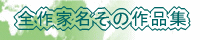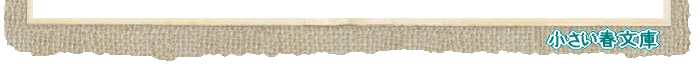小礼手与志
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
わたしはずっと夢見ていた。
いつかきっと、ふるさとの田園風景を見渡せる高台に上り、
空には、乳白色の雲がぽっかりと浮かび、
遠くの、紅葉に彩られた山並みはかすみ、
その山のふもとからは、稲の刈り取られた田んぼが広がり、
そして、そのところどころには、籾殻を焼く煙が立ち昇り、
ときおり、草の陰のように農婦が動いている、
そんな風景を、
いまだに何者でもないわたしが、
あの人に認められて、
ぼんやりと、しかし、満たされた気持ちで眺めているのを、
だが、わたしはいっこうに、この繁栄の町から逃れられずにいた。
わたしは日々憂いを深め、
ふくらみすぎた風船のように空しさを抱えながら、
はぐれた幼な子のように寄る辺なかった。
そして、この目の前から何もかも遠ざかってしまうような不安におびえながら、
いくたびも、人知れずうずくまり頭を抱えていた。
はたして、そのときわたしは、
広場を吹き抜ける風ほど伸びやかだっただろうか、
刈り払われた夏草ほどみずみずしかったのだろうか、
それとも、道端に立ち昇る陽炎ほど確かだったのだろうか。
わたしはかつて、
会社に行くためにバスから降りたとき、
若葉をいっせいに揺らす風が吹いていた、
あまりにもそれが爽やかだったので、わたしはずっと吹かれていたかった。
でも、わたしは仕事に行かなければならなかったので、
「そのうちにまた吹くことがあるだろう。」と考え、
わたしは会社に急いだ。
だが、そのときの風は、もう二度と吹くことはなかった。
あのとき、わたしは、初めて訪れた町で、両側を平屋住宅に挟まれた狭い坂道を下っていた。
そして、突然のように目の前に広がった海に、わたしは心を奪われた。
そこから、それまで味わったことのないような自由や生命力を感じ取ったからだった。
わたしはそのままずっと見ていたかった。
しかし、次の日は受験だった。
そこで、わたしは、
「いつかまた見る機会があるだろう。」と考え、その場を離れた。
だが、あのときの感動は、もう二度と味わうことはできなかった。
そのとき、ゆっくりと走る電車の窓から外の景色を眺めていたわたしは、
ビルの隙間からのぞいた桜の花に目を奪われた。
わたしは途中下車して、そこに向かった。
「どんなに美しい光景が、そこで待ち受けているのか。」と期待に胸を躍らせながら。
だが、そこには、酔っ払ってけんかをし、大声でわめき散らす者がいるだけだった。
二十世紀の半ば、永遠の平和が日本に訪れた。
傲慢な野心と尊大な支配欲に突き動かされ、
幾多の破壊と殺戮を繰り返してきた、
暗く絶望的な諸民族の熱狂が、
悪魔も尻込みするような、さらなる破壊と殺戮によって鎮められ、
その熱狂に遅れて参加したわたしたちの父たちに、
その破壊と殺戮のすべての罪を背負わせながら、、、、
そして、わたしたちは、
春先のみぞれ混じりの嵐が過ぎ去った後に、晴天が現れ、
その暖かい日差しを受けて、若草がいっせいに萌えいずるように、
地から湧き出るように生まれてきた。
やがてわたしたちは、毎日のように、
西の空が赤く染まるまで、朗らかに歌を歌いながら、
軽やかに飛び跳ねるようになっていた。
その永遠に続くかのような平和のもと、
人間の欲望と意欲は熱烈に歓迎されるものとなり、
民族の繁栄は必然となった。
社会はより効率的となりますます便利になっていった。
店先には商品があふれ、
生活は加速度的に良くなっていった。
都市には昼でも夜でも人々が集まり、賑やかさにあふれ、
わたしたちを退屈させないように、
五感を刺激する快楽を次々と作り出して行っては、
昨日の風景が思い出せないくらいに、めまぐるしくその姿を変えて行った。
そして、どの華やかな通りにも、
手を伸ばせば今にも届きそうな感じで、
そのしなやかな肉体をくねらせるように、踵の高い靴の音を響かせながら、
さっそうと歩いている美しい女性があふれていった。
そして人間の自由と平等を愛し、
集団よりも個人を大切にする新しい思想に満ち溢れていた。
その新しい思想は個人の確立を重要視していたので、
他人を思いやりながらも、他人と競いながら、自分を高めアピールし、
精力的に働くものなら、誰でもより幸せになり、
より豊かになれることを約束していた。
さらなる繁栄は、わたしたちに空前の豊かさをもたらした。
その豊かさは人々を穏やかにし、余裕を持たせ、さらなる夢と欲望を育んだ。
そして人々の夢は際限なく拡大していき、
はるか上空を越えてロケットに乗って星々の間にまで散りばめられた。
希望は高速道路を走る車によって全国至る所にばら撒かれた。
そしてわたしたちの社会はますますわたしたちの意見によって作られるようになり、
差別も不正も貧困も病気もだんだん少なくなっていき、
より住み良く長生きができるようになっていった。
さらに社会は豊かになっていき、福祉政策が充実するようになり、
それまでわたしたちを苦しめ悩ませていた孤独から来る寂しさや、
容赦なく襲う突然の悲しみから開放されるようになっていった。
そこでは、誰もがみんな幸せになれると思っていた。というのも、
わたしたちが戦争を絶対悪とみなして、平和を願い、
平和を望むことによって、平和が続くものと思っていたからだった。
そして、そのようなわたしたちの考えこそ、世界の先頭に立つ思想になると思っていた。
さらに、わたしたちの繁栄は、わたしたちが世界に稀に見る勤勉な国民であることからして。
そしてわたしは、
時代の要請を受け入れるかのように、そのような思想にどっぷりと漬かり、
自己を確立するべく、まずは自分についてよく知り、そして他人についてもっとに知り、
さらに社会について、悪戦苦闘しながらも深く学んでいき、
常識を持った普通の大人として振舞えるようになっていった。
それなのに、、、、
わたしは十九歳のとき、
日差しの穏やかな秋の日に、
深く長い思索の結果として、しかも突然のように一つの洞察を獲得した。
生と死には絶対的な違いがあるという洞察を。
死んだら何も残らない、今こうして生きていることがすべてであるということを。
この世に存在していることが、喜びであり楽しいことであるという根本的な洞察に基づいて。
わたしは繁栄を受け入れた。新しい思想とともに。
そして、より豊かな生活を求める人々と同じように働き幸せになることを願った。
だが、わたしはいつまでたっても不安を覚え、満ち足りた気持ちになることはなかった。
わたしは時間とともに、その豊かさや楽しさの背後にひそむ虚無感を感じるようになっていた。
それまでわたしはずっと、わたしが立っている場所は、
豊かさと喜びと希望と生命力に満ち、正義と公正と平等にあふれた、
輝かしい通りに面したところだと思っていた。
だが、よく見るとそこはもう一つの通りが横切る交差点だった。
そこにはこの世のあらゆる死とあらゆる悪とあらゆる悲しみが溢れ、
暗く寂しく、人間を蝕む忌まわしいすべての感情がうようよしていた。
そして、その通りの様子が気になるあまり、わたしは知らず知らずのうちに、
他の人たちと同じような足取りで前に進むことはできなくなっていた。
わたしは悩みを深め、迷うばかりだった。
それでもわたしの周りには、いつも知恵に溢れた伝統的な古い思想があった。
その古い思想は新しい思想のように人々には人気がなかった。
それは、人間は、個人の努力や意志力によって成長することができ、
物事にあまりこだわらない豊かな気持ちになって、不安や悩み事から解放されて、
子供のような素直な心で自信を持って生きられるようになり、
最後は安らかに死ぬことができるというものだった。
だから、その新しい思想と古い思想から学んだものは、
平和と平等を愛し、悪と不正を憎み、知識と教養を身につけ、
時計のように規律を重んじ、いつも明るく笑顔で振る舞い、
他人を思いやり、他人と語り合いながら自己を高め、ゆるぎない自己を確立して、
他人の模範となって、エンジンのように休むことなく働くものは、だれでもが、
より豊かにより幸せになれることが約束されていたはずだった。
だが、それでもわたしは幸せからはほど遠く、少しも安らぐことはできなかった。
わたしはいつも自分のこと以上に他人のことが気になっていた。
人々は自分でもその原因がよく判らずに悪を行い罪を犯していた。
むしろそれは善と正義を目指したために起こることでもあった。
また人々は突然の名状しがたい死におびえていた。
そして耐え切れない空しさに襲われて自ら死を選ぶものもいた。
さらに、あらゆる自由が保障されているにもかかわらず、その自由を忌み嫌い、
自由に生きることができない人々がいた。
わたしの横を通り過ぎる人々は、
道路を猛スピードで走る車や、規則どおり動くコンベアのように、
プラスチックのような表情と乾いた会話を残して行った。
どんなに言葉巧みに世界の飢餓や戦争を冷静に、そして論理的に語っても、
それが世界から消えてなくなることは決してなかった。
わたしはますます困惑を深めていくばかりだった。
みんなと同じように冷静に論理的に語っても良かったのだったが、
どうしてもそうすることはできなかった。
その古い思想は実際なんの役にも立たなかった。
星々の間にちりばめられた夢は、膨大な空虚をはらんでいた。
全国にばら撒かれた希望は、わたしたちの犠牲の上に成り立つ、
幻のように、見せ掛けのようにわたしたちの目の前を通り過ぎていく欲望に過ぎなかった。
それらは大きければ大きいほど、より大きな空しさを孕んでいるものでもあった。
それだけではなかった。
わたしは人間として少しも成長していなかった。
突然いらだつ、怒りを覚えて、意味もなく怒鳴り散らしたりて、
なんども他人といさかいを起こしていた。
そして、そのたびに、耐え難い孤独と激しい後悔の念に襲われ、
自分はこのままでは壊れてしまうのではないかと言う不安にさいなまれていた。
こんなことがあった。
新しい思想は、人間は生まれながらにして平等であるということから、
人間を差別しないことがもっとも好ましいとされていた。
だから、わたしは何者であるか、その印をつけることを積極的に嫌い、
上の者も下の者も、できるだけ平等に扱うことを心がけた。
だが、それは、結果的には、内部だけではなく、外部にも混乱をもたらすだけだった。
またあるとき、わたしは、人に何か物を教えるとき、
身分的で暴力的で何も言わない方法よりも、
筋道立てて言葉で教えるほうが人間的民主的と考えていたので、
そういう環境を好むものがより多く集まってくるに違いないと思い、それを実行に移した。
だがそれはわたしの浅知恵から来るまったくの間違いだった。
人間が集まって来て賑わいを見せるどころか、
周囲に不機嫌そうな沈黙を撒き散らすだけで、何の効果も挙げるものではなかった。
またあるとき、わたしは、ほかのグループに有利な立場を譲った。
それは自分の心の広さと謙虚さを示したものでもあった。
だがそれは、わたしのとんでもない勘違いだった。
なぜならそれは、個人同士には当てはまる美徳だったかもしれないが、
集団同士にはまったく当てはまらないものだったからだ。
結局、そのことは、グループ内部に激しい不満を巻き起こしただけでなく、
取り返しのつかない不利益をもたらしただけだった。
わたしはさらに悩みを深め、不安になり、空しく迷うばかりであった。
もしかしたら、わたしは古い思想にこだわりすぎていたのかもしれなかった。
そしてそれが心をいつになっても満たされないものにしているのかもしれなかった。
というのも、わたしがその古い教えに従い、
物事にあまりこだわらないようにし、いつも頭の中を空っぽにしているせいか、知らず知らずのうちに、その空 っぽの頭の中に進入してきたいろいろな物が、我が物顔に振舞う傾向があるみたいだったからだ。
わたしは毎日のように押し寄せる孤独や苦痛を、何とか受け入れ、
絶望や不安にさいなまれようが、どうにか耐えることはできる。
でも、夜寝ている間にわたしの頭の中に忍び込んで来る物はどうすることもできない。
そのためわたしはいつも激しい苦痛を感じながら目覚めなければならないのだ。
そしてわたしは必死の思いで、わたしの頭の中から、
その毒草を一本一本引っこ抜き、悪霊と狂気を追い払わなければ、
わたしは正気に戻ることはできないのだ。
わたしは他の人とどこか違っているのだろうか。
外見はほとんど変わっていない。行動も特別ではない。
群集に紛れれば、わたしはすぐに他の誰かと区別がつかなくなってしまう。
というのも、わたしは目立つことがあまり好きではないからだ。
そしてみんなと同じように平和と平等を受け入れ、
勤勉に働き、みんなと同じように豊かさを求めていた。
それなのにわたしには、みんなの方がわたしよりも、
比べ物にならないくらいに満ち足りているように見えた。
いや、それともみんなはわたしと同じ気持ちだったのだろうか。
そして、みんなはあえて幸せそうに振舞っていたのだろうか。
わたしはいつも、気がつくとみんながわたしから遠ざかっていくような感じがしていた。
それは、わたしはみんなと同じように
世の中の出来事を熱狂的に受け入れなかったことからも知ることができる。
なぜなら、みんなが両手を振りかざして、満面の笑みを浮かべて、
そのものにいっせいに走り寄って行くとき、立ち止まっているわたしは、
みんなから見ればきっと後退しているように見えるだろう。
いや、人によっては積極的に反対しているように見えるはずだ。
たしかにわたしはみんなと少し違うところがあった。たとえば、
わたしは欲しい物を求めるとき、決して行列には並ばなかった。
電車に乗るとき、毎日決して同じ場所からは乗らなかった。
政治について意見を求められても、決して一票以上のことは話さなかった。
みんなのように歌は歌わないし、ダンスもうまくお踊れない。
新聞も週刊誌もあまり買って読まない。
そして、みんなよりも少しは寂しいことや悲しいことに耐えることはできる。
でも、そんなことが、わたしの不安や焦燥や苦痛の原因になるとは思えないのだが。
その他にも、たしかに違うところがあった。
みんなといっしょに酒を飲んで不満や愚痴を言うのは好きじゃなかった。
群れて騒ぐ祭りはあまり好きじゃなかった。
その日に起こった問題をその日のうちに解決しないで眠ることはできなかった。
買ったものを大事にすることができなかったので、できるだけ物を所有しないことにした。
わたしは、みんなと同じことをやらなくても、
生きていける人々の仲間に入ればよかったのかもしれなかった。
でも、わたしは涼しい顔をして悲しみや苦しみを言うことができなかった。
わたしは、孤独や不安はそれほど苦ではないので、
人間との接触を避け、常に心を平安に保つことができる、
職業や場所を択んで生活すればよかったのかもしれなかった。
でも、わたしは、自分にとって心の平安がどれほどの意味があるのか判らなかった。
つまり、自分だけの心の平安が、、、、
そして、突然のように、苦しみの底が割れ、
いまだ経験したことがないような苦痛がわたしたちを襲う。
わたしはうろたえながら思った、
わたしたちは苦しみから解放されたはずではなかったのかと。
さらに、突然のように、空しさの底が割れ、
いまだ経験したことがないような空虚感がわたしたちを襲う。
わたしは途惑いながら思った、
あんなにたくさんの消費物質に囲まれて、
わたしたちは豊かで満ち足りていたはずではなかったのかと。
さらにまた、突然のように悪の底が割れ、
かつては考えられなかったような犯罪が繰り返されるようになった。
わたしはその不可解さに頭を抱えながら思った。
豊かで平和で心穏やかな人たちに囲まれて、
わたしたちは誰もが幸せになっていたはずではなかったのかと。
そして、子供たちは、教育と躾の名の下に、
かつて経験したことがないくらいに痛めつけられ、
その自由で伸びやかな感性が奪われ喘ぎ苦しんでいる。
当時、わたしの心を最も引き付けていたある噂があった。
それは有史以来決して人前に姿を現したことがない者が死んだという噂だった。
そこでわたしは、ほうぼうを駆けまわり、必死にその死体を探したが、
ついにどこにもそれを見つけることはできなかった。
いや、それどころか、世界中のいたるところに、
その決して人前に姿を現さないものから選ばれた人たちがたくさんいた。
というと、その噂は間違いで、あの者は決して死んではいなかったということになるのか。
だが、もし生きているというなら、どうして人間はこんなにも苦しい思いをしなければならないのか。
突然のように死神が現れ、理由も告げずに情け容赦なくわたしたちから生命を奪っていく。
わたしたちは激しい苦痛に襲われ、周囲に悲しみだけを撒き散らして死んでいく。
その苦痛がどんなものか、永遠にわからない。
なぜなら死んだものは何も語らないから。わたしたちの最後が、苦痛だということに、
いったいどれほども人間が耐えられるだろうか。
でも、それはまだ良いのだ。
その決して姿を現さないものの芸術作品といわれている子供たちでさえも、
激しい苦痛の中で死んでいくというのはいったいどういうことなのだ。
なぜ、まだ生きる喜びも楽しみも知らない子供たちが、
もがき苦しみながら死んでいかなければならないのか。
なぜわたしたちは、傷つけられ、胸部に震え、泣き叫ぶ悲鳴を聞き続けなければならなかったのか。
わたしは混乱し迷いを深めていくばかりだった。
そして、憂いは深まり、はぐれた幼な子のように不安なるだけだった。
なぜ子供たちは、大空を翔け渡る鳥のように、自由に軽やかに飛びまわることはできないのか。
子供たちは鳥たちよりも優れているはずなのに。
子供のとき、わたしは親の言いつけを守る素直な子だった。
だからわたしは近所の女の子といつも仲良く遊んでいた。
だがそれを見ていた周りのものがよってたかってわたしたちを引き裂いた。
いったいあれは誰も仕業だったのか。
そして、わたしが青年になったとき、わたしはある少女と仲良くなった。
わたしたちは兄妹のように穏やかに親密に、青春の憂いや不安から開放されたかのように、
時の経つのも忘れてお互いの未来や夢について語り合った。
あるとき、、わたしたち二人の間に奇跡のような出来事が起ころうとしていた。
それはまさに時間が止まってしまったかのように思われる瞬間だった。
だが次の瞬間わたしたちは永遠に引き裂かれた。
いったいあれは誰の仕業だったのか。
わたしは事あるごとに、テレビニュースのように社会の不正を批判し、信念のように自分を主張した。
だが人々は面倒なことには関わりたくないという風な顔をして、わたしから離れていくだけだった。
わたしは他人に厳しくすることが苦手だったので、トラブルは話し合いによって解決することにして、できるだ け優しく接することにした。
だが、人々は張り合いがなさそうな顔をしてわたしから離れていくだけだった。
わたしはあるとき、常に上司に対する不安で渦巻いている人々の中にいた。
その通りだと思ったわたしはそのことを堂々と抗議した。
だが、だからと言って、周りの人々が、わたしに味方してくれるわけではなかった。
むしろ変わり者を見るような目をしてわたしから離れていくだけだった。
わたしはずっと、不公正を遠ざけ、平等に接し、
穏やかな気持ちで穏やかに振舞えば周囲を穏やかにすると信じていた。
だが人々はそうは見なかった。
ある者はそれをやり易さ、付け込み易さと受け取った。
だから、わたしは侮られないために、言葉遣いが荒々しくなり、動作も乱暴に野卑になっていった。
わたしは、新しい思想の要請にしたがって、自分というものを持とうとしていたのに、
自分というものをもたない周囲の人々と何も変わらない人間に、
知らず知らずのうちになっていることを気づかされ始めていた。
揺るぎない考えに従って行動していれば、
人間は年を経るに従って心穏やかに自信を持って生きられるという古い思想の教えに、
憤りにも似た激しい疑念を抱きながら、
わたしは途惑いますます苦悩を深くしていくだけだった。
だからわたしは、あのガラスだまのような冷たい目をした奴を思い浮かべるしかなかった。
奴の実在を疑いながらも。
そして、突然のように、夢と希望の天蓋はひび割れ、砕け飛び、
プライドと羞恥心と思いやりを巻きこみながら星と共に消え去った。
わたしは気づき始めていた。
まぶしすぎる光には、より深い暗闇が潜んでいるように、
星々の間にまでちりばめられた夢には巨大な空虚がその背後に控えており、
高速道路に乗って全国にばら撒かれた希望には、
とどまる事を知らない無際限の欲望がその裏側に控えていることに。
わたしは実際ずっと自由だった。
だから、なりたいものにならなんにでも慣れるはずだった。
しかし、わたしは、なんににもならなかった。
それは、わたしが更なる自由を求めていたからか、
それとも、わたしが自由をもてあましていたからなのか、、、、
わたしはずっと古い思想と新しい思想の教えどおりに、
自己の確立を目指しながら、自分というものを知り、
さらにそれ以上に他人というものを知り、
わたしは自分というものに幾分かの自信がもてるようになっていたはずだった。
だから、わたしは将来に対する不安から開放されるはずだった。
それなのに、、、、
かつてわたしたちはすべての人たちが平等になることを望んでいた。
そして、それもある程度達成された。ところが、いざそうなってみると、
みんなはそこに何か居心地の悪いものを感じるようになっていった。
なぜそうなるのか、、、、
水は水位差があればあるほど激しく流れ、
そこから膨大なエネルギーが生まれることは確かだった。
人間は悪いことを行うとき、誰一人としていま自分は悪いことをしていると思ってやっているものはいなかった 。
むしろ自分は積極的に良いことをやっていると思っているものさえいた。
わたしは何がよいことで、何が悪いことか判らなくなっていった。
そしてわたしはますます混乱し憔悴し迷いを深めていくばかりであった。
だが、そんなわたしに対して、誰も答えを出してくれるものはいなかった。
そこで、わたしはますます孤独を深めていくばかりだった。
だからわたしは、あのガラスだまのような冷たい目をし、
時折黄色い歯を見せて笑う奴と通じるしかなかったのだ。
というのも、わたしが疑問に思うことを質問すると、
みんなは面倒なことには巻き込まれたくないといったような顔をして、
みんなわたしを遠ざけるようになっていたからだった。
やがてわたしは確信し始めていた。
光が強ければ強いほど濃い影を作るように、
山は高けれは高いほど深い谷を作るように、
善と悪は相対的なものであり、
水を役立てるためには低い所が必要であるように、
熱を利用するためには冷たさが必要であるように、
善にはそこに寄り添うような悪が必要であることが。
だから、わたしはもう、自己の確立とか人格の完成などと、そんな質面倒くさいことは忘れて、
周囲の人たちに合わせるように、みんなと同じような行動をすればよかったのだった。
なにせ、普通に働いてさえいれば、たとえそれが、
それを手にしたときのありがたみがそんなに感じなくても、
ほしいと思うものは何でも手に入れることはできたし、
最低限の礼儀作法を心得ていれば、他人とトラブルを起こすことなく、
ときたま見知らぬ人から親切にされても、それほど感謝の気持ちを感じることなく、
みんなと同じように生活することができていたし、
飢餓に苦しむ子供たちの姿をテレビニュースで見ながら、
食べたい物をたらふく食べることができていたのだから。
でも、確かにそれはそうなのだが、、、、
いつしかわたしは、奴と出会うことをひそかに願うようになっていた。
そこでわたしは、わたしのそれまでの経験から推し量って、奴が好んで出歩きそうな、
薄暗い裏通りとか公園の片隅とかを頻繁に通るようになっていった。
そこは、社会に受け入れられなかったものたちや行き場を失った者たちが集まっていて、
不器用な悪巧みから狡猾な悪巧みまであらやる悪や犯罪がはびこり、
恐怖と暴力と退廃に支配されながら、弱い人間同士がお互いに苦しめあう場所だったからだ。
それに、それらのすべての原因が奴の所為だと思っていたからだった。
ところが、そんな場所のどこを探して歩いても、奴の姿を発見することはできなかった。
それどころか、そこには、原始の欲望を刺激する赤い花が、
全身から、そのかぐわしい香りを放ちながら、
その追い詰められた生命を必死で生きるように、
豊かでないながらも、かすかに希望の光を灯しながら笑顔を絶やさずに、
決して夢をあきらめることなく、奴が付け入る隙がないくらいに、
今日を生きる喜びに満ち、ひたむきに生きている人たちで溢れていた。
さらにわたしは、奴が最も好みそうな場所、葬儀場の周辺に、奴の姿を探し求めた。
そこはいつも厳粛な雰囲気を漂わせながら、
悲しみと絶望に打ちひしがれた人たちで溢れていた。
だが、奴の姿をついに発見することはできなかった。
それどころか、葬儀場の出入りロから喪服のミニスカートを履いた若い女性を目にしたとき、
わたしは恍惚としてめまいを覚えながら、
そのとき、宇宙が振動し、星々が衝突し、天が割れ砕けたような感じがしていた。
さらにわたしは、奴の姿を求めて悲惨極まりない災害現場をうろついた。
そこには家を失い家族を失い、絶望し悲嘆にくれている人たちで溢れていたが、
わたしはどこを探し求めても奴の姿を発見することはできなかった。
それどころか、何もかも失ったように見える瓦礫の山から、
陽炎のように立ち上る新たな創造のエネルギーを感じ取るばかりだった。
その後もわたしはことあるごとに奴の姿を探し求めたが、でこにも見つけることはできなかった。
だが、ついにある夜、わたしは奴を発見した。
そこは夜の色とりどりの照明と、華やかなネオンサインに照らしだされた人通りの激しい駅前通りだった。
それは痩せ型で長身の身なりのかなりきちんとした男だった。
男は、どこと泣く陰気な雰囲気を漂わせながら、通りの反対側にときおり鋭い視線を送っては、
老木の黒い影のように歩道の脇に立っていた。
その所為か、通り過ぎる人々は誰も彼に目をやるものは居なかった。
だが、わたしは、その男の冷たすぎる目の輝きから投げ出されるその鋭い視線や、
あまりにも無表情すぎるその表情から、彼が、
わたしが長い間探し求めていた奴だということを直感したのだった。
直視することに不安な気持ちにさせるその男の様子をじっと見ていると、
その男の視線の先には華やかに装飾されたケーキ屋があることがわかった。
わたしはとっさに絶望的な不安にとらわれた。
なぜなら、その店には一人の少女が働いていたからだ。
わたしはその少女がどんな娘であるかを知っていた。
店に入ってくるお客に応対するときのその笑顔が、
世界や他人のことをまったく疑うことを知らない純真無垢な子供のようで、
わたしはその前を通るとき、今日はどんなだろうと、
いつも中の様子を見ざるを得なかった。
そして偶然にも、その笑顔を目にすることができたときには、
心のそこから安堵感を覚えながら満ちたりた気持ちになるのだった。
そう感じるのは決してわたしだけではないはずだ。
彼女を見るものは誰でも、きっとわたしと同じように喜びと元気を与えられているはずだ。
わたしはその不気味な男を見ながら、どんどん不安な気持ちになっていくのを感じていた。
あの少女がわたしたちを魅了したように、あの男をも魅了したに違いないと思ったからだった。
その男の鋭い視線は確実に少女の姿を追いかけていた。
そして、少女が店の奥に消えると、その男はかすかに表情を緩めながらゆっくりと瞬きをして、
歩道のほうに向き直ると、何事もなかったかのように歩き出した。
わたしは、その男が、わたしが捜し求めている男であると確信すると同時に、
その男のたくらみも確信した。
わたしは波のように押し寄せる不安で怖気つきそうになったが、
勇気を振り絞りその男の後を追った。
わたしはそれまでずっとやつの存在には半信半疑だった。
歩きながらわたしは、そう言えばあの黒い影のような男を、
今までに何度か見たことがあるような気がすると思った。
でも、そのときはわたしの錯覚だと思っていた。なぜなら、
その場所はいつも喜びに満ち溢れた入学式場や結婚式場だったからだ。
こんな場所にあんな不吉な男が現れるわけはないと思っていたからだ。
わたしは常に数メートルの距離をを保ちながらその男の後を歩き続けた。
その男はしばらくの間華やかな表通りを歩いていたが
、突然のように人通りの少ない薄暗い裏通りに入った。
わたしはなおも気づかれぬように距離を保って歩いた。
やがてその男は急に速足になると、角を曲がってさらに薄暗い通りに入った。
わたしも見失うまいと歩みを速めて後を追った。
ところが、角を曲がったとたん、その男は立ちはだかるように、わたしの目の前に立っていた。
そして、驚いたように、とっさに身をかわすわたしに対して、その男が低い声で言った。
「なぜ、オレの後をつける。」
わたしは正直に答えた。
「わたしが捜し求めていた人に似ていたものですから。」
「オレは、お前のこと知らない、人違いだろう。」
「ええ、たしかに知り合いではないのですが。でも知り合いになりたいというか、それで探していたというか。もしかしたらあなたは、良いことや楽しいことだけではなく、悪いことや悲しいことにとても通じていらっしゃる方ではないかと思いまして。」
すると、その男はあごを上げて言った。
「まあ、そうだが。」
「やっぱりそうでしたか。」
「それでオレになんのようだ。」
「用と言いますか、とにかく知り合いになったかったと言ったほうか。」
「これは不思議だ、奇妙だ。ほとんどの人間がオレを気味悪がって避けているというのに。お前はなんとも思わんのか。あっ、そうか、察すると、お前には友達がいないな。」
「いや、ええ、ちっとも、さすが、、、、それで、、、、まだ、お会いして間もないのに、突然このようなことを聞くのは失礼だとは思いますが。あなたは先ほど、駅前で、ケーキ屋のほうをじっと見ていましたね。どうしてですか。」
その男は薄笑いを浮かべた。そしてかすかに開いたロ元から黄色すぎる歯をのぞかせながら言った。
「これから何か面白そうなことが起こりそうな気がしてな。」
「えっと、まだ知り合って間もないのに、こんなお願いをすねのはあつかましいんですが、どうか、あの娘に手を出すのだけ早めてもらえますか。」
「お前は、オレが誰だか判っていないようだな。」
「いいえ、判っています。たぶん、、、、いや、絶対に、さっきも言ったように、悪いこと悲しいこと人が嫌がることに、とても通じている、つまり、悪魔のような人というか、悪魔そのものというか、、、、」
すると、その男は顔を歪めながら言った。
「お前はずいぶんものをはっきり言う奴だなあ。でもオレは悪魔ではない、悪魔みたいだけどな。だいいち悪魔というのはだな、まあ、そんなことはどうでも良い。さっきの話だけど、オレは止めてくれなんていわれるとだな、どうしてそうなるのかは判らないんだけど、かえって気持ちが高ぶって、ようし絶対にやってやろうと力が全身からびりびりと沸いて来るんだよな。」
「そういう天邪鬼な感じっていうの判るような気がします。でも、あの娘にだけは手を出さないでほしいんです。あの娘はとにかく純粋で無垢な少女なんですから。」
「ふん、純粋、無垢。だめだね。いちいちお前たちの言うことを聞いてたら、オレたちの生きがいがなくなっちゃうじゃないか。」
「いったいなんになるんですか。そういう人の嫌がることをして。悪いことだとは思わないんですか。」
「ふん。悪いこと。あの娘のためじゃないか。どうして安い時給でこき使われなきゃいけないんだよ。あの娘の顔とスタイルなら、十倍も二十倍も高い時給の所で働くことができるというのに。それにだ、若いときから、何もあんなに真面目に働くことはないよ。もう少し遊んだほうがあの娘のためになると思うんだよ。だから、それを手伝って何が悪いんだよ。」
「それをあなたがやるんですか。」
「オレは直接やらないさ。見た瞬間に恋に落ちそうな若くて美しい男をけしかけて、その男に誘惑させるのさ。そしてオレは高見の見物。なにせ、それは、オレにとっては服からチリを払い落とすことくらいに簡単なことだからな。誰がなんと言おうと、オレはあう云う娘を見ると無性に何かを仕掛けたくなるんだよな。本能のようなかんじでな。とくに純真でひたむきそうであればあるほどな。」
その男は終始鋭い視線をわたしに投げかけながら話し続けた。わたしは彼の目を、まともに見ることに苦痛を感じ始めていた。そこでわたしは彼を促し並んで歩くことにした。わたしは本当はその男の氷のように冷たい視線や高慢な態度に耐え難いものを感じていたので、いっこくも早く彼から離れたかった。でも、その男の本当の意図を知りたかったのでもう少し付き合うことにしたのだった。
わたしから遠慮がちに彼に話しかけた。
「なぜあなたは、みんなが嫌がることや悲しむことをやるのですか。それは悪いことだとは思わないんですか。人を苦しめていったいなんになるんですか。」
「ふっ、苦しめて。それはオレにもよくわからないよ。なんていうか、体の奥底から沸いてくるんだわ。衝動っていうか、習慣って云うか、伝統って云うか、さっきも言ったけど、本能って云うか、どうしてもそうせざるを得なくなるんだよ。お前たちだってそうじゃないか。とくにお前のような善良そうな顔をしているやつはそうだろうけどさ。何か良いことをするとき、そうせざるを得ないからやるんだろう。そうすると気持ちがいいからするんだろう。それと変わらないんだよ。おっ、ついでに言っとくけど、俺たちは自分たちのやることを悪いことだなんて、ちっとも思ってやしないよ。とにかくみんなが嫌がることをやるのが生きがいなんだから。人がどうでもいいことやつまらないことで、苦しんだり悩んだり悲しんだりするのを見ると、とてつもなく楽しんだよ。快感なんだよ。とくに、それまで幸せそうな人間がだめになっていくのを見ると、その落差が大きい所為かたまらなく気持ちが良いんだよ。さらにだ、お前のように、そんなことはやめてくれなんて懇願されると、これは裏に何かがあるなと思って、かえってどんどんファイトが沸いてくるんだわ。はあ、不思議だね。
ところで、お前、なんとなく鼻につくんだけど。お前、あいつのこと好きだろう。」
「あいつって。」
「この世界を作ったとされるお方だよ。あいつは、お前のような真面目そうな人間が好きだからね。お前は信じているのかあいつのことを。」
「いや、自分でもよく判らない。ずっと前から死んだという噂は聞いているけど。でも、その死体はまだ見ていないし、それにまだ生きていると信じている人はたくさんいるし、それだけじゃないんだ、、、、とにかく、わたしにはなんとも言えない。」
「そうだろうな。オレも、あいつが死んだときかされたときは、最初は信じられなかったもんな。これからいったいどうなるんだろうかって真剣に考えたもんだよ。でも、あいつが死のうが生きていようが、オレにとってはどうでも良いことだけどな。あいつはどうもオレのこと大嫌いみたいだからな。オレもあいつのこと大嫌いだから。」
わたしは、奴が漂わす陰気な雰囲気に気が滅入りそうになりながらも、その本心を確かめるために念を押すように言った。
「もう一度お願いします。あの娘は本当にいい娘なんです。ひたむきで誠実で、あの娘の笑顔には、見る人たちを幸せな気持ちにさせる力があるんです。あの娘はみんなの宝物なんです。天使のような娘なんです。だから、どうかそっとしておいてほしいんです。おそらく、経験豊かなあなたの手に掛かったら。ひとたまりもないでしょうから。」
「はっ、それが気に入らないんだ。誠実だと、天使だと。それじゃまるでこのオレが悪魔みたいじゃないか。この際はっきり言っておくけど、オレは、お前やあの娘と同じように人間の子なんだ。それなのに、どうしてこうも姿かたちが他の人間と違うのか、さあ、目をそらさないでオレの顔を良く見ろ、お前は考えたことがあるか。」
「、、、、、、、、、、」
「姿かたちだけじゃない、こうも言動がみんなと変わっているのは、お前には判るか。お前のように善良そうな顔つきで生まれ、善良そうな人間の中で育てられた者には判らんだろうな。理由もなく忌み嫌われ、ぼろきれのように無視され侮られた人間がどんな顔つきになるのか、お前には判るまい。いや、勘違いするな、俺がそうされたのではない、ましてや、俺は小さいときからこんなひどい顔はしていなかったさ。オレがこうなったのはだな、、、、みんなと同じように人間の母親から生まれたのに、少しだけみんなと違うだけで、暗いとか気味が悪いとか言われ、無視され嫌われ侮られ続けた人間には恨みや怨念が自然と生まれてくるもんだよ、そのようなことが何百年も何千年も繰り返されるうちに、そのような恨みや怨念が消えずに残り、見えない雲のように寄せ集まって濃くなり、つまり霊となって時代を超えて世界に漂うようになり、それがオレのように見た目がみんなと違うような人間にとりついて、ますますオレを陰湿に邪悪に冷酷にさせるのだ。だが、それはオレの運命なんだ。ちょうど、ケーキ屋のあの娘が、愛情と思いやりに溢れた人たちに囲まれて育てられ。生来の可愛さだけでなく、周囲よりも際立つその可愛さのために、より大切にされ賞賛されてますます表情が豊かになっていき、そして善意や喜びや希望に満ち溢れた幸福の女神に祝福されるとき、彼女が天使のような純真無垢な笑顔になるのは当然のことなんだ。オレには判っている、お前たちがどんなにオレたちのことを嫌っているかということを。でも、しょうがない、オレの顔を見れば判るだろう。」
そのとき、わたしたちは再び華やかな表通りに出ていた。奴はさらに話し続けた。
「こうやってすれ違う人間を見てみろ。みんな健康的で賢そうで自信ありげで満足げだ。わたしたちはこんなにも幸せなんだといわんばかりじゃないか。でもな、このオレが、その気になって思いっきり不気味な表情をしてあいつらのそばを通り過ぎるだけで、今まですべてが順調に行って来た者もそうは行かなくなるだろう。歯車が狂ったように不幸な道を歩み始めなければならなくなるだろう。」
「やっぱりそうだったのか。わたしは今まで人々がいろんな不幸な目や悲しい出来事にあうのを見てきた。彼らはどう見たって何にも悪くないのにだ。なぜそうなるんだろうかってずっと長い間疑問だった。でも、今これでようやくその本当の原因がはっきりしたみたいです。どんなに夢を持って会社に入ってきても、何が不満なのか突然やめていってしまう若者がいるということ。そうするのには何かがあると思っていたが。そういうことだったのか。根は真面目なんだから多少いやなことがあっても、もう少し辛抱すればそのうちに道は開けてくると言いたいところだったが、本人が自分の自由意志で決めたことだからと思っているみたいだったのでどうしようもなかった。逆にこんなこともあった。どんなにやる気がある若者が現れても、周囲の既得権益にしがみつく大人たちによってたかってその芽を摘み取られてしまうこともあった。そうするとその若者は無力感にとらわれ、社会への不信感をあらわにしながら生きる気力さえ失ってしまうことがあった。大人たちは決してそこまでは追い詰めようとは思っていなかったようなのだったが。そうか、そういうことだったのか。ほかにもこんなことがあった。わたしの場合だが。わたしが小学校に入ったとき、わたしは親の言いつけを真剣に守り、近所の幼な馴染みと仲良くしながら登下校していた。ところがわたしたちのその仲の良さを見ていた者がいて、わたしたちがあたかも何か悪いことをしているかのように冷やかし囃し立てた。そのためにわたしたちはもう二度といっしょに帰ることも遊ぶこともなくなった。わたしはそのことを、これは決して人間だけの所為ではないとずっと思っていた。それからこんなこともあった。わたしが二十歳のとき、五歳年下の少女と知り合った。わたしたちは兄妹のように親密になった。わたしたちは将来の夢について語り合った。周りがどんなに暗く絶望的であっても、わたしたちだけはひそかに確実にささやかな希望に導かれていた。わたしたちの愛と信頼は確実に結晶し始めていた。それがどんなに周囲の状況や現実の逃れられない制約や呪縛からかけ離れていようとも、そして、それがまさに完成しようとしていたとき、わたしたちは突然何者かに力によって引き裂かれた。わたしはそのとき何が原因でそうなったのか判らなかった。でも、その後だんだんこう思うようになって行った。わたしにとって、その青春の不安と憂愁の真っ只中で、そのような少女と愛と信頼の結晶を育み、それを完成させるということは奇跡を起こすようなことである。つまり時間を止めようとする行為に等しいことだと。だから時間を止められて欲しくない何者かが、それを阻止しようとして、わたしたちの仲を永遠にを引き裂いたのだと。そうだったのか、やっぱりそういうことだったのか。」
すると、その男は声を荒げて言った。
「おい、何でも俺たちの所為にするなよ。今の俺たちにでさえ判らないことがあるんだからな。まあ、多分俺たちの仲間がやったんだろうがな。悪くおもわんでくれ、なにせ性分なもんで。とにかく、あいつが死んだと、孤独で賢くて理屈っぽい人たちが盛んに言い始めたとき、正直いってオレは困惑した。大嫌いだったから、居なくなれは居なくなったでそれで良いんだけど、でも本当に居なくなったら、オレはこれからどうすれば良いんだろうかって不安になったもんだよ。理屈っぽい人たちは、あいつが居るせいで人間は自由ではない、あいつが居るせいで不幸なことや悲惨なことが怒るんだ、あいつこそ諸悪の根源なんだと思って、あいつが死んだこと、いや、あいつを死に追いやったこと、いや、あいつを殺してしまったことを良いことだと思っているようだが、でも、理屈っぽい人たちが考えるほどこの世は単純じゃなかったみたいだ。あいつが居なくなったといっても、人間は相変わらず不自由だし、不幸だし、悩んだいるし、不条理な目にあって苦しんでいるし、オレから見たら、なんだかんだといっても人間が自滅したって感じかな。笑いが止まらんよ。」
「じゃ、悲惨な戦争や、大量虐殺は、あなたがたが引き起こしたのではないというのですか。」
「じょ、冗談じゃないよ。俺たちはそんなことには興味がないよ。俺たちが興味あるのは、ちょっとしたことで悩んだりくよくよしたりして、人間関係を悪くしたり人生を駄目にしたりして、それで苦しんだり悲しんだりしているどうしようもない人間だよ。とくにその悩む内容がつまらなければつまらないほど、興味が引き付けられるんだよ。なにせ、オレがその気になれば、どんなにうまく行っている者たちでも仲たがいさせ、傷つけ合わせて別れさせることなんかほんの目配せするくらいに簡単なことなんだ。なにせお前らは、ひがみっぽくねたみ深いだけでなく、プライドが高く意地っ張りで真面目で空想好きで、その上無類の誤解好きと来ているからにや。花壇の鉢植えを落としたり、予定表の日付を変えたり、冷たい風で顔をしかめさせたり、物音で注意をそらし聞こえなくさせたり、開いているはずのドアを閉じたりしてな、そんな取る似たらないことでお前たちは、考えられない行動を取るようになるんだからな、なにも大掛かりな作戦なんで必要ないんだ。本当にこたえられないよ、お前たちを苦しめ懊悩させるって言うのは。
ところが、近年起こっていることを見てると、いったいどうなっているのが、オレにもさっぱり判らんよ。もともと俺たちはあんな戦争とか虐殺とか、膨大なエネルギーが必要とすることにはまったく興味がないのだからね。なにせ俺たちは肉体労働が大嫌いだからね。それに、俺たちは、お前たちが思うほど目立ちたがりやではないんだ。なにせ過去の悲惨な歴史があるからな。俺たちが何か大事件や大事故のあったところをうろついてみろ、すぐ俺たちの所為にされる。あのかわいそうな野良犬を見てみろ。奴らがどんなに人間に気を使って目立たないようにびくびくしながら生きていることか。奴らは知っているんだよ。なにか良くないことがあったら、自分たちに怒りと不満の矛先が向けられるということをな。ふむ、もしかしたら、あいつが知らぬ間に生き返っていたりして。」
「あいつって、例の死んだという噂のある、、、、」
「そうだよ。当然だよ。孤独で思考好きで理屈っぽい人間のいうとおり、諸悪の根源のあいつならやりかねんな。いや、そうだ。もともと死んではいなかったりして。お前何をそんなに不思議そうな顔をしている。オレの言うことがでたらめだともいうのか。」
「でも、どうしても、戦争や虐殺が、あの姿を決して見せない者によって引き起こされたとは思えないですよ。」
「お前は甘いな。既成概念や噂話にとらわれすぎだよ。物事は見かけとは違うんだよ。本当の姿はそう簡単には判らないよ。とくにお前のような人間にはな。この世には思っていたこととは逆だったりすることがいっぱいあるんだ。本当に甘いよ。現にお前は、俺たちは、薄暗い裏通りを好んで歩いていると思っているだろう。とんでもない。その正反対だよ。俺たちはこう云う表通りがすきなんだよ。華やかなところが大好きなんだよ。幸せそうで善良そうな人間は大嫌いだけど、そういう人間を見るのはたまらなくに好きなんだよ。なぜだか判るか。そういう人間がだめになっていくのを堕落していくのを思い浮かべるだけでたまらなくいい気持ちになるんだ。特に、幸せそうであればあるほど善良そうであればあるほどその落差が大きいから、その楽しみも快感も大きいということだ。俺たちにとってそれは生きる希望なんだ。」
「そうすると、結婚式とか入学式とか、人がたくさん集まって幸せそうにしているところが好きだと言うことですか。」
「そうだよ、おっ、意外と物わかりが良いじゃないか。」
「以前、あなたのような人を知人の結婚式場で見たことがあるけど、やっぱりそうだったんだ。錯覚ではなかったんだ。」
「どうだ、判ったか。俺たち本当の狙いが。とにかく俺たちは、人間が楽しそうにしていたり、幸せそうにしていたりしているのを見ると無性にいらだってくるんだ。ときには苦痛を与えられているように感じるときもある。だから、人間が仲良くしていたり物事がうまく行こうとしているときに、それの邪魔をして、喧嘩別れさせたり、それまでうまく行っていた事を駄目にさせたくなるんだよ。思惑がうまく行ってそれが成功したときの快感といったら、お前にはわからんだろうな。オレだけの恨みではなく、俺たち仲間の積年の恨みを晴らしているっていう感じだからな。」
「それじゃ、わたしたちが悲しんだり苦しんだり悩んだりしているところを見るのはあまり好きじゃないと言うことですか。」
「そうじゃないさ。たまになら良い。でも、それだけだ。それ以上どうこうしようって気は起こらない。なんの張り合いもないからな。より高い所にいていい気になっている者を引きずり降ろして絶望させるという張り合いがな。そうだ、お前のさっきの話し、それは俺たちの仲間がやったのかもしれないな。でも、後のほうの話しは、もしかしたらあいつかもしれない。はっはっはっ。」
わたしはその男の言うことがよく判らなかった。でも、時間がだいぶ遅くなっていたのでそろそろ別れなければならないと思っていた。そこで最後にもう一度言った。
「あなたがどんなことに興味を持ち、どんなことに生きがいを感じているのかが判りました。でもあの娘にだけは手を出さないでほしいんです。」
「まあ、無理だろうな。」
「そんなにわたしたちのことが憎いんですか。」
「はっはっはっはっはっ、はっはっはっ、はっはっ、はっ、はっ、はっ、これはおかしい、憎い、オレが、お前らのことを憎いだと笑わせるな。はあ、それにしてもこんなに笑ったりは久しぶりだな。なんでオレがお前えらのことを憎まなければならないんだよ。お前らがどうなろうとなんとも思ってもいやしないのにさ。でも、お前らのことが好きなあいつを、ときどき無性に憎たらしくなるときがあるけどな。
まあ、物好きなお前のためだから、聞いてやってもいいがな。考えとくよ。じゃ、あばよ。」
「そのうちにまた会いましょう。さよなら。」
わたしは奴にあって話したからといって、それまでわたしを悩ませていたさまざまな問題が何一つ解決したわけではなかった。わたしはますます困惑し自信を失い、迷路に迷い込んだかのように途方にくれていくばかりであった。
わたしはもう一度奴に出会えることをひそかに期待していた。
それからしばらくして、わたしは偶然のように奴の姿を見かけることができた。それは駅前の街頭演説に聞き入る群衆の中にだった。
群衆にまぎれていても、その体全体から漂ってくる雰囲気で、すぐあのときの男だとわかった。やがてその男は、不機嫌そうな顔をよりいっそうこわばらせながらその群集から抜け出ると、時を刻むような確かな足取りで舗道を歩き出した。わたしは急いで後を追った。というのも、あのケーキ屋の娘が店に見えなくなったので、もしかしたらあの男が何かを知っているのではないかと思ったからだ。そして、もし知っているのなら彼女がいったいどうなったのか、ぜひとも問いただしたいと思ったからだ。ほどなく追いつくとわたしは並んで歩くようにした。そして奴に横から話しかけた。
「やあ、しばらくでした。ぜひもう一度会いたかったです。」
するとその男は、冷たい視線をチラッと投げかけただけで、そのままじっと前方に目をやりながら歩き続けた。
そしてしばらくするとその男は独り言のように言い始めた。
「本当に腹立たしい。何であんなにおとなしいんだろう。昔はそうではなかった。もっと激しく遣り合ってくれないかな。罵倒したり怒りを掻き立てるようなことを言ったり、できれば乱闘でもやってくれないかな、興奮した群集を巻き込んでさ。そうでないとちっとも面白くない。お前はどう思う。」
わたしはすぐに答えた。
「そうですね。政治家はいつもわたしたちの生活をよくするとか、わたしたちを幸せにするとかって言う、でも、そんなことを何十年もいってるけど、少しも変わっていない、もう聞き飽きたって感じかな。それに生活を良くするって言うのはまだ許せるが、わたしたちを幸せにするって言うのは、余計なお世話って感じかな。そんなこと個人の問題だよ、お前たちに言われたくないっていう感じだからね。ところで、あなたに聞きたいことがあるんですけど。最近、あの娘を、ケーキ屋の例の娘を見いないんですが。どうかしたんですか。」
「なんだよ、オレが何かをやったような言い方をして。俺は何もやってないし何にも知らない。別にお前に頼まれたからって訳じゃないけどね。でも、どうなったかはだいたいは見当がつく。お前よう、あの娘が何をやろうが、あの娘の自由じゃないか。それにさ、より良い生活を求めてお金を稼ぐことが、どこが悪いんだよ。みんながやっていることじゃないか。それよりも、お前はあの娘のこと何が判っていると言うんだよ。見掛けだけに捉われて、常日頃どんなことを考えているのか、何にも知らんくせに。おまえは、もう少し現実的になったほうが良いみたいだな。お前こそ余計なお世話じゃないのか。」
「、、、、、、、、、、」
「そんなもんだよ。お前にとっては残念なことかもしれないけど。ふん、オレにとっては喜ばしいことだ。もうたまらないね、人間が自滅していくのを見ているっていうのは。 さあ、あの親子連れを見てみたまえ。」
そう言いながらその男は前の方を指差した。そこには、ショーウィンドウに目をやりながら舗道を歩いている、両親とその一人娘と思われる高校生ぐらいの少女の三人の親子連れがいた。洗練された身なりからして裕福そうで、三人とも幸せそうな笑顔に溢れていた。そして、その男はその様子を見ながら得意げに話を続けた。
「子供も親もみんな賢そうだね。なんて屈託のない笑顔なんだろう。きっと夢と希望で未来はバラ色なんだろうね。身なりもきちんとして清潔感に溢れ幸せそうだね。あの娘は親の言うことをよく聞き、勉強もでき向上心もあり、親の自慢だろうね。まだ若々しい母親はしっかりと家庭を守っている感じじゃないか。父親は、あの自信に満ちた感じからして一流企業に勤務しているのかな。でもオレは知っているぞ。あんな幸せもろいもんだってことをな。それに、あういう火の打ち所のない幸せをだめにするのが最高の快感とするオレの手に掛かれば、ひとたまりもないってことがな。でもオレが手を下すまでもないさ。今の世の中何が起こるか判らないからな。確かにやつらは身なりもきちんとしていてお金持ちに違いない。おそらく父親は周囲との競争に打ち勝った成功者に違いない。生まれついた才能と人並み以上努力によって、その地位にたどり着いたに違いない。だが、どんなに良い会社だって突然ダメになるときもある。どんなに自分では優秀と思っていても嫌われたり必要とされなくなれば首になることもある。でもそれはあの男の所為じゃない。あの男がどんなにがんばってもそれはどうすることもできない。今はそういう社会なのだから。そうなると男は絶望し自信を失い途方にくれ社会に不信感を抱くようになるだろう。プライドが高いだろうから人並み以上にもがき苦しむだろう。人が変わったようになるだろう。すると家庭がギクシャクするようになるだろう。収入がなくなれば、あの可愛い娘だって、生きるためには何でもやらなければならなくなるだろう。はっはっはっ、たまらないね、幸せそうな人間が落ちて行くのは。それに比べたら、あいつらには、」
そう言いながらその男は、歩道から外れたところにたむろしている若者たちを指差した。そして話を続けた。
「やつら不良はつまらない。なんとも張り合いがない。やつらはあれ以上落ちようがないからな。適当に遊んでは適当に仕事をし、適当に人生を楽しんでいるからな。オレの罠にはそう簡単にははまらないんだ。」
その男の言い方に傲慢な印象を受けていたわたしは少し冷ややかに言い返すように言った。
「あいつらは大変なんですよ。仕事もなくって。みんな政治家が悪いから、政治家がしっかりしていれば失業なんかしないですむんですよ。」
「はっ、笑止。お前があいつらの心配をするなんて。本当は喜んでいるくせに、なんと言う嘘つきなんだろう。お前たちはすぐ失業率が高いのは政治が悪いからだと言って嘆いては、政治家に失業対策を求めて、そのことを実行する政治家は良い政治のように褒め称えるけど、それはお前らの振りだろう。なぜなら、五パーセントの失業者のおかげで、あとの九十五パーセントのものが仕事につけるんだということに、うすうす感じているはずだからだ。政治家が、それをやることによって経済から活力を奪い不況にさせてしまい、自分たちが失業してしまいかねないような下手な失業対策をとるよりも、何にもしないことを本当は政治家に望んでいるのだ。本音ではお前たちはいつも現状維持を望んでいるのだ。誰もがロでは失業者の味方みたいなことを言っておきながら、九十五パーセントの人間が心の底ではあまり変わってほしくないと思っていたら政治なんて変わる訳ないじゃないか。そのくせ何か良くないことが起こるとすぐお前たちは政治家の所為にするんだから。お前たちはまったく度し難い偽善者だよ。絶対に本当のことを言わないんだから。」
「、、、、、、、、、、」
「なんか、お前を見てると本当に鼻につく、いらいらしてくる。もしかしたら、お前は、オレがもっとも嫌いなタイプのような気がしてきた。この際はっきり言おう、いったい何の用が在ってオレに付きまとっているんだ。」
その男の辛らつな物言いに、わたしは怖気づきそうになったが何とか気力を振り絞って話し始めた。
「ずっと今まで、わたしは平和であることを願い、人間が平等であることを望み、個人というものを大切にしながら、何とか周囲の人たちとうまくやってきた。その間経済も発展し生活もどんどん豊かになり、ほとんどの人が人生に満足を感じるようになった。そう、確かにそれはそうなんですが、でも、その傍らではまだ苦しんでいる人たちがいる。戦争はいまだになくならない。飢餓もなくならない。突然の事故で悲惨な死を遂げる人もいる。犯罪も減らない。ときには考えられないような事件が起こりわたしたちを激しく苦しめ悲しませる。何もかもが自由で便利になったはずなのに、さまざまな問題が次々と起こっては悩ませ惑わせる。どうしてこうなるのか、わたしはわたしなりに考えた。だが、答えはなかなか見つからなかった。そこでわたしは周囲の人たちにたずねた。でも、誰も応えてくれなかった。それどころか、わたしが問いかけると、人々は、変なことを聞くやつだなあと言うような顔をして、わたしを避けるようになった。そしてわたしは誰にも相手にされなくなり独りぼっちになった。そこでわたしは、わたしとは違った意味で孤独なあなたにぜひ聞きたかったのです。」
「ふん、そんなことか。それこそオレのオレの思う壺ではないか。お前たちが苦しめば苦しむほど、俺たちの目的が達成され、気持ち良くなるってもんじゃないか。はっはっはっ。だがな、答えてやっても良いよ。でも、その前に言いたい。お前たちは本当に度し難いね。嘘つきだな。というよりも、本当のことを言わないって言ったほうが良いかな。あいつを殺そうとしたときもそうだった。お前たちは、賢くて、合理的だから、この世界を悪しているのは、不合理な魅力で人間を引き付けるあいつの所為だから、あいつさえ亡き者にすれば、この世はきっと良くなるに違いないとまくし立てていた。ところが、あいつが死んでしまったかのようにまったく姿をあわさなくなっても、この世はちっとも良くならなかった。それどころかますます悲惨を極め悪くなるばかりであった。
そこで今度は、お前たちは、金儲けのためにいっしょう懸命働く金持ちが悪いから、汚職をやる政治家が悪いから、弱い者を助けない社会の仕組みが悪いから、この世はちっとも良くならんいんだと言う始末。何か解決不能なことが起こるとすぐお前たちは誰か他人の所為にしたがる、本当に救いがたいよ。そもそも人間が平等なわけないだろう。こんなにも容姿や能力に差があるというのに。まさか、お前は、美人には興味がないなんて言わないだろうな。ふっふっふっ。
それに、このままだと人口が増えすぎていずれ食糧危機になるだろうなんて、笑わせるなよ。そもそも食料がなければ人口なんて増えるわけないだろう。戦争は悪だから悲惨だからしてはいけないと言っておきながら。裏ではこれは戦争ではないと言いながら殺し合いをやっているではないか。正々堂々とこれは戦争だと宣言してやればいいではないか。お前たちは大嘘つきだよ。他人に対してだけでなく自分自身に対してもね。お前たちは、戦争に反対して平和を願っていれば平和になると思っている、今まがりなりにも平和であるのは自分たち、平和を願う者たちのおかげだと思っている。
はたして本当にそうなのだろうか。お前はそこまで徹底して物を考えたことがあるのか。ふっふっふっ。これもみんなお前たち、思考好きなものの悪い癖だ。所詮中途半端な知恵よ、カラスの知恵よ。
お前たち賢いものは、自分たちの考えで社会を動かせると思っている。お前たちは自分たちの意識が変われば社会を帰られると思っている。そこがお前たちが根本的に間違っているところだ。勘違いしているところだ。そもそも今までに一度でも人間の意識でこの世界がよく変わったことがあるか。はっはっはっ。
さらにだ、お前たちはあまりにもお金のことをバカにしすぎている。お金の悪い面否定的なイメージにだけ捉われすぎて、お金の本当の意味や価値がぜんぜん判っていない。どんなに陰で人間の社会の発展に貢献しているのかも知らないで。まあ、それが判らん限りお前たちは永久に問題を解決できないだろうね。かつて何か悪いことの原因をあいつやオレや金持ちや政治家の所為にしたように、なにかほかのものにするだけでね。ふっふっふっ。」
期待していたような答えが得られなかったために、わたしは少し落胆し反発を覚えながらも、その男の機嫌を損 ねることを恐れて、それを悟られない様に冷静に言った。
「それじゃ、この世界を悪くしているのは、いったい誰なんだろう。何が原因なんだろう。」
「そんなことオレにはわからんよ。考えたこともない。お前たちがひどい目にあって苦しんだり悲しんだりする のを見て楽しんでいるこのオレが、この世界が悪くなればなるほど、混乱すればするほどいいと思っているこの オレがだよ、この世界を悪くしているという、その原因を考えるわけないだろう。でも、そんなに聞きたいなら 言っても良いがな。これはオレの単なる思い付きだが、ひょっとしたら、この世界を悪くしている真の原因は、 お前たち、いかにも善良そうなお前たち自身にあったりしてな。どう、不満かな。」
「不満ではないが、納得はできないです。この世界を少しでも良くしようとしているわたしたちが、諸悪の根源 だなんて到底考えられない。それから、わたしたちの考えや意識が世界を変えていないなんていうのも、まった く考えられないですよ。もし、あなたの言うとおりだとしたら、それはお金だということですか。お金がわたし たちの世界を平和で平等で民主主義の社会にしているということですが。そんなことはありえないですよ。もし そうだとすると、わたしたちがそれを実現することを目標として行動している正義とか真実とかいうことは何の 意味も持たなくなりますからね。」
「はっ、またでた。正義だと、真実だと。ふっ、オレはお前たちがその言葉を言うといつも大笑いをしたくなる 。なんと言う愚か者なんだろう、なんと言う偽善者なんだろうとね。でも、まあ、そのおかげで俺はお前たちを 罠にかけやすいんだけどな。それはお前たち、思考好きな者の悪い癖だ。何か良いことや正しいことは、それだ けにとどめておけば良いのに、すぐそれよりいいこと、それより正しいことを求めようとする。そしてそのこと をいろんなことに当てはめて拡大して体系化して普遍化しようとする。それは結果的にはどういうことになるか というと、悪いことも体系化し普遍化して、この世界から意識的に排除しようとしていることになることに少し も気づいていないということなんだよ。そういう自分たちだけが正しいんだ、自分たちがこの世界から悪を追放 するんだという無自覚で傲慢な態度が、何の責任のないものに責任を負わせようとすることにつながるんだ。お 前たちが偽善者だというのはそう云うことなんだ。
つまり、この世から悪や不正をなくそうとしていながら、結局は悪や不正がなければ身動きが取れない、そこで 心の奥底ではひそかにそれを必要としていることがな。それはまるでこの世から貧困や不公平をなくそうとして いるものが、その活動を続けていくためには、貧困や不公平がこの世界に存在し続けることが必要であるみたい にな。それから医者や弁護士も同じことだ。彼らはこの世から病気やトラブルがなくなることを願っているが、 本心はそうではないはずだ。だって、病気やトラブルがなくなったら、彼らは生活出来なくなるからな。それか ら、悲惨な事故や事件を取り上げるマスコミや、不正や悪を追及する評論家も似たようなものだ。彼らは顔をし かめて嘆き悲しみ、そして声をそろえて、批判し、最後には、こんなことは二度と起こらないことを望むとは言 っているが、もし本当に起こらなかったらどうするんだろう。何もすることなくて退屈で退屈でしょうがなくな るだろう。ところで、こんな話はどうだ。ある若者がいて、その若者の母親が再婚しようとしていた。普通だっ たらというか、建前上は、母親が再婚する相手は、母親を幸せにできるような、立派な大人であることを望むも のだが、でも、その若者は心の底から、その男が尊敬に値しない大人であることを望んでいた。だから、実際に 母親の再婚相手に会って、その男が社会的地位もあり素晴らしい人間であると判ったときには、けっして母親が 幸せになることを望んでいないわけではなかったが、その若者はひそかに絶望し落胆したということだ。どうだ 。ふん、お前たちが大切にしている正義とか真実とか言うものは、所詮そんなものよ。誰にもほんとうのことな んか判らんよ。人間の知恵なんてカラスとたいして変わらないんだから。」
「あなたにも本当に判らないんですか。」
「判らんよ。オレはとにかく、人間が苦しんだり悲しんだりすることにしか興味がないからね。それにオレはお 前らと同じ人間だからな。」
「では、その答えを判っているのは、あの方、わたしたちを作ったといわれているあの方、決してわたしたちの 前にその姿を見せないあの方が知っているということになりますかね。」
「はっ、また、あいつのことか。お前はやっぱりオレよりあいつのことを信じているんだな。オレのことを信じ ているような振りをして近づいてきて意見を求めたくせに。だから最初からお前らみたいなのと話をするのはい やだったんだ。それをうるさく付きまとうからしょうがなく付き合ってやったのに。」
「いや、あなたのことを信じてないというのではなく、言うことがあまりにもとっぴなことなので、納得できな いというか、よく判らなかっただけです。」
「それが嘘だというんだよ。お前はずっとオレの眼を見て話していない。それはお前がオレに何かわだかまりを 持っているという証拠じゃないか。つまりオレをちっとも信じていないのに、信じているという振りをしている やましさがな。何にもないならオレの眼を見れるはずだ。それとも怖いのかな。」
「わたしがあなたの眼を見て話さないのは決して怖いからではなく、あなたの眼の中に冬の荒野のような寒々と したものや、悲しみ、いや、言いようのない寂しさを感じるからです。」
「はっ、このオレが寂しいだと。友達もいなくてオレの所に泣き付いてきたお前のような人間に言われたくない わ。俺は毎日が忙しくて忙しくて、楽しいことで満ち溢れているんだ。だから、お前がオレの言うことをそんな に納得ができないと言うのなら、もう話すのはやめても良いんだよ。せっかくヒントらしいものを出してやった というのに。お前以外と物わかりが悪いんだな。」
「でも、この世界を悪くしているのは、誰でもないとか、わたしたちの意識が社会を良く変えていないなんて言 われると、やっぱりどうしても納得ができませんよ。それで、そのヒントというのは何ですか。」
「それは、すべての原因はお前たち自身にあるんではないかということだよ。」
「まさか、どうしてわたしたちに。」
「お前たちのそういう真面目なところにね。お前たちのそういう努力してがんばるところにね。お前たちのそう いうバカ正直なところにね。とくに、少しの悪も不正も認めようとしない完全主義者的なところにね。」
「、、、、、、、、、、」
「まだ、納得できてないみたいだな。お前たちはこの世界に何か起こると、すぐ自分たちが勝手に思い描く理想 社会に照らし合わせて、これは悪いことだ良いことだと判別して、悪いことは徹底時に排除して良いことだけを やろうとする。ひたすら真面目に努力してがんばってな。これはとても良いことをやっていると思ってな。そし てそれを良い事だということで世界に広めながらね。」
「人間は努力するものですから。」
「ふん、そこだよ。おそらくお前は若いときから勉強して努力して今のまずまずの位置にあるのだろう。そして 、もし、もっと努力すればもっと上に行くことができるだろう。でも、その所為で、お前ががんばれはがっばっ た所為で、どれほどの人間が敗れ去っていったことか、どれほどの人間が悔しい思いをしたり自暴自棄になって 人生を捨てたくなったことか、お前は考えたことがあるか。」
「いや、ないですけど。でもそれは少し大げさじゃないですか。少なくとも今の社会は競争社会ですから、勝っ たり負けたりすねのは仕方がないことですよ。」
「けっ、大げさだと。なんにも判ってないくせに。負けたり勝ったりすることが悪いことだなんて、オレが言っ ているのではない。お前たちが良い事だと思って、真面目に努力してがんばってやることが、結果的には思わぬ こと引き起こしたり、望んでもいなかったことを生み出したりするということを言いたかったんだよ。それには 当然、お前たちが予想もしなかったようなまったく正反対の悪いことや悲しいことが含まれるということなんだ よ。お前は抗議集会に出たことがあるか。オレはある。ほとんどが平和的だが。ときには血なまぐさい騒乱事件 になってしまうこともある。そこに集まってくる人たちが平和的で穏やかで、そんなことをまったく望んでいな いにも関わらずだ。なぜだと思う。おっと、オレじゃないよ。まったく単純なんだ。狭いところに人が集まりす ぎるということなんだ。余裕のあるところでやれば、過激な人間がいない限り絶対にそんなことは起こらない。 だから、オレから見たら興奮したい群衆は自らより狭いところを目指して突き進んでいるとしか思えない。
これと似たようなことだが、どこかで大災害が起こったとき、被災して困っている人たちを助けようとして、援 助物資を持って周りから人が集まってくることがある。でもあまりにも多く集まりすぎると、その人たちがどん なに善意に溢れた者たちであっても、救助の妨げとなって、かえって迷惑をかけてしまうことがあるんだ。まだ 他にもある。お前も知っているだろうが、漁民ががんばっていっぱい魚を取れば、かえって貧乏になることがあ る。農民も努力して工夫して米をたくさん取れるようにしても、怠け者よりほめられることは決してない。むし ろ周りから煙たがられる。他にもまだまだいっぱいある。そうだ、逆の場合もある。良くないこと否定的なこと だが、良い結果につながることもある。オレはこんな礼を知っている。俺の知り合いが高校のとき、登山クラブ に入っていたことがあった。その知り合いが新入部員のとき、合宿として初めて山に登ったとき、その知り合い よりも体力が劣るものが、みんなの足を引っ張った。苦しそうに顔をしかめてぜいぜい言いながら、どうしても みんなのように早く歩くことはできなかった。そこでその体力のない部員は、先輩から終始励まされたり皮肉を 言われたりどやされたりしてた。他の新入部員の中には、その苦しそうな表情は演技じゃないかというものもい た。わたしの知り合いの男もそのとき、そうかもしれないし、そうでもないかも知れないと思っていた。でも、 結果的には、その体力のない部員のおかげで、全員がゆっくり歩いていたので、その知り合いの男にとっては体 力的には楽であったということには気づいていなかった。それからこんなおとぎ話はどうだろう。それぞれ少し だけ太さの違う九本の柱で、ある建物を支えていたということじゃ。ところが大地震がおきて、それまでの何倍 以上もの重みをこらえなければならなくなった。最初みんなで協力して必死に支えていたが、その中の他のもの よりは少しだけ細い一本の柱が、間断なく押し寄せる重みに耐え切れずに曲がって裂けてしまった。そのおかげ で周りの八本の柱は楽になり、傷つくことなく、そして地震もおさまったということだよ。どうだ少しは参考に なったかな。」
「、、、、、、、、、、」
「そうか、どうしてもオレの言うことが信用できないということか。ふん、あいつか。どうだろう、あいつは、 お前たちがあいつのことを思うほど、お前たちのことを思ってやしないよ。それにあいつは決して人間に自分の 姿を見せないから、話すことも聞くこともできないよ、あきらめな。まあ、でも、お前は物好きにも、オレのよ うなものに助けを求めてきたんだから、話してやっても良いけどな。とっておきの話をな。俺たちの仲間同士で ひそかに語り継がれているうわさ話をな。こういうことだ。あいつは、人間が何かとんでもないことを考えて問 いかけると、反応するということだ。星が消えたり現れたり流れたり、そして突風が起こったり地震が起こった り火山が爆発したりしてな。」
「とんでもないことって。」
「たとえばだな。お前が本当に思っていること。つまり本音だな。それを言うと周りの人間をお前のことを変人 とか狂人とか思うようなことだよ。」
「人生は、食べて働いて寝て、そのくり返し、死んでしまえばそれで終わり、何も残らない、すべては無だ、と か。」
「はっ、そんなのは古臭い、あいつはもう聞き飽きているよ。」
「、、、、、、、、、、」
「ふん、そんなに深刻そうな顔をして。お前はあれだな、オレの前では、あいつのことを信じてないような言い 方をするけど、本当は信じているんだろう。本当はあいつに気にかけてもらいたいんじゃないか。ああ、やっと 判ったよ。お前が何で鼻につくのか。あいつはお前のような真剣に悩んで苦しんで努力する人間が大好きなんだ よ。オレと違ってな。ふん、なってこった、ちくしょう。まあ、いいか、しょうがない。お前は苦しめばいいん だよ。それがお似合いだ。そうすればますますあいつに愛されるようになるんだから。オレはますますいじめた くなるけどね。はっはっはっ、はあ。もう良いだろう、もうお前と話すことは何もない。そうだ、この前お前は 気にしてたな、時間を止めようとしたから永遠に引き裂かれたって。それは俺たちの仲間の所為でもあいつの所 為でもないよ。おまえ自身のせいだよ。お前のその極度の内気な性格の所為だよ。さあ、悩め、苦しめ。オレは 帰る。その前に最後に言っておこう。お前はもう少し好きなように、やりたいようにやったら、オレも好きなよ うに、やりたいようなやるからさ。じゃあ、あばよ。」
そう言ってその男は、さらに薄暗い路地へと入っていった。それがあまりにも素早かったので暗闇の中へ消えた かのようにも思われるぐらいだった。わたしたちが別れたのはちょうど教会の真裏になっていた。
奴と別れてから、わたしは奴が別れ際に言った言葉
「もう少し好きなように、やりたいようにやったら。」
という言葉を思い起こし、実際そうするように何度も試みてみたが、でも、なぜかわたしにはそのようには出来 なかった。
それどころか、奴の言った不気味な言葉がわたしの頭の中に居座り続け、病原菌のように増殖続けていくばかり であった。
そして、わたしが最後のよりどころとしていた奴の知恵をもってしても、わたしの苦しみや悩みを解決できなか ったと云う落胆と絶望から、わたしはますます混迷を深め不安になっていくばかりであった。
わたしは暗く沈み込み、人々との接触を絶ち言葉を忘れたかのようにしゃべることもせず、周囲に何が起こって も道端の石ころのように沈黙し続けていた。
そして止むことなく悪のそこは割れ続けていた。
そのたびにわたしたちは、考えられないような犯罪に途惑い慌てふためき恐怖に怯えるようになっていった。
そしていくたびも、苦しみの底も割れ続けた。
そのたびにわたしたちは、罪のない子供たちの非業の最後を目にしながら、顔を両手で覆って嘆き我を忘れて怒 り狂うようになっていった。
さらにいくたびも寂しさの底も割れ続けた。
そのたびにわたしたちの硬くもろくなった心は打ち砕かれ、二度と立ち直れないほどに打ちのめされ、たくさん 人たちが自ら死を決意せざるをえないほどに追い詰められていった。
そしてわたしはといえば、そのような世界の出来事を他人事のように傍観し続けては、どうすることも出来ない という無力感と孤独感に苛まれながら、まるで絶望の淵に身を沈めているかのように、相変わらずこの繁栄の街 から逃れられずに住み続けるだけだった。
社会から忘れ去られたかのようにひっそりと。
そして、ついに悲しみの底が割れた。
それは突然ドアを叩く音から始まった。
「実家から電話ですよ。」という呼びかけはすべてを物語った。
わたしがずっと夢見ていた風景、
その晩秋の穏やか過ぎる風景、
あなたに許されて満ち足りた気持ちで眺めているに違いなかった風景を、
もう見ることは永遠にできなくなってしまった。
なぜなら、そのたなびく煙は、
あなたが来年の春の農作業のために籾殻を焼いている煙だったからです。
そして、その草の陰のような人の姿は、
ひたむきに働くあなたそのものだったからです。
十六年前、あなたと別れたとき、わたしは三十六歳になっていた。
そのとき、わたしたちは涙を流した。
なぜなら、これが最後の別れになるのではないかとお互いに予感したからだった。
そして、最も愛するもの同士はいっしょに住めないということにうすうす気づきながら。
でも、本当は最後にならないようにすることも出来た。
だが本当に最後になってしまった。
わたしは旅立つとき、何者かになってあなたに認められることをひそかに決意していた。
だが何者かになろうと努力したが、結局、何者にもなることができなかった。
わたしは何にも変わらなかった。
わたしは何者にもならなかったことを、決して後悔はしていない。だが、、、、
わたしはいつもあなたの姿を追って後から歩いていた。
あるときわたしはあなたの姿を追い越して歩き始めた。
そして、わたしは後ろを振り返った。
するとあなたはわたしの方を心配そうに見ていてくれた。
しばらく歩いた後わたしは、わたしは再び後ろを振り返った。
だが、そこにはあなたの姿はなかった。なぜ、、、、
わたしはちょっとの間前を見て歩いていただけなのに、、、、
わたしは繁華街を歩くとき、迷子にならないようにと、
いつもあなたにしがみつくようにして歩いていました。
でも、見たことのないものを眼にすると、
どうしてもそっちのほうに注意が行って手を離してしまうのでした。
そして気が済んだ再びあなたを捕らえようとすると、
そこにはあなたの姿はなくて手は空を舞うばかりでした。なぜ、、、、、
わたしはほんのちょっとの間よそ見していただけだというのに、、、、
その期間がたとえどんなに短かったとしても、
あなたといっしょにいるときはいつも退屈過ぎるかのように、
永遠のように感じていました。
でも、今こうしてゆっくりとまぶたを閉じて、
再び開けると、それは幻の出来事のような、
あまりにも短すぎる瞬きのような瞬間の出来事のようにも思えるのです。
そのあまりにも短すぎる瞬間が、、、、
永遠がその姿を変えたかのような、あまりにも短すぎる、星の瞬きのような瞬間が、いま、、、、
わたしが気がつくと、そこにはあなたの笑顔が在った。
祖母や父や兄や姉たちと共に。そして、わたしは祝福され満たされた。
それまでどんな暗闇と虚無を潜り抜けてきたのかも知らずに。
わたしはあなたの愛を注がれていっしょにすごした。
そのときがあまりにも豊かで喜びに溢れたものであったために、
わたしは何度も永遠を感じたほどだった。
たとえ、そのときがあまりにも短すぎる星の瞬きのような瞬間であったとしても。
そして、あなたは突然のように、わたしよりも先に、
わたしが潜り抜けてきた暗闇と虚無へと去っていってしまった。
最後の恥ずかしそうな不安そうな心配そうな笑みをわたしの心に永遠に刻みつけながら。
そのあまりにも長すぎる永遠が、、、、
瞬間がその姿を変えたかのような、あまりにも長すぎる、想像することさえ不可能な永遠が、いま、、、、
そうなのだ、わたしたちはこの宇宙で光の速度ですれ違ったのだ。
光と光がすれ違う瞬間、たとえ、それがどんなにわずかな時間であったとしても、
わたしたちは互いにはっきりと確認しあった。
永遠の時を感じなから。
だから、わたしは全力でその時を大切にすべきだったのだ。
取り返しがつかなくなる前に。
星の瞬きのような瞬間が永遠に姿を変えない前に。
だが、すべては終わった。
もう手遅れだ。
わたしたちは再び光の速度で歩み始めてしまったから。
永遠に出会うことのない旅へと。
たとえ、宇宙が造り変えられても、
決して出会うことがないに違いない暗黒の虚無の旅へと、、、、
これが、
わたしは十九歳のとき、
日差しの穏やかな秋の日に、
深く長い思索の結果として、
しかも突然のように一つの洞察を獲得したことなのだ。
生と死には絶対的な違いがあるという、洞察を。
死んだら何も残らない、
今こうして生きていることがすべてであるということを、
この世に存在していることが、
喜びであり楽しいことであるという、
洞察を獲得したことなのだ。
割れた悲しみの底から滑り落ちたわたしは、廃棄された人形のように際限なく落ちていくばかりであった。
そして、いつの間にか狂気と死がわたしに寄り添うようになっていた。
わたしは気力を振り絞り全力で悲しみの底を作り直さなければならなくなった。
わたしは奴が言ったことを試みることにした。
「あいつは、人間が何かとんでもないことを考えて問いかけると、反応するということだ。
星が消えたり現れたり流れたり、そして突風が起こったり地震が起こったり火山が爆発したりしてな。」と言っ たことを。
そしてわたしは、満天に星が輝き風のない静かな深夜にそれを決行した。
わたしは、それまで誰にも言ったことがないようなことを、あの有史以来決して姿を見せたことがない方に、次 々に問いかけた。
まず最初は、次のように。
「もしかして、狭き門とは、そこを通る者が寂しいということではないのですね、、、、」
なんにも起こらない。
そして、次に。
「もしかしたら、大いなる悲しみの裏には大いなる喜びが隠れているように、深い憎しみの陰には深い愛が潜ん でいるのではないでしょうか、、、、」
なんにも起こらない。
そして、次に。
「もしかして、悪魔の反対は天使ではなく、神様、つまりあなたではないでしょうか、、、、」
なんにも起こらない。
そして、次に。
「もしかしたら、女性の美しさとは永遠に所有できないものなのではないでしょうか、本人だけでなく、男性に とっても、、、、」
なんにも起こらない。
そして、次に。
「もしかしたらあなたは、人間たちを羨ましがっているのではないですか。どんなに傷つけ苦しめあっていても やっぱり最後は愛し信じあっているということに、、、、」
なんにも起こらない。
そして、次に。
「もしかしたらあなたは、ほんとうは自分のことをほとんど考えたことはないのではないでしょうか。わたした ち人間にあなたについて考えることを任せきりにして、、、、」
なんにも起こらない。
そして、次に。
「もしかしてあなたは、人間がどんな苦境や困難もがんばって克服していくのを、そして、死ぬまで悩み苦しみ 努力するのを見て、本当はこんなはずじゃなかったと思っているのではないですか、、、、」
なんにも起こらない。
そして、次に。
「もしかしてあなたは、人間にはその不器用さのために人並みに努力できないものが居るということ、そして、 どの母親とも同じようにわが子を愛せない母親がいるということをご存知ないのではないでしょうか、、、、」
なんにも起こらない。
そして、次に。
「もしかして、わたしたちの国がこの二十世紀後半から、永遠とも絶対的ともいえるような平和に入っていった のは、わたしたちが平和を望み平和を愛していたからではなく、その絶対的ともいえる破壊兵器のおかげだった のではないでしょう。だから、この世界は七本の知恵の柱ではなく、本当は七本の炎の柱によって支えられてい るのではないでしょうか、、、、」
なんにも起こらない。
そして、次に。
「もしかして、わたしたちの地球が、豊かな自然環境を保ちながら存続するということと、世界が経済的に繁栄 して、飢餓も戦争もなくなり、わたしたちがあらゆる欲望を満たしながら平和に豊かに便利に快適に生活すると いうことと、そして、物質的には恵まれていなくても心豊かに道徳的にありふれた幸せを感じながら生きるとい うこととは、それぞれ絶対に相容れることができない法則の支配下にあるのではないでしょうか。だから、もし この地球上に、自然環境に恵まれ、戦争も飢餓もなく、平和で搾取や抑圧がなく、犯罪や災害もなく、便利で快 適で、どんな欲望や願いをかなえながら、すべての人たちが幸せに満ち足りた気持ちで生きることができるよう な平等で思いやりに溢れた世界が実現したら、その瞬間に世界はあっという間に崩壊していくのではないでしょ うか、、、、」
なんにも起こらない。
わたしはなおも続けた。
「あなたはご存知でしょうか。人間には自分の肉体を傷つけ犠牲にして魂を救おうとするものだけではなく、そ の自分の魂をも傷つけ犠牲にする者たちがいるということを、、、、」
なんにも起こらない。
わたしはさらに続けた。
「もしかしたら、あなたはご存知ではないでしょうか。人間の最後は決して幸福ではないということを。つまり 、生きている限り死の間際まで苦痛から逃れられることはできないということを。だったら言いたい、わたしが その前に、なんて幸せなんだろうとか、なんて満ち足りた気分なんだろうなどとぬかしたら、どうか、あなたの 軍勢を引き連れてきてわたしを八つ裂きにしてもかまわないと、、、、」
なんにも起こらない。
最後にわたしは次のように問いかけた。
「はたして、人間の心というものは自分のものでしょうか、、、、」
だが、なんにも起こらない。
その決して姿を現さない者がなんにも応えないからだ。
なぜ、決して人前にその姿を現さないあなたは、なんにも答えようとしないのですか、、、、
時間は凍結し、星のない暗闇が果てしなく続く
なんだろう、この背後のざわめきは、、、、
わたしはひとりではなかった。
もしかしてわたしは本当の自由を獲得しようとしているのかもしれない。
さあ、腰を伸ばして、顔を上げろ、胸を張れ。
《ざわめきを求めてへつづく》