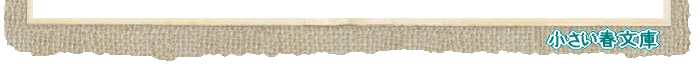わたしたちが出会うまで、
わたしたちは激流に飲み込まれた枯葉のように、
どこからともなく現れてはどこへともなく消えていくような、
群集の単なる構成員に過ぎなかった。
* * * * * * * * * * * * * * *
詩集悲歌(第一から第七まで)
小礼手与志
* * * * * * * * * * * * * * *
わたしたちは果たして
夢を見ずに生きられるだろうか
わたしたちは果たして
何かに熱狂せずに生きられるだろうか
そして、非存在と不可能性に向かって
わたしたちは限りない自己変容へ
生命はひとつの星だから
・・・・・・・・・・・・・・
第一悲歌
また夜になった
湿った夜空に乱反射する街の光
まだぬくもりを残す陸橋の欄干
無数に散在する塵埃と
町の光にさえぎられた見えない星の下に
電車は徐行をし始めた
窓からのぞく乗客の顔に
視線が合うのを恐れるように
こっそりと人類の自画像を盗み見る
わたしは今日も数知れない人々とすれ違った
一人一人みな違う表情を持っているに違いないのだが
わたしにはただすれ違うだけの関係に過ぎない
車にはねられそうになった先ほどの老人
もうじき死ぬだろう
わたしの胸に沸き起こる不気味な安堵感
嘘のひとつでもつきたい昼は終わった
錯綜惑乱な昼は終わった
それにしても昼はなんと錯覚に満ち満ちていることか
わたしは夜だけしか愛せなくなったのだろうか
思い起こそう
かつて、わたしがわたしでも
わたしがわたしでもなくてもよかったころ
過酷な太陽に突き刺されようが
青空を見失おうが
ただ母の前の幼児のようでありばよかったころ
限りない大地との黙契
やさしい人間たちの愛のなか
命の河は流れていた
明日への本流に向かって
昼はさんさんと光をたたえ
夜は豊穣に横たわっていた
叫びは約束された歓喜であり
眠りは明日へのたしかな希望
思いは人々への愛につながり
想いは美しい実在だった
そしてある国土への夢のような憧れ
信じられ信じさせられた言葉の数々
自由、平等、民主主義、、、、、
思い起こそう
色あせた昨日を
わたしがわたしでなけれがならなくなった今日を
大空の前によりどころを見失ったわたしと人類
打ち砕かれた自然との黙契
神なる人間の永遠の不在への自覚
生命の川はよどみ
明日への怠惰な濁流に変貌した
叫びは背光人間の乾きとなり
眠りは明日への不安となり
思いは人々への憎しみにつながり
想いは美しい非在になった
そして、人間共同体への限りない不信
疑われる数々の言葉
自由、平等、民主主義、、、、
わたしがわたしでなければならないこの夜
わたしが人々から逃げたのか
人々がわたしから逃げたのか
ふとわたしの脳髄を突き刺す
「もしかして、わたしは敗者ではないか。」という思い
わたしは幻想の勝利者など決して信じていないのだが、、、、
わたしはこの情景を
永遠の感光版に焼き付けてみたい
光と塵埃にさえぎられた星の瞬く宇宙から
この地球時をとめてみたい
永久に涙が流れないように
永久に涙が流れ続けるように
・・・・・・・・・・・・・・
第二悲歌
この騒然とした遊技場の窓から夕暮れの街を眺めても
目に映るのはおびただしい車と家路を急ぐ人々の群れ
ネオンサインは裏通りを飲み屋街に変え
ケーキ屋の売り娘は客の応対に忙しい
車は絶え間なく流れ続け
群衆は一心に信号の青を待っている
きこえない
わたしのまっているにんげんたちの
やさしいにくせいがきこえない
人々は
生の意義という素朴な問いに
もうすでに答えを出しているのだろうか
人々は
果たすべき義務の前に
もうすでに許されているのだろうか
人々は
確実に訪れる死の前に
もうすでに安らぎを見出しているのだろうか
ただ与えられた生を生きるに過ぎないのに
ただ与えられた死を待つに過ぎないのに
なぜにわたしは
このおびただしい車と人々を見つめていなければならないのか
いったいだれが
この騒然とした遊技場にわたしを立たせるのか
なぜにわたしは
乱暴に手をはねのけ、いかにも当然のように
電車を降りていった女に激しい怒りを覚えなければいけないのか
なぜにわたしは
深夜、電車の窓に映る様々な顔のなかに
他の人と区別がつかない自分の顔を見出さなければならないのか
なぜにわたしは
たわいない映像や活字に一日の終わりまで
慰められなければならないのか
なぜにわたしたちは
よそよそしい隣人たちに不安や敵意を抱き
肉親のなかにだけ安息を見出そうとするのか
なぜにわたしたちは
まるで愛が不在であるかのように
愛を取り立てて言わなければならないのか
なぜにわたしたちは
善良そうなニュース解説者に同調し、あたかも
この世にあくが必要であるかのように悪を捏造するのか
なぜにわたしたちは
空虚な脳裏をのぞき見られるのを恐れるかのように
一日中忙しそうに動き回って働かなければならないのか
なぜにわたしたちは
酒を飲み突然饒舌になり、そのときだけしか
お互いを明かそうとしないのか
なぜにわたしたちは
生の意義へ自己の内から求められないのか
なぜにわたしたちは
生の意義を与えられないのか
与えるものはもはやいないのか
どうしてもきこえない
わたしのまっているにんげんたちの
やさしいにくせいがきこえない
途切れることのない車の列
憑かれたように歩く人々の群れ
めまぐるしく点滅するネオンサイン
をみつめている
わたしでないわたしがタバコを吸う
・・・・・・・・・・・・・・
第三悲歌
動物園にて
東京に行ったらパンダが見たいと
あどけなく言ったぼくの少女は
半年でぼくたちの生まれた北の地に帰っていった
少女の体は半年もたなかった
東京は半年もたせなかった
パンダを見たいというのは陳腐であろうが
国会議事堂や東京タワーを見たいという俗悪さよりはすばらしい
ぼくはやってきた
少女が乗ったであろう電車に乗って
それはかつてぼくの父や兄や
もう別れた昔の友達が乗ったであろう電車ではなく
まぎれもなく少女が乗ったであろう電車に乗って
ぼくはやってきた
少女が見たいと言っていたパンダを見るために
だが今日はパンダの休演日
パンだの怠けぶりや惰眠を見るのも良いが
ぼくが見たかったのは
少女が話してくれた思い出の中のパンダ
ぼくが本当に見たかったのは
少女が見たであろうこの風景
だが、もうどうでも良い、今日は暖かい春の日。
冬の気団はいつしか北の地に消え。
ふりそそぐ桜の花びらは盛んに日の光をはじき、
風に流され、ぬかるみに沈み、
人々はどこからともなく、
陽炎のようにわき出し地にあふれている
ぼくは見る。
不気味な輝きを持ち、
その極度に発達した眼は遠く空間をつかまえ、
そしてただ空間のみに生きる鳥たちを。
その眼は熱病患者のように病み、
ずうたいだけは大きい内気な子供のような象を。
それはあまりの退屈さのためか、
それとも人間の目を意識するためか、
人間のあらゆる悪ふざけを模倣するサルたちを。
狭められたパーソナルスペースに生きる動物たちよ、
眠れ、今日のような日は怠惰であれ。
たとえ、お前たちが怠惰であっても、
いったいだれが不満を言おうか。
人間はお前たちの正体を見抜くことはできないから。
少女よ、追憶の少女よ。
ぼくはあなたのように不幸な宿命に身をゆだね、
ここから逃れることはできそうにもない。
ぼくはあまりにも自分を知りすぎた。
たとえどこに逃れようと、ぼくは、
すべてを知り尽くしたと豪語する、
ぼくの傲慢な頭を引き連れて歩かなければならない。
そのとき、ぼくの前では世界は空虚な広がりに過ぎなくなるだろう。
また、冬の気団のように、広大な自然の営みの中に逃れることもできそうにない。
自然よ、たとえお前が、緑の光とともに豊饒に、
また、荒涼とした涸れ地と共に非情にぼくを迎え入れても、
お前を否定する人々の思想が、
ぼくの頭の中で、侵略者のように荒らしまわり、
お前を犯し引き裂きばらばらにする。
無力さに怯えているぼくにかまいなく。
そのとき、ぼくの前で世界は廃墟となるだろう。
ああ、過剰な光、過剰な花びら、過剰な人々。
破局の予感。
残照のような意志。
反逆も涸れ、僕はここで陽炎のように生きなければならない。
壁画ように
バッファローはたたずむ
象やサルのように愛嬌を振りまかないから
見るものはいない
ぼくは独りたたずむ、彼のように
ぼくは思い浮かべる
この狭い囲繞地の荒れた泥土から
そのこぶのように盛り上がった肩の筋肉から
人知れず狂ったように走り出す勇姿を
柵の向こうに広がる静かな大平原を
彼は時を刻むかのようにゆるやかに
壁画を離れ、振り向き、ぼくを見た
獣でも人間でもないかのようにぼくらは見つめあい
残照のような意志を交換する
ぼくたちだけのときは流れ、そして
彼は再びもとの壁画に帰った
たしか瞳は潤んでいた
ぼくはあえてそれを涙と見る
・・・・・・・・・・・・・・
第四悲歌
ベッドに横たわる老人の顔に
青黒く浮かび出た死の影
それに気づかず
笑いかけようとする痛ましさ
のがれがたく
とどまることもなく
死はにくたいの内から
与えられた生理に逆らうことなく
美しくなりすぎた女たち
太陽はそのやわらかい肌を貫き
ゆれる影まで明るくする
透けるスカートは風をはらみ
ストッキング色の太ももがはだける
隠されていた秘部は暴かれ
無邪気すぎて
光と戯れ
風と戯れ
恍惚と
生は肉体の内から
精神病院の裏庭にたむろする
白っぽい服を着た人々の群れ
その眼は
いつも鏡の中に見る目と同じ
太陽は急速に傾き
毛細血管のように枝を広げた巨木の中を
風はあわただしく通り過ぎる
日々のねたみと苦痛を人々から取り去り
穏やかな明日を予告するかのように
町を夕陽色に染めながら
ゆるやかに沈む秋の太陽
その母に連れ去られる子供たち
ブランコは最後の軋みを
だが、なぜかいたたまれなく
狂おしく
新たな悔恨が生まれ
地平線の向こうで祈りが燃え尽きる
そして
星の見えない黒い空と
枯れた街路樹と
水銀灯を反射する夜の車道
冷たく
よそよそしく
よりどころもなく
うちのめされて
うちのめされて、祈りも
願いも、想いも消えうせ
おのれの頭脳をせせら笑いながら
愚かしく、気まぐれに
投げやりがあろうとするのに
なぜあなたは
悲しい目をしてわたしを見る
なにをそんなに恐れるのか
不安は瞳の奥に沈めてほしい
なぜあなたは
自分のむなしさを打ち明ける
それも、わたしだけに
黙って、寄り添い
抱き合うこともできるのに
それにしても
なぜ
わたしだけが、、、、
・・・・・・・・・・・・・・
第五悲歌
もう夜中
命あるものを焼き尽くそうとしていた
白昼の容赦ない日差しも
今は冷たい雫となり軒下の草の葉に帰り
虫たちの腹を湿らす月は七月の厚い雲に隠れ
泥酔者もいなくなった裏通りは
どぶくさい夜気につつまれる聞こえてくる
あっちの家からこっちの家から
聞こえてくるつつましく愛し合い
さびしい夢を見ているものたちの寝息が
誰にも知られず互いに聞くこともない
長い長い一日だった今日の最後の吐息が
明日は日曜日だから
みんなで町に出かけ
テーブルを囲んで食事をし
デパートの屋上で夕暮れまで遊びましょう
いったいなぜ人々は
家並みをなして生きているのか
路上照らす水銀灯よりもさびしい家並み
気づかれないように過ぎ去った一日を
重いまぶたの裏に映しながらさびしい夢を見ているものたちよ
わたしの足音が聞こえるだろうか
人々への愛を見出せない不眠の足音が
わたしにはあなたたちの嘆息にも似た寝息が聞こえてくる
夏の夜空に星が流れても あなたたちからは見えない
・・・・・・・・・・・・・・
第六悲歌
こんなに静かだから
ほら聞こえるだろう
遠く走る電車の音が
それに虫たちの鳴き声や 風にゆれる街路樹のざわめきが
かすかにかすかに
もしかしたらここは二人だけの森の中かも
遠のいた雷光に驚きの声をあげるなんて
それもわたしに聞こえるように 冷たい雨が降り続いた今日
どこへもいきたくなかったから
部屋の中で花模様の傘を広げ
その下で昼寝をしていたよ
こんなにも静かだからわたしはひとつの個体に帰れそうだ
そして切り離されていた首と手足を取り戻し
人間の形となってあなたを愛することができる
今日の雷雨で夏が終わると良いね
もう夏の町には出かけたくないから
そして気づかれぬように
静かに静かに秋が来ると良いね
・・・・・・・・・・・・・・
第七悲歌
わたしたちが出会うまで、
わたしたちは激流に飲み込まれた枯葉のように、
どこからともなく現れてはどこへともなく消えていくような、
群集の単なる構成員に過ぎなかった。
そしてわたしたちは限りない誤解と独善と虚栄のなかで、
不安と不信と不快さをひたかくしにしながら、
挨拶を交わし流星のように近づき交差した。
そのときわたしは頭に描いていた世界が壊れてしまっていたのを感じていた。
でもあなたはもともと壊れれてしまうような世界など持っていなかった。
だからわたしたちは、絶望の泥沼に沈み込んでいても良いはずであった。
ところがわたしたちは、
原始の森のような静けさと安らぎに包まれて生きようとする、
かすかな生命を感じ始めていた。
たしかに、わたしたちは、
森に住むあらゆる生き物のように、
壊れやすく傷つきやすく、
うち捨てられた幼い兄妹のような、
無力で寄る辺ない二つの肉体に過ぎなかった。
しかし、わたしたちは、
その原始の森のような静けさと安らぎのなかで、
欲望の場は欲望の場でなくなっていることに、
そして、わたしたちは生命の意味を取り違えていたことに気づきはじめていた。
そして、それまで美しいと思っていたものが美しいものでなくなり、
大切なものと思っていたものが大切なものでなくなり、
役に立つと思っていたものが役に立たないものであることに気づき始めていた。
そして、わたしたちは、
むくげの花びらのように心を開き、
なにか新しいものを感じ取ろうとしていた。
もしかしたら、わたしたちは永遠に近づいていたのかもしれない。
その入りロを垣間見ていたのかもしれない。
その夢のような永遠の。
後で懐かしいと思い返せるような永遠の。
何故なら、その後のわたしは、
あの時崩壊してしまったと思われていた騒々しい世界が再びよみがえり、
相変わらず群集の人以外の何者にもなっていないからである。
幼いころに離れ離れになった本当の妹のような親しみをこめて、あなたは出会ったばかりのわたしに話し掛けた。
あなたには、わたしはそんなに愛情に飢えた捨て猫のように見えたのだろうか。
たしかに、そのときのわたしは、それまでなんの気兼ねなく帰ることができた故郷を失いかけていたのだが。
そして、あなたは、決して人間の目に触れることなく枯れていく名もない花のような笑みを浮かべて、わたしを慰めようさした。
あなたには、わたしが、そんなに夢を失った寂しそうな人間に見えたのだろうか。
たしかに、わたしは、そのとき一日中群衆の中を歩いてきていて、もう夕陽のことしか思い返せなかったからだ。
そして、あなたは、世界が美しく描かれた壁紙がはがれようとするのを必死でおさえながら、わたしを励まそうとした。
あなたには、わたしは、そんなに絶望にうちひしがれているように見えたのだろうか。
たしかに、わたしは、そのとき欲望と共に世界が崩壊していったということに気づいていたのだが。
それよりも、あなたはなぜわたしのことが判ったのだろうか。
あなたにとって少し前まではビルの外壁にように冷たい他人であったわたしのことが。
町の華やかな灯りや無数の男たちの欲望をブラックホールのように吸い込んでしまうあなたに。
汚辱や侮辱や無視やニヤニヤ笑いにさらされ続けているあなたに。
下品や貧相さや軽薄さや卑屈さよりも、無関心や無表情や冷たさや傲慢さを嫌うあなたに。
なぜ、わたしのことが判ったのだろう。
それとも、あなたとわたしはとこか似ている所があったのだろうか。
あなたは見捨てられた犬のように、自分に許された生存の場所を、全身の触覚で探り当てるようにして生きてきた。
そして、わたしは、無謀にも過去を断ち切り、今と少し先を見つめながら、自分に合う生存の場所を求めて生きてきた。
その意味でわたしたちは似ている所があったかもしれない。
また、あなたは、自分の未来が輝かしいものであることを、かたく信じているかのように振舞おうとしていた。
そして、わたしは、未来というものに対して、ひそかに疑いを持ち始めていた。
その意味でわたしたちは似ている所があったかもしれない。
また、あなたは自分の夢を語ろうと知るとき、挫折の影におびえているようであった。
そして、わたしは、人間には挫折以外の道が残されているのだろうかと感じ始めていた。
その意味でわたしたちは似ている所があったかもしれない。
また、あなたは、社会の決まりごとや約束事をそれほど気にかけているようではなかった。
そして、わたしは、それらを超えようとずっと思い続けていた。
その意味でわたしたちは似ている所があったかもしれない。
また、あなたは、臆病でか弱い草食動物のように、つねに不意の死にさらされていた。
そして、わたしは、つねに不意の死を受け入れようとしていた。
その意味でわたしたちは似ている所があったかもしれない。
また、あなたは野生動物のような本能で、言葉巧みなものを恐れ警戒していた。
そして、わたしは、思考が暴走するものであるということに気づき始めていた。
その意味でわたしたちは似ている所があったかもしれない。
また、あなたは、我が物顔に振舞うものに対して、どうしようもないことのように無言であきらめのまなざしを投げかけるだけだった。
そして、わたしは、考えを押し付けるものに対しては激しく抵抗し嫌悪しながらも、最後はその場から逃げるようにして離れ孤独を深めるだけだった。
その意味でわたしたちは似ている所があったかもしれない。
また、あなたは、欲望の行為になれすぎていて、欲望の微妙な価値を理解できなくなっていた。
そして、わたしは、欲望の対象に近づき過ぎたために、欲望の本当の姿が見えなくなっていた。
その意味でわたしたちは似ている所があったかもしれない。
また、あなたは、肉体と心のあいだには無限の隔たりがあると思っていた。
そして、わたしは、行為と思考のあいだには無限の隔たりがあることに気づき始めていた。
その意味でわたしたちは似ている所があったかもしれない。
また、あなたは、目立たぬように人々の外にいながら、ひそかに人々の中に入ることを願っていた。
そして、わたしは、目立たぬように人々の中にいながら。
できるだけ人々から遠ざかろうとひそかに思っていた。
その意味でわたしたちは似ている所があったかもしれない。
また、あなたは、正直言ってわたしの未来を思い描くことはできないでいるようであった。
そして、わたしも、正直言ってあなたの未来を思い描くことはできなかった。
その意味でわたしたちは似ている所があったのかもしれない。
そして、わたしたちは、お互いに、子供のころに思い描いていた将来の夢を語った。
できるなら触れられたくない、つらく悲しい思い出を話すかのように。
その意味でわたしたちは似ている所があったかもしれない。
さらに、わたしたちは、お互いの心の奥底に、どんなに親しくてもいえない様な本源的な羞恥心を隠していた。
その意味でわたしたちは双子のように似ていたのかもしれない。