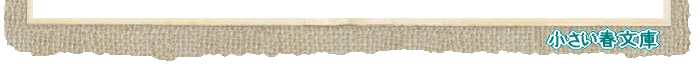1980年代作
やがて夕暮れが(2部)
はだい悠
* * * * * * * * * * * * *
二十二歳になっていたとはいえ、知子はさいしょ戸惑った。
自分の一生のことと思うと胸がときめいた。しかし自分の年齢
のことを思うと、つい人より遅れているような気がして、素直
な気持ちになれず、なかなか打ち解けなかった。だが、そのう
ちに楽観的な姿勢に押されてか、自分でも愚かしいと思うほど
少女のように浮かれていった。 だが、そういう気持ちも長く
は続かなかった。回を重ねて付き合っていくうちに、何かちぐ
はぐなものを感じるようになっていった。そして、退屈さを感
じて、楽しそうに振舞おうとしたり、良夫の話しに意識的にあ
わせようとしたり、また、人前では仲良さそうに振舞おうとし
たりする自分に気づいていた。男と女とはもともとこういうも
のであるのか、それとも自分が交際前に現実離れした夢を見て
いたのか、知子にはわからなかった。だがその一方で、同僚た
ちとの会話に余裕ができたり、自分が話題の中心になったりし
て楽しい思いもした。そして派手な車で乗り付ける良夫を、同
僚たちにさりげなく自慢したりして、良夫を頼もしく感じるこ
ともあった。しかしそれでも他人の噂話に夢中になっていたと
きのような甘美な思いには程遠かった。良夫と二人っきりでド
ライブしたり食事をしたりしても、それほど充実した気分には
なれなかった。そして独りになって冷静に考えるとき、良夫と
の付き合いがなぜか煩わしいとさえ思うこともあった。そのう
ちに、つまらないことに意地を張り合って、後々までしこりを
残す口喧嘩などをするようになった。知子は、良夫が他の人と
比べて特別に性格が変っているとか、自分たちはそれほど不釣
合いなカップルだとは思えなかった。でも?誘うなるのか、知
子にはわからなかった。ただ知子の数少ない体験から、交際と
言うものはこういうものだと思わざるを得なかった。そして知
子は、今日まで、ただなんとなく付き合うようになっていた。
雨は容赦なく大地に降り注いでいた。
夕闇のなか路上には車の形をしたよそよそしい沈黙が溢れて
いた。たとえ車内がどんなに親密な雰囲気に溢れていようとも
外から見たらそれは冷たくよそよそしい車の形をした鉄の固ま
りに過ぎないからだ。
良夫はいつものように車を自分の手足のように走らせた。後
続の車のライトがかすむほど水しぶきを上げて走っていた。
良夫は知子の表情にこだわっていた。知子の浮かべている笑
みが自分のためではないような気がしていたからだ。わざとら
しいものに思われ気に入らなかった。良夫は、知子から先に話
しかけるべきだと思い、自分から話しかける気がしなかった。
先ほどから前を走っている車が遅いので良夫はいらだった。良
夫は乱暴にハンドルをきるとスピードをさらに上げて追い抜き
に掛かった。「危ない」と知子は良夫の鼻筋の通った横顔を一
瞬覗き込みながら呟くように言った。良夫の車は対向車と衝突
しそうになりながら前の車を追い抜いた。
「のろのろと走りやがって、へたくそめ」
と良夫は罵るように言った。車に乗っているときの良夫は人が
変ったように性格が荒くなることは知子は判っていた。親密な
雰囲気が急速に息苦しいものに変っていった。知子は今日もま
た、わだかまりを残したまま別れなければならないのかと思う
と、気持ちが沈んだ。そしてふと付き合い始めたころの出来事
を頭に思い浮かべた。
それは付き合い始めてから二ヵ月後のことだった。車で食事
に言ったとき良夫は酒を飲んだ。知子は心配したが、良夫は女
の心配することではないと言わんばかりに相手にしなかった。
知子は反面そんな良夫を頼もしいものと感じた。良夫は酒を飲
んでいても運転にたしかだった。自分の運転に酔いしれるよう
にスピードを上げて他の車をせせら笑うように追い抜いては得
意になっていた。そのときの良夫の表情は誇らしげで自信に満
ちていた。だが知子の心配どおり、車が警察の検問に引っかか
ってしまった。酒を飲んでいたせいもあって良夫は最初たかが
警察と強気な姿勢を知子に見せていたが、取調べが長くなると
、猫に捕らえられたねずみのようにだらしくなくってしまった
。そのうちに観念したのか酔っ払いざまを全身に表し、もう誇
らしげな表情も自信も消えうせてしまっていた。知子は何か騙
されたみたいで腹立たしかった。だが良夫は自分の弁解に精い
っぱいで知子のことは忘れているようであった。知子は良夫を
頼もしく感じた自分を情けなく思った。知子はこのままひとり
で帰りたかった。そしてそんな良夫にこれからも付き合わなけ
ればならないのかと思うと不安になった。
結局、知子は良夫と別れることを硬く決意して、寂しい気持
ちのままひとりで帰った。
だが数日後、良夫が何事もなかったかのように知子の前に現
れた。知子は良夫の熱意にほだされた。そして過ぎ去ったこと
は忘れることにして再び付き合うようになった。
知子は良夫の表情の硬さを感じながら、先程までの様な親密
な雰囲気を取り戻したいと思った。西の空が明るくなって来て
いた。雨が小降りになっているのに知子は気づいた。知子は弾
んだ声で言った。
「ねえ、見て、明るくなってきた。もうじき晴れるわ」
良夫が不機嫌そうな顔で言った。
「晴れたからって、どうってことないだろう。車に乗ってんだ
から」
「それは、そうだけど」
と知子は思わず答えた。気まずい沈黙が続いた。
外は急速に暗くなっていった。気を取り戻すと知子は笑みを
浮かべて言った。
「ねえ、今日はどこかへ連れて行ってくれるの?」
「どこへも行かないよ。家に送るだけだよ」
三十分後、良夫の車は知子の家に通じる路地前に止まった。
知子は良夫にお礼を言って車から降りた。雨はすっかり止んで
いた。夕闇に走り去る良夫の車を見送っていると、知子は声を
掛けられた。
「いいわね。今お帰りなの?」
見ると隣家の小母さんだった。知子は恥ずかしそうに笑みを浮
かべすれ違いながら挨拶をした。知子は妙にうきうきとした気
分になった。だが、家に向かって歩いているうちにそんな気分
も急速に醒めていった。知子は路面に反射する街灯の光りをい
つもより強く感じながら、木の香りのする板塀に挟まれた路地
を通り抜けた。そして電気のついた居間に眼をやりながら薄暗
い玄関の戸を開けた。
それから三日後。朝から暑い日差しの午前。マサオは冷房の
効いた部屋で仕事をしていた。そのうちにふとまだ冷静さを保
っている頭に外の様子が気にかかった。マサオは仕事の手を休
めて窓の外の風景に眼を向けた。ビルの屋上越しに、よく晴れ
渡った空の所々に穏かな雲を浮かべているのが見えた。ぼんや
りと眺めているうちにマサオの頭に正体不明の思い出が浮かん
できそうになった。だが、自分のところに上司のが近づいてく
るのを感じて再び仕事に取り掛かった。
上司の話は、ある場所まで至急手荷物を届けてくれと言うこ
とだった。
マサオが外に出られることを楽しみに思いながら外出の準備
をしていると、牧本が近づいて来て言った。
「どこへ行くの?」
「出張です」
マサオは楽しそうにそう答えながら足元あった手荷物をぶら下
げて見せた。すると牧本が納得しかねる表情をしながら小声で
言った。
「アッ、それっ、でもそれは君が持っていく必要はないんだよ
」
「どうしてですか?」
「上のほうミスなんだから、そんなものはほっとけばいいんだ
よ。間違えた奴が持っていけばいいんだよ。」
と不愉快そうに言う牧本を見ながらマサオは戸惑った。間違え
た奴とはマサオの上司を意味していた。だが、いまさら牧本に
そういわれてもどうしようもなかった。
「でも命令ですから。それに誰かが持っていかなければならな
いですから、、、、」
「まっ、良いか。君も素直なんだね。ところで場所は知ってい
るの?」
「はい」
マサオは日頃から上の人たちの人間関係には自分は関係がない
と思っていた。自分はただ命令どおりに動けばいいと思ってい
た。だが、いずれ自分がそういう人間関係に巻き込まれ泣けれ
がならないと思うと暗い気持ちになった。
マサオは開放されたように外に出た。
会社を出て二時間後、マサオは初めての駅に着いた。駅を出
ると強い陽射しと熱気がマサオの全身を襲った。
マサオはまぶしそうに眼を細めて、地図を見ながら見知らぬ町
を歩き始めた。ときおり風が吹いたが熱風を吹き付けるだけだ
った。まもなく全身から汗が吹き出た。二十分後マサオはよう
やく目的の場所を探し当てた。
そこはマサオの会社の十分の一ぐらいの小さな工場であった
。開けっ放しのドアから黙々と働いている十人ほどの労働者の
姿が見えた。
マサオは冷房によく効いた二階の部屋に通された。マサオは
だらしなく椅子に腰をかけると顔の汗を拭きながら出された麦
茶を飲んだ。まもなく部長と呼ばれる丸顔の誠実そうな中年男
が現れた。男はわざわざやって来たマサオに対してねぎらうか
のように丁寧に挨拶をした。ただ荷物を届けるだけだと思って
いたマサオはすこし戸惑いながら曖昧な笑みを浮かべて挨拶を
返した。
荷物の受け渡しが終わるとその男は、マサオの向かいに座り
商談するかのような礼儀正しさで、荷物の中身や自分の会社の
業績などについて話し始めた。
マサオははっきり言って荷物の中身を知らなかったし、それ
に企業の業績などについて世間話をするほど知識も経験もなか
ったので少し困惑した。そこで曖昧な返事をしては適当に話し
をあわせた。だが内心はとても辛かった。部長とまで呼ばれる
中年男が、いくら商売のためとはいえ、自分よりははるかに年
下のものに真剣にしかも低姿勢で接してくれているのに、それ
に対してマサオは、先程から曖昧な返事ばかりして、自分がい
い加減な態度で臨んでいるような気がして、恥ずかしさを覚え
たからだった。マサオは弱者の取らざるを得ない習慣を思うと
いたたまれない気持ちになった。
マサオは電車の時間がないと嘘を言って、逃げ出すように外
に出た。
その後マサオはまっすぐに会社に帰らず、繁華街に出てをぶ
らぶらしたりして時間をつぶした。そして時間のつじつまを合
わせるかのように四時過ぎに会社に戻った。
退社時間になった。マサオは知子の帰る姿を見て後を追うよ
うに部屋を出た。
そして会社の正門のところで待ち合わせていたかのように二
人は近づいた。
今日の午後マサオが出張から帰ってきて、仕事も手につかな
くぼんやりしていると、知子が近づいてきて小声で話しかけた
。それは今度ある女性を紹介するからぜひ会ってくれというこ
とであった。先日マサオがいい人いたら紹介してよとほんの冗
談で言ったつまりだったが、まさか知子が本気にするとは思っ
ていなかった。マサオは知子があまりにも真剣な表情で話すの
でうろたえた。そして今は仕事中だから詳しくは帰りに話そう
と言うことにしたのだった。
知子と並んで歩いていたが、マサオはなんと切り出してよい
か判らなかった。知子がマサオのほうを見ながら先に言った。
「今日は、朝から居なかったみたいね?」
「いや、十時ころかな?」
そう答えながらマサオはこのまま知子がさっきの話しのことを
忘れてくれることを願った。
知子が落ち着いた口調で話しかけた。
「ところでさっきの話しの続きなんだけど、今度会ってくれる
?」
「そのことなんだが、、、、」
マサオは考え込むかのような仕草をしながらそう言いかけたが
、それ以上続かなかった。知子の真剣な表情を見ていると、い
まさらあれは冗談だったよなどとは、とても言えそうになかっ
たからだ。マサオは困った。どうして知子は本気にしてしまっ
たんだろうと考えた。知子を話を続けた。
「私といっしょに学校に行っている人なんだけど、、、、」
マサオは黙って前を向いたまま、でも心なしか早足になってい
た。そして知子の方を振り返るように見ながら思い切って言っ
た。
「その話しのことなんだけど、、、なかったことにしてくれる
、、、、」
「なかったことって」
知子は住んだ眼でマサオを見ながらそう言った。マサオはその
視線を避けるようにして前を見ると、途切れ途切れに話し続け
た。
「うーん、なんていうのかなあ、、、あれは冗談なの、、、ち
ょっとした言葉の弾みって言うか、、、」
「冗談?」
知子のその声は呟くように小さかった。
マサオはそれ以上何もいわなくなった知子を見て、何かとん
でもなく悪いことをしたなという気持ちになった。知子の素直
そうな性格を思うとなおさらだった。
そのとき知子が急に声を弾ませて言った。
「すると、やっぱりこういうこと、他に好きな人が居るとか、
もう心に決めた人が居るとか、、、」
「いや、そういうことじゃなくって、なんていうのかな?」
そう言うマサオの困惑した表情を盗み見るようにしながら知子
はさらに話し掛ける。
「私が紹介する人だからなの?」
「いや、そんなことはない」
とマサオはとっさに否定した。それは知子に決して思わせても
言わせてもならない言葉だった。
マサオは辛かった。マサオは冗談の弁解に努めた。
「よく人が言うでしょう。話を楽しくするために言う冗談。僕
も調子に乗ってつい言ったんだけど、僕は冗談が下手なのかな
あ、、、、、」
とマサオは苦笑いを浮かべながら自分に語りかけるように言っ
た。だが知子は感情を隠しているかのように少しも表情を変え
なかった。マサオはその冷静な表情が気になった。そしてマサ
オはあれは冗談であることを知子に理解させることはもう不可
能に近い気がした。
「もう、その人には話してあるの?」
「ええ、、、、」
「それじゃ悪いことしたね」
「良い人なのよ」
と知子は少し残念そうに言った。マサオは《あなたの友達なら
良い人に決まっているさ》と言おうと思ったが言葉にならなか
った。二人はしばらく黙って歩いた。
「ねえ、もう少しゆっくり歩かない?」
と知子は笑みを浮かべて話しかけた。マサオはその表情を見て
ほっとした。そしてゆっくり歩き始めた。二人はやや賑やかな
通りに出た。
「今日は出張だったんですか。大変ね」
「それほどでもないけどね。会社に居るときよりも気軽でいい
よ」
「マサオさんは、会社でよくやっているみたいね」
「そう見える?、ほんとうのこと言うとどうもうまく行かない
んだ、ずるやすみでもしたいよ。もしかしたら僕にはあわない
のかも」
「そんなことないわよ」
と知子は少し表情を曇らせて言った。
「きみこそよくやっているじゃない。まじめなんだね」
「そんなことないわよ。わたしこれでも入ったころ会社わずる
休みしたことあるのよ。会社に来るのがイヤでイヤでたまらな
くてね」
と知子は子供のような無邪気さで言った。
「えっ、君にもそんなことあったの?」
そういいながらマサオは知子を見ると、知子は少し恥ずかしそ
うな笑みを浮かべた。
「ところで、さっきの話し、ほんとうになかったことにして良
いの?」
「うん、良いよ。どうもおかしいな?」
「なにが?」
「やっぱりあれなのかな、自分たちがうまく行っていると、他
人の世話をしたがるもんなのかな? 女の人って」
そういいながらマサオは知子のほう見ると、知子は少し表情を
曇らせて見返した。だがすぐに先ほどのような穏かな表情に戻
った。それを見てなんとなくほっとしたマサオは少しニヤニヤ
しながら言った。
「ところでその人美人?」
「ええ、そうよ」
「惜しいことしたかな?
「ほんと、すぐニヤける人だ」
「えっ!」
といいながらマサオは知子を見ると、知子を下を向いて笑いを
こらえていた。
「そう言われても、もともとこういう顔だからね、しょうがな
いよ」
マサオは、知子とならこのままなんでも気軽に話せそうな気
がした。
駅が近くなった。人ごみの中をしばらく歩いたあと二人は判
れた。
翌朝、マサオは重苦しい気分のまま目覚めた。
それは暑く寝苦しい昨夜のせいだけではなさそうであった。
何か恐ろしい夢の余韻を引きずっているような気持ちだった。
だがその夢がどんなものであったのか、マサオの覚めた頭には
何も残っていなかった。マサオは体を動かすのも億劫な気持ち
だった。そしてマサオは、これから電車に乗り、人ごみにもま
れながら会社に行く自分の姿を思い浮かべた。すると急に外の
世界が自分を脅かすもののように感じられた。マサオは憂鬱な
気分になった。どこにも行きたくない、会社を休みたいと思っ
た。だが、そのようにはっきりと自覚された事柄は、マサオの
性格上実行できなかった。病気なら休む正当な理由になりえた
が、そのような理由は自分から逃げるようにしか思われなかっ
たからである。ましてやその程度で休むということは、最近自
分の内部に芽生えてきた《敗北者》という言葉通りに自分がな
るように思われたからである。
天気の良さそうな外の気配に眼を配り、マサオは自分を励ま
すように起き上がり、水道の水で顔を洗った。そしてタオルで
顔を拭き終わると大きくため息をすると、ふと頭の中を《訳も
なく怯えている子供の姿》がかすめた。だが、朝のあわただし
さのなかではそれっきり二度と現れなかった。マサオはそのこ
とを忘れてしまったかのようにいつも通りに外に出た。
マサオの一日は上司の朝礼を聞くことから始まる。だが最近
のマサオは、毎日同じような内容に飽き飽きしたせいか、それ
が煩わしいものに思えてきてほとんど関心を示さなくなってい
た。
午前中のマサオは、まだ頭もすっきりし精神状態も安定して
いた。そしてただ自分を習慣に従わせながら他の同僚たちのよ
うに落ち着いて仕事が出来るのであった。しかし、昼休みも過
ぎ、午後もだんだん深まってくると、いろいろな疲労が重なっ
てくるせいか、マサオの精神状態が乱れてくる。頭がボォッし
てきて、自分がやっていることと無関係なことを考えるように
なっていた。それは自分の意志からではなく、外部からの強制
のように、自然と頭の中にいろいろな考えが浮かんでくるので
あった。
そうした不安定な精神状態の中で、自分が毎日のようにやっ
ていることに疑問を持ち始めた。自分は組織という大きな塊の
なかの一員であることは漠然とではあるが判っていた。そして
自分の果たしている役割もあるていどは判っていた。しかし、
自分が、どんな目的、どんな成果のためにやっているのか、そ
の具体的イメージがつかめなかった。いったい何のために働い
ているのか? それは食うためであると、これまでのように単
純に結論を出してもよかったのだが、不満足であった。ハッキ
リしなかった。これから自分がどうなるのであろうか? その
未来の明確な自分の姿が見えなかった。ただこのまま行けば上
司や先輩たちのようになると思われたが、それは自分が思い描
く未来像とはどこか違うように思われた。それに自分には上に
立って人を使うということは似合わないように思われた。しか
し、組織内では、上に立つか、下で従うか、二つに一つしかな
いように思われた。どちらにせよ、定年まで続きそうなそのよ
うな人間関係は息苦しいものに感じられた。そして、それが組
織に所属する人間の究極の目標であるなら、それはただそれだ
けのことであり、そんな自分たちは狭い場所で動きまわるアリ
のような存在に思われた。マサオは朝礼のわざとらしさを思っ
た。《なるほど、今の自分の様に目的を失っているときにあの
押し付けがましい言葉が役に立っているのか》とマサオは思っ
た。だがマサオはそんな言葉や考え方を信じるきにはなれなか
った。子供だましのこじつけのように思われた。
僚たちは終日変わりなくやっている。午後になると多少顔を
紅潮させるものもいるが、自分のように精神的混乱には陥って
はいないようである。まれには午後になるとかえって楽しそう
にしながら張り切るものもいた。マサオはそういう人間を見る
とますます気分が滅入ってくるのである。結局なんの結論も得
ることなく、捕われた精神状態のままその日の仕事を終えるの
である。
勤務終了後、マサオは軽い頭痛を覚えながらトイレに入った
。そして手を洗いながら鏡にうつる自分の顔に眼を向けた。た
るんだ皮膚に落ち着きのない眼、そして意志の失われたような
まとまりのない表情を見てマサオは醜いと思った。そこへ顔を
紅潮させた牧本が入ってきた。マサオは知らん振りして出よう
としたが、牧本のまだ余力を残した声で呼び止められた。それ
は《ちょっと話しがあるから今晩付き合わないか》というもの
であった。マサオはトイレのドアのところに立ったまま牧本の
自信に満ちた視線を窮屈に感じながら、少し考える振りをした
あと、承諾した。マサオはできることなら断りたかった。それ
はいつものように飲んで騒いでそれで終わるだけだろうと思っ
たからである。だがマサオは《ちょっと話しがある》というの
が気になった。それにこれといって断るような特別の理由が見
つからなかったので付き合うことにしたのだった。
二人は街の繁華街を歩いていた。マサオにとってうんざりす
る雑踏も牧本には楽しいらしく、牧本は軽快な足取りで人ごみ
をうまくかわしながら歩いていた。マサオはやや不自由さを感
じながらも牧本の後からついていった。歩きながらマサオは、
牧本の話しはなんだろうと思うと気が滅入った。
まだ暮れ切れない空の下に、町はさまざまな人たちで溢れ活
気に満ちていた。人はミナ閉じこもった笑顔や陽気な動作に仕
事を終えた開放感に現していた。マサオにはそれが生き生きと
したものに見え、少し気後れを感じた。
牧本の顔からは完全に疲労の色は消え、快楽を求める陽気な
表情に変っていた。歩きながらマサオはショーウィンドーにう
つる自分の顔を見た。相変わらずおどおどとしている自分の顔
を見てますます気分が滅入った。そして人々の満足げな表情に
嫉妬を覚えた。自分だけがのけ者にされているような気分に襲
われ、、衝動的にいらだった。そしてマサオは陽気さ装いなが
ら牧本に話しかけた。
「話しってなんですか?」
牧本は忘れていたのか思い出したように話し始めた。
「アッ、あのこと。今日係長と話していてね、君の事が出たん
だよ。彼も意外とぼんやりしているところがあるからっていう
、話しだったんだよ」
マサオは牧本のそのもったいぶった言い方が気になった。マサ
オは不満げに言った。
「それで、どうなんですか?」
「仕事にミスがあるんだって」
「ミス? どんなミスですか?」
「そこまでは聞かなかったが、、、気にすることはないよ、誰
にも苦手なことはあるんだから」
マサオはひどく気になった。どうして直接言わないのだろうか
と思った。無言になったマサオを見て牧本は慰めるように言っ
た。
「気にすることはないって、あの係長は自分のことは棚に上げ
て、部下の失敗は平気で責めるんだから、あれじゃ誰もついて
いかないよ。どうしようもないよ。そんなことより今日は久し
ぶりに飲もうや!」
そう言い終ると牧本は何事もなかったかのように再び陽気な表
情に戻っていた。だが、マサオの気分は晴れなかった。日頃の
牧本と係長の関係からして牧本のそのような気分の変わりよう
に疑問を抱いたからである。牧本のその度を越した陽気さも、
その背後には性格の二面性があると思うと、いまいましいもの
に感じられた。そして、自分を取り囲む世界が曖昧でつかみど
ころのないようなものに感じられた。マサオは眼に見えない何
かに向かって敵意を覚えた。牧本は嬉しそうな顔をしてここが
良いといって飲み屋に入った。
牧本はマサオの三年先輩である。二年前に結婚していた。社
内では仕事への積極性が買われて有能な人物の一人として通っ
ていた。斉木も仕事への積極性という点では、目立っていたが
、気まぐれな性格から来る一貫性のなさがほとんどの同僚から
の信頼が薄く、牧本よりは評価は低かった。他人に与える印象
面からいって、牧本とマサオは正反対の性格といってよかった
。だが、能力と評判に裏付けられた牧本と自信に溢れた態度は
、マサオの眼にはときおり傲慢と映るときがあった。牧本は斉
木のように自分とはまったく相容れない人物ではなかったが、
それでもマサオにとっては理解しがたい人間であった。
店内で二人はカウンターに並んで座った。酔うと愚痴っぽく
なる斉木と違い、牧本は終始陽気だった。そして飲めば必ず仕
事や女の話をすると決まっていたのだが、牧本はマサオとは、
仕事の話しをしても始まらないといって風で、仕事の話をしよ
うとはしなかった。二人にとって仕事の話は共通の話題にはな
りえなかった。その変り、牧本はよく女子社員の話をした。マ
サオも興味があったが、牧本の場合は噂話の域を出ないもので
、しかも、自分の勝手な解釈によって面白おかしく話すのでマ
サオにとっては聞きづらいものであった。そして話せば話すほ
ど牧本の自己中心的な性格が鼻につくようになり、だんだん興
味も失われていくのである。それでも知子の話しが出なかった
ことはマサオにとって救われる思いであった。
はっきり言って眼の前の牧本が、仕事以外のことで、いつも
何を考えいてるのは判らなかった。マサオは今まで牧本と飲ん
でもうちとけた気分になったことはなかった。何年も同じ会社
で仕事をしていて、たまにいっしょに飲むようなあいだがらで
あるのに、話しをしても何の共感がすることがないというのは
寂しいことである。
二人はお互いにぎこちなかった。きっと牧本も同じ気持ちで
あろうと思った。牧本は隣の客が歌を歌い終わると盛んに拍手
をしては、今度は自分の番だとばかりにマイクを握ると、気持
ち良さそうに歌い始めた。酔いしれるように歌う牧本を見なが
らマサオは独りでいるような気分になった。マサオにとっては
異様な光景であった。到底真似できないことであった。牧本に
とってマサオも見知らぬ客も同じようであった。マサオは自分
が付き合うほどのことではないと思うと腹立たしくなった。二
時間ほどで二人は店を出た。二人は再び夜の雑踏のなかを歩き
だした。牧本は宵を全身に現し我が物顔に通りを歩いた。そん
な上機嫌の牧本を見てマサオは反感を覚え、見苦しいと思った
。牧本はまだ遊び足らないといった風に落ち着きなく周囲を見
まわしながら歩いた。マサオは酔いは感じていたがしらけきっ
た気分だった。体がだるく早く帰って休みたいと思っていた。
牧本がマサオに誘いかけるように言った。
「これからもう一軒行こうか?」
「もう帰りましょう」
とマサオは突き放すように言った。牧本は急に子供のような不
機嫌な表情になって言った。
「付き合いが悪いな! たまに飲んだときぐらいは大いに楽し
もうよ。もう一軒行こうよ」
「もう止めましょう、どうせ歌を歌うだけでしょうから」
「君も歌えばいいじゃないか、楽しいよ」
「趣味に合わないことはやりたくないですから、それに下手く
そな歌は聞きたくないですから」
「でも楽しいことだから、いいことじゃないの?」
「見ず知らずの人と歌うなんて気持ちが悪いですよ。それに雰
囲気がなんとなくみじめったらしいですよ」
「そんなことないよ、歌ひとつで楽しくやれるなんて、新しい
コミュニケーションの手段なんだよ」
「いや、自己満足ですよ。酒飲んで歌を歌って憂さを晴らすな
んて、新しい等比ですよ。ああ、気持ち悪い」
「そういうことじゃダメだよ」
と牧本は意味ありげに言った。マサオはその言い方に反発を覚
え、くってかかるように言った。
「何がダメなんですか?」
「君にはまだみんなといっしょになって何かをやろうという気
持ちがないんだよ。自分本位なんだな、だから仕事にもそれが
現れるんだよ」
「それは論点のすり替えですね。自分本位なのはあなたですよ
」
とマサオは酔いに任せてはき捨てるように言った。牧本は少し
ちゅうちょしながら投げやりな口調で言い返した。
「そうかな、でもたまには妥協も必要なんじゃないの?」
「そんなの妥協以前の問題ですよ。自己満足に妥協は必要ない
ですね」
すると牧本はややおどけた表情で言った。
「君もなかなか言うじゃないの!」
「言いますよ、ただ普段はそういう話をしないだけですから」
牧本が口調を和らげて言った。
「そう硬いことを言わずにさ、ぼくだって飲みたくもなるさ、
毎日上司にはなんだかんだって言われるしさ、今日だって君の
ことで、僕は君のことをかばってやったんだぜ、、、、、」
マサオは牧本の弱気な態度を見て少し腹立たしくなった。そ
して少し強い口調で言った。
「そういうのがイヤなんですよ。どうして影でコソコソするん
で過、不満があったらはっきり言えばいいじゃないですか」
「そうもいかないんだよ、そのうちに君には判るよ」
「イヤですね、そんなの、それじゃ一生不満のまま終わってし
まうじゃないですか。上か下かではない、もっと別の生き方が
必要なんですよ。そういうものに対抗する別の価値観や考え方
が必要なんですよ。飲んで憂さを晴らしてばかりいないで、他
に何かやることがあるでしょう」
「すごいこと考えているんだね。でも、そういうことを言って
いるようじゃダメだよ。今の世の中通用しないよ」
「あっ、そうですか」
マサオはそう言ったきり黙ってしまった。牧本の逃げ腰の態度
を見ているとこれ以上何を話しても拉致があかないと思った。
二人はお互いの不愉快さを確認するかのように黙って歩いた。
「そうか、君も斉木に逃げられたことがあるのか」
と牧本は独り言のように言った。マサオは聞こえない振りをし
た。
しばらくするともとの陽気な表情にもっだ牧本がある通りを
指差しながら言った。
「こっちへ行こうよ、久しぶりだからなあ」
「そっちは若いもんが集まるところですよ。ただ騒々しいだけ
で何も面白くないですよ」
「いいじゃない、僕たちだってまだ若いんだから、行こうよ」
と牧本は駄々をこねる子供のような表情で言った。
「バカもんになりたけりゃ、自分ひとり行けばでいいでしょう
「すぐムキになる、付き合いが悪いんだから」
二人は引き返すかのように別の道を歩いた。
最初のような元気が失われている牧本を見てマサオは少し言
い過ぎたかなと思った。マサオは穏かな口調で話しかけた。
「そうだね、やっぱり帰った方がいいですよ。奥さんも待って
いることでしょうから」
「奥さん? 誰の? ちくしょう」
と牧本は訳の判らないことを呟きながら歩いた。そして突然「
今日はやるぞ、バンザイ」と大声で叫んだ。
マサオにとって、牧本のそのマサオの存在を忘れたかのよう
な行動は、気味の悪い瞬間であった。マサオは、肌に粘りつく
汗のようにまき本にまとわり着いて牧本を苦しめる得体の知れ
ないものを感じた。
通りには人影が少なかった。
牧本は鼻歌を歌いながら道の真ん中を肩で風を切るようにし
て歩いた。前方から三つの人影が近づいてきた。マサオはその
人影を避けるように道の端を歩いた。だが牧本は避けようとも
せずそのままの姿勢で歩き続けた。すれ違った瞬間向こうから
「気をつけろ」と怒鳴り声が掛かった。牧本は「なんだ」と言
い返しながら相手を睨みつけた。マサオはこれはまずいと思い
ながら牧本の腕を引くようにして歩いた。
「引き下がることはないよ、向こうが悪いんだから。若造に舐
められてたまるか、チンピラめ、いいきになりやがって」
「だって勝ち目はないですよ!」
「負けやしないよ、一人や二人、ぼくは柔道二段だよ」
「三人ですよ」
「二人だろうよ、君が一人相手をするんだから」
「そんな、いやですよ。僕は逃げますからね」
「そうかい、そうかい、俺を見捨てるきかい?」
そんな牧本を見ていると急におかしさを感じた。そして牧本の
話しで初めて共感を覚えたような気がした。マサオは急にいた
ずらっぽい気分になった。そこで、マサオ後ろを振り向き、二
三十メートル離れた三人に向かって「バカやろう、気をつけろ
」と声をおさえて叫んだ。すると三つの人影は立ち止まり、マ
サオたちのほうを振り向いた。マサオは「聞こえた、やばい」
といいながら五歩ほど牧本の前に走り出た。
「逃げることはないよ。やってやろうじゃないか」
と言いながら牧本は振り向いたあと、ゆっくりと前に向き直り
ながら呟くように言った。
「でも三人じゃなあ、やっぱり勝ち目まないか?」
思いがけないことで二人はうちとけた気分になっていった。
会社では見せない牧本の言動に、マサオは初めは嫌悪をいだい
たり腹を立てたりしていたが、それほど自分とは変らない人間
だと思うと、牧本に親しみがわいてきた。そして牧本も自分の
ように得たい知れないものに操られている小さな人間にような
気がしてきた。
その後二人は駅で別れた。
夏も終わりに。
ある日の夕刻。沈みきれない夕日が町をオレンジ色に染めて
いる。
知子は帰りのバスから降りた。涼しくなった風が知子の半そ
でのブラウスを通して汗ばんだ肌に気持ちよかった。知子はい
つもと違う帰り道を歩き出した。意識して別の道を選んだわけ
ではなかった。それは知子のほんの気まぐれと言ってよかった
。知子は《こっちは少し遠回りになるんだわ》と思いながら歩
いた。ときおりビルの切れ目からのぞく夕日をまぶしく感じた
。自分の町の見慣れない風景に知子は、新鮮な印象を覚え、気
持ちが引き締まる思いであった。
坂道があった。知子はやや息を切らしながらその坂道を登っ
た。坂の下は線路が走っていた。上りきったところで目の前に
知子の住む地区の全風景が広がった。小さな家々が六十件ほど
、瓦屋根や色さまざまのトタン屋根を覗かせながら重なり合う
ようにして建っているのが見えた。
知子はゆっくり歩きながら自分の家のある方角に確認するか
のように眼を向けた。自分の家が見えた。赤茶けたトタン屋根
のくすんだ感じの家が、隣の家々に挟まれるかのように、ひっ
そりと建っているのわかった。ちょうど隣の家が新築のために
取り越されているので、自分の家のたたずまいをはっきりと知
ることができた。知子は自分の家の屋根や壁の色が周囲の家々
のそれと違うのに初めて気がついた。《どうして自分の家だけ
が孤立したように屋根は赤く壁は白いのだろう》と不思議な気
がした。そしてしゅういのいえいえのおおくがいがいとあたら
しいたてものにかわっているのにきづいた。
この夕暮れ時に、手に乗りそうな小さな家々が寄り添うよう
に建っているのを見ていると、知子は少し悲しい気分になった
。なぜか惨めなほど狭い場所に自分たちが住んでいるように感
じられた。父母や、そして今はいない祖父母たちの時代からず
っとこんな場所に住んでいるのかと思った。そして無邪気にす
ごしていた子供の頃の自分の姿がふと頭に浮かんできた。
坂を下ってしばらく歩くと、いつもの見慣れた道に合流した
。この道がそうだったのかと思った。
家に通じる路地を歩きながら知子は思った。《いつからかは
判らないが毎日が同じよう、単調な毎日の繰り返し、もしかし
たら死ぬまでこうなのではないだろうか?、若いときのように
何かが起こりそうだと胸をときめかせるようなことは、もうや
ってこないのでないかしら。一生父母たちのようにこんな狭苦
しい場所で細々と終えるのではないか》と。そう思うとかつて
味わったことのないような寂しさを感じた。
路地は長いあいだの風雨でそり曲がり所々に隙間のできた板
塀や、黒ずんだブロック塀にはさまれ、薄暗く、その何間置き
かにさまざまな形の門が構えられていた。そしてそれらの門の
奥には様ざまな家が閉じこもるように建っていて、それぞれの
家のいまや台所から電灯の灯りが漏れていた。ときおり排水溝
に音を立てて汚水が吐き出される。暖かい空気に混じりドブが
かすかに匂った。知子は自分の家の板塀の上からはみ出したよ
く茂った庭木に眼を向けながら門をくぐった。そして陽に焼け
た木の香りを感じながら玄関の戸を開けた。
静かな気配のなかに、奥から母の「お帰り」と言う声が聞こ
えてきた。まだ父たちは帰ってこないらしい。薄暗い玄関で知
子はだるそうに靴を脱いで上がった。居間の灯りを反射する廊
下を通して、なんともいえない湿っぽい匂いを感じた。《そう
だわ、そういえば昨日も一昨日もこうだった。毎日がこんな感
じだったわ》と知子はふと思った。すると急に重苦しい気分に
襲われた。知子は妹といっしょの部屋に入ると、電気をつけず
に汗ばんだスカートとブラウスを脱いだ。
知子は家に帰っても自分のための自由な時間と言うものを持
ってなかった。いつも、家族の食事の準備や後片づけをする母
の手伝いをしながら一日を終えていた。今まで知子はそういう
自分に不満を感じたことはなかった。長いあいだの習慣で当た
り前なことと思っていた。末っ子と言うことでほとんど手伝わ
ない妹や、不規則に帰ってくる父、毎日のように食事の時間に
間に合わない兄たちに煩わされても、知子は母親と同じくらい
に献身的に振舞っていた。
母の話によると、今晩妹が婚約者を連れてくるということで
ある。知子をご馳走を作る母の手伝いを始めた。
七時ごろ妹たちが帰ってきた。家の中が急に明るくなった。
知子もなんとなく落ち着かなく自分のことのようにうきうきし
た気分になっていた。まもなく父が帰ってきた。みんながそろ
うといっそう話しが弾んだ。だがそのうちに知子は、いつもと
違いそんな家族を冷静に眺めている自分に気がつき始め、とて
も奇妙な感じがしてきた。主役の気分で明るく無邪気に話しこ
む妹、やや遠慮深げにぎこちなく座っているその婚約者、満足
そうに笑みを浮かべている父、そして適当に話を合わせる母を
見ながら、素直に楽しめなくなっている自分に気づいた。
《確かに子供の頃家族の集まりは楽しかった。それは必要なこ
とであったように思われる。だが、高校の終わりごろから、自
分が家族といっしょに居ることがほんとうに楽しかったのだろ
うか》と知子は自分を疑い始めた。そして《いや、もしかした
ら、子供の頃からも、家族の楽しい雰囲気を壊したくないため
に、不満をひたすら押し隠しながら自分は楽しそうに振舞って
いたのではないだろうか? ほんとうは楽しくなんかなかった
のかも。自分が洋裁学校に行くようになったのも、無意識のう
ちにそんな家族から離れたいという気持ちが働いていたのでは
ないだろうか》と思い始めた。
八時過ぎ兄が珍しく早めに帰ってきた。いつもは無愛想な兄
ではあったが、好きな酒とご馳走を見るとさっそく仲間に加わ
った。テレビを見ながらときどき会話に割り込む兄を見ながら
最近ほとんど話していないことに気づいた。兄はいったい何を
考えているんだろうと知子は怪しんだ。今まで兄弟と言うこと
で何も話さなくても判ったつもりでいたが、ほんとうは何も判
っていないような気がした。
知子は退屈さを覚えた。ふと自分はこの場にはふさわしくな
いような気がした。今まで何気なしにやってきたが知子は初め
てのように自分の近い将来のことを考えた。《妹はもうじき結
婚してこの家から出て行くだろう。兄はいずれ嫁さんをもらっ
てこの家でいっしょに住むようになるだろう。そうなると自分
はきっと居ずらくなるだろう。女と言うものはやはり住みなれ
た家から出て行かなければならないのだろうか》
時計は十時を過ぎていた。知子は母と後片付けの準備に取り
掛かった。
あわただしい一日が終わった。知子は居間で話す妹と母の話
し声を耳にしながら床についた。十二時を過ぎていた。
知子がうとうとしかけていると、母と話を終えた妹が乱暴に
足音を立てながら部屋に入ってきた。そして部屋の電気をつけ
ながら弾んだ声で話しかけた。
「もう寝ちゃったの? つまんないの」
興奮した面持ちの妹はまだ何か話したそうであった。知子は「
まだよ」と眠気を降り晴らすようにはっきりとした口調で答え
た。いもうとは寝支度をしながら言った。
「今日の姉さん、楽しそうじゃなかったみたいね」
「そんなことないわよ。楽しかったわよ」
「そうお、なんかいつもと違ってたみたい。ところで姉さんた
ちうまく行っているの?」
「うまくいってるわよ」
「姉さんたちがうまく行ってくれないと不味いのよね」
妹はそう言いながら電気を消して床に就いた。一瞬静かになっ
たが、妹は大きくため息をつくと、やや声を押さえ気味にふた
たび知子に話しかけた。
「姉さんたち、もしかしてまだ済んでないんじゃない?」
「済んでないって、何が?」
「言わなくても判るでしょう。その調子ならまだのようね。姉
さんはこだわりやさんだからね」
「何を言っているの?」
そう言いながらも知子は妹に見透かされているような気がして
動揺を覚えた。
「一度許してしまったら、結婚してくれなくなるんじゃないか
とか、そのまま捨てられてしまうんじゃないかとかって思って
いるんじゃないの、、、、どうってことないのにね、、、なん
とかなるものよ、、、」
妹の生意気な言い方に知子は激しくいらだった。
「心配ないって、うまく行ってるから」
と知子は落ち着いた口調で言った。だが内心は妹に心の動揺を
見抜かれまいと冷や汗の出る思いであった。
「ほんとかしら、姉さんがねえ、それならうまく行ってるはず
ね。でも、姉さんがね」
そういう妹の声にはあざけりの響きが感じられた。執拗に詮索
して人の心をもてあそぶような妹の態度に知子は激しく腹を立
てたが冷静さを装いながら言った。
「遅いから、もう寝ましょう」
すると妹は「うふふ」といって黙ってしまった。耐え難い沈黙
であった。人を食ったようなその笑い声に知子はいくら自分の
妹とはいえ許せない気がした。
妹の現金な寝息を耳にしながら知子は自分と良夫とはこれか
らどうなるのだろうかと思った。二人は今までちぐはぐな感じ
であったのは、妹が言うとおり、そんな関係が欠けていたから
ではないだろうかと、ふと思った。《それにしても今まで良夫
にはそんな言動は見られなかった。それに二人にはそんな雰囲
気にもならなかった。もし今度そんな雰囲気になったら素直な
気持ちになったほうがいいのではないだろうか、妹の言うとお
り何もこだわる必要はなさそうだ。それにもうそんな年齢でも
ないのだから》と思った。そして、そのことで二人の関係が深
まり新たな段階に発展するに違いないと思った。薄れ行く意識
のなかで知子は自分と良夫との夢のような未来が開けてきたよ
うな気がした。
陽は沈んだ。町は夕闇に包まれ、夜の照明はいっせいに輝き
だす。雑踏に慰めを求める人々は町に溢れる。店先から街頭か
ら流れる音楽は足取りをリズミカルにさせ、いやがうえにも人
々の気分を高揚させる。そして快楽的な風景をさらに扇情的な
雰囲気にさせる。人々は我を忘れて酔いしれる。特に若い男と
女たちは風景の一部になりきり、夜の光と闇を演じようとする
。そして町は雑踏と光と音楽で夢幻的な風景を形作る。
八月も終わりの土曜日。しのぎやすくなった午後を、アパー
トの一室で過ごしたマサオは、誘われるように夕闇の町に出た
。
薄暗い路地の角を曲がると眼の前に華やかな風景が広がった
。殺風景な部屋になれたマサオの眼には衝撃的に映った。とく
に女性たち伸びやかでで生き生きとした姿が眼に入った。ショ
ーウィンドーの前を明るい笑顔の少女たちが通り過ぎる。しな
やかな肉体を髣髴とさせる薄着の女が軽やかな足取りで通り過
ぎる。マサオの眼はイメージの世界のように美しいもの華やか
なものだけを捉えるようになっていた。そしてマサオの頭の中
は快楽的な風景で満たされる。マサオの横を通り過ぎる女たち
の肉声や香水のにおいに、マサオの内部に潜み隠れていた欲望
がめざめ、マサオの肉体を心地よくしびれさせる。そして時間
とともにその欲望は静電気のようにマサオの肉体に蓄えられて
いく。風景の一部になりきったように明るく満足そうに振舞う
アベックの姿にマサオは妬みを覚える。そして自分だけが華や
かな風景に取り残されているような孤独感に襲われる。そんな
孤独感のなかで、マサオの肉体に、今にも青いスパークを放つ
ほどに高められた欲望は、暗い暗いはけ口を求めた情欲へと代
わって行った。
二時間後、快楽的な風景に酔いしれ、もてあそばれるように
歩いているうちに、マサオは不快な疲れを感じた。そして欲望
のとりことなった衝動的な自分を感じながら帰り道を歩き出し
た。
マサオは人気ない薄暗い跨線橋を渡り始めた。
徐行し始めた電車の明るい窓から、座席に座っている若い女
性の姿が見えた。その女性の白いスカートからのぞいた肉感的
な足がマサオの眼に焼きついた。
マサオはちゅうちょなくある決心をすると、今来た道を引き
返し、駅へ向かった。そして目的の場所へと電車に乗った。
十五分後、電車から降りたマサオは、マサオの住む町と同じ
ように町を歩きだした。
陽が沈んでからだいぶ経っているにもかかわらず、空気は相
変わらず生暖かかった。埃っぽい湿った空気がマサオの興奮し
た肌にまとわりついた。マサオは欲望に満たされた肉体を引き
づるようにして歩いた。まもなく人出が異常に多い通りに行き
当たった。そこは浴衣姿の大人の男女や小さな子供たちで溢れ
ていた。どうやら商店街の主宰する夏祭りのようである。人垣
のなかから太鼓の音が聞こえて来る。そのなかでは道路を通行
止めにして盆踊りが行われていた。舗道には昔を思わせるよう
な夜店が並んでいたが、欲望のとりことなっているマサオには
なんら興味はわかなかった。大人たちのハシャギ振りを見てい
るとかえって反発を覚えさせるものがあった。盆踊りの主役は
子供たちであった。興奮した大人たちの見守るなか、子供たち
が夢中になって踊っている。そんな子供たちを見てもマサオは
何の感慨も沸かなかった。マサオにってはうんざりする雑踏で
あったが、目的の場所に行くためにはどうしてもここを通らな
ければならなかった。
マサオにとって、太鼓のリズムも子供たちの踊りも、楽しい
ものでも微笑ましいものでもなかった。猥雑で狂気じみたもの
に映った。わざわざ通行止めまでして行うほどのものではない
ような気がした。大人たちの意図を思うとその安易さに腹立た
しいものを感じた。マサオは人ごみを掻き分けるように歩いた
。
その混雑を通り抜けると、目的の場所の看板が横丁に見えた
。マサオはその通りに入り何気なく歩くと、なんら物色する気
配もみせずに、とある店のドアを開けて入った。
マサオは興奮の高まりを感じながら部屋で女が来るのを待っ
た。まもなくさりげなく女が入ってきた。マサオにとって最も
心ときめく瞬間であった。だが、落ち着き払った女の表情を見
ていると、意外な感じを受けた。マサオが日頃から頭の中で思
い描いていたような女性ではないような気がした。少なくとも
白いスカートの女よりもあらわにされた脚をみても、ただそれ
だけで、何の感情も沸き起こらなかった。
「町は賑やかだったでしょう」
と女は言った。
「祭りを見に行かないの?」
とマサオはやや声が上ずるのを感じながらいった。
「子供たちだけだから」
と女は少しも表情を変えないで言った。
「ガキだらけ、今はガキ文化の時代だから」
とマサオは呟くように言った。だが女にはよく聞こえなかった
ようで、怪訝な顔をしてマサオのほうを振り向いた。マサオは
なぜかちぐはぐな気持ちであった。
人影もない暗く寒々とした情景を脳裏に感じながら、眼の前
が明るくなっていくのに気づいた。そして眼の前に白い空間が
広がった。マサオはここがどこであるのか? 自分は何をして
いるのか? まったく判らなかった。ただ身動きが取れない恐
怖を感じている状態だった。意味の理解できない女の声が聞こ
えてくる。と同時に肩をたたかれていることに気づいた。横を
見ると、整った眉毛に眼をきりっと見開いた人形のような女の
顔が見えてきた。母親にしかられた子供のようにおどおどして
いる自分を感じながら、マサオはやっと何が起こったのか判り
かけてきた。貧血を起こしたらしく、ベットの縁にもたれるよ
うに倒れていたのだ。マサオは倒れる前の記憶を思い起こしな
がら、女に勧められるままに静かにベットに横になった。意識
が薄れていくときの気持ちがこんなには心地よいものだとは思
わなかった。《死ぬときもこんな気分なのだろうか? それに
してもどうして意識が戻ったのだろう? このまま戻らなくて
もよかったのに》とマサオは思った。
マサオはどのくらいの時間気を失っていたのかと女に訊いた
。女は驚いた口調で二十秒ぐらいよと答えた。だが厚化粧の顔
からはその表情は読み取れなかった。マサオは意識を取り戻す
ときの異様な気分を思い起こした。これから行われようとする
ことと、そのときの気分は相容れないような気がした。そして
脅かすように脳裏に浮かんでいた廃墟のような風景がマサオは
気にかかった。
五十分後、マサオは外に出て歩き出した。混雑は相変わらず
激しく、祭りはまだ続いていた。だが、マサオにとってそれは
、楽しそうに動きまわる人間の群れに過ぎなく、なんの感慨も
沸かなかった。そして、先ほどのような腹立たしさも煩わしさ
も感じなくなっていた。汚れた舗道に紙くずが散らばっている
。疲れた大人があくびをしている。まとまりのないしらけた風
景である。快楽的でも、幻想的でもなく、ただ華やかそうな風
景が広がっているだけであった。マサオの心は風景の外にも内
にもなかった。たとえようもなく空虚な気持ちであった。マサ
オは自分の寂しい欲望を思うと後悔しても仕切れない気持ちだ
あった。自分のあまりの惨めさのために泣き出したいぐらいで
あった。だがそれも行為となるほどの感情の高まりもなく、た
だそんなイメージが頭をかすめたに過ぎなかった。抜け殻のよ
うな自分を感じながらマサオは帰りの電車に乗った。
エンジンがいつものようにかからないことに良夫はいらだっ
ていた。そんな良夫を横目に見ながら知子は吹っ切れない思い
でいる自分を感じていた。部屋を出る前からお互いに一言も口
を利かなくなっていることに知子は気になっていた。知子は笑
顔を作って良夫の方を見たもののどことなくぎこちなく、ばつ
の悪さは隠しきれなかった。話しかけようとしたが適当な言葉
が見つからなかった。たとえ見つかったとしても、言い表しが
たい虚しさのあまり、実際に声になりそうになかった。
二人を乗せた車はけばけばしい看板のホテルの門から外に走
り出た。
人影のない寂しい裏町風景を窓の外に見ながら知子は依然と
してわだかまりを残している自分に気がついた。自分は妹のよ
うにあけすけな気持ちにはどうしてもなれな気がした。自分が
思い描いていたものとあまりに違う結果を思うとだんだん悲し
い気持ちになっていった。知子は眼を閉じるとただひたすらエ
ンジン音に耳を傾けた。今まで見えてい二人の新しい関係が急
に見えなくなっていった。
九月初めの土曜日。真夏のような暑さがぶり返した。マサオ
は部屋に居たたまれなくなって午後の町に出た。
風はあったが湿り気を含んでいた。まもなく全身が汗ばんだ
。マサオはいつものようにただぶらぶらと歩くだけであった。
週末の午後と会って繁華街の賑わいは格別であった。あれほど
人ごみを嫌っていながら、つい足を踏み入れてしまう自分に不
思議な気がした。ほとんどの人々は蒸し暑さに顔を紅潮させて
いた。ショーウィンドーに眼を奪われながら歩く人々、店先に
並んだ洋服を我を忘れて物色する少女たち、外食点の前に行列
を作る女子高生や親子連れ、交差点にはどこからともなく人々
が集まり、どこへともなく散っていく、みんなそれぞれ目的を
持って歩いているらしいが、マサオには何かに取り付かれたよ
うに集まり、そしてさって行く様にしか感じられなかった。暑
さと不可解な雑踏のなかでマサオは散漫な気分になっていく自
分を感じた。眼の前に現われた本屋の看板を眼にするとマサオ
は吸い込まれるように入った。
店内は混んでいた。涼むにはちょうど良かった。だが、なん
となく落ち着かなかった。おびただしい本が、人々の心を圧倒
するように、そして人々の目をひきつけるように陳列されてい
た。ふと手を伸ばしてみたくなるような表紙の装丁や帯の言葉
、どれもみな刺激的で興味を引きそうなものばかりであった。
魅せられたように眺めまわっているうちにマサオは自分が今何
を求めているのかだんだん判らなくなってきた。とくに虚栄し
んや自尊心をくすぐる帯の言葉にマサオの心はかき乱されてい
た。帯の言葉に動揺を覚えながらも、もてあそばれた自尊心の
余りかえって、反発や嫉妬心を感じて、手にとって見ると言う
ほどでもなかった。マサオはそのうちに、そんな自分を惨めに
存在に感じられてきて息苦しくなった。結局マサオはただ眺め
るだけで、まとまりのない気分のまま再び外に出た。そして流
行らなさそうな喫茶店を選んで入った。
予想したとおりであった。広々とした店内に客はまばらであ
った。音楽が静かに流れていた。マサオは他の客の話し声に邪
魔されないように、なるべく奥の方の席を選んだ。照明は薄暗
く、高い仕切りで周囲の様子が判らないようになっていた。マ
サオはほっとした。自分にはやはりこういう雰囲気が似合うよ
うに思われた。マサオは気持ちが落ち着いたところで、店に備
え付けの新聞をゆっくりと読み始めた。漫然と読んでいたが、
そのうちにある箇所に来るとマサオは思わず活字から眼を背け
てしまった。だがマサオの内部に起こった動揺は隠しきれなか
った。マサオはナイフを突きつけられたような感覚を味わいな
がら、自分はどうして他人の自信にあふれた意見や行き方が気
になるのだろうと思った。マサオは閉じかける心を押し開くよ
うに再び恐る恐る眼をやった。すばらしい考え方のように思え
た。うらやましい生き方のように思えた。こんなところでくす
ぶっている自分と比べてまったく違う人間のように思えた。す
るとマサオは急に外の世界が恐ろしいものに思えてきて、内気
で臆病な子供のように、これから外に出て歩くことが億劫にな
ってきた。そして、他人のそんな才能や自信に妬みの絡んだ複
雑な感情覚え、全身が熱くなるのを感じた。マサオは焦りにも
似た不安を覚えながら新聞を横に置いた。そしてコップの水を
飲みながら気持ちが静まるのを待った。
流れる音楽が聞き慣れたものに変っていた。マサオは頭の片
隅に動揺する気持ちを追いやりながら一心に耳を傾けた。流れ
るようなメロディと小気味よいリズムにマサオの心は同調して
言った。そしてその高揚した気分が動揺する気持ちを忘れさせ
ていった。マサオは心地よい感傷的な気分に浸り、酔いしれた
。すると不安も臆病な気持ちもいつのまにかマサオの心から消
え去り、満たされた気持ちになっていた。むしろ充実感を覚え
、先ほどの滅入った気持ちが嘘のような気がした。マサオは心
が広くなったような気がした。そして外を堂々と歩けるような
勇気がわいてきたような気がした。
マサオは晴れ晴れとした気持ちで喫茶店を出た。
だが外に出て、まぶしく蒸し暑い雑踏のなかに入ると、その
充実した気持ちもたちどころに失われかけていった。先ほどの
音楽に酔いしれていた自分を思うと苦々しい気持ちになった。
マサオは裏切られたような白けた気分で人ごみを歩いた。
繁華街を過ぎると眼に見えて人通りが少なくなっていった。
砂埃を舞い上げる風が強くなっている。真夏のような陽射しに
マサオの冷えた体たちまち元に戻っていた。アスファルトの照
り返しがまぶしく、蒸気のような風が足元にまとわりついた。
町外れの見通しのきく通りを歩いていると、前方の交差点の
騒然とした雰囲気に気づいた。道路わきに救急車が止まってお
り、人だかりができている。付近の店先には店の者が出てきて
交差点のほうを見ている。道を歩いている人たちも立ち止まっ
ては振り返り、マサオのほうに歩いてくる。そこは通行の頻繁
なところである。マサオは交通事故に違いないと思った。マサ
オは興奮する気持ちを感じながら足を速めた。《大破した車、
飛び散った血しぶき、熱いアスファルトに焼け付く血のり、物
々しく動きまわる警察官》を思い浮かべると期待感に胸が高鳴
るのを抑えきれなかった。
人だかりで交差点の様子が良く見えなかった。マサオを好奇
心に身を任せて前に進み出た。だがそれらしいものは何も見え
ない。焼け付く血のりも大破した車も警察官の姿もない。もう
片付けられたのかと思った。でもそれにしても様子がおかしい
。マサオは周囲を見た。するとマサオが人だかりだと思ってい
たのは実はそうではなかった。人々が何が起こったのかと言う
風に見ながら通り過ぎているだけだった。自分と同じように誰
も何も知っていない様子であった。
交差点には普段と変わりなく、排気音を響かせてあわただし
く車が走っている。ときおり風か起こり砂埃を舞い上げる。そ
れだけの風景である。車に反射する日差しがまぶしい。マサオ
の額から汗が落ちた。マサオは再び歩き出した。もう決して後
を振る変えることもなく。
暑さとけだるさで頭がボォッとしてくるのを感じながら、マ
サオはやや涼しげな路地に入った。なんだかはぐらかされたよ
うな気分であった。
歩きながらマサオは思った。
《もしかすると私たちは化かされて生きているのではないだろ
うか? 人々が群れを作り、みな同じ方向を見ているというだ
けで、私たちは、そこには何か注目すべきもの、必要なものが
あると思ってる。だがそこにはもともと何もないのではないだ
ろうか? ただ風が吹いているだけの風景であるにもかかわら
ず、私たちは勝手にそこには何かがあると思い込んでいるので
はないだろうか? 私たちは、私たちの話題のなかに、伝え聞
く噂話のなかに、私たちに共通した楽しいもの、幸せなもの、
美しいもの、華やかなもの、そして欲望の形を見い出し、同じ
ように思い描き、そしてそのようになりたい、そういうものを
手に入れたいと、他人を意識しあい、あこがれ妬みながら生き
ているのではないだろうか? だが、その行き着く先はいつも
何もない、ただのがらんどうで、虚しさだけではないのか?
二十数年のあいだ、自分は他の人との思惑のあいだで、そして
群集によって作られた価値のなかで、無意識のうちに操られ、
もてあそばれるように生きてきたのではないだろうか? 確か
にそのこと自体には安心感があった。そして一見楽しげであり
、幸福そうであった。だが、決して生きる意義や目的を指し示
してくれるものではなかった。それならもうなにも、群集の作
り上げたそんな曖昧な価値に頼って生きることはないのだ》
そう考えるとマサオは、今までの煮え切らない自分に腹立たし
さを覚えた。
この発見にマサオは生きる自信を取り戻せるような気がした
。
アパートに帰ったマサオは部屋に入ろうとしたが、うかつに
も鍵を部屋に置いたままであることに気づいた。大家に開けて
もらおうとしたが留守であった。埃と汗まみれの不快感のなか
で、いつ帰るとも判らない大家を待つことにマサオは絶望的な
気分になりかけた。だが、京の発見を何度も何度も自分に言い
聞かせていると自分の内部にある力強さがよき起こってくるの
を感じた。そしてマサオはその充実した気持ちを頼りにじっと
耐えるように待った。蒸し暑さと興奮で汗がたえまなく流れ落
ちた。二時間後、顔を紅潮させたタカがおぼつかない足取りで
帰ってきた。玄関で待つマサオを見ると、「熱くて大変ね」
と呟くように話しかけてきた。タカが玄関に入り少し落ち着く
のを待ってからマサオは用件を言った。
タカが部屋の鍵をマサオに渡しながら言った。
「おじいさんが倒れてね、入院の手続きで忙しくて、忙しく
て、、、、」
とこともなげに言うタカを見ながらマサオが言った。
「夏バテですか?」
「どうなんだか? 血圧が低いらしくって、五年前にがんの手
術をしたことがあるからね、さあ、どうなんだか? 精密検査
を受けて見なくてはねえ、、、、」
マサオは鍵を受け取り階段を上がった。
職場の壁に掛かっている時計を見ながら帰り支度を整えたマ
サオは、いつものように会社の玄関に向かった。ちょうど知子
が玄関に差し掛かっていた。だがそのとき、廊下の奥のほうか
ら怒鳴り声が響いた。それは知子に対してのようであった。知
子は甘えるような笑顔でその声の主のほうを振り向くと、やや
おどおどとした動作で二度三度と頷いたあと、気を取り直した
ように冷静な表情に戻り、玄関の外に歩き出た。そんな知子を
見てマサオは、どうして怒鳴られてもへいきに笑みなど浮かべ
ていられるのだろうと気になった。なにも皆の前で怒鳴るほど
のことでもないのに、いったい誰だろうと思うと、マサオは無
性に腹が立った。マサオは知子の後を追うように外に出た。マ
サオは知子に追いつくと少し興奮気味に話しかけた。
「どうしたの?」
「アッ、今のこと? なんでもないの」
「仕事のことで?」
「そうみたい」
「そうか、失敗をしたんですか」
「うふふ、、、、」
と知子は曖昧な笑みを浮かべた。知子にはそれほど気にはなら
なかったらしい。でもマサオにはそれがなんとなく気に入らな
かった。
二人の前を歩いている年配の女性に追いつくと知子は親しそ
うに話しかけた。同じ会社の従業員らしい。
マサオは女同士の世間話にときおり耳を傾けながら歩いた。
ビル越しに太陽がまぶしい。まもなくその年配の女性とは交
差点で別れた。
横断歩道を渡り終えてからマサオは話しかけた。
「さっきの人、会社の人?」
「そうよ、パートで働いている人。これからまた仕事なんです
って」
「仕事って、まだ他に勤めているの?」
「そうらしいわ、だんなさんがちっとも働かないんだって」
「体でも悪いの?」
「違うみたい、毎日酒ばかり飲んでいるんですって」
怒鳴られても笑みを浮かべていた知子の表情が頭にこびりつい
ていたマサオにとって、急に真剣な表情になって話す知子に何
かちぐはぐな感じを受けた。マサオはからかう気分で言った。
「その割には明るそうじゃない、男を養うために働くのも結構
楽しかったりして」
「そうかしら」
自分のことのように心配顔で話す知子を見ていると、マサオは
さらにからかいたくなった。
「君だってそうなるかもしれないよ」
「私だったら、殺してやるわ」
その言葉でマサオは、ないふのきらめきが脳裏をよぎったよう
な気がした。マサオは知子を見ることはできなかった。
陽はビルに隠れかかっていた。
日陰になると肌にひんやり感じた。マサオは「おう、涼しい
」とわざと声に出して言いながら知子を見た。
知子は涼しさを肌で感じ取っているかのようにさわやかな笑み
を浮かべていた。
踏み切りに差し掛かったとき、ちょうど警報がなり遮断機が
下りた。まもなく電車が轟音を響かせながら通りかかった。マ
サオは周囲を見る振りをしたあと、先ほどの知子の言葉を思い
起こしながら、知子の横顔を盗むように見た。厳しい言葉が出
たとは思えないほど穏かな表情である。深く物思うような瞳、
抑制された化粧。決して眼を奪われるような美形ではないが、
なんとなくひきつけられる横顔である。秘められた意志、深い
思いやり、静かな心情の広がり、じっと見ていると、遠い記憶
のほのぼのとした思い出につながっていくような気がした。電
車が通り過ぎると、知子の横顔に夕日の赤みが射した。マサオ
は知子に印象に浸りながら踏み切りを渡った。そこから駅まで
は日陰になっていた。ひんやりとした空気に身が引き締まる思
いで気持ちがよかった。
「もう、夏も終わったのか」
とマサオは独り言のように言った。
「あっと言う間って感じね」
と知子は同調するかのように声を弾ませて言った。その声の興
奮した響きにマサオは心地よさを感じた。知子がマサオの顔を
覗き込みながらたずねるように話しかけた。
「こんなに早く帰って何かやることあるの?」
「何にもやらないよ、夕食食べて、風呂に入って、あとはぐっ
する寝るだけだよ」
「ほんとかしら、何か楽しいことがあるんじゃないの?」
「部屋に帰っても一人だからね、楽しいことなんてないよ」
「君こそ家族といっしょなんだから、楽しいことあるんじゃな
いの? それに何にもやることないんじゃないの?」
「そんなことないわよ。皆の食事の用意、それの後片付け。寝
るまで落ちついたことないわよ」
「たしか妹さん居たよね?」
「居るけど、、、、」
「なるほど、、、、」
とマサオは独り言のように言いながら知子を見た。知子はすべ
てを理解した言わんばかりに笑みを浮かべていた。言葉に出さ
なくても何かに共感できることは楽しいことであった。
「独りで寂しいなんで思わないのかしら?」
その知子の子供のような疑問にマサオは心やすまるのを覚えな
がら、少し無邪気な気分になってマサオは答える。
「それは慣れですね。それに独りのほうが楽だったりして、、
、、もしかして家族なんて案外煩わしかったりして、、、」
「なんだかわかるように気もする、、、、、」
マサオは知子の優しい心遣いを感じながら、だんだん知子の心
の内側に入り込んでいくような気がした。マサオは満たされた
興奮を覚えた。
「お嫁に行っても、また色々と大変なんでしょうね」
知子のすぐにでも返答を求めているようなその口振りに、マサ
オは何とか答えようとしたが、駅が見えてきた。マサオはこの
ままずっと話していたい気持ちになっていた。
マサオは通りすがりの喫茶店を指差して、「ここに入る」と
冗談ぽく言って誘いかけたが、知子は気づかなかったのか、そ
のまま歩き続けた。
「今日は学校に行く陽だったの?」
「いえ、違うわ」
知子の事情ありげな戸惑いの表情を見てマサオはこれ以上追及
するとは悪いような気がした。
知子はひょっこりと迎えに来ることがある良夫を気にしてい
た。できるならこんなところを良夫に見られたくないと思って
いた。
マサオはやや名残惜しさを覚えながら駅前で知子と別れた。
ある日の夕刻。残業を得るとマサオは虚脱感を覚えながら時
計を見た。六時を過ぎていた。マサオは散漫な気分のまま会社
を出た。外はもう夕闇に包まれていた。空気がひんやりとして
いた。だが疲労でこわばっていた肌には身震いを起こすような
不快な冷たさであった。西の空が真っ赤に焼けているのが眼に
入ってきた。だが、マサオの心は何の反応も示さなかった。写
真のような風景がそこにあるだけであった。固いアスファルト
の道をマサオは駅に向かって歩き続けた。
車内の混雑を拷問のように感じながらマサオは冷たく光る鋼
鉄の棒に老人のようにもたれかかった。硬い棒はマサオの意思
を無視するかのように肩に食い込んだ。金属的なきしみ音がマ
サオの周囲に響いた。窓ガラスに映る疲れきった自分の顔から
マサオは思わず眼をそむけた。マサオは手足が自分のものでは
ないように感じながらアパートに向かって歩いた。部屋に帰る
といつものようにだらしなく横たわった。少し休むと気分が落
ち着き思考力が回復してくるのがわかった。マサオは一日の出
来事を思った。このあいだ自分に生きる自信を取り戻してくれ
た考えが、何の役にも立たないもののような気がした。朝、仕
事が始まるときは、そんな考えと自信をよりどころに余裕を持
って臨むのであるが、会社のあわただしいな彼のなかでは、そ
んな考えも余裕も消えてしまい、いつものように仕事に追われ
ながら呆然と一日を終えてしまうのである。《結局以前とちっ
とも変らない状態ではないのか? どうしてだろう? あれは
単なる思いつきで現実の前ではなんら通用しないものなのだろ
うか?》とマサオは思った。
夜も更けた。マサオは寝床に入った。風が出ているのか、窓
ガラスが音をたてた。電車の音が聞こえた。だが、マサオの心
は外の気配を拒絶するかのように身体のうちに閉じこもってい
た。外の世界はマサオの心とは無関係によそよそしくあるだけ
であった。
マサオは帰り際に見た夕焼けを思い起こした。ある思いとそ
れにまつわる感情が沸き起こりそうになったが、何か眼に見え
ない障害物に邪魔されたかのように、胸につかえたままだった
。マサオは言葉にもイメージにもならない感情に苦しめられた
。
九月も終わりに。
夕方になると風は肌寒いほどだった。
勤務を終えた良夫は開放感に浸りながら駐車場の車に乗り込
んだ。そしてなれた手つきでラジオのスイッチを押すと、座席
のバックミラーを見ながら乱れた髪の毛を整えた。すると、ふ
と知子を迎えに行くことを思いつき、急いで車を走らせた。
二十分後、良夫は知子が帰ってくるのが見えるように、道路
のわきに車を止めた。家路を急ぐ人々がひっきりなしに良夫の
車のわきを通っては駅へと歩いていた。
良夫は知子がいつもより遅いような気がした。また会社の誰
かといっしょに帰ってくるのかと思うと苛立った。楽しそうに
話しながらいるいてくる男女の姿が眼に入ってきた。知子では
なかったが、その二人の親しそうな関係が不自然なものに感じ
られ、良夫には見苦しいものに思われた。人々がひとつのまと
まりのように歩いていることに良夫は理由もなく反発を覚えた
。
まもなく知子が独りで歩いてくる姿が群集に浮き立つように
見えた。良夫は知子のおっとりとした歩き方がなんとなく気に
なった。良夫は人ごみを横目に意識しながら知子の後を追うよ
うに車を乱暴に走らせた。そして知子のわきに車をつけると、
ややきもちの高ぶりを覚えながらクラクションを小さく鳴らし
た。
知子を乗せると良夫はやや落ち着きを取り戻しながら車を走
らせた。良夫は無意識のうちに、知子を車の部品のように、な
くてはならないもののように感じていた。
繁華街の通りの駐車場に車を止めると、良夫と知子はは賑や
かな通りを歩き出した。二人は群集にのみこまれるように華や
かな風景に酔いしれながら歩いた。良夫はいつになく智子に注
意を配り気遣った。知子は良夫の思いやりを素直に受け入れた
。良夫は誇らしげであった。騒々しさのあまり会話がうまく通
じなかったが、知子は良夫の言うとおりに従って歩いた。そし
て食事のため華やかなレストランに入った。
食事中、良夫はやや気取りながら話しかけた。知子はなにも
考えずに賑やかな雰囲気に溶け込みながら終始楽しそうに振舞
った。一時間後、食事を終えた二人は、再び車に乗り夜の街を
走り出した。満足そうな良夫の横顔を見ていると知子は、ほっ
とするのを感じた。これから自分たちはきっとうまく行くに違
いないと思った。
知子はふと買い物を忘れていることに気がつき、良夫に頼ん
で店の前に車を止めてもらった。店に駆け込み、商品を物色し
ている知子を車のなかから見ながら良夫は《知子には自分しか
必要ない、自分だけか知子を幸せにできる》と思い込んでいた
。
思ったより知子が遅かった。良夫は再び店の様子を見た。知
子が男の店員と笑顔で親しそうに話しているのが見えた。なぜ
見ず知らずの男にまで笑顔を振りまくのか? 良夫には知子の
行動がどうしても理解できなかった。良夫は裏切られたような
感情を抱きながら無性に苛立った。
知子が戻ってきた。良夫は不機嫌な表情で乱暴に車を走らせ
た。買い物も無事に終えてほっとしたのか知子は、そんな良夫
にも気づかず和やかな気分になっていた。
しばらくすると良夫は、知子に横顔を見せたまま少しぶっき
らぼうに言った。
「そんなに楽しいことがあったの? でれでれして、、、、」
なごやかな気分に浸っていた知子には、それは良夫のちょっと
した冷やかしのように思えた。知子は満ち足りた気持ちで「だ
っておかしいじゃない」と言いながら良夫のほうを見たが、良
夫は車を運転しているときにいつも見せる硬い表情に変ってい
た。それを眼にして知子はそれ以上言葉を続けることができな
かった。《どうしてこうなるのだろう?》と思うと情けない気
持ちになった。そして自然と顔から笑みが消えていくのが判っ
た。
笑みの消えた知子の不満顔に良夫は知子の強情さを感じた。
そして知子が自分に逆らっているように思え、憎しみに近い感
情が沸き起こってきた。さらに良夫は、知子は自分のことが好
きで付き合っているのではなく、また自分といっしょに居るこ
とを楽しんではいないように思われた。
「俺と付き合うのがいやならはっきり言えば良いじゃないか」
「どうしてそんなこと言うの?」
と知子は興奮する気持ちを抑えながら穏やかに言った。だが良
夫には知子のそんな落ちつきぶりが気にいらなかった。
「でも、いまさら別れようたってそうはいかないよ」
《なぜこんなことを言うのだろう? せっかく今まで楽しくや
ってきたのに、良夫はいったい何が気に入らないのだろう?》
と知子は思った。
知子には良夫の突然の気持ちの変化が理解できなかった。や
っぱり自分たちはダメなのだろうかと思うと悲しい気持ちにな
っていった。そしてもうなにも話したくない気分になった。
押し黙っている知子を見て良夫は、知子が自分より大人びて
いるように思われ、そしてその優越感を知子が味わっているよ
うに思われると、訳もなく苛立った。そしてますます憎しみの
感情が高まっていった。
「ほかの男と付き合うようなことがあったら、俺との関係を全
部しゃべって、邪魔してやるから、、、、」
あの日以来、やや傲慢さの目立つ良夫をわがままのように感
じてはいたが、今の言葉だけは許せない気がした。二人の関係
がどこまで行っているにせよ、そんなところまで干渉する権利
はないはずだ、と知子は思った。
《いくら信頼を深めようと、いくら楽しそうに振舞おうと、思
いがけないところで亀裂が生じてしまい、いつも後味の悪いも
のになってしまう、二人の性格がほんとうに合わないのではな
いだろうか》と知子は思った。そして、良夫の不可解な言動を
思うと、知子はもはや自分たちを結びつけるものはなにも残っ
てないような気がした。良夫はいつものように思い通りにいか
ない運転に苛立ちながら車を走らせ続けた。
十月になった。ある日の朝、まぶしすぎる外の気配に、マサ
オは驚いて飛び起きた。朦朧とする意識のまま時計をみると八
時を過ぎていた。完全に遅刻だと思うとマサオは犯罪者のよう
にうろたえ、鼓動が高鳴った。急いで身支度を整えようとした
、だが、意識がだんだんハッキリしてくると、どうも様子がお
かしいことにづいた。落ち着きを取り戻してきたところで、昨
夜の寝る前のことを思い起こした。昨日は金曜日、そして今日
は土曜日、休みだったのである。マサオは神経の高ぶりを覚え
ながらまた眠りについた。
再び眼が覚めると十時を過ぎていた。先ほどのことを悪い夢
のように思い出しながら寝床でじっとしていた。かすかに興奮
の余韻が残っているのを感じた。
下の大家の家から賑やかな話し声が聞こえてきた。心配そう
なタカの声と濁った源三の声である。源三が退院して来たらし
い。
昼前、マサオは家賃を払いに階段を下りて言った。やわらか
い日差しが射していた。タカが独りで居た。
「おじさんは、いつ退院してきたんですか?」
「昨日」
「それじゃ、もうよくなったんですか?」
「そうでもない見たいなんだけどね、もうすっかり痩せちゃっ
て、まだ出歩いちゃいけないというのにねえ、、、、」
「どこかへ行ったんですか?」
「パチンコに行ったんだよ。もう少しよくなってから行けばい
いのにねえ、ほんとにすきなんだねえ、、、、」
「パチンコですか、、、、」
「タバコを取ってくるってきかないんだよ。お医者さんにあま
り無理しちゃいけないっていわれているのにねえ、、、、」
午後にはやわらかい日差しが差し込む。窓の外は初夏のよう
にまぶしい。そして暖められた部屋のなかをどこからともなく
現われたハエが飛びまわる。部屋に差し込む陽射しは時間とと
もに短くなっていく。やがて風が起こり、窓際のカーテンを揺
らしながら涼しい空気が部屋に流れ込むようになる。
隣家の屋根が窓ガラスに映るようになるころ、子供たちのわ
めき声や走りまわる足音が聞こえてくるようになる。するとま
もなく窓の外は赤紫色に染まり、やがて気づかれぬように薄暗
くなっていき、肌寒い空気が部屋に流れ込むようになる。
午後を自分の部屋で過ごしたマサオは、陽が暮れた外の気配
に眼をやりながら窓を閉めように窓際に寄った。隣家の壁に翔
子の部屋の灯りがほの明るく反射しているのが見えた。《そう
いえば最近翔子の部屋からは話し声が聞こえてこない、どうし
たんだろう?》とマサオは思った。
たしか二週間ほどまえ、翔子の部屋から重苦しい雰囲気が伝
わってきた。耳を澄ますと、いつもの無邪気で屈託のない会話
ではなく、大人びた口調で話す男の声や、「イヤよ、お願い」
という翔子の興奮した声が聞き取れた。マサオはただならぬ気
配を感じて自然と注意を奪われた。マサオには別れ話のように
聞こえた。
男が冷静な口調で、その説明に入ろうとすると、翔子は、「
もうやめて、それ以上言わないで」と絶叫するようにいっては
話を止めさせ、何度も何度も男の説明を遮っている。翔子は男
の話は別れ話であることを察しているようであった。結局男の
口からは「別れよう」と言う言葉は出なかったようである。そ
して深夜まで、あくまで冷静な男の説得と、翔子の哀れと思え
るほどの懇願する声が続いていた。翔子は必死によりを戻そう
としているようであった。
マサオは窓を閉めながら思った。
《やっぱり別れたのだろうか? あれほど楽しそうにやってい
たのに。何が原因で? 春に引っ越してきたばかりなのに。な
んとあっけない》
翌日翔子は部屋を引き払っていた。
会社での昼休み。ビルの窓の外には、よく晴れ渡った穏かな
町並が広がっている。マサオはそんな風景に誘われるように外
に出た。はるか彼方まで広がる青い空から秋のやわらかい陽射
しが降り注いでいる。風は春のような爽やかさであった。マサ
オは開放感を覚えた。
昼食時とあってか、通りは会社員風の人々で賑わっていた。
彼らはいつものようによそよそしく、他人の存在には感心がな
いと言った様子で、取り澄ました表情をして歩いている。マサ
オは人々のそんな表情や態度に見慣れていたとはいえ、どこと
なく気後れを覚えて、自分が余所者であるような気分になった
。
マサオはやや窮屈な思いをしながら人ごみを歩いていたが、
ふと見晴らしのいい場所から遠くを眺めてみたい気持ちになっ
た。マサオはデパートの屋上に上がることを思いついた。
屋上に出ると、人間の姿は思ったよりも少なく、子供を連れ
た母親や遊び人風の男、そして学生らしき男女の姿がばらばら
と言った程度で、通りのような賑やかさはなかった。大掛かり
な遊戯施設はなく、子供が乗る小さなおもちゃの馬や、アイス
クリームの売店があり、所々に望遠鏡があるが見ているものは
誰もいなく、手摺り沿いにはビニールの屋根のついた椅子が並
べられている。スピーカーからは音楽が流れていたが、ときお
り中断して迷子の呼び出しが響いていた。
空は青い巨大な天幕のように広がっているだけである。眼を
遮るものはなにもなく、はるか遠くまで見わたせた。ぼんやり
眺めていると、先ほどまでの急迫した思いはだんだん薄れてい
くようであった。
マサオは椅子に腰をかけた。じっとしていると陽射しで額に
うっすらと汗がにじみ出てくるが、ほどなくして乾いた風が吹
き寄せてきて、涼しさが戻ってくる。そんな心地よいくり返し
が眠気を誘うほどであった。マサオはこのままここにじってし
ていたい気持ちになった。少しぐらい遅刻してもかまわないと
決心すると、ゆっくりと椅子にもたれかかり眼を閉じた。敗れ
かけたビニールの屋根がときおり拭く風に音をたてた。
しばらくしてマサオは眠りから目覚めるようにそっと眼を開
けると視界に奇妙なものが入ってきた。それは人間の姿ではあ
るが、その眼は熱病患者のように輝き、どこを見つめるという
風でもなく、うつろに青い空に向けられ、顔を風にさらしなが
ら、その方角を探り当てるかのように揺れ動かしている。両手
は無造作に放られ、何かをつかもうとするかのように空中をさ
迷う。身につけている衣服はなんとなくみすぼらしく、足取り
もおぼつかない。年齢もわからない、子供のようにも見えるが
、青年のようにも見える。マサオは普通に人間が持っているは
ずの何かが欠けていると思った。そして町で見かける人間とど
こか違っているように感じられた。
その男はマサオに近寄ってきた。見慣れないものを見たとき
のようにマサオはとっさに気味の悪さを感じた。男はマサオに
かまわず先ほどからの動作を繰り返した。よく見るとその男は
重度の知的障害者のようだった。マサオは不快な気持ちになっ
た。それは心地よい眠りを妨げられたときの不快さに似ていた
。その男はマサオの近くに寄ってきても、自分の感情に酔いし
れるように、先ほどからのこっけてと思えるほどの仕草をくり
返していた。マサオはなんとなくその男に親近感を持たれてい
るような気がして、その場から去りたい気持ちになった。マサ
オは少し迷惑な気持ちを覚えた。そのうちに、マサオの近くに
座っていた親子が、やはり気味悪がったのか、そそくさと席を
立ちどこかへ行ってしまった。マサオはその男を無視するかの
ように再び眼を閉じた。
しばらくして眼を開けると、再び奇妙な光景が眼に入ってき
た。電気仕掛けのおもちゃの馬の上で、その振動にあわせるか
のように手足をばたばたさせてその喜びを全身に表しながら奇
矯な声を張り上げる盲目の幼な子。それを傍で支えながら満足
げな笑顔で見守るそのこの母らしい女。その笑顔は泣いた鬼の
ようである。何か悪い遺伝に支配されているかのような容貌で
ある。それに服装がなんとなくみすぼらしい。やはり町だ見か
ける人間と比べて何かが欠けているようにマサオには思われた
。ふと先ほどの障害者がその親子の傍に寄り添っているのが眼
に入ってきた。マサオは彼らは親子であることに初めて気がつ
いた。
マサオは心の動揺を感じながら彼らから眼を離したものの、
頭の中には彼らの細々とした生活や、彼らが住む寂しい裏通り
の風景が自然と浮かんできた。マサオは彼らの不幸な遺伝を思
わずにはいられなかった。すると急に涙がこみ上げてきそうに
なった。マサオの頭は混乱した。屋上の風が砂埃とともにマサ
オの顔に吹きつけた。マサオはいたたまれない気持ちで席を立
つと、ふたたび町の風景に眼をやった。巨大なクレーンを使っ
て新しいビルディングが建てられているのが見えた。赤い鉄骨
が甲高い槌音を町中に響かせながら、組み立てられている。日
増しに高く築き上げられていくその営みが、マサオには、何か
暴力的な営みのように感じられた。そしてその槌音は脅迫的な
響きに聞こえ、鉄骨のその赤い色は忌まわしい色に映った。
はとが青い空に、白い残影を落として目の前を飛んでいった
。だが空はただの空虚な広がりのようにしか感じられなかった
。
時計を見ると昼休みの時間が過ぎていた。マサオは感情の高
ぶりを感じながらデパートを出た。街は普段と変らない賑わい
を見せていた。だがマサオには、町を歩いている人間の表情が
、不思議と感情を失った乾いたもののように感じられた。そし
てその表情のなかに、何の深みもない、乾きすぎた風のような
サッパリとして類型的な心情を感じた。きっと自分もそんな表
情をしているに違いないとマサオは思った。
歩きながらマサオは、奇妙に見えた障害者親子のことを考え
た。
《なぜあのときあの知的障害者は気味の悪い行為をしたんだろ
う? そのとき内部にはどのような感情の高まりがあったのだ
ろう?》と思った。そしてマサオはあの知的障害者の表情や行
為をもう一度思い起こした。《もしかして、あのとき、あの知
的障害者にとって、風は、魚にとっての水のように感じていた
のではないだろうか? そして青い空は、今にも手が届きそう
な青いカーテンのように感じていたのではないだろうか?》と
マサオま考えた。《それならば、あの行為や表情は隠すことを
知らない素直で豊かな感情の表現なのではないだろうか? そ
して、それは素朴で汚れを知らない迸るような心情の現われで
はないだろうか?》とマサオは考えた。v
マサオはあの知的障害者のの行為や表情の意味を理解できた
ようなきがした。そしてその中に自分がわすれていて懐かしさ
を感じさせるような感情の形を見たような気がした。《それは
誰もが心の奥底に持っている根源的なものなのであるが、日々
の生活のなかでも、町の人ごみの中でも、皆押し隠しているの
ではないだろうか》とマサオま思った。《自分を含めて、なぜ
人間は、素直な感情表現を失ってしまったのだろうか?》とマ
サオはさらに思った。そしてマサオは、人々は装い取り澄まし
、お互いにぎこちなく窮屈な生き方をしているような気がした
。
なんとか仕事の整理がついた知子はほっとしながら手を休め
た。時計を見ると修了までまだ二十分もあった。知子は開放感
に浸るようにぼんやりと窓の外に目をやった。ブラインドの隙
間から黄ばんだ陽射しが差し込んでいるのに気がついた。知子
は席を立ってブラインドを少し上げて外を見た。太陽がビルの
陰に沈みかけているところだった。もうこんな季節になったの
かしらと知子は思った。もうこれからはだんだん日が短くなる
だけだと思うとなんとなく寂しい気持ちになった。知子はブラ
インドを元に戻すと、もう一度ゆっくりと整理のしなおしを始
めた。まとまりのない気分であったがそのけだるさがとても心
地よかった。そして頬にほてりを感じながら思った。
《どうしてこんなにも一年が早いんだろう? 若いときはもっ
と長かったようなのに、それに色んなことがあったような気が
する。今年は何かあったかしら? 何にもなかったような気が
する。ただ毎日が単調な繰り返しだったような気がする》
まだ誰もいない更衣室で知子は、いつもより早めに帰り支度
をはじめた。まもなく弾んだ声で話しながらやってきた同僚た
ちであっというまに賑やかになった。若い同僚たちは、開放感
を全身に表しながら無邪気な会話に夢中になっていた。だが知
子はそんな会話には素直に入れなくなっている自分に気づいた
。そんな同僚たちの今晩の予定を耳にしていると、自分は何の
予定もなく家に帰り、そして家族の食事などの世話で忙しいだ
けの自分と比較して、なんとなくうらやましく感じた。みんな
はきっと毎日が楽しくてしようがないのだろうと、知子は思っ
た。そして、ふと自分は家に帰ることをそれほど楽しみにして
いないことに気づいた。するとなぜか急に気分が沈みこんでい
くのを覚えた。
仕事を終えても、マサオは開放感がわかなかった。終了間際
の斉木の動物的な顔から出た不可解な笑いが、先ほどから何度
も頭のなかに消えては現われ、脅迫的にマサオの心を占領して
いた。捕われた気持ちのままマサオは帰る支度を始めた。なん
となく窓の外に眼を向けた。薄暮の町の風景が眼に入ってきた
がなんの感慨も沸かなかった。どんな考えや思いを抱いて一日
に臨んでも、結局はいつものように軽い頭痛と閉じ込められた
ような気持ちで耐えるように一日を終えるだけのような気がし
て、マサオはやりきれない気持ちになっていた。
窓から独りで帰って行く知子の姿が見えた。急に和らぐ気分
を覚えながらマサオは、無性に知子と話したくなった。マサオ
は知子の後を追うように急いで外に出た。
会社の通用門の賑わいを横目に感じながら知子は歩き出した
。冷たい空気が火照った頬に気持ちよかった。しばらくすると
背後から聞いたことがあるような足音に気がついた。
知子は思わず振り向いた。
マサオであった。
思わず知子の笑顔を眼にして、マサオは照れくささもあって
言葉が出なかった。
知子も嬉しそうな笑みをたたえたまま何も言わなかった。
二人は並んで歩いた。
お互いに黙って歩いていてもなんら不自然な感じはしなかっ
た。お互い言うべきことを考える必要ながないように思われた
。不思議な気持ちであった。ビルの隙間から夕日が沈んでいく
のが見えた。マサオま内部に沸き起こる喜びで体が温まり疲れ
が取れていくような気がした。
町のざわめきをついて、知子の柔らかい声が、耳元のささや
きのように響いた。
「今日は休みだと思ったわ」
「どうして?」
「だって、ぜんぜん、見かけなかったから」
感情の高ぶりを隠すようにマサオはややふざけた気分になって
言った。
「ちゃんと働いてましたよ。私はずる休みなんかしませんよ。
なにせまじめですからね」
「そうね、高橋さんは真面目だから、、、、」
マサオは冗談のつもりで言ったのだったが。少し沈黙が続いた
が知子が思いついたように弾んだ声で言った。
「ねえ、陽が短くなったと思わない?」
「うん、そうだね」
とマサオは、今初めて気がついたように周囲に眼を向けながら
言った。
「五時前よ。もう五時前には太陽がビルの向こうに沈んでいく
のよ。見なかった?」
「ふーん、そうなの、気がつかなかった」
「ほんとに速いわ、一年って、、、、」
「、、、、」
マサオは曖昧な返事しかできなかったが、興奮気味に言う知子
の話を聞いているだけで楽しさを感じた。そして知子の見たと
言う、太陽が沈んでいく光景を思い浮かべながら歩いた。満ち
足りた気分であった。マサオが舗道の敷石につまづきかけた。
それを見て知子はいたずらっぽい笑みを浮かべながら話しかけ
た。
「どうも変ね、今日は何かいいことがあるみたいね」
「どうして?」
「だって、さっきから上の空じゃない。それになんか楽しそう
じゃない」
「楽しそうに見える? そう、今日はいいことがあるんだよ」
《いや、ほんとうは何もないよ。君とこうして歩いてあること
がいいことなんだよ。君と歩いていることが楽しいことなんだ
よ。それ以外今の僕には楽しいことなんてないんだよ》
とほんとうはマサオは言い続けたかったのだったが。
マサオはなにも言わなくなったとも子がなんとなく気になり
、知子のほうを見ながら大げさな身振りを交えていった。
「君だって、さっきから楽しそうじゃない、何かあるんだろう
。デート!、デートか、うらやましいなぁ!」
《どうしてそんなことをいうのかしら》
と知子は不満げに思った。
知子の顔から笑みが消えていくのがマサオに判った。
《なんてつまらないことを言ってしまったんだろう》とマサオ
は思った。
《正直になろう。照れ隠しは止めよう。さっきからこうしてい
っしょに歩いていることに、自分が楽しんでいるように、知子
は楽しんでいることは判りきっていることではないか》とマサ
オは思った。
夕日はもうどこにも見えなくなっていた。そして町は薄暮の
風景に変っていた。マサオは息を大きく吸って呼吸を整えた。
空気がいちだんと冷たくなっていた。
マサオは先ほどから黙っている知子を気遣うように話しかけ
た。
「今日はなにも予定はないの?」
「ええ」
「それじゃ、まっすぐ家に帰るだけなんだ」
そのとき一台の車が二人の会話をさえぎるように排気音を響か
せながら猛スピードで通り過ぎて行った。表情を曇らせてその
車に眼をやる知子を見ながら、マサオも話を中断するように何
気なくその車を眼で追った。そして黙っている知子に注意を向
けながら歩いた。しばらくして知子が穏かに話しかけた。
「男の人って良いわね。自分の思い通りに好きなことやれて、
、、、自由気ままに遊んで楽しんで、、、、」
「僕が自由気ままに遊んでいるって言うの?」
とマサオは笑みを浮かべながら言った。
「あなたのことじゃないけど、ふつう、男の人ってそうじゃな
い。よく言うじゃない、それに比べて、、、、」
「女の人だって好き勝手に遊んでいる人いるよ。どう、君も遊
んだら。でも楽しいか楽しくないかは本人次第だからね。君に
はね、、、、」
「高橋さんもやっぱり普通の人にように、いろいろと遊ぶの?
」
「いろいろって?」
「ギャンブルとか、それに独身の男の人が楽しむところ、、、
、」
「そう見える?」
「そうは見えないけど」
「ないことも、ないけど、、、、」
そのとき驚いたようにマサオの顔を覗きこむ知子のようすがマ
サオには判った。
《そんなに驚かないでおくれ。僕だって普通の男さ、でもそれ
は現代にあってとても不幸なことなのだよ。それは苦しみなの
だよ、だから、、、、》
とマサオは言いたかったが言葉にならなかった。
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
「最近、女の人も酒を飲んだり、ギャンブルをしたりして楽し
むのが普通なんだってね、、、、」
そういう知子の表情にマサオは迷いのようなものを感じた。
「そんなこと、だれが言っているの?」
「だれって?、テレビとか新聞とかで、、、、」
知子がそんなことに惑わされ頭を悩ますことはないとマサオは
思った。そして知子にはふさわしくないように思われた。マサ
オは強い口調で言った。
「それは人の好き好きだよ。女だって男だって、遊びたけりゃ
遊べばいい、楽しみ炊きゃ楽しめばいい、なにも人の真似をす
ることはないよ。君には似合わないよ。必要ないよ、だいいち
、そんなことは普通でもなんでもない、、、、」
そういいながら最後のほうになるとマサオの声は怒ってでもい
るかのようにだんだん大きくなっていった。
「真似しようとは思わないけど、ただ、、、、」
と声を低めてはなす知子を見ながら、マサオはふと、自分のこ
とのように興奮していることに気づいた。すこし言い過ぎたか
なと思った。マサオは興奮を鎮めるかのように苦笑いをしなが
ら知子の方を見た。知子の表情に怯えた気配はなく、少しも気
にしていない風であった。それは何か考えごとに耽っているか
のように、とても穏かな表情であった。なぜこんなに興奮した
んだろうとマサオは思った。だがそれほど後味のあるさはなか
った。むしろその前よりも充実した気持ちになっているのを感
じた。
夕闇に車のライトが目立ってきた。知子が言いにくそうに話
しかけた。
「男の人ってやっぱりあれなのかしら?、、、、他の人と話す
のイヤなのかしら?、、、、」
マサオは怪訝な顔をして知子を見た。知子は恥ずかしそうに笑
みを浮かべていたが、思い切ったように話し始めた。v
「私が付き合っている人、私がほかの男の人と話したりすると
、とてもイヤな顔をするの、ひどいときには人が変ったように
不機嫌になって、怒ったり、言わなくてもいいようなことまで
言うの、それも突然、、、、やはり男の人ってイヤなのかしら
?、みんなそうなのかしら?」
漠然としていたがマサオには、知子の言おうとすることはよ
く判った。マサオは以前から、知子が自分を信頼したように素
直な気持ちでなんでも打ち明けてくれることを嬉しく思ってい
た。ありがたかった。そこでマサオは、何とかして思い悩む知
子を助けてあげたい、迷いからすく出してあげたいと思った。
ちょうど騒々しい交差点にさしかかった。渡りかけようとす
ると信号が赤に変った。おびただしい車がいっせいに目の前を
通り過ぎる。マサオはなにげなく知子に眼をやった。マサオの
存在を忘れたかのように思い悩む知子の横顔にマサオは眼を奪
われた。それは寂しすぎる孤独な表情だったからだ。
マサオは祈るように思った。
《僕は知っている。
僕が君に好意を寄せていて、君が僕に好意を感じていることを
。
そして、君が僕に好意を感じていることを君自身が知っている
ことを。
だが、君は知らない。
僕が君に好意を寄せ続けていることを》
このかんマサオは、美しい音楽を聞いているような気分だった
。マサオはますます知子を何とかしてあげたいと思った。だが
これから先は人通りが激しくなり、さらに騒々しくなる。落ち
着いて話せない。満足に答えて上げられないと、マサオは思っ
た。
信号が変った。マサオはふとまわり道をすることを考え付い
た。そして歩き出そうとする知子に言った。
「今日は、ほんとうに、なにも予定はないの? それなら、少
し遠まわりをしない、、、、」
そう言いながらマサオはいつもと違う道を歩き始めた。知子は
一瞬ちゅうちょしかかった。良夫のことが頭に浮かんだからで
ある。だが、知子はそんな自分に不満を感じた。そして、こん
なことで良夫に気を使う必要はない、もう良夫のことなんかど
うでも良いと思い定めると、少し顔を上げてマサオの後をつい
て歩き出した。歩きながら知子は、何にも悪いことをするわけ
ではないんだからと自分に言い聞かせた。
切れ目なく通り過ぎる車の騒々しさに、マサオは苛立った。
だがまもなく車も少ない静かな通りに出た。マサオはゆっくり
歩きながら、知子の言ったことを思い返した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「さっきの話しだけど、いつもそういうふうなの?」
「そうね、いつもっていうわけじゃないけど、、、、ただ、、
、、」
そのときマサオにはなんとなく知子ののろけのようにも感じら
れた。
「君があんまり目立つようにするからじゃないの?」
「そんなこと!」
そういう知子の表情は堅いものに変っていた。惚気ではない、
知子にとってやはり深刻な問題なのだ、とマサオは感じた。
「いや、、、、たぶん、、、、きみのことすきだから、ついそ
うなるんじゃないのかな、、、、」
「そうかしら、なにもあんな言い方をしなくても、ごうまんよ
、、、、」
その知子の口調には憎しみに近い響きが感じられた。
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
「高橋さんも、そうなのかしら、、、、」
マサオは返答に困った。そしてなぜか迷った。
「・・・そうなるかもしれないし、そうならないかもしれない
、、、、そのときになってみないと判らないなぁ、、、、」
とマサオは考えにまとまりのつかないまま曖昧に答えた。その
せいか会話が不自然に途切れてしまった。
深刻な表情で黙っている知子をながらマサオは、《役に立っ
たのだろうか?、何にも役に立たなかったのでは、かえって知
子の気持ちを混乱させてしまったのではないか?》と思った。
そして独りで思い悩む知子の姿に、精神的な支えを必要として
いるような女のか弱さを覚えたマサオは、知子をこのまま放っ
て置けない気持ちになった。そして、いっそのこと、『お互い
に信頼しあっていれば、そんな問題は起きない』と言えばよか
ったのだろうかと、少し激しく後悔した。
マサオはその男のことを思った。傲慢で自分本位で嫉妬心の
塊のような人間像が浮かんできた。ふと自分のほうが優れてい
るような気持ちに捕われた。そして、自分ならそんなイヤな思
いにさせないだろう、自分のほうが知子を幸せにできるのでは
ないかという気がしてきた。マサオは急に、知子の気持ちをそ
の男から自分のほうに向けさせたい気持ちになった。そして、
そんな男とは別れてしまえというべきだろうかと迷った。
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
「高橋さんの生まれはどこだったかしら?」
「生まれ? どうして?」
「ただ、なんとなく、、、、」
「・・・生まれは、、、遠い遠い北の国、、、、」
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
「高橋さんて、あまり自分のこと話さないのね、、、、私とは
話しづらいのかしら、、、、」
「いや、そんなことはないよ。君の話を聞いているほうが楽し
いんだよ。それでつい、じぶんのことをわすれてしまうのかな
、、、、」
「うそ!、他の人にはちゃんと話すんでしょう」
「ほんとうだよ。まあ、話したって良いんだけど、君にはつま
らないと思ってね」
そういい終わるとマサオは次のように心のなかで呟いた。
《ほんとうさ、君の話を聞いているのがどんなに楽しいか、君
はまだ何にも気づいていないようだね》
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
知子の表情に落ち着いた晴れやかさが戻ってきた。
このままでいいのだとマサオは思った。
《もう知子の気持ちを自分のほうに引き寄せる必要はない。今
のように話しながら歩いているだけで十分なのだ。お互いに愛
情を告白し合い、確かめ合い、拘束しあう、なんと煩わしいこ
とか。恋人気取りで町を歩いたり、映画を見たり、食事をした
り、それがどうしたというのだろう。なんと愚かしいことか。
やがて、家族親戚への紹介、結婚、新婚生活、そして子供の誕
生、、、、なんと遠まわりな、なんと退屈な、ことか。これか
らどんなに発展しようと、今のこのような関係に勝るものはな
いのだ。このように知子を思い続けていることが最高なのだ》
とマサオは恍惚として思った。
マサオはそれが二人の理想の関係のように思われ、ますます
満ち足りた気分になっていった。マサオはただひたすら自分の
思いに酔いしれた。
だいぶ薄暗くなって来ているのにマサオは気がついた。駅が
近くなったのか、人通りが多くなってきた。
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
「この前、君の住む町を通りかかった。近くに川が流れていた
ね、、、、」
「川?」
「なんか凄く汚れていたけど」
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
駅前の人ごみが見えてきた。華やかな夜の光が輝き始めてい
た。時計は六時を過ぎていた。
「斉木さんて、会社止めるみたいね、聞いてない?」
「まだ、何にも、あの人は、女の人の混じって話すのがスキだ
からね。何かあるとすぐ、女の人たちに話して噂をばら撒くん
だから、、、、」
「ふーん、ほんとかしら?」
「さあ、判らないけど、でもいろいろと不満があるみたいだね
。大変なんだよね。僕も持ちそうにないな、、、」
「どうして?」
「・・・今の仕事も、こういうところでの生活も僕には合わな
いような気がして、、、、」
「そんなことないわよ。今までやってきたんだから、大丈夫よ
。それに高橋さんはやさしいから、、、、」
やさしいことと都会で生きぬくこことは別の問題のように思わ
れた。だがマサオには知子の励ましの言葉がなんとなくうれし
かった。
混雑する駅前まで来ると二人は何気なく別れた。
第三部に続く
* * * * * * * * * * * * *