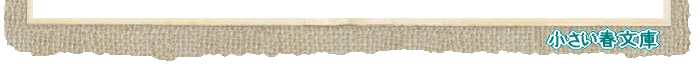もうこうなったら、勉強して勉強して勉強しまくって、テストの鬼になってやる。
いまに見てろ、ぜったいにみんなを見返してやるから、、、、
+ + + + + + + + + + + + + + +
帰り道がおもしろい
はだい悠
+ + + ++ + + + + + + + + + + +
いつ頃からだろうか?一人娘であるレイにとって、父親であるコウジと一緒の食事が、居心地の悪いものに変わっていったのは。
今日も、父を交えての久しぶりの夕食であったにもかかわらず、レイは一言もしゃべることなく、さっさと食べ終えると、急ぐようにして食卓を離れ、二階の自分の部屋に閉じこもってしまった。
きっかけは、レイが中学一年になった頃にさかのぼる。
あるとき、レイが、それまでのように日頃から思っていることを、リラックスした気分で,両親に話しかけながら食事をしていると、父親のコウジが、それまで一度も見せたことがないような不機嫌な顔をして、
「レイ、行儀が悪いよ、食べながらくだらん話はしないの。もう子供じゃないんだから」
と、しかりつけるように言った。
あまりにも突然のことだったので、レイは面食らい沈んだ気持になった。
レイにとってそれは、ディズーニランドに出かける日に、快晴だと思って外に飛び出たのだが、西の空に不吉な黒雲を発見したような気持だった。
でも、レイが、父コウジを避けるようになったのは、それだけではなかった。
レイが小さいころからずっと感じていた安心感のようなものが、なぜか最近まったく感じられなくなり。
いや、それどころかむしろ、自分を拒絶するような圧迫感のようなものを、レイは感じるようになっていたからだ。
レイは、いったん部屋に戻ったが、居間に、今日買ったばかりで、夕方テレビを見ながら読んでいた漫画本を置き忘れていることに気づいたので、それをとりに再び部屋を出た。
食堂に前を通り過ぎようとしたとき、レイは思わず歩みを止めた。
なぜなら父コウジと母サチエが話している会話の雰囲気が、レイを不安な気持にさせるものがあったからだ。
それはあの不吉な黒くもがどんどん広がっていく感じだった。
レイは思わず聞き入った。
「下がりっぱなしって感じ」
「いったいなにを考えてんだろう。最近、なんかぼやっとした顔してない。普通中学生ぐらいだったら、もっと、はつらつとしていない。夢と希望にあふれたような目をしてさ。ちゃんと環境は整えてあげてやってんだから、あとは本人のやる気次第なんだよ。勉強に必要なものはすべて買ってあげてやってるんだろう。いったいなにが不満なんだろう。なにか悩み事でもあるのかなあ。
「ないとおもうけど。もしあるならきっと話すはずよ。隠しておくような子じゃないから」
「いじめにでもあってんじゃないの?」
「最近良く話したことないけど、たぶん、ないと思うわ。だって、小さいときにいっしょに誕生会をやった子供たちの話が頻繁に出るくらいだから」
「クラブ活動のほうはどうなの、うまくいってるの?」
「なんか、やめたみたいなの、最近早く帰ってくるから」
「それじゃ、成績が下がってくるのはちょっと変じゃない。その分ちゃんと勉強してるんだろう。なにか、他に才能があると良いんだけどね。スポーツができるとか、歌がうまいとか、抜群に頭が良いとかさ、あの子みんな中途半端なんだよね」
「そんなにできなくても良いから、せめてもう少し女の子らしいところがあれば良いんだけど。でも、いまのままじゃあんまり期待が持てそうにないしね」
「とにかくレイは勉強で頑張るしかないんだよ。わたしは仕事で忙しいから見てやれないけど、お母さんはしっかり見てないとね。来年はいよいよ受験なんだから」
レイはなんとなく食堂の前を通りづらくなったので、とりあえずいまは、自分の部屋に戻ることにした。
「、、、、ってことは、あたしはブスッてこと、頭が悪いってこと、なんてこと言うんだ、親のくせして。小さいときは可愛い可愛いって言ってくれたじゃない。それでさあ、あたしはずっと自分のこと可愛いと思ってたのにさ。それはないぜよ、いまさら。それにさ、なにかできると、すぐさ、レイちゃんは天才だ、天才だ、と言って誉めてくれたじゃない。学校の成績が良いと、将来はお医者さんになるのねって言ってよろこんでくれたじゃない。だからあたしいっしょうけんめい勉強して良い子でいたじゃない。それなのにさ、なあんだよ。中途半端だなんて、おまえたちの子供じゃないか、、、、」
と、レイは心の中でつぶやきながら、静かに、でも、こきみ良く階段を上がり自分の部屋に入った。
だが、少しも勉強する気になれず、いつものようにベットに横たわった。
そして、あの不吉な黒雲がどんどん広がっていくような気がして、さらに沈んだ気持になりながら思った。
「、、、、勉強、勉強って、勉強してどうなるの。しない人だっていっぱいいるのに、成績が下がったからってなんなのよ。小学生のころはさ、まじめにやればやるほどみんなが誉めてくれたから、いっしょうけんめいやったんで、ほんとうはさ、こんなこと覚えていったいなんの役にたつのさといつも感じていたよ。あたしはほんとうはさ、勉強なんて好きでもなんでもないんだよね。嫌いな鳥の名前と足の形を覚えてなんになるのよ。たし算やひき算がはやくやれたからっていったいなんの役に立つんだよ。さっぱり判らないよ。おかあさんだって、大学まで十年間英語を勉強したっていうのに、ぜんぜん喋れないじゃないか。おとうさんだって、大学で物理を勉強したのに、なんで公務員なんかやっているのよ、勉強したことなんの役にも立っていないじゃない。 ほんとうはさ、あたし中学に入ったころ自分のことまだ頭が良いと思っていたからまじめに勉強したんだよ。それで成績はずっと上位だったけど、でもさ、いつのまにかに下がり始めてさ、そのうちにだんだんついていけなくなったんだよね。国語と社会と理科はそうでもないけど、英語と数学がだめなんだよね。いくら勉強しても英語が伸びないんだよね。いや伸びるどころかかえって下がるばっかりだったよ。どうして発音記号とかアクセントの位置とかを覚えなければいけないのさ。 ひどいもんだよなあ、自信がなくなるとさ、普段は簡単にできるような問題でも、なぜかあせって難しく考えるようになって、間違えたりするんだよね。それでますます点数が悪くなるばかりだったよ。それから数学は前から苦手だったから、それだとくに、いっしよう懸命勉強したんだけど、どうしてもテストの点数がついてこないんだよね。ゆっくりと考えればたいていの問題は解けるんだけど.テストの時間内ではいつも半分ぐらいしかできないんだよね。それでいつも五十点ぐらいなんだよ。時間があれば絶対百点まちがいないのにさ。それで自信なくしてさ、ますます苦手意識が強くなってさ、勉強する気がなくなったんだよね。いいじゃないか、時間がみんなの倍かかったって、最後に解ければそれで良いじゃないか。普通二分で解ける問題を四分かかったからって、あたしが生きていく上でなにが問題があるの、さっぱりわからない。でも、点数が悪いとやっぱり、やる気なくしちゃうよね。それじゃ成績が下がるのも無理ないか。ああ、あたしなんかなりたいものがあったら、そのために勉強するんだけど、なんにもないもんね。あたしにはいったいなにが合ってんだろう。みんなは良いよなあ、ものすごく勉強ができる子、スポーツが得意な子、人気がある子、人前で思ったことをはっきりと言える子、あたしにはなんにも自信がないよ。あういうのをきっと個性って言うんだろうね。でもあたしの個性っていったいなんだろう。さっぱりわからん。みんながうらやましいよなあ。もっとあたしにも自信が欲しいよお、、、、、」
そう思っているとレイは、突然寂しさにおそわれ、それ以上なにも考えられなくなってしまった。レイにとってその寂しさは、なにも写らなくなってザアッーと言ってるだけのテレビ画面を見ているような感じだった。
そう言えばこの感じ、つい最近あったような気がしたとレイは思った。
それは四五日前、クラスの女友達と話しているときに起こったことだった。
レイにとって、彼女たちは、それまでは思ったことをなんでも言える間柄だったが、みんながみんな同じことに興味を示したり、同じような意見を言ったりすることに、なんとなく不自然さを感じていたので思わず、
「あのさあ、みんなさあ、真似することないジャン、それぞれ自分の好きなことすれば良いじゃん」と言うと、みんなの表情がいっせいに凍りついたように止まり、ほんの一瞬沈黙が訪れたのだった。
そのときレイは、目の前の風景がふにゃふにゃと歪んだように見え、そして、あのザアッーと言う音が聞こえたような気がしたのだった。
ベットの上でレイはぼんやりと目を向けたままだったが、しばらくすると、今日起こったいろいろな出来事が頭に浮かんできた。
そして考えた。
「、、、、やっぱり、勉強なんかより先生の表情とか服装を観察してるほうがずっとおもしろいよ。今日は機嫌が良いとか悪いとかさ。それであとでみんなとベチャクチャと話すのがどんなに楽しいか。それにさ、学校にいるより帰り道の方がよっぽど楽しいじゃん。ときどき回り道をして繁華街を通るけど、いろいろな店があって賑やかで楽しそうじゃない。いまは、まだ寄り道ができないけど、いつか絶対に中に入ってやるんだ。それにテレビや漫画だって断然面白いね。良くテレビや漫画は中身がないとか見るとバカになると言うけど、あれは絶対に嘘だね。あんなに人をひきつけるんだから中身がないはずないじゃん。それに比べるとなんて勉強は退屈なんだろう。ちっとも興味が沸かないよ。いままではとにかく良い子ぶって我慢してきたけど、もう限界だね、、、、」
そう思うとレイはさらに寂しさが増したような気がした。そしてこんどは目を閉じてじっとしていた。しばらくするとその耐えがたい寂しさに誘われるように、レイは、今日学校で起こったどうしても納得できないことを思った。
それは昼休みに起こった。
レイがある用事で職員室に入ろうとしたとき、まったく面識のない先生から、
「中に入るときは一礼をしてから入るように」
と厳しく叱責されたのだった。
レイは、はじめは何を言われているのか良く理解できなかったが、だんだんその意味がわかってくると、どうしてそんな必要があるんだろうかという疑問が沸いてきた。
個人的に会ったときなら挨拶するのは当然だろうが、なぜ入るときに職員室全体に向かって挨拶しなければならないのか、それがどうしても納得ができなかった。
レイは用事を済ませたあと、他の生徒たちはどうしているのかと、観察することにした。
するとみんなは人形のように規則的に腰を曲げ頭を下げてから入っていった。
いままで一度も見たことがなかったし、そんなこと誰もやってこなかったはずなのに、なぜいま、あたしはなにも聞いてない、いったい誰が、いつそんなことを決めたんだろう、と思ったとき、レイはふと寂しさを感じたのだった。
レイは、あの時もたしか目の前に見えるものが一瞬ふにゃふにゃと歪み、あのザアッーと言う音が聞こえたような気がしたと思った。
レイは寂しさを伴ってやってくるそのザアッーという音がどうしようもなく気になり始めていた。
そしてレイは、これが、もしかして孤独って言うこと、と、生まれて始めて、孤独と言う言葉を思い浮かべた。おさまらない寂しさに不安を覚えながら。
そのとき、階段を上がってくる足音が聞こえてきた。レイは急いで机に向かい、カバンから最初に手に触れたものを取り出し、それを机の上に広げた。
保健体育の本だった。
母サチエが気をきかしてマンガ本を居間から持ってきてくれたようだった。
レイは母が出ていった後もまったく勉強する気にはなれず、再びぼんやりと前のほうに目をやっていたが、なにか思い立ったようにカバンから筆入れを取り出すと、保健体育の本をわきにどけ、筆入れの中身を全部机の上にぶちまけた。
そして筆入れのごみをティッシュペーパーの上に払い落とすと、今度はえんぴつや消しゴムを一つ一つていねいに入れ始めた。
それが終わると次に、机の上に散らばっていたごみを、大きいもの手でつまみあげ小さいものはティッシュでふき取って、机の上をきれいにした。
そしてまたぼんやりと前のほうに目を向けた。
だが、しばらくすると、突然レイは再び筆入れを手にすると、中に入っているものをふたたび全部机の上にぶちまけると、それを今度は一つ一つていねいにティッシュペーパーでごみをふき取っては、再び筆入れに戻した。
そしてそれをなんどか意味もなく繰り返したあと、最後に消しゴムだけを取り出して、それについている黒いしみを手でこすって取り始めた。
レイはどんなかすかなものでも気になり、なにが何でもそれを取らないと、きがすまない状態になっていた。
レイは黒いしみが完全に消えるまで一心不乱に、こすりつづけた。
やがてレイは、
「なんであたしこんなにイライラしなければならないんだろう」
と言って、消しゴムを壁に投げつけた。
そして、
「ああ、いやなこと思い出した」
と言って、机の上に顔を伏せてしまった。
それは三日前、レイは、まだ買ったばかりの真っ白いブラウスに、いつ付いたのかわからない茶色いしみを、なんとか落とそうとして洗ったのだったが、どうしてもその跡が残り気になるので、再び洗うのであったが、やはり跡が残るので、それなら完全になくなるまでとことん洗ってやろうということで、レイは、その後もイライラした気持をエスカレートさせながら、なんども洗うのだった。そして少しづつではあったが、薄くはなっては行ったが、それでも完璧になくなるというわけにはいかず、レイはそれがどうしても気になり、絶望的な気分におそわれ、ついにはイライラが頂点に達して、いまにも爆発しそうになったことを思い出したからだった。
レイが勉強に身が入らなかったのは家だけではなかった。
学校でも同じことだった。
授業中は前のほうを見てはいるが、だが決して集中しているからではなく、その振りをしているだけで、時折先生を観察する以外は、ほとんどぼんやりとしているだけだった。
ノートをとっとはいるが、それは周囲のみんながそうしているからで、それ以外にやることがないので、仕方なく取っているという感じだった。
だからいつもなんにも頭に入っていなかった。
まじめにやらなければと、レイは思っているのだったが、どうしても興味が沸かず集中できなかった。
でもそんなレイでも、生き生きとした表情をして興味を示すときがあった。
それは先生が本来の授業から脱線して面白い話をするときだった。そんなときレイはほんとうに楽しく感じて、なんか自分が生き返ったような気分になるのだった。
とくに笑える話しのときは、声をあげ手をたたいて笑ったりした。
そんな不安とも不満ともつかない微妙な感情を抱えながら過ごしていたある日、レイのクラスでホームルームが開かれ、中学生にふさわしい服装と行動について、話し合われ、最後に、クラス全員で順番に、短く自分の意見を述べることになった。
それは一人の女生徒からこんな風に始まった。
「わたしはまず校則を守ることが一番大事だと思います」
「決められたことを守らないと、みんな勝手なことをやりだすから、ぼくもそれで良いと思います」
「やっぱり中学生には中学生らしい服装があると思います。だから、たとえばあんまり派手でないものが良いと思います」
「髪を染めたり、ピアスを付けたりするのは中学生にはまだ早いと思います」
「おしゃれをするのは良いと思います。でも大人みたいに化粧するのはまだ早いと思います。それは本当のおしゃれだとは思いません。中学生にとっての本当のおしゃれとは清潔感だと思います」
「わたしは男女交際はまだ早いと思います。まずは勉強だと思います。それをやってから余裕のある人はやっても良いと思います」
「わたしはは学校というのは勉強するところだと思いますから、マンガやゲーム機を持ちこむのは禁止すべきだと思います」
「化粧とかマンガとかは別にかまわないと思います。それより暴力とか、、、、人のものを盗んだりとか、、、、隠れてタバコを吸うのは絶対に良くないと思います」
ここまでぼんやりと、だが冷静に聞いていたレイは、みんな嘘を言っているなと思い少しいらだった。そして思った。
「いったいみんなは、なにを言ってんだろう。ミオのやつ、男女交際は良くないと言ってるけど、普段はあの先輩は格好良いから付き合いたいとか、あの人とあの人はつきあっているとか、男の子のことしか話さないくせにさ、とくに、あの二人はもう大変なことになっているとか言ってさ、いやらしい話になると断然生き生きとしてくるくせにさ。サキだってなんだよ、中学生にはふさわしくないと言いながら、いつも化粧とかおしゃれの話しかしないくせにさ。あたし知ってんだよ、ひそかにおしゃれ道具を持ち歩いてんの」
さらに意見は続いた。
「中学生はまず勉強することだと思います。それから色んなことを自由にやれば良いと思います。あんまりあれはだめだ、これはだめだなんて言うと、個性がなくなると思います」
レイの頭の中は再び活発になった。
「なにを訳のわからないことをこいつは言ってんだ」
と思った。
「個性とはそんなものではないと思います。それはけっして外面的なものではなくもっと内面的なものだと思います」
それを聞いてレイはさらにいらだちながら思った。
「なに言ってんだよ、おまえは。いつもファッションのことしか言ってないくせに。よく嘘言えるよ。何にも考えてないくせに」
そしてレイは、ブラウスのしみを落とそうとして、いまにも爆発しそうになったときと同じような苛立ちを覚えながら、みんなを疑った。
「みんなだってそうだよ、普段はそんなこと考えてないくせにさ。良い子みたいなことばかり言って」
さらにレイは、
「それにしてもみんなは、どうして同じようなことばかり言うんだろう」
と不思議に思った。
だがその一方で、レイは急に不安になりあせり出した。
というのも確実に自分に順番が回ってきて、自分もなにかを言わなければならないことに気づいたからだ。
「なにを言えば良いんだかわからない。みんなと同じことを言うのはいやだ。だってそんなことちっとも思ってないもの。ああ、でもなにかを言わなければ、でも、みんなみたいに良い子ぶってさ嘘をつくのはいやだ」
そしてとうとうレイの番がやってきた。
レイは席から立ちあがっては見たものの、なんにも喋れずに黙っていたが、周囲に視線を感じるようになったので、もうどうにでもなれという気持で話し始めた。
「あっ、ええと、わたし、わたしはなにも考えていません。ですから、どうでも、もうどうでも良いんじゃないですか。こんなことよく言うじゃないですか、嘘つきは泥棒の始まりって。わたしは泥棒になりたくありませんから」
それを聞いて周囲からいっせいに笑いが起こった。
そして担任が笑いをこらえながら言った。
「もう良いでしょう。でも中学生なんだから、これからはよく考えるようにね。そういうのをトンカチ、じゃなくてトンチンカンって言うんだよ。では、つぎ行こうか」
レイはいまにも泣きそうになりながら席に着いたが、周囲の笑いはなかなかおさまらなかった。
レイは恥ずかしさと悔しさで一刻も早くこの場から消え去りたい気持になった。
そして、あたしってほんとうにだめな子かしらと思いはじめると同時に、あのザァッーというテレビ音が頭の中で響き始め、もうその後のことはなにも耳に入らなくなった。
レイの気持は、あの不吉な黒雲がそら一面に広がったかのように完全に沈みこんでしまった。
その出来事があって以来、もうなにをやってもしょうがないと思うようになったせいか、頭の中はいつももやがかかったような状態で、なにも考えられなくなり、気分もばくぜんとした不安からか、ずっと暗く沈んだままだった。
それでも、習慣に従っているだけにすぎないにせよ、レイは時間どおりに起きて学校に行き、食事もきちんと取っていたので、外見的にはそれほど変わったようには見えなかった。
しかし、レイはもう以前のような気安さで、クラスの仲間たちに話しかけることはできなくなっていた。
しかも彼らも、そんなレイに積極的に話しかけようとはしなかったので、レイは学校でも帰り道でも、ずっと独りぼっちになっていた。
そんな鬱屈した日々が続いた後、ある日、クラスが三班に分かれて、市の介護施設にボランティアに行くことになった。
レイたちを引率してくれるのが社会担当の先生だとわかったとき、レイは、あのずっとずっと広がり続けているだけの不吉な黒雲の中に青い切れ間を発見したような気持になり、今日は絶対に楽しいことになるに違いないと思った。
なぜならその社会の先生というのは、歳はそれほど若くはなかったが、授業だけでなく授業以外の話しも大変おもしろいので、レイのクラスだけでなく学校全体で評判が高く尊敬され人望も厚く人気者であったからであっだ。
退屈な教室に閉じこもって授業を聞くより、ボランティアのほうがどんなに楽しいことかと、レイはうきうきしながら遠足気分で出かけた。
施設ではまず、先生よりやや年上の施設長の挨拶があり、つぎに今日はなにをやるか、そして、その他の注意事項を聞いた後、さっそく手伝いに入った。
二時間ほどで終えると、もう一度全員で集まり、施設長からお礼の挨拶があり、そこで今日のボランティアは終了ということになった。
全員で施設長に挨拶をして帰ろうとしたとき、レイはその引率の社会の先生から呼び止められた。そして、その先生はレイをとがめるように言った。
「きみのあの態度はなんだ。施設長の前で腕を組んで話しを聞くとは失礼じゃないか。いったいどういう考えをしているんだ。わたしはどんなに恥ずかしかったか、わかるか。まったくどうしようもない子だね。それからね、前々からきみに言おうと思っていたんだが、きみはあれだよね、わたしの授業中よく大声で笑うよね、あういうのを小娘の馬鹿笑いって言うんだよ。品位も知性のかけらもないね。これからは気をつけてくれよ」
レイは久しぶりに何かをやったという感じで充実した気持になっていたせいか、その内容が期待していたものとはまったく正反対だったので、頭の上に高速道路から車が落下してきたような衝撃を受けた。
気分は底無しに落ち込むばかりだった。
「あんまりよく覚えてないけど、好きなほうの先生でもあったし、それに、ちょっと開放的な気分になっていたから、もしかしたら、そうなっていたかもしれない。でも、そんなに怒られるほど、あたし悪いことやったのかしら、あたしってそんなにだめな子なのかしら」
そう思いながら、レイは他の誰かに問いただしたい気持だったが、あまりにもショックが大きすぎて、もうそんな気力は残っていなかった。
もうあの不吉な黒雲は完全に空をおおいつくして、雨はどしゃ降りになっており、雷鳴もどんどん烈しくなっていくばかりだった。
そのことがあってから、レイの気持はずっと暗く重く縮んだままだった。
だから、レイは学校に行くのもつらく感じるようになっていた。
それでも通いつづけたのは、帰りに寄り道をして、賑やかな繁華街をうろついて、以前から、ぜひ入ってみたいと思っていた店に入ったりして、時間をつぶすことが何にも増して楽しいと感じるようになっていたからだった。
というのも、その開放的で華やかな雰囲気が、レイの鬱屈した気持を紛らすのに十分だったからだ。
その日の学校帰り、レイが繁華街からはずれたアクセサリー店出て、コンビニエンスストアーの前を通り過ぎようとしたとき、斜め前からレイの方に空き缶が転がってきた。
レイがそっちに目をやると、ビルの間の空き地のような小さな公園で、四人の女性とがニヤニヤしながらレイのほうを見ていた。
それはレイの中学の上級生の三人と、レイの隣のクラスの同級生の一人だった。
彼女たちは、このあいだのホームルームの時間で、だれも名指しこそしなかったが、もっとも中学生らしくない生徒として、集中的に批判の対象となっていた生徒たちだった。
彼女たちは全員きらきらと光るチェーンをアクセサリーのように腰に巻いていた。
その中の目のまわりがやたらと黒い子が、ロ元をだらしなくゆがめながら言った。
「へい、トンカチ、トンカチなんだって」
すると他に者は全員バカにしたようにケラケラと笑った。
おそらく少し前までのレイだったら、彼女たちを警戒するあまり、不安と恐怖でどきどきしながら、なにも見なかったかのような顔をして目を伏せてそのまま通りすぎてしまっていたのだろうが、このときのレイは不思議なほど冷静で、警戒するどころか、むしろ彼女たちに親密感を覚えるほどだった。
レイは少しも動揺することなく、笑顔で彼女たちに近づきながら言った。
「なにかようなの?」
「べつに、ないけど。でもなんか楽しそうじゃない、さえないのをからかうのって」
と、他より唇が赤く髪の毛が長い子が、笑いの消えた笑顔で言った。レイは笑みを浮かべて答えた。
「楽しいはずないじゃん。それよりそっちのほうが楽しそうじゃない。ねえ、オイラにもなんか教えてよ」
すると耳にピアスをした子が、再び笑みを取り戻しながら言った。
「はあ、なんだ、やっぱりな。でも話しは判るみたいだな。これはやすいじゃん。ねえ、あたしたちってさあ、いまタバコきれてんの、欲しいんだけどなあ」
「どう、たのめるかな?」
と、白いマニュキュアをした同級生の子が言った。
「なあに、簡単じゃない、そんなこと、オイラに任せてよ。ちょっと時間がかかるけど待っててね」
そう言うとレイは、急いでその場を離れ、走って家に向かった。
レイはこれからなにか楽しいことが起こりそうな気がして気分がどんどん良くなっていくのがわかった。
いつのまにか、あのどしゃ降りの雨を降らしていた黒雲が消えうせ、そらは雲ひとつない青空に変わった感じだった。
「どうしてみんなは、あんなに困った顔して言うんだろう。タバコなんて簡単に手に入るのにさ。困った人の役に立つってこんなに気持が良いもんなんだね」
と、レイは走りながら思った。
自宅に着くとレイはカバンだけを置いてまたすぐ外に出た。
そして自転車に飛び乗ると再び家を離れた。
ちょっと走って、タバコ店の前で自転車から降りると、そこで十個入りケースをひとつ買うと、ふたたび自転車に乗って走り出した。
そのタバコ店は、レイが小さいときから父コウジに頼まれてよくお使いしていた場所だった。
レイは歌をクチずさみながら走りつづけた。
やがてチェーン少女たちがいる公園に着くと、自転車から降り、笑顔で少女たちに近づき、手に持っていたタバコのケースを差し出しながら言った。
「待った、これでも急いできたつもりなんだけど、これで良かったかな?」
チェーン少女たち早や表情をこわばらせながら顔を見合わせたが、ピアスをした少女がレイからタバコを受け取ると、それをカバンに入れながら言った。
「おまえ、なかなかやるじゃない。トンチンカンじゃないな。これ、どこでやったんだ?」
レイが目を丸くして聞いた。
「やったって?」
「どこから盗んできたかってことだよ」
「盗んでなんかないよ、買ったんだよ、子供のときさ、おとう、じゃなくておやじに頼まれてよく買いに行ってたタバコ屋でね」
「なんだ買ってきたんかい、ちょっとびっくりしたよ、まあ、良いか」
「かまへん、あたしたちはもうだめだもんね。もうどの店もこんなには売ってくれないもんね」
「ところでさ、ここはちょっとまずいからさ、もうちょっと奥に行こう。さあ、トンチ、いまからおまえの歓迎パーティーだ。こっちこい」
レイたちが移動した場所は、高い樹木と植え込みにかこまれており、通りからは見えにくかった。
少女たちはレイが買ってきたタバコを吸い始めた。
レイも一本もらい、子供のころふざけて父コウジが吸おうとしていたタバコを、わきから横取りして父の吸うまねをしたことを、思い出しながら、吸っては吐き、吸っては吐いた。
「トンチは、まだまねだけでいいよ」
と、赤い髪の毛の女の子が言うと、目の周りの黒い子がロをはさんできた。
「ねえ、少し塗ってみる」
レイが躊躇していると、ピアスの女の子が言った。
「ちょっとまって、トンチはこのままで良いよ。なあ、トンチ。おまえには、まだ頼みたいことがあるんだけど」
と言って、カバンから五六冊のマンガ本を取り出すと、それをレイに差し出しながらさらに続けた。
「ねえ、これを駅前の本屋で売ってきて欲しいんだけど、良いかな?」
「うん、良いよ、簡単じゃん。まかせて」
そう言いながらレイはマンガ本を受け取ると、急いで自転車のあるところまで行き、そしてふたたびそれに乗って走り出した。
しばらくして、レイが本を売った代金を持って、そして少し息を切らしながらも、にこにこ顔で戻ってくると、チェーン少女たちは声をかけ笑顔で出迎えてくれた。
ピアスをした子がレイから本の代金を受け取りながら、不思議そうな表情で言った。
「店の人になにか言われなかったか?」
「うん、なんにも、どうして?」
そう言いながら笑みを浮かべるレイを見て、他のものたちはいっせいにレイに話しかけてきた。
「おまえは、ほんとうに使えるやつだなあ」
「良い度胸してるよ」
「これから絶対にいけるね。トンチは」
「もう完全に仲間だなあ。トンチは。いや、もうトンチじゃない、なんていったっけ、マヨ、」
「レイっていうんだ」
「レイか、これからはレイって呼ぼう。アイ、これでなにか買ってこい、あそこのコンビニで。きょうは特別だからな。さあ始まるぞ、レイの歓迎パーティが」
目の周りが黒いアイが、その場を離れると、他の者たちは葉の落ちたイチョウの木の下に移動した。
赤い髪の毛の子がレイに言った。
「あたしはケイよ」
そしてピアスをした子のほうを見ながら、
「こいつはサトミ。それからこいつはマヨ。知ってたかな。それから、いまコンビニにいっているのがアイよね。あっ、あそこが良いんじゃない」
と言いながら、二重三重に積み重なったイチョウの葉で絨毯が敷かれたようになった地面を指差すと、そこに行って腰をおろした。
他のものもケイに従って丸くなって座った。
アイが戻ってくると、買ってきたものをみんなの前に広げた。
缶ビール二本、ジュース三本、そしてポテトチップ、チョコボール、マシュマロ、それぞれひと袋づつ。
ピアスのサトミが缶ビールを手に取りながら言った。
「さあ、いまからレイの歓迎パーティだ。みんな楽しくやろうぜ。さあ、好きなものを取って、いやぁ」
その最後の言葉を掛け声のように、みんなで叫んだあと、子供のような笑顔で楽しそうに飲み、そして食べ始めた。
レイはみんなが地べたに座って、とても開放的で、生き生きとしているのを見て、自分もますます伸び伸びとした気分になっていった。
アイが言った。
「ねえ、あたしって、いつもあそこでつまづくんだけど、どうしてかしら?」
「足が太いからじゃない、重くって上にあがんないからじゃない」
「いや、違うね。頭が大きいからじゃない。それで前につんのめるんだよ」
「そうかな、あたしってさ、これからなにか食べれると思うと、つい急いんじゃう見たいなんだよね」
「ねえ、もう少し隠したほうが良いんじゃない。それじゃ道路から丸見えよ」
「だいじょうぶさ、見えやしないよ。仮に見えても、あたしたちに注意をする人間なんてどこにもいやしないさ」
「ねえ、あそこのレジの女さ、ちょっとむかつかない。あたしが買ったものじっと見てるんだよ。こっちはお客だよ、なにを買ったって自由じゃん。ほんとうにむかつくよ」
[あのアルバイトね。他の客のときは、にこにこしてるくせに、あたしのときはブスッとしているの、マジ気分悪いわ。なんか差別されているっていう感じだもんね」
「いくつぐらいなの?」
「たぶん高校生ね、なまいきだよ」
レイが少し興奮して言った。
「なまいきなら、やっつけちゃえば良いんだよ。高校生だからって関係ないよ。こっちはいっばいなんだから、ボコボコにしちゃえば良いんだよ」
「そうだよ、呼び出してさ、みんなでかこんでさ、殴っちゃえば良いんだよ」
「うん、そうそう、こうやって蹴飛ばしちゃえば良いんだよ」
みんなのびのびと自由に喋っているのを見てレイは、こんなすばらしい世界があったなんてと思うと、はじけるように開放的な気分になって行った。
そしてあのブラウスのことなど完全に頭から消え去ってしまっていた。
また、あのザァッーというテレビ音もその鳴り響く気配すら完全になくなっていた。
そのとき、植え込みの陰に子猫を見つけたマヨが叫ぶように言った。
「みんな見て、子猫よ。可愛い。こっちにおいでよ。こわくないから。なんかレイみたいね」
そう言いながらマヨは立ちあがって子猫に近づいて行った。子猫は少しおびえたような表情をしてはいるが決して逃げようとはせず、マヨに抱きかかえられるままになった。
「ねえ、どうしたのかしら、捨て猫なの?可愛いなあ、あっ、こんなにやせてる。なにか食べる」
そう言いながら席に戻ってきたマヨは子猫をひざの上において、食べ物をロ元まで運んでやった。
「あら、食べないの、おなかへってないの?」
「なんかものすごく汚いって感じ、においそう、あたしいやだ」
「ほんとうだ」
「ねえ、さっき、オイラみたいだって言ったけど、それってどういう意味なの?」
「どういう意味って、なんとなくそう思ったの」
「顔の四角いところが似てるからじゃない」
「可愛いからださ」
「えっ、まさか、、、、」
それを聞いてみんな引きつるように笑った。
レイも笑ったが、ほんとうはいったいどこが似てるんだろうと不思議だった。
でも、こんなに楽しいことは生まれて初めてだと云うぐらいに楽しかった。
黄金色の夕日が木々の間から、レイたちを照らしていた。
レイの少し開きかけていた好奇心のトビラは、いまや完全に開け放たれていた。
レイは思ったこと感じたことを包み隠さずに自由にはなすことの喜びを全身で感じていた。
ケイが少し興奮気味に話しつづける。
「、、、、あれは絶対に嘘だね。よく大人が言うじゃない、正直に言えば許してやるって。でもさ、あたしさ、小学生のとき間違って校舎の窓ガラス割ったのね。黙っていれば判らなかったのね、だって誰も見ていなかったから。でもあたし正直に言ったの、先生に。そしたら、おまえはバカだクズたとか言われて、ものすごく怒られたの、そのうえ弁償までさせられたのよ。その日からあたしは、もうどんなにあたしが悪くても絶対に正直に言わないって決めたの」
「あたしんかさ、ちょっと前にさ、財布拾ったのね。それを正直に届けたらさ、先生がしつこく聞くのよ、いつ、どこで、だれと一緒に居たときに拾ったんだって。まるであたしが盗んだような言い方をしたのよ。もう、ほんとうにむかついた。だからこれからは絶対に届けないもんね」
「そうだよね、先生なんか信用おけないもんね。あたしね、中学生になったとき体操着がなくなったときがあったの、それで先生に探して欲しいって言ったら、先生は、おまえ、家に忘れてきたんじゃないかって、全然信じてくれないの、そんなこと絶対にない、なくなったのはあたしのだけだから、きっと、だれかに盗まれたのだと言うと、どろぼうをを捕まえるのは警察の仕事だから学校ではそういうことはできないって言うの。それで、もし、どうしても見つけて欲しいんだったらで警察に届ければって言うの。あたしひとりでね。いつもはさ、なにかあったら、学校に届けろって言っているけど、でも、いざ届けるとなんにもやってくんないだもんね。あのとき、こんなひどいことも言ってた。おまえといっしょに探せるわけないだろうって」
「まだ良いよ、それくらい。あたしなんか蹴られたんだよ。目障りだとか言ってさ。思いっきりにらみつけてやったけど、平気な顔してんの。ほんとうにむかついた。
「あたしもやられたよ。いたかったなあ」
「なぐられたの?」
「いや、なぐられはしないけど。あたしがちょっと反抗的な態度を取ったら、生意気だとか言って、ロッカーとロッカーの間に押し込まれてさ、げん骨で胸をぐぅっとおしつけられたんだよ。痛くて息が止まりそうだったよ」
「蹴飛ばして逃げれば良かったじゃない」
「だめだよ、狭いしさ、それに相手は大きい体を押しつけてくるんだよ。ほんとうに苦しかった。でも負けたくないからさ、痛いの我慢して、おもいっきりにらみつけてやったら、負け犬みたいな情けなさそうな目をしていたっけ」
「そんなのまだ、ましじゃん。あたしなんてクソジジィに殴られたんだよ。おまえがお金を取ったんだろうって。ボカンボカンよ。いつもはさ、酔っ払ってて役立たずのくせにさ」
「ほんとうに盗ったの?」
「あれ、あのときは盗ったんだっけ、、、、忘れたよ」
そのときレイがここぞとばかりに話しはじめた。
「そうだよね。大人なんて、とくに男はさ、見た目じゃ全然わかんないよね。言うこととやることが全然違うって感じ。あの社会の先生いるじゃん、みんなに人気があってさ話が面白くってさ、あたしとっても好きだったの、でも、このあいださ、つまんないことでグチュグチュ言うのよ、ほんとうに小さいんだから。がっかりしたよ。なんなんだよ、大人って。うちのお父さんって言うか、クソジジィなんだけど、そのクソジジィとクソババァがとにかくうるさいんだよね。勉強しろ勉強しろって。小さいころはよくディズニーランドとか遊園地につれて行ってくれたんだけど、最近は全然だもんね。いったい勉強してなんの役に立つんだろうね。聞きたいもんだよ。絶対に役に立たないね。だって、クソジジィや、クソババァをみてればわかるじゃん。まじめに勉強してもあんな程度じゃ意味ないよ。変に期待されてもこっちが迷惑なんだよ。それにさ、ちょっとしたことでいちいちうるさいよね。あれはだめこれはだめって、もう子供じゃないんだから、判ってるって言いたいよね。だからさ、最近全然聞いてないもんね。完全無視って感じ。ねえ、みんなのうちもそうなの?」
「ああ、おなじようなもんさ。それがいやだから、みんなここにいるんじゃない」
「そんなんじゃ、あたしんちなんか、なんて言えば良いの、クソジジィなんかいないもん。いつもどっかに出かけててさ、家で顔を合わしたことなんてないもんね、かってにやってる感じだからさ、こっちだってかってにやるしかないもんね。だって、あたしは自由なんだもの」
「そうだよね、自由だもんね、自由っていいもんだよね」
「あたしさ、引きこもる人の気持わかんないの、なんで家にいるのか、あたしだったら絶対に外に出るわ。そして、好きなことやって、めちゃくちゃ遊ぶの」
「ねえ、レイ、あたしたちっていうのは、やりたいことはなんでもやるのよ。でも他の子たちみたいにオヤジとつき合うことなんか絶対にしないから」
「あっ、だめ。この子ったら全然食べないで、眠ってしまったみたい」
「どうしたの、ミィちゃん」
レイは、いまのこの楽しい時間が永久に続くような気がした。
そして、これからもずっとみんなと友達でいられるような気がした。
やがて日が沈み、ネオンサインがいちだんとその輝きを増しはじめたころ、レイは明日また絶対に遊ぼうねと誓い、みんなと別れた。
レイが家に帰ると。夕食の準備ができていたので、レイは母サチエといっしょに食べ始めた。サチエが言った。
「ねえ、レイちゃん、もう寒くなってきたから、もう少し早く帰ってきたほうが良いよ。ところでさっき、ミチルくんのお母さんから電話があってね、今日の夕方、公園で不良少女たちがたむろをしているのを見たんだって、その中にレイちゃんに似た子を見かけたって言うんだけど、どうなの?」
「ええ、なにそれ、不良少女?それってなんか人違いじゃないの?おかあさん、、、、」
と、レイはなんにも知らないかのように少しかん高い声で、そして最後のほうは少し甘えるような声で。レイは何事もなかったかのようにいつものように食べつづけた。
父コウジが帰ってきた。コウジがいきなり食堂に入ってきて言った。
「あれ、今日はだれかお客さんがあったの?」
「なかったけど、どうして?」
「うん、なんか、タバコの匂いがするんだけど、いま禁煙してるから、ちょっと、過敏になっているのかなあ」
「それより、今晩遅くなるはずじゃなかったの?」
「いや、思ったより早く済んでね」
レイは普段どおりにすみやかに食事を済ませる都、急ぐように食卓を離れ自分の部屋に戻った。
翌日、レイは学校に行くと、早くみんなと会いたいという思いから、さっそく朝から彼女たちが居そうな場所にねらいをつけて、その姿を探しつづけたが、その短い休憩時間ではなかなか見つけることはできなかった。
昼休み。レイはようやく四人を発見した。
そこは人目につく廊下の曲がり角で、レイにとっては意外な場所だった。
彼女たちは横一列に並んで壁に背をもたせかけて話しこんでいた。
レイはほっとしたような笑みを浮かべてみんなに近づいて行った。そして四人と同じように壁に背をもたせかけた。
だが四人はレイが近づいて行っても、表情や態度を少しも変えることなく、それどころか他人を見るような目でチラッと見ただけで、なんにも話しかけようとしなかった。
そんな気まずい雰囲気がしばらくつづいたあと、サトミがポケットから財布を取り出して、その中から千円札を三枚引き抜くと、それをレイに渡しながら言った。
「これ、昨日のタバコ代、返すから。それからさ、これから、あたしたちに会っても、もう二度と声をかけないで欲しいの、わかった」
そう言い終わると、サトミはなにごともなかったかのような表情で、レイから離れて行った。他の三人も黙ってそれに従った。
レイは、これはどう言うことなの?いったいなにがあったの?と、激しく自分に問いかけながら、その場に立ちつくしてしまい、しばらく動くことができなかった。
午後の授業が始まっても、レイはなにも考えられずにぼぉっとしていた。そして授業の終わり頃になって、レイは重大決心をした。
「そうなの、そういうことなの。みんなわたしのこと邪魔者扱いするなら、あたしにも考えがある。もうこうなったら、勉強して勉強して勉強しまくって、テストの鬼になってやる。いまに見てろ、ぜったいにみんなを見返してやるから」
それから何日か後のある日。
レイは母と二人で夕食をとってした。
母サチエが心配そうな表情で話し始めた。
「ねえ、レイちゃん。レイの学校の女性徒たちが傷害事件を起こしたのって聞いてる?」
「なんか、騒いでいるみたいだけど」
「どんな子たちなのか、あなた知ってる?」
「ふうん、知らない」
「なんか、コンビニでアルバイトしている子を、集団で殴ったり蹴ったりしたんだって。中学生の女の子が高校生をよ。どんな子たちか、ほんとうに知らない?」
「もう、知らないってば、おかあさん、変なこと言って気を散らさないでくれる。もうじきテストがあるんだから」
そう言って、レイは何か考えごとでもするかのように上のほうに目をやった。
今のレイにはテストのことしか頭になかった。