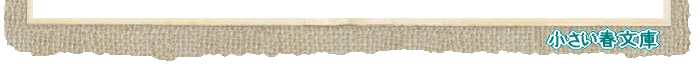青い精霊の森から(2部)
はだい悠
* * *
たとえ深夜になっても決して人通りの衰えることのない交
差点では、すでに多くの人々が足を止めてその中心に眼を向
けていた。
そこには五人が期待したとおりに、二日前に公園の広場に
突然出現したあの男がバイクに乗っていた。バイクの男はま
るで楽しむかのように、交差点を通り抜けようとするものを
妨害するようにゆっくりと円やS字を描きながら走りまわっ
ていた。そのため車は渋滞し始め、クラクションは鳴り響き、
騒然とした雰囲気になり始めていた。しかしバイクの男は周
囲からどんなに罵声を浴びせられてもまったくひるむ様子も
なく、車の通行を妨害するように自由自在に車のあいだを走
りまわっていた。その表情はトキュウの眼には笑みを浮かべ
た余裕のあるものに見えた。やがてパトカーのサイレンが聞
こえ、まもなく数名の警察官が現われた。彼らはしばらく様
子を見たあと、手分けして四方の交通を止めると、その内の
一人がバイクの男に近寄って話しかけようとした。しかしバ
イクの男は聞こえないのか、それとも無視しているのか、ま
ったく止めようとしなかった。それはまさに何かが起こりそ
うな一触即発の緊張感に満ちていた。
トキュウはその気配を全身で感じ激しく興奮した。なぜな
らトキュウはその何かをひそかに期待していたからだ。その
うちに気体は抑えきれない欲望に変り、興奮はじょじょに不
安と恍惚をはらむようになっていった。
やがてバイクの男は止まった。先ほどの警官がもう一度近
づいた。そしてなにやら話しかけたあと、バイクの男の腕に
手をかけようとしたその瞬間、バイクの男は爆発的にエンジ
ンをふかすと激しく白煙を上げながら急発進した。そのため
その景観をバランスを失って倒れてしまった。しかしバイク
の男は何事もなかったかのように、ふたたび平然と走り始め
ていた。
抑えようもなく高まっていく不安と恍惚感を覚えながらト
キュウは、これから起こるであろう暴力と混乱を熱狂的に思
い描いた。いつのまにか交差点の周囲には多くのパトカーが
道路を封鎖するかのように増えていた。後からやってきた警
察官たちは、逃げられないようにするためか、均等の間隔で
横断歩道に沿って立ってバイクの男を遠巻きに取り囲んだ。
それでもバイクの男は少しも表情を変えずに悠然と走りまわ
っていた。
やがてあまりにも突然バイクはスピードを上げると、道路
を封鎖しているパトカーめがけて走り出した。そして衝突寸
前でバイクは前輪を上げてパトカーに乗り上げると、そのま
まあっという間にパトカーの上を通り越して、どこかへ走り
去って行ってしまった。その瞬間、あとは捕まるだけだと思
っていた群集はどよめいた。トキュウも思わず声を上げたが、
なんて凄いんだろうという言葉が真っ先に頭に浮かんできた。
そして、どうだ凄いだろうという言葉を何度も何度も頭のか
なで呟きながら、なぜか誇らしげな気持ちになっていった。
そしてトキュウた五人は騒然とする交差点をあとにして、一
目散に公園に向かって走り出した。なぜなら、きっとバイク
の男が自分たちを待っているような気がしたからだ。
トキュウは走っているうちに自然と顔がほころび、だんだ
ん愉快な気持ちになって来るのを抑えることができなかった。
そして渋滞にはまってしまった車も、交差点に集まってきた
群集や警察もみんな間抜けでかっこ悪いものに思えてきた。
走りながらトキュウはさらにつぎのようにつぶやいた。
「なんだ役たたずめ、いつもはピカピカに光って猛スピード
で走っているくせに、ジャマなだけどゃないか! 大人も同
じだ、いつもは判ったような顔をしているくせに、あんなこ
とで驚くようじゃたいしたことないな、警察も相当に能無し
だ、いつもは偉そうにしているくせに何にもできないんだか
ら」
五人は公園にやってきた。思ったとおりバイクの男は人影
もまばらな広場に、二日前と同じようにステージのような花
壇の上でバイクにもたれかかるように立っていた。五人は入
り口の階段を降りると、バイクの男に近寄った。そしてゲン
キが真っ先に言った。
「隠れなくてもいいの? 捕まるよ!」
サンドが笑みを浮かべながら言った。
「だいじょぶだよ、また逃げれば良いじゃないか、あんなヘ
ナチンポに捕まるわけないじゃないか」
タイヨウが言った。
「ヘナチンポ、ほんとにヘナチンポだ」
バイクの男が笑みを浮かべ語りかけるように言った。
「どうだい面白かったかい、もう少し彼らも本気になってく
れたらもっと面白かったのに、まあ、クライマックスはこれ
からだよ」
そうい言うとバイクの男はバイクから離れ、花壇のヘリに立
って再び話し始めた。
「なあ、みんな判っただろう、やりたいことをやるって言う
のはこういうことなんだよ。ゴチャゴチャシテ、バタバタし
て、ギャアギャアいって、ドカンドカンとなるのがみんな楽
しいんだよ。みんな好きなんだよ。そういうことをするのに
みんなウズウズしているんだよ。みんなほんとうは壊したが
っているんだよ、何でも良いから。お前たちもやりたいこと
やりたいだろう。判るよその気持ち。その前にまあ座れよ」
そういわれて五人は階段まで下がった。そして思い思いにバ
イクの男と向き合えように座った。
ゲンキがバイクの男に言った。
「どうして、あんなにうまいの、どこかで習ったの?」
「習った? 違うね、自然なんだよ。自然にできるようにな
るんだよ。なんだってやりたいと思ったら、自然にできるよ
うになるんだよ。だからさみんなも、やりたいと思ったらな
んでもやればいいんだよ、どうしたい、そんなに不思議そう
な顔してさ、まさかいまさら良い子ぶるんじゃないだろうな、
判ってんだよ、みんな何をやってきたかぐらい、ところで君
の名前はなんていうんだい?」
「ゲンキ」
「君は?」
「タイヨウ」
「君は?」
「サンド」
「君は?」
「ショウ」
「君は?」
「トキュウ」
「君たちは?」
「コウイチ」
「ダイスケ」
「ケイタ」
「君たちは?」
「ミュウ」
「サク」
「レイ」
「モチ」
「マイ」
一人一人の声を聞いているうちに、トキュウたちは自分たち
五人だけじゃないということが判り、よりいっそう自分たち
が大きくなったような気がした。
ゲンキがバイクの男に言った。
「たいちょう、隊長はなんていうんですか?」
バイクの男は表情をこわばらせ首を振りながら言った。
「たいちょう? 笑わせるよ。オレは、サイスでいい、それ
より隊長なんてそんな変な呼び方をするなよ。オレはサイス、
オレは自由なんだから。とにかくオレはちょうのつくのが大
っきらいなんだ。お前たちだってきらいだろう、コウチョウ
とか、シャチョウとか、もっと他にあるな、チョウがつくの
は」
サンドが言った。
「あるあるテンチョウだ」
ゲンキが言った。
「エキチョウ、ショチョウ」
そして次から次へとみんな自由に言った。
「センチョウに、エンチョウ」
「ケンチョウもある」
「シチョウにチョウチョウ」
「ダッチョウにモウチョウ」
「チョクチョウにカンチョウだ」
「ブチョウ、カチョウ、カカリチョウ、ハンチョウ」
あっちこっちで笑いがもれるなか、バイクの男サイスが言っ
た。
「とくにあのエンチョウっていうのはろくなもんじゃない、
大人のなかでも最低の奴らだ」
そのとき少女たちの一人が言った。
「あら、そんなことないよ、幼稚園の園長さん、とってもい
いひとだったよ。ねえ、そうだよね」
「いい人、そうだよ、いい人だよ、でも、みんなの前でちょ
っと良いことやりすぎるんだよ。だからなんだよ。アッ、ち
ょっとみんなには難しすぎたかな。みんなちょっとおとなし
いな、なんか心配になってきた。みんないい子になろうとし
てるんじゃないかな。あれほど決していいことはするなよっ
て言ったのに。いいかい、俺たちは自由なんだ、何でもでき
るんだ」
そのときサンドが話しをさえぎるように言った
「なんかやばいんじゃないか、近くまで警察が来てるみたい
だよ」
ミュウと少女が言った。
「ねえ、サク、あんた見に行ってきて、やばいと思ったらケ
ータイで連絡して」
「うん、いいわよ」
そういってサクは階段を入り口のほうに駆け上がって行った。
サイスが再び話し始めた。
「今まで通りやりたいことやろうよ、食いたいと思ったら盗
んで食ってんだろう、欲しいと思ったら盗んで自分のものに
してるんだろう、面白くないことがあったら何かを壊すこと
ぐらい大したことないよな、もたもたしてる奴見たら蹴飛ば
せばいいんだよな、なにか気に入らない奴がいたらどんどん
文句を言えばいいんだよな、それで良いんだよ」
するとひとりの少女が話しをさえぎるように言った。
「それはイジメだよ、イジメはよくないよ」
「あたし、よく苛められた」
少年たちのひとりが言った」
「イジメは良いんだよ」
「ああ、オレもよくいじめたよ、あれは苛められる奴が悪い
んだよ」
サイスが頷きながら言った。
「だんだんわかって来たようなだな。みんなはもっと言いた
いこと、思ったことをどんどん言って良いんだよ。みんなも
っと怒ろうぜ、もっと切れようぜ、イライラしたら叫びたく
なるだろう、頭にきたら殴りたくなるだろう、それで良いん
だよ」
そのときゲンキが不満そうに言った。
「そんなことやったらすぐ喧嘩になっちゃうよ」
サイスが答えた。
「ゲンキといったなおまえタイヨウに何か言いたいことある
だろう」
「あるけど」
「かくさずにいえよ」
「ちょっとかったるいかな」
「タイヨウ、お前それを聞いて腹が立たないか? 腹が立っ
たら言い返せよ」
「いや、べつに、腹はたたないよ、ほんとだから」
「なかなか良いじゃないか、それでいい。オレがいいたいの
は腹が立ったらどんどん喧嘩しろということだ。何も押さえ
ることなんかないんだ、もし腹が立っていなかったらそれで
良いのさ、何か言いたいことがあったら自然に言えば良いの
さ。いいかい、我われは自由なんだ、何でもできるんだ、遠
慮することはない、我われは食いたいと思ったら盗んで食っ
てんだ、欲しいも思ったら盗んで自分のものにしてるんだ。
それなら言いたいことを言うくらいたいしたことないだろう。
ブス、チビ、バカ、落ちこぼれ、とろい、キモイか、なあ、
どうだ」
少女たちの誰かが抗議するように言った。
「それって差別じゃない、良くないよ」
サイスが初めて笑みを見せずに話し始めた。
「甘いな、何にもわかっていないな、どうしてそんなに話し
のうまい大人みたいなことを言うんだ。
それじゃ何かい、
差別が良くないって言えば、差別がなくなるとでもいうのか
い。
エコヒイキが良くないって言えば、エコヒイキがなくなると
でもいうのかい。
イジメが良くないって言えば、イジメがなくなるとでもいう
のかい。
盗みが良くないって言えば、盗みがなくなるとでもいうのか
い。
暴力が良くないって言えば、暴力がなくなるとでもいうのか
い。
戦争が良くないって言えば、戦争がなくなるとでもいうのか
い。
狼に羊を襲うなといえば、もう羊を襲わなくなるとでもいう
のかい。
ブスは良くないといえば、もうブスで無くなるとでもいうの
かい。
バカは良くないといえば、もうバカで無くなるとでもいうの
かい。
そんなこと背広を着てネクタイを締めた大人の言うことだよ
。いいかい、大人ってどんな奴らかみんな知っているだろう。
なあ、思い出そう世、今までにあったことを。
お前たちのなかにはきっと、拾い物だといって届けたのに、
盗んだのだろうと、大人に言われたものがいるだろう、なあ。
お前たちのなかにはきっと、初めて規則を破ったのには、い
つも破っているかのように、大人に言われたものがいるだろ
う、なあ。
お前たちのなかにはきっと、生徒には人気のある先生だとい
うことで、せっかく相談に言ったのに、その先生からゴミく
ずのように無視されたものがいるだろう、なあ。
お前たちのなかにはきっと、大人から言われたとおりにやっ
ていたのに、それでも大人から怒られた者がいるだろう、な
あ。
お前たちのなかにはきっと、人間よりも猫や鳩の方を大切に
する大人を見たことがある者がいるだろう、なあ。
お前たちのなかにはきっと、子供のためとはいいながら、ほ
んとうは自分のことしか考えていない大人を見たものがいる
だろう、なあ。
お前たちなかにはきっと、なんだかんだ言っても結局最後は
暴力で抑える大人を見たものがいるだろう、なあ。
お前たちのなかにはきっと、他人が失敗すると子供のように
喜んでいる大人を見たものがいるだろう、なあ。
お前たちのなかにはきっと、子供たちのように苛めあってい
る大人たちを見たものがいるだろう、なあ。
お前たちのなかにはきっと、動作がのろいというだけで、ま
るで怠け者のように言う大人を見たものがいるだろう、なあ」
そのとき突然ミュウが話しをさえぎるように言った。
「ねえ、今、サクから電話があった。警察がそこまできてる
って、逃げたほうがいいよ」
サイスが頷きながら聞いた後再び話し始めた。
「オレは判ってんだ、ほんとは皆は大人より賢いってことを。
みんなは本当は、真面目そうな顔をして話す大人ほどどっか
信用できないと思ってんだろう。みんなは本当は、どういう
ことを言えば大人が喜ぶかっていうことを知っているんだろ
う。大人なんてそんなもんだよ。だからいいかい、とにかく
みんなはかんじたとおりにさ、思ったとおりにさ、やりたい
ように行動すればいいんだよ。決して自分を抑えるな、誰に
も遠慮するな。もし身を歩いていて、大きな犬に吼えられた
らどうする、びっくりするだろう、それからどうする、殺し
てやりたいと思うだろう、それでいいんだ。もし、お金がな
かったらどうする、腹が減るだけだろう、それからどうする。
盗んで食うだろう、それでいいんだ。もし、どうしても仕事
がなかったらどうする、生きていけないよな、それではどう
する、なんでもやるしかないよな。それでいいんだ。誰にも
文句は言わせねえ世、なぜなら我われは自由なんだ、何でも
できるんだからな。鳥だって魚だって自由にやってんだ。我
われ人間に出来ない訳ないよな」
そう言うとサイスはバイクにまたがりエンジンをかけた。そ
して言った。
「とにかく、いいことは決してするなよ。それから今日静か
になったらまた会おう」
そう言うとサイスはステージのような花壇からたくみに飛び
降り、林の奥へと消えていった。
呆然と見送っているトキュウにショウが話しかけた。
「なあ、トキュウ、お前楽しそうにしているけど、あいつの
言うこと本当に判ったか? オレには良く判らなかった」
トキュウが答えた。
「オレにもわからないよ。でも、こうやって皆といっしょに
聞いていると、なんかとても気持ちがいいんだ。夢を見てる
みたいでさ、こんな気分は始めてた。いいじゃないか、とに
かく何か楽しいことが起こりそうじゃないか」
その後夜がさらに深まるにつれて警察の姿は次第に見えな
くなっていた。そして繁華街の喧騒も人通りもおさまり、町
が落ち着きを取り戻した午前三時ごろ、トキュウたちは予告
どおりにバイクの男サイスと合流した。
しかし今度はサイスはバイクには乗らずに歩いて現われた。
そしてサイスを先頭にして若い男たちだけが、同道と胸を張
り、周囲に眼を配りながら自信を得た肉食獣の群れのように
ゆっくりと歩いた。
やがて隣町の繁華街についた。そこは大きな駅を中心に賑
わっている町だった。駅の周囲には深夜にもかかわらずおび
ただしい数の自転車が放置されていた。
人影もほとんどなくなった通りを歩きながらサイスは突然、
ジャマなんだよ、といって一台の自転車をけり倒した。する
と隣に並んであって自転車がドミノのように次々と倒れてい
った。そしてサイスはトキュウたちを振り返りながら言った。
「たしか言ったよな、ジャマなものは蹴飛ばしてかまわない
って、まあ、こんなもんだよ。どうだい、みんなもやって見
たいと思わないか、ここの自転車が一台残らず倒れているの
をさ、たまには変わった風景もいいもんだぜ。さあ皆で手分
けしてけり倒そうじゃないか、すっきりするぜ」
若者たちに何のちゅうちょもなくサイス言うことにに従っ
た。けり倒す様は人によって違っていたが、みんな軽快で楽
しそうだった。さすがに人影が現れたときには控えたが、見
えなくなるとここぞとばかりに容赦なくけり倒した。
やがて縁の周辺のすべての放置自転車がけり倒された。そ
の様子は何か得体の知れない巨大な力が働いたかのようだっ
た。そのあいだトキュウは何も考えずに他の誰よりも俊敏に
動いた。とにかく仲間いっしょに何かをやっていることが楽
しくてたまらなかった。そして夜明けとともに一群は解散す
ると、みんなそれぞれのねぐらに帰って行った。
それから二日後の深夜、サイスとトキュウたちは群れた。
そして午前三時になると再びサイスを先頭にして男たちだけ
でどこへともなく歩いて移動を始めた。着いたのは二日前と
は違う町だった。そこもやはり駅を中心としたにぎわってい
るところで、駅の周辺にはおびただしい数の自転車が放置さ
れてあった。しかし今度はすべてのタイヤから空気を抜くこ
とだった。トキュウはサイスの言葉をひとつの秘密指令のよ
うに受け取り、何も考えずに楽しそうに行動した。そして誰
にも見つからぬように逃げた。
それから二日後の深夜、サイスとトキュウたちはまた動い
た。今度はある日解けない通りの両側に隙間なく注射してい
る自動車のすべてのタイヤをナイフで傷つけパンクさせた。
そして誰にも見つからぬように逃げた。
その次の日、トキュウとショウは空き家に無断で住み込ん
でいるところを発見され追い出された。しかしすぐに代わり
を見つけることができた。それが現在の住処だある。
その次の日、サイスとトキュウたちはまた動いた。今度は
ある場所に生えてある木を切り倒すことだった。そこは道路
のようでもあり広場のようでもある場所だった。トキュウた
ちはサイスの用意したのこぎりで子本気を切った。そして誰
にも見つからぬように逃げた。
それから二日後、今度は広い工場の跡地のような場所に忍
び込み、そこにある高さ二十メートルほどのコンクリート製
の煙突を倒すことだった。トキュウたちはハンマーと鉄の楔
を巧みに操り、その煙突を倒し粉々に破壊した。倒れるとき
大音響を上げたが、誰にも見つからぬようにバラバラに逃げ
た。
それから二日後、今度はある場所の幅二十メートルほどの
川に掛かっている橋を川に落とすことだった。それは鉄骨と
ボルトで組み立てられている橋で、長いあいだ使われていた
ようすはなく、ほとんどがさび付き壊れかかっていて正面に
は通行止めの看板が立てられていた。トキュウたちはサイス
の用意したスパナでボルトをはずし橋を川に落とした。そし
て誰にも見つからぬように逃げた。
トキュウはサイスに対して少しも疑念を抱いてなかった。
だから彼の指令を果たすことの目的や意義をまったく知らな
くても、いつでも他の誰よりも忠実に積極的に行動すること
ができた。とにかくトキュウにとって仲間といっしょに何で
も良いから何かをやることが無性に楽しかった。なぜなら、
それはトキュウが町に見い出したはじめての意味であり夢で
あったからだ。
夢は凍結しかかっていたトキュウの心を一瞬のうちに温め、
溶解させ、水のように自由にさせた。さらに夢は、トキュウ
の心を、いざ何かがあると一気に熱くさせながら、やがて激
しく沸騰させて蒸気となって自由自在に形を変えることがで
きるようになっていた。そして今では、今日はいったいどん
なことが待ち受けているんだろうかという、期待感で夢見る
ような毎日を過ごすことができるようになっていた。
太陽は完全にビル群の陰に姿を隠した。
トキュウは体を動かし薄目をあけると、ショウも同じよう
に体を動かし薄目を開けた。二人は目覚めた。そして無造作
にティーシャツを切ると、二人はできるだけ音を立てないよ
うにしながら、コッソリと無人ビルを抜け出し公園に向かっ
た。
初夏の夕暮れの蒸し暑い通りは、二人にとってちょっとの
あいだ我慢するだけでよかった。やがて公園に着くと水道の
栓をいっぱいに開けて、あたり一面にしぶきを撒き散らしな
がら体を洗い、そして冷やした。ちょうどビルの隙間から漏
れた金色の夕日を浴びながら。
最近の二人の一日の始まりは、いつもこの爽快さから始ま
っていた。
ショウはトキュウに軽い合図を送るとどこかへ行った。そ
れは今までのように食べ物を手に入れてくるという合図だっ
た。
トキュウはまばらに人影が見える階段を下まで降りきると
、そこに腰をかけた。そして広場の中央に満ち足りた眼を向
けた。三十分もすると、ショウがプラスチック容器に入った
弁当をいくつか手に持って戻ってくると、その内のひとつを
トキュウに渡しながら言った。
「今日は本当についてたな一番いいやつ手に入れたよ。
トキュウはふたを開けながら言った。
「ついてたって?」
「今日はオレが一番早かったみたいなんだ。いつもは誰かが
先に来て一番いい奴を持っていくんだ」
トキュウが不思議そうな顔をして言った。
「よく判らないよ、言ってることが」
「だから今日はオレが一番早かったってこと、それで一番い
いやつを持ってきたってこと」
今度はトキュウは首をかしげながら言った。
「へえ、なに、するとこれは店から盗んできたんじゃないの
?」
ショウが少し不満そうに言った。
「違うよ、あるだろう、あるところに、賞味期限が切れてさ
捨てられてあるのを、それを持ってきたんだよ」
トキュウが急に声を荒げて言った。
「なんだ、それじゃまるでホームレス見たいじゃないか!
こんなもの食えるか!」
そういってトキュウは弁当を乱暴に放り投げた。
ショウも声を荒げて言った。
「なにすんだよせっかく持ってきたのに」
「今まですっとそうだったのか、盗んできたんじゃなかった
のか」
「ああ、そうだよ、いいじゃないか食えれば、なんだって」
「よくねえよ、俺たちホームレスじゃないんだから、これじ
ゃまるで道に落ちいてるものを食う猫や犬とおんなじじゃな
いか、なさけねえ、そんなの堕落って言うんだよ」
それまであまり表情に出さなかったショウが始めて怒ったよ
うな表情をしてトキュウを睨みつけながら言った。
「よく言えるなそんなこと、お前は何様なんだよ」
トキュウも応えるように睨み返しながら言った。
「なんだ文句あるのか」
「あるよ、なんだ、このやろう」
その瞬間爆発的に沸き起こってくる力でお互いに相手をつか
むと、もつれ合うようにして地面に倒れた。そして激しく筋
肉をぶつけ合いながら地面を転げまわった。
そのとき突如ひとりの少女が近寄ってきてところかまわず
靴で蹴り上げながら叫ぶように言った。
「何やってんのあんたたち、バカじゃないの! こんなくだ
らないことで喧嘩して、止めなさいよ、あんたたち仲間でし
ょう!」
その迫力にときゅうとショウの腕からは自然と力が抜けてい
った。そして力が抜けていくとともに怒りも消えていった。
二人は地べたに座ったまま少し驚いたような表情をして離れ
た。二人はその少女は、サイスとの集まりにほとんど顔を出
していた少女たちの内の一人だと判った。そしてトキュウは
すぐに、仲間からミュウと呼ばれている少女だと気づいた。
ミュウはまだ少し興奮を残しながら言った。
「まったくバカみたい、せっかくの食べ物をこんなにグチャ
グチャにして、もういい判った。あたしんちに来て、さあ、
それを片付けて、あたしに付いて来て」
トキュウとショウは不思議なくらい素直にミュウに従った。
ミュウの後を歩きながらトキュウは、ミュウの撒き散らす
香りに懐かしいものに出会ったような安心感を覚えていった。
十五分ほど歩いて、五階建てのありふれた四角いビルのよ
うなミュウのマンションに入った。部屋は二つあり、生活に
必要なものはすべてそろっているようだった。トキュウとシ
ョウは思わず顔を見合わせた。というのも、ミュウひとりで
住むには少し贅沢すぎると思ったからだ。そのことは自然と、
どのようにしてお金を得ているのかという漠然とした疑問に
つながっていった。そのせいかトキュウとショウはなんとな
く落ち着かなかった。でもそのおかげか、ついさっき取っ組
み合いの喧嘩をしたことなどもうすっかり忘れていた。
ミュウは手に抱えて持ってきた食べ物をテーブルの上に置
きながらいった。
「食べるものはいくらでもあるから、遠慮しないで。まだあ
るから」
そう言いながら台所のほうに言った。やがて再び手にいっぱ
いの食べ物を持って戻ってきた。テーブルの上には、ジュー
ス、牛乳、サンドイッチ、お菓子、缶詰、ハム、ソーセージ、
りんご、グレープフルーツと、一度では食べきれないほどの
沢山の食べ物が並んだ。
三人もう長く付き合っている友達のように打ち解けていた。
トキュウとショウは遠慮なく食べた。その様子を見ながら
ミュウが話しかけた。
「ねえ、あんたたち、サイスと何やってんの? ふっ、言わ
なくてもいいの世、あたしにはだいだい判ってんだから、ニ
ュースでチラッと聞いたわ。たぶん、あれね。でもばかばか
しいけど面白いじゃない。大人たちが真面目な顔をして騒い
でいるのを見るって、なんか、とっても愉快じゃない。ええ
と、あたしはミュウって言うの、あんたはたしかトキュウだ
よね、それからあんたか確かショウだよね。びっくりしなく
てもいいのよ、あたしは案外見かけによらず覚えがいいのよ。
一度聞いたら忘れないの。大人たちはみんなあたしたちのこ
とをバカだと思っているみたいだけどね。ねえ、今度何やる
の?、教えて」
トキュウが食べながら応えた。
「判らない、何をやるか、そのときまでは。みんなサイスが
決めるんだ」
「へえ、そうなの。あっ、電話だ、きっとみんなからだ。ミ
ュウです。あっ、サク、ゴメンね、いなくて、急に用事がで
きちゃって、何って、たいしたことないけど、あとで、話す
わ、いいわよ、先に踊りに言ってて、あとで行くから、うん、
それじゃひとまわりしてて、あっ、それから、マイいる?
いい、あたしからかけるから。ええと、マイわっと。あっ、
マイ、どうしたの? なんかあったの? うん、それで、え
え! なに! あの男に・・・それでやられたんだ・・・ま
あ、そうだね、ちょっとしつこいね・・・言葉遣いが悪かろ
うがマイには関係ないって、ねえ、あいつらにはなんにも判
んないんだよなあ・・・あっ、それで付きまとわれてんだ、
とんでもない男だね。そんなもんだよ大人って、良さそうな
大人ほど危ないんだから・・・そう、いまに見てろって感じ
ね・・・そのうちにね、もうちょっとで行くから。なんか面
白くなりそうね、じゃ、バァーイ。あっ、暑いでしょう。今
ちょっとエアコンが壊れているから」
トキュウが食べながら言った。
「それほどでもないさ、なあ、俺たち暑いのには慣れてるも
んね」
ミュウが立ち上がりながら言った。
「まあ、ワイルドなのね。窓を開けるわ。そうすれば少しは
涼しくなるよ」
ミュウが窓を開けるとトキュウが驚いたように顔を上げなが
ら言った。
「あっ、なんだこの匂いは、臭い、ドブの匂いだ」
ショウが同調するように乱暴に言った。
「ドブだ、ドブのにおいだ。そういえばたしかこの辺にこ汚
い川が流れていたな。あれか、本当に汚いんだよ、真っ黒で
どろどろしてさ」
それを聞いて窓際に立っていたミュウがたしなめるように言
った。
「そんな言い方しないで、ドブだって好き好んで臭くなって
いるんじゃないのよ。戦っているから臭くなるんじゃない、
いっしょうけんめい生きようとして戦っているから臭くなる
んじゃない。いいわ、それじゃ閉める」
「大丈夫、もうなれてきたから、もうなんとも感じないよ、
なあ、ショウ」
ショウは黙って頷いた。
ミュウが再びテーブルの前に座って話し始めた。
「ねえ、ほんとにサイスって最高ね。あの破壊的なところワ
クワクするわ。
『良いことやるな!』
なんて普通絶対にそんなこと言えないよね。あれにはびっく
りよね。なんか気持ちがとっても楽になったようがきがした
わ。これからもっともっと楽しいことが起こりそうね。こう
なったらなんでもぶち壊しちゃえばいいのよ。ほんとうはさ、
あたしたちだって行きたいのにさ、なんで男の子ばっかりな
のなしら? ねえ、サイスってほんとうはどんな人なの?
年とか、何をやってるとか」
するとトキュウとショウは食べるのを止めてしばらく顔を見
合わせた。それを見てミュウが驚いて言った。
「えっ、なんにも知らないの! だれも! いったい誰なの
かしらね? さあ、でかけなくっちゃ、いいのよ、このまま
いて。それより、あんなことで二度と喧嘩しちゃダメよ、み
んな仲間なんだから。あんたたちは本当に危なっかしいね。
今度からさあ、お腹が空いたらあたしんとこに来なさい。そ
うすればもうヤバイことしないで済むじゃない。あっ、そう
だカギ渡しておくわ、だからいつでも自由に来て食べればい
いわ、判った」
ミュウはマンションのスペアキーを二人に渡すと外に出て行
った。
トキュウは食べるのを止め、部屋の様子を見わたしながら
ずっと疑問に思っていたことを言った。
「なあ、ショウ、ミュウはどうやって生活しているのかな?
ずいぶん掛かりそうだよ。まだ、高校生ぐらいだよね、ミュ
ウは。あっ、そうか、親がよっぽど金持ちなんだ。きっと、
そうだ」
ショウは食べ続けているためか曖昧な返事しかしなかった。
二人が十分に食べて飲んで落ち着いたころ、突然部屋に電
子音が響いた。ショウが首をかしげながら言った。
「あれ、なんだろう?」
トキュウが言った。
「たぶん携帯電話の音だ。へえ、二つ持ってんだ。どこだろ
う? ここだ、これだ。はい、もしもし」
携帯を耳に当てるとミュウの声が聞こえてきた。
「トキュウ? ショウ? いいだれでも。今大変なの、あん
たたちの仲間が、見たこともないグループと衝突しそうなの
よ。いったいみんなどうしちゃったんだろう。興奮しちゃっ
てさ、ねえ、聞いてる? このまま放っておかないでしょう。
電波塔の下のところ。なんか違うこんなはずじゃないって感
じ。ダメよ若者同士がやっちゃ。ああ、今日はなんか変だわ。
他にもいっぱいいる。今まで見たこともない人たちも見たわ。
ねえ、応援に来るでしょう。じゃあね」
携帯を耳から話すとトキュウはショウに言った。
「サンドたちに何かあったみたいだ」
「よし、すぐ行こう」
「あっ、このカギどうする?」
「お前が持ってろ」
トキュウとショウは電波塔をめざして急いだ。しかし二人
が駆けつけたときにはサンドたちの姿はその付近にはなかっ
た。
二人は若者がたむろしそうな、しかも余り人目が及ばない
ような場所を中心に探しまわった。
だが、二人が、彼らを眼にしたもの意外にもこの町でもっ
とも人通りが激しい通りだった。そこは普段車は通行止めに
されていて、そこへ通じる大小さまざまな通りから、ひっき
りなしに流れ込んでくる人々で、いつも賑わっている場所だ
った。
二人はその通りに面した店先に沿って並んでいるサンドた
ちの見慣れた顔を発見した。みんな通りの反対側に眼をやっ
ていた。そこには初めて眼にする若者たちの姿があった。や
はり同じようにこっちを見て並んだ立っていた。サンドの話
しからまだ決定的な衝突に至ってないことが判った。トキュ
ウは反射的に相手の人数を計った。そしてこっちは八人、相
手は五人だと直感すると同時に、相手も自分たちと同じ年頃
の若者だとわかった。
しばらく喧騒の時間が過ぎていった。だれもがこれから何
かが起こるなどとは予想もできない雰囲気だった。繁華街は
そこに流れ込んでくるすべての人々を、その華やかさのなか
に平等に包み込んで充足しているかのようであった。しかし、
敵対心をむき出しにした若者たちにとっては、眼の前の風景
がどんなにまばゆく、通り過ぎる人々がどんなに満足そうで
あっても、灼熱の太陽にもとで風にそよぐサバンナの草木の
ようなものでしかなく、だれも関心を持ってるものなどいな
かった。今トキュウたちの心を占めているのは、野性的な力
の誇示であり、本能的な暴力への渇望である。
夢と享楽とをもとめて集まってくる様ざまな人々よって作
り出された活気と賑やかさは、ほとんどの人々にとって調和
の取れた快適なものになるが、爆発的なエネルギーの解放を
願っているトキュウたちのような若者にとっては、夢見るよ
うな陶酔や不安や恐れをいだかせる。華やかな混沌となる若
者たちの誰もが個人的にははっきりとした理由も意志も持っ
ていなかった。しかし、集団としてはそうせざるを得なかっ
た。というのも、他のグループと激しく敵対すればするほど、
今の彼らにとっては唯一の心のよりどころである仲間同士の
結束力を高めて、その親密さを深めることになったからであ
る。だから、もし彼らが動き出すとしたら偶然過ぎるきっか
けで十分だった。
やがてその時がやってきた。目の前を通り過ぎる人々が一
瞬途切れると、対峙する若者たちはお互いにその姿をはっき
りと見ざるを得なくなった。すると、誰かが指図したわけで
もないのに、ケイタが勢いよく前に出ると、じっと相手の若
者たちに眼を向けたままゆっくりとと歩き出した。すると他
のものもそれにつられるように前に出ると、みんなケイタと
同じように、じっと敵対する若者たちに眼をむけながら、ひ
とつの群れのように固まってゆっくりと歩き出した。そして
その距離が、五六メートルになったとき、敵の群れは二人と
三人に分かれて逃走した。逃げるものを追うのは本能だった。
その瞬間トキュウは、全身に沸き起こる新たな力を感じなが
ら、しかも、その力に身を任せるように激しく叫んで敵をの
のしり威嚇した。トキュウたちも二つに分かれて追いかけた。
逃げるものは容赦しなかった。通りから通りへとどこまでも
しつこく追いかけた。逃げるものが途中で転倒したりすれば、
すぐに追いついて寄ってたかって、蹴り上げ、再び逃げれば
また追いかけた。それは生存をかけた真剣な戦いのようでも
あったが、自然な遊びのように楽しんでいるかのようでもあ
った。
このことをきっかけとして若者たちの町を舞台にした縄張
り争いが表面化した。やがてそれは近隣の町にも伝染病によ
うに広まっていき、若者たちにとって、戦々恐々とした毎日
が続くようになった。
それまでほとんど二日ごとに現れていたサイスが三日目に
なっても四日目になっても現れなかった。
そして五日目になってようやく現れた。しかも今度は深夜
出などではなく一日でもっともあわただしい日没後に、あの
骸骨のようなバイクのエンジン音を高らかに響かせながら、
以前騒動をまきおこしたメインストリートに堂々と現れた。
サイスは自分の存在を誰かに知らせようとするためなのか、
それとも何かに向かって挑発しようとするためなのか、やは
り以前と同様に自分以外の車や歩行者を存在しないがごとく、
すべての交通ルールを無視しながら傍若無人に振舞った。
そしてメインストリートを二度三度と往復したあと、ある
方角へと走り去って行った。
それを見てトキュウたちは公園へと駆けつけた。
公園につくとステージのような花壇を前にして陣取った。
やがて林の奥にバイク音が響くと、ほどなくしてサイスが
バイクに乗って現れた。そして初めてのときのように花壇の
上に乱暴に乗り上げると、少し間を置いて、エンジンを切り
バイクから降りた。 サイスはそのまま集まってきていたト
キュウたちのほうを向いてゆっくりと話し始めた。口元には
十分すぎるくらいの笑みをたたえて。
「しばらくだったな、なんか最近面白くなってきたみたいだ
な。今までずっと息苦しくってやりきれなかったもんな。そ
こらじゅうに善がはびこっていたもんな。でもようやくまと
もな人間が出てきたって感じだな。なあに、みんなのことを
言ってんだよ。しかしまだ物足りないな、もっともっと面白
いことをやらなくちゃな、大人がイヤがるようなことをな。
それにはさ、ありふれたことをやっちゃダメなんだ、人の真
似はダメだなんだ。何か新しいことをやらなくちゃダメなん
だ。今までに見たこともないような変ったことを、今まで誰
も考え付かなかったことをだよ。オレは今世間をあっといわ
せるようにいいアイデアを持っているんだ。それを今夜はぜ
ひみんなに見せたいんだ。今後のためにもな。おまえ、お前、
ちょっとこっちに来いよ」
サイスに指差されたのはミュウの仲間のモチという少女だっ
た。モチは少しおどおどしながらサイスに近づいていった。
そしてサイスは大きな声でモチに言った。
「いいかい、これから俺たちは、俺たちの自由の証として、
あることをやる。これからの俺たちにとってもっとも重要で
輝かしいことだ。命がけのな、だから半端な気持ちじゃダメ
だ、覚悟はできてるな、よおしバイクに乗れ。良いか、今日
は俺たちにとっては記念すべき日となるだろう」
そのサイスの声は珍しく興奮していて最後のほうは叫ぶよう
になっていた。
サイスはモチを前にしてバイクにまたがると、すぐにエン
ジンを掛けそのまま話しの暗闇へと消えていった。
そして二三分後にて再び現れた。しかし二人の様子は、最
初は誰もが気づかなかったようだが、よく見ると激変してい
ることに気がついた。二人とも下半身には何も身につけてい
なかった。二人は向き合い、モチは両足と両手をサイスにし
がみつくように巻きつけていた。バイクは広場をゆっくりと
走ったあと、急にスピードを上げて、花壇に飛び乗った。そ
してそのままスピードを落とさずに再び地面に降りて広場を
走りまわったあと、今度は激しく上下運動をさせながら、階
段を昇り始めた。そのあいだモチは振り落とされまいと必死
にしがみついていた。その顔は恐怖と苦痛でゆがんでいた。
階段を下りるときもその不安定さは変らなかった。やがてサ
イスはさらにスピードを上げて、ベンチからベンチへと跳び
移ろうとしたり、花壇全体を飛び越えようとしたり、不可能
と思えることにどんどん挑戦しはじめ、だんだん過激になっ
ていった。
トキュウは最初眼の前で何が起こっているのか理解できな
かった。まさに文字通り初めて見るものだったからである。
やがて今までに味わったことのないような感情が沸き起こっ
てくるのを全身で感じた。そしてその感情に浸っていると得
体の知れない力が自分に働いているような気がした。やがて
周囲の様子が徐々にではあるか判ってくると、他の若者たち
と同じように反応ができないことに気づいた。仲間の少年た
ちは、サイスたちに向かって口笛を吹いたり、奇声を発した
りして激しくはやしたて、少女たちも、いっこうに心配する
気配はなく、少年たちに合わせるかのように、ときおり手を
たたいたりして楽しそうに笑顔を見せていた。偶然居合わせ
ていたに違いない数少ない大人たちも、こらえきれないとい
った様子で笑ってみていた。そのなかには、どういう意味な
のか、トキュウには理解できなかったが、もっと階段を走り
まわれと叫ぶものもいた。
やがて、サイスたちは再び林の奥に消えていった。そして
二三分後再び現れた。今度は上半身も裸になっていた。サイ
スはみんなの前でバイクを止めると
「今夜もやるからな、いつものように会おう」
と言って、再びバイクを勢いよく走らせ、いっきに階段を昇
りきると、そのままみんなの視界から消えた。そして、バイ
クの音がだんだん小さくなっていくことに気づいた。
若者たちは驚いたようにいっせいに階段を駆け上がってき
て、眼を凝らした。しかし、かすかにエンジン音が聞こえる
だけで、二人の姿を捉えることはできなかった。
大人たちの誰かが言った。
「あいつら捕まるぞ」
別の大人が言った。
「あういうのは痛い目にあったほうがいいのさ」
「そうだな、人騒がせな、なにを考えているんだか」
「いったい何のためになるって言うんだろうね?」
ミュウがトキュウたちのところに来て言った。
「あそこまでやるとはね。まあ、いいさ。とにかく面白くな
りそうね。どんどん大騒ぎになるといいね、お祭りみたいに
ね。ああ、でも、このまま終わりって言うのは、なんかもの
たりないって感じだね。ねえ、トキュウ、どうしてあんたカ
タまってんのよ、もう少し楽しそうにしなさいよ。そうだ、
ねえ、これからあたしんとこに行こう。マイ、良いわね。あ
いつらも来てるみたいだし、もしかして調子に乗ってついて
くるかもよ。そしたらみんなでひどい眼にあわしちゃおうよ」
若者たちはこれからどうするかで集まって相談した。結局
夜も浅くこれから色んなことを楽しみたいと言うことで、ミ
ュウに従ったのは、マイとトキュウとショウとゲンキだった。
五人はミュウのマンションへと歩みを進めた。ミュウは歩
きながらときおり後ろを振り向いたあと、納得したように笑
みを浮かべてトキュウたち男には聞こえないようにマイにな
にやら話しかけた。
ミュウのマンションにつくとすべての食べ物がテーブルに
並べられた。さっそく食べ始めたが、なかなか手が伸びない
ゲンキに、トキュウは自分のもののように勧めた。ゲンキは
どうにか食べ始めたが、やがて少し心配そうな顔をして話し
始めた。
「ああ、今夜は出なきゃなんないんだろうな。でも明日用事
があるしな、昼までに来いって言うんだ。いい仕事を教えて
やるから絶対に来いって言うんだ。でもオレ行きたくないん
だ。オッカアに頼まれたって言うんだけどさ、オレ好きじゃ
ないよ、あんな奴、すぐに命令したがるんだぜ、あうやれ、
こうやれってさ。まるで父親みたいな言い方をするんだぜ、
オレとどういう関係があると言うんだい」
トキュウが訊いた。
「いい仕事って、なんなんだい?」
「わかんない、とにかく何をやっているか判んないやつなん
だ」
「そんなにイヤなのか?」
「ああ、イヤだ。話しになんないんだ。デタラメでさ、酒を
飲むととくにそうなんだ。あんな欠点だらけの大人のどこが
いいんだろうな?」
そのときショウが食べながら独り言のように言った。
「欠点のない大人っていうのもむかつくぞ。
『だからどうしたっていうんだよ』
っていう感じでな。」
「そんなにイヤなら行かなければいい」
ゲンキがとっさに答えた。
「なんか逃げるみたいでイヤなんだよ」
「それじゃオレが代わりにいってやるよ。ちょっトキュウに
具合が悪くなった、とかって理由を見つけてさ」
「へえ、それはいい、助かったよ。ほんとのこと言うとさ、
オレそんなに早く起きれねえんだよ」
「とこに行けば良いんだ?」
「あそこの公園の入り口さ、十二時に」
ショウが言った。
「なに、お前、真面目に仕事しようてんのか、止めろやめろ」
「いや、そういうわけではないけど。あんまりイヤかっている
から」
そのときマイが割り込むように話し始めた。
「ねえ、あたし思うのね、そのいい仕事っていうのは。いい
仕事っていうほど気をつけたほうが良いのよ。まだ良いじゃ
ない、仕事しなくたって、そんなに貧乏してるわけじゃない
んでしょう」
「そうだ、そうだ」
とゲンキが同調するように言った。そのとき突然、ベットを
隠すように部屋を二つに仕切っていたカーテンの陰からミュ
ウが声をかけた。
「さあ、準備ができたわよ。これかにみんなに面白いもの見
せてあげる」
それまで誰もがミュウが席をはずしていることに気づいて
いなかったのでみんな驚いたように顔を上げ、その声のする
ほうを見た。ミュウはカーテンの陰から話し続けた。
「あたしみんなに謝りたいことがあるの。今までみんなに嘘
ついていたのね。みんなはうすうす感じていたかもしれない
けど、実はあたし男なの」
そう言うとミュウはカーテンを半分開けその姿を現した。そ
こには全裸のミュウが立っていた。たしかに、胸は小さめで
股間からは茶色で十センチぐらいの棒が延びていた。少年た
ちの誰もがその衝撃的なミュウの姿に微動だにせずじっと眼
を向けていたが、マイはチラッと眼をやっては意味もなく手
をたたくだけだった。ミュウは再びカーテンの陰に隠れた。
そして言った。
「マイ、あんたもこっちに来なさい。あんた確か女優になっ
て言ってなかった。それなら何でもできなくっちゃね」
マイが席を立ってカーテンの陰に姿を隠した。ショウは最
初小声で笑っていたが、その内にこらえきれなくなったよう
で大声で笑い出した。ゲンキも同じように笑い始めた。しか
し、トキュウはどうしても笑うことができなかった。ショウ
が笑いをおさえながら言った。
「だまされないぞ、あれじゃまるで包茎じゃないか。何にも
判ってないぞ、あいつらは、なあ、トキュウ!」
そういわれてもトキュウには良く判らなかった。自分と同じ
ようなものがぶら下がっているとしか思えなかったからだ。
ひそひそ話しが聞こえてしばらくすると再びカーテンが開
けられた。今度はマイもミュウと同じような姿になって、ミ
ュウと並んで立っていた。そして声をそろえて歌えように言
った。
「ランランラン、実は私たち男だったんです。ランランラン」
そう言うと二人は激しく腰を振った。すると棒のようなもの
は左右にゆれて二人の内ももを打った。 ショウとゲンキは
さらに大声を上げて笑った。それを見てミュウもマイも楽し
そうに笑いながらなおも腰を振り続けた。しかし、トキュウ
はまだ笑うことができなかった。するトキュウに自分だけが
のけ者にされているような気がして、だんだん重苦しい気分
になっていった。
そして二人はほんの数秒カーテンの陰に身を隠したあと再
び現れた。このときミュウの手に鋏があった。すかさずミュ
ウが言った。
「でも、あたしたち、男にはもう飽き飽きです。ですからこ
のオチンチンを切っちゃいます。えい、えい」
そのときマイは痛そうに腰を曲げ顔をゆがめた。ミュウはそ
れほど表情を変えずに、その切られて床に落ちたものを拾い
上げながら言った。
「では、このオチンチン、どうしましょう。食べちゃいまし
ょうね。ああ、美味しい」
マイも自分のを拾って子供のように無邪気な顔をして食べた。
それを見てトキュウはようやく眼の前で起こっていることが
理解できた。そして笑いがこみ上げてきた。眼の前で起こっ
ていることとは別のことを感じながら。 やがて笑いがだん
だん大きくなっていくにつれて、それまでの孤独感が癒され
ていくように感じて気分が軽くなっていった。
ミュウは残りを股間から引き抜くと、それをマイに示しな
がら言った。
「いい、これをあいつにくれてやろうよ。あの勘違い男にさ。
あいつ窓の下に来てるからさ。さあ、マイも抜いて、こっち
の窓よ」
そう言うとミュウは、ベッドの隣の道路に面した窓を開けた。
そして下を見ながら言った。
「ほら、いるでしょう、あの男いったいなにを考えているん
だろうね。しつこいんだろう、仕返してやりたいんだろう、
だったらこれを投げるのよ、やつに食べさせるのよ。驚くだ
ろうね。えい、やあ、そこの犬、食べなさいよ、お前、犬だ
ろう、マイ、あんたも投げるのよ。さあ、食べなさいよ。そ
れはあたしたちのオチンチンよ」
そういってミュウは思いっきり笑った。マイもつられて笑っ
た。そしてミュウは笑いを抑えながらトキュウたちのほうを
見て言った。
「さあ、みんなもこっちに着てみて、オチンチンを食べてい
る犬がいるから。あいつなのマイに付きまとっている男って
言うのは。みんな見たことがあるでしょう、あの大人よ、い
つか公園で偉そうなことをいっていた奴よ。相談に乗ってや
るとか言ってたけどさ、マイを連れ込んで無理やりやっちま
ったんだとさ、まったくなんで大人はみんなおんなじなんだ
ろうね。まあ、それだけならいいんだけどさ、マイにもっと
真面目になったほうがいいとか、オレと付き合ったほうがい
いとか言ってさ、しつこく付きまとってさ、結局、なにをや
りたいんだか、さっぱりわからねえ奴なんだよ。ねえ、みん
なも裸になろうよ、やつに見せてやるのよ、あたしたちがど
んなに楽しいことをやっているかってことをさ」
ミュウには逆らえないような雰囲気だったのでトキュウた
ちもティーシャツを脱いだ。すると音楽をかけて戻ってきた
ミュウはそれを見ていった。
「なに半端なことやってのよ。全部脱ぐのよ。さっきあたし
たちのを見てだいだい判ってんでしょう。そんなに変ってな
いって、だからもう何をやったってたいしたことないのよ。
まあね、マイのオッパイはみんなより大きいけどね。でも、
すぐ慣れるよ。さあ、ビンビン踊るよ、奴に見せ付けるのよ」
五人は自分たちの姿を他の誰かに見せ付けるかのように、
わざと窓際に集まって踊り始めた。
衝動的に発せられる奇声と開放的な笑いのなかで、あるもの
はどうしようもなく不器用に、またあるものは何かに突き動
かされるように限りなく軽快に、ときおり窓の外に眼をやり
ながら熱狂的に踊り続けた。
それは窓の下の男がいなくなっても続けられた。
しかし、やがてその突発的な熱狂や衝動も収まってきて、
誰も疲労と倦怠を感じながらただ惰性で踊っているだけにな
ってしまっていた。
ふとトキュウは、ミュウとマイがいなくなっていることに
気づいた。
そこで音楽は止められダンスは終わった。
トキュウはミュウたちにいったい何が起こったのか考えよ
うとしたが、頭にぼんやりと浮かんでくるのは、ケータイで
何かを話しているミュウの姿だけだった。今のトキュウにと
っては、ミュウは何か急な用事ができて、きっと出かけたに
違いないと思うことが精いっぱいだった。それは決して肉体
の疲労から来るものではなかった。心を破壊しかねないほど
の何かとてつもない喪失感を覚えながら、何も考えられない
状態が続いていたからである。
みんな汗で光る自分の肉体を邪魔者扱いしているかのよう
に、トキュウは生気なくうづくまり、ショウはだらしなくう
つぶせになり、ゲンキは力なく横たわっている。誰一人とし
て喋ろうとしない重苦しい時間がどれほど経過しただろうか。
やがてゲンキが真っ先に回復したようだった。ゲンキが体を
仰向けにしてつぶやくように言った。
「ああ、のとが、のどがたまらない、まだあるかな?」
そしてゆっくりと起き上がるとテーブルに近寄り残っている
飲み物を次から次へと飲み干し食べ物に食らいつ来ながら言
った。
「なあ、元気だそうよ、今日はまだ何にもやってないじゃな
いか、もうそろそろ出かけたほうがいいんじゃないか」
トキュウもゆっくりと立ち上がりながら言った。
「そうだな、こんなところで死んでる場合じゃないよな。な
あ、ショウよ、今日はまだこれからだぞ」
ゲンキがさらに食べながら言った。
「なあ、トキュウ、明日はほんとうに言ってくれる。助かる
よ、急に腹が痛くなったって言ってよ。ああ、どうしてやっ
ちまわなかったんだろうな、あれじゃまるっきしはだかじゃ
ないか、俺たちを誘っていたのかな、でっかいオッパイして
さ、やっても良いってことじゃなかったのかな、なあ、トキ
ュウ、お前どうして何もしなかったんだい?」
「うっ、うん、なんかそんな雰囲気じゃなかったよ」
「ショウは?」
「ああ、オレも、どうしてもそんな気分にはならなかったん
だ」
「きっと、あうやって色んな男にやらせているんだろうな、
でも今度はそうはいかないぞ、なあ、トキュウ」
と少し大人びた言い方をするゲンキにあわせるかのようにト
キュウも少し声を低めていった。
「ああ、そうだな」
ゲンキはさらに続けた。
「でもなあ、オレは、サクって言う娘がいいな、何をやって
も許してくれそうじゃないか、どっかバカっぼくってさ、レ
イも良いな、なあ、トキュウ、お前は誰が良いんだ? ミュ
ウか?、まさか、ミュウはちょっく怖くないか?」
そのとき部屋の携帯がなった。
ミュウからで、町に見たこともない暴走族が現われて騒ぎ
を起こしているということだった。それを聞いてトキュウた
ちはいっきに元気を取り戻した。そして急いで駆けつけた。
すでに待ちのいたるところに警官が立ち、重要な交差点に
はパトカーが待機していた。
爆発的な排気音が町中にに響き渡り、人々は群れとなって
あちこちによどんでいた。みんな繁華街に暴走族が現われた
ことは不思議そうだった。トキュウたちはミュウたちの姿を
目にしながらもタイヨウとサンドを見つけて合流した。
トキュウたちがついたときには、バイク十数台と車二台が、
あらゆる通りを舗道ぎりぎりに、すべての交通ルールを無視
しながら自由自在に走りまわっていた。しかし時間の経過と
ともにその走行範囲が狭められていき、やがてひとつの通り
だけになった。そこで暴走族は網に追い詰められた魚のよう
に、よりいっそう激しく走りまわるようになった。
そして群衆の一人として舗道から見ていたトキュウは、ト
キュウの眼の前を一台の車が通り過ぎようとしたとき、トキ
ュウは何者かに押されて道路に飛び出した。そのためトキュ
ウはその車と激しく衝突し撥ね飛ばされ舗道にたたきつけら
れた。初めは何が起こったのか判らず痛みもそれほど感じな
かったが、すぐに全身の激痛に苦しめられた。
仲間が近寄ってきた。サンドがトキュウの顔を覗き込みな
がら言った。
「いったいどうしたんだ?」
「わ、から、ない」
とトキュウは激痛にあまりたどたどしく答えた。
ショウが言った」
「オレは見たよ、あいつさ、あいつが押したんだよ」
サンドが言った。
「あいつって?」
「スーパーの店員さ、以前にもめたことがある」
トキュウが苦しそうに言った。
「やつか、し か え し だな」
ショウが言った。
「あの野郎、このままじゃ済まないぞ。決着つけなきゃな」
苦痛が収まったのかトキュウがようやく普段のように言った。
「いや、良いよ、たいしたことないから、もう大丈夫さ」
ずっと黙ってみていたタイヨウが言った。
「も、う、おしまいか、と、おもった。おまえ、がまん、づ
よいんだな、おれだったら、ないちゃうよ」
その間、通りは激変した。徐々に追い詰められていった暴
走族はついに突破をはかった。まず車がパトカーに体当たり
して、そこにできた感激から、動揺する警官隊の隙をついて、
バイクが次から次へとすり抜けていった。なかには捕まえよ
うとする警察官をかわしきれずに転倒してしまい、そのまま
捕まってしまうものもいたが、ほとんどは逃げ延びていった。
そしてトキュウが歩けるようになったころ、通りは普段の
平静さを取り戻していた。しかし若者たちはまだ騒乱の興奮
に浸りきっていた。
トキュウの様子を見に来ていた少女たちのひとりサクがト
キュウの腕の擦り傷を見て言った。
「あたしいいもの持ってる、バンドエイド、これ貼ったほう
がいいよ。貼ってあげるね」
それを見ながらレイが言った。
「なんか、最近さあ、ドンドンおもしろくなってきたって感
じね」
するとマイが同調するように言った。
「そうね、こんなこと毎日あったら良いね。そしたら絶対退
屈しないね」
モチが言った。
「車の体当たりって凄かったね。ほんとうに物が壊れるって
良いね、なんか変になりそう」
それを聞いてミュウがはき捨てるように言った。
「なにが、あとがダメじゃない、かっこつけようとしたんだ
ろうけど、捕まっちゃ何にもならないよ。まだがきよ」
サンドが少女たちの会話に割り込んだ。
「見たこともない奴らだな、どっから沸いてきたって感じだ
な、でも真似はよくないよ。なあ、目立ちたかったんだろう
な、でも、どうせやるならもっと思い切ったことをやらない
と、半端なんだよな」
そのとき、それまでトキュウたちの前ではほとんど無言だっ
たサクが言った。
「あたしよくないと思うの、信号むしするのは」
ミュウが言った。
「良いのよ、たまには、とくに今夜みたいなときはね」
サクが急に興奮して言った。
「ダメ、絶対に良くない、おじいちゃんが言ってたもん」
ゲンキが言った。
「楽しければ何をやったって良いんだよ、みんな面白がって
いるじゃない」
サクがさらに興奮して言った。
「ダメなものはダメだって、あたしずっと守ってきたもん」
それを聞いて周囲の少年たちから次々とサクに言葉が飛んだ。
「それじゃ、万引きするのとどっちが良くないんだい」
「人に病気を移すのとどっちが良くないんだい」
「何をそんなにいい子ぶってんだい」
「そんなんじゃないわよ」
と言ってサクは突然子供のように泣きじゃくり始めた。それ
を見てミュウがサクに近づきながら言った。
「みんなで苛めちゃダメだよ、サクはサクなんだから。サク、
もう気にしない、気にしない、あんたはあんたで良いんだら。
みんなはさあ、たまにはとんでもないことをやりたがってい
るだけなんだから」
サクが泣き止むと、若者たちはひときわ映える電波塔の点
滅する光を眼にしながら公園へと歩き始めた。光れと音に溢
れた繁華街から水銀灯に照らされただけの公園に着いた。
若者たちは思い思いに階段に席を取ると、ひたすらサイス
が現れるのを待った。
やがて時計が二時をまわったころ、サイスが林の暗闇から
歩いて現れた。そして若者たちの前に立つと、いつものよう
に少し笑みを浮かべて話し始めた。
「今日は、みんな楽しめて本当にいい日だったな。以前から
言っていたように誰もがやりたいことをやったみたいだな、
それで良いんだ。それにしても思ったより効果があった見た
いだな。ほんとうに真面目づらした人間どもが、慌てふため
いてバタバタするっていうのは愉快だな。まあ、そこで今日
は、せっかくだから、このまま終わらせるのはちょっともっ
たいない、もう一発派手にやりたいと思う、それではさっそ
く出かけるが、今日はそんなに人数はいらない、行きたい者
は手を上げて、ああ、女はいい」
そのとき手をあげていたミュウが言った。
「ねえ、たまには連れて行ってよ、あたしだって、やってみ
たいのよ」
サイスが答えた。
「ダメだ、今日はすばやくやらないとダメなんだ。それにそ
んなにいらない。五人だけでいい。ゲンキ、サンド、ケイタ、
ショウ、それに、トキュウだ」
そのとき、ショウがさえぎるように言った。
「トキュウはダメだと思う、怪我したみたいなんだ」
すると、トキュウが言った。
「いや、オレは大丈夫だ、もうなんともない」
サイスが言った。
「よし、それでは行くぞ、ついて来い」
サイスと五人の少年たちは林の暗闇に入っていった。そし
てほとんど人影のない公園の裏側に出ると、そのまま人目に
つかないようにするために、できるだけ人通りの少ない道を
選んだ歩き出した。やがて付いたところは、ちょっと前に舗
道に沿って駐車していた車を一台残らずパンクさせた通りだ
った。サイスの指令は、今度は一台残らず火をつけることだ
った。六人は綿密に打ち合わせを下あと手分けして火をつけ
るとそのままバラバラに逃走した。