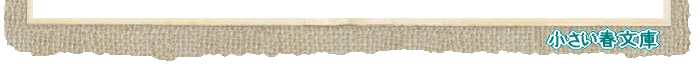1980年代作
やがて夕暮れが(1部)
はだい悠
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
季節の微妙な移り変わりが、他人事のようにテレビや活字の
中の出来事となってしまってからすでに久しい。
人々がそんなことに心を動かされなくなった訳ではない。
もともと厳しい自然の制約のもとで、長い間生き続けてきた
人間にとって、それを忘れるはずはない。
ただ一時的にそんなことに関心を持たなくても生きられるよ
うに生かされているに過ぎないのだが、、、、
六月初めの街にようやく日が暮れた。
夜になっても空気はまだ昼のぬくもりを残している。
車一台通れるだけの狭い路地の両側には、ぎっしりと家々
が建ち並んでいる。その静まり返った家並みのあちこちから、
ときおり勢いよく一日の汚水が吐き出される。人々は一日の疲
れや不満を汚水とともに流しさってしまった後、味噌汁や化粧
やオムツの匂いのする部屋の中で、肌を寄せ合い明日のささや
かな夢を温めあう。そして吐き出された汚水は、ドブとなって
、六月の夜気に交じり合い、悪臭を放ち始める。
ある路地を茶色く狼のようにたくましい犬が、ときおり鼻先
を地面にこすり付けるようにしながら歩いている。地面を嗅い
でいるのだ。毛並みもよく首輪をつけているが、その所在無く
振舞う様子から明らかに主人を失った犬だと判る。その野良犬
は向こうから歩いてくる人影を覚えても、その人影には関心が
ないといった風に、再び地面を嗅ぎながら歩き出した。人影と
すれ違い、しばらくすると突然何を思ったのか、今来た道を
振り返りると勢いよく走り出し、先ほどの人影の傍らを通り過
ぎ、別の路地へと消えた。
周囲を広い通りに囲まれた街のある一区画には、たいてい一
二匹の野良犬が済み付いている。以前には、先ほどの犬よりも
毛並みの悪いやせこけた野良犬がうろついていたが、保健所に
連れ去られたのか、それともさっきの犬に追い出されたのか、
最近まったく見当たらない。ということは、さっきの犬がこの
狭い一区画を自分の縄張りにしていることになる。そして、わ
ずか十数分で歩きつくしてしまうこの狭い地域を、塀の隙間か
ら中を覗いたり、地面に鼻をこすり付けたりしながら、路地か
ら路地へと、用心深く、そして卑屈なすばしっこさで一日中歩
き廻っているに違いない。その間なんど同じ道を歩くことか。
主人を失った犬は必要以上に遠慮深い。人間に危害を加える
ということは確実に自分の破滅につながるということを知って
いる。だから、自分の背後に逃げ場をもっている飼い犬のよう
な生意気さや、通行人に突然吠え掛かるような無礼さはなく、
むしろ、人間と眼が会うことを避けたり、無関心さを装ったり
する。そのときの表情があまりにも人間と似ていて、非常に滑
稽でさえある。
その野良犬はとある家の破れた板塀の隙間をすばやく通り抜
けると、そこに居る白い黒ブチのメス犬の後ろから不意をつい
た。白いメス犬は格別驚きもせずに、かすかにうなり声を上げ
ながら飛び跳ねるようにして迎えた。そして二匹は何かに気遣
うように、そしてそのことを申し合わせたかのようにうなる声
を押し殺して、毛に覆われた肩や腰をゴツゴツと鈍い音をたて
ながらぶつけ合っては、不器用に絡み、もつれ合う。やがてお
互いの情欲を確かめ合うと、二匹は家のものに気づかれないよ
うにドブ臭い夜気に包まれて密かに交尾をする。
その白い飼い犬は数ヶ月前まではキャンキャンと吼える臆病
な子犬だった。
夕刻の電車がつくと、駅は華やかなあわただしさに包まれる
。人々ははじき出されるように駅を出ると、駅前の快楽的な風
景に眼を奪われることもなく、それぞれによそよそしい表情を
しながら足早に家路を急ぐ。その決められたような歩き方や表
情は不思議と賑やかな町の風景に似合っている。
マサオは駅近くでは、他の人影を前後にして歩いていたが、
自分のアパートに近づくに従ってひとりになった。マサオはい
つもひとりになると、なぜかほっとするものを感じていたが、
そんなことになんら意味もないと思い特別気にもしなかった。
でも心なしか歩調が緩やかになるのである。
アパートの大家の妻タカは家のドアを開けたまま入るのでも
出るのでもなく、所在無い様子で何かぶつぶつと独り言を言っ
ていたが、帰ってくるマサオの姿を眼にすると、急に表情を和
らげ、「お帰り」と言った。マサオは疲れていたので軽く頭を
下げただけで自分の部屋に入った。
大家の源三は家の中では妻タカに暴君のように振舞った。毎
日欠かさず飲む酒が入ると時は、とくにひどく、大声で怒鳴っ
たり、荒々しい口調でタカに用事を言いつけたりする。そして
タカが自分のいうことをきかないでグズグズしていると、物を
投げつけたりする。
源三は長年連れ添ったタカを決して憎んではいなかったが、
それは男のわがままであることを知っていたし、それほど悪い
ことだとも思っていなかった。タカの男性的な容貌や女性らし
くない振る舞いに対して、これが相応だ、お似合いだ、と言う
風に無意識に思っている節があった。そのせいか、威圧と暴力
で人を支配したら、こうも臆病になるものかと思うくらいに、
タカはいつも動作がぎこちなくおどおどしていた。タカは、源
三が自分を怒鳴りつけたり、ものを投げつけると言っても、そ
れ以上はひどくならないと判っていたが、怒鳴り声や、その扱
いに対しては不満であった。そのためにときどき反抗的な態度
を取るのであったが、やはり威圧や暴力が怖いので、不服では
あるがたいてい従うのである。その不満のやり場のなさが独り
言となるのである。マサオが部屋代などを払いに行くと、その
口調が増幅されて、源三を前にして、役者まがいの身振りで源
三の乱暴振りを罵るようにしゃべるのであった。そんなとき源
三は、ニヤニヤしながら「ババァ、うるさい」などといって、
ほとんど黙ってきいているのである。源三は妻意外には世間並
みに人当たりがいい気の小さい夫である。それがタカには不満
のひとつではあるが。
大家夫婦は初老に近く、若いとき職場で知り合い結婚したと
言うことだが、二人には子供がいない。タカはそのことを気に
しているようである。そのためか、おりあるごとに若いときに
卵巣を摘出したということを子供のいない積極的な理由にして
いるようである。そしてそれが原因しているのであろうか、タ
カは年齢とはいえ、女性的な容姿に乏しく、動きも男性的でさ
えある。源三は退職後にアパートの経営を始めた。遊びは派手
ではないが、町内会の会合に積極的に参加したりして夜遅くま
で飲み歩くことたびたびであった。趣味としては狭い庭の植木
の手入れ、そしてそれに飽きると、パチンコに出かけていた。
そのパチンコの景品のタバコをマサオはときどき安く譲り受け
ることがあった。
マサオが寝付くまで、タカのぶつぶつ言う独り言が聞こえて
いた。
静まり返る深夜の町。
人間の食べ残しを求めてさ迷う猫が路上にあらわれる。とき
おり車のライトがそれらをくっきりと照らし出す。通り過ぎる
人も響き渡る自分の足音でその静けさに気づく。
電気の消えたネオンサイン。
威圧するようにそびえたつビルディング。いまや夕暮れまで
の町の賑わいも華やかさもない。もしこの深夜の町が、人影も
車も猫もいない冷たい水銀灯に取らされただけの風景であった
ら、町に生物のすめない廃墟のように見えても不思議ではない
だろう。
でも深夜の町は眼に見えない表情を持っているようだ。
人間がものを食べ排泄して生きているように、町も、入り口
も出口もないような、それ自体が巨大な生理体として生きてい
る。そして複雑である。
ビルの白い壁には、夕暮れ時の雑踏ざわめきが吸い込まれて
いる。
舗道には無数の足跡が、街灯の鉄柱には無数の人間の手垢が
、そして、空気中には無数の人間の体温が残っている。そして
一見無秩序で猥雑な町並にも、一人の人間の考えや思惑ではど
うにもならないかのように、無数の人間の意志が絡み合いなが
ら取り込まれているようだ。
それは歴史的であり快楽的でさえある。
知らぬ間に古いビルが壊されて新しいビルが建ち、気づかぬ
うちに新しい店が開店しては、不振な店はひっそりと廃業する
。そしていつの間にかに新しい町並みに変っている。しかし町
並がこのようにめまぐるしく変化しても、そこを通り過ぎる人
も、そこにとどまる人も格別心を痛める必要もなく、他人事の
ように無関心でいられる。そして古い町並の思い出を思うこと
もなく、新しい町並に慣れていくようである。いったいどうし
て町を歩いている人々は無関心でいられるのだろうか? たし
かに町の中で人々は、無愛想であったり、よそよそしい表情で
あったりするが、でもそれはあくまでも外見的に過ぎないよう
である。またそれは本人たちの自由意志ではなく、そうさせら
れているようでもある。もし隣り合うたびごとに、またすれ違
うたびごとに、お互いに意識しあいながら人間的に振舞おうと
したら、たちまち身も心も疲れきってしまうだろう。まためま
ぐるしい変化をいちいち気にしたり、快楽的な風景やつかみど
ころのない都市生理に疑問を投げかけて、それを把握しようと
したら、その人間の存在の無力さや卑小さや惨めさに気づかさ
れ、たちまちにして打ちのめされてしまうだろう。まさに自分
を見失うに違いない。すると、自分を守るためには自己に閉じ
こもって生きなければならないようである。それは余計な地人
や出来事に対しては閉鎖的になる。そしてそれは他人から見れ
ばよそよそしく見えることになるのであるが。そして結局残さ
れているのは、装飾ガラスと金属とコンクリートと七色の光の
町で、流されるままに快楽的に生きることだけかもしれない。
そしてそこで生きつづけるためには格別の思想も必要ないのか
もしれない。日々の倦怠とめまぐるしい変化に、痴呆のように
関わりあいながら刹那的に生きられるのかもしれない。だがそ
の一方、もしそんな中で自己を確認して生きたいのなら、強い
意思と能力を必要とするであろう。そのような人間にとって、
おびただしい広告塔のひとつにでも、「これこれのために生き
よ!」とか「このように生きよ!」などと書いてあったら、ど
んなに助かることであろうか! しかしこのような快楽的な風
景や、つかみどころのない巨大な都市整理を前にしては、たと
え全部の広告塔が気のきいた文言に変ったとしても何の役にも
たたないであろう。
町で快適に生きていくためには、決まりきった思想は必要と
しないようだが、そこを通り過ぎる人たちはある印象を持つよ
うになる。「町に住む人々は冷たい」と、しかしこれをもう少
し正確に言うなら、「『町に住む人々は冷たい』とお互いにそ
う思いながら暮らしている人々が住んでいるところだ」と言っ
たほうがいいのかもしれない。もしこのからくりがお互いに理
解しあえたら、不必要に他人を避けたり、相互不信に陥ったり
して、お互いに苦しめあうことは泣くなり、人々はお互いに笑
いあえるようになるのであるが。
もしかして町は人間関係が希薄なのではなく、過剰なのかも
しれない。そして夜の街から人影も猫も車もいなくなるころ、
東の空がしらみ始める。
誰でも夜眠りに突きながら、明朝再び眼が覚めることに漠然
と期待をかけるものであるが、今のマサオはそれほどでもなか
った。むしろこのままずっと眠り続けて二度と醒めなくてもか
まわないと思うほどになっていた。決して生きることに投げや
りになっていたわけではなかったが、何も考えることなく、死
んだように眠る心地よさのせいでもあった。
マサオはアパートの部屋に帰るとこれと言ってやることも泣
く、疲労した肉体と、思考力の低下した頭をだらしなく布団の
上に投げ出して、そのまま眠る毎日である。このような変り映
えのしない生活は、以前のマサオにって予想だにしなかったこ
となのであるが・・・・・・マサオにって、何かをするという
ことは、友人と付き合うとか、夜の街に出て遊ぶとかいう、あ
る特定の行為だけを意味してはいない。何かまだ自分にわから
ないことを考えるとか、自分の過去の出来事を思い浮かべると
か、自分のためになる本を読むとか、少年時代のように好奇心
に満ちた想像力と自由な思考力を生かして、新しい知識を組み
立てたりしながら、みずみずしい感情を自分の体内に作り出し
てそれを楽しむことなのである。しかし今のマサオに硬直した
頭の中には、そのようなよゆうも能力も失われかけていた。ま
だ二十五歳であるのに。マサオにとって、このような味気ない
生活が自分のすべてであり、今後もこんな状態が続くだろうな
どとは思いたくもなかった。しかしこれ以外の生活を求めには
どうすれば良いかまったく判らなかった。
マサオは眠りに入るまでの短い間にやや思考力が回復してく
るので、その間にこのような状態になった自分に疑問を投げか
けるのである。もともと人間の生活はこんなものなのだろうか
? または自分の特異な性格のためにそうなのか? それとも
自分を取り囲む環境に問題があるのではないだろうか? など
と。しかし眠るまでの短い間には何の解決の糸口さえ見つける
ことができないのである。マサオは乏しい思考力の中で迷い焦
る。が、結局は眠る事の心地良さも手伝ってか、いつもそのま
まの状態でおしまいになるのである。
そしてそういう疑問を自分に投げかけているうちに、いつし
かマサオは、《こうして独りで部屋に居てくつろいでいる自分
》と《仕事をして仲間と交わり町を歩いている自分》とは、ま
ったく別の人間ではないかということに、漠然とではあるが気
づき始めていた。
だが、この二つの自分の発見はマサオにとっては苦痛なこと
である。自分が町や人々の中にいるときに、独りでゆったりし
ているときの自分はどれほど煩わしさから開放されているかと
思ったり、またわはその逆に、独りでくつろいでいるときに、
仕事や仲間たちとの交わりが、どれほど煩わしいものかと思わ
なければならないからである。そしてそれを意識的に使い分け
る作業をしなければならないからである。
マサオにとって、二つの自分の状態が、いつどのようにして
切り替わるのか? またどちらの状態が自分にって好ましいの
か? はっきりと判断の下しようもなかった。ただ、マサオに
とって、独り部屋に居て、ゆったりとしているほうの状態が、
自分には似合っているように感じられるのではあるが・・・・
だがそのように感じる背後には、同時にこの世界からの落伍
者や敗北者の惨めな姿を表象させる。マサオにって、自分に好
ましい状態になるには、現在のこの中流の生活を捨て去らなけ
ればならない。そして、誰デモが持ってるであろう将来の夢、
《美しい女性と結婚する》とか《出世して社会的名声を得てよ
りよいせいかつをする》とか、そういう漠然とした夢を捨てな
ければならない。しかし、今のマサオには、そうなる勇気はな
い。まだまだ今の生活や将来の夢には捨てるには捨て切れない
ものがある。また、自分は惨めな落伍者や敗北者にはなりたく
ない。
この世の中には、気に食わない人間や許せない人間がいる。
そういう人間の鼻を明かしたい、見返したい、負けたくない、
自分にはできるという確固とした気持ちがある。そしてその一
方には、自分もやはり社会の一員である、みんなと同じように
働き、交わり、社会的義務を果たさなければならないという気
持ちもある。
マサオのこのような考えはすべてうつらうつらした頭の中で
の出来事に過ぎないのである。そして、どんなに想像力の低下
して頭でも、素っ裸で放り出されたときの自分の惨めな姿や、
そのときの心細さや不安を思うだけの想像力は残っていた。
結局、二つの自分の切り替えが、まだ眠い朝にやらなければ
ならないのは最も辛いことではあるが、習慣に身をゆだね、ネ
クタイを締め、背広にひきづられるようにして、毎日ドアの外
に出るのである。
ビルの窓の外は六月の陽射しで眩しい。ときおり窓の隙間が
涼しい風が入って来る。
マサオは会社の上司や同僚たちとテーブルを囲み、午後の会
議に出席している。だがあまり発言する機械もなく、会議に退
屈な様子で、ときどき手元の資料から窓の外の風景に眼をやっ
ている。
町は強い陽射しを受けながらも穏かである。建物は皆その影
を色濃くし、街路樹の若葉は日の光を受けてみずみずしく、吹
き抜ける風に揺れている。
いつのまに若葉に変ったのだろうとマサオは思った。またそ
ういう季節の微妙な移り変わりを見逃していることを惜しいと
も思った。
マサオは何事もなかったかのように再び手元の資料に眼をやる
。マサオはふと、季節の移り変わりが自分とまったく変わりの
ない世界の出来事になっていくかのように思われ、不安ともつ
かない寂しさに襲われた。
会議ではマサオはほとんど発言しない。そのためができるだ
け参加したくないと日頃から思っていた。しかし組織内でもそ
うも行かない。たいていのものはそういう会議の時間を楽しみ
にしている。とくに同僚の牧本や斉木は話し好きのせいもある
が、俄然張り切る。《判りきったことだなあ》とか《どうでも
いいことだなあ》と思われることもちゅうちょなく論争の舞台
に乗せる。最初のうちは、それは会議の雰囲気をたのしいもの
したりして会議を活性化させるだけの効果しかないので、たい
ていは聞き流してよいのだが、そのうちになかなか良い発言も
飛び出ることもあるので、その積極性や雰囲気作りのうまさは
、結局は頭の回転のよさがそうさせているのだと、上司からは
受け取られているようである。彼らは話し合いながら、衝突し
あいながら問題を解決していくタイプのようである。そういう
二人を見ているとマサオはどうしても気後れして消極的になっ
てしまう。でもマサオは決してぼんやりと他のことを考えてい
るわけではない。資料にいたずら書きしながらも、《なるほど
》などと思いながらみんなの発言することをちゃんと聞いてい
るのである。でも、聞いているだけでも、対立する意見などが
あると、どちらの言い分ももっともだと思えるようになったり
して、どちらが良いかなどは判らなくなってしまうのである。
また、自分でも良い案が浮かんだりするときが在るが、みんな
のように話し合いの流れに乗り切れずに言わずじまいになって
しまうのである。たまたまチャンスに恵まれても、その口調に
勢いがないためにみんなに通じなかったり、場違いなものにな
ったりする。意見を求められても、その妙案をかすれていたり
、内容があいまいだったりして、かえって自分の無能さをさら
け出すような気がしてますます居心地の悪いものにする。意見
を求めるほうも、さして期待しているようでもなく、理解して
いるように頷いては見せるが、根本は無視なのである。付け足
しなのである。
マサオはそのうちに、発言力には、その発言者の存在感、つ
まり日頃の好印象と多弁、離れと切り出しのタイミングが必要
であることがわかってきた。しかしそうは判っていても、自分
は牧本や斉木にようにはなれないような気がした。自分には彼
らのような積極性や多弁や雰囲気作りのうまさはないような気
がした。マサオは自分が発言しなくても、それほど重大な影響
は与えないと思う反面、自分がみんなから取り残されたように
感じ、心細く思い自分が情けなくなるのある。マサオにとって
会議に出席し聞いているだけでも苦痛なのである。
結局会議はマサオが不必要な劣等感に陥るほど重要な決定を
するわけでもなく、いつものように牧本や斉木のような人間の
自己発散の場として終わるのである。
その日の夕方、マサオは牧本に誘われるままに斉木といっし
ょに夜の街に出ることになった。
マサオは最初、町の人ごみや騒々しさを思うと、断りたかっ
たが、《明日は休みじゃないか》と言う牧本の強引な誘いに抗
しきれなく、また、マサオの心の奥に、昼間の会議での屈辱的
な思いがまだくすぶり続けていて、その名誉挽回と言う気持ち
も働いてか、付き合うことにした。
牧本と斉木は、町の賑やかな雑踏でも傍若無人と思えるほど
、陽気に振舞った。マサオは二人のそういう性格がうらやまし
いと思った。そしてそういう二人についていくと、自分もなぜ
か、独りで歩くときのような居心地の悪さや煩わしさがなくな
り、華やいだ町の風景に溶け込めそうな気がしてきた。
三人は目が眩むばかりのけばけばしい広告塔がおびただしく
立ち並び、人ごみが激しい通りをしばらく歩いていたが、その
うちにあたかも唯一のものを選択したかのように、とある喫茶
店に入った。
マサオは席に座るが、落ち着きのなさを感じていた。隣席と
はついたてもなく近く、話し声も良く聞こえる。
そして混雑していて全体としては騒々しいのである。マサオは
周囲の見知らぬ人間を意識すると気持ちが萎縮した。他の二人
はそんなことにはお構いなく、慣れたように席に座り無心に漫
画を読み始める。マサオはそんな二人に戸惑いをや違和感を覚
えながら、だんだん居心地の悪いものになっていった。
隣の人声や、食器の音がマサオをいらだたせる。
斉木は急に漫画をテーブルの上に置くと牧本に話し掛ける。
だが、マサオには関係のない内容のようである。 ・・・・・
・・・・・・・・・・
《みんなはどうしてこういうざわざわとしたところで話し合
えるのであろうか》とマサオは思う。
・・・・・・・・・・・・・・・
《隣のアベック、お互いの話し声が聞こえるのだろうか》と
マサオは思う。
・・・・・・・・・・・・・・
「昨日おもしろいことが在ったよ」と斉木の声がマサオにも聞
こえた。
「実は、昨日ね、立ち食いそばを食っていたら、隣の客が食い
終わって帰ろうとしたの、そしたら『お客さん! お勘定』っ
て、店のオヤジに止められてね、その客、『払ったよ』って言
うんだよ。そしたらオヤジは『もらってねえ』って言うんだよ
。その客は酔っ払っていて『いや払ったよ、さっき払ったじゃ
ないか』って言うんだよ。オヤジはもらってねえって言うし、
なんだかんだで、そのうちに喧嘩になってしまってね、野次馬
は集まるし、警察は来るし、、」
「その客は本当に払ったの?」
「いや、俺が来たときには、もうそば食っていたから、判らな
い」
「それで結局どうなったの?」
「俺も最後まで見てなかったから判らないけど」
「ところで、君払ったの?」
「そこなんだよ、面白いのは、俺も結局、どさくさにまぎれて
そのまま帰ってきたから、もうけちゃったって感じ」
「ふーん、そう、よかったね」
マサオはニヤニヤしながら聞いていたが、ますます居心地の
悪いものになって行った。
・・・・・・・・・・・・・・
「そんな話しなら僕にもあるよ。こっちに引越ししてくるまえ
、まだ独身だったころ、ツケで飲んだり食ったりしていてね、
そのままこっちに来たものだから、そのままチャラになってね
、もう時効だからね、、、、」
そう言いながら牧本はゆったりと椅子に背を持たせかけネクタ
イをゆるめた。
「いくらぐらいだったの?」
「まあ、二、三万かな、、、、」
茶色のガラス製の灰皿に灰が落ち、触れ合うカップとスプー
ンが音を鳴らし、色さまざまの照明器具が店内を照らしている
。
マサオの意味のないニヤニヤ笑いを見て、牧本が声を掛ける
。
「君にもあるだろう」
「いやあ、えぇ、まぁ、ある、あります。新聞代三ヶ月ほど、
引っ越したから、、、、」
そういいながらもマサオは周囲が気になった。
「あるんだよな、だれにも、おもしろいねぇ」と斉木はマサオ
を見ながら話しかけるが、ふたたび牧本の方を見て話し掛ける
。
「あの新聞拡張員っていうのは、いやだなぁ、しつこくて」
「内はひとつにって決めているから」
「いらないって言うのに、押し売りみたいだよ」
「そりゃあ、奴らだって生活が掛かっているからね。商売、商
売」
「洗剤やシャンプーもらったって、どうってことないのに、頭
を下げて頼まれると、つい話しに乗って、取ってしまうんだよ
な、なんか騙されたみたいで、、、、」
《人情の弱みに付け込んで、頭を下げれば何でも通ると思っ
て》とマサオは言おうと思ったが、タイミングが悪く切り出せ
ない。
「そりゃあ、やつらがうまいんだよ」
「そうかなぁ? よくあれだけのサービスをして、元が取れる
ね。どうせサービスするなら値下げすればいいのに、相当もう
かっているんだろうな」
「売ったってそんなに儲からないよ。新聞は広告料さ」
「そうかなぁ? それにしてもうますぎるなあ、まあ、こっち
も損するわ訳じゃないけど」
「何でも商売、商売!」
・・・・・・・・・・・・
「ところで今日の会議で決まったこと、、、、、、、、」
店内の騒然とした雰囲気の中で二人の会話は続くが、マサオ
はいっこうに加われず居心地が悪い。
喫茶店を出ると三人は、ふたたび賑やかな通りを我が物顔で
歩きながら、昂揚する欲望に吸い込まれるように飲み屋に入っ
た。牧本や斉木は互いに褒めあい、また罵りあいながらも、不
思議と会話が途切れない。そして二人は見知らぬ客とも友人の
ように親しくなり、いっしょに歌など歌い終始陽気なのである
。だが、マサオは飲んでいるときもただあいまいな笑みを浮か
べているだけで、やはり孤立している。どこもかしこも騒々し
く快楽的ではあるがマサオは他人のようにしか関われない。
マサオが酔いと疲れでくたくたになって部屋に帰ったのは十
一時である。さすがに疲れたと思い何もしたくなかった。そし
て何も考えたくもないと思い寝床に付くが、なかなか寝付かれ
ない。一日の出来事が頭の中にちらつき始めてマサオを苦しめ
る。
《町の華やかな風景》《おびただしい人々》《牧本や斉木の歌
いわめく顔》《自分の孤立している姿》などが、くり返しくり
返し現れては消え、消えては現れ、マサオの頭の中を洪水のよ
うに暴れまわる。マサオはかすかな思考力で、《今日は有益だ
ったろうか?》《それとも無益だったろうか?》と多少後悔の
念も含めて思うが、どうしようもなく判断がつかない。ただ胸
苦しく、寝付けない。そしてときどきマサオの頭の中をある思
いが閃光のようにかすめる。《なんと猥雑な、なんと愚劣な、
、、、》
六月の町に雨が激しく降った。うっとうしい季節の始まりで
ある。大粒の雨は、町を蔽い尽くしていたチリやごみを洗い流
し、街路樹や花壇の花々に休息を与える。トタン屋根で激しく
打つ雨音を聞きながら、マサオが目覚めた。窓の外は、冬の朝
のように薄暗く、雨水が窓ガラスを伝わり激しく流れ落ちる。
しかし手足を動かすにも億劫なほどの倦怠感のためふたたび眼
を閉じる。《もっと激しく降ってくれ、何もできないほどに、
何も考えられないほどに》マサオはそう思いながら、雨音だけ
に耳を傾ける。その不思議な静けさの中で意識が薄れていく。
昼過ぎふたたび眼が覚めた。
起きて歩くが頭が痛い。振ると割れるように痛い。
その日マサオは、雨の音を聞きながら一日じゅう部屋の中で
ごろごろしていた。
雨音はなぜか自分を安心させるとマサオは気づいた。
翌日の日曜も雨だった。
マサオは物音ひとつ聞こえない静かな気配の中で目覚めた。
時計は昼の十二時を過ぎていた。だがよくよく耳を澄ますと、
弱い雨音が聞こえてきた。窓の外は相変わらず薄暗く、布団か
ら出る手足に触れる空気がひんやりとして気持ちがよい。起き
て歩くが昨日のような頭の重みはない。窓を開けると湿っ
た空気が部屋に流れ込んだ。マサオは大きく息を吸った。雨は
小降りになっている。町並は雲が見えない灰色の空の下に、靄
が掛かったように煙っている。マサオは《嘘のように静かだ》
と思う。窓枠についたほこりが雨水の流れの跡を残している。
マサオは窓に腰をかけ、ゆっくりとタバコを吸いながら、隣家
との間の狭い路地にぼんやりと目を向ける。
ときどき雨どいから漏れるしずくが隣家のひさしに撥ね、マサ
オの手や頬に掛かる。
マサオはそれも心地よいものに思われ、拭おうともせずに昨日
の大雨の名残を思わせるかのような、水溜りや、足跡の消えた
路地を眺め続けた。
植木鉢のはの緑が生き生きとマサオの眼に映った。その葉が
雨だれを受けて規則正しく揺れ動いている。水溜りのかすかな
水の流れや、規則的な雨だれなどの小さな世界を眺めていると
、自分は回復しつつある病人のようにマサオは感じた。
しばらく眺めたあと、窓を閉めてふたたび布団の上に横にな
った。雨が降り続けている外の世界に耳を傾けていると、不思
議と心が安らぎ、手足や頭が自分のところに戻ってきたかのよ
うに感じるのである。
薄暗い部屋の静けさの中でマサオは、何もしないまま、だが
充実した気持ちの夕暮れを迎えた。
知らない人が見たら、薄暗い部屋の中でくすぶっている気味
の悪い人間に見えるかもしれないが、マサオにとっては唯一の
安らぎであり心の平安なのである。少なくとも、こうして雨の
日の夕暮れを迎えているほうが自分には似合っているように思
うのである。そして、昨日までの人ごみや騒々しい雰囲気の中
で迎えている夕暮れは狂気じみたものに思えるのである。
《もう町には出かけたくない、人にも会いたくない、このまま
こうしていたい》とマサオは思うのだが、でもそれはマサオに
とっては、自分の頭から葬りさりたい思いでもある。
マサオはタバコが切れていることに気がついた。
部屋のドアを開けて外に出ると、湿っぽいひんやりとした外
気がマサオを包み込んだ。吸い込むと生臭く、土や青草の匂い
を含んでいるようにも感じられた。と同時にある心の広がりを
感じた。それは過去の出来事へと自分を連れ戻すかのようだっ
た。しかし、それが、いつ、どこでの出来事なのかは、漠然と
してハッキリしない、だが、それはなつかしい物のようであっ
た。そして、そうして静かに外気を吸い込んでいると、自分の
懐かしい思い出を呼び起こせるような気がして、非常に心地よ
いものに思われた。マサオはそのままじっとして居たかった。
雨は霧雨になっていた。マサオは傘を広げると、狭く薄暗い
路地をゆっくりと歩き出した。雨は家々の屋根をぬらし音もな
く降り注いでいる。マサオは街灯の下まで来ると、ふと立ち止
まり、空を見上げた。降り注ぐ霧雨が街灯の光を受けて、そこ
だけボォッと白く光を放っている。マサオは顔や腕を濡れるま
まにして、じっと霧雨の舞い落ちる様子を眺めた。肌を通して
静かな世界が自分の体内に入っていくようにマサオは感じられ
た。
マサオはタバコを買ったらそのまま部屋に帰って来ようと思
っていた。町の人ごみや騒然として雰囲気に今の自分の充実し
た気持ちが乱されたくないと思ったからである。それになんと
いっても煩わしかった。
人がけの少ない通りにぽつんと自動販売機が置いてあった。
マサオはタバコを買い求めて帰ろうとしたが、ちょうどそのと
きひとりの若い女性がマサオの後ろを通り過ぎた。マサオはそ
のリズミカルな歩き方や、真っ赤なレインコートに眼を奪われ
た。まさおは静かな動揺を覚えた。《まあ、いいだろう、遠回
りをするのも悪くない》とマサオは思い、その女性の跡から歩
いていった。コッソリと後をつけて歩く快感を覚えながらマサ
オは歩き続けた。女の前方には、霧雨に煙るビルディングがそ
の黒々とした輪郭を現し、夜空には赤や緑の原色のネオンサイ
ンがぼんやり浮かんでいる。そして通りには遠く人々のうごめ
きが見えた。
このまま行くと、町の賑やかな通りに出ると思い、マサオは
横道にそれようと思ったが、ちょうどそのとき、遠くかすかに
駅の構内に響くスピーカーの声が聞こえてきた。そして車のラ
イトが女性の姿をはっきりと映し出した。マサオは憑かれたよ
うにふたたび女性の後を追った。いつの間にか人影がマサオの
後ろにも現れ始めた。
車が頻繁に通るようになり、マサオは歩きにくさのために道
路の端に寄った。こじんまりとした店が、道のよう側に現れ始
め、それらの店先から漏れる照明が霧雨に湿った道を光らせ、
歩む人々の姿を照らした。人々は二人三人と群れを作りマサオ
の前後を歩き始める。ビルの灰色の壁が歩く人々を威圧するか
のように道の両側にそびえたち始め、人々は傘の下に表情を隠
しもくもくと歩いている。マサオは引き返そうかと、ふと思っ
たが、それほど自分の心が乱れていないことに気づき、それに
町の風景や人々の姿がいつもと違ったように感じられ、そのま
ま進むことにした。
マサオは人々の群れとともにさらに歩いた。ビルディングの
窓から漏れる光や、目立ち始めた広告塔の光が霧雨に乱反射し
上方を明るくしている。マサオはそれらに眼を奪われて歩いて
いるうちに、いつの間にか先ほどの女性の姿を見失っていた。
いきなり駅前の華やかな風景がマサオの全視界に飛び込んで
きた。マサオは心地よい動揺を覚えながら捕われたように雑踏
の中を歩いた。どこからともなく鳴り響く扇情的な音楽が町全
体に溢れ、人々の足取りをいやおうなく軽快にする。マサオは
その押し付けがましさにやや不満を感じながらも、体全体に沸
き起こる躍動感を無視することはできなかった。おびただしい
車の排気音がひとつの騒音なり、人々の全身にまとわりつく。
マサオ方角を見失いそうになりかけながらも人々の流れに従い
歩き続けた。駅に通じるすべての通りの建物には、色さまざま
のおびただしい広告塔やネオンサインが乱雑に掲げられ、激し
く人々の資格をかく乱する。マサオは思考力が失いかけそうに
なりながらも、昂揚する気持ちを感じながら歩き続けた。
人々は相変わらす霧雨のなか傘の下に表情を隠して歩いてい
る。デパートに出入りする人々、駅に出入りする人々、そして
これといった目的もなさそうに歩いている人々が、衝突し渦を
巻き、舗道に溢れるほど混雑している。マサオは人々の流れに
従いながら、帯びた足しい人々とすれ違い、すれ違い、歩き続
けた。そして、いつの間にか、駅の構内に来てしまっていた。
だがマサオは、自分はどこかへ行こうとしているのではないこ
とに気がつき、ふたたび混雑する構内を通り抜け、通りに出た。
霧雨の駅前風景はいつもと違う趣きが感じられた。色さまざ
まのかさやレインコートが夜の光に映えていた。とくに女性た
ちのそれは色鮮やかで華やかである。そして人々は華やかで快
楽的な風景に不思議なほど調和している。霧雨に夜の光が乱反
射して町は巨大なドームのように光を放っている。
マサオは閉店間際のデパートになんとなく入った。何を買う
わけでもなく、綺麗に陳列された靴や楽器や章ケースの宝石を
横目で見ながら、そのまま足早に外に。マサオは先ほどとは気
分が変ったことを感じながら、人々の流れに逆らうようにゆっ
くりと歩いた。マサオは自分が意外と冷静で思考力を失ってい
ないことに気づき、安心した。そしてやや傍観者のような気持
ちで町を歩く人々や風景に眼をやりながら歩いた。
マサオはすれ違う若い女性の花もようの傘の下からのぞく容
貌に突然眼を奪われた。それは夜の華やかさや快楽的な町並に
似合った造花のような美しさである。マサオは後頭部がしびれ
、両腕が抜け落ちてしまいそうな興奮を覚えた。マサオにとっ
てはそれは絶望的な恍惚感であった。
マサオはさらに歩いた。高められた気分のまま。ときどき上
方を見上げながら。マサオは歩きながら気づいた。傘の下に隠
れている人々の表情がほとんど同じであることに。ときどき満
足げに笑みを浮かべているものもいるが、それはあくまでも本
人自身のためのものである。そしてほとんどは自己に閉じこも
り、無表情でよそよそしいのである。どうしてあのようなそっ
けない表情になるのだろうかと思うと、マサオはいらだち、反
発とも嫌悪ともつかない感情を覚えた。
霧雨が降り続くなかマサオは通りから通りへとさ迷い歩いた
。人間はどこでもいっぱいだった。そしてその表情は皆こじん
まりとしていて他人そのものだった。マサオは要約群集の流れ
からはずれ自分の速度で歩くことにした。そしてゆっくりと歩
きながら人々や町の風景を眺めた。そしてふとショウウインド
ウに映る自分の顔を見て思わず愕然とした。こんな顔をしてい
るはずはないと思った。一時間ほど前に部屋に居たときの自分
の顔の表情とは似ても似つかなかったからである。それは町を
歩いている人々と同じ表情をしていたのだ。マサオの思考力は
急速に低下し始めた。そしてマサオはふたたび群衆の流れに任
せて、当てもなく歩いた。
それから一時間後、マサオは疲れたと思った。ただ歩いてい
るだけなのに、前身にけだるさを覚え、頭が重く、軽い吐き気
を感じた。マサオは気づいたように自分のアパートのほうへと
向きを変え歩き出した。
賑やかな通りの喧騒を離れて、マサオは人気ない通りを歩い
ていた。先程までの全身を投げ出しなくなるような陶酔感も、
今は全神経を使い果たした肉体のなかに、肌のこわばり
としてその痕跡を残していた。そしてマサオの意識を広げてく
れて霧雨も、鈍感になった手足にまとわりつくだけである。町
の風景に翻弄された頭はもう平常の思考力を失い、ただ全身を
蔽う虚脱感を感じながら、マサオは手足を引きずるようにして
歩いた。重くこわばった両肩、ぷつんと切れそうな視神経、そ
してバラバラになりそうな手足のために、マサオはとにかく休
息が欲しいと思った。マサオは振り返り遠くなった町を見た。
霧雨のなかに町はマサオを拒絶するかのように夜の光に泰然と
輝いていた。
マサオは軽いめまいと吐き気を覚えながら跨線橋を渡り始め
た。マサオがその中央に差し掛かったとき、電車が跨線橋を揺
らしながらマサオの真下を轟音とともに通り始めた。
《大轟音のなか、迫り来る鋼鉄の車輪、一瞬の内に頭蓋骨が打
ち砕かれ、血しぶきが上がり、人形のように手足が引きちぎら
れ、飛び散った赤い肉片の血のりが、冷たい線路に粘りつく》
マサオがこの幻影から逃れたのは、ちょうど電車がマサオの
下を通り過ぎたときであった。そこまでわずか四五メートルの
距離。マサオは呪縛されたかのように足が動かなかったのであ
る。
マサオは自分のアパートに通じる路地に入るまえにもう一度
振り返り遠くなった町の風景を見た。マサオには捕らえようが
なかった。ただ漠然と、妬ましいもののようにも、巨大で得体
の知れないもののようにも思われた。そしてマサオは自分がど
うしようもなく小さく惨めなものに思われた。
部屋に帰るとマサオは、ぐったりとして布団の上に横たわっ
た。
だが、しばらくすると猛烈な空腹感に襲われた。
夜は何事もなく更けた。時計は十二時を回っていた。明日は
仕事だと思いながらマサオは眠りに掛かった。外は静かだ。ガ
チャンとガラスが割れるような音がした。マサオはいやな予感
がした。その音は大家のほうからである。男とも女ともつかな
いわめき声が聞こえると、ふたたびガチャンと音がした。《ま
さか、源三がタカに暴力を振るっているのではないだろうか》
とマサオは思った。日頃源三はタカに横暴に振舞っていること
はわかっていたが、それもせいぜい大声で怒鳴るとか、手元に
あった軽いものを投げつけるぐらいで、いつもはそれほど大事
にはならないことをマサオは知っていた。しかしガラスが割れ
るほどなら、もしかして大変なことになっているのではないか
と不安になった。もしそうなら様子を見にいき止めに入らなけ
ればと思った。が、そう思うまもなく、マサオの斜め下に住む
同棲中の翔子が、やはりその音を聞きつけたのか、ドアを勢い
よく開け、駆けつけるのが聞こえてきた。源三がいくら年寄り
とはいえ、若い女の力で男の暴力をとめることはできるのだろ
うかと心配になった。翔子が駆けつけた後も、ののしるような
声がしたあと、ガチャンという音が聞こえた。《やはり、翔子
ではダメか、人騒がせな》と思いながらマサオは起き上がろう
としたが、なんとなく様子がおかしい、意外と静かである。大
変なことになっているのなら、翔子の悲鳴でも聞こえてきても
良さそうなものだと思った。マサオはまず様子を見ることにし
た。そこでトイレの窓をそっと開けて見た。大家の玄関のドア
は開けっ放しで、翔子がそのそばで、少し途惑った様子でたっ
ている。その足元には割れた植木鉢が散乱している。そこへふ
たたび植木鉢が勢いよく投げつけられた。翔子は軽くよけなが
ら、どうして良いか判らなそうにただじっと見ているだけであ
る。そこへ両手で植木鉢を持ったタカが出てきた。そしてのの
しり声を上げながら、それをコンクリートの地面にたたきつけ
た。それらはすべて源三が大切にしている鉢である。
最近になって源三は、偶然にも連日のように酒を飲む機会恵
まれた。町内の会合とか、自分の気まぐれとかで。そして夜遅
く帰ってきては、タカを怒鳴っては用事を言い付けていた。《
今頃までどこで》と不満顔で独り言を言うタカに、《会合、会
合》と余計なことだと言わんばかりに怒鳴り散らしては、納得
いくように答えようとしなかった。タカはそれをひどく怪しん
だ。
今日もしたたか酔い、上機嫌で帰るなり、寝いてるタカを怒
鳴りつけて起こし、それでもグズグズしているタカをめがけて
靴下を投げつけた。タカは不満ながら返事もしないで無視し続
けた。源三は「クソババア」といいながらタカの背中を足で小
突いた。タカは憤懣が胸までこみ上げ、逆上したかったが、で
もできなかった。やはり内心源三が怖かったからである。そし
ていつものように台所に逃げた。だが気持ちが収まらない。そ
してぶつぶつ言いながら、居間と台所の間をオロオロと行き来
していた。いつもならここで源三の怒声が追い討ちをかけるの
であるが、でもどうしたわけか、今日はなかった。タカは日頃
から、《今日こそはこう言ってやろう》《今日こそはこうして
やろう》と思っているのであるが、いざ反抗するとなると、長
い間の習慣のせいか、源三の前では金縛りにあったように身動
きが取れなくなってしまうのであった。
反抗にはその重圧を撥ね退ける、感情的、肉体的きっかけが
必要なのであるが。タカは手元にあった食器を上ずった声を上
げながら投げつけた。それはふとした気済みであった。何か明
確な考えを持ってやったわけではなかった。
食器が音をたてて砕け散ると同時に、タカは全身が身震いす
るほどの恐怖に襲われた。そして破滅的な気分になった。源三
は突然の剣幕に気後れして声も出なくなった。タカはそういう
源三をとっさに見抜いた。そしてタカは勇気付けられ、気が大
きくなった。後はもう積もりに積もった怒りのマグマを破滅的
な気分の裂け目からあふれ出させるだけで十分であった。
「いままで何してやがった!」
とタカは眼を吊り上げののしった。そしてふたたび食器を投げ
つけた。源三は面食らったようにただ黙っていた。そのとき翔
子が駆けつけてきたのだ。それでタカはさらに勇気づけられ、
このときばかりと怒りをあらわにした。そして今度は玄関先に
おいてあった植木鉢を投げつけた。
「あうせい、こうせいって、人を何だと思っていやがる」
そういいながら今度は鉢を持って玄関の外に出ると勢いよく投
げつけた。
トイレの小窓から見ていたマサオは、タカのその姿を見て、
こういうことだったのかと少し安心した。源三は身動きがとれ
ずに無言のまま今に座っていた。まさかこういうことになると
き思ってもいなかった。高を括っていたのだ。いまさら大声で
威圧して抑えることもできそうになかった。かといって、みっ
ともないから止めろともいえなかった。後は自然に収まるまで
待つしかないとあきらめた。
「ババァ、ババァと、バカにしやがって、こら、出て来い」
タカは玄関から今に居る源三に向かってののしり続けた。荒々
しい言葉の割には、タカのその表情は意外と穏かであるように
マサオには見えた。そのとき隣近所の人々が集まってきた。や
はりただならぬ物音に心配だったのだろう。でも翔子と同じよ
うに、手の出しようもなく、また別に止めようともしなかった
。まもなくタカは、《出てこないなら、こっちから出て行って
やる、もう二度と帰ってくるもんか》と言って、霧雨のなか、
傘も持たずにどこかへ歩いていってしまった。源三は相変わら
ず無言であった。しばらくしてタカが隣家の人ともに帰ってき
た。《もうこれで大丈夫だ、安心して眠れるだろう》とマサオ
は思った。しかしタカは玄関に入るなりふたたび鉢を持ち出し
てきて地面にたたきつけた。そしてののしった。
「やい、ジジィ、もう怖くなんかないからな」
タカは収まりかける源三への自分の怒りを鉢を投げることによ
ってふたたび高めることによって、心の奥底にある源三への恐
れを抑えていなければ不安だった。
「出て来い、どこで、××××してきやがった」
タカは玄関の柱を強くたたきながらののしった。翔子の姿はも
う見えなくなっていた。タカは決して玄関から中へは入らず外
をうろうろしながら口汚くののしり続けた。その後しばらく静
かになったので、収まったのかなと思いきや、ふたたびタカが
、外をうろうろしながら、自分の怒りを再確認するかのように
、怒りの表情を浮かべてののしった。しかし、源三の反応は依
然として無言である。そして再び、タカは《こっちから出て行
ってやる》と強くはき捨てるように言うと、霧雨のなかをどこ
へともなく歩いていった。
マサオはタカの後を追う隣家の人の足音を聞きながら布団に
入った。《たぶん、大丈夫だろう、それにしてもずいぶん人騒
がせな》と思いながら眠りに掛かった。
その夕刻、マサオは帰りの電車に乗り込んだ。車内はいつも
のように混み合っている。埃を吸い込んだ汗が腕や首筋に粘り
つく。ビルの間に沈みかける夕日に額の皮膚が焼けるように暑
い。電車が揺れるたびに、隣り合わせる人との肌がふれあい、
汗ばんだぬくもりが伝わる。マサオの内部の抜け出せない親密
感は、疲労した肉体において反射的な不快感となって現れ、そ
の苦痛のあまり、マサオに人々の疲労した表情を見ることや、
人々と眼を合うことを、犯罪者のように恐れさせた。マサオは
閉じ込められたような息苦しさを覚えながら、出来るだけ人間
の密度の薄い場所へと移動する。そして波のようにマサオの内
部に侵入してくる見知らぬ人間の息づかいや汗の匂いの不快感
に耐えながら、額の汗を拭い、窓の外に眼をやる。
陽は完全に沈んだ。電車は駅に止まるたびに、その乗客の数
を減らしていった。マサオは広く開いた席にぎこちなく腰をか
けた。乗客たちは相変わらず親近感をあらわすことがタブーで
あるかのように、無表情に座り続けたままお互いをよそよそし
くしている。マサオも無表情を装い少し足を広げ楽な姿勢でシ
ートにもたれた。
《もう少しの辛抱だ。それにしてもいくら見知らぬもの同士と
はいえ、こうも窮屈で不快な思いをしながら、お互いに我慢し
ていなければならないなんて、まさに拷問を掛け合っているみ
たいだ。だがもうじき開放される。もう少しの辛抱だ》マサオ
は心の中でそう呟きながらじっと耐えた。
次の駅で乗客がやや増え、マサオの隣にも座るようになり、
座れない乗客かあちこちに立つようになった。マサオは座りな
おし窮屈な時間から逃れるのを待ち続けるかのように眼を閉じ
た。
突然、電車の走音のなかに怒声が響いた。《酔っ払い? ま
さかこんな早くから》とマサオは思いながら眼を開け、その方
角を見た。つり革にぶら下がり立っている中年の男が、その眼
の前に座っている若い男に向かい、顔を真っ赤にして怒鳴りつ
けている。傍に立っているその男の妻らしき女も、ときおり同
調を求めるかのような眼つきで周囲を見まわしては、その若い
男を睨みつけている。やがてその中年の男は、若い男のひざを
激しく手でたたいて、その組んだ足を払いのけた。足をはらわ
れた若い男は少しも表情を変えずにそのまま再び脚を組んだ。
「君のような人間がいるから、、、、何度注意したらわかるん
だ、、、、」
義憤の表情をいっぱいにだしながら興奮して喋る男の怒声が途
切れ途切れに聞こえる。しかしマサオには、その中年の男がな
ぜあのように怒り続けているのは判らなかった。どなられ脚を
払われても、その若い男は、じっと耐えるように視線を下げ無
言で座っている。電車が止まり席が空いた。その中年の男は顔
をこわばらせたまま座った。妻らしき女もあきれたような薄笑
いを浮かべながら、その若い男をじろっと睨みつけて座った。
それでも若い男は終始なんら弁解めいた表情をすることもなく
座り続けていた。不思議なことに周囲の乗客もそれほど関心を
示しているようではなかった。
《いったい何が起こったのだろう? みんなの眼の前で、当然
のごとく怒りの表情を浮かべる中年男女の一方的な怒声や薄笑
いや暴力の屈辱を甘んじて受けなければならないほど、その若
い男は、彼らに対していったいどうな無礼を働いたのだろうか
?》とマサオは悩んだ。まもなく電車はマサオが降りる駅につ
いた。
マサオは人ごみにもまれるようにして駅の構内を出た。駅前
の華やかな光景を目にしながら自分が解放的な喜びに満たされ
ていくのを覚えた。電車内の息苦しさとは違い、自由気ままに
歩き廻れると言うことが、なんとも奇妙で楽しかった。マサオ
は不思議と勇気づけられ子供のように気分がうきうきした。ア
パートに帰っても別に何をすることもないと思い、このまま夜
の街を歩くことにした。公衆便所に入りすっきりすると再び夜
の街を歩き出した。もともとどこかへ行こうという目的もなか
ったので、成り行きに任せ、通りから通りへと、繁華街から繁
華街へと歩いた。薄着の女たちの後をさりげなくいるいてみた
り、映画の看板の前に立ち止まって大胆に眺めたりしながら気
まぐれに歩いた。そして人影の少ない通りに出るとすぐに引き
返して再び華やかな通りを歩いた。マサオはいつもより胸を張
って歩いていることに気がついた。快楽的なネオンに誘われそ
うになったが、自分ひとりで飲んでいる姿を思い浮かべると、
さまにならないような気がして、そのまま通り過ぎた。パチン
コをやろうとして入ったが、店内の混雑振りや騒々しさには堪
えられないと思い、急いで外に出た。本屋に入ったが、これと
言って興味がわかず、適当に眺めては通り過ぎるように外に出
た。
行き当たりばったりに歩いているうちにマサオは食事はまだ
であることに気がついた。そして食堂に入ろうとして、ポケッ
トに手を入れたが、財布がない、あちこちのポケットを調べた
が、やはりない。《落としたのだろうか? それにしても、い
つ? どこで?》と思い巡らしたが、頭には何も浮かんでこな
い。華やかで快楽的な風景を眼の前にして、方角も時間も失っ
た痴呆のようにマサオの頭は混乱した。たったさっきまで、ど
こをどう歩いてきたか、どこで何をしたのかの記憶がすべて失
われたかのように何も思い出せない。《いつものように駅を出
たところまでは、それから先が、、、、、》マサオは焦り無力
感に捕われた。そして一瞬絶望的な気分に襲われそうになった
。しかし気力を振り絞り、衰えかけた想像力を働かせながら《
財布の中身は期限まじかの定期券とわずかな金、それにアパー
トには買い置きの食料が在ったはず》とこれ以上くよくよしな
いように、自分を納得させて帰ることにした。
アパートに帰ると、玄関にまずまきをしていた大家のタカが
、いつもより心なしか穏かな表情でマサオに挨拶をした。マサ
オも自然と沸き起こる笑みを浮かべて挨拶をした。
マサオが夕食の用意をしていると、タカから電話の呼び出し
を受けた。
電話の相手はマサオの財布を拾ったと言う男からであった。
マサオは再びと外に出た。そして相手の男から指定された場
所へと急いだ。
マサオにとってほとんど諦めかけていたことであったが、見
つかってみるとやはり安心したのか、空腹であるにもかかわら
ず不思議と足取りが軽かった。たぶん駅の近くの公衆便所で手
を洗ったときに置き忘れたのだろうと、マサオは歩きながら考
えた。それにしても相手の男は?判りやすい駅前とかではなく
、わざわざ駅から離れた公園を待ち合わせの場所に指定してき
たのだろう? 受話器腰ながらも、相手の男は人前や目立つ場
所を必要以上に避けているようにもうかがえたが、もしかした
ら浮浪者か?それともある種の趣味を持ち男か?それにしても
どうして交番に届けなかったのだろうか? なぜ直接、、、、
マサオはあれやこれやと疑問を抱いているうちに気味の悪さを
感じ始めた。打がその一方では、男同士とはいえ、人目を避け
て会うことに何か冒険に挑むときのような心ときめくものもあ
った。
駅から少しはなれたところに、昼間よく子供たちがブランコ
のりや砂遊びをする程度の小さな公園があった。
夜には人影はなく薄暗い。雅夫はそれらしい男とを見つけると
、少し警戒心を抱いて近づき自分の名を名乗った。拾い主はサ
ラリーマン風で人の良さそうな五十歳ぐらいの男性であった。
マサオは「どうも」と曖昧な挨拶をして用心深そうな笑みを浮
かべた。
「どこに落ちてましたか?」
「駅前の広場のベンチ」
と男は友人のような親しさで答えた。
マサオはなぜそんなところにと思ったが、相手の親切心を裏
切ってはいけないと思い表情は変えなかった。
「調べてみてください」
男にそういわれて、マサオは途惑ったように自分の財布を調べ
た。
「あぁ、えぇ、だいじょうぶ、あります」
とマサオは曖昧な笑みを浮かべて言った。そして、
「いやぁ、助かりました。どうも、どうも」
とやや警戒心を抱きながらお礼を言った。中年の男の表情は、
人ごみや電車内の人々のよそよそしい表情とは違い、ドキッと
させるような親しみに溢れていた。それがマサオにとっては不
気味であったが、同時にそのような表情に触れていると、マサ
オの心も自然と和らぎ、子供頃友達といっしょに暗い押入れに
入ったときのような、怪しい連帯感を覚えた。マサオはもう一
度お礼をいうとその男と別れた。
別れて歩きながらマサオは、その男の妙に親しみに溢れた表
情が気にかかった。お礼のためいっしょ飲むべきではなかった
かなとも思った。マサオはそのほかにもいろいろな疑問がわい
たが、結局それ以上何も考えないことにした。
マサオは寝床に入りながら今日一日の出来事を何とはなしに
思い浮かべた。そしてふと全身が熱くなるほどの衝撃に襲われ
た。電車内で青年が中年の男女に一方的に怒鳴られていたその
原因が判ったような気がしたのだ。
もしかしてあの青年は足を組んでいたからではなかったかと。
人が前に居るときや、混雑しているときは足を組んではいけな
いというのが、乗客たちの暗黙のルールであるらしい。マサオ
も何気なく足を組む習慣がある。それを今まで特別意識するこ
ともなく行ってきた。《もしあの青年が自分だったら、どんな
に居たたまれない気持ちに、いや帰ってあの中年の男女に怒り
を覚えていたかもしれない》と思うと暗然とした。もう何年も
この都会に住んでいて、そんなことに気がついていなかったこ
とに冷や汗の出る思いであった。そしてこの都会が自分とは関
わりのないところで動いているように思われ、マサオはいつま
でたっても住み慣れない余所者のような気持ちがした。少し興
奮が収まり、意識が薄れていくのを感じながらマサオはもう一
度電車内での出来事を思い浮かべた。でも車内はそれほど混雑
していた訳ではなかったのに、と思うだけだった。
その土曜日。長いあいだ雨や曇りの日が続いていたが、久し
ぶりに朝から晴れ渡っていた。陽射しは強く、マサオの部屋の
温度は寝苦しいほど上昇していた。十時頃、マサオは里の騒々
しさで眼が覚めた。それは翔子の大げさな悲鳴で始まった。洗
濯物を乾していたら、軒先を這っていたヘビを発見したのであ
った。翔子は急いで大家に駆け込んだが、源三が出かけている
ため、タカひとりではどうしようもなかった。翔子とタカが、
あっちに逃げた、こっちに来たと子供のように大声で騒ぎ立て
るうちに、ヘビは逃げ場を失ったのか、軒先にたけかけてあっ
たガスボンベの底に入ったらしい。
「たいへん、入る、入る」
と言う翔子の叫び声を聞きながらマサオは布団のなかでうつら
うつらしていた。
「アッ、いやだ、顔出している。ねえ、おじさんはどこへ行っ
たの?」
「どこへ行ったんでろう?」
「他に男の人はないのかな?」
二人の会話を聞きながらマサオは、今起きるのはまずいと思
い、寝苦しいがまた眠ることにした。
まもなく階段を駆け足で上がってくる足音が聞こえ、マサオ
の部屋のドアを強く叩く音がした。
マサオに助けを求めに来たらしい。だがマサオもヘビは苦手
である。
「起きてますか?」
翔子の声である。マサオは寝た振りをして無視することにした
。しかし翔子はしつこかった。マサオがなかに居ると決めて掛
かっている。マサオは仕方なく起きて、ドア越しに「なんです
か?」と訊いた。
「アッ、起きた、起きた」と翔子は安心したようには呟いたあ
と言った。
「ヘビが出たんです! つかまえて! 」
「ヘビは苦手ですから」
「お願い! 」
「わかりました。ちょっとまって」
翔子は急いで階段を降りると、嬉しそうに「居た! 居た! 」と
言いながらタカに走り寄る。
《まったく、人を何だと思っているんだ》とマサオは心の中で
呟きながらも、妙に気負いの気持ちを抑えることはできなかっ
た。そして急いで身支度をして階段を下りて行った。さっきま
で眠っていたマサオの眼には外はまぶしかった。マサオはなる
べく翔子を避けてタカに話しかけた。
「どこに居るの?」
「ここ、この穴から入ったんだよ」
とタカはガスボンペの底を指差した。たしかに穴はあった。だ
が直径一センチほどである。マサオにはヘビが入るとは信じら
れなかった。
「ほんとうにここから入ったの?」
「そう」
とミニスカートをはいた翔子が口を挟んだ。
マサオは底の高いサンダルをはいた翔子の素足に何気なく眼を
やりながらたずねた。
「小さいの?」
「ううん、ものすごく大きいの! 」
と翔子は無邪気に答えた。
マサオは追い詰められたヘビが身をくねらせて無理やり自分
の体をその小さい穴に押し込んでいる姿を思い浮かべた。だが
、正直なところマサオには手の下しようがなかった。でも、頼
られているのだから、何とかしなければと思い、勇気を奮い立
たせるとマサオは、棒を見つけてきて、ボンベを片手で傾け、
この奥に目を輝かせて潜んでいるヘビの姿を思い起こしながら
、底の砂利を取り除き始めた。マサオは取り出し口を作り、ヘ
ビを引きづり出そうとしたのだ。しかし、もし仮にヘビが出て
きたとしても、マサオは棒切れでヘビを家の遠くへと追い払う
ことしかできなかったのだが。
マサオはヘビが自分に向かって這って来るのではないかとい
う恐れを抱きながら、なるべくボンベから離れて恐る恐る砂利
を取り除き続けた。
マサオは寝起きと暑さのため意識がぼおっとしてきて顔から
は汗が噴きでて来た。だがヘビの姿はなかなか見つからない。
やがてタイトのミニスカートをはいた翔子がマサオとは反対側
からしゃがんでその様子をみていることにマサオは気づいた。
「ほんとうに入ったの?」
といいながらマサオは何気なく翔子のほうに眼を向ける。
「うん」
と翔子は安心しきった子供のように答える。
「もっとこっちに来て手伝ってくれない?」
「いやん! 」
そのうち腕が疲れてきたマサオは、少し脅かせば出てくると
思い小刻みに乱暴につついた。だが出てくる気配はなかった。
それでもマサオは、冷たく湿っぽいヘビに巻きつかれる恐れ
をいだきながら穴を掘り続ける。
翔子とタカを安心したように話しこんでいる。
「いいかい、ヘビが出てきたら、そっちに追い払うから」
とマサオが言うと、翔子は
「まあ、たいへん」
といいながら飛び跳ねるようにして逃げた。
翔子とのやり取りで不思議と新たな力が沸いてくるのを感じ
たマサオはなおも掘りつづけるが、それでも出てくる気配はな
い。なんとか自分で解決したいと思っていたが、暑さと疲労の
せいもありもう諦めるしかないような気がしてきた。
「おじさんは、いつごろ帰ってくるの?」
とマサオはつかれきった表情でタカにたずねた」
「もうそろそろ帰ってくるだろうけど」
そうこうしている内に源三が友達といっしょに帰ってきた。
マサオはこれで助かったと思った。
タカから事情を聞いた源三は、「何ヘビだろう?」と言いな
がら、急いで帰ってくると途方にくれているマサオを見てささ
やくように話し掛ける。
「女たちはヘビが怖がるからな!」
その言葉には気負った男の優しさが込められていた。
マサオはただ力なく「はい」とこたえるだけだった。連
れの男はどこからかしゃべるを持ち出してきて、「これでどう
だ」と言いながらスコップの先を地面に突き刺した。ヘビを殺
すつもりらしい。源三は「大丈夫」と言いながら、いさましく
ボンベの底に開いた穴から手を差し入れた。そして「あぁ、居
た居た」と言いながらヘビを引きずり出した。ヘビはアオダイ
ショウだった。源三は腕にヘビを巻きつかせたまま「捨ててく
る」と言って路地を歩いていった。
部屋に戻るとマサオは水道の冷たい水で汗ばんだ手や顔を洗
った。そして窓を開け布団の上に横になった。まだざわつく外
の気配を感じながらマサオは自分の興奮が収まるのを待った。
窓からは暖められた空気が流れ込み、刻々と部屋の温度が上
昇していった。いつのまにか紛れこんだハエが、部屋の中を旋
回し始めた。そして投げ出しているマサオの足に止まった。マ
サオはける上げるようにして追い払うと、ハエは驚いたように
飛び回り、そして窓際のカーテンに止まり、しばらくじっとし
た後、どこへともなく飛び去っていってしまった。
陽が高くなってきて、隣家の壁にマサオの屋根がくっきりと
影を作った。その黒々とした影から、かすかな揺らめきが立ち
昇っているのがマサオの眼に映った。強い陽射しで暖められた
トタン屋根から、陽炎が上っていたのだ。そしてときおり見え
なくなった。かすかに風が起こっているのだ。
午後になると窓際のカーテンを揺らすほどの風が起こってき
た。暑くなりさえしなければ、どこへも出かけずに部屋の中で
じっとしていたいのであるが、マサオは風に誘われるように外
に出た。
《何しに来たんだろう? このまま進めば煩わしい雑踏に巻
き込まれる》と思いながらも、引き返すほどの意志も失われ、
マサオは何かに操られるように歩かなければならなかった。暑
さと混雑の中でマサオは、冷静に思考し自由に判断することが
できなくなっていた。
《どこへ行けばいいのだろうか?》とマサオは不安なまま交
差点にたどり着き、信号が変るのを待った。
マサオは街に出て雑踏にもまれるたびに、動揺し意志の自由
を奪われている自分に気づき始めていた。そしてそういう自分
に腹立たしかった。
交差点は車の走音と雑踏で騒々しく舞い上がる砂埃と排気ガ
スで煙っている。
するとふと猫の甲高い鳴き声が聞こえてきた。
《まさか、こんなところで、錯覚だろうか?》とマサオは思
った。だがたしかに聞こえてくる。その神経質さのために、深
夜人気ない通りなどを好んで歩くものだとマサオは思っていた
。それがそんな猫にはふさわしくないようなこんな騒々しい所
で鳴いているということは、何か異常な出来事を告げているよ
うにマサオには思われた。マサオは大きく動揺しながらやりき
れない気持ちで耳を澄ました。鳴き声はマサオの背後からだと
判った。マサオを振り返りその方角を見た。するとマサオから
五メートルほど離れた車道と舗道の境目に猫が横たわっていた
。何かを訴えるような眼つきで舗道を歩く人々を見上げながら
、赤い口を大きく開けて、狂ったように泣き喚いている。どう
やら車に惹かれたらしい。前足は踏ん張っているが、後ろ足は
力なく地面に投げ出し腰を重そうにして横たわっている。その
白い腹は黄色い液体で濡れていた。《なぜ黄色なのか?》と思
うとマサオは居たたまれなくなり、急いでその場を去った。そ
して暑さから逃れるかのように喫茶店に入った。
店内は涼しかったが、独りのマサオには居心地の悪いところ
だった。
他の客の話し声や笑い声がマサオをいらだたせた。新聞を読
んだりしたがほとんど頭に入らなかった。それでも少し冷静さ
を取り戻すと、もう帰るしかないと思いながら暑い外に出た。
駅から少しはなれたところにテニスコートほどの広さの雑木
林があった。二方が線路にはさまれ、もう一方は人家と道路に
囲まれた三角地帯である。道路側には人が容易に入らないよう
に木の柵が設けられている。そこにはナラなどの木が二三十本
こんもりと生え、地面には雑草が青々と茂っている。
マサオはそこを通るときはたいていその風景を横に見ながら
歩いている。
ときおり強い風が吹くと、枝が大きくたわみ、青々と茂った
葉はいっせいにひるがえり、雑草は風の通り道を示すかのよう
になびいていた。
マサオはその小さな森を吹き抜ける風を思うと、暑さや不快
な出来事を忘れさせてくれるようなすがすがしい気分に満たさ
れた。ぼんやり眺めているうちに、木々のあいだに建物のよう
なものがあるのが、マサオの眼に入ってきた。それはダンボー
ルや朽ちかけた板で作られた広さ一畳、高さ一メートルほどの
小さな小屋だった。ダンボールの屋根にはそれが飛ばされない
ようにするためか、頭大の石が載せられてある。《子供たちの
いたずらかな》とも思った。《それにしても手がこんでいるな
》とも思った。マサオはふと、町で見かける浮浪者の姿を思い
浮かべた。《なるほどここなら誰にも追い立てられることもな
く住むことができる。うまいことを考えたものだ》と思った。
マサオは板の隙間から、のんびりと寝そべっている浮浪者の
姿が見えないものかと、じっと中の様子を覗いた。なぜならマ
サオは、マサオとは違う世界に住むそんな浮浪者が羨ましい者
に思われたからである。
そんなある日の午後。マサオの同僚の斉木は中学生の卒業式
のような礼儀正しさで、上司の係長からリーダー資格試験の合
格証書を受け取っていた。いつものように自信に溢れた笑みを
浮かべながら話しかける上司に、斉木は、手渡された紙切れを
大事そうに持ち、やや腰をかがめながらも得意げな笑みを浮か
べながら、その喜びの言葉を歯切れよく答えていた。その合格
証書は、三日前車内に掲示板に発表された合格者たちへの正式
な通知となるものであった。
合格者が発表されたとき、掲示板の前には受験したものや女
子社員たちがいっせいに群がり、ため息をついたり小声で話を
したりしてみていたが、マサオは無関心を装い、群れには加わ
らなかった。だが人が居なくなると通りすがりに、その中に同
僚たちの名前を見つけては複雑な気持ちで眺めていた。
マサオは受験資格は持っていたが、受験しなかった。マサオ
はそのことを人に言えるほどはっきりとした理由を持っている
わけではなかったが、なんとなくそんな制度に息苦しい雰囲気
を感じていた。資格試験に合格したからと言って、即、給料が
上がるとか、昇進するとかというわけではなかった。ただ合格
者たちは、今後、他のものより昇進のチャンスに恵まれている
といった程度のものであった。だから受験しないものは、そう
いうチャンスを将来にわたって放棄していることになるのであ
る。
斉木と話しが済んだ上司が、しばらくすると、手持ち無沙汰
そうにしてマサオに近づいてきた。
「君はどうして受けないの?」
マサオは答えようがなかった。上司は無表情のままさらに言っ
た。
「みんな受けるんだから、君も受けたらどうかね」
「はあい」
とマサオは横を向いたまま曖昧に答えた。
「君、仕事には積極性が必要だよ! 」
振り返りながらそういうと、上司は悠然とマサオから離れてい
った。勝ち誇ったように引き上げていく上司にマサオは何か言
いたい気持ちだった。だが、具体的なことは何にも浮かんでこ
なかった。
最近マサオは、午後になると決まって軽い頭痛に悩まされる
ようになった。そしてやや神経の苛立ちを覚え、仕事上のこと
でも他人と話をしたりすることが億劫になってきた。マサオは
そんな自分に気がついていた。だが、?そうなるのか、思考の
衰弱したマサオには、その原因を探しあてるることはできなか
った。ただじっと退社時間まで耐えるしかなかった。またマサ
オは、そんな病的な自分を認めたくなかった。ましてや他人の
前ではできるだけそんな素振りは見せまいとした。とくに上司
の前では。なぜなら、それを見せることは、自分が他人より劣
っていることを認めるように思われたからである。
《なぜ他の人は、生き生きと仕事をし、楽しそうに人と接触を
しながらやっていけるのだろう》と他人をうらやましく思いな
がらマサオは自分の苦痛に耐えているのである。とくに今日は
《自分は他の人とどこが違うのだろう》と悶々として過ごした
。
そして夕刻。マサオは冷房の効いた社内からむっとするよう
な外に出て歩き出した。傾きかけた太陽は正面からマサオを照
らしている。マサオは不機嫌そうにもくもくと歩き続けた。前
を歩いている女性を追い越そうとしたとき、マサオはその女性
から声をかけられた。
「まあ、ひどい!」
振りかえるとそれは同じ会社の知子であった。
知子が少し怒ったように続ける。
「知らん振りして!」
「いや、気が付かなかった、下を向いていたもんで、、」
マサオは苦笑いをしながらそう言った。
知子は笑顔で追いつくとマサオと並んで歩いた。マサオは悪い
気はしなかった。部署は違っていたが、マサオは知子とときど
き話したことがあった。マサオにとっては最も話しやすいタイ
プであり、以前からやや好感を持っていた。マサオは何気なく
知子を見る。そして話し掛ける。
「こっちの方角なの?」
「そう、、、、」
「すると、たぶん同じ駅だね」
「そうね、、、、」
「どうして今まで会わなかったんだろうね?」
とマサオはやや大げさに不思議そうな表情をして言った。そし
て続ける。
「いつも独りで帰るの?」
「そうよ、いつも独りよ」
と知子はいたずらっぽい笑みを浮かべて答えた。
「そうか、今まで帰る時間が違っていたのか!」
とマサオは独り言のように呟いたあと、すぐに続けた。
「いつも今頃かえるの?」
「いつも同じよ。今日はちょっと違うけどね、、、、」
片言の会話ではあったが、マサオは不思議と和らいだ。
「よう、お二人さん」
と追いついてきた斉木が突然声をかけ、二人の間に割って入っ
た。そして息を切らせながら知子に話し掛ける。
「見たよ、このあいだ、いっしょのところ、凄い車に乗ってい
るんだね、、、、」
マサオは二人の会話に入り込めないような気がして、自然と
消極的になり、やや後ろから二人の様子を見て歩くようになっ
た。知子は斉木に陽気に答えてはいるが、先ほどまでの知子と
違い、マサオには少しはしたないように思われた。
斉木の冗談やからかいに、知子は笑顔で適当に受け答えをし
ている。二人はマサオの存在を忘れたかのように楽しそうにし
てとりとめのない話しに夢中になっていた。マサオは二人のそ
んな会話を聞きながら、二人のように気楽に話せない自分を意
識すると寂しい気持ちになった。
駅がもうすぐという所で、知子が突然二人にサヨナラうを言
うと、別の道に向かって歩き出した。
「どうしたの?」
とマサオは怪訝そうな顔をして斉木に尋ねた。斉木はマサオの
言葉がうまく聞き取れなかったらしく、表情を変えず黙って歩
いている。
「たしかこの駅だって、言ってたよ」
マサオは後ろを振り返りながら独り言のようにそう言った。
「デート、デートだよ」
と斉木は乱暴な口調で言った。
「あっ、そう、、、、」
とマサオは曖昧に答えた。
「としだから、焦ってんだよ!」
「年っていくつ?」
「二十五」
「僕と同じじゃない、どうりで落ち着いていると思った」
「ダメだよ、もう決まっているんだから。女ってわからないな
ぁ。陰で何をやっているのか本当に判らないよ。」
と斉木ははき捨てるように言った。
駅前は人ごみで混雑していた。マサオは前から来る人影をう
まく避けて歩きながら、斉木に話しかけた。
「試験受かってよかったですね」
「あっ、あれ、、、、」
と斉木は言いかけたが、構内の混雑で、二人の会話は続かなか
った。二人は黙って改札を抜け、同じ電車に乗った。電車はい
つものように混んでいた。マサオは混雑を避けるように少し斉
木とも離れながら夕日の当たらないドア際にたった。電車が走
ると斉木がそばによって来て話しかけた。
「受かったからって、どうってことないんだよなあ、、、、、
」
斉木はドアに寄りかかりながらがっかりしたような口調でそう
いうと、さらにしゃべり続けた。
「それで給料上げてくれるわけでもないしさあ、あんなの会社
の気休めなんだよ。君は受けなかったの?」
マサオは周囲の沈黙が気になり判ったように頷いた。そして斉
木は周囲に聞こえてもかまわないといった風にさらにしゃべり
続ける。
「そう、僕は係長に言われたんだよ。受けたほうが良いよって
。なんか受けないと、出世しないぞって脅かされているみたい
でね。本当の子と言うと僕は受けたくなかったんだけどね、、
、、なにせ受けたのは僕一人じゃないからね。他にいっぱいい
るからね。半分以上は受かっているんだよ。試験だって、それ
ほど難しくないしさ。そのうちみんな合格者になったらどうす
るんだろうね。出世なんてできっこないよ。たぶん試験の合格
で甘い夢を見させて、このままずっと飼い殺しに使用すする会
社側の魂胆なんだろうね。やんなっちゃうよ、、、、、」
マサオは斉木のいうことにいちいち頷いたりして聞いているの
がとても苦痛だった。それに周囲を意識するとなぜか恥ずかし
い気持ちであった。それに比べて斉木は周囲にまったく気兼ね
せずしゃべり続ける。だからマサオは聞いている振りをしなが
らときどき頷いてみたり、窓の外に眼をやったりしながら斉木
が降りる駅を待った。
電車が斉木が降りる駅に着いた。先に降りた斉木が振り向い
て、降りてこないマサオに向かって《来いよ、つきあえよ》と
頼み込むように言うので、マサオは人目を考えて、仕方なく電
車から降りて斉木についていった。
駅を出ると日はとっぷりと暮れていた。斉木の済む町もマサ
オの住む町と同様に、ネオンサインと広告塔に飾られた賑やか
な、そして快楽的な町だった。雅夫はその見知らぬ町を少し期
待感をいだきながら斉木の行くがままについて歩いた。道すが
ら斉木は、投げやりな口調で意味の判らないことを言ったり、
舌打ちをしたりしながら歩いた。そんな斉木を見ていると、マ
サオは話しかける気にもなれず、なんかひとりで歩いているよ
うな気分だった。斉木は何かを探しているようだったが、迷っ
ているようでもあった。マサオはどうしても打ち解けない気持
ちを抱いたまま歩いた。
繁華街を過ぎて、駅も遠くなり方角も判らなくなったころ、
斉木は人影の少ない通りに面した落ち着いた雰囲気の飲み屋に
決断よく入った。それを見てマサオはほっとしたような表情で
斉木の後から入って行った。
テーブルに座ると斉木にネクタイを緩め慣れた口調でビール
を注文した。マサオは《ここはきっと斉木の行きつけの店に違
いない》と思いながら、店の様子をぼんやり眺めまわした。斉
木はビールを運んできた若い女にからかうように意味のないこ
とを言って笑わせた。そしてニヤニヤしながらその女の後姿を
眼で追っていたが、すぐに振り返りマサオをチラッと見ては、
満足そうに飲み始めた。
「どう仕事は楽しい?」
と斉木が先に話し始めた。
「楽しくはないけど、食うためには仕方がないよ」
「食うためにね」
と呟きながら斉木は自分のコップにビールをそそいだ。
「君は確か僕より一年遅く入ってきたんだよね」
マサオは飲みながら頷いた。そして斉木は話し続ける。
「君はよく文句も言わずにもくもくとやっているよ、辛抱強い
んだね」
「そう見えるだけで、そんなことはないですよ」
「僕なんかダメだなあ、毎日同じことばっかりやっていると頭
がおかしくなってくるよ。こうして気晴らしをやらなくちゃや
っていけないよ。なにせ毎日飲むからね。給料なんてぜんぜん
残らないよ。君は残る?」
「少しぐらい」
「ああ、毎日飲まないとやっていけないよ」
斉木ははき捨てるようにそういうと、勢いよくビールを飲んだ
。マサオはひとりで飲んでいるような気持ちになった。斉木は
だいぶ酔いがまわってきたようだった。
「ああ、毎日同じことばっかりやっているなんて、頭がおかし
くなってくるよ。給料も安いし、、、本にいいところは沢山在
るのに、何もあんなところにしがみついていなければならない
理由なんてないんだよね。そう思わない?」
「他のところと言ったって、大して変らないと思っているから
」
「そうかなあ、そんなことないよ。いいところはいっぱいある
よ。今度ぼくは仕事を変えようと思っているんだよ。君そんな
こと考えたことない?」
「ええ、あんまり」
「幸せものだ。ぼくはどうもあの係長の下で働くのはイヤなん
だよ。ありゃ、相当に陰険だよ。そう思わない?」
「でも楽しそうにやっているじゃないですか!」
「そんなことないよ。どうも肌があわないんだよなあ。ずっと
あいつに頭が上がらないなんて、うんざりだよ。まぁっ、追い
抜けば別だけどね。でもあいつは意外と頭が切れるからね。ま
あ、あと十年はこのままで行くんだろうな」
「試験に受かったから案外早いんじゃないですか?」
「イヤ、僕の前にはあいつらがいるだろう、それに牧本先輩も
いる。お先真っ暗だよ。もしかして君が出てくるかもしれない
ね」
「いや、そんなことはないでしょう」
「冗談だよ」
「、、、、、」
「それにね牧本先輩は話しうまいからなあ、上司に取り入るの
がうまいんだよ、、、、」
斉木は相当によっているらしく、際限もなくおしゃべりが続
きそうだった。マサオは自分のことだけしか言わない斉木にう
んざりし始めた。斉木はビール瓶を振って空になっているのに
気づくと大声で追加注文をした。
斉木は追加されたビールを飲んでいたが、喋り疲れたのか、
先ほどのような元気は亡くなっていた。飲んだ跡は下をむきが
ちになった。そんな斉木を見ながらマサオは話しかける言葉が
見つからなかった。ちんもくがしばらく続いたあと、斉木が神
妙な顔つきで話しかけてきた。
「何を楽しみに生きてんの?」
あまりにも唐突なのでマサオは面食らった。マサオは考える振
りをして下を向いた。その仕草が斉木をますます滅入らせたら
しく、斉木は大きくため息をついて黙ってしまった。《どうし
て打ち解けた話ができないのか》と思うとマサオは腹立たしか
った。しばらくして斉木は気持ちが悪くなってきたと言って外
に出て行った。
目の前に斉木がいなくなって、マサオは今まで息苦しい思い
でいたことに改めて気づいた。マサオは椅子に背を持たせかけ
、ゆったりとした気分で店内を見わたした。
職人風の男が一人で酒を飲んでは、しきりとテレビ画面に眼
をやっていた。その隣にサラリーマン風の男二人がなにやら話
ししながら飲んでいる。店の主人はもうもうと立ち込める煙の
中で魚を焼いていた。店内は思ったよりも汚く雑然としている
ことにマサオは気がついた。マサオも相当酔っているらしく、
先ほどまでの会話をほとんど忘れていた。思い起こそうとする
が頭ががんがんしてできない。なぜ自分がここにいるのかも不
思議なくらいであった。
三十分経っても斉木は戻ってこなかった。《家に帰ってしま
ったのだろうか》とマサオは思った。一時間経っても斉木は戻
ってこなかった。店内が他の客で込んできたのでマサオは居心
地が悪くなった。マサオは醒めかけた頭でもう帰るしかないと
思った。
マサオは席を立ち、店の主人に勘定してもらうように言った
。だが、ふと心配になった。先輩の斉木の誘いということで別
に気にも留めなかったが、初めて持ち合わせが少なかったこと
に気づき始めたのだ。思ったとおりであった。二千円足りなか
った。マサオは一瞬焦ったが、斉木が常連客であるらしいので
、その訳を言って明日にでも不足分を持ってくると言えばなん
とかなるだろうと思い安心した。
マサオはレジに立っている若い女にやや申し訳なさそうな顔
をして、その旨を告げた。その女は作り笑いを浮かべると店の
主人のところに行きなにやら小声でささやいた。主人はフライ
パンで何かを料理しながら黙って聞いていたが、マサオを睨み
つけるようにして見たあと、カウンター越しに近づいてきた
。マサオは苦笑いを浮かべて「あの、斉木さん、、、、」とし
どろもどろに言いかけたが、主人がすぐ「なに、斉木?」と語
気を荒げて言うと《何をとぼけたことを言ってんのか》という
ような鋭い目つきでマサオを睨んだ。マサオは間をはずされた
ようにその後言葉が出なかった。
主人は不機嫌な表情をして、そのまま何も言わずに再び料理
に取り掛かった。マサオは気づいた。主人は斉木ことを知らな
いということ、斉木もこの店の常連ではないということ、自分
が勝手にそう思いこんでいたということに。マサオは混乱した
。周囲の視線が気になり体がこわばる思いであった。なんとう
かつなと後悔した。だが遅かった。
「その斉木って言うのは、どこに住んでいるの?」
と主人が険しい表情をして言う。
「ええと」
とマサオは言いかけたが、すぐに困惑した表情のまま何も言え
なくなってしまっ。マサオは斉木がこの町のどの辺に住んでい
るのか、まだ知らなかったのだ。さらにここの町名さえ知らな
いのだから、適当な地区名を言って、その場を取り繕うことさ
えできなかったのだ。マサオはいたずらをした子供のようにう
ろたえた。
「お客さん、いい加減にしてくださいよ」
と主人は呆れ返ったように言った。他の客がマサオを注目した
。店内が急に静かになり、テレビの音だけが響いた。マサオは
頭が上げられないほど恥ずかしかった。主人は険しい表情で料
理をフライパンから皿に移していた。完全にマサオは信用を失
っていた。いまさらどう弁解しても、主人の印象をよくするこ
とは不可能だと判ると、急いでこの場から逃げ出したい気持ち
になった。しばらくすると、主人が薄笑いを浮かべて言った。
「あんたどこの人、何か自分を証明するものは持ってないの?
」
マサオはようやく自分の社員証を提示することを思いついた。
マサオは全身から汗が吹き出るような恥ずかしさを感じなが
ら社員証を提出して、不足分は明日必ず持ってくることを約束
した。
マサオは酔いと気落ちでよろけそうになったが気力を振り絞
り外に出た。
街路樹がかすかに風に揺れた。マサオはそのざわめきが気に
なった。忌々しいと思った。マサオは気を取り直し何事もなか
ったかのように歩きだそうとしたが、帰り道が判らなかった。
マサオはここに来た道順を思い出そうとしたが、疲労と酔いで
頭には何にも浮かんでこなかった。マサオは早くこの場から離
れたいいっしんから、どっちでもかまわないと思い半ばやけ気
味に歩き出した。
歩きながら恥ずかしさと悔しさが交互にこみ上げてきた。マ
サオはすれ違う人に見られているような気がして歩きづらかっ
た。
ちょっとした誤解からとはいえ、ごろつきのように扱われた
ことを思うと腹立たしかった。
マサオはまず駅を見つけださなければと思った。だが、行っ
ても、行っても、駅がありそうな場所には辿りつけなかった。
マサオは見知らぬ町を迷い犬のような心細さで歩いた。歩きな
がら忘れかけていた悔しさがこみ上げた。
道を横ぎっていると一台の車が、マサオの前を通り過ぎなが
ら「ばかやろう、気をつけろ」とマサオを怒鳴りつけた。その
瞬間マサオは反射的に敵意を覚え、そして過ぎ去った車を睨み
つけた。信号を無視したのはマサオだった。マサオは自分が悪
いと思いながらもこみ上げる怒りにやりきれなかった。情けな
いと思った。
マサオは泣き出したいぐらい惨めな気持ちのまま歩き続けた
。だが駅は見つからなかった。
いつのまにかマサオは広い通りに出ていた。
都会のど真ん中にこんな寂しい通りがあるのかと思うぐらい
人影もなく、車もほとんど通らない薄暗く広い道であった。道
の両側は電気の消えた高層ビルが旅人を威嚇する荒野の絶壁の
ように黒々とそびえたち、所々にある水銀等が青白く道路を照
らしていて、まるで廃墟のように静まり返っている。道路は下
り坂になっていて、遠くに繁華街の灯りが見えるが、前方は暗
く、その先がどうなっているのか判らない。不安を抱かせる洞
窟のようである。都会の裏側のような風景のなかでマサオは固
いアスファルトの道をとぼとぼと歩いた。汗ばんだ指と手には
無意識のうちに力が入り、何かをつかもうとするかのように折
れ曲がり硬直している。マサオは風がないことに気づいた。つ
かれきった足を引きづりながら歩く植えた狼のようにマサオは
ただ訳もなく叫びたい衝動に駆られた。埃にまみれた額や首筋
に汗が粘りつく。マサオは頭からは思考力も判断力も失われ、
ただ不安と憎悪に満たさ暑さと不快感で消耗した重い肉体を引
きずるようにして歩き続けた。マサオは完全に無力感に打ちひ
しがれていた。
マサオがようやく駅を探し当てたのはそれから一時間後だっ
た。
電車のなかでマサオはだらしなく足を投げ足して座り、眠っ
た振りをした。
沈みこんだ気持ちのままマサオはアパートに帰ってきたが、
部屋に入って独りになるとほっとしたのか、少し平静さを取り
戻した。マサオは以前から外での自分の状態を部屋の中まで持
ち込むまいと考えていたので、《今日外で起こったことは忘れ
よう、何も考えまい》として眠ることにした。しかし眼を閉じ
て眠ろうとすると、マサオの思いに反して、今日起こった出来
事が次から次へと頭に浮かんできた。マサオは眠りながら再び
追い詰められたような精神状態になって行った。そしてふと《
俺はやっぱりダメなのかなあ》という思いが脳裏をかすめた。
いやな瞬間であった。今までマサオはそんな思いを無意識的に
打ち消そうとしてきたきらいがあった。だがいまやその思いは
脳裏に強烈に刻み込まれたらしい。そして次から次へとさまざ
まな思いが脅迫的に浮かんできた。マサオはだんだん身動きの
取れない精神状態になって行った。マサオは思い込まされた。
《他の人たちは屈託なく精力的に生きているようだ。俺はみん
なのようには生きていけない。俺はみんなとどこが違っている
ような気がする。皆より劣っているのだろうか? 俺はみんな
についていけない。俺はやっぱり敗北者なのだろうか?》
抹殺したい瞬間であった。マサオにとってそれだけは認めた
くない言葉であった。今までどうもうまく行かないと多少予感
してはいたが、その言葉が自分自身の内部から心の現実として
生じてきたことはマサオにとってショックであった。マサオは
そんな思いをなんとか振り払おうとしたがムダであった。追い
詰められた精神状態において、それらを振り払うほどの気持ち
の余裕はなかった。そして振り払おうと思えば思うほど、その
言葉は強迫観念のようにますます深くマサオの内部に入り込ん
だ。
真夏の都市は暑さをもてあましていた。
日中、強い陽射しを受け続けたコンクリートの壁やアスファ
ルトの道路は、夜になっても暖かく、空気中にその余熱を放射
し続ける。それに各家庭に普及した冷房によって吐き出される
暖められた空気のため、外気はいっそう夜になっても醒めない
。その結果、蒸し暑い夜が続き、はるか上空以外逃げ場のない
熱は翌日に持ち越されることになる。
冷房のない部屋にとっては、同じように日中暖められた室内
の壁や天井が、夜になってもぬくもりを残し、その余熱を室内
に放射し続ける。窓を開けてはいるが、外気が暖かいため、そ
の効果はあまりない。それでもいくらか夜明け前には室温が下
がるときもあるが、それもつかのま、陽が昇るとともに室温も
上昇し、熱い暑い一日の始まりとなるのである。
土曜の休日。マサオは寝苦しい一夜から目覚めた。昨晩から
開けっ放しの窓からは、もう夏の強い陽射しが差し込んでいる
。窓の外の空気は靄が掛かったように白っぽい。
せっかくの休みであるのに、マサオにとっては何もすること
がなかった。かといってどんどん熱くなる部屋で寝ているわけ
には行かなかった。仕方なくマサオは起きると、水道の水を出
しっぱなしにして、冷たい水で顔や手を洗った。十分すぎるく
らいの開放感を味わいながらマサオは、流しの小窓を開けると
、大家のタカが洗濯をしているのが見えた。
マサオは再び寝床に横になりタバコをゆっくりと吸った。
陽は窓の正面から差し込むようになった。暑い午後の始まり
である。起き上がってマサオはカーテンを閉めた。じっとして
いても汗ばむようになった。風はカーテンをほんのかすかに揺
らす程度であった。汗ばんだ手や顔を洗おうとしてマサオは水
道の水を出したが、水はもう生ぬるくなっていた。小窓からタ
カが玄関に水を巻いているのが見えた。マサオにはそれがとて
も涼しげに見えた。そして風も通らない部屋に居るよりは外に
出たほうが良いと思い、身支度をした。
階段を降りると、タカが玄関から出てきた。そしてマサオを
見かけると「暑いねえ」と独り言のように言って,手持ち無沙
汰そうに再び玄関のなかへ入っていった。水をまいてあるせい
か、部屋の中よりは幾分涼しかった。それに風があるように感
じられた。マサオは散歩することにした。
マサオの足は自然と先日みた小さな森のあるほうへと向かっ
ていた。
歩いているうちにマサオは、路地の両側のほとんどの家の窓
は、この暑さの中でも、窓を閉め切っているのに気がついた。
休日であるのに子供たちの遊ぶ姿もなく、その声さえ聞こえな
い。
マサオの眼に小さな森の全景が入ってきた。高いところは風
があるらしく、上方の葉がかすかに揺らいでいた。歩き名がマ
サオは柵越しに半ば首を延ばすようにして、その小さな粗末な
小屋のある場所を除いた。だが見えなかった。マサオはもっと
近寄り柵に寄りかかるようにして見た。だが、やっぱり先日見
た小屋はなかった。ただ四方八方にダンボールや板切れや石が
散らばっていた。それは風や何かで壊れたという風ではなかっ
た。それは明らかに人為的に破壊されたように散らばっていた
の容赦ない陽射しのもと窓を締め切った家々は物音ひとつなく
静まり返っている。歩きながらマサオは《どうもいまくいかな
い》という言葉を思い浮かべた。
町に出て当てもなくぶらぶらしたり、涼を求めて喫茶店やパ
チンコ屋に入ったりして、マサオがアパートに帰ってきたのは
夕方近くであった。
階段を昇りかけると、翔子が同棲中の男と部屋から出てきた
。マサオは見ない振りをして階段を上がった。
部屋は温室のように暑くなっていた。マサオはドアを開けっ
放しにして、お湯のように暑くなった水道の水を冷たくなるま
で出しっぱなしにした。そして窓のカーテンを開けた。窓から
壁の陰に居る翔子が見える。どうやら先に出て隠れているらし
い。そして「わっ」といって飛び出すと、後から来た男を驚か
した。 翔子は子供のようにかくれんぼを楽しんでいるよう
だった。マサオは意識的に男を見るのを避けた。そして翔子た
ちの無邪気な話し声を聞きながら、やや冷たくなって水で汗ば
んだ手や顔を洗った。
マサオは下着一枚で横になり、涼しくなるのを待った。窓の
外の風景は夕日色に染まり始めていた。夕方になると毎日のよ
うに泣き出す子供の鳴き声が聞こえてきた。
翌日の日曜日も朝から晴れ渡っていた。
休みの日は眠れるだけ眠ろうと考えていたマサオにとっても
、さすがに温室のように上昇する部屋の暑さには耐え切れず、
仕方なく起きることに下。時計は十一時を回っていた。マサオ
はさっそく冷たい水で顔を洗おうとしたが、水はもう温くなっ
ていた。マサオは水を出しっぱなしにしたまま、窓に腰をかけ
、《今日も暑く長い一日になりそうだ》と思いながらタバコを
吸った。
外のまぶしい光がマサオの眼に慣れたころ、マサオは流し
に戻りやや冷たくなった水で顔を洗った。
そのとき階段を駆け足で昇ってくる足音が聞こえた。若々し
くリズミカルに弾んだ足音である。そしてマサオの部屋の前に
来て止まると、うわずった声で叫んだ。
「高橋さん、たいへんよ、みずがもれてる!」
少し開けられた窓から翔子の紅潮した顔が見えた。
マサオは下着姿なのでドアを少し開けてみると、マサオの穴
の開いた流しの排水パイプから水が溢れ出しており、通路が水
浸しになっていた。マサオはあわてて蛇口を閉め《まずいこと
になったなあ》と思いながら、急いで身支度をした。そのあい
だ、翔子の騒々しい叫び声を聞きつけて出てきた大家の源三の
「なに! 水が漏れている?」という興奮した声が聞こえてき
た。マサオには翔子のあわてぶりがはしゃぎすぎのようにも感
じられた。
マサオが降りていくと、源三は笑みを浮かべて「水が漏れて
いるのか、そうか古くなったからなあ」と独り言のように言い
ながら、排水パイプ見上げていた。二階の通路から溢れた水で
、階下の部屋のドア前が水びたしになっていた。
二階の三つの部屋の流しから伸びた排水パイプは、二階の通
路の下に設けられた一本のパイプにつながれ、それがアパート
の過度の柱に沿って垂直に地中の下水溝へと延びていた。水漏
れは以前マサオの流しが詰まった時に開けられた穴からであっ
たが、そうすると実際に詰まっている箇所は、マサオの流しの
前の所から、地中の下水溝の間のどこかであるらしい。タカが
出てきて
「みんな、大きいごみまで流すからだよ」
と愚痴っぽく言った。いったん自分の部屋に帰っていた翔子も
、ふたたび手に箒を持ったまま出てきて、水びたしになった二
階の通路を見上げていた。
このアパートのすべての部屋には人が入っている。だが、日
曜日となるとみんな出かけていていないらしい。だから水漏れ
に驚いて野次馬のように集まってくるのも、あまり外出を好ま
ないマサオや、仕事を持たずいつも部屋に居る翔子や、暇をも
てあましている大家夫妻だけとなる。彼らにとって、たかが水
が漏れたということであるが、暑い夏の日には不思議と興奮を
呼ぶひとつの事件なのである。源三は年甲斐もなく俺に任せろ
といわんばかりに張り切った。そして源三は、どうやら源三は
通路の下のパイプが詰まっているらしいと判断すると、はしご
を持ってきて立てかけた。そして勢いよく登った。はしごが少
しぐらついた。「アブナイ」といってタカが近寄りはしごを抑
えた。マサオはなんとなく大丈夫だと思いながらぼんやりと見
ていた。
源三は二階の通路の下に設けられた排水パイプの先端のふた
を回そうとした。それはねじ式になってあり回せばふたが取れ
るようになっていた。源三は力を込めて回そうとしたがまわら
なかった。そのときはしごがぐらついた。源三はちゃんと抑え
ているようにとタカを怒鳴った。二度三度と試みたが回らなか
った。源三は硬くてだめだと言いながら降りてくると、今度は
ドライバーとハンマーを持って昇り、そのふたを打ち砕こうと
した。タカは若者のように気負う源三を見て心配そうに気をつ
けてよと声から掛けたが、源三は余計なことだといわんばかり
に乱暴にハンマーをたたきつけた。マサオもやや責任を感じて
いたせいか心配そうに見守った。ふたが勢いよく打ち砕かれる
と、なかに詰まっていた水がどっとながれ出た。下で見上げて
いたマサオとタカが驚いて逃げた。源三は「やった、やった」
と満面に笑みを浮かべて勝ち誇ったかのように喜んだ。
だがそれは解決にはならなかった。
詰まっているのは、そこから地中までの間のどこかであると
いうことが判っただけだった。それでマサオは自分だけの責任
ではないということが判って少しほっとした。
今度は源三は太い針金を持ってきて、地中まで伸びたパイプ
の上からそれを差し入れようとした。詰まっている箇所をそれ
で押し流そうとしたのだ。だがなかなか入らなかった。「水道
屋さんに頼んだら」とタカが言うと、源三は「うるさい、文句
を言わずに抑えてろ」と荒々しく言い返した。しばらくすると
針金が入り始めた。源三は「入った、入った」と呟きながら、
押したり引いたりしている。マサオは暑さを感じながら不安な
気持ちで見守っていた。そこへ掃除の終えた翔子が出てきて言
った。
「こっちのほうで音がしているよ」
こっちのほうとは二階の通路下のパイプのことである。つまり
針金は最初から目当てとするところに入っていなかったのであ
る。源三は薄笑いを浮かべながら「やっぱりダメなのかな」と
初めて弱音を吐いた。マサオは立ってみているだで疲れてきた
。暑さも答えてきたので《やっぱり業者に頼んだほうがいいの
ではないか》と思いながら半ばあきらめの気分になってきた。
そのとき翔子がマサオの前横に立って、はしごを抑えているタ
カにたずねるように言った。
「やっぱりダメなの?」
マサオは流すように翔子に眼を向けたあと、再び悪戦苦闘する
源三の目を向けた。
翔子は薄いピンクのティーシャツを着ていた。マサオは一瞬で
、翔子は何も身につけていない素肌にただ蔽うように無造作に
そのティーシャツを身につけていることが判った。
マサオは何のためにその場に居るのかも忘れ、何も身につけ
ていない翔子の若くてしなやかな肉体を思い浮かべた。
源三はなかなか諦めなかった。
それまで傍観者のように見ていたマサオであったが、ある思
い付きが浮かんできた。マサオは「いっそのことパイプを切っ
て調べてみたらどうか」と源三に提案した。マサオの案はすぐ
に受け入れられた。
源三は照れ笑いを浮かべ「頭がいいなあ」と冗談ぽく言いな
がらはしごを降りてきた。タカも暑さに参ったようで「そのほ
うが良い」と言いながら日陰に身を寄せた。そして「大きいご
みさえ流さなければね」と翔子に訴えるように話しかけた。
源三がノコギリを持ってきて地表面近くでパイプを切り始め
た。マサオもパイプを抑えて参加した。そのうちマサオはなぜ
か楽しいもののように思われてきた。
案の定切れ目から水が吹き出すように流れ出てきた。これで
詰まっているのは地中であることが判った。
源三はパイプの切り口から先ほどの針金を差し入れ、押した
り引いたりし始めた。だがいっこうに針金が突き抜ける気配は
なかった。源三は深くしわが刻まれたほほを緩ませながら「こ
りゃあ、凄いなあ」と弱気に呟いた。
「よし掘ろう」と突然それまでの作業やめて源三がいった。こ
れから地中のパイプを掘り起こさなければならない。
源三がスコップを持ってきた。マサオはもう作業の一員にな
っていた。マサオは源三からスコップを受け取ると照りつける
夏の日差しの下で穴を掘り始めた。
タカはいつ終わるか判らない作業を見かねてか「暑い、暑い
」と言いながら部屋に帰っていってしまった。
地表面は砂と小石が硬くなっており思うようにはかどらなか
った。手を休めてみていた源三が笑みを浮かべながらマサオに
近寄ると「だいじょうぶかな」と言った。その言葉を聞いてマ
サオは「軽い、軽い」と子供のように気負い力を込めて掘り続
けた。翔子は二人の様子を黙って立ってみていた。ようやく硬
い地表面は終わり、あとは柔らかい土だけである。マサオは源
三と交代した。マサオは額ににじんだ汗を気持ちよく感じなが
ら源三の様子を見ていた。
ようやく源三がパイプを掘り当てた。翔子は珍しそうにマサ
オの傍まで寄ってきて掘り当てられたパイプを覗いたが、マサ
オはなぜか意識的に無視した。そして源三にほうに注意を向け
たが、少し動揺しているが判った。
だがパイプは容易に引き抜くことはできそうになかった。パ
イプの先がコンクリートの地下へと延びていたからである。マ
サオと源三が申し合わせたかのように眼を合わせては苦笑いを
した。しかし二人ともここまでやってきていまさら諦めるわけ
には行かなかった。マサオは地面にひざを突き手に持ったドラ
イバーで土をかき出し始めた。子供のときの砂遊びのような心
地よさを感じだ。源三が心配げに溝の中を覗いた。マサオは手
足が真っ黒になりか柄もこれは若者の仕事だと言わんばかりに
力強くかき出し続けた。陽射しをまともに受けているため、マ
サオの顔や体からは汗が吹き出てきた。湿った土の香りがマサ
オの鼻先に匂った。
マサオと源三の共同作業が続いていた。いつのまにか翔子が
マサオの斜め前で子供のようにしゃがみこみミニスカートから
細い両足のほとんどをあらわにして見ていた。サンダルのかか
とが高いため少し危なげな姿勢である。強い陽射しを受けて素
肌が透き通るようにつややかである。マサオは動揺した。でも
無表情を装い、源三と意味のない会話を交わした。地面からの
照り返しが暑くまぶしかった。マサオは不法侵入者のような翔
子の無邪気な姿に耐えながらもくもくと掘り続けた。《なぜこ
うも無頓着なのだろう、何気ない行為がどんなに動揺を与える
のか翔子は知らないのだろうか?》とマサオは思った。そのう
ちにだんだんと動揺が苦痛に変りつつあった。
十九歳の翔子は、マサオの斜め下の部屋で同じ年ぐらいの男
と同棲していた。夜になると屈託のない笑い声やあどけない会
話が隣家の壁に反射してよく聞こえてきた。翔子の体にはまだ
熟しきらない少女の面影が残っていた。そして自分が女である
ことを自覚していないような無邪気な言動や、投げやりとも思
えるような生活にマサオは日頃から気になっていた。そして深
夜になるとマサオはたびたび、翔子のそのリズミカルな原始の
声に悩まされていた。マサオは必要以上に翔子の存在にこだわ
っていた。だからマサオは必要以上に翔子を無視せざるを得な
かったのだ。
苦痛と暑さでマサオの額から吹き出た汗が頬を伝いだらだら
と流れた。翔子がよろけそうになりながら手に持っていたハン
カチでマサオの額の汗をふき取ろうとした。そのときマサオは
憤りにも似た興奮に苦しめられた。《なんと余計なことを、こ
れ以上苦しめないで欲しい》とマサオは思った。無警戒な心に
進入してきて自分の心をかき乱す翔子の姿や行為にマサオは腹
だたしさを覚えたのだ。だがマサオは、そんな心の変化を隠す
ために、少し驚いたようにただ曖昧な笑みを浮かべて、作業に
夢中になっている振りをするだけであった。
マサオは暑さと狂おしい気持ちを感じながらもくもくと土を
かき出し続けた。そして翔子の存在を無視することに全精力を
注いだ。
ようやく地中のパイプを引き抜くことができた。マサオは汗
と泥まみれの姿で源三と顔を見合わせた。そのとき翔子の姿は
そこにはなかった。
作業のすべてが済んだのは二時過ぎであった。マサオは汗と
泥を洗い落とすと、暑さも忘れるほどすがすがしい気分になっ
た。マサオはねぎらいの言葉とともにタカからに差し出された
ジュースを飲みながら、風が起こってきた路地にぼんやりと眼
を向けた。そのとき、翔子が手持ち無沙汰そうに自分の部屋か
ら出てきたが、ドアを勢いよく閉めて再び中へ入ってしまった
。マサオは再び路地に眼を向けながらゆっくりとジュースを飲
んだ。
暑い日が続いていた。
ある日の午後、西の空に沸き起こった雷雲が、暑さにうだる
都会の上空をみるみる蔽いつくした。そして四時過ぎ、雷を伴
った激しいにわか雨を降らした。大粒の雨は空中に浮遊するチ
リや、街路樹の葉のほこりを洗い流した。
夕刻、マサオは退社時間になるといつもより早めに外に出た
。はるか南の空は透き通るような青みを残していたが、上空に
は一時間ほど前に強い俄か雨をもたらした雷雲がまだ黒ぐろと
覆い、あわただしくうごめいていた。そしてその黒雲ははるか
西の空まで続いていたが、地平近くは薄くなったその黒雲の切
れ目から、オレンジ色の夕日が射し込んでいた。
マサオは今にも降りだしそうな上空の雷雲を見上げると、急
いで歩き出した。湿りを含んだ舗道の所々に水溜りができてい
た。街路樹の葉が風に揺れるたびに雫を落とした。
マサオはいつもより涼しさを感じながら歩いていると、前方
に会社の同僚たちと歩いている知子の姿を見つけた。まもなく
知子は同僚たちと別れひとりで歩き出した。マサオはさらに足
早に歩いた。
「雨が降ってきそうだね」
マサオはそう声をかけながら知子に追いつくと横に並んで歩き
始めた。知子は一瞬驚きの表情を見せたが、マサオだと判っ
てほっとしたのか、すぐに表情が和らいだ。マサオも安心して
言葉を続けた。
「今日は知らん振りをしないからね」
それを聞いて知子は少し不思議そうな顔をしたが、すぐにそ
の意味が判ったらしく、やさしい笑みを浮かべながら答えるよ
うに言った。
「やっぱり雨が降ると少し涼しくなるわね」
「?!?」
「ほんと、また降ってきそうだね」
と知子は空を見上げながら言った。
「またって? いつ降ったの?」
「あら、知らなかったの? 四時ごろ、凄い土砂降りだったの
よ」
と知子は子供っぽく言った。
「窓のブラインド閉めていたから判らなかったけど、そんなに
凄かったの?」
「それに雷が凄いの! 怖かったわ」
「雷も?」
「怖くないの?」
「ひとりで居るときは落ち着かないけど、みんなといるときは
平気だよ」
「私はダメだわ」
マサオの頭は疲れてボォッとしてはいたが、窓の外の稲光やそ
れを見て怯えている知子の姿を自然と思い浮かべることができ
た。そして黒い雷雲を引き裂くように走る閃光を見逃したこと
を惜しい気がした。
「今降って来たらこまるわ。傘は持ってないし、どうしよう、
早く帰らないと、、、、」
「大丈夫だよ。どっかに雨宿りすればいいさ。それとも早く帰
りたいわけでもあるの?」
マサオがそういいながら知子を見ると、知子は曖昧な笑みを
浮かべてマサオを見返した。
マサオはちぐはぐな会話が気になっていた。どうして斉木の
ように冗談などを言い合って開放的に進められないのだろうか
と思った。
マサオはなんとか会話を続けたかった。マサオは斉木の口調
を思い浮かべながら冗談ぽく言った。
「このあいだ、デートだったんだってね」
「このあいだ? ああ、あの日、違うわ、学校に行ったの」
マサオは怪訝な顔をして知子を見ながら言った。
「学校って?」
「洋裁学校」
そう言いながら知子は視線をそらした。マサオは黙って前を向
いた。
知子はマサオの顔をのぞきこむようにして言った。
「アッ、笑った。いま笑ったでしょう」
「いや!」
「うそ! いい年をしてとかなんて思っているんでしょう!」
マサオは真剣な表情で答えた。
「イヤ、そんなことはないよ。感心しているんだよ。年なんて
関係ないよ」
マサオがそういい終わると踏み切りに差し掛かった。マサオは
人や来るの流れにのって渡り始めたが、知子は少し歩きづらそ
うにしてマサオの後からついてきた。マサオが渡り終えて黙っ
て歩いていると、知子が追いついてきて、マサオの顔をのぞき
こむようにしてみた。マサオは笑みを浮かべ知子のほうを見な
がら言った。
「いつ頃からやっているの?」
「半年前から」
「そう、どうして、もっと若いときから行かなかったの?」
「うーん、判らない。それほど興味がわかなかったからかな?
でも、最近、このまま何もやらないでいるのがもったいない
ような気がして、それに、、、、」
「毎日なの?」
「月曜、木曜の週二回」
交差点で二人は立ち止まった。排気ガスの白さが目立った。
マサオは水滴を残す街路樹の葉を見ながら雷雨の様子を思った
。信号が青に変った。歩きながら知子がいたずらっぽい笑みを
浮かべてマサオに話しかけた。
「自分こそいつもより早く帰ってデートなんでしょう」
「そんな、相手がいないよ」
「うそ!」
「ほんとだよ。アッ、そうだ、誰か良い人が居たら今度紹介し
てよ」
マサオが言い終わると、ポツリポツリと雨が降り出してきた。
二人は今までよりも急いで歩き出した。駅に近くなったころ、
後ろの方で車のクラクションがなった。すると知子が急にバス
で帰るからと言って、マサオから離れて歩き出した。そのとき
ちょうど雨が激しくなってきた。マサオは知子の姿も見ずに、
そのまま急いで駅に駆け込んだ。構内に入ったマサオは、ほっ
としたような表情をしながら何気なく振り返ったが、どこにも
ほど表情を変えることなく振り返り構内を歩き始めた。
激しく降り出した雨のなか、知子は迎えに来てくれた恋人の
良夫の車のドアを急いで開けた。そして「わあっ」無邪気な声
を上げながらあわてて乗り込むと、良夫の「早く閉めて」と言
う声を聞きながら、ぎこちなくドアを閉めた。そして雨にぬれ
た髪の毛を両手でなでるようにして整えた。
狭い車のなかが親密感に溢れた。そして窓の外の様子が悪意
を持ったようなよそよそしい風景に変っていった。大粒の雨が
突き刺さるように車のボンネットやフロントガラスに降り注い
でいる。知子は満面に笑みを浮かべて「迎えに来てくれたの?
」と息を弾ませながら良夫に言ったあと、自分のスカートの乱
れを手でたたくようにして直した。そしてほっとしたように軽
くため息をつきながら、ゆっくりとシートにもたれかかった。
良夫は少しも表情を変えずに乱暴に車を走らせた。そしてスピ
ードを上げながらカーブを切ると、雨にたたきつけるようにし
て走らせた。広い通りに出ても良夫の表情は硬いままだった。
「さっきの男、誰?」
「あの人、会社の人」
と知子は笑みを浮かべたまま言った。良夫が鋭い視線を前方
に向けながら続けた。
「にやけた男だ」
「そう、ちょっとね」
と知子は良夫に同調するかのように笑みを浮かべたまま答え
たが、言い終わったあと、何か別の思いが頭に浮かんできて、
なんとなく言い足りない気がした。だが、車内の親密な雰囲気
のなかではそれもすぐ消えてしまった。
マサオが乗った電車が走り出した。雨は電車にたたきつける
ように降り注いだ。マサオはドアにもたれかかり、ぼんやりと
窓の外の風景に眼をやった。眼の前の窓ガラスを雨水が勢いよ
く流れている。その流れに注意を向けていると気持ちが落ち着
いて行くのを感じた。そして疲労でボォッとしていた頭がだん
だん回復していくような気がした。
マサオは窓から雲の状態を眺めた。西の空の明るさがだいぶ
広がってきたのが判った。電車が着くまでに止めば良いなと思
いながらただひたすら雨水の流れを見続けた。
知子は二年前、二十二歳のとき、女友達の紹介で良夫と知り
合った。それまでの知子は異性を意識しての個人的な付き合い
はまったくなかった。同僚の結婚話や噂話を耳にし足りしてう
らやましく思ったり、また、自分から興味半分にそういう話し
に加わって甘美な思いに浸ったりすることはあったが、自分の
身近なこととしては何も起こらなかった。それにそういうこと
はきわめて少数の人に起こるもの、自分には縁遠いことのよう
に思っていた。かといって、それで知子が自分の容姿に自信が
あるとかないとかということではなかった。知子はそういうこ
とに特別気を配ったり、生活の中心において考えたり行動した
りしないだけであった。
第二部に続く
* * * * * * * * * * * * * * * * * *