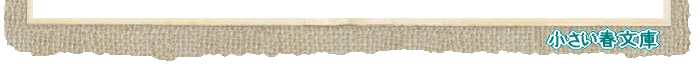はだい悠
* * * * * * * * * * * * * *
二十世紀半ば、東北地方のある村に、大家族のもとで、自由に伸び伸びと育てられ、真面目で勉強も良くでき、ひょっとしたら賢いんではないかと周囲から思われていた少年がいた。
—————————–
その少年が二歳の頃、遠くの空を飛んでいる飛行機をみながら、あの後ろが上がっているのは爆弾を積んでいる飛行機だと兄弟たちに脅かされ、そのたびに泣いていた。だから、その後、家の近くを通過するジェット機の爆音を聞くと、全力で走って家に逃げ帰るようになっていた。
そのころ少年は、父と母と兄と姉二人の六人で、二つの布団に入って夜は寝るようになっていた。
その春のある夜に兄弟四人は、以前地主だった家に田植えの手伝いに行った父と母が帰ってくるのを仲良く布団の中に入ってあれこれと話をしながら待っていた。玄関の戸があいたとき、四人は布団を抜け出しいっせいに玄関にむかって駆け出した。父と母が、休憩のときにもらったアメやお菓子を自分たちは食べないで子供たちの為に持ち帰ってくるからだった。
——————————
その少年が三歳の頃、突然のようにダンスを踊り始めた。自由に伸び伸びと自分の思い通りに。すると家族のものが皆面白がって少年の周りに集まってきた。少年は何がそんなに興味をひくのかわからなかった。でも自分のやっていることが自分には似合わないことのような気がした。だから、少年にとってダンスを自分の思い通りに踊ったのはこれが最初で最後だった。
この頃少年は、父と母が近所の人と挨拶するとき、お互いに
正座をし床に両手をつき、さらに頭が床につくまでに体を曲げて何やら呟きながら長々と挨拶をしているのを、傍らで不思議そうな顔をしてじっと見ていた。
その冬、少年は母と二人で寝るようになっていた。少年は長兄だけが湯たんぽを使っていることに気づいた。ある夜少年は母に無理を言った。長兄が使っている湯たんぽが欲しいと。母はごねる少年に抗し切れずに湯たんぽを持って来てくれた。でも湯たんぽはちっとも暖かくなかった。母の懐に抱かれて寝ていることがどんなに暖かいことか、少年はそのときまで気付いていなかったのだった。
その頃、近所の家の前を通りかかると、庭先で一人の青年が額に汗して薪を割っていた。立ち止まってその様子をじっと見ていると、その青年が少年に話しかけて来た。英語で一、ニ、三って知っているか、ワン、ツー、スリーって言うんだぞ、と。少年はそれを覚えた。
次の日、少年が再びそこを通ると、また青年が薪を割っていた。少年は昨日と同じ様にその様子をじっと見始めた。するとその青年が話しかけて来た。昨日教えたこと覚えているか、と。少年はとっさに答えた。
「うん、覚えているよ、ワン、ツー、スリーだよね。それからその次も言えるよ、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイと、ナイン、テンだよね。」
と。だが、その青年は、その後は何も話し掛けようとはせず、ただひたすら薪を割り続けるだけだった。
その頃のある日の夕方、少年は母に連れられ、とぼとぼ歩いて、五、六キロはなれた祖母の実家に泊まりに行った。その家には祖母の子供のいない姪夫婦が住んでいた。次の日の朝、家に帰るとき、次のように母に聞かれた。「もっと、こっちのうちに泊まっていくか?」と。そのとき、少年は即座にきっぱりと、「いやだ。」と答えた。普段は恥ずかしがり屋であまりはっきりとものを言わない少年が。
この頃、少年は姉や兄たちの後をついてまわり、近所の子供たちと夕方西の空が赤くなるまで遊ぶようになっていた。
さらにこの頃、少年の家にようやく電気がついた。その後少年は、そのとき家族みんなで歓声を上げたことや、それ以前のランプ生活のことは決した忘れることはなかった。
——————————
その少年が四歳の頃、母がなんでもない足の怪我を悪化させ、生命が危ぶまれるほどになり、三週間ほど遠く離れた町の病院に入院した。そして無事治って家に帰ってきて少年の顔を見たとき、喜びの笑顔ではなく悲しそうな顔をして涙ぐんだ。
その春、少年とその近所の遊び仲間たちは、近くの野山に遊びに行った。野イチゴを食べ、そして悪い遊びをした。家に帰ってくると、普段は訊ねたこともない母が「何をやってきたの。」と聞いた。少年は少し間をおいてから言った。「野イチゴを食べてきた。」と。
その秋の頃、少年は仏教徒になるための試験を受けることになった。ナンマイダと唱える何回かの訓練の後、その当日が来た。母親が作ってくれた一張羅の着物に身を包み、少年は薄暗い部屋でナンマイダと唱え続けた。前評判では行儀もよく真面目だったので何の問題もないだろうということだったが、しかし少年はなかなか合格しなかった。結局合格はしたが、順番としては最後のほうだった。そのことを少年の母は家に帰ってから家族に話した。それを聞いて誰かが言った。「大きな声で言わなかったんじゃないの。」と。少年は、なんだそうだったのかと悔しがった。作法に従い、真剣に心から唱えていれば良いとずっと思っていただけに。
この頃、少年の家に電気が付いた。
さらにこの頃、少年のおばの恋人が町から文化を運んできた。貧しかったにもかかわらず皆といっしょに弁等を持ってハイキングに行き、カメラを知り、自動車を知り、蓄音機を知り、バターを知り、ココアを知った。
——————————
その少年が五歳の頃、近所の家から五人の子供たちが遊びに来た。その五人の子供たちは、少年の家の五人の兄弟たちと年齢構成が似ていて、しか全員が女の子で、少年の姉たちの仲の良い友達だった。そして少年の家とその女の子たちの家はその地域で一二を争うくらい貧しかった。どのくらい貧しかったかというと、少年の家は、墓石にどこかの川原で拾って来たような石が置いてあるだけだったし、少女たちの家は、母を亡くし父は病気で働けないくらい貧しかった。
その少女たちは、午前に遊びに来て、昼近くになってもなかなか帰ろうとしなかった。
そこで自由にのびのびと育てられちょっと賢いんではないかと思われていた少年はその能力を発揮して考えた。そしてその理由がわかると少年は、すこし離れた場所ではあったが聞こえるような大きな声で言った。
「家で昼ごはんを食べたいから帰らないんだよ。」
その表情は少しも屈託がなく得意げであった。そして、それを見て母と姉たちは苦笑いをするだけだった。
その春、村にバスが来るようになった。少年の家の近くが折り返し地点となっていたので、バスガイドが時間あわせの為によく少年の家の近くの土手で遊んだりして休んでいることがあった。少年は、その紺の制服を着た若い女性の出来るだけ近くにいることをいつも願っていた。子供たちと歩いているとき、そのバスガイドは土手のふきのとうを摘み始めた。誰かが「バッキャ」(方言でふきのとうのこと)と言うと、そのバスガイドも「バッキャ」と言いながら摘み続けた。そして誰かが「バッ、キャッコ」と、バッとキャの間にちょっと間をおき、キャにッコを付け加えて言うと、彼女も「バッ、キャッコ」と、恥ずかしそうに悪戯っぽく言った。少年はそのバスガイドの傍らで全身がとろけそうな恍惚感をひそかに味わっていた。なぜなら、キャにッコがついた言葉が何を意味しており、そして若い女性が人前では絶対に言わない言葉であると云うことを薄々感づいていたからだった。
この頃、少年はひとつ年下の近所の男のこと何かにつけて対立し意地を張り合い激しく喧嘩するようになっていた。普段はとても仲が良く、その喧嘩も次の日には忘れてしまうようなものではあったが。
——————————
その少年が六歳の頃、六月のある日、それまで行っていた幼稚園に、突然行きたくないと言い出した。母は何も言わずにそれを認めてくれた。少年は言いたいこと言わなければならないことがいっぱいあっただけに開放されたような気持になった。そして再び自由で伸び伸びとした生活が戻った。
この頃、近所の子供たちが集まれば二十人くらいになり、その遊びは多種多様で時間も暇さえあれば朝から晩まで、隆盛を極めていた。
そのころ、少年とその兄弟は、わがままを言ったりして親の言うことを聞かなくなることがあった。そんなとき父親は言った。家に火をつけるぞと。すると子供たちはみんな大人しくなり言うことを聞く様になった。というのも、父親がそれを本当にやりかねないと思ったからだった。
さらにその頃、少年の家にラジオが入った。父が買ってきたそのラジオは中古だったので、なるかどうか心配で家族みんながその周りに集まった。でも無事なったのでみんなで喜んだ。
——————————
その少年が七歳のとき、小学校に入学した。少年にとっては何もかも不安で不安でたまらなかった。でもそのことは決して態度や表情にはあらわさなかった。幼稚園のときのことがあって、少しでも成長したところを見せたかったからなのだろうか。当日、泣きじゃくって母親から離れようとしない同級生を見たとき、少年はなんとなくほっとして、これからやっていけそうな勇気がわいてくるのを感じた。
その日家に帰った少年は、姉たちから同じクラスに可愛い子は居る、ときかれて、少年は判んないと答えた。姉たちが、XXちゃんが同じクラスなんだと言ったとき、少年は無関心を装った。
あるとき隣の席の男の子が、十円なくなったと先生に訴えた。その先生は少年のところに来て、筆箱を調べ、弁当は開けて調べた。少年はとても恥ずかしかった。食べかすが残っていて汚く見える中を見られたからであった。
少年は近所の同級生の女の子と一緒に帰るようになっていた。母親に仲良くするようにと言われていたからであった。ところがあるとき、もう一人の男の子が途中まで一緒に帰ることになった。少年はその男の子と組んで女の子をいじめた。次の日二人は担任の教師に呼ばれた。なぜいじめたのかと聞かれて、少年は、その男の子に命令されたからと、ちょっぴり泣き顔になって、半分嘘、半分本当の答えを言った。
さらにその頃、あるとき、その少女にとっては少し遠まわりであったが少年にとっては普段の帰り道を土手に坐ったり寝そべったりしながらゆっくりと道草を食いながら帰ってきた。ところがその二人の様子を見ていたものがいた。そしてその仲のよさを冷やかした。少年は母親の言い付けを守っただけなのにと思いながらも、その恥辱に耐え切れずにある決心をした。次の日、その道をいっしょに帰って来ないようにした。別れ道に来て少女が少年の後を付いて来ようとしたとき、少年が両手を広げてとうせんぼをし、こっちに来ちゃだめと言って。そして少女はそれまでどおりの道を帰っていった。少年にとって一生忘れ得ぬほどの寂しくも悲しげな不思議そうな表情を残して。
この頃、少年と近所の男の子との喧嘩は激しさを増していた。お互いに意地を張り通し決して妥協しなかった。だからきっかけはいつも些細なことで始まり、いつも惨めな結果で終わっていた。たとえばこんなふうに、その男の子が少年の家の田んぼの苗をひとつ抜くと、少年は男の子の家の田んぼの苗をひとつ抜いて報復する。するとそれを見て男の子はさらにもうひとつ抜く、少年も負けじとさらにもうひとつ抜く、すると男の子の方もさらにと言うふうに、そのことがしばらく続いたあと、最後は、お互いに自分の家の田んぼの苗を、悲しく寂しく惨めな気持で元に戻しては、罵りあいながらその日は別れるのであった。
さらにこの頃になると、男の子のグループと女の子のグループはだんだんいっしょに遊ばなくなっていった。男の子たちの遊びはだんだん過激になって行き、いじめも喧嘩も日常茶飯事になっていた。でも翌日にはすっかり忘れてしまうような内容だったので、遊びが途絶えることはなかった。
——————————
その少年が二年生の頃、ある男の子が喧嘩していたのを若い女の先生に咎められて、そこで泣きながらホウキを手に持って立ち向かっていったとき、その先生に後ろから抱きしめられるように抑えられてホウキを取り上げられたのを見て、少年はうらやましいと思った。
そのころ少年は、母から、猫が死ぬときは、人に見られないように山奥に入っていってひっそりと死ぬということを聞いた。それは確かめようがなかったが、そういえば、それまで何度か猫を飼っていたが、死骸を見たことは一度もないことに気づいた。
その冬、昼休み、少年は雪の積もった校庭で遊んでいた。すると突然一瞬意識が無くなるくらいの重い衝撃を頭に受けた。意識を取り戻すとともに少年はいったい何が起こったのだろうと思いながら周りを見渡した。すると十メートルほど離れたところで担任の男の先生がニタニタしながら少年のほうを見ていた。少年は何が起こったのか判った。それまで、その担任に先生が握った雪球を上空に高々と放り投げているのを見ていたから。大人の手のひらで握られた大きな雪球が、上空高くから落下してきて、少年の脳天に激突し、割れて砕け散ったのだった。
——————————
その少年が三年生の頃、近所の男の子との喧嘩は来るところまで来ていた。そして、ついに親たちの介入を招くことになった。少年は暴力では何も解決しないということ、そして、親たちの介入を招いたという敗北感と共に、暴力の悲しさむなしさ惨めさをひしひしと味わった。
その春、少年は自分で作った水中銃を持って田んぼに出かけ、次から次へとカエルをいたぶった。そして家に帰ってみると、従妹がやけどをしていた。家のものが少年に言った。「お前がそんなことをやっているからだ。」と。「そんなこと。どうしてじぶんのやっていることがわかったんだろう。」と少年は思った。そして「決して見えるような場所ではやっていたのではないのに。」と思った。
その頃、少年の書いた作文が話題になった。それはこの様な事を書けば大人たちはきっと喜ぶだろうなということが判って書いたものだった。だから本当に書きたいものが他にあるような気がしていた。
この頃、少年はクラスで何かにつけて注目されることに気付き始めていた。少年も出来るだけそれに応えるようにしていた。
さらにこの頃。少年の近所に小さな家に独りで暮らしている女性がいた。その家の裏の畑に一本のりんごの木があった。少年と仲間たちはそのりんごをぬ盗むことを計画した。そして秘密の任務を帯びた特殊部隊のように裏山に潜み様子をうかがった。まず年上の三人がスキを見てその木にすばやく駆け寄り、激しく揺さぶり、木になっているりんごをことごとく落として、急いで引き返すと、次に年下の少年たちがいっせいに走り寄っては、そのりんごをポケットというポケットに詰め込み、手にも持てるだけ持って、見つからないように裏山に逃げ込んだ。少年たちは勝利に歓喜し酔いしれた。そして戦利品であるりんごを食べたいだけ食べ、乱暴に食い散らかした。少年たちは、もうひとつのりんごも木にが残っていないのを確認しながらその場を去った。
この夏、少年は父親の自転車に乗せられて墓参りに行った。その帰り食堂に入りかき氷を食べた。父親はもう一杯食べるかと聞いた。物事を合理的に考えることを覚え始めていた少年は、このときあっさりとそれを断った。
この秋、少年は給食に出た牛乳を家に持ち帰った。遊びにきていた従妹と一緒に飲むためだった。だが、思わぬことが起こった。持っているところを従妹と家の者とに同時に見られてしまったのだ。少年はあれほど一緒に飲もうと思って持ち帰ってきたのに、その家の者の前ではなぜかその従妹に牛乳を分け与えることは出来なかった。そして家の者から激しく咎められた。「飲ませないのなら、家に持ってくるんじゃない。」と。
その頃の冬の終わりに、少年は次年度の新しい教科書を買ってもらった。それまでは少年の兄や姉たちは古いもので間に合わせていたのだったが、少年はずっと新しいものを買ってもらっていた。家に持ち帰ってそれを母親に見せると、母親はその真新しい良い匂いのする教科書を嬉しそうな顔をして手にとって見ていた。そのしわだらけの節くれだった両手で。
——————————
その少年が四年生の春、学校から帰ってくると家の前のあぜ道に坐って母の働く姿を見ていた。母は牛に鋤を引かせて田んぼを耕していた。少年は周りの広い広い田園風景を見渡した。でも女性が田んぼを耕している姿は他に見ることはできなかった。それどころかその後どこに行ってもそのような光景を目にすることはなかった。
さらにその春。近くの町でお祭りがあった。少年は近所の遊び仲間と八キロほど離れたその町に見に行った。コルク銃を打って、的となっている商品にそのコルクを当てたら、その商品をもらえるゲームが行われていた。少年はあまりお金を持っていなかったので、みんながやるのを見ているだけだったが、そのうちに、一緒に行った遊び仲間が、はじけ飛んできて外に落ちているコルクを拾って只でゲームをやっているのに気づいた。そこで少年もコルクを拾ってやろうとした。ところが二、三個拾ったとき、それを見ていた見知らぬ中学生ぐらいの男が、少年の手からその拾ったコルクを叩き落した。他の者は許されているのに、なぜ自分だけがと、少年は少し不満だった。
その初夏、少年は学校の帰り道、道路に沿って低空を飛んでくるツバメに向かって帽子を投げた。どうせすばやいツバメにはあたりっこないと思っていたから。ところが、帽子はツバメにあたった。ツバメは死んだように帽子の傍らに横たわった。でも数秒後にツバメは動き出し再び元気に飛んでいった。衝突のショックで気を失っただけのようだった。次の日、学校でそのことを友達に話しても誰も信じてくれなかった。
この頃少年は火薬を使った銃を作った。一回だけ試みた。成功した。でも二回目の火薬はなかったのでそれっきりだった。すでに少年はこの頃までに考えられるあらゆる武器を作って試していた。パチンコ、水中銃、弓矢、トタンを切り抜いた手裏剣、火薬をまとめた爆弾などなど。弓矢は実際にそれで狩に出かけた。でも的の大きい鴨は居なかった。爆弾の場合周囲を固めれば固めるほどその威力が増すと云うことをまだ知らなかった。だが、これらのことは親たちはいっさい知らなかった。
その頃、学校帰り、少年の友達が路上に止めてあった車のバックミラーを悪戯をして壊した。その友達は正直にそのことを車の持ち主に申し出た。だがその友達は激しく怒られ、弁償させられるはめになった。その友達がなく姿を見て、少年は何か悪いことをしてもこれからは絶対に言わないことを誓った。
さらにこの頃、少年は大勢や年上を敵にまわして喧嘩するようになっていた。もちろんいつもボコボコにされていた。
この秋、少年にとって、家族みんなで八キロほど離れた大きな町に日帰りで行くというのが最後となった。それはいつも、朝バスに乗って町まで行き、そして必要な買い物をし、食堂に入って昼ごはんを食べ、そのあと午後には買い忘れたものを買ったりしながら、名残惜しげに街中をぶらぶらしては、その八キロの帰り道を二時間ほどかけて歩いて帰って来るというものであった。それは、帰りはのんびりと風景を見ながら歩いて、と云うのは嘘で、バス代をもったいないと考えたからだった。
さらにこの秋、少年は、自分が飼っていたウサギを、日課の餌やりを面倒くさいということで忘れてしまい死なせてしまった。それまでに少年はいろんな生き物を殺していた。それを知れば大人たちが少年の将来を心配するような方法で。少年の母はウサギを死なせたことをなかなか許さなかった。少年はいやになり、近所の家に家出した。夜になると母親が迎えに来た。そのことはもう言わなくなっていた。でも、東の空の星の塊りが天の萎縮した傷跡のように見えた。
その冬、少年は学芸会の劇で、演出上どうしてもある女の子の体に触れなければならなくなった。でも少年は拒否した。特にその女の子がひときわ可愛いとずっと思っていた子だっただけに。でも、それが他人には想像出来ないほどの病的な羞恥心の始まりだった。
——————————
その少年が五年生の頃、学芸会の劇の主役に先生から指名されたとき、少年はそれをうじうじと断った。それも他人には想像が出来ないほどの病的な羞恥心の所為だった。
その頃、少年は母親に買っててもらった新しい学生服に腕を通したとき、それまで経験したことのないような感情におそわれた。それは楽しさや喜びではなく、その場に立っていられないほどの漠然とした不安に包まれた悲しみだった。その卸し立ての匂いに包まれていると。
さらにその頃、少年の父が、自転車の荷台に何かが入った箱を乗っけて帰ってきた。父と母がそれを見ながら真剣な表情で話していた。少年は近づいてみた。するとそれは、安かったということで町で買ってきたトマトだった。少年はもっと重要な話しかと思っていたので、なんか不思議な気持だった。
この頃、少年が版画の下絵に書いた絵が先生に褒められた。それは母親の働く姿を自然描写したものだった。だが、最終的に出来上がった版画を見て先生は手で顔を覆って落胆した、怒りの表情にも取れるような激しさで。少年はどうしてこんな結果になったのか判らなかった。でもちょっと真剣味が足りなかったのかなとも思った。
さらにこの頃、少年は人生で最後の激しい取っ組み合いの喧嘩をやった。
その秋、地区対抗の運動会があった。少年はリレーのスタートを勤めた。少年は学校でいつもトップをとっていたので、ここでもトップでバトンを渡せると思っていた。まだ一緒に走ったことはなかったが、自分よりは体が小さいものばかりだったので、これなら絶対に勝てると思ったからだ。少年は運動会のときのように緊張することはなく、安心してリラックスしていた。笑顔を見せたり他の者とふざけあったりもした。そして号砲がなった。だが結果はビリだった。
——————————
その少年が六年生の頃、図書係りとしてポスターを書かねばならなくなったとき、誰が書くかということになって、少年は字が下手だから断りたかった、でも学級委員でもあり、男のプライドもあり、女々しく断ることは出来なかった。そこで頼まれて仕方なく書くような振りをしてマジックを手にとって書き始めると、ある一人の女の子が、「うまい。」と言って手を叩いて褒めた。他の女の子もそれにうなずいた。少年はそうかなあと思いながらもなんとなく嬉しくなって、そのまま最後まで一人で書き終えた。後から何度見ても、少年にはそれがうまいとはどうしても思えなかったのだが。
この頃、少年の家にテレビが入った。少年は思った。いずれ方言でしゃべる人は居なくなるだろうと。
その頃、少年はある女の子とそれとはなく目が合った。少年は思わず手に持っていた画板で自分の頭を脳天から思いっきり叩いた。するとその女の子は驚いたように少年を見つめた。そこで少年は再び、今度は前よりも強く激しく叩いた。すると女の子はさらに目を丸くして少年を見続けた。少年はもうどうしてよいか判らなくなってしまった。その女の子が今までずっと可愛いと、いや、入学以来ずっとずっと学校で誰よりも可愛いと思っていた女の子だっただけに。
さらにその頃、宮沢賢治の雨にも負けずを呼んで、作者がこの詩で言いたかったことは何かと先生に聞かれて、少年は、雨にも負けない風にも負けないような丈夫な体を持つことがどんなに大切かということですと応えた。すると先生はこれはたとえで言っているのよと苦笑いをした。少年は雨の日でも風の日でも農作業に励む父と母の姿をいつも見ていたから、本当にそうだと思ったのだったが。
その初夏、子牛が売られていった。母親牛は突然居なくなった我が子を求めて鳴いていた。夕方になっても鳴いていた。夜になっても鳴いていた。夜中になっても鳴き止まなかった。次の日の朝になっても鳴いていた。でも少年が学校から帰ってきたときにはもう鳴かなくなっていた。
この夏、少年は近所の遊び仲間といっしょに、自転車で一時間ほどの大きな川に弁等を持って遊びに言った。午後になって家に帰ってくると、母親が少年を激しく怒った。親に黙って遊びに行くなんてと。ふだんは、昼ごはんを食べずにどこかに遊びに行っても決して怒らないのに、と少年は思った。それにしてもどうして母親が少年が川に遊びに行ったのを知っているだろうと不思議だった。
この頃、少年は秋の文化祭のための水彩画を描いた。秋の風景を絵の具を水に溶かさず描いた。するとそれが先生たちを驚かせ評判になった。思いつきで適当に塗りたくっただけなのに。でもそれが油絵の技法を真似たものだと判ると誰も話題にしなくなった。
さらにこの頃、少年の家の周りを、やせこけてあばら骨の見える一匹の野良犬がうろつくようになった。少年はそのイヌを目にするたびに激しく追い払った。というのも、その薄汚れた肌にへばりついたかのように見える茶色い毛と、そのあまりの不格好さが、少年の目にはどうしてもイヌの様には見えず、不幸をもたらす疫病神の化身の様にも見えたからであった。
その秋、少年が学校の校庭にカバンを置きっぱなしにして遊んでいるとき、大きなトラックが入ってきてタイヤで少年のカバンを踏み潰した。カバンの中を開けてみると弁当箱が薄いせんべいのようにつぶれていた。それを見て少年は、なんだこれくらいのことでと思いながらも子供のように泣きじゃくりとめどなく涙を流し続けた。周囲に友達がいっぱい見ていたにもかかわらず。その弁当箱は幼稚園に入るときに母親に買ってもらった青い角の丸い弁当箱だったのだが。
さらにその秋、少年は家の前で近所のひとつ年下の友達と遊んでいた。そこから少し離れたところをその友達の叔父が、リヤカーを轢いて通りかかった。ちょうどそのとき何かの手違いで少年の家の薪が道路に置かれていた。その叔父は通行の邪魔をするその薪を傍らの小川に放り込んだ。その男は四十過ぎても独身で、子供の頃からの習慣をそのまま引きずっているような自分の感情に正直な男だった。仕事に忠実で、そして肉親には優しく他人には厳しくというように自分なりにどこまでも合理的に行動する男だった。だから意味もなく騒ぎ立てる子供は嫌いなようだった。とくによその子供は。少年は小さい頃から恐さを感じていたので出来るだけ避けるようにしていた。少年はその光景を、その友達の傍らで抗議の目で見ていた。やがて、少年と別れて家に帰ることになったその友達は、遠まわりをしてその現場に立ち寄り、小川に放り投げられていた薪を元に戻していから帰って行った。その友達は、かつて少年と盛んに意地を張り合い喧嘩をし、お互いの田んぼの稲を抜き合ったり、挙句の果てには親たちの干渉を招いたりしたことがあった者であった。
——————————–
十三歳の春、その少年は中学生になっていた。
その春、テストの総合点が発表されたとき、最高点は自分じゃないといって他の者たちに期待を持たせた。すぐバレルと判っていながら思わず嘘を行ってしまったのだった。
その頃、少年は、あの不格好な野良犬を頻繁に目にするようになった。少年の母親がときどき残飯を与えていたからだった。
最初は、少年もその家族も、その犬を見かけると、大声をあげたり物を投げつけるまねをすると、その犬はすばやく身を隠していたのだが、どうやらそのうち慣れてきて何も危害が及ぶことがないと判ったらしく、一応逃げるには逃げるのだが、ある程度はなれると、姿を見せたまま、そこで安心したように歩き出すようになっていた。だから、時折ではあったが、母親が残飯を与えるようになったからには、犬もますます安心して家の周りで頻繁に目に付くようになったのは当然のことだった。
やがて犬は、庭先や玄関の前をうろつくようになり、稀にではあったが玄関の中に入ってくるようになった。少年はそれを苦々しく思った。どうしてもすきにはなれなかったし野良犬の分際でずうずうしいと思ったからだった。それでそのたびに、少年は大声を上げて追い払った。でも逃げるのはいつも庭先までだった。そこであるとき、少年は玄関を出て追い払い、さらに逃げる犬を走って追いかけた。犬は懸命に逃げた。でも少年が止まると、犬も止まった。そこで少年は再び追いかけると犬も逃げた。そして少年が止まると犬も止まった。そのとき、追いかけているときも止まっているときも、少年と犬の距離はほとんど一定だった。
少年は追い払うのをあきらめて戻ってくるが、犬は、しばらくはその遠く離れたところでうろうろしているが、気がついて姿が見えなくなったなと思っていると、いつのまにかに庭先で歩いている姿を見かけるというようなありさまだった。
あるとき、遠く離れた畑に、家族そうで手農作業に以降としたとき、その犬がついてきた。少し後ろからではあったが、その馴れ馴れしさに少年は腹正しさを覚えた。腹いせに少年はその犬に名前をつけることを思いついた。その醜さから、ポチでもブチでもない、ペチと。多少の侮りをこめて。その後少年の母は、ペチを呼びつけるときは、ペッ、ぺっと呼ぶようになった。
ペチは日増しに馴れ馴れしくなっていった。誰かが尋ねてくると、自分があたかもこの家の飼い犬かのようにほえるようになった。少年は、ペチがだんだん付け上がっていくような気がして、それが忌々しかった。
あるとき、ペチがこのまま家に居着くのではないかと不安になった少年は、母親に尋ねた。なぜ他にいっぱい家があるのに自分の家に、ペチが寄り付くようになったんだと。
母は言った。聞くところによると、他の家では、薪を投げつけられたりお湯をかけられたりしたそうだと。
そう聞いても少年はあまり納得ができなかった。やっぱり、なぜこの家なんだと。
少年はなにかものを食べているとペチが尻尾を振ってよってきた。少年は食べているものを投げて分け与えた。ペチはそれを食べようとするとき、顔は地面のほうを向けているが目は上目使いだった。少年はそれがなんとなく気に入らなかった。時には投げようとして手をあげただけで怯えたように逃げようともした。それもどうにも腹ただしかった。だからときどき物を投げる真似をして驚いて逃げるペチを追いかけたりもした。ほとんどが遊び半分で。追いかけては逃げ、止まると止まり、また追いかけては逃げ、また止まると止まるというように。そんなことがあっても、、しばらくして、少し距離をとった所にいるペチを呼ぶと、なにか食べ物を分けてもらえると思ったらしく、勢いよく走り寄ってくるのである。それを見て少年はほんとうにあきれるほかなかった。
そのうち、ペチは鎖でつながれるようになった。その醜さと訳のわからない性格で、どうしても好きになれなかった少年は、なぜ飼い犬でもないのに飼い犬のようにつなぐのかと母親にたずねた。母親は言った。ペチが近所の家に上がりこんで食べ物だけではなく、砂糖や味噌の袋を盗むからで。飼い犬ではないが飼い犬のように周りから見られているのでどうしようもないのだと。砂糖や味噌を盗んできてどうするのだと少年は母親に聞いた。すると母親は言った。裏山で土を彫って隠しているのを見たと。
それでもペチは一日中つながれているわけではなかった。あるとき、少年が学校から帰ってくると、家の奥に動く物の陰を感じた。少年が中に入るとその陰は勢いよく裏の開け放たれた引き戸から外に出て行った。少年はそれがペチだとわかった。そして裏切られたような気がして激しく腹を立てた。なぜならペチは家の中に人がいるときは、玄関には入ってきても絶対に部屋に上がる事など今までなかったからだ。少年はすぐにでも見つけて怒鳴りつけようと思った。ところがあきれたことに、ペチは勢いよく玄関に入ってきてはうれしそうに尻尾を振って、何かもらえるんではないかのような表情をして少年を見上げているだけだった。少年はもう何も言うことはできなかった。
だがそのことが二度、三度と続いたとき、少年はついにペチに制裁を加えることにした。少年はペチがつながれているときに、勝手に部屋にあがるんじゃないといいながら、手に持っていた竹の棒で地面をたたいた。するとペチは歯をむき出してうなり返した。威嚇には威嚇で応えるかのように。少年それが許せなく、さらに激しく地面をたたいた。ペチはうなり返した。少年はさらに続けた。でもペチは本能をかけて自分を守るかのように決してひるまなかった。その様子を見て母親が少年をたしなめた。少年は制裁を止めた。
そのことがあってもペチは以前と少しも変わらなかった。上目遣いはするし、人がいないとき無断で家に上がりこむこともやめなかった。
その秋、少年は文化祭で同級生や他校生の絵を見た。みんな比べ物にならないくらいうまかった。やれば自分には何でも出来ると思っていたにとってはショックだった。それ以来少年は本気で絵をかくことを止めた。
—————————–
十四歳の春、少年の人生にとって最も忌まわしい出来事が起こった。実力テストの結果が表となって少年の名前が一番右側で、廊下の壁に貼り出されたのであった。くそ真面目で自負心が強く、そして恥ずかしさを屈辱と感じる少年にとっては、そこからひとつでも左側に順番を移動することは自分にとって許されないことであった。そこで、その日から少年は時間を惜しんで勉強を始めた。大人たちが仕掛けた巧妙で安易な罠とも知らずに。
その夏休み前、少年が学校の校庭で友達と遊んでいると、犬が二匹迷い込んできた。よく見るとそのうちの一匹はあのペチだった。二匹は仲良く遊んでいるようだった。家から遠く二キロも離れているのに、よくこんなところまできたと少年は思った。少年は気づかない振りをした。なぜならペチが少年を見つけて、あの全身で喜びを表す動作、尻尾をふり、前足でリズミカルに地面をたたいて飛び上がり、うれしそうな表情で首を振る動作をしたら、周りから、このやせこけた醜い野良色のような犬と少年が知り合いと思われたら、どんなに恥ずかしい思いをするだろうかと少年は思ったからだった。そのとき一人の友達が少年に言った。
「あれ、あの犬、xx君の家の犬じゃない。」
少年はとっさに答えた。
「知らないよ。」
その友達はなおも続けた。
「そうかな、xx君の家の犬だよ。」
少年は表情を変えずに答えた。
「あんな犬、見たこともない。」
そういって少年は、ペチが自分のことを見つけてくれないことをただひたすら願った。
その頃、少年は大人たちの前で自分の意見をいうことをほとんどしなくなった。それは何も考えていないからでも、しゃべることが恥ずかしいからでもなく、ほんとうに自分の話したいことと、何を話せば大人たちが満足するかということとに、もはや調整が利かなくなっていたからであった。
この秋、少年は些細なことで母親と言い争いをした。母親は子供のように泣きじゃくった。少年は驚いた。その晩母親は居なくなった。父と二人だけのさびしい夕食となった。少年は母が居なくなった訳を父親に聞くことがどうしても出来なかった。でも、内心では自分が原因で母親が居なくなったのではないかと思っていた。もしかしたらこのまま永久に母親が帰ってこないんではないかとも思うと、不安で不安でたまらなかった。
翌日、学校から帰ってきても母親の姿は見えなかった。少年は父親の稲刈りを手伝った。こんな忙しいときに家をあけるなんて、やっぱり自分がひどいことを言ったから母親は家出をしたんだなと思うと、少年は不安がますます高まっていった。夕方、母親が帰ってきた。母親は仕事をしている少年に近づき、買ってきたりんごを手渡した。そのとき母親は喧嘩別れをしていた恋人のように恥ずかしそうに笑みを浮かべた。少年はやっぱり自分が原因だったのかと思った。でもたとえようもなくほっとした。
その秋の冷え込んだ夜、少年が寝ている布団にネコがもぐりこんできた。少年は夏からの名残りでまだパンツひとつで寝るくせがあった。それに寒い時期になるとネコといっしょに寝るのが習慣になっていた。ネコが入るとまもなく、少年の体の胸から脚にかけての肌に、かすかになでるように、それもずっと一定の強さで触れるものがあった。そしてその感覚は足元のところで終わった。ネコがそこに自分の寝る場所を確保したからであった。少年は、それはネコが少年の体と掛け布団の間のわずかな隙間を少年の足元のほうへ進んでいたのだということがわかった。そしてあのかすかな感触も、ネコが真っ暗闇の中を探り当てるようにして進むために使っていたひげが自分の肌に触れたものであるということも。
この冬、ペチが子供を生んだ。床下の掘りごたつの周りに、そこは暖かかったから。それから何日かして、少年が学校から帰ってくると子犬の泣き声は聞こえなくなっていた。ペチのクゥ、クゥと泣く声はしていたが。少年はすべてを察した。
—————————–
十五歳の春、少年はその地区の生徒たちの長に選ばれた。とにかく目立つことが嫌いな少年は本当は断りたかった。だが断ることは良くないこと男らしくないことと思っていたので仕方なく引き受けた。
その初夏、少年たちの地区で大人と若者たちの野球の試合がおこなわれた。その試合で少年はホームランを打った。家に帰ってきてそのことを父親に言った。でも父親は何の関心も示さなかった。そのとき少年は思った。それほど大したことではないなと。 それからしばらくして、父親が帰ってくるなり嬉しそうな顔をして少年に言った。「野球で、ホームラン打ったんだって。」と。少年は何をいまさらと思いながらも、父親というものは、子供が外で褒められることはうれしい事なんだなと云うことに気づいた。
この頃少年は、他のクラスの者が体育の授業でフォークダンスをやっているのを初めて見た。そのうち少年たちのクラスでもやることが知らされたとき、少年は絶対に学校を休むことを決意した。少年にとって恥ずかしさは人前で拷問を受けるような苦しさであり苦痛であったからだ。
さらにこの頃、少年の家に少年の家の牛が逃げているという電話がかかってきた。家には少年のほか誰も居なかった。外に出てみると、牛が牛小屋を抜け出して二百メートルほど離れた草地にいた。少年は非常に困惑した。今まで牛に触ったことがないだけでなく、その巨体と暴れたらきっと人を刺し貫くに違いない角をのこと思うと、恐怖に打ち勝って牛を連れ戻すことは自分には無理だと感じたからだった。少年は途方にくれて立ちすくんでいると、牛が自分から戻ってきた。牛が少年のほうに近づいてきたので、少年は勇気を振り絞り意を決した。そして、かつて母親が言った言葉「牛は時々人をなめるときがあるから、なめられないように強く出なければならない。」と云うことを頭に思い描きながら、牛に近づき、鼻輪をつかみ力を込めて、そして少し乱暴に牛を引き出した。その巨体や相貌に似合わず牛は思ったより従順だった、むしろ穏やかさや優しさを感じさせるくらいだった。そのことが鼻輪を通して少年の半ば硬直しかかった腕を通して伝わってきた。少年は穏やかな気持になりながら、乱暴に鼻輪をひいたことを後悔した。そして遠くはなれた草地のことを思った。
その秋、少年は、誰よりも早く学校に行って学級文庫を読むことを思いついた。初日いつもより三十分ほど早く行くとさっそく本を読み始めた。しばらくすると足音がし、戸が開き、一人の女の子が入ってきた。それは少年が小学校に入ったときからずっと可愛いと思っていた女の子であり、学芸会の劇で体に触れることに恥ずかしさを感じ、そのことを拒否したり、見つめられて思わず自分の脳天を画板で叩いたりしてしまった女の子でもあった。クラスはほとんど同じであったが、まだ直接的には一度も話したことがなかった。女の子はなんとなく落ちつかない様子だったが、少年は気づかない振りをして本を読み続けた。まもなくその女の子は教室からいなくなった。次の日も少年は早めに学校に言って本を読み始めた。まもなく足音がして女の子が入ってきた。昨日と同じ様に少年は気付かぬ振りをして本を読み続けていると、その女の子もなんとなく落ちつかない様子、まもなくどこかに居なくなってしまった。次の日、少年は早めに学校に行くことをやめた。少女がそれまでのように来ることも来ないことも恐れたからだった。
さらにこの秋、級友が、これが宇宙の形だといって、大きな黒板に楕円を描いたとき、少年はなんとなくそれは違うと思いながら眩暈を感じていた。
この頃、病的な羞恥心が災いしてか、少年は人前で話すことがとても苦手だった。そのことで先生と話し合った。先生は言った。それは慣れであると。でも、少年はどうしても自分の本当に思うことや感じることを捨てて、もうひとりの自分になることはできなかった。
その冬、少年は卒業文集に何も書かなかった。本当に自分の思っていることではなく、どのようなことを書けば卒業文集にふさわしいかが判っていたからであった。でも、本当に自分の思っていることを表現する術はまだ持っていなかった。
—————————–
十六歳の春。田舎の変わり映えのしない風景や、そのありきたりの生活に退屈さを覚え、自分の故郷をほかの所よりも、なにか劣った所貧しい所と感じるようになり、それに比べてこの世にはもっと良い事ばかりがあるに違いないと思い、と同時に大人たちが仕掛けた罠から逃れるために、少年は家を出た。
—————————–
その後少年は自由にのびのびと物を言えなくなり地獄の季節を駆け抜け青年になった。そしていつのまにか勉強もできなくなっていた。だからもう賢いとは言われなくなっていた。
—————————–
その少年が成年になったころ、ペチが死んだときの様子を母から聞いた。それによると、冬の寒い朝、全身が真っ白になって死んでいたと言うことだった。少年はその不思議さよりも、不思議そうに話す母のことが印象的だった。
—————————–
そして、三十七年後、病院で苦しみながらこの世を去っていった父と母の死と引き換えに、その大人になった少年は、出て行ったときと同様、何ももたずに、いや老眼鏡だけを手に、故郷に住むために帰ってきた。何者でもなく出て行き、何者でもなく帰ってきたその男を、故郷の兄弟も親戚も、風景も、その変わることのない豊かさと暖かさで迎え入れた。
—————————–
—————————–
—————————–