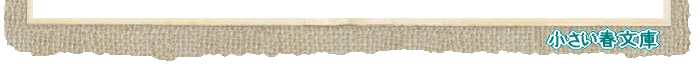スズメバチを見つけてパニックになった妻が、必要以上に騒いでハチを興奮させたために、さされてしまい、泣き叫び、もがき苦しむその様子を思い浮かべることが、快感にさえなっていた。
* * * * * * * * * * * * * * *
スズメバチ
はだい悠
* * * * * * * * * * * * * * *
オカムラコウジ、銀行員、二十九歳、身長百八十センチ、体重七十五キロ、A型、容貌は端正だが男性的、性格はだれが見ても素直で明朗。
そして、周囲対する順応性と協調性がひときわすぐれていて、その人柄の良さと誠実さは、顧客だけでなく、上司や部下からも心底信頼されるに十分なものがあった。
その上、ただ単に仕事が出来るというだけではなく、統率力や指導力が人よりぬきんでたものがあるため、現在だけでなく将来にわたっても、銀行にとってはなくとはならない人材であることは、衆目の一致するところであり、ひそかに期待されていた。
彼にとって、この十年に起こった良い事とは、一流といわれる大学に入学したこと。そして上位の成績で卒業したあと、一流企業といわれる現在の銀行に就職したこと。
そして学生時代にテニス同好会で知り合った、人もうらやむような資産家の娘である美しい女性と結婚したこと。
さらには、華やかな反映の時代に、スポーツで培った体力と天性の知力、そしてそのひたむきで楽天的な性格を十二分に生かして、子犬のような愛嬌のよさと豹のような俊敏さで動きまわっては、ずば抜けた実力を発揮し、銀行の業績の向上に多大なる貢献をし、そしてそのことが公然と認められて、同期の誰よりも早く係長に昇進したこと。
その上さらに、妻の実家から多額の援助を受けて、駅にも近い閑静な住宅街に周囲と見劣りしない家を新築したことであった。
彼に起こった悪い事とは、ここ二三年の経済活動が、かつての青春期のような輝きを失ってきているということ。
そして、その当時、彼も直接かかわっていた事が原因となり、銀行がその融資先であった顧客から、商法に反するような不正な契約ではなかったかということで訴えられ、マスコミからも無垢な人々をだまし陥れ、その財産を根こそぎ巻き上げてしまう悪徳金融業強者まがいの行為であるかのように、著しく社会道義に反することとして非難されていること。
その当時入社して間もない彼は、銀行の経営方針や上司の命令に忠実に従いながら、繁栄を極める時代の寵児として、その本流をその、才能の赴くままに先頭を切って、働き蜂のような従順さと戦士のような規律正しさで、果敢に走り抜けたに過ぎないのであったが。
しかし、繁栄が陰りを見せてきている現在からみれば、彼を含めて銀行のやったことは、なんの先見性も経営戦略も持たないままに、業績至上主義に目がくらむあまり、社会が変化するということを見逃してしまい、結果的には、その返済能力を無視した、しかも、ちょっとした経済状況の変化で破綻をきたすことは目に見えていた無謀な過剰融資ということになり、そしてそのことが原因で、融資を受けた顧客の大半を破産の瀬戸際に追いやり、絶望と不安の日々に落とし入れて、自殺者を出したり家庭崩壊を招いたりして、たくさんの人々を不幸な目に合わせたというので、連日のように抗議のデモを受けたり、マスコミから不道徳的な商行為として非難されるのやむを得ないことであった。
このような状況をテレビニュースではじめて知ったとき、(コウジにとってはそれが最初で最後ではあったが) そのとき彼は、自分が直接かかわっていたことであるとはいえ、それはもう済んだ事過去の事であるから、いまさら、どうのこうのと言っても始まらない、という思いと、自分はあくまでも組織の一員として、必然的に上司の命令に従ったまでのことであり、自分のやったことは誰からも非難されることのないまったく正当なものである、という思いで、何がそんなに問題なのだろうと、むしろ反発を感じるくらいに批判的な気持ちだった。
それから、その後も、ときおり表の通りが、抗議のデモで騒々しくなることは何度かあったが、彼にとっては、遠い世界で起こっている出来事のように、それほど重要なことではないという思いで、ほとんど気にはならなかった。
といのも、自分は決して、いや天地神明に誓って、悪徳金融業者のようにお客をだまして落とし入れ、その挙句に破損させて、その全財産を巻き上げようとしてお客に近づいたのではなく、あくまでも、顧客のため、社会のため、銀行のため、そしてひいては自分のためになると信じてやったことであり、自分は頭の先からつま先まで潔白であり、少しのやましさもないことに、彼は絶対的な自信を感じていたからである。
またそのようなトラブルの解決には、上層部の人間が直接あたることであり、彼を含めて多くの現場の人間にとっては、日々の業務に忙しく、上からも下からも、そのことについて話題になることはまったくなかったからでもあった。
それよりもなによりも、とにかく彼は、自分が周囲から期待されていることが肌で感じていたので、係長としての新しい職務に誇りと生きがいをもって、あるときは、大理石のような冷静さと、コンピューターのような堅実さで、またあるときは、心臓のような規則正しさと、電子時計のような正確さで、献身的に働くことに夢中であったためでもあった。
それは、九月に入って最初の日曜日の朝のことであった。
コウジは普段どおりに起きると、洗面台で顔をあらい、鏡を見ながら、決まりきったように髪を整えメガネを掛けなおした。
そして、朝食のため食堂に入った。
しかし、ここのところずっとそうなのであるが、つまり、二週間前に、この新しい家に引っ越してきてからは、毎日ずっと、それ以前のように朝食の準備らしい準備はされていなく、彼も妻の姿もいつもそこにはなかった。
というのも、新しい末に引っ越してきてからもうすでに二週間もたつというのに、彼の妻は朝食そっちのけで、引越し後のあとかた付けや整理整頓だけでなく、家具や備え付けの照明器具、それに食器類の配置や飾り付けに、いまだにかかりっきりだったからである。
特に彼の妻は、インテリアに凝っていたので、その変更は毎日のように続き、部屋の雰囲気は翌日にはまったく変わっているというありさまであった。
だからここ二週間は一緒に朝食をとったことがないというだけでなく、ご飯だけはどうにか炊けてあるという状態のなかで、自分で食器とおかずを用意して、なんとなく落ち着かない気分のまま一人で食べていたのである。
新居に引っ越してからの二週間というものは、彼が残業を終えて帰ってくると、玄関には新しい家具や電気製品、それに食器類や絵画や日用品が連日山のように積まれていた。それはほとんどがデパートから届けられたもので、段ボール箱に入っているため、はじめは一見して何が入っているかわからないのだが。
それを妻は翌日になると朝から整理し始めるのである。
つまり彼の妻は、午前は整理整頓、午後はデパートにいって買いものという毎日をこの二週間おくっていたのである。
しかし、なかには、前の晩、確かに玄関にあったものが、翌日にはどこにも見当たらなくなっている物もあった。
だが、それは彼の妻が、趣味の部屋とか自由に部屋とか称して、夫のコウジをまだ一度も入れたことがない、八畳ほどの広さの彼女自身の部屋に入っているんだろうと思っていた。
そこには彼女専用のオーディオ機器とともに、彼女が子供のころから親しんでいた家具や絵本やぬいぐるみ、それにピアノと油絵の道具、そして彼女が結婚する前までのアルバムやビデオテープなどの思い出の品物のすべてから始まって、かつては妻の趣味に合わせるかのように二人して頻繁に出かけていたが、最近はまったく行かなく買った映画や演劇のパンフレットなど、彼女一人だけで楽しむような趣味に関するものがいっぱい入っていて、壁も新しく彼女ごのみの壁紙に全面張り替えられ、そこには二人の共有の場所にはふさわしくないような彼女の好きな俳優やタレントの写真とともに、お気に入りの絵やポスターも飾られてあった。
コウジは朝食をとりながらテーブルの上に無造作に置かれてあったお菓子の空箱に目をやった。そこには日用品と共に、二人が知り合ったころにとった写真が収められている写真立てが入っていた。 それはここ数年、どこかに紛れ込んでいたのか、まったく目にしていないものだった。
彼は最初、その写真に写っている男がメガネを掛けていなかったというせいも多少はあったが、その十年前の若々しい自分の姿が、他人であるかのような不思議な印象を受けた。それは無意識のうちに、先ほど洗面台で見た自分の顔と比較していたからである。彼はそれを手にとってじっと見ていると、あるはっきりとした匂いの感覚と共に、風景とも何かの形ともはっきりしないが、確実な広がりを持ったイメージが頭の中でフラッシュのように激しく明滅するのを覚えながら、その自分の過去の若々しく屈託のない明るい表情に、生意気さや傲慢さを読み取り、憎しみにも近い反発を覚えた。そして、世間知らずの顔をしていると、不機嫌そうにつぶやきながら、それを元に戻した。
彼はこれ以上食べる気がしなくなった。そこでさっさとそれを片付けると、居間に行きソファーに背を持たせかけた。
そして、いつになく落ち着かない気持ちで妻が通りかかるのをじっと待った。
妻はなかなか通りかからなかった。
新聞を広げては見たが少しも頭に入らなかった。
そこで放り出すようにしてそれを脇に置くと、背をソファーに深く持たせかけると、なにげなく天井のほうに目をやった。すると、薄茶色の天井と似た色で、しかも照明器具の陰に隠れて、よほど注意をしてみないと目に付きにくいところに、天井にへばりついているかのように微動だにしない、その人差し指大の黄色い物体を目にして、思わずオッと驚きの声を上げながら、子供のころに味わったような感動にとらわれた。
そして、まだ、居たのかという不思議な思いでその物体に目を見張った。
それはちょうど六月の日曜日の午後のこと。
今日のように一人でくつろいでいるときに、窓から入ってきた一匹のスズメバチであった。
最初そのスズメバチは開かれた窓のところに、突然のように羽音を響かせながら現れると、しばらくのあいだ、何か中の様子をうかがうかのように、そこでホバァーリングをしていた。
彼はスズメバチに対して凶暴な印象をもっていたので、すぐさまソファーから上体を起こして、警戒するかのようにじっと見つめながらも、できれば居間に入ってくるのを阻止したいと思い、それに役立つものを探すかのように、ときおりすばやく周囲に目をやった。
やがて、そのスズメバチは一段と羽音を高く響かせながら侵略者のように悠然と入ってきた。そして、何かを探索するかのように、ゆっくりゆっくりと天井近くを旋回し始めた。彼は万一の攻撃に備えて、そっと立ち上がると、その防御になるようなものを必死で探しながらも、その一方では悠々と飛び続けるスズメバチの姿を、注意深く目で追い続けた。そして、スズメバチは今いる場所に止まり急に静かになった。
それでも彼は警戒心を解かず何とか退治することを考えていたが、どうしてもこれといった手ごろな道具が手近に見つからず、胸の高鳴りを覚えながら、そのままじっと見ているだけであった。しかし、そのスズメバチは、その後まったくといって良いほど動く気配を見せなくなってしまった。彼は再びソファーに腰をおろしたが、手には先ほどの新聞を丸めてもちながら、じっと見続けた。
だが、相変わらずそのスズメバチは動く気配を見せなかった。
そのうちに彼は、もしかしたらスズメバチは自分が攻撃されない限り、人間にはなんの危害も及ぼさないのではないかという気持ちにだんだんなっていった。
そして、それ以後は、ときおりその所在の確認をかねて、あたかも観察するかのように冷静に見るだけで、それほど気にならなくなっていった。そして、今日まで、その存在をまったく忘れていたのである。
さらに彼はこのことを、なぜか妻にはいっさい話してなかった。
コウジの目の前を妻のユキエが忙しそうに、ばたばたと足音を立てながら通りかかった。彼は窓の外に目を向けたままぶっきらぼうに言った。
「ごはんは?」
「できてるわよ、見なかった」
「そうじゃなくって、たべないのかって?」
「わたし?わたしは後で食べるわ。いまはそれどころじゃないのよ。いそがしくって、ああ、いそがし、、、、」
そう言いながら居間を出て行くユキエを、彼は勢いよくソファーから立ち上がり、追った。そしてキッチンに入っていくユキエの背に向かってややいらだって言った。
「そうじゃないんだよ。いっしょに食べないかって聞いてんだよ」
「なあに、なに言っているのよ、急に。いままで一人で食べていたじゃないの。いったいどうしたって言うのよ」
ユキエはそう言いながら、綺麗な包装紙に包まれた箱の中から真新しい食器を出し始めた。それを見ながら彼はさらに苛立って言った。
「どう下もこう下もないよ。そんなの後だって良いじゃないか。どうしていっしょに食べようとしないんだよ」
「だから、さっきいったでしょう、いまはいそがしいって」
「そんなのいつでも良いじゃないか、もう止めろよ」
「ねえ、どうしたの急に、なにかあったの?あなた少し変じゃない?」
「へんだと、変なのはお前じゃないか。はい、そうしますって、なぜ素直にいえないんだよ」
「おまえ、おまえって、威張っちゃって、ああ、いやだ。わたしが何をしたって言うの?朝からもうやめてよ。せっかくの日曜日がだいなしじゃない」
「そんな問題じゃないんだよ。いったい、いつまでかかっているんだ。引っ越してからもう二週間にもなるんだぞ。いったい、いつになったら落ち着くんだ」
「だって、かかるんだからしょうがないじゃない。遊んでるわけじゃないんだから」
「いや、ちがう、買いすぎなんだよ。無駄遣いなんだよ」
「良いじゃないの、別にあなたに負担を掛けているわけじゃないんだから」
「いや、ちがう、違うんだ。そういう問題じゃないんだ」
「「じゃあ、どういう問題なの?そんなもったいぶった言い方しないで、もっとはっきり言ってよ。そんなにわたしに不満や言いたいことがあるならこの際はっきり言ってよ」
「そういうことじゃないんだよなあ。なんか違うんだよなあ、とにかくオレはいやなんだよ。なあ、良いじゃないか、そんなにいっぺんに買い揃えなくても。ボクの給料だけで十分にやっていけるんだから。その中から毎月少しずつ当てて、徐々に買い揃えていけば、そのほうがずっと楽しいと思うよ。今それほど不自由している訳じゃないんだし、いっぺんに買ってしまってこの後どうするの?物がいっぱいあるからって幸せとは限らないんだから」
「ああ、もういや、そんな奥歯に物が挟まった言い方、耐えられないわ。なにが言いたいの?いったいなにが不満なの?わたしにはあなたの言うことがさっぱり判らないわ。良いじゃない、いまいっぺんに買おうが、こつこつ買おうが、同じじゃない」
「そういうことじゃないって言ってるだろう。つまりだなあ、とにかくオレはいやなんだよ。買いすぎなんだよ。もうやめろよ、やめろって言ってるだろう。そんなにオレの金で買うのがいやなのか?」
そう言いながらコウジは、食器の整理をしているユキエの腕をつかみ止めさせようとしたが、彼女はとっさに激しく抵抗しながら叫ぶように言った。
「いやぁ、はなして、あぶない、キャア、落ちる、いやぁ、ああ、、、、」
「わかった、わかった、もうわかったよ。でも、いったいどうするつもりなんだ。二人だけだというのに、こんなに食器を買い集めて、なにに使うんだよ。それになんだよ、あの帽子にくつした、大きいのから小さいのまで、あんなにいっぱい買い集めて、いったいどうしようっていうの?幼稚園のクリスマスじゃあるまいし、、、、」
「あっ、あなた、見たのね。わたしに無断で見たのね。かってに入って見たんでしょう」
「何をいってるか、おまえの部屋なんかに誰が入るもんか。玄関の荷物の中に同じような箱が毎日のようにあったから、なにが入っているのかなあと思ってチラッと見ただけだよ」
「まあ、いやらしい、女性のものを黙って見るなんて、ヘンタイ」
「言うに事欠いて、なんてことを言うんだよ。そういうお前こそヘンタイじゃないか。帽子や靴下だけじゃない、ぬいぐるみだってあんなにいっぱい集めて」
「かわいいでしょうよ。きれいでしょうよ。なにもあなたに迷惑を掛けているわけでもないし、良いじゃない、わたしの勝手でしょう」
「いや、まともじゃないよ。大人の女性のやることじゃないよ。ちょっとおかしいんじゃないの?」
「ああ、もう、うるさい、うるさい」
そう言いながらユキエは作業の手を休めると、もうなにも聞きたくないといわんばかりに両手で耳をふさいだ。コウジはその様子に冷たい視線を投げかけていたが、再び手を動かし始めた妻に向かって見下すように言った。
「お前も代わったな、前はそんなんじゃなかった。もっと理性的だったし、素直だった。それに浪費家でもなかった」
「あら、それはこっちの言うせりふよ。あなたにそんなこと言われる筋合いはないわ。変わったのはあなたのほうよ」
「なにも変わってないよ」
「変わったわよ。あなたはそれに気づかないだけよ。もっとも気づくようなら変わってないかもね。前は適度に遊ぶことをしていたわ。スポーツをしたり、映画を見たり、音楽会に行ったり、よくパーティーや食事にも出かけたわね。それにいっぱい話もした。楽しい話からくだらないばかばかしい話まで、面白おかしく、あなたはいろんな顔して話していたわ。それが今どう、仕事の話だけ、仕事の話しか興味を示さないじゃない」
「可愛くないなあ。どこまでも逆らいやがる」
とコウジは小さくつぶやくように言った。するとユキエは眉を少し吊り上げながら反抗的に答えた。
「どこが可愛くないの?」
「いや、それは違うね。お前は根本的に間違っているよ。あまい、あまいなあ。それなら言わせてもらうよ。まずだ、あのころオレは映画やコンサートはあまり好きでなかったんだ。でも周りの人たちがそうするし、お前も無理に誘うから、仕方なくというか、義理というか、それで付き合っていたんだよ。それに、いまはもう遊んでなんかいられないんだよ。学生気分がいまだ抜け切らないお前とは違うんだよ。女と違ってね、男はそんなのんきなことを言ってられないの。男は競争に負けたらおしまいなの。遊びにうつつを抜かしていたら落ちごぼれになってしまうんだよ。だいいち昔のように映画やコンサートや食事に行ったからって、いったい何か役に立つというんだい。ものすごい量の情報が世界を飛び交っていて、めまぐるしく社会が変化しているんだよ。それに全神経を使って注意していないと、たちまち時代遅れになってしまうんだよ。そんなときに、そんな遊びがいったいなんの役にたつと言うんだい」
「語るに落ちたってまさにこのことね。やっぱり変わったじゃない。ますます理屈っぽくなってるじゃない。ぞれだから余裕がないって言うか、つまらないと言うか、、、、」
その自信たっぷりの、しかも小ばかにしたような冷たい言い方に、コウジは瞬間的に激怒した。そして今までに二三度会った夫婦喧嘩でも決して見せなかったような荒々しい声で言った。
「なんだ、つまらないだと、利いた風なロを利くな。二度とそんなことを言ったら許さんぞ」
「なによ、それ、威張っちゃって、何様だと思っているの。まるで思い通りに行かない駄々っ子ね」
「生意気言うな、オレはこの家の主人なんだぞ。今日からは俺の言うとおりにするんだ。良いか、お前はオレの言うことを黙って聞いてりゃあいいんだ。今度逆らったら絶対に許さんぞ」
「まあ、あなたがそんな、、、、人だとは思わなかったわ」
「ああ、オレは昔からこうなんだよ。どんな人間だと思っていたんだ。いやなら出て行け、馬鹿野郎」
彼がそういい終わると、ユキエは怒りと驚きの目でじっと夫を見ていたが、そのうち徐々に涙目になり、手に持っていた食器を放り出すと、その場から走り去るようにして離れ、自分の部屋に閉じこもってしまった。直後コウジは、食堂と居間を意味もなく行ったり来たりしていたが、それを含めて、その後をどうやって過ごしたかは彼の記憶にとどまらなかった。
次の日から二人はいっしょに朝食をとるようになった。しかしロはいっさい利かなくなった。
ユキエの買い物も以前よりは明らかに少なくなった。だがそれは、買うのを控えたというよりも、もう買うものがなくなったという感じであった。
それに彼はもう妻が何を買おうが関心がなくなったというべきかは、たとえデパートから届けられたものがいまだに玄関にあったとしても、まったく目を向けなくなってしまっていた。
そして以前にもまして、夫婦の会話が少なくなってきているということにも、ほとんど気にならなくなっていた。
それは前よりも仕事に熱中するようになったからでもあったが、しかし、仕事に熱中するといっても、彼が入ったころのように、がむしゃらと言っても良いくらいに情熱的に、しかも、ひたむきにやっているということではなかった。というのも、役職といっても慣れてしまえば楽なもので、あとはごく普通にやっていれば、無難にこなせるという能力をコウジは持っていたからである。
だが、彼の心の変化を正確に言えば、彼はもう仕事以外には興味がなくなったということであった。
そんな中でも例外的なことはあった。
それは居間の天井にへばりついているあのスズメバチについてであった。その不思議な行動が気になり、勤務中でも、なぜあそこにじっととどまっているんだろうかとか、その目的は一体なんだろうかとか、色々と考えるようになっていた。そして思わずニヤリとすることがあった。それは妻があのスズメバチを思いがけずに発見して、うろたえ恐怖におののく姿を思い浮かべたからであった。そしてそのうちに、スズメバチを見つけてパニックになった妻が、必要以上に騒いでハチを興奮させたためにさされて、泣き叫び、もがき苦しむ妻の様子を思い浮かべることが、快感にさえなっていた。そして彼にとっては、朝出かけるときと夜に帰ってきたときに、その所在を確かめることが習慣となっていた。
そしてある休日に、妻が出かけていないとき、コウジは食堂から椅子を持ち出してきて、それを踏み台にして、そのスズメバチを観察することにした。それはスズメバチの不思議な行動を解明するためでもあったが、怖いもの見たさでもあった。
彼は慎重に椅子にあがり、恐る恐る八十センチほどの近さにまで顔を近づけた。ハチが微動だにしないというのは間違いであることに気づいた。前足と頭を何かの作業をやっているかのように繰り返し繰り返し、かすかに動かしているのである。黒光りのする目は、深い闇のように不気味で、鉤のように鋭いロは獰猛さをたたえていたが、今にも攻撃を仕掛けてくるという気配はまったく感じられなかった。
彼はスズメバチが同じ所に三ヶ月もとどまっているその理由や目的として、近くに自分たちの巣があるので、それが発見されて壊されないようにするために、この家にどんな人間が住んでいるかを観察し、かつ、その行動を監視しているのではないかと、考えたがそれほど納得のいくものではなかった。
そして、ついでに、どうしてその凶暴性が失われたのかについても考えたが、これといって答えらしいものは思いつかなかった。
十月のある晴れた日曜の朝。居間で新聞を読んでいたコウジはある見出しに目を奪われた。
そこには自分の銀行の名前と、銀行の信用性を強く否定する文字があった。
彼は動揺し一瞬目をそらしたい気持ちに襲われたが、それが返って逆に働いたようで、まるで外からの力で強制されたかのように目が釘付けとなり、禁制を破るかのような胸の高鳴りを覚えながら、そして勢いのある流れに押し流されるように一気にその記事を読んだ。
そして、副頭取の次のような発言
「正当な商行為である。もし万が一、過ちがあったとしても、当時の行員にはいっさい責任がない」を目にして体の芯から熱いものがこみ上げてくるのを感じた。
そして、それが体の隅々のカチカチに凍りついた血液を溶かして、勢いよく流れ始めたような気がして、顔は高潮し、体全体が開放されのびのびとした気分にとらわれた。
そして頭の中には、その姿や形は漠然としていたが、楽しさやうれしさをともなうイメージが満ち溢れてきた。
なぜそうなるのか、その理由をコウジははっきりとは判らなかったが、次々と沸き起こる喜びの感情の中で、
「正しいのだ、正しかったのだ」
と自分に言い聞かせるようにつぶやきながら、家の中をこれといった目的もないのに、夢遊病者のようにぼうぜんと歩きまわった。そのうちに家の中に閉じこもっている場合ではないような気がして外に出た。
秋の柔らかな日差しを浴びながら、人影の少ない通りをコウジは晴れ晴れとした気持ちで歩いた。
特にどこに行こうかというはっきりとした目的はなかったが、とにかく歩かずにはおれない気分であった。歩きながら彼は、
「正しいのだ、正しいのだ、正当なのだ、正当なのだ」
と自分の軽やかな歩調に合わせるかのように何度も何度も小さくつぶやいた。
そしてさらに自分を元気付けるかのように次のようなことを思った。
≪わたしたちは決して間違っていなかったのだ、
わたしたちの行為は正統なものだったのだ。
人間は決して一人では生きられないのだ。
組織や集団の中でしか生きられないのだ。
命令するものがいて、それに従うものがいて、
はじめて組織や集団は成り立つのだ。
社会は動くのだ。
もしも、わたしたち一人一人が別々に目的をもって勝手に行動したら、
いったい何ができるというのだ。
組織や集団がはっきりとした目的をもって、
その目的のために命令に従い、規律を重んじ忠実に働くことが、
社会の発展につながり、ひいては、
自分の幸せにもなるのだ。
見るが良いあのスズメバチを。
仲間から離れて何にもできないじゃないか。
元気がなくなっているじゃないか。
人が一人一人集まって社会があるのではない。
社会があるから人は一人一人あるのだ。
一人一人の意思や目的が集まって、社会の意思や目的となるのではない。
まず社会に意思や目的があって、それが一人一人の意思や目的となるのだ。
わたしのやったことは決して間違っていなかったのだ。
今日は本当に気持ちが良い、こんな晴れやかな気分は久しぶりだ。
本当によかった≫
コウジは踏み切りに近づいた。
警報機がなった。
遮断機が下りた。
それまでコウジの前をゆっくりと歩いていた親子連れが立ち止まった。五歳ぐらいの女の子と、その母親らしい妊婦服を着た女性。母親に手を引かれているようにも、母親の手を引いてるようにも見えるその小さな女の子は、全身に不安さをあらわしながら心配そうに母親の顔をのぞきこんでいる。 なにげなく二人の様子に目をやっていたコウジは、そのときそれまで味わっていた感情、つまり伸びやかでうきうきとした喜びに満ち溢れた感情とはまったく異質の、というよりも、まったく正反対の重苦しい感情に突然襲われた。
それは今にも胸が押しつぶされそうな、せつなく悲しくとてつもなくさびしい感情だった。彼は二人の様子に眼を奪われ続けた。
なにか目に見えない者の意思が働いて彼にそうさせているかにように。
それは爆発的な勢いで彼の内部に芽生え始めた新しい感情がそうさせているのであったが、彼には それがどのようなものであるのか、まだはっきりと意識されていなかった。
そのとき不意に、その母親は子供の手を引いて遮断機をくぐり、ゆっくりと線路の方へ歩き始めた。
コウジは反射的にごう音のする方向を見た。
電車が目に入ってきた。
五十メートルほど先のところであった。
彼は一瞬にしてすべてを把握した。
まだ二秒はあると。
彼は、一秒、二秒と、頭の中でカウントしながら、すばやく遮断機をくぐり、姿勢を低くしてダッシュをかけ、その勢いで線路上の親子を抱え込むようにして前方に突き飛ばした。
そして、二秒といい終わったあと激痛を覚えた。
というより激痛そのもので激痛の真っ只中にいるという感じであった。そのうちに激痛を感じているのは自分であるということがだんだん判ってきた。
そして、それ以前までのことが頭に浮かんできて、いま自分になにが起こっているのか漠然とつかめるようになってきた。
激痛を感じながらコウジは、失敗だったのかな、と思った。
これが、自分の体が電車にばらばらに引き裂かれていることなのかな、と思った。
うまく行くと思ったのになあ、とも思った。
そのうちにコウジは、痛いのは頭だけであるということが判ってきた。
そして、周囲がざわついていることに気がついてきた。
閉じた目に明るさを感じてきた。人の声が聞こえてきた。
「いやあ、びっくりしたよ、あっというまだったよ。
それにしてもすごかったね。
もうだめかと思ったよ、本当に勇気のある人だ。
ヒーローだよ。
それにしても何でまたこんなところに杭があるんだよ。
勢い余ってこれに頭をぶつけたんだよなあ。
おい、だれか、救急車を呼んでくれ。
まあ、多分大丈夫だと思うけどな。
なにせものすごい勢いだったからね。
脳しんとうを起こしたんだと思うよ。
みんな助かってほんとうによかった。
子供も元気そうだし、母親も大丈夫みたいだし、もう大丈夫だな。
この人の痙攣もなくなったし、ほら、顔つきもだんだん穏やかになってきてるだろう。
もう大丈夫だ。
そのうちに気がつくだろう。
この人はヒーローだね、現代のヒーローだよ」
そんな声を耳にしながら、コウジは静かに静かに体に力を入れては、熱を感じ、風を感じ、自分の肉体の所在をはっきりとか感じ取ることができた。
そして、まだ激しい痛みは続いていたが、このままここにずっと横たわっていたいような不思議な幸福感に満たされていた。