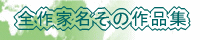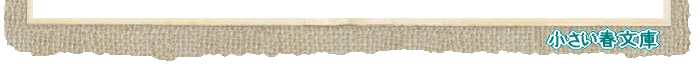これで誰でもが英会話が出来るようになる。
* * * * * * * * * * * * * *
英会話ができる
真善美
* * * * * * * * * * * * * *
序論
本題
わたしのように、かつて、
けっこう真面目に勉強したつもりでも、英語のテストの点数が、
どうしても二十点とか三十点とかしか取れなくて、
もしかしたら自分は頭が悪いのではないか、
才能がないのではないかと思いながらも、
それなりに懸命に努力するのであるが、でも成果には結びつかず、
やっぱり自分は頭が悪かったのかと、半ばあきらめ、半ば絶望して、
英語に対する苦手意識が芽生え、
それがいつしかコンプレックスとなって意識の奥底に潜むようになり、
そしてやがて大人になり、仕事の上でも、
また教養の上でも英語の必要性にせまられ、
さらに多少の見栄もあってか、あの過去の苦々しい経験も忘れさり、
身のほど知らずにも再び英語の勉強を始めるのだが、
やはり無残にも再び挫折して、今度こそ、
本気で自分は頭が悪いのだ才能がないのだと思い込むようになり、
そして本当にあきらめ絶望して、そのコンプレックスが高じて
英語そのものに対して拒絶反応を起こすようになり、
いつしか脳がレンガのようにカチカチになってしまっていた者が、
人生の折り返し地点に差しかかっていたある日の午後、
突然のように天から啓示を授けられ、
その教えに従って英語の勉強を始めたら、
学ぶ事がかつてのように苦痛なものではなくなり、
むしろ喜びであり楽しい事のようになり、
それによってみるみる英会話能力が向上して行った、
その方法について。
副題
失敗と挫折の繰り返しの人生において、
現実的にも実践的にも唯一の勝利らしい勝利といえるもの、
永久に不可能と思われていた英会話が、
なんと一ヶ月わずか缶ジュース一本の費用で身についているという、
その方法について。
本論Ⅰ
まずはじめに、わたしがなぜこのような小論を書くに至ったかについて述べなければならない。
現在、わたしたちの社会は、若者たちがかつては考えられなかったような犯罪に手を染め問題を起こすと、大きく揺さぶられる。
大人たちはいっせいに戸惑い頭を抱える。
このような豊かな社会にあって、若者たちはいったい何に悩み、何に不満で、そしてどこに問題があるのかと。
そして膨大な労力と時間を費やして考える。
これからどのように若者を教育し指導していけばいいのかと。
かつて私はこのような問題に対して、まったくと言って良いほど関心を示さなかった。
私にとっては、もうどうでも良い事であったからだ。
というのも、私は若いときから。
私を含めてその若さというものが嫌いだったからだ。
若者たちが生きる事にどんなに迷い苦しみもがこうとも、それは彼ら自身の努力で自己責任で解決していくべき事だと考えていた。
わたし自身もそうしていたのだからと。
もし若者たちが自らの力で問題を処理できなくなり、生きる事に行き詰まり怠け者になり犯罪に手を染めようとも、それは彼ら自身の努力不足によるもので、自業自得だと考えていた。
だが人生の折り返し地点に近づいていた頃から私の考えはまったく変わってしまっていた。
そのような考えは根本的に間違っていたのではないかと。
若者たちの自主性に任せるということ。
美しい言葉である。
ほとんどの大人たちはそう思っている。はたしてそれで良いのか、もっと積極的に働きかけるべきではないのか。
というのも、わたし自身は、青春というその地獄の季節を、大人の助言も干渉も受けることなく自力で乗り越えてきたとずっと思ってきたのだったが、実はそうではなかったということに、陰ながら精神的にも物質的にも親や周りの大人たちから支えられていたということに気付き始めていたからである。
そして私がかつて大人になっても若者たちに無関心であったことに激しく反省し後悔をするようになっていたからである。
なぜなら、あのときの若者のふてくされた表情や、反抗的な言動は、ほんとうは彼ら自身の自信のなさや未来に対する不安からくるもので、実際はわたしたち大人から助言や支えを求めていたということに思い返されるからである。
若者たちは相変わらず大人たちを見下し侮辱し、無責任でわがままで傲慢で独り善がりで見境がない。
しかし、だからと言ってほっといて置いて良いという事にはならない。
現代はわたしたちの若いときに比べて、はるかに豊かで便利で様々な情報にあふれている。
にもかかわらず若者は生きる事に迷い不安げである。
それは競争にさらされているほとんどの若者たちが、その厳しさにたじろぎながらも挑みはするが、それに敗れたものは、より豊かで幸せな生活は送れないという思いを抱いているからである。でもそれてあふれる情報に惑わされた間違った考えである。
妄想である。
競争の厳しさは今も昔もちっとも変わっていない。
それでも、いまの大人たちは生きてきた。
それは競争に打ち勝ってではない。
大人たちは長い間の経験から、決して勝ち負けで人生の幸せが左右するとは考えていない。
人生というものはもっとたくさんの要素が複雑に絡み合って成り立っていて、それぞれの人生も多種多様であるという事に気付いている。
でも大人たちはあまりその事を言わない。
それは言ってもどうせ聞いてもらえないからということで言わないのか、または、はなからそんな事を言うつもりはないと冷たく突き放しているのか、それとも言いたくても言う手段や方法が見つからないのか。
若者たちが何かを注意されて不機嫌になったり、言葉づかいが荒くなって激しく反抗したりするのは、彼らの自信のなさや不安から来る虚勢である。
だから大人たちは決してたじろいではいけない。
どんなに激しく抵抗されても辛抱強く関わり、積極的に助言を与え忍耐強く指導して行かなければならない。
なぜなら若者たちは心の底ではいつも大人たちの適切な助言や指導を、そして失敗したときには大人たちに寛大な対応をしてくれる事を求めているからである。
若者たちがその表面的な明るさや元気さではなく、陰のような寂しそうな心ぼさそうな表情をかいま見させるとき、私にはその事が手に取るように判るのである。
私は現在、若者たちに直接助言を与え指導をするような立場にはない。
でも、この小論を書く事によって、教育に関連して、特に英語教育に関しては有益な助言を与える事が出来る。
現在わが国では、せっかく学歴社会から抜け出そうとしているときに、今度は学力至上主義社会に陥ろうとしている。
学力をペーパーテストではかるという意味に置いてはそれは間違いではない。だが人間の能力をそれではかるとなると話は全然別である。
人間の能力は学力ではかる事が出来ないほど多相多元的で複雑である。
筆者は学校教育というものは人生においては百分の一か千分の一ぐらいの比重しか持たないと独断的に考えている。
その結果をペーパーテストではかった学力というものを人間の能力であるかのように見なすことは愚の極みである。
なぜこんな簡単なことが誰にも判らないのだろうか。
あの賢明で博学で超有名な評論家さえ気づいていないのだから仕方がない事なのか。
ペーパーテストというものは、ペーパーテストをやっているときにおいてのみ意味がある。
サッカーのシュート練習がサッカ-の試合でゴールを決めるときにおいてのみ役立つように。
その結果が人生の応用に利くとか役立つ等と言うことは迷妄であり錯覚である。
もしそのような考えが今後のさばり続け、若者たちを悩ませ苦しませ続けるなら、不必要な劣等感を産み付けるだけで人類にとっとは有害なものとなるであろう。
ペーパーテストというものは人間の特殊な一部の能力を測る学力というものを測る単なる目安に過ぎない。
そして現在まで過去百年と続き、今後も永久に続くと思われる文部科学省の方針のもとで、内なる官僚主義(注Ⅰ)に蝕まれて膨張する既得権益に群がるおびただしい数のパラサイターたちのために、教育は、若者たちにとってどのような教育が最も適切で有効か、などとはまったく考えられる事もなく、若者たちの心に傷深く無用な劣等感や敗北感や挫折感を産み付けながら、膨大なエネルギーとお金を飲み込むだけの巨大な産業と化してしまっている。
—————————————————
注Ⅰ 内なる官僚主義
内なる官僚主義とは
現実の社会がどのように成り立っていて、
今後どうなっていくかを抽象し分析し、
そして、その結果として自分たちはどのように振舞うのが、
最も適切でふさわしいのかを導き出すのが、官僚であるのだが、
ところがその現実を抽象し分析する能力でしかない自分の能力を、
あたかも現実を管理しコントロールする能力であるかのように思い込み、
官僚として自分たちが現実の社会を支配しているかのように錯覚すること。
これは万人がすべからく陥る錯誤である。
それが転じて、わたしたちの肉体で起こっている事や、
肉体そのものを抽象し分析し、
その結果、知識として色々な事を知るのだが、
その知る能力でしかないものを、
あたかもその能力がわたしたちの肉体そのものを、
支配コントロールしているかのように思いこむこと。
特にこの小論においては、
文法や英語に関する知識が英会話能力を、
支配コントロールしているかのように思いこむこと。
—————————————————
特に英語教育においては、いまのやり方では何年勉強しても、苦痛と拒絶反応を起こすだけで、英会話は出来ないということが判っていながら、いまだにその有効な手立てが打ち出されていないのである。その主な理由は、どのような対策も受験勉強とは相容れないということに、つまり受験にはなんの役にも立たないという事にあるらしいのだが。
私は決して近代教育のすべてを否定する過激派ではないが、でもそれに近いものがある。
たとえばこのように考えている。
日本が経済発展をとげたのは高等教育のおかげではない。
子供たちに高等教育を受けさせるためのその費用を稼ぎ出すために、世界に知られた勤勉な国民として名に恥じぬように親たちが一生懸命働いたからであり、と同時に自分たちは高等教育をやっているのだからきっと優秀であるに違いない、なにかをやれるに違いないと思い込んでいたからである。決して子供たちが真面目に勉強したからではない。これは間違いない。
私は、受験英語を百年勉強しても英会話は出来ないが、私がこれから述べる方法だと十年勉強すれば英会話が出来るようになるだけでなく、受験にもいくらかは役立つと考えている。
将来たぶん役に立つだろうと信じ込まされ、苦手意識やアレルギー反応しか生み出さない英語教育にあえぎ苦しむ若者を見かねて、私はわたし自身の成功例を元にして、本来言葉を学ぶという事はダンスを学ぶように楽しく喜びに満ちたものであるということを、彼らに気付かせその不必要な苦痛から開放してあげたいがために、どのような反論や批判も恐れることなくこの小論を発表することにしたのである。
そもそもである、私たちが子供のとき言葉を覚えるとき、その母の前で言葉を発し覚えることが無上の喜びであり楽しみであったはずだ。
本論Ⅱ
人生の折り返し地点をやや後方にかえりみながら、普段と何ひとつ変わる事のない退屈な毎日をすごしていたある日の午後、突然私は天からの啓示によって (これは冗漫な内容にもかかわらずわざわざここまで付き合ってくれた読者を退屈させないために考え出されたフィクションです) 次のような戒めを授けられた。
十二戒
一、英語を机に坐って学ぶな
二、英語を記憶しようとするな
三、日本語を英語に訳すな
四、英語を日本語に訳すな
五、文法を覚えるな
六、文字を覚えるな
七、文字を書くな
八、日本人に習うな
九、英語を読むな
十、発音記号を覚えるな
十一、アクセントの位置を覚えるな
十二、畳の上で英語を勉強するな
十三、お金をたくさんかけて英語を習うな
それでは次に、この十二戒のひとつひとつについて解説する前に、私がなぜこのようなフィクションを思いついたか、その理由となるそれまで私がどのような経験を経てどのような考えに至っていたかについて述べなければならない。
わたしは幾度かの挫折の経験の後、英会話を身につけることは自分には永久に不可能だとあきらめてはいたが、言葉そのものに関しては決して無関心であったわけではない。
いやむしろ敏感に注意を向けていたといっても差し支えない。
その関心は言葉と思考、言葉と行為の関係についても向けられるようになっていた。そして言葉に関して行為に関して思考に関して、様々な不思議なことや不可解な事を見聞きするたびに私は深く考えさせられるようになっていた。
たとえば、言葉に関しては、なぜ子供のほうが大人よりも英語を覚えるのが早いのか。大人は頭が固くなっているから、その上脳細胞がだんだん死滅しているからだなどと一般には言われているが、はたして本当にそうなのか。
哺乳動物と比較して知能がそれほど発達しているとは思えない鳥が言葉をしゃべり歌を歌い、はたまた昔話をしゃべるというとなるとこれはいったいどういうことなのか。
それは発声器官が発達しているからだというが、はたしてそれだけなのか。
脳との関係はどうなっているのか。
校歌などを覚えさせられるとき、わたしたちはそれを暗記し練習にのぞんだが、いつしか自由に歌えるようになると暗記した内容が頭から消えてなくなっていても歌うことが出来るのはなぜか。
それどころか何十年経っても忘れないのはなぜか。
いったいどこに記憶されているのか。
さらに歌の場合、特別に歌詞を覚えようとしなくても、何度も繰り返し歌っているうちに自然といつでも自由に歌えるようになってしまうのはなぜか。
いったいどのようなメカニズムが働いているのか。
決してその言葉やフレーズを特別に勉強したわけでもないのに、なぜ他のものより際立って聞き分けられるようになっているのか。
かつてある国からきた不法就労者といっしょに働いていた頃、その本国でも雇ってもらえそうにないくらいに休みがちで、いつもボォッとしていたその男は、私の話す言葉はほとんど理解をし、仕事に差し支えがないくらいにしゃべることもできた。
その男は日本語を覚える気などさらさらなかったが、コミュニケーションにはまったく不自由しなかった。
私が子供の頃、都会生活にはなじめない不良都会っ子がやってきた。彼は大切にしているナイフを見せてくれたり、お金にまつわる自慢話をしてくれたが何よりも困ったのは、彼のしゃべり方が早くてよく聞き取れなかったということだった。でもしばらくすると聞き取れるようになっていた。何が変わったのだろうか。
もちろん彼はしゃべり方が少し遅くはなっていたのではあるが。
行為に関しては、たとえば、学校の音楽の授業で、クラシック音楽を聞かされたとき、私は大げさで騒々しいだけの音楽のようにしか聞き取る事が出来なかった。
今ではほとんどクラシックしか聞かないのだが。その間にいったいどんな変化があったと言うのだろうか。
さらに自転車に一度乗る事を覚えたら二度と忘れる事がないように、スポーツやダンスや技能芸能などの世界において一度身につけたらその後忘れることがないのはなぜか。それは肉体に記憶されているといっても良い事なのか。
思考に関しては、わたしたちはある目的をもって何かを聞き取ろうとすればするほど、それがますます聞き取りにくくなるものである事を経験している。
またある何かをやろうとして、前もってその事に関する知識を頭に詰め込んでいても体は少しもいうことを聞いてくれず、そのような知識はなんの役にも立たないことを経験している。
さらには、これは情報と行為の関係に関してであるが、野球で、高めには手を出すなと指示された打者が、結局高めに手を出して空振り三振をしてしまったのか。
私はこの他にもまだ色々な経験をしているのだが、それが引き合いに出される最もふさわしい場所で披露していきたいと思っている。
以上これら言葉の介在によって起こる思考と行為、記憶と行為、情報と行為の奇妙で不思議な関係についての様々な経験と、その考察の結果として、私は次のような考えを持つに至った。
行為の始まるところに思考は終わり、思考の始まるところに行為は終わると。
そして、この大原則をもとに、この十二戒はさらに次のような考えを基本として考え出されたものである。
その一
わたしたちの肉体に起こる事を抽象し分析し、それを知識として取り出し、そしてそれを情報として他の誰かに伝えても、その伝えられた人がその情報を元にして、それと同じことを自分の肉体に起こす事は出来ないということ。
つまりそのような情報は肉体から精神へ、精神から精神へとはながれるが、精神から肉体には流れないということ。それは不可逆的であるということ。
その二
わたしたちが言葉を発するときは、思想的意味だけではなく、感覚的、感情的、時間的、空間的な意味を含んだ様々な情感に満たされているということ。
その三
聞く事と話す事は、まるで同じ神経を共同で使っているかのように密接な関係にあるということ。わたしたちは誰かが話しているのを聞いて、それを言葉にして復誦できないようなら、それをよく聞き取れないだけでなく、頭にも残らない。
つまり聞く事が不安定なものになり、なにか不完全な感じがする。
その四
聞く事は聞く事によってしか上達しないし、話す事は話す事によってしか上達しないということ。
その五
わたしたちが言葉を実際に発するとき、無限に近い情報を必要としている。つまり無限に近い情報が神経を行き交っているという事になっている。
だが、それはわたしたちの意識化にはない。無限に近い情報を意識化に置くなんてどだい無理な話しではあるが。
それは実際に行為として言葉を発することによって肉体的に自動的に行われ保障されている。意識的に発信されるわたしたちの頭からの情報からではなく。
だから話す事は話す事によってのみ完成に近づいていく。
つまりできるだけ発声器官に任せたほうが良い。
それでは、最初の
「英語を机に坐って学ぶな。」
(これは学校に勉強、つまり受験勉強をするな。と云うことを比ゆ的に言ったものであるが)
と云うことであるが。
これはわたしたちがどのようにして日本語を話せるようになったかを見れば判る。わたしたちが日本語を話せるようになったのは、日本語を学んだからではない。
それは幼いとき、心から信頼してその母たちと向き合う日々の生活のなかで、それを学ぼうとしてではなく、楽しい遊びのように、話すことが自分の利益にかなう喜びであるかのようにして、自然と身につけて行ったのである。
(ここでは一応母としておく。それは父であっても、兄弟姉妹であっても、親戚であってもかまわないのだが、筆者のようなマザコンにあっては特にそうしておきたい)
もう少し詳しく言うと、その母と幼児との一対一の関係性において、全的に実践的に、声と態度と表情を通して無限に繰り出されるお互いの情報をもとに、半ば無自覚的にも必要に迫られながら、それが今現在の喜びとなっているのを自覚しては、やがてそれがゆくゆくは自分の利益となる事を予感しながら、楽しい遊びのように自然と身につけて行ったのである。
それに比べたら机に坐った勉強と云うのは、脳のほんの一部分だけを使って、抽象的でしかも限定的な情報を元にして会話能力を身につけていこうとする方法だからである。
それはある目的、つまり受験にはとても役立つらしいのだが、英語を日本語のように話すようになるためにはなんの役にも立たないであろう。むしろ、この理由はこれから徐々に述べていくつもりだが、有害でさえある。
なぜなら、言葉というのもは、その母の前の幼児のように、母親のやる事を全面的に信頼して自分のすべてを預けるような素直な気持でのぞみながら、感覚的肉体的行為を通してのみ始めて身につくものである。
だから、幼児のようにも素直になれず、頭だけを使って英会話を身につけようとする大人が子供より覚えが悪いというのは納得が出来るのである。
次に二番目の「英語を記憶しようとするな。」ということであるが。これは英語を覚えるな、または英単語を覚えるなと言いかえでも良い。
私たちはがっ声で、文字をおほえさせられ、いやというほど単語や文を覚えさせられてきた。
それは何よりもまず英語の基礎とされ、そしてペーパーテストの成績につながりひいては受験に役立つと言われているからである。
確かにその通りである。でも、英語を文字として単語として単語の羅列として覚えることは、英語を話すこととはまったく関係ない、むしろ妨げとなるであろう。
それは私たちが日本語を話すときの事を思えば判る。
私たちは何かを話そうとするとき決して文字を単語を頭に思い浮かべない。
そもそも言葉をしゃべり始めた幼児は文字など知らない。
英語を覚えて役に立つのはまさにペーパーテストのときだけである。
それは頭のハードディスクに機械的に記憶された事が文字として再現される事が最も重要視されているからである。
(もちろんここでは文字の持つ重要な役割については本質的な会話能力とは直接的な関係がないので言及しない事にする)
わたしたちが言葉を話すというのは、まずなにか言いたい伝えたい思いがあって、次に、頭のハードディスクに記憶された単語をそこから取り出してきて、それを文法に合うように並べかえてから、ようやく声にして出すというようなものでは決してない。
それは幼児かその母の前で言葉をしゃべり始める過程を注意深く見れば判る。幼児はその母の前で、声を発しなにか言葉を話すことが自分の利益になり楽しいことである事に気付き、繰り返し繰り返しその言葉を発し、そしてその単語の数が増えていき、やがて単語が連なったひとつの短い文として自然と話せるようになる。そして話せる単語の数はさらに増えていき、文の数も飛躍的に増えていく。
わたしたちはここに言葉に関する様々な窮屈でしかも退屈な規則や約束事を見ることは出来ない。言葉は自由で伸び伸びとした楽しい事のようにして覚えられ発せられている。
わたしはここに人間が本来持っている無意識的な能力、だれの身にも備わっていると思われる能力を想定しざるを得ない。
行為として繰り返される事によって肉体に刻み込まれる能力、わたしはそれを肉体の記憶と呼びたい。それは学校での勉強のように頭のハードディスクだけを使って記憶されるような、時間が経てば忘れ去られてしまうようなものではない。
それは言葉を話すことが厳然たる行為として、行為としては同様の次のような例においても似たような結論が導き出されるのである。
これは少し前に述べた事であるが、歌を覚えようとして、まず歌詞を暗記するが、実際にメロディにあわせて歌っているうちに、その覚えた歌詞は頭にちらつかなくなり、やがてまったく気にならなくなったころに自由に歌えるようになり、その後もその歌詞をまったく忘れてしまっていてもその歌は歌えるということ。
また特別に覚えようとしなくても何度も繰り返し歌っているうちに覚えてしまうということ。
さらには自転車やスポーツや芸能などのように一度見についた行為や技や技術は二度と忘れることがないということ。
とくにスポーツの場合、こうしなけれがならないとあまりにもはっきりと意識すると
(これは言葉を発するときの文字としての単語や文に相当するが)
やらなければならない事が出来なくなったりまったく逆の事を行ったりしてしまう事がある。
これは言葉や情報を取り扱っている意識からは、わたしたちの肉体の記憶はかなり独立性を保ってあまり影響を受けないと云うことを意味している。
以上、これらから私は英語を覚えることは、英会話能力にもあまり役立たないだけではなく、ときには妨げとなる事もあるという結論にならざるを得ない。
それには、まず母親の前の幼児のように素直な気持になって、その言葉が発せられたように自分も何度も繰り返し繰り返し発して、いつでも自然と再現出来るように身につけることである。
次に三番目の
「英語を日本語に訳すな。」
ということであるが。
英語を日本語に訳して覚えるということは、言葉が持つ主なる二つの側面、意味と感情を伝え表現するという事の、その意味を伝え表現するという面だけに重点を置いた、学校の教育、受験勉強には大いに役立つのであるが、英会話能力を身につけるという面においてはむしろ有害となるであろう。 英語を日本語に訳して学ぶということは、英語を理解するという初期の段階においてはどうしてもやむを得ない面があるが、だがそれが習慣化するとますます英会話能力から遠ざかるだけでなく、それの妨げとなるであろう。
というのも、わたしたちが誰かが話す日本語を聞いてその言わんとすることを理解しようとするとき、わたしたちはその日本語をまず厳密な意味に訳して、それからその意味をもとにして相手の言わんとすることを理解しようとするだろうか。
そんな事はしない。相手の話しているときの語調や表情や身振り素振りからかもし出される雰囲気を全感覚的に感じ取りながら、言葉のもつもう一つの側面である感情をも同時に感じ取っているのである。
だから同様に、英語を聞いて、それを日本語の意味に訳してそれから相手の言わんとしていることを理解しようとすることは二重の遠まわりである。
もしわたしたちがすべての英語を日本語に訳して理解しようとしていたら、たとえば、グッドモーニングと声をかけられたら、まずその音から good morning という英語を頭に思い浮かべ、good は日本語で良い、morning は朝だから、その二つの言葉を合わせたgood morningの意味は、良い朝、そしてこの英語は、日本語では朝の挨拶である、おはよう、という言葉に相当する、というように頭で考えて理解する事になるのだか。
いったい誰がそんなまどろっこしい事をしているだろうか。誰もやっていない。わたしたちは反射的にそれを挨拶の言葉として受け取りその言葉の意味というよりも、大部分が占められているその言葉を発した人の感情的な側面、今日は気分が良さそうだとか悪そうだとかを一瞬にして感じ取るのである。
それが言葉の持つ現実的実践的役割であり、本質である。
ではなぜこれが可能かというと、それは何度もその言葉を日常的に耳にしており日本語のように肉体化しているからである。
わたしたちの意識が言葉のもつ意味的な側面に引きずられて、感情的な側面をおろそかにしているといつまで経っても言葉は身につかないといえる。
それは言葉が常に相対立する二つの法則に支配されながら意味的なものと感情的なものを表現しようとしているからである。その上でわたしたちは発せられた言葉に全的に向かい合いながら意味的なものと感情的なものを同時にバランスよく感じ取って行かなければならないのである。
そうするには、それが日本語であろうと英語であろうと意味だけに限定して解釈しようとしている余裕はないのである。
この相対立する法則というのは、たとえてみれば、絶対に相容れない二人の独裁者の様にも言う事が出来る。
つまり人々は両方の独裁者に気を使わなければならないように、言葉は意味の世界だけに偏る事も出来なければ感情の世界だけに偏ることはできないということである。
もし言葉が意味だけを重要視したら、なんとも喋りにくく人にも伝えにくい晦渋なものになってしまうだろう。
もし言葉が感情だけを重要視したら、それはまた同時に音声としての側面であるリズムや強弱や抑揚を重要視するということであるからしゃべりやすく人にも伝わりやすくなり、その発声器官としての機能がいかんなく発揮されるだろうが、それが高じて内容が空疎なリズムだけの音楽のようなものになってしまうだろう。
わたしたちは言葉が抽象的な情報を伝う足り知識を蓄えたりするために大いに役立ってきたことは認める。
だが、言葉で表現する事によって個人の人間の考えが発展するとか進歩するとかという考えには賛成できない。
言葉はあくまでも借り物で、わたしたちの思いを表現する手段に過ぎないのだ。
言葉はわたしたちが思いを表現するほかの手段、たとえば、音楽やダンス、絵や彫刻、スポーツやその他の様々な趣味などがあるように、その中のひとつに過ぎないのであり、音楽やダンスをやる人がその一度表現されたものを捨て去り、そこから抜け出して、更なる表現を目指して自由に飛躍しようとするように、わたしたちは一度表現されたものから決して縛られる事はない。
わたしたちは本質的に自由なのだから。
もしある言葉で表現されたものに永久に変わることがない絶対的価値を認めるとしたら、その人は変化することを望まない原理主義者におちいってしまうだろう。
人間は常に自由であり、変化するものであり、それに合わせるように表現する内容も変わって行かなければならないからである。
わたしたちは何かをやろうとするとき、そのやろうとする事がはっきりと意識されているときは、その行為は完成しないと云うことを知っている。
つまり、この場合、相手の話すことの意味にばかり気を取られていると、その言葉の持つ限定的な役割にとらわれすぎて全的に感じ取る能力が妨げられ、聞く能力さえも損なわれるだろう。
それは言葉で表現することの精神の自由性や柔軟性からの逸脱であり、言葉が担わされている根源的な役割からいっても邪道である。
くり返しになるが、表現というものは、まず表現したいという思いや感情があって、言葉や絵の具や音や自分の肉体を使って表現するのである。
そしてその思いや感情は時間と共に変化するものであり、以前に表現したものからは束縛されず自由である。
そしてそれは常に漠然としていてあるときは抽象的であったり、またあるときは具体的であったりして非常に不安定でもあるのであるが。
だから言葉は変化していくのである。
もし言葉に定まった意味しか与えられなかったとしたら、それは言葉が不自由なのではなく、人間の精神が不自由ということなのだ。
言葉に具体的なひとつ意味を結びつけそれを固定させたら、どのように表現の世界が混乱するか、次の例で示したい。yet という単語かある。
これは学校の授業では、まだ、とか場合によっては、もう、とかという訳が当てられる。それは表現されている内容によってそう訳されるのだが。
これは非常にまどろっこしい、いらいらさせる。この場合こういうことを表現しているのだからこれは、まだ、と訳し、この場合はこういうことを表現しているのだから、もう、と訳すとか、もう頭が痛くなりそう、だった。
これは英単語に無理やり日本語の訳を当てはめた為に起こった混乱である。英語を話す人は yet に二つの日本語訳が当てられるなんて考えもしないだろうに。
そうなのだ。英語を話す人は、このような具体的な意味ではなく、もっと漠然とした抽象的な意味をこの yet に込めながら話しているのである。
つまり、少し感情的な強調をこめて
「この今までの時間内において」
という抽象的な意味をこめてである。
それで、もし、その事柄が
「この今までの時間内において」
成し遂げられていたら、yet は
「もう」
という日本語の意味を持つのであり、その事柄が
「この今までの時間内において」
成し遂げられていなかったら、それは
「まだ」
という日本語の意味を持つのである。
以上の事から結論めいた事を言うと、英語を聞いて訳そうとするとやはりどうしてもその単語の文字が目の前にちらつき邪魔くさい。
その様に勉強させられてきたのだから仕方がない。それから抜け出すには相手の言う事を直感的に理解出来るようにしなければならないのだが、それがけっこう難しい。
次に四番目の
「日本語を英語に訳すな」
ということであるが、何か言いたいことがあり、それをまず日本語で頭に思い浮かべそれを英語の文にしてから言葉として発するという事はいかにもまどろっこしい。
私たちは日本語を発するときでさえ、話す前にいちいち日本語の文字を思い浮かべ、それから話すなどというそんな遠まわりなことはしていない。
英語を聞いて直接的に相手の言いたい事を理解するように、言いたい事を直接的に英語で表現することが言葉の本質的役割であり機能である。
その詳しい理由は前に述べた事がだいたい当てはまるのでここでは省略する。
次に五番目の
「文法を覚えるな」
ということであるが、わたしたちは前に述べたように、わたしたちは、わたしたちの体に起こっている事を抽象し分析し、それがどのように起こっているかを意味として取り出し、それを言葉で表現し、さらにそれを情報として他者に伝えても、その人がその情報を元にしてその情報をつたえた人と同じことを自分の体に起こすことは出来ないということを、そのような情報は、体から脳へ、そして言葉を介して他人の脳へと伝わるが、その脳から体へは伝わらないということ、つまり不可逆的であると云うことをすでに知っている。
この事は、スポーツや伝統芸能、その他の様々な行為者によって、知り尽くされ言い古されてきた事なのである。
なぜそうなのかは、生物の進化と、その脳の発達過程を見れば充分に説明がつくので、省略する事にする。
これを言葉に当てはめればこういうことになるだろう。
表現したいという思いや感情があって言葉で表現されたものを、その何かを表現されたものして受け取る限りにおいて、その表現されたものは言葉本来の持つみずみずしい生命力に満たされているのだが、それがどのような構造をしているか、抽象し分析し調べて様々な文法用語で体系的に合理的にまとめたものを知識として覚えても、そこからは言葉の持つみずみずしい生命力は失われており、その表現されたものを再現することにはほとんど役に立たないということ。
いや、むしろそのような知識は再現することに妨げとなるであろう。
わたしたちは表現されたものを耳にするとき、動詞はこの位置にあるから形容詞はこの順番にあるからこの表現された文は文法にあっているなどとは決して意識しない。
それは話すときでも同じである。
わたしたちが表現されたものを耳で聞いて理解し、そしてそれに応えるように言葉を発するということには直接的な肉体的音声的なメカニズムが働いているのである。
そこで私は前に出てきた言葉「内なる官僚主義」という言葉を用いて、それが誰の心にも巣食っているものであり、それが知識化された文法の弊害性とどのような関係にあるのかを説明したいと思う。
官僚がいて、国家というものがどのように成立し構成され運営されているかについて考え分析し、その結果として最適と思われる管理方法や仕組みが考えられ、そしてその役割を担うのであるが。ところが、いつのまにかに、官僚たちはその能力でもって自分たちが国家を管理し支配しているものと、または支配できるものと錯覚するのである。
つまり単に物事を抽象し分析する能力でしかないものを現実的な支配管理能力と勘違いしてしまうのである。
言葉においても、文法というものが言葉というものを管理支配しているものと思い込み、文法さえ覚えていれば言葉は話せるようになると錯覚する事である。
文法によって言葉という現象が起こり、文法によってことばが自由自在に話せるようになると思い込むのである。
とんでもない勘違いである。
というのも、言葉というものは、長い間の肉体的感覚的経験を経て、人々との相互関係からどうしようもなく生まれてきた表現したいという思いや感情を、漠然とした時間的空間的広がりの意識のもとで、微妙な感情を表現するために音声の強弱やその合理性の制約を受けながら、現実的に音としての言葉を発するのである。
それはあくまでも経験的なものでしかないのである。
わたしたちはある行為ををやろうとして、それに関する情報を元にしてやろうとしても体は動かない。
実際にそれと似たような事をやってみて違いを知り、それを修正して再度やってみて、そして再び違いを知り、それを修正して、というように何度も繰り返してやってみながら、その本来の形にあわせるようにして、自分なりに完成体に近づけていくしかないのである。
この情報が文法であるならば、私たちがしゃべるということは行為であるのであるから。このことは話すことにも当てはまるのである。
私たちはある行為をその行為に関する言葉だけの情報で再現しようとするとき、それはかなり困難である事は前述で知った。
それはその行為をするためには無限に近い情報を必要とするからであるが、そのことは言葉を発するときにも当てはまる。だが実際にはわたしたちはそんなことはやっていない、いや、やってられない。
わたしたちはまず言葉を聞いて、それと同じ様に発してみて、違う所を修正しては、また発して、という様に繰り返し繰り返し修正しながらだんだんとその完成体に近づけていくという、どうやらわたしたち肉体に生まれつき備わっていると思われるその自動性に任せている次第なのである。
そのことをわたしたちは幼児のときから無意識的にやっている。
その母と幼な児との一対一の充足した関係性において。
そこには人間が言葉を覚えていく初期の様子を見る事が出来る。幼な児は声を音節として発する事を覚え、そして母親の真似をして単語としての言葉を発するようになる。それは喜びであり楽しい事であり、必要に迫られている事であるから。
その発する事が母親の表情を曇らせたら、幼な児は言い換えて母親の希望に添うように修正する。そしてその様なことを時間をかけてくり返しやっているうちに、発することのできる単語は増えていき、やがてフレーズや短い文まで発する事が出来るようになる。
このとき幼な児は、単語を覚えたときのようにフレーズや文を声に出して修正しながら覚えていく。つまり身につけていく。その後は時間と共に単語の数はさらに増えていき、文も長くなり内容も複雑になっていくだけである。その過程はすべて無意識的である。
言葉を覚えようとして覚えるのではない、話そうとして話すのでもない。自動的であり本能的であり、実践的必要性に迫られたものである。
そこには知識としての文法など入り込む余地はない。その後文字を覚え多少の文法じみたものを教え込まれて表現する内容が豊かになり文が複雑になっても本質的には変わりはない。
このように幼な児にもまたその母親にも文法などというものはまったく意識にない、それなのに幼な児たちは言葉を身に付けていく。
これで如何に文法というものは役にたたないものであることが判るであろう。そんな物は私なんかよりずっと賢い学者先生に任せておけばいいのである。このように言葉というものは母と子の現実的実践的な関係性において身につけていくものである事が判る。
これから述べる例は言葉とは直接関係ないが、もし、今まさに歩み始めようとしている幼な児に向かって、母親が歩き方の法則を言い続けたら、つまり、まず右足を出して、次に左足をだして、また右、そして左、そのとき脚と反対の側の手を交互に前に出すのよ、などと、これは大切な法則ということでうるさく厳しく言い続けたら、きっと幼な児はノイローゼになって歩けなくなってしまうだろう。
そんなバカな母親はどこにもいない。
私たちが言葉を発するとき、頭のハードディスクに単語として記憶されているものを、なにかを表現したいという思いにかられたときに、いちいちそこから文法に合わせて取り出して言葉を並べ、それを文として声にして発するのではないことは、すでに述べた。
(いや、この世の中には実際にそういうことをやっている、私なんかよりもずっと賢い人がいるかもしれないが、たぶん稀でしょうからここでは言及しないことにする)
前に述べたように、私たちが何か表現したいという思いにかられて言葉で表現しようとするとき、文法を意識しないだけでなく、文字としての、形としてのはっきりとした言葉のイメージもない。
なんとなくあるようだがハッキリしない。
それは決して手にとるように具体的なものではない。
限りなく影のようである。もしかしたらそれは限りなく純化され単純化され電気信号として送るときには最も都合の良いものになっているかもしれない。
私はこのことから、言葉で何かを表現するときには、文法や文字には影響されない、それらからはまったく独立した本能的自動的なメカニズムが人間の体には生まれつき備わっていると考えざるを得ない。
私たちのほとんどはある行為を、たとえば自転車に乗ることとかスポーツが出来るようになるためには、その事をくり返し練習すれば身に付くことを経験的に知っている。それは言葉を発するという行為にも当てはまることである。
幼な児はそのことを母親の前で屋って言葉を身に間つけている。
わたしはここで大胆な仮説を立てざるを得ない。
つまり行為として繰り返されることによって、肉体に刻み込まれるように記録される記憶があると云うことを。
その記憶のことをこれからは肉体の記憶と呼ぶことにする。
私は其のことに関してこれ以上詳しく言うことは出来ないが、言葉はその働きによって発展し話され続けていることは間違いない。
というのもその肉体の記憶は経験を積むことによって時間と共により多くのものを取り入れてますます複雑なものを受け入れることが出来るシステムになっているから。
このことは神経科学的に言えば、電気信号が通る回路がますます複雑で多元多相的なものになっていると云うことに行きつくのであろうが、わたしがそれについて言及することは私の能力の限界をはるかに超えている。
わたしは以上のことを踏まえて、さらにもっと大胆な仮説を立ててみることにする。
もしかすると、その母の前の幼な児
(この世に赤ちゃんとして生まれたすべての人間の子供)
は誰かが言ったことをそのまま復誦できる能力を生まれながらにして持っているのではないか。
そして、それは、鳥のように本能的ではなく、人間の進化の過程で獲得したものであり、少しの時間と練習によって、鳥以上にその能力を発揮するものであるが、そのおかげで、幼な児は言葉を覚え会話能力を見につけていき、それこそが、その後の言語能力の発達の基本となっているのではないか。 幼な児はその生まれつき持っている能力を発揮して、まず母親が言った事と同じ事を言ってみる、そしてそのことばが母親との相互関係で、何かを意味し、何かを指示しているのかが、だんだんと判ってくる。
と同時にそのことは肉体のの無意識的な記憶装置に記憶される。復誦できる単語は増え、単語からフレーズ、フレーズから短い文へと発展していき、それはさらに記憶され、つまり、その思いが頭に浮かぶときはいつでも復誦出来るようになり、そしてその復誦できる文の単語を別の単語で置き換えることによって意味が変わることを知ると同時に、自分の様々な思いを表現できることを知るようになり、やがて、その表現されることは声に出して言えるという条件のもとでますます複雑で豊かになっていくのではないか。このことは長い間の思考を経て考え出された複雑で抽象的な内容が表現されるときには当てはまらないかも知れないが、言葉を覚える初期の段階、そしてその後のすべての言語活動の基本になっていることは間違いない。
もしこの復誦できる能力がわたしたちの言語活動の基本となっているとするならば、前に述べた疑問も解決することになる。子供が大人よりも早く外国語を身につけるということ。
これは子供は何も考えずに遊びのように楽しく素直に誰かが言ったことを反復できるからである。大人はプライドや既成概念が邪魔をしてそこまで素直にはなれない。
その次は、誰かが行っていることを反復できない様なら聞くことはなんかうまく行かないこと。わたしは前にそのことは聞く事と話すことは同じ神経を共同で使っているではないかと比ゆ的に言ってみたが。
それはそのくらい密接な関係にあると云うことを言おうとしたのだが、これは、もし言語活動が聞くことによってではなく、話すことによってより支えられているとするなら、その二つの関係が密接であるということには納得がいく。
だが現在わたしたちの教育現場で行われていることはどうだろう、本当は受験のためなのだが学力を上げるという名目のために、聞くことはおろか話すことさえしない授業が行われている。たえず苦手意識を植付け劣等感にさいなまれる若者たちを生み出しながら。
それをやっている所もあるがお飾り程度である。本当はその配分を逆転しなければならないのに。文法は言語活動の基本ではない、それはその発達を妨げるだけである。
ところが、どのテレビ番組
(ラジオ番組はほとんど問題はない。筆者がお世話になっているから)
を見ても文法が花盛りである。
わたしたちはそのような教育から決別しなければならない。
言語活動の基本は声に出して話すということにあるのだから。
幼な児はその母の前で話すことは喜びであり楽しいことであるようにして言葉を身に付けていく、鳥たちは歌うようにして人間の言葉を覚えて歌うようにしゃべる、子供たちは遊ぶようにしてその外国語を復誦しながら覚えていく。
そこにはいつも生命力と躍動感が満ちあふれている。
本来言語というものはこのように楽しみながら身につけていくものなのだ。だからそこのは文法など入り込む余地は少しもない。
もし子供たちの英語教育がそのような環境のもとで行われたら、どんなにすばらしいことだろう。
言語における文法というものは、音楽における楽譜や音楽記号や作曲方法であり、人間の体においては、骨格や血管の構造や器官の配置のようなものだろう。
楽譜や音楽記号や作曲方法を知らなくても、歌を覚え、歌を作り、歌を歌い、歌を楽しむことができる。
人間を知るのに相手の骨格や血管の構造をまったく知らなくても、充分に相手のことを知ることができ、コミュニケーションになに不自由ない。
では本当に文法は役に立たないのか、わたしは思わず黙ってしまう。
なぜなら、わたしは日本語を話すときにはまったくと言って良いほど文法などというものが頭にないからだ。
もしあるとしたならそれは無意識的にで、日本語の場合だったら、最後に結論めいたものを言いたいためにそれに合わせるかにようにして内容を豊富にしながら言葉を連ねていくと云うか、英語の場合だったら、最初に結論めいたものを言って、それにくっつけるかのようにして内容を豊富にしながら言葉を連ねていくと云うか、その程度のことだろう。
でも文法を発見するために費やされる能力や労力のことを思うと頭が下がる。
それも人間に備わっている大切な才能のひとつなのだから。
わたしは前にも述べたが言葉は思いや感情を表現するための手段であり、あくまでも借り物であり、一度表現したものからは、人間の心は束縛されない。
心は常に自由であり、変化していくものであるから。
だから言葉に影のように寄り添っている文法などというものにも縛られることはない。
文法は人間の自由性に従属して、後から付き従ってくるもので、その自由性は決して言葉をゆがめることはない。
むしろ言葉を新たな可能性へと開放する。
時制、冠詞、不定詞、現在完了、仮定法、いまだに何の事やらさっぱり判らない、なぜわたしたちは日本語をしゃべるときそんな事をまったく意識しなくてもしゃべれるのだろう。
とても不思議だ。
それでは次に六番目の
「文字を覚えるな」
と七番目の「文字を書くな。」ということであるが、これは今まで述べてきたことからもわかるように、言葉を話せるようになっていく過程において、文字は何の役割も果たしていない。
文字はあくまでも知識や情報を広く遠く、そして後世の人々に伝えたり、また、それによって生きていくために必要なより多くの知識や情報を得るために手段に過ぎない。
そしてそれは受験勉強には大いに役立つ。
でも、会話能力とは本質的に関係がない。
だから少なくとも英語を学ぼうとするときには文字を書いたりして覚えないほうが良い。
なぜなら、文字を覚えることは正確に言葉を発することよりも比較的簡単なので、文字を覚えることに重点をおくようになり、それで英語を身につけたかのように錯覚して、最も大切な話すことによって言語能力を高めようとすることがおろそかになるから。
人はたとえそれが子供であっても「内なる官僚主義」に陥りやすい。
ではここで、受験勉強は会話力を身につける上でなんの役にも立たないという主張に対して、いや大いに役立つと主張する人の話をはさみたいと思う。
その高名な英語学者は日本での優秀な成績を引っさげて意気揚揚とアメリカに行ったそうだ。こんなにも英語の知識があるのだから絶対に会話には不自由しないはずだと。
ところが自分の話すことはまったく通じなくコミュニケーションもままならなかったそうだ。
そんな状態が二年間ぐらい続いたある日、突然のようにぺらぺらと英語がしゃべれるようになったそうだ。
周囲の人たちは突然英語がしゃべれるようになっただけでなく、その英語に関する知識の豊富さにびっくりしたそうだ。
それもみな受験勉強のおかげだとその偉大な英語学者は言った。
でもそれは偉大な錯誤である。なぜなら、コミュニケーションはその言語に関する知識がまったくなくでもすぐ出来るから。
二年も住んでいれば誰だってぺらぺらとしゃべれるようになる。
あの不法就労者たちは二三週間で仕事に差し支えないくらいにしゃべれるようになっていた。
では次に八番目の
「日本人に習うな」
ということであるが、この場合の日本人とは、ネイティブのように話す日本人のことではなく、文部科学省の方針に従っている日本の学校で真面目にひたむきに勉強をしてきて日本語のように英語を話す優秀な先生たちのことである。
これは主に発音上のというよりも発声上の問題であるが。
発音はたんにその単語を正確に発音していれば良いという様なものではなく、言葉のつながりや前後の関係、そしてそこに表現される内容を豊かにするために、アクセントや強弱や抑揚によって影響される、もっと複雑で総合的なものである。
それは発声器官の合理性に支えられて、その言語のもつ特有のリズムと発声に制約されている。ネイティブな発声もしらずに日本語を読むようにして学んできた人たちには、その技能は備わってはいない。
英語をネイティブにように話すということが最も大事だというのに。世の中には、ネイティブのように発音が出来ないなら発音できなくても良いと言う人がいるが、これは受験勉強の悪弊から来る詭弁である。
特殊な場合を除いて人間は誰でも外国語の発音が出来るのである。その言語のもつ発声器官の合理性に従うことが会話能力を身につける最速の早道である。
子供たちを見れば判る、みんな適応しているではないか、だから覚えが早いのである。
(もちろん筆者は年齢上の問題と訓練不足でまだそこまで行っていない。でも真面目に訓練を続けていけば、いつかはそれに近づけるものと信じている。)
もし英語を日本人のように話す人から学んで、英語を日本語のように話すことが身についたら、その後の会話能力の進歩はおぼつかなくなるであろう。
わたしは今ラジオの英語番組のお世話になっているが、その先生方はみんな、頭が良さそうで誠実で、学校では真面目に勉強して大変優秀な学生さんだったに違いないと思われる方たちばかりのようです。
というのも、まだ会話能力が幼稚園児並みのわたしでも、生意気にも、先生方の発音が、ネイティブの人より聞き取りにくいなあと、時折感じることがあるからです。
わたしが聞きにくいならおそらくネイティブの人にとってもおそらく聞きにくいものに違いありません。
たぶん学生時代にあまりにも一生懸命学校の勉強をしたから、日本語のようにしゃべる癖が身についたのでしょうね。あんなにも優秀な方たちなのにとても残念です。
これで、なぜ相撲取りや、かつて一緒に働いていた不法就労者たちが自由に日本語が話せたのかわかるような気がします。
その次は九番目の
「英語を読むな」
ということであるが、この読むということは、学校の授業で、リーディングと称して日本語のように英語を読むことである。
これによる弊害は前の
「日本人に習うな」
というところで詳しく述べたのでここでは省略する。
では次に十番目の
「発音記号を覚えるな」
と十一番目の
「アクセントの位置を覚えるな」
ということであるが、ほんともう、これは嫌だった。
今思い出すだけで頭が痛くなりそう。
こんなもの覚えていったいなんになるんだと思いながらも、テストの点数を上げたいがために必死で覚えようとしたが、結果につながらず放棄。今もこんなばかげたことをやっているかどうかは知らないが、とにかく無意味無駄時間の浪費、青春の空費、英語に対する拒絶反応を起こさせるだけ。
今まで何度も述べてきたが、覚えれば覚えるほど会話能力を身につける上で妨げとなるだろう。
それでは次に十二番目の
「畳の上で勉強するな」
ということだが、この
「畳の上で」
とは日本的な環境や雰囲気のもとでという意味で、最初の
「机に坐って、、、、」
で述べた内容とは基本的には変わらない。ですから
「日本人に習うな」
の所で述べた事を含めて今まで述べてきた事のすべてがほとんど当てはまる。
語学の基本は勉強ではなく体験である。
日本的な環境や雰囲気のもとだとどうしても日本語をしゃべる延長線上で英語に対しそうとする。 これだといくら相手がネイティブの人でも日本語のリズムや発声に影響されて、その言語にとって最も重要な部分となっていると発音や表情や身振りを含めた総合的な表現が発揮されないであろう。
それでは語学はいつまで立っても身につかない。
英語は日本語とはまったく異なった体系化にある体験なのである。
頭で知識情報を処理することではない。
そのためには日本的環境や雰囲気から出来るだけ遠ざかったほうがよい。
では最後の
「お金をたくさんかけて英語を習うな」
ということであるが。
英語を母語とする人について学ぶことはとても良い事なのだが、そのために年間何万何十万もお金をかけるのはもったいない、わたしがやっている方法を採用すれば一ヶ月わずか缶ジュース一本分のお金で済むのだから。
とかく私たちはある目的のためにお金を掛ければそれで目的が達成したかのように思い込む悪い癖がある。
たとえば、新しい教科書を手にするだけで、勉強が出来たかのように思い込むこと、新しいパソコンを手に入れるだけで時代の最先端を行っているかのように思いこむこと、そして美しい嫁さんをもらえば、それだけで幸せになれたかのように思いこむことなどなど。
とにかく語学を身につけることは努力を必要とするひたむきな訓練であるからくれぐれもお金をかけることが目的とならないでほしい。
それではその方法となるものはいったいどういうものなのか、ということになるのだが、わたしはそのことに関して、いままではほのめかす程度にしておいて、直接的にはあまり触れてこなかった。 というのもその方法というのはあまりにも単純でばかばかしく、しかも誰にもすぐ実行できるようなありふれたものなので、それを知れば、ある者は、なあんだそんなことか、もう判っているよと言って、またある者は思わず吹き出しながらこの小論を読むのを止めると思ったからです。
では、その方法ですが、それはラジオの語学番組でながされている英文をテープにとってくり返し何度も聞くというものです。
わたしがこの方法をはじめる前まで、ずっと思っていたこと、それは、なんだかんだ言っても結局は何を言っているのか聞き取れないということが、語学を身につける上で最大の問題だということでした。
それには英語に関するどんなに膨大な知識もなんの役にも立たないことにも薄々気付いていました。
その一方では、勉強した比重がそれほど変わらないのに直感的に反応できる英語のフレーズがあることにも気付いていました。
そういうものは何度も耳にするフレーズであることに気付いていました。
そこで次のような結論に達するのは当然のことだったのです。
「何を言っているか判らなければ判るまで何度もくり返し聞けば良いではないか」
と。
そう言えば最初は判らなかったクラシック音楽もそのうちにわかるようになったし、しゃべり方が早くて聞き取れなかった都会人の言葉もそのうちに判るようになったのだからと。
この方法をはじめる前はこの程度の考えしかありませんでした。
ですから今まで述べてきたことはすべて後付けです。
この方法をやり始めたとき、最初は確信がありませんでした。
でも、すぐに成果が見られました。あとはもう病み付きです。
それ以来毎日欠かさずやっています。
英語依存症にかかったようです。
どうやら依存症というのは頭を使うからではなく体を使うからかかるようです。
もちろん最初は文字を、テキストを見ました。
(これはこの小論の主張に反するかもしれませんが)
とにかく何を言っているのかまったく聞き取れなかったものですから。
そして徐々にテキストが不必要になりました。
これらの過程をたとえて見ればこの様になるでしょうか。
この方法を始める前までは、英語に対する私の脳みその感受性は、カチカチのレンガのような状態にあったと思います。
それにいきなり激しい刺激
(たとえばあまり日常的でない文を聞き取らせようとして拒絶反応を起こさせ昔のように挫折に導くこと)
を与えるとレンガが粉々に砕けそうな気がしたので、優しくなでるような刺激
(日常的な平易な文)
を与えて徐々に豆腐のようにやわらかくて柔軟性を持ったものにしようとしたのです。
それが見事成功したようでした。今の日常的な英会話番組においてテキストが必要ない状態は、そのカチカチのレンガから、凍り豆腐をへて、木綿豆腐になりかかろうとするあたりでしょうか。わたしはその木綿豆腐の状態からさらに進めて絹ごし豆腐、そしてあのプリプリとした卵豆腐のようにしたいのですが、まあ、年齢的にも時間的にもたぶん無理でしょうね。
わたしのやっている方法を知って、ほとんどの人は、なんて地味な、退屈な、夢のない方法なんだろう、そんなことはもう知っている。
ここまで読んで来て損をした、と思っていることでしょう。でもこれこそは実際に効果があるのです。おかげでわたしは、英語に対する拒絶反応がなくなっただけでなく、自分には才能がないなどと劣等感にさいなまれることもなくなりました。
かつて自分が英語が出来なかったのは頭が悪かったからではなくその勉強方法が悪かったからだということで。
おそらくそんなことはもう知っていると冷ややかに思った人は、知識として知っていたか、多少試みたが成果は得られなかったという方たちなのでしょう。
というのも、そのテープで何度も繰り返して聞くというわたしのやり方は、執拗で度を越しているからです。
同じ単語やフレーズや文を何十回もくり返し繰り返し納得が行くまで、カセットテープレコーダーが壊れてもかまわないというくらいに連続して聞き続けるのです。
その様子を他の人が見たらきっと頭が変になったと思うでしょう。
人には見せられません。
そういう事を何日もやってようやく一つの単語やフレーズや文が物になったと実感するのです。おそらくわたしのようなやり方をした人は他にはいないと思います。
私のやり方の良い点は、何度も繰り返して聴く相手が現実のネイティブの人なら不可能だということです。
まさか十回も二十回も連続して同じ事を言ってくれなんて頼めませんからね。
ところで、最初この方法を始める前までは話す事は出来なくても、せめて聞き取る事くらいは出来たらなあと思っていました。
というのもカセットテープを聞くだけで正確に話す事なんか身につくはずはないと思い込んでいましたから。
だから最初はとにかく聞くだけにしていました。
ところが、だんだん時が経つにつれて、くり返し聞いているというだけなのに、より正確な発音でしゃべれる様になっている事に気がつきました。そしてやがて、くり返しはなすことがくり返し聞く事と同じように聞く能力の発達に重要な役割を果たしている事に気がつきました。
それは、前に少しも述べましたが、それは聞く事と話す事の密接な相関関係の発見でした。
そこでわたしは聞くだけでなく話すことも積極的に繰り返してやるようにしました。
効果はてきめんでした。
おそらく十倍ぐらいのスピードで、聞くだけのときよりも聴く能力の発達をうながしたようにわたしは感じました。
これらのことをもう少し詳しく言うとこういうことになるでしょうか。
わたしたちは言葉を耳にするとき、その音を頭で反復しているように思えるのです。
反復しながらその意味を感じてっているように思えるのです。
そしてなんとなく舌も動いているというか、動き出したがっている様な気がするのです。
わたしはその事を前に聞く事と話すことは同じ神経を共同で使っているのではないかと非科学的な表現をしてみました。
それほど二つは密接な関係にあると云うことを言いたかったわけです。
どうやら、聞くことは話すことを活性化させ、話す事を聞くことを活性化させていることは確かなようです。
特にしゃべる事はその作用が強く、そこで、もし、その意味をあまりよく理解していなくても、積極的にしゃべっていたらわたしたちの言語空間なるものは安定したものになり、わたしたちの言語に対する感受性の発達に役立つのではないか。
余談になりますが、わたしは今中国語を学んでいます。
始める前、韓国語にしようか中国語にしようか迷いました。
韓国語は未知の文字を覚えなければならないが、中国語は漢字だから、これは楽だということで、中国語をやり始めたわけですが、思わぬ障害にぶつかりました。
四声という奴です。
文法などは少しも気にはならなかったのですが、四声が重要だ重要だと何度もいわれると、そうかなあ、覚えなければいけけないのかな、と思い、なんとか覚えようとするのですが、とても無理、挫折しかかりました。
どうやらわたしはかつて英語を勉強し始めたときのように、知らず知らずのうちに内なる官僚主義に毒されていたようです。
そんな事は覚える必要はないのです、くり返し聞けばそれで良いのです。
おそらく中国人だってそんなものは覚えていないでしょうし、そんなものを意識して発音してはいないでしょう。少しぐらい間違っていても通じるはずです。
もし間違っていたらそのつど実践的に直して行けばいいのです。
中国語の発音に関して、ある高名な先生はこんな事を話していました。
「もし、十年前に、その発音の微妙な違いのことを教えてくれていたら、その発音の違いがわかり正確に発音ができるようになるまでに、十年もかからなかったでしょう。」
と。
これは錯誤だと思います。
おそらくそのことを知識として教えられても、正確に発音して聞き取れるようになる事には役立たなかったでしょう。発音は実践的なもので時間がかかるものなのです。
たぶん、その先生は十年間、中国語に慣れ親しみ、勉強する事によって、ようやく正確に聴くこともや話すことが出来たということでしょう。
つまり身についたということです。
わたしは話すことは、声帯とロと舌でやるダンスだと思っています、ダンスは練習によってしかうまくならないように、話すことは話すことによってしかうまくならないのです。
どうでしたか目からうろこ体験になったでしょうか。
いや、目からうろこ体験はわたしの方のようです。
わたしがこれまで何日にもわたる時間と労力をさいて述べたきたことは、すでに次のようなことわざで簡潔に語られているからです。
「習うより慣れろ。」
と。
プラクティス メイクス パーフェクト なんという先人たちの素晴らしき知恵でしょう。
最後に、貴重な時間を割いてここまで付き合ってくれた読者の皆さんにこんなことをいうのも恐縮ですが。
私はこれまでに述べてきたことが間違っていたとしても、それはそれでかまわないと思っています。つまり私よりもはるかに優秀な人の反論によって、または、後世の科学的検証によって、私の考えが根底から覆されても。
なぜなら、私が成果を上げているのは理論や考えからではなく、一つの実践からだからです。
人間は考える事とやる事が一致しなくても別にかまわないのです、所詮そういうものだからです。私がすばらしい反論や批判をうらやみ意地になって私の考えに固執する様なら、それこそわたし自身が「内なる官僚主儀」に蝕まれている証拠でしょう。
むしろ私はここに述べられている事が積極的に書き換えられることを望む。もし私がここに書かれていることが、私が行っている方法よりも大切だと思い守ろうとするなら、この小論は有害図書として、図書館や本屋や家庭の本棚に収まっている膨大な数の文法書や参考書と一緒に廃棄されなければならない。だからこの小論から実践の方法が判った方は二度と読まないことをお勧めします。
それから断っておきますが、この方法はあくまでも私のように頭が悪いというか覚えが悪い者だけのための方法です。
わたしたちの社会にはとてつもなく頭が良い方がいらっしゃいますから、その中には言いたいことをパソコンのようなスピードと正確さで日本語の文字として思い浮かべ、それを英語の文字に変換し、それを声に出して話し、そして聞くときもそれと逆のことを一瞬にしておこなって、会話を成立させることが出来るという方がいらっしゃっても不思議ではあるません。
そういう方は、決して私の方法を真似しないほうが良いでしょう。まあ私には関係のない世界のことですけどね。
でもこれだけは言っておきたい。
受験勉強を百年勉強しても英語を話すことは出来ませんが、私のやっている方法を十年やれば英語を話せるようになるだけではなく、半分ぐらいは受験にも役立つでしょう。
わたしのやっている方法というのはとにかく地味で格好悪いです。
時間も毎日一時間から二時間はかけなればなりません。
それ位やらないと成果はあがってこないのです。
(でも、成果を実感すると、それからはとても楽しくなるだけなのですが)
というのも、この方法による上達の程度というのは、頭のハードディスクに機械的に記憶する受験勉強と違って、絶対的時間量に比例する様なのです。
時間をかければかけるほど上達するということです。
このことはすべての人に当てはまるといっても良いでしょう。
それは頭のハードディスクは人によって大きな容量差はありますが、人間の肉体的感覚的感受性にはそれほど差がないからです。
かといって、それは受験勉強のように短時間で成果が見られるというようなものでは決してないのです。
牛歩のようにゆっくりゆっくりと上達していくものなのです。
<受験英語をしっかりやっている者なら誰でも数行ほどの英文を見せられれば、それを十分ほどで意味を理解し暗記し、さらに後にそれを書いて再現して見せることも出来るでしょう。
つまりテストには充分だと言うことです。
ところがわたしの方法というのは、その数行の英文を聞いて理解し話せるようになるには何日も何ヶ月も、いや人によっては何年もかかるかもしれないということです。
それ位時間をかけて地道に、しかも集中してやらないと進歩がみられないものなのです。
なにせ、レンガのようなカチカチの脳みそをやわらかい豆腐のようにするという一種の肉体改造をおこなっている様なものですから。
おそらく受験勉強の達人は、英単語などは数秒で覚え、つまり暗記し、それをしばらくは、少なくとも十年くらいは紙に書いて見せることは出来るでしょう。
でも、わたしの方法で覚えるということは、その単語または文を聞き取ることが出来それを話すことが出来るということです。聞き取れなければ聞き取れるまで聞かなければなりませんし、話なければ話せるまで話す訓練をしなければならないということです。
ですから時間が何日も何ヶ月もかかるのです。
だからもし運動機能が鈍かったり衰えていたりするとその時間は人よりさらにかかるということです。それが人によっては何年もかかるという意味です。
でもわたしの方法は一度覚えたら一生忘れないと思いますが。
最後に。私がこの暴論を書いたのは決してかつて苦しめられた英語教師たちに対する復讐心から、彼らの存在価値や名誉を傷つけようと思ったからではない。
様々な状況で生きることに迷い悩む多くの若者たちが、本来はもっと自由で伸び伸びとし可能性を許容すべき教育の現場においても、特に英語教育においては、間違った教育をおしつけられ、既得権益にしがみつく膨大な数のパラサイタ-や内なる官僚主義者の保身や金儲けの犠牲なり、もがき苦しんでいる姿を見るにしのびず、今現在わたしに出来る唯一の手段で、なんとかそこからだけは解放してあげたいと思ったからである。
何度も言うようだが、若者たちは難しい、出来るならば関わりたくない。
でも、若者たちは心のそこでは、大人たちの指導を助言を、そして寛容さを必要としている。わたしたちはわが身を細めてもそれに応えて行かなければならない。
それでは本当に最後に、英語を身につけるにはどのような方法が最も良いか、その良い順番に述べていく。
まず一番良いのは、外国に行って実際に職業などについて生きること。
言葉を覚えなければ職業に就けないので、いやがうえにも覚えざるを得ない。
二番目に良いのは、留学や遊学で行って短期間でも良いから滞在して、その国の人と積極的に触れ合うこと。
友達や好きな人が出来るのはより良い。
三番目に良いのは、英語学校に行ってネイティブの人と知り合うこと。
(金がかかりすぎるのは難点だが)
四番目に良いのは、日本にいて外国の人と知り合うこと。
もしかしたらこれは三番目よりは良いかもしれない。
五番目に良いのは、わたしがやっている方法を採用すること。
(これはわたしのような恥ずかしがりやな人間にとってはぴったりです)
最後に良いのは、つまり最悪なのは、従来通りに学校で受験勉強をすること。
わたしの方法を知った人は、そのやり方があまりにも単純で地味なのでおそらく誰も試みないような気がします。
でもぜひやって見てください。すぐ成果を実感できます。
病み付きになります。
依存症になればしめたもの。
それから注意ですが、この方法は、日本語とは違う聞き取り方や発声の仕方を身につけることですから、わたしたちの体が違う血液を受け付けないように英語に対する拒絶反応のようなものがおきます。でもそれは忍耐と頑張りと時間が解決してくれます。
それは脳が管轄する場所は日本語と英語は違うということなのでしょうか。
詳しいことは後世の人の研究に。
わたしは、ほとんどの学校の先生は、誠実で使命感にあふれ、若者たちの将来のことを考え、よりよい学校に入ってもらおうと日夜努力して、指導してきてくれていることを知っている。
だがその内容が、将来若者たちが生きていく上でどのように役に立つかは別のことだ。
この詳論で私は学校の英語教育は無意味だ役に立たないと言ったのだから、きっと全国の何十万という有能な学生思いの心やさしき英語の教師の皆さんや、その周りに群がる何百万という仕事熱心な関係者の皆さんの感情を害しプライドを傷つけたに違いありません。
人によっては怒りの炎を燃やし始めている人もいるに違いありません。
そのことはほんの少しばかり申し訳ないなと思っています。
でもそれと真実は別です。
なぜか大人たちは本当のことを言おうとしません。
でもわたしは言います。
最後の最後に、ほんとの最後に、ダンスは練習することによってしか上達しないように、聞くことは聞くことによってしか上達しないし、話すことは話すことによってしか上達しない。
言葉の持つ高度な知識蓄積能力や情報伝達能力は副次的なものであり、本質は会話にある。その始めは我が子を慈しむ母親とその母を神のように信頼する子供の絆にある。
本当のことを言うと世界を凍らせるそうだ。
でもわたしの場合正気を失っていくようだ。
[追記Ⅰ]
私たちは、人間に生まれつき備わっている内的合理性をただひたすら信じるしかない。
その働きは、日本語と英語では文法において対照的な形で現れているが本質的には同じものである。
英語は、最初の結論に意味や修飾を加えていくという方法である。
それに対して、日本語は最後の結論に向かって、意味や修飾を加えていくという方法である。
これらは一見すると、矛盾していて、どちらかが非合理的に見えるかもしれない。
でも、どちらもそれぞれに合理的なのである。
このことからすると、この二つの言語は統合や融合などというものは決して起こりえないだろう。
なぜなら、これら言語を支配している内的合理性が、そのことを原理的に妨げることになるだろうからである。
だから、もしかすると、その文法の違いから、日本人は英語が苦手だということは、迷信となるかもしれない。
というのも、私たち日本人が、その文法の違いにこだわろうがこだわるまいが、その内的合理性が、そんな違いを飛び越えて、私たちを、本能的に、自然的に、英語を聞き分け話せるように導いてくれるにちがいないからである。
[追記Ⅱ]
この小論を書いたときは、利用できる機器としては、まだカセットテープレコーダーだけでしたが、現在は、専用の機器だけでなく、パソコンや電子辞書もあるので、それらの音声くり返し機能によって十分に利用出来ると考えられます。
[追記Ⅲ]
テレビコマーシャルの《スピードラーニング》は、その上達の根拠の真偽は定かでないとしても、実践的にはなんら問題のない方法だと思います。
でも、少し付け加えるなら、学習者が漫然と《聞き流す》というだけではなく、主体的に、意欲的に、聞こうとすれば、もっと上達が早まると思います。
[追記Ⅳ]
この《FC2文学》に投稿しておられる《貢献そして感動》さんの中国語を身につける方法、最近知りました。アプローチの仕方が私とはちょっと違うようですが、目指すところは同じような気がします。いや、わたしよりも深く根源的で、より実践的な方法のように思われます。