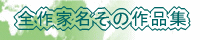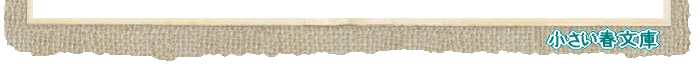私は弘美からこれ以上離されるのを恐れるかのように、必死に後を追った。
きっと、私があげていた、あの子供のような情けない声を聞かれたに違いないと思いながらも。
そのとき私の脚は、それまでと違い思い通りに動くようになっていた。
* * * * * * * * * * * * * * * * *
稲光
はだい悠
* * * * * * * * * * * * * * * * *
数年ぶりに私は故郷に帰ってきた。
三十才を過ぎた私に対して、家族や親戚のものが、今どこで何をしているのかを、少しも訊ねようとしないのは、私にとっては最大の歓迎だった。
家族や親戚の者は、この前来たときと変わることなく元気である。
そして、いつも素朴で屈託がない。
それは、私にとっては、本来、とても喜ばしてことのはずなのだが、いつも私を不思議な気持ちにさせ、血族であるのにもかかわらず、心から打ち解けない気持ちにさせる原因ともなっているのだ。
なぜなら、どんなに身近なものが私に好意を示してくれたとしても、わたしが十六のときに家を離れて以来、ずっともち続けている将来に対する漠然とした不安を、私から拭い去ることはできないからだ。
ましてや、無職でいまだ半人前という負い目を常に感じているからには。
そして密かに、穏やかで伸びやかな心を持った田舎の人たちに、畏敬にも似た羨ましさを感じ続けているからには。
私が帰って来てから風景は着実に変化していった。
周囲の森や雑木林は日毎にその緑を濃くし、まるで私の家だけが自然の中に孤立して存在してあるかのように、近所の家々を視界からさえぎりながら、ますます深く生い茂って行った。
そして、機械による田植えも終わった。
私は以前から、どんなに久しぶりに懐かしい故郷に帰ってきても、私を知っている近所の人たちの目に触れぬように、いつも目立たぬように行動していた。
私はずっと、胸を張って近所を出歩けるような立場にはないと思っているからである。
そして生活のリズムが自然に合わせたものになるにしたがって、わたしはだんだん退屈を感じるようになっていた。
そしてある晩、私は夕食後独り散歩に出た。
水を湛えて広がる水田は、水面に星空をかすかに映している。どこまで行っても暗がり。
周りに見えるのは我が家の灯りだけ。
そして、私ひとりだけ。
カエルが鳴いている。あっちこっちで。
うるさいくらいに。
文字通り合唱だ。
でも、わたしは平気だ。
田舎に住んだことのない者にとっては、このカエルの声はきっとうるさいに違いないのだが、わたしにとってはまったくといっていいほど気にならない。
たぶん子供の頃から聞きなれているからに違いない。
私は、むしろそこに静寂を感じ取る。
そして、私は必然的に、その静寂の背後に潜む、何百年、何千年と変わることなく続いているに違いない、大自然の営みに耳を傾けざるを得ないのだ。
遠くにその周囲よりも、ひときわ黒っぽく見えるところがある。
見事に成長した杉林だ。
子供の頃、父や兄と一緒にその苗を植えるのを手伝ったところだ。
あれからもう二十年以上経つのだ。
私はそこに、隙あれば、人間を排除し威圧し従属させるかのような大自然の密かな企みを感じざるを得ない。
そして人間の営みの小ささと、はかなさも。
突然襲う名状しがたい寂しさとともに。
この二十年、人々はめまぐるしく変化する社会を、その繁栄の証として受け入れることに、ようやく慣れてきた。
未来に対する多少の疑念や不安を抱きながらも、それが自分たちの幸せに通じる唯一の道であるかのように。
私もその例に漏れず、ただひたすら、商品のように送り出される大量の思想やイメージで頭をいっぱいに満たしながら、昼は都会の雑踏にもまれ、夜はまばゆい光に快楽を求めて生きてきた。
そして、その変化はすでに田舎にもやって来ていた。
五年前に帰ってきたとき、農協は統合されて大きく建て替えられ、役場も町の中心部へと移転されて現代的に建て替えられ、さらには、総合病院、幾多のスポーツ施設、自家用車のための道路、そして町民の文化水準を向上させたり、老人の健康や体力増進するための、ありとあらゆる公共施設が整備され、町は過去百年にもわたる変化をわずか数年で成し遂げていた。
人々はその生来の陽気さや暢気さに輪をかけたように、まるで人生の悩み事がすべて吹き飛んでしまったかのように楽天的になっていた。
だが、いまこうして暗闇のなかに独りたたずんでいると、そのようなことはほんの一時的なことだったかのように思えてならない。
それは、この前、来たときと、農村風景はさほど変わってないという印象を受けているからでもある。そのような、社会が発展し、生活が豊かになっているという高揚感は、毎年のように新たな建物が建ったりして、目に見える変化しているときに感じるものだからである。
自然は、人間がその発展や変化のスピードをやめると、その本性を表すということなのか。
いや違う、これは、人間社会が発展し豊かになり、人間が、あたかも自然を征服したかのように自惚れ傲慢になっても、自然はそんなことをまるで無視するかのように、 そして、私がどんなに都会生活の便利さや快適さに惑溺し、その一方では、洪水のように押し寄せる時代の観念と格闘しながら、そこから何か意味を見つけ出そうと、どんなに深く悩み、あえいでいようが、そんなことにはまったく関心がないかのように、ときおり冷酷とも思える相貌を見せながら、堅実で、静謐で、ひたむきな時間を自ら絶え間なく流し続けているからなのだ。
私はますます寂しくなった。
遠くに暖かそうにもれている、家の灯りが見える我が家へと急いだ。 歩きながら私は、昼間、何かの用事で来ていた従兄弟の和子が、明日は夫の作次が十時から地区対抗の野球大会に出る、と言ったことを思い出した。
私は幾分寂しさがまぎれたような気がした。
翌日、私は、二キロほど離れた町営野球場に、少し余裕を持って自転車に乗って出かけた。
着くとちょうど見知らぬ地区の試合が始まろうとしていた。
私は人影もまばらなバックネット裏に陣取った。
試合は一回の表から一方的になった。
両チームの力にあまりにも差がありすぎたからだ。
エラー、フォアボール、エラーと続き、それがたまに出るヒットで大量点につながった。
私は子供の頃から遊びといっては野球をやり、大人になっても草野球チームで四番を打ったこともあるくらいなので、少なくとも草野球に関してはうるさいのである。
だから、私は、これは、エラーとフォアボールで自滅する、弱い草野球チームの典型的なパターンだと思った。
連係プレーがまったくできていなかったので、みんなで集まって満足に練習したこともないのだろうと思った。
だが、大量失点の真の原因は、練習不足というよりも、全員が全員同じように不器用だと言うことであった。
その裏の攻撃は三振の連続。
二回の表も大量失点は続いた。
私から見ると、誰一人として野球の経験があるようにも思えなかった。
はっきり言って皆へたくそだった。
私は、
『これじゃいつまで掛かるか判らない、俺だったら、こんなんだったら地区の恥をさらすだけだから出場しないだろう、おそらく酒を飲んだ勢いでこんな無謀なことを考えついたんだろう』などと、くり返しくり返しは思いながら、ときおりあきれたような苦笑いを浮かべては見続けていた。
そのうち、私はあることに気づいた。
へたくそチームの、私と同じ年ぐらいのショートを守っている男が、見方がエラーをしたりフォアボールを出したりするたびに、ドンマイ、ドンマイといって仲間を励まし続けているのである。
その男も仲間と同じように不器用だった。
自分もエラーした。 だが、それでもって決して意気消沈するようなことはなく、なおも大きな声を上げて仲間を励まし続けた。
その後も大量失点は続き、試合は五回コールド負けになりそうになった。
そのとき私はふと思った。
もし次の従兄弟の夫の作次が出る試合もこのような試合になったら、つまり、作次のチームが弱く、作次も不器用だったら、あまり見たくはないなと。
私は作次の応援をしないで帰ることにした。
球場を出ようとしたとき、私は従兄弟の和子に会った。
和子は私に声をかけた。
「これから試合だよ。どこに行くの?」
「帰る。急に用事を思い出したから」
と私は嘘をついた。
和子は続けた。
「残念ね。あっ、そうだ、ねえ、いま、弘美ちゃんとあったんだけど、話してみたら。久し振りじゃない」
「ひろみ、って?
「隣の家の弘美ちゃんよ」
「えっ。ここで。何しに来てるんだろう?」
「何しにって、だんなさんの応援にでしょう」
「野球の?」
「そうよ。あれ、見てなかった今の試合。出てたのよ。ショートで。試合には負けたみたいだけどね。せっかくだから会ってみたら」
「なにも話しすることないしね。もう二十年以上会ってないから。たぶん、お互いに忘れていると思うよ」
と私はとっさにまた嘘をついた。
私がそうしたのは、なによりもまず、まだ自分を周囲の人たちの目から隠しておきたかったのだが。
私はそのまま球場を出たが、帰り道を間違えるくらい動揺をしていた。
嘘をついた後ろめたさではなく、嘘をついたことによって、弘美との思い出が次からつぎへと、いや応なく甦って来たからである。
定職にもつかず毎日をぶらぶらしている私が、いまだ半人前という負い目を感じながらも、普通の人間のように名に食わない顔で生きていられるのは、普通の人間よりも多くの本を読んだり勉強したりして知識を身につけ、そして、今まさに、洪水のように押し寄せる時代の観念と悪戦苦闘しながら、そこから何か人間に役に立つような特別の意味を見つけ出すことに価値があると信じているからであった。
だが、わたしが激しく動揺したのは、そのような考えは、もしかしたら根底から間違っているのではないかと、なにげなく和子からもたらされたある事柄にやって疑念を抱かされたからである。
そして、疑念はたちどころに、今までまがりなりにも私が自負と自信を持ってやってきたことに対するぐらつきとなったのだ。
その事柄とは、弘美とその夫についてのことである。
十年位前に、私は弘美がこの町の大工さんと結婚したことを聞いた。
そのとき私は、これは田舎にはありがちなことで、べつに取り立てて言うほどのことではないといった程度にしか、感心を示さなかった。
だが、その夫が、先ほどの試合で、ショートを守り、惨めな負け試合になろうとしているにもかかわらず、仲間を絶えず励まし続けた男であると言う事実は、堅実で静謐でひたむきな時間が流れているのは、自然だけではなく、常に素朴な相貌を見せながら田舎に住んでいる人々の間にも流れていることを、私に気づかせるに十分だったのだ。
弘美とは私の家から百メートルほど離れた隣に住んでいた、私と同い年の女の子の幼なじみである。
物心ついたころから仲良く遊んでいた。
もちろんほとんどは、周囲の子供たちを交えてだが。
私には弘美との生涯忘れえぬ思い出がある。
小学校に入るまではとにかくよく遊んでいた。
だから小学校に入っても、その帰り道はいつも一緒だった。
それは、親から仲良くするんだよと言われたことを素直に守っているためでもあったが、真実は、無垢な二人の自然な成り行きのようであった。
五月ごろだったろうか。
途中までいっしょに帰っていたもう一人の同級生の男の子が、私に弘美をいじめるように仕向けた。
その男の子は私よりも少しからだが大きく乱暴なところがあった。
私はそれがいつも気にかかっていた。
私はその男の子といっしょになって弘美をいじめた。
弘美は泣いて帰った。
次の日、私とその男の子は担任の先生に呼ばれた。
わたしは泣きそうになりながら、その男の子からいじめるように言われたからいじめたと言った。 先生は私の言葉に納得したようで、私だけを許して先に返してくれた。
だが、私の気持ちは晴れることはなかった。
いくら脅かされたとはいえ、私にも博美をいじめたいていう気持ちが少しもなかったのかと、そしてなによりも、それは、わたしが弘美をいじめたことへの言い訳にはならないはずだと。
現在になってもそのことは決して忘れえぬほどに、深く心に刻み付けたからである。
その後私たちは再び仲良く帰っていたに違いない。
と言うのも、その後の記憶が私にはまったくないからだ。
そして、それはおそらく、いじめ事件からしばらくして二人の間に起きた、とても寂しく悲しい出来事が、それらをすべて吹き飛ばしてしまったからに違いない。
その出来事とは。
あるとき私たちは、弘美にとっては遠まわりだが、私にとっては近道を帰った。 土手の草地に寝転んだり、名前も知らない花を摘んだりしながら、たわいない話をしながらゆっくりと楽しそうに帰った。
だが、その私たちの様子をひそかにじっと見ていた者がいた。
その者は、私に、私たち二人がやっていたことを再現するかのように言って、私たちの仲のよさ振りを冷やかした。
私はそのとき、母親から言われたことを守っているだけだと思いながらも、自分たちがやっていることが何か悪いことのように、そして、とても恥ずかしいことをやっているかのように屈辱的なものを感じた。
次の日、弘美が昨日と同じ道を、私の後について来ようとしたとき、私は両手を広げて通せんぼをし、こっちに来ちゃだめだと、それまで見せたことがないような表情できつく言った。
私はその理由を決して言わなかった。
ただ無言で両手を広げているだけだった。
弘美は驚いたように限りなく不思議そうな顔をして私を見ていた。
その目はとてつもなく寂しそうで不安そうだった。
私にとっては生涯忘れえぬほどに。
いったい誰が、何のために、僕たちに悪い遊びを教え込み、卑劣な感情を植えつけ、僕たちの仲を引き裂いたのだろう。
弘美は一人で帰って行った。
私たちはそれ以来いっしょに帰ったことがない。
いや、たぶん帰ったことがないのだろう、その後の記憶がまったくないのだから。
あの小学五年のときの清冽な出来事をのぞいては。
その年の初夏、放課後、私はいつものように、家までの二キロの帰り道を独りで歩いていた。
ちょうど真ん中あたりに来たとき、ふと、前方の西の空が黒雲に覆われ真っ暗になっているのに気づいた。 でも、私はそれほど気にしなかった。
だが、しばらくすると、目の前で突然のように閃光が走り、黒雲を真っ二つに引き裂いた。
そして、地をも揺るがすような雷鳴とともに突風が起こり、大粒の雨がたたきつけるように降り出した。
私は恐怖に襲われ、脚は止まりかけた。
だが、どこにも逃れようがなかった。
とにかく勇気を出して家まで帰るしかなかった。
私は走った。
しかし、稲光も、雷鳴も、風も、雨も、まるで私が嵐の中心部へとどんどん突き進んでいるかのように激しさを増すばかりであった。
とくにまじかで閃光が走り雷鳴がとどろくたびに、私は何度も脚がすくみそうになった。
私はその場に頭を抱えてうずくまりたかった。
でも、どうにか勇気を振り絞って走り続けた。
脚は夢の中で怖いものに追いかけられて逃げるときのように思うように動かなかったのだが。
衰えることなく、風はうなり声を上げながら、巨木のこずえを激しく翻し、大粒の雨は、たたきつけるように降り注いでは、視界をさえぎり、稲光は、絶え間なく黒雲を引き裂き、森を走り抜け、頭上を掠め、地に突き刺さり、そして、天の上げる悲鳴がこだまとなって、とどろき渡っていた。
私は恐怖でもう限界だった。
泣きそうになっていた。
いや、泣いてはいなかったが、声は確かにあげていた。
恐怖に怯えた小さい子供のような情けない声を。
そのときだった。
私の傍らを追い越して通り過ぎて行く者がいた。
それは私よりも小さい女の子だった。
弘美だった。
黙々と、決然と、そして足早に。
弘美は見る見る私から離れていった。
私は弘美からこれ以上離されるのを恐れるかのように、必死に後を追った。
きっと、私があげていた、あの子供のような情けない声を聞かれたに違いないと思いながらも。
そのとき私の脚は、それまでと違い思い通りに動くようになっていた。