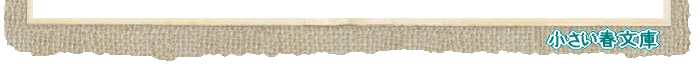それはあなたが会いたいと思えば思うほど、恋焦がれれば焦がれるほどに、その永遠の輝きを増していき、そしてもう二度と絶対に会うことができないからこそ、永遠の女性、永遠の恋人となるのです
* * * * * * * * * * * * * * * * *
永遠の女性
はだい悠
* * * * * * * * * * * * * * * * *
立花茂人、もうじき三十にもなろうとするのに、この数年、もらった給料から最低限必要な生活費を差し引いた、その残りのほとんどを風俗に使っていた。
だから今のところ貯えなどはまったくなかった。 それは彼が、国家公務員として何かよっぽどヘマをやらない限り死ぬまで、その生活が保障されているために、その必要性を少しも感じていないからでもあったのだが。
彼が風俗に通うようになったのは、二十五歳のとき、突然母親をなくしてからだった。
彼は、大学で宗教学を教えていた母親を尊敬し愛していた。
だからその衝撃は計り知れなかった。
彼は葬儀を終えたその夜、ひとり街にさまよい出た。
そして気がつくと原色の看板が掲げられたドアを開けていた。
それまで彼は風俗などに行ったことはなかった。
それは欲望がなかったからではなく、精神的な問題とタイミングの問題が、彼が行くことを妨げていたからだった。
精神的な問題とは、昼間に公衆の面前でロにすることが、はばかられるようなところに通うことは倫理的に少しふさわしくないと思っていたこと。
タイミングの問題とは、今まで無性に風俗に行きたいと思ったときに限って、なぜかお金を持ち合わせていなかったり、お金を持っているときには、不思議とそういう欲望が起こらなく、そのうちにいつでも行けるやと思っているうちに、次第にお金もなくなり、結局、行く機会を逃してしまうということであった。
では、そんな彼が、なぜ母親の葬儀の日に始めて風俗に行ったかというと、それも三軒も続けて。 ふところに香典の束を忍ばせていたということもその理由のひとつにもなるだろうが、本当の理由は彼にはわからなかった。
今まで分析したことも、分析したいと思ったこともなかったから。
ただ、そのときは無性に、衝動的に、爆発的に、駆り立てられていたことはうすぼんやりと記憶に残っていた。
彼が毎週のように通っている店を出ようとして、受付のカウンターの前を通り過ぎようとしたときだった。
入って来たときとは違う、見慣れない男が、そこから茂人に微笑みかけながら言った。
「満足いただけたでしょうか」
彼は歩みを緩めながら、そして少し笑みを浮かべて答えた。
「まあまあかな、いつもどおり、かな」
その男は通り過ぎようとする茂人を呼び止めるようにさらに言った。
「あのう、お客様、すみません。よろしかったら、私どもは大変ご贔屓になさっていただいておりますお客様のために、特別のサービス、スペシャルサービスを、ご用意させておいてありますが」
「スペシャルサービス?」
「はい、そうです。特別のお客様に特別のサービスということで準備させていただいております。詳しくはこのカードに書かれてある番号に電話していだだければと思っております」
茂人は名刺大のカードを受け取り外に出た。そして歩きながら、繁華街の明かりでそれを見た。そこには次のように書いてあった。
《夢を追い求めるあなたに、永遠の恋人を!》 そして電話番号が。
彼はさっそく携帯を取り出し電話をした。
このような店を出たとき、茂人はいつも、感情も思考もない空虚な気持ちがしばらくの間は続くのであったが、もう好奇心が抑えがたく沸き起こってくるのを感じたからであった。
電話が通じた。
「はい、お待たせしました。こちらは永遠企画です。夢案内役の浅本と申します。よろしくお願いします」
「今もらったカードを見て電話しているんですが。それでどんなサービスを」
「失礼ですがどちらからの紹介でしょうか」
「夢乙女の店の人から」
「今どちらにおいでになられますか」
「ちょうど今、夢乙女を出たばかりで。歩きながら電話をしているんですが」
「判りました。そうするとどちらに向かっているんでしょうか。駅でしょうか、それとも聖愛女子大学や法務局があるほうでしょうか」
「駅のほうです」
「はい、判りました。それではこちらからお迎えに参ります。というもの、このサービスの内容は電話では大変お判りいただけにくいので直接あってお話したいと思っておりますので。これからよろしいでしょうか」。
「はい、良いですよ」
「それでは、駅前広場に噴水がありますね。その隣にある武将の銅像の下で待ち合わせをするということで、どうでしょうか」
「はい」
「それでは大至急お迎えに参りますから、よろしくお願いします」
茂人はまだ自分が社会に慣れていなかったときのような、期待と不安が入り混じった気持ちで待った。
五分後、少し離れたところに黒い大型の車が止まり、一人の男が降りて、茂人のほうに近づいてきた。茂人はその男が目の前に来てようやく判った。
先ほど自分にカードを渡した夢乙女の人間であるということに。
そして期待だけが残った。
二人は笑みを浮かべて軽く会釈をした。
そして茂人は男に促されるままに、その男の車に乗った。
男はゆっくりと車を走らせた。
そして話を切り出した。
「わたくし浅本と申します。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。きっと、お電話いただけると思っていました。このような商売をやっておりますと、お客の表情や雰囲気を見ただけで、サービスに満足しているか、いないか、それに本当はどんなサービスを望んでいるのかも、だいたい判ってくるようになるんですよ。単刀直入に言いましょう。お客様は、今のあの夢乙女のサービスに、本当は満足していないでしょう。当たりでしょう。そうですよね、マンネリというか、あまりにも即物過ぎて想像力を刺激しないとか。夢がないとか。そこで私が考えた企画がこれなんですよ」
そういいながら浅本は、茂人に一枚の紙を手渡した。
そこにはおおよそのサービスの内容が書かれてあった。
浅本の車に乗り込んだときから茂人は上の空になっていた。
なぜならその車が母親が乗っていたのと同じものだったからだ。
よみがえる母親との思い出に浸るように窓の外に目をやっていた茂人は、その紙を受け取り、見た。
そして言った。
「そうすると、これは見合いみたいなものですか」
「見合い、いや見合いではないです。出会いです」
「でも、ようするにこれは、その後付き合うための出会い、つまり見合い見たいなものでしょう」
「いや違います。あくまでも出会いです。永遠の女性とのね」
「でも、出会って、その後付き合って結婚すれば、結局見合いと同じでしょう。まして相手が理想の女性なら」
「いえ違います。この企画、このサービスで出会うのは、理想の女性ではなく、永遠の女性、永遠の恋人です」
「まあ、僕にとっては永遠の女性でも理想の女性でも、素敵な女性と出会うならどちらでも良いですけどね。それでパーティなんかあるんでしょうか」
「そうです。パーティをやります。男女合わせて二十名ほどの」
「費用はいくらぐらいなんですか」
「二万円です」
「まあまあかな、ちょっと安いぐらいかな。それで理想の女性、いや永遠の女性に会えるなら」
「いや、もちろんそれだけではないです。もしわたしどもが示す条件に同意していただければ、、、、ひゃく、二百万円ほどいただくことになっております」
「に、二百万円。それは高い、いくら永遠の女性と出会うためとはいえ」
「私はそんなに高いとは思っておりません。普通の女性と遊ぶのなら二万円、ちょっと素敵な女性となら数万円。それに比べて永遠の女性ですよ。二百万であっても高くはないでしょう。もしわたしだったら、その十倍払っても惜しくはないですね」
「それで、その条件とはどういうことですか」
「まずはあなたに、私どもが主催するパーティに出席していただいて、そしてパーティが終わり、帰るとき、もしあなたがそのパーティで、永遠の女性に出会えたと思ったら、前もって私どもが用意した支払い同意契約書にサインして、それを渡してもらえば良いだけです」
「きれいな女性が来るんでしょうか。女優とか、アイドルのような」
「もちろんですとも、永遠の女性、永遠の恋人ですから」
そのとき浅本の携帯が鳴った。
「はい、、、、はい、そうです。そうですが、それは残念です。わざわざどうもありがとうございます。いえ、ちっともかまいませんよ。どうもありがとうございました。さよなら」
浅本は電話を切ると、苦笑いをしながら話し始めた。
「あや、驚きましたよ。わざわざ断りの電話をかけてくるとはね。真面目な娘なんですね。昼間面接に来た娘なんですけどね。わたしはあの娘にはこの仕事は無理だなあと思っていましたので、あの娘もそれに気づいて、もう電話などかけてこないと思っていたんですがね。どうもその娘は仕事の内容も判らずに、アルバイト感覚で面接に来たみたいです。何しろ一日五万円と聞いて驚いていましたから、何を見てきたのか、一ヶ月五万円と勘違いしていたみたいです。わたしにはわかりますよ。こういう仕事がふさわしい娘と、ふさわしくない娘との違いがね。あの娘だったら面接が終わって家に帰る途中に自分がとんでもない所に面接に行ったことに気づいて、もう電話など掛けてくるとは思ってなかったんですがね。律儀なんですね。お客の中にはあういう娘が好きな人も居ますけどね。でもそれとこれとは違いますからね。やっぱりこの仕事が向いている娘と向いてない娘が居るということは社会の厳然たる事実ですから」
茂人は再び窓の外に目をやっていた。
それは久しぶりに車の窓から外の風景をやっくりと眺められるというためでもあったが、紅葉が始まりかけた舗道の上を一人の若い女性に目を奪われたからだった。
それは茂人が大学に入りキャンパスを歩いているときに、一人の美しい上級生を見かけ、こんなきれいな女性が大学に居たなんてと驚き、でも話すことなんで到底無理だろうななんて思いながら、ただすれ違うだけたったにもかかわらず、でも、もしかしたら、いつかはという期待をこめた、そのときの夢見るような甘く感傷的な気持ちとまったく同様な気持ちで見ていたのだった。
それは紛れもなくあこがれであり、茂人は自分がまだ何も知らなかった青年のときのような気持ちがしていた。
そしてじっと眺めているうちに、さらに自分が少年のときのような夢と希望に満ち溢れていた気持ちになっていくような気がした。
浅本が声をはずませるように言った。
「どうですか、パーティに参加してみませんか」
茂人は自分より幾分年上と思われる浅本の穏やかな表情や理知的な話し方から。
常日頃このような商売をやっているものに対して抱いている、あまり親しくはならないほうが良い、という警戒感は少しも起こらなかったが、まだ決断は出来かねていた。
茂人は窓から目を離したずねるように言った。
「どうしてこのようなサービスをやるようになったんですか。つまり、今の商売を続けていても何も問題はないでしょう。男がこの世に存在する限り絶対に廃れることはない商売ですから。やっぱりお金ですか、急に大金が必要になったとか」
「お金ね。そう見えますか。確かにお金はいっぱいあったほうがいいですけどね。ふう、、、、まあ、正直に言いますが、実は、この仕事をやっていて、こんなことを言うのも変なんですが、女の子と遊びに店に来るお客は、果たして本当に満足しているんだろうか、つまりいったい何が面白くて店に来るんだろうかって、ときどき思うことがあるんですよ。いつも同じような肉体的サービスを受けていて、なぜ飽きないんだろうかってね。わたしの言うこと変ですかね。もちろんはじめは誰だって楽しいはずですよ。わたしもそうでしたから。でも、やっぱり飽きるでしょう。肉体的なサービスだけじゃ。そこには精神的なものは何にもないですからね。慣れてくると、初めのころは感じたに違いない想像力を刺激するものもまったくありませんからね。わたしは最近つくづく思うようになってきたんですよ。人間は徹頭徹尾精神的な生き物だってことをね。もちろん肉体的なものも大事ですよ、でも精神的なものと肉体的なものとは根本的に違うんです。別次元に存在するくらい違うものなんです。肉体的な満足を精神的な満足に置き換えることはできないんです。お客が女の子からサービスを受けて店から出て行くときの表情を見ていて、わたしは店に遊びに来るお客には二種類のタイプがあると思っています。肉体的なサービスだけで満足する人と、それだけでは満足できなくて、通えば通えほどだんだんさびしげで悲しそうな表情になっていく人の。なぜなんでしょうね。でも、わたしにはそういう人の気持ちがわかるんです。いや、正確に言うと最近わかるようになってきたんです。はっきり言うと、あなたもそういう人です。つまり通えば通うほど寂しげで悲しそうな表情になっていく人。あなたは自分ではお気づきでないでしょうが、あなたは本当は少しも満足などしてないんですよ。わたしにはよく判るんですよ。それで今日声をお掛けしたんですがね。わたしたち男というものは、少年から青年にかけてどんなにか女性にあこがれたことでしょう。胸を締め付けられるようなときめき、夢を見ているような恍惚感、そして、純粋、可憐、清純という言葉で表現されるような清冽な感情。でも大人になるにしたがって、いろんな経験をするに従って。そんなものどっかに吹き飛んでしまいました。どこに行ったんでしょう。物質的にも肉体的にも次から次へと満足を得ている間に、その美しいあこがれはどこかに行ってしまいました。でも本当はどこにも行ってないんですよ。いるんですよ。わたしたちの心の奥の奥にひっそりといるんですよ。どうですか、お気づきになりませんか、いや、気づかないかもしれないが、あなたにはそういうものが再び芽生え始めているというか、よみがえり始めているということがわたしには感じ取られるんですが。どうでしょうか、わたしに賛同していただけますでしょうか」
茂人から浅本に対する警戒心はほとんどなくなっていた。
そして言った。
「そうするとこの企画は、私が得ていないという、その精神的な満足を得るためということですか」
「ええ、早い話そういうことです。いや、それ以上かな。何しろ永遠の女性と出会えるのですから」
「永遠の女性ね。ふう、よく判らない。それではいつそのパーティをやるんですか」
「ええとですね。今度の、いや、来週の土曜日ですね。詳しくは後で電話でということで。その前にちょっと失礼して」
そういって浅本は携帯を手に取ると、どこかに電話をした。
「浅本です。大至急、銅像に花束をお願いします」
電話を切ると浅本は再び話し始めた。
「いや、大変失礼いたしました。突然急用を思い出したものですから。それで今度のパーティに出席していただけるわけですね」
「ええ。その前にもう少し聞きたいんですが。やはり費用が二百万円というのは少し高いと思うんですが」
「いや、わたしは決してそうは思いません。むしろ安すぎるくらいだと思います。あっ、失礼ですが、お名前は」
「立花といいます」
「立花さん、お職業は?、お医者さんとか? 青年実業化とか? それとも大学の若き教授とか? 」
「いえ、そんな、とにかく今は内緒に、、、、」
「どう見てもセレブな生活を楽しんでいる方のようにお見受けしますが」
「いや、それほど、、、、」
「そんなあなたにとって、二百万なんてお小遣いのようなものでしょう。立花さんね、あなたは今まで、風俗でどのくらい使いましたか。百万、二百万、いやもっとでしょう。それなのに、記憶に残る、いや心に残るような女の子いましたか。いないでしょう。みんなみんな忘却の彼方でしょう。それに比べたら、永遠の女性と出会うための百万は安いでしょう。えっ、決めるのは今じゃなくてかまいません。二、三日じゅうに電話していただければ。それから、例の支払い同意契約書はこの封筒に入っておりますから、当日サインしたものをパーティが終わって帰るときに、わたしに渡していただければ幸いと思っております。なお、パーティに出席するだけなら二万円となっております。それでは駅までお送りします」
茂人は車から降りて改札に向かって歩き出した。
そのとき茂人の脇を芳香を放ちながら、一人の若い女性が足早に通り過ぎるのに気づいた。
なにげなく見ると、見覚えがあるような気がした。
すぐに、先ほど車の窓から見た美しい女性だとわかった。
茂人はその女性の後を追うように歩いた。
できれば同じ電車なら良いなあと、淡い期待を胸に膨らませながら。
町はすっかり晩秋の気配だった。
人々の服装も街路樹も。
茂人はその女性の後姿に激しく引かれた。
そこから何もかも包み込むかのようなおおらかさや豊かさを感じ取ったからだった。
構内に入ると女は歩みを緩めた。
乗降客で混雑してきたから。
改札を通り過ぎるとき女は駅員に挨拶をした。
駅員は笑顔でこたえた。
茂人はなおも追ったが、違う電車と判ってそこで追うのをやめた。
だが、なぜか印象に深く残った。
そして思った。年齢は、職業は、あの通りを歩いていたから、法務局の職員か、大学の職員、それとも学生か、駅員と親しげに挨拶をしていた、それはなぜか、などと。
茂人にとって夜の電車は、プラスチックのような乗客の表情を眼にしたり、ときには意味のわからない乾いた会話を耳にしながら、いつも変化がとまったような冴え冴えとして空虚な気持ちだったが、今は思わず顔がほころんでしまいそうな満ち足りた気持ちだった。
翌日、茂人はパーティに出席することを決断していた。
そして次の土曜日の夜、有名ブランドのスーツに身を包んだ茂人はその会場である高級ホテルのホールを歩いていた。
ホテルに足を踏み入れたときから茂人は、押し寄せる期待と煌びやかながらもその上品な夜の照明で、もう華やいだ気分になっていた。
会場となっている部屋の前に来ると浅本が出迎えた。
部屋に通された茂人は、三十七階の窓から見える夜景に目を見張った。
パーティは時間通りに始まった。
だが、茂人は動揺し始め、より深くへと気持ちが沈み始めていた。
それはパーティが始まる前、参加者が部屋に入り始めたときに始まったのであった。
参加者の服装を見て、これは違う、男はタキシード、女は華やかなドレス、それにくらぺて自分はスーツ、どんなに一流でも見劣りがする、どう見たって場違いな感じがすると思いながら。
そしてその落ち込みは、この間電話したときになぜタキシードを着てくるようにと言わなかったのだろうかと、浅本への憤りに変わって行った。
参加者が一人一人紹介されても誰も茂人の印象に残らないほどに。
少し動揺が納まりかけた茂人は、ようやく周囲の様子が理解できるようになった。
参加者は男女とも七、八名。男性はほとんどが茂人と同じぐらいの年齢かまたは年下。
女性はみな若くほとんどが二十代前半であるが、なかには十代と見える者もいた。
会場には穏やかな環境音楽が流れ、落ち着いた証明のもと、椅子やソファーはないが、三箇所に置かれた丸いテーブルの上にはちょっとした食べ物が備えられ、飲み物はホテルのサーバーが世話をした。
パーティが始まるとともに、男と女、男二人に女、または女二人に男というふうに会話が始まった。
だが、茂人はどうしてもはじめることは出来なかった。
もともと女性と話すのはそれほど得意ではなかった所為もあるが、みんなと違う服装のせいで気後れをし、雰囲気に圧倒されていたからだった。
茂人は、期待していたものとはだいぶ違うなと思いながらも、せっかくお金を出してきたのだから、ここは自分から積極的に話しかけねばと思うのであったが、みんなが笑顔を交えて楽しそうに話しているのを見ていると、自分にはあう言うユーモアのセンスもなければ、まるで昨日までの友達のように急に打ち解けた気分に放れないと思うと、結局は消極的な気持ちに負けてしまうのだった。
茂人は来たことを激しく後悔しはじめた。
でも二万円の元は取ろうとして欲のみ、食べた。
そしてその合間によく観察した。
特に女性たちを。
みんな華やかで美しかったが、特にまだ十代ににも見える女性のやや短めのドレスからのぞいたきれいな足が魅力的だった。
それでもドレスはそれほど派手ではなかったがほとんどの男性から話しかけられながらも、それに笑顔で応えている女性が気になった。
美しいだけではなく、その上品で落ち着いた雰囲気、心情の豊かさを感じさせ、気持ちを穏やかにさせるような笑顔。
茂人は思った。
あのような女性こそ、ま会話をするだけで男どもの心を暖め和ませ、癒すに違いないと。
やがてダンスが始まった。
だが茂人は踊らなかった。
いや、踊れなかった。
そもそも女性とダンスなどしたことがなかったからだ。
こんな話はきいてない、電話で話したときに言ってくれれば、最初からパーティなんかに参加しなかったのにと、茂人は浅本に激しく憤りを覚えた。
茂人はほんとうに自分が場違いな人間に思えてだんだん惨めな気持ちになっていった。
このまま帰ろうかと思った、でもなんとなくもったいないような気がした。
それなら最後に思い切って声をかけてみようと思った。 それも一番若くてしかも脚の美しい女性に。
ちょうどその女性はダンスを終えたばかりだった。
茂人はなにげなく近づき、そして声をかけた。
「ダンス、お上手でしたね」
「ありがとうございます」
「もしかしたら。あなたは女子大生ですか。とても若く見えるもんですから」
「はい、そうです」
「すると、聖愛?、とか」
「ご存知ですの、聖愛女子大のこと」
「もちろんですとも。あの近くにちょくちょく用事で行くものですから。でも、ただ前を通り過ぎるだけですけどね」
「いえ、でも、とてもうれしいです。あまり有名じゃないので、どこにあるのかも知らない人が多くて、ときどき寂しい思いもするときがあるんです。真面目な学生ばかりいるいい大学なんですがね。」
「あなたのような綺麗な方がいる大学なら、きっといい大学に決まってますよ」
「そう言っていただけると本当にうれしいです。あのう、失礼ですが、立花さんて。どこの医学部でしたっけ」
「イガクブ、いがくぶ、ああ医学部ね。ケッ、ケイオウです」
と茂人はとっさに応えては見たものの、その状況を良く飲み込めないままに、さらに言葉を続けた。
「あれ、ところでどうしてわたしの名前を」
「えっ、あれ、ええと、プロフィール、写真取りませんでした。男性の方は判りませんが、女性には前もって渡されるんです。男性参加者全員の名前や経歴が書かれたものが、写真入りで。わたしそういうの覚えるのとても得意なんです。特に学歴なんかは。ケイオウって、あの、慶応」
確か写真を取った覚えはないと思い、茂人は一瞬戸惑い混乱したが、すぐに機転を利かせ、なんだそういう性格のパーティなのか、それならそれでもかまわない、もう開き直り嘘をついてでもこの場を楽しむしかないと決心した。
「そうです。慶応の医学部です」
「優秀なんですね。さぞやおもてになるんでしょうね」
「いえ、まったくだめですよ。わたしなんか、この通りですから。あなたこそ、あっ、お名前は」
「わたし、わたしは星野といいます」
「星野さん、あなたこそ、それだけ美しいんですから、ほかの大学の男子学生から、合コンなんかで引っ張りだこじゃないですか」
「わたし、同じ年頃の男の子は嫌いなんです。なんか子供っぽくて。話してても面白くないんです。それに比べたら働いている男の人って包容力があってとても魅力的です。遊びだって学生みたいに貧乏くさくないし、そのリッチな感じがとても素敵です」
そういい終わったとき、彼女にダンスの誘いの声がかかった。
彼女はそれに応じた。
でも茂人はそれでいいと思った
なぜなら、彼女とはこれ以上どのようにも発展しそうにないと、うすうす感じていたからだった。
茂人は、せっかく若くて美しい女性と話をしたのに、なぜか後味が悪かった。
再び気が滅入った。
今度こそ本当に帰ろうかと思った。
だが、そのときなにげなく会場の様子に目を転じたとき、ぽつんと独りでいる女性が目に入ってきた。
あの落ち着いた雰囲気の、ひときわ心情の豊かさを感じさせる女性だった。
茂人は、どうしてあんなに素敵な女性が独りぼっちなのだろうかと不思議に思う反面、今が彼女に話しかける絶好のチャンスだと思った。
だが二人の間には少し距離があった。
茂人としては不自然な形では近づきたくなかった。
しかし欲求は高まるばかりだった。
するとそのとき、幸運というか、奇跡的な出来事が起こった。
新しい飲み物をグラスに入れて用意してきたサーバーが足をつまづき、そのうちの何本かを床に落してしまったのだ。
グラスが倒れ落ちる音に気づいて二人はそこに近寄ったが、落ちたグラスはすぐに片付けられ後は、何事もなかったかのように、二人だけがそこに残された。
茂人はもうこれで何もかも整ったと思った。
そして彼女に声をかけた。
「いやあ、びっくりしましたよ。何が起こったかと思いましたよ」
「ええ、わたしも」
「あれ、ダンスはなさらないんですか」
「わたし踊れないんですの」
「あっ、そうですか。実はわたしもなんですよ。同じですね。みんな踊れるので、わたしだけかと思ってましたよ、踊れないのは。ダンスがあると判っていたら始めから参加しなかったんですけどね。あなたはよくこういうパーティに来られるんですか」
「わたしは今度が初めてなんです」
「初めて。へえ、そうなんですか。実はわたしもそうなんですが。なんかまだ、この通りなじめなくて。それに比べたらあなたはとても雰囲気になじんでいて、ぜんぜん初めてだとは思うませんね。ほんとですか」
「ほんとうです。友達に一度出てみないかって、今晩初めて参加したんです」
やわらかい笑みを浮かべて話す彼女の表情に、茂人は何もかも包み込むかのような心の豊かさと懐かしさを直感した。
そしてそれまでのいらだった気持ちも治まり、だんだん心が温まっていくのを感じながら言った。
「学生じゃないですよね」
「はい、もう働いております」
そのとき茂人の脳裏を掠めたものがあった。
どこかで見たことがあると、それもつい最近。
すぐに思い出した。
浅本とあった夜、車の窓から見かけ、その後、駅でも、その後ろ姿に惹かれて後を追うようにして見続けた女性に似ていると。
茂人はきっとそのときの女性に違いないと思いながら言った。
「このあいだ、たしか法務局や聖愛女子大がある通りを駅に向かって歩いていませんでしたか。
その辺にお勤めとか?」
「あの時は、たぶん、病院からの帰りじゃないでしょうか。通りの裏のほうに大学の付属病院がありますね。そこに父が入院しているんです。それで見舞いに行った帰りに、わたしを見られたんだと思います」
「お父さんが入院なされておられるんですか」
そう言い終った後、茂人は、彼女は笑みを浮かべてはいるが、ほかの男たちと話しているときのような笑顔ではないことに気づいた。
茂人は冷静に話しかけた。
「もしかして、わたしと話しているの退屈じゃないですか」
「いいえ、そんなことありませんよ」
「そうですか。ほかの男の人と話しているときは、笑顔が見られましたけど。わたしと話しているときは、ちっとも笑顔じゃないので。もっともわたしには、女性を笑わせるような楽しい話をしていませんけどね。そもそもそんな才能は始めからないんですけどね。なんか不器用というか、決して話し上手じゃないものですから」
「誤解なさらないでください。笑顔にもいろんな種類があるんですのよ。男の人と話しているときに笑顔だからといって、それが楽しいからそうしているのだとは限りませんのよ。男の人は、わたしたち女性を楽しませようとして、よく面白おかしくお話をしてくださるんですけど、それが必ずしも楽しいとは限りませんの。でもせっかく退屈させまいとして話してくださっているので、笑ってあげないのは失礼ではないのか、思いやりに欠けるのではないかと思い、無理に笑顔を作っているときもあるんですのよ。たとえどんなにつまらなくてもね。ですから、そういうことはあまり気になさらないほうがいいと思います」
「あっそうなんですか。そういうものなんですか。ぜんぜん知りませんでした。それを聞いてものすごく気が楽になりました。今までそういう人たちを見ていると、自分には出来そうもないので、とてもうらやましいなあと思っていたんですけど、なんだそういうことだったんですか」
そういいながら茂人は、彼女の顔を見ると、女性は穏やかな笑顔で、そうなんですよと言いたげに茂人を見つめ返していた。
茂人はそこに彼女のあふれでるような心情の豊かさや深い知性を感じとった。そしてこの笑顔は絶対に真実の笑顔だと思った。
もしこんな笑顔で挨拶されたら誰だって笑顔で応えたくなるはずだ、あの夜の駅員もきっとそういう気持ちだったに違いないと思った。
茂人は満たされた気持ちになった。
そしてだんだん少年のような素直な気持ちになっていくのを感じながら言った。
「あのう、実は私、どんな資料を渡されたかわかりませんが、本当のことを言うと、わたしは医者ではないんですよ。公務員、国の研究機関で働いている、ごく普通の、真面目ですけどね、平凡な公務員なんですよ。だから、あそこに書かれている学歴とか職業とかは全部嘘だと思います。どんな手違いがあったのかわたしには判りませんが。それに関しては申し訳ないと思っております」
「そんなに気になさらないでください。わたしは友達に誘われて、初めてこういうパーティに参加しただけですから、そういうものを見る余裕などまったくありませんでしたから。もしあったとしても、わたしはそういうものにはあまり関心がありませんの。男の人に限らず人はみな人柄だと思っていますから」
「それを聞いて本当に安心しました。ところであなたはどのようにお仕事を」
「わたしですか、わたしは母の経営しておりますブティックを手伝っております」
「店長みたいなものですね」
「いえ、とんでもありません、まだ見習いみたいなものです。よく叱られております。母にも、お客様にも」
「大変でしょうけど、でも夢のある素敵なお仕事だと思います。がんばってください。あなたならきっと成功すると思います」
「ありがとうございます」
「わたしのような公務員から見ると、ちょっぴり、あなたがうらやましいですね。たしかに生活は安定しているんですが。でも、夢はないですから」
「でも、わたしのほうから見ると逆にあなたのほうがうらやましいですわ。生活が安定しているというのは、とても魅力的なことです。夢も大切ですけど現実も大切です。どんなに夢を求めようと現実には否応なく行き詰まることがあるんです。かといって、女同士の意地っていうんでしょうか。おいそれとは母に相談できませんし、なにしろ仕事上のことですら。そういうときにはよく父に相談するんです。ちょうどこの間も見舞いをかねて、父に悩み事を相談しに行ったんです」
「はあ、そうだったんですか」
茂人は彼女の悩み事が理解できたかのような気がしてそう言うと、なんとか自分が力になってあげたいような気持ちになった。
そのとき音楽は止み、ダンスは休憩となった。
やがて再びダンスが始まったが、始めたのは半分ぐらいだった。
ほかのものは会話をはじめた。
その様子が茂人には会話が弾み明るく楽しんでいるように見えた。
それに比べて自分たち会話は途切れがちで暗く沈んでいるように思えた。
そこで茂人は女性に言った。
「わたしはこの通り話は得意なほうじゃないので、よければ、ほかのところで会話に混じって、楽しんでみてはどうですか、わたしは独りでもまったくかまいませんから」
「そんなに気になさらないでください。先ほども申しましたが、わたし本当のこと言うとおしゃべりな男の人ってあまり好きじゃないんです。そういう人は、女の人を楽しませようとして話を作ったりしているんでしょうが、そんなとき、こちらとしては無視するなんてことは絶対に出来ませんから、それで話に合わせようとしたり、無理に笑顔を作ろうとしたりすることに気を使うために、かえってとても疲れるんです。はたから見るほどにそれほど楽しんでなんかいないんです。なんに話さないというのも一緒にいても苦痛ですが、わたしとしてもこのくらいがちょうどいいです。今のままが、好き、です」
それを聞いて茂人は、胸の奥から沸き起こる暖かいものが全身を包み込むかのような恍惚感に襲われ、かつい味わったことのないような幸福感を覚えた。
茂人はボォッとして窓の外に目をやった。
夜景がたとえようもなく美しかった。
そのとき女性が茂人に言った。
「すみません。ちょっと失礼して、、、、」
そういって彼女は茂人のところから離れていった。
茂人は、電話かお手洗いかだろうと思った。
だが彼女はなかなか姿を見せなかった。
そうこうするうちにパーティは終了となった。
それでも茂人の幸福感は続いていた。
そして茂人は、消費者金融からかき集めた二百万円と同意契約書が入った封筒を、満足げな笑みを浮かべながら、浅本に手渡してホテルを出た。
三日間、幸せな気分で過ごした後、茂人は浅本に電話をした。
「はい、永遠企画です」
「あっ、浅本さんですか。わたし、わたしです。立花です。この間はどうもありがとうございました」
「いえ、こちらこそ、ご契約ありがとうございます」
「いやあ、何をおっしゃいます、本当にお礼を言いたいのはこちらのほうです。あんなすばらしい出会いを提供していただいて、もう何も言うことはありませんよ」
「それは良かったです。こちらとしても、そんなに喜んでいただけるとうれしい限りです」
「もう、パーフェクトでしたよ。いくら感謝しても感謝しきれないくらいですよ。そこでですね。ちょっとせっかちみたいで、言いにくいんですが、今度またいつ会えるんでしょうか」
「いつ、と言いますか、あのようなパーティを、いつまた開くかということですか? それはちょっと教えられないですね」
「えっ、それは、どういうことですか」
「どういうことって、、、、あのう、失礼ですが、立花さんはもう一度あのようなパーティに出席なさるつもりですか」
「はい、当然でしょう」
「えっ、それは出来ません。ありえません。不可能なことです」
「だってもう一度あの人に会うためには、パーティに出なければならないでしょう。あっ、そういうことですか。パーティではなく、プライベートに二人っきりで会えるということですか。それなら話は別ですが」
「いや、そういうことではないんです。パーティでも、プライベートでも、あなたはその女性と、もう会うことは出来ないのです。おそらく永久に」
「何を訳のわからないこと言っているんですか、浅本さん。あれほどの大金を出して、もう二度と会えないなんてことはないでしょう。それは詐欺、ペテン、契約違反でしょう」
「詐欺でもペテンでもなければ、契約違反でもないですよ。まさに契約どおりですよ。完璧にね。あの時わたしが何度も念を押すように言ったこと、よもやお忘れではないでしょうね。あの時わたしが約束したことは。あなたに永遠の女性を出会いさせると言うことだったんですよ。そして、あなたがパーティで永遠の女性に出会えたらと思ったら、わたしに二百万円と同意契約書を渡すということだったんですよね。そしてあなたはその永遠の女性に出会えた。そこでわたしに契約書の入った封筒を帰りがけに渡した。それだけのことでしょう。そこにはお互い何の不満も生まれる余地はないはずです」
「わかってますよ。永遠の女性、素晴らしい女性、素敵な女性、要するに理想の女性に会えたということですから」
「ああ、そこが違うんですよ。根本的にね。わたしが約束したのは、理想の女性じゃありません、永遠の女性です。永遠の女性との出会いです」
「永遠の女性と理想の女性とはどこが違うんですか」
「大いに違います。天と地ほどの開きがあります。おそらく理想の女性とは、人によっては多少の違いがあるでしょうが、誰もが思い描くようにですね、ようするに美しくて頭が良くてスタイルもよくて、そして性格も良くて、結婚するには申し分のない女性と言うことでしょう。ところが永遠の女性とはそれとまったく違うんです。一度会ったきりで二度と会うことはなく、その出会ったときの印象や状況があまりにも強烈で喜びに満ち溢れたものなので、そのときの雰囲気や面影が、忘れえぬ思い出となって、あなたの胸の奥底に、その後ずっと、永遠に生き続ける女性のことなのです」
「なんかよく判らないですね。とにかくわたしは彼女にもう一度会いたいのです」
「その方はなんと云う方でしたか」
「あっ、えっ、、、、」
「ほう、そうですか。あなたは名前も知らない女性と会いたい。名前も知らない女性に魅入られたわけですね。まさに思うつ、、、、いや、完璧ですね。永遠の女性としては。名前も知らない謎の女性として今後あなたの胸の奥で永遠に生き続ける訳ですから」
「もう、そんな話はいいです。とにかくわたしは彼女に会いたいのです。会わせてください。金がどうこうと言うのじゃないです。ただ会いたいだけなんです」
「無理です。会えません。会っていったいどうするんですか。結婚するですか。結婚して彼女を幸せにしてあげたいとでも思っているんですか」
「えっ、まあ」
「やめなさい。せっかく永遠の女性にめぐり合えたと言うのに。結婚して幸せにする女性は、他の人にしなさい」
「できません。わたしにとって彼女は理想なんです。美しくて賢くて性格が良くて、そして寂しげで、どことなく頼りなげなさそうで、わたしが守ってやらなければ駄目になってしまいそうな感じの女性なんです」
「まさに完璧だ。いや、失礼。とにかくその人に会うことはできません。そもそも名前も知らないんでしょう。どうして調べるんですか」
「そちらにプロフィールを書いたものがあるんでしょう。あるって聞きましたが。それで判るんじゃないですか」
「そんなものはもうありませんよ。最初にちょっと参考程度に作りますが、企画の性格上、パーティが終われば直ちにそれを破棄しますから。だから、あの日の出席者に関してはもう調べようがないんです」
「名簿やなんかもないんですか。あのときはけっこう場慣れした人もいたみたいですから」
「そういうものはありません。みんな初めての方ばかりです。第一わたしがあなたの住所や職業を聞きましたか。みんな同じ条件なんです。あの日はみんなそれぞれ、永遠の女性、永遠の男性を求めてやってきたんです。ですからパーティが終われば、たとえ出会えても出会えなくても、もうお互いに二度と会うことはないんです。というよりも、むしろ二度と会うことができないようにと一切の資料はその日のうちに破棄してしまうんです」
「わたしはどうしても納得ができません。彼女に合わせてください」
「しょうがない人ですね。せっかく永遠の女性を手にしておきながら、それをみすみす手放すんですか。結婚してどうするんですか。結婚て人生の墓場って言うじゃないですか。まさにその通り、結婚て生活なんですよ。そこには、綺麗、汚いもない、ねたみひがみ、愛憎入り乱れたごった煮のような世界があるだけなんですよ。だいいち奥さんが美しいからと言ってなんなんですか。周囲には自慢できて虚栄心を満足させることはできるかもしれませんが、三日見れは飽きると言うじゃありませんか。それに女性が本当に美しい期間というのは、何年、いや何ヶ月でしょう。それを過ぎれば、後は見る影もなく日に日に衰えていくのです。まるで自然から復讐されるようにね。それに逆らおうとでもしたら、修理費や維持費は相当なものになるでしょうね。それでなくても毎日の化粧代がかかっているというのに。それからあなたは賢い女性が好きみたいですけど、女性の賢さなんて当てになりません。女性の知性がかつて世界を動かしたことありましたか、ほとんどと言っていいくらいないんですよ。それにもし女性があなたより賢かったり、あなたより学歴が上だったら嫌でしょう。立場がないでしょう。それから、性格が良いと言っても、人間は所詮、誰でもが例外なく二面性を持っているものです。とくに女性の場合はその落差が激しんですよ。おそらくほとんどの男性は女性の性格の良さということに、女性特有のやさしさを求めているのでしょうが、つまり母親のようなね、でもそんな優しさはずっと続くわけではありません。とくに女性の二面性においてそれが現れる場合、強烈にでますからね。つまり、やさしければやさしいほどその反対側の冷たさというものは、きついですからね。まさに血も凍るような恐怖ですからね。だから、もしそれがヒステリーの場合なら、もう地獄ですよ。ようするに、なんだかんだ言っても女性は最後は情念に生きるものなんですよ。知性や性格の良さは少しも当てにもなりません。そしてみんなババアになり、さらに情念の激しい者はオニババアになるのです。それでもあなたは結婚したいんですか」
「いや、わたしは結婚したいとかしたくないとか言うのではなくて、彼女に会いたいだけなんです。もう一度会って色んなことを話したいだけなんです」
「つまり、付き合いたいと言うことですね」
「まあ、そういうことになりますか」
「まず付き合って、あわよくば結婚したい、ということですね」
「、、、、」
「結婚してどうするんですか。もし結婚しなければ、あなたはこれからずっと、彼女との夢のような美しい思い出を生涯持ち続けていられるんですよ」
「結婚しても、美しい思い出は残るはずです。それから結婚すればさらに美しい思い出を作れるはずです」
「甘いな。まあ、判りました。でも、わたしどもは一応契約上、それに手元にはもう資料がないため実際上も、これ以上なにも協力することはできませんが、よろしいでしょうか」
「良いですよ、もう。そちらには頼みません。自力で探し出しますよ。名前はわかりませんが、だいたいのことは判ってますから。何しろ理想の女性のためですから。どんなに時間がかかろうが、がんばりますよ」
「ご健闘をお祈りします。最後に老婆心ながら少し言わせてもらっても良いでしょうか」
「よろしいですよ。どうぞ」
「立花さん、あなたはどうも最後の最後まで、理想の女性と永遠の女性を混同していらっしゃるようです。理想の女性というのは現実的に申し分なくすばらしい女性のことです。もちろんこれは相対的にですが。ところが永遠の女性というのはこれとはまったく違うんです。絶対的にすばらしいのです。長くもあり短くもあるこの人生において、いくたびか、ふと懐かしくもあり悲しくもある甘美な思い出として、押入れの奥にしまいこんではいるが、いつでも開いてみることが出来る秘密のアルバムのように、あなたの心の奥底で思い起こすことができる女性の面影のことなのです。それはあなたに、ひそかに、人生の意味を見い出させたり、また生きる元気や慰安を与えたり、ときには密かにあなたの支えにもなったりするような女性の面影のことなのです。それはあなたが会いたいと思えば思うほど、恋焦がれれば焦がれるほどに、その永遠の輝きを増していき、そしてもう二度と絶対に会うことができないからこそ、永遠の女性、永遠の恋人となるのです」
「、、、、、、、、、、、、、」