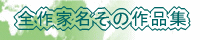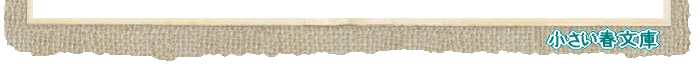狩宇無梨
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
第七紀元745年(注1)秋
その朝、マシルは青い落ち葉の混じった道を走っていた。
砂丘のように光る屋根を、幾十もの柱で支えた校舎に飛び込むように入ると、そこからは静かに歩き、今日で最後の授業となる教室を目指した。
そしてTR3と文字が刻まれた床の上を通って、二つの段差を降り、周囲が丸い石柱と電子機器で囲まれた小さな広場のような教室に入った。
授業はすでに始まっていた。マシルは遅刻したのだ。でも、誰もそのことを気にするものも、とがめるものもいなかった。
生徒はあわせて十二人、それぞれ思い思いの場所に、自由であるかのように、高さと形が違う椅子に腰掛けていた。
生徒たちに話しかけている男は、彼らの兄のように若く、普段はセイダ先生とかセイダ指導員と呼ばれていた。マシルは椅子を使わずそのまま床に腰を下ろした。
十三歳のマシルたちの授業は地球環境についてだった。
呼吸が落ち着くと、ようやくマシルの耳に周囲の声が届くようになった。
セイダ指導員の声が響いた。
「それでは誰かに、それぞれの良い点や優れている点を、それにどっちが好きか述べてもらいましょう。では、ケルスから」
ケルスが上げた手を下ろしながら話し始めた。
「僕は電気植物(注2)のほうが優れていると思います。核融合から電気を取り出すためには、巨大な施設が必要です。そのためには莫大なお金が掛かります。でも、電気を発生する植物から電気を取り出すためには、それほど費用はかかりませんからね。それで、僕は電気植物のほうが好きです」
「では、他に、、、、カラム」
「私は、核融合のほうが優れていると思います。なぜなら、電気植物のほうは、天候に左右されるのでとても不安定です。それに比べたら、核融合は常に安定した電力が得られますから」
「はい、セイダ先生」
「セキル、どうぞ」
「私も核融合のほうが優れていると思います。なぜなら核融合のほうは環境に与える影響が、すでに、だいたいですけどね、それほどでないことが判っているんですが、それに比べて電気植物のほうは、まだ判らないことがいっぱいあるということですから。好きなのは電気植物なんですけどね。だって落ち葉が青くてきれいだがら」
セイダがさらに発言を促すように見まわすと、ラクルがゆっくりと手を上げた。
「はい、僕は、好きでも嫌いでもないんでが、電気植物のほうが断然優れていると思います。今環境への影響を問題にしているようですが、でもそれはもう解決されていると思います。なぜなら、電気植物が発明されてから、もう何年になるんですか、ええと、、、、何千、何万年、、、、それで、そのあいだに何か問題がありましたか。ありませんよね。だったらそれはもう何にも問題が無いということではないですか。ですから、これからは、莫大な費用が掛かる核融合発電はやめて、電気植物発電をどんどん進めたほうがいいと思います」
「はい」
「では、ジュンカ」
「僕はラクルの意見に反対です。なんにも問題が起こってないというけど、それはまだ起こってないというだけです。これから起こるかも知れません。遺伝子を操作して人工的に作ったものの影響を見るには、もっと長い時間が必要だと思います。もしかして、この先、電気植物が勢力を伸ばして、他の植物を絶滅に追いやるかもしれませんから。そうなったら地球の生態系は壊れ、植物だけでなく人類もその他の生き物も、たぶん絶滅です」
「それは考えすぎだよ。でも、もし仮に電気植物が勢力を伸ばしたとしても、人間は地球を守るためにちゃんと対策を考えるよ。今までだって人類はそうやって何度も地球の危機を克服してきたんだからさ」
このラクルの発言には、納得したように頷くものがでたので、少し沈黙が続いたが、セイダはもう少し違う意見が必要な気がした。
「他に、意見のある人は、なんか興味なさそうにしているリセ、君はどう思いますか」
「ええと、どっちが優れているのか、私にはよく判らないです。今まであまり考えたことが無いですから」
「リセらしい意見ありがとう。でも、これからはもう少し社会について考えたほうが良いでしょうね」
それを聞いて周囲から笑いが漏れたが、セイダはさらに続けた。
「たぶんリセは他のことに興味があるんでしょうね。大事なのは人それぞれ何かに興味を持っているということですから。たとえ年齢が同じでも、同じようなことを考える必要はないですからね。では、他には、はい、マホミ」
「私もよく判らないです。セイダ先生自身は、どっちが優れていると思うんですか」
「うん、難しい問題だ。正直言って私にもよく判らないんですね。それぞれに長所や短所があって専門化レベルでも、未だに結論を得ていないぐらいですから。おそらく私たち人類にとっては、今後の最大の課題となるでしょうね。ええと、実はですね、今なんの為にこんな討論をしているかというと、それは、どちらが優れているかの結論を出すためではないのです。つまりですね、皆さんがこれから成長して、大人になって、より良い人生を送っていくためには、おそらく毎日のように遭遇するに違いない疑問やトラブルを解決しながら、生きていかなければならないことは確かです。そこですね、前もって、なにかの問題を提起して、そしてそれに対して意見を出し合うことによって、このような問題を解決する能力を身につけるために、訓練として行っているのです。ですから結論そのものは、今はそれほど重要でないのです。これまでは友達についてとか、家族についてとか、学校についてとか、君たちにとって身近なことをやってきましたが、今日は思い切って地球的な規模の問題についてやってみました。その結果、個人差はありますが、皆さんには、もうだいぶその問題解決能力が身についてきていると実感しました」
「はい、セイダ先生、他のことを質問しても良いですか?」
「良いですよ。ヘレス、どうぞ」
「昨日お父さんが言ってました。大昔は、学校は勉強するところだって、今みたいに遊んでばかり居なかったって、それ本当ですか?」
「どうもそうらしいですね。でも、心配しないでください。君たちは遊びながら、知らず知らずのうちに、生きていく上で本当に役立つものを身につけていますから。詳しいことは、もうちょっと後で話しますが。他には、、、、たぶんこれが最後の質問になると思うけど、、、、はい、マシル」
「昨日、地球の地図を見ていたんですが、判らないことがあったんですよ。ユーラシア大陸の南のほうの太平洋上に、緑色の雑巾のような形をしたシミのようなものがあるんですが、それはいったいなんですか?それにはなんにも書いてないんですが、誰に聞いても判らないというんですが」
「それね、ええと、それは、おそらく完全立ち入り禁止地域ですね。たぶん濃い緑色になっていると思うんですが、人間がどんな理由があろうと、絶対に立ち入ってはいけないという地域です。なんか大昔に決められたみたいですね」
「島なんですか?」
「島であることは確かです」
「人間は住んでいないんですか?」
「いませんね。完全立ち入り禁止地域ですから」
「いつからですか?」
「うっ、よく判らない。とにかく大昔からそうなっているみたいだ」
「なぜ、立ち入り禁止地域なんですか?」
「ふう、詳しいことは私にも判らないが。たぶん地球の環境を考えてのことじゃないかな。かつて人間は自然を犠牲にして、というか破壊をして、生きていました。でも、そのうちに、こんなことを続けていたら、自然だけでなく、人間そのものも滅んでしまうということに気がついて、自然を積極的に保護しようと考えたわけです。そしてそのために最も良いことは、人間が自然に立ち入らないことだという結論に達したのです。そこで世界のところどころに、
A種立ち入り禁止地域(注3)、
B種立ち入り禁止地域(注4)、
それから、
完全立ち入り禁止地域(注5)
と、三段階に分けて設けられたわけです。
A種というのは、希望して許された者だけが入れるということ、
B種というのは、管理者だけが入れるということ、
完全というのは人間であるかぎり誰であっても永久に入れないということです。おそらくマシルが訊いているところは世界に三箇所ある完全立ち入り禁止地域の内のひとつだと思います」
「そこには本当に人が住んでいないのですか?」
「いません」
「今どうなっているかも判らないんですか?」
「判らないです。それが完全立ち入り禁止地域の意味ですから。もし、マシルがこれ以上知りたかったら、世界資料館にアクセスして自分で調べてください。そこには詳しいことが出ているはずです。ええと、それではですね、今日で私の授業も終わりですから、次に、君たちに今までほとんどしたことがなかった長い長いお話しをしたいと思います。さて、いよいよ、君たちは今日でこの学校は卒業ですが、卒業後は、君たちが選んだそれぞれの道で、今までに学んだことを参考にして、生きるためにさらに、より多くのものを学んでいくことを願っています。これまで君たちがこの学校で学んだことは、これから君たちが成長して大人になり、そして、そのときに人間らしく生きていくうえで、本当に必要とされるたくさんの知恵や技能を身につけるためにですね、準備されていなければならないとされている基礎的なことを学んだに過ぎません。君たちにとってはこれからが学びの本番です。人間が人間らしく生きて行くためには色んなことを学んでいく必要があります。でも、学ぶといっても本を読んでいれば良いというものでは決してありません。真に学ぶためには、その本人の努力や忍耐力が必要なのです。その努力や忍耐力を養成するのが、この学校の目的だったのです。これまでのやってきた沢山のプログラムのおかげで、さっきも言ったように、君たちにはその能力がすでに身についています。ですから、君たちは自信を持って次なる道を進んでください。それでは、ついでですからここで君たちがちょっと驚くような話をしますよ。かつて教育というものは、現在とはまったく違うものだったのです。学校というものは今と同じようにありましたが、君たちが今自分の家で自由にやっているようなこと、たとえば本を読んだり、文字を書いたり、計算の仕方を覚えたり、過去の出来事を記憶したりすることを授業でやってました。しかも、計算は出来るだけ早くできるように、記憶することは出来るだけ多くのことが記憶できるようにと、それらのためにより多くの時間をかけてですね、半ば強制的にやらされていたようです。そして、その成果を見るためにテストが行われたのです」
セイダが生徒たちの怪訝そうな表情に気がついて話を止めると、ラクルがつかさず言った。
「今だって、ときどきテストをやるじゃないですか」
「そうか、君たちはまだ経験がないから判らないか。その当時のテストと今のテストは根本的に違っているんですよ。今のテストは、君たちがどんな能力がどの位あるかを調べるためのものですが、その当時は生徒たちが、どれくらい早く計算できるか、どれぐらいいっぱい記憶しているかを調べるためです」
「それを調べてどうするんですか?」
「うむん、まずは、誰が劣っていて、誰が優れているかを判断するためのようです。その当時はですよ」
「どうして判るんですか?」
「テストの結果に点数をつけるんですよ。それで高ければ高いほど優秀だということがわかるらしいんですよ」
「へえ、というと、優秀というのは良いことなんですか?」
「当時はそのようだったようですね。現代では優秀であることは、個性的であるという意味以外には、それが特別に良いことだなんて考えられないですがね。とにかくその当時は何かと良いことがあったみたいですよ」
「へえ、変なの」
「今はやりたいという意欲さえあれば、誰でもどんな職業につけますが、かつては優秀でなければ就けないという職業があったみたいですよ。たとえば、今はあまり人気がない肉体の病気を治す医者とか、犯罪者を裁く裁判官とか。そこで、その優秀さを計るためにテストが行われたようです」
「本当に優秀だったんですか?」
「さあ、どうなんでしょう。点数は高かったことは確かなんでしょうが。それで優秀かどうかは、、、、」
「それじゃ、そのころは優秀でなければ生きていけないということだったんですか?」
「もちろん、そうじゃないですよ」
「だったら、点数が悪くたって良いじゃないですか」
「なるほどね。でも、さっきもいったように、優秀だということは何か良いことがあったんですよ。それは誰もが望むような良い職業につけたということですよ。その良い職業というのは、つまり、判りやすく言うとですね、お金がいっぱい入ってくる職業という意味なんですよ」
「なんだ、そういうことか」
「お金って?」
「そうか、君たちはお金というものを見たことも使ったこともないんですね。今は無限信用社会(注6)になってから必要ないんだけど。私は歴史博物館で見たことがあるんですが、昔は物を買うときにそれを使っていたんですよ。ほとんど紙とか金属で出来ているだけど。リセ、今度余裕があるときにぜひ博物館にいってみて見るといいよ」
「お金っていっぱいあったほうがいいんですか?」
「当然だよ。あれば欲しい物いっぱい買えるじゃないか」
「セキル、不思議そうに首をかしげているけど、どう思う」
「よく判らないです」
「そうですね。それでは話を元に戻します。そんな訳で、テストで良い点数をとる子供は、将来より良い生活ができるということで、誰もが良い点数を取ることを目標にしたわけですよ。古い記録によるとですね、その当時のほとんどの子供たちは一日に十時間以上も勉強してたそうです」
「えっ、信じられない。やりたくない人はどうするんですか?」
「周りが皆やっているから、自分だけやらないということも出来なかったみたいですよ。 アッ、そうそう、当時は現代のように、何を勉強するかは子ども自身が決めるのではなく、周囲から賢いと言われている大人たちが集まって会議をして、子供たちに何を勉強させるかを決めていたそうです」
「今の時代に生まれてよかったな」
「僕は絶対にやらないな」
「私もやらない、十時間なんて」
「その当時の子供たちは、お金がいっぱい入って来る職業に就けるというだけで、そんなに勉強したんですか」
セイダが笑みを浮かべながら話し続ける。
「とにかく、当時は計算が速くできたり、色んなことをいっぱい記憶していることが良いことだとされていましたからね。 それに、大人たちは、そういう子供たちを社会全体で褒めたみたいなんですね」
「僕はそれでもやらないな」
「褒められるから勉強するなんて、ご褒美をもらって芸をする動物みたいじゃないか、その頃の子供ってまだ原始的だったんじゃない」
「さあ、どうでしょう。 原始的かどうかは疑問ですけど。それから当時は、子供たちを勉強させるもっとも効果的な方法として、そのテストの結果を公表するという方法を取っていたそうです」
「ええっ、どうして?」
「どうしてなの?なんかイヤ」
「なぜ、公表するんですか」
「それは、子供たちを競争させるためらしいです。とにかく当時は、点数の高いものは学力が高い、学力が高いものは優秀な人間であり、その優秀人間は社会の役に立つというとことを唱える学者や政治家たちが沢山いて、学力主義派と呼ばれている人たちなんですが、それで、そういう優秀な人間こそが国家の発展に貢献する望ましい人間として、ますます歓迎されるようになり、そういう人間をたくさん生み出すためなら、競争までして勉強することが最高の価値と思われていたようなのですよ。 つまり、当時はそうすることが人生を生き抜くためにもっとも必要なことだと考えられていたからです。 そこで子供たちは、出来るだけ早く計算できるように訓練させられたり、できるだけ多くのことを記憶するように教え込まれたようです。 当時はそのような教育方法のことを詰め込み教育といったそうです。
そのときケルスがすばやく手を上げた。
「 はい、ケルス」
「コッカって何ですか?」
「国家ですか?それはですね、むかし世界が三百ぐらいの地域に分かれていた頃に、そのひとつの地域を国家といったそうです。 それらの国家同士は、経済や軍隊やスポーツでお互いに競争していたみたいですね。ときには何かの原因で仲が悪くなったりして戦争というものもしていたみたいですね。とにかくその当時は、よい生活をするには国を発展させて、よその国に競争で勝つ必要があったみたいです」
「はい、質問、戦争って何ですか?」
「そうですね。 人と人が集団で殺しあうことですかね。大昔は頻繁に行われていたみたいですよ」
「おじいさんに聞いたことがある。 大昔人間が狩猟生活していた頃、分け前を多く取ろうとして棒を持って殺し合いをしていたって。 野蛮な時代があったんだよ」
ラクルが誰よりも不思議そうな顔で話し始めた。
「今まで僕たちは、人間は人それぞれ色んな能力を持っていて、そしてその能力にも差があるということを教わってきましたが、なぜその能力差をいちいち公表しなくてはいけないのか、本当に理解できないんですが」
「なぜなんでしょうね。私もまだそこまでは調べてないんですが、そうする必要があったからなんでしょうが、現代ではまったく考えられないことですけどね。それでは、ええと、話は元に戻ってと、、、、、でも、そんなことを続けているうちに、その詰め込み教育が人生に於いて何の役にも経たないというだけではなく、人間の精神的発達を妨げるということが、だんだん判ってきて、とくに、その精神的発達を妨げる結果として、色んな精神的な障害を引き起こしたりするだけでなく、人間としての生きる気力や能力までも萎縮させるということ、さらにはその悪影響として、人間の生殖能力をも減退させて、全般的には、人間性そのものを、そして人間社会そのものを減退させ、衰弱させるということが判って来たのです。それはそうでしょうね。いま君たちにそんなに嫌がられているくらいですから。 もっとも現代は、子供たちは学校に行くのも行かないのも自由な上に、子供たちはまず自分の持っている能力を伸ばすために必要なことを学び、先生はそれの手助けするという方法に改善されていますから、そんな深刻な問題は起こらないでしょうが。とにかく当時は教室という狭いところに大勢閉じ込められるようにして、ほとんど強制的に勉強させられたようですから、そういう影響が出たんでしょうね」
「どんな精神的な障害が出たんですか?」
「その当時の歴史書を読んでみると、こんなことがあったようです。 たとえば、勉強をしなくなったり、学校に行かないだけでなく外出が出来なくなったり、人と話せなくなったり、食べ物をまったく食べれなくなったり、またはその逆にものを食べ続けたり、自分の体を自分で傷つけたり、現代ではとても考えられないような異常行動が頻繁に起こったみたいですよ。 でも、そのくらいならまだいいほうで、ときには、自殺に追いやるような悪質ないじめがあったり、教室で銃を乱射してクラスメイトを殺す者がいたり、学校に爆弾を仕掛けて、皆殺しにしようとしたりする子供たちが現れたそうです。 今では、それらは全部、テストや詰め込み教育が原因と考えられています。 今、君たちは信じられないように顔をしていますが、もちろん、すべての人がそういう行動をしたわけではないです。 でも、その当時の作家の本には、このように書かれているのを以前読んだことがあります。
『ほとんどの人はテストの悪夢に生涯苦しめられ続けている。』
と、そんなに笑わないでください。
きっと昔の制度は、現代の伸び伸びとして教育制度のもとで育った君たちから見れば、信じられないくらい、抑圧的で不合理なものに見えるんだろうけどね」
このときはラクルが勢いよく手を上げていった。
「はい、先生、昔は学校に行くのは強制的だったのですか」
「強制的というか、義務だったようですね。 いま君たちが、友達と遊んだり親の仕事を手伝ったりすることが、半ば強制的で義務的であるようにね。今は勉強は、家でやっても良いし学校でやっても良いことになっているが、とにかく昔は、学校に行くのも、勉強するのも、テストで出来るだけ高い点数を取るのも強制的で義務的だったようです。 でも、大昔の大昔は、子供たちは学校なんかに行かないで、毎日友達と遊んだり親の手伝いをしていたんですけどね。その意味では現代の教育方法は大昔に戻ったということなんでしょうね」
するとリセが不思議そうな顔をしてつぶやくように言った。
「昔のテストって辛いものだったんだ」
「現代のテストはみんな楽しみながらやりますからね。 ちなみにですね、昔はさらに上の学校に行くためには受験といって必ずテストをやりました。 そして点数の高い順番に進学できたのです。なんか変でしょう。 今とまったく逆でしょう。いまは勉強が必要とされる者が、上の学校に行けるのですが、その当時は優秀な者だけが行けたみたいです。とまあ、色んなことがあって、結局、そんな問題がありすぎる教育は止めて、人間が人間らしく生きていくために必要なことを身につけさせるという現代のような教育に変ってきたのです。
つまり、いつの時代でも、人間が自分たちの社会を発展させ、そして豊かで人間らしく生きていくためには豊かな発想で社会の変化に対応でき、そして次から次へと起こる問題やトラブルを処理することが、絶対的に必要だということが判ってきたのです。そこで、そういう豊かな発想力と問題解決能力を持った人間を教育によって養成しようと考えたわけです。そこでなんですが、では、その豊かな発想力と問題解決能力とは、具体的にはどういうことか、ということになったのですが、それは何よりもまず本人が個性的であり、その上で、未来のことを考えたり、物事を分析したり洞察したりする能力でした。そこで、そういう能力を養うにはどうしたら良いかという研究が、沢山の学者や専門家によって行われるようになったのです。その結果、色んな方法が考えられて実践されたのです。たとえば子供たちが集まって集団で問題を解決したり、記憶に頼る詰め込みではなく、基本的なことを体を使って反復的に学ぶということが、子供たちの考える能力を養うのに最もよいということになり、世界各地で盛んに取り入られるようになりました。ちなみに個性を伸ばす教育の重要性は、そのだいぶ以前から言われていましたが、本格的に行われるようになったのはこの頃からようです。ところが、その方法も、どの程度それらの能力が身についているかとということを判断するのに、やはり従来のようにテストを行ったのです。 テストの成績のいいものはそういう能力が身についているというわけです。 でも、それは所詮、紙の上での試験で単なる目安に過ぎません。実践はまた別のことです。 実践というものはもっと総合的で人間的なものです。 それに、その当時の個性を伸ばす教育といっても、今のように子供に合わせたものではなく、そのことを専門に研究する大人によって、世界の発展のために役立つような人間を作り出そうという理念の下で考え出された方法によって行われていたので、あくまでも形式的で気休め的なものにすぎず、実践的にはそれほど役立たないものでした。 なぜなら、テストの結果は公表されるために、以前のように高い点数を取るものは優秀な人間とみなされ褒められるので、誰もがそうなりたいと思うようになり、いつのまにか、そこに以前のような競争が働くようになり、結果的に再びテストで高い点数を取るためのテクニックを教える授業に戻っていったのでした。 そして以前と変ることのない管理的で抑圧的な教育がふたたび行われ続けたのです。 本来テストというものは、現在のようにあくまでもその本人の理解度を調べるために行われるものに過ぎないのに、すぐ高い点数を取ることを目的とするように変っていくようです。それもみんな、現在では誰も信じていないようなこと、いわゆるテストで高い点数を取るものは優秀であり、将来はより良い人生を送ることが出来るだろうと、迷信のように信じられていたからなのだろうね」
マシルが手を上げて言った。
「先生、どうしてテストで点数をつけると、管理的で抑圧的な教育になるんですか」
「それはですね、子供というものは、人それぞれ色んな才能を持っているにもかかわらず、テストの点数を基準にして、どの子供がより優秀であるかないかを順位を決めて教育するということは、ものすごく管理的なんです。 しかも、とても安易な。 というのも、その方法は指導者にとってはとても簡単で楽だからです。
だから、そんな理由でもって教育者たちが、生徒たちにより高い点数を取るように競争させることは、とんでもなく無責任であるだけでなく抑圧的でもあるのです。 でも、やがてそんな教育も行き詰まりを見せ始めました。 というのも、依然として子供たちの精神的な問題や、それによって引き起こされる問題が解決されないだけでなく、さらに深刻な問題が起こり始めたということです」
「その問題というのはどんなことなんですか」
「子供から大人まであらゆる世代にわたって自殺者が増えたってことでしょうか。 人間が豊かで人間らしく生きるために考え出された方法が、かえって人間性を萎縮させて生きる力を奪っていったのです。
それはそうでしょうね、なぜなら、その当時豊かで人間らしくというのは、国家同士が競争していたために、それに打ち勝って経済的に豊かな生活をする、ということと同じ意味になっていましたからね。それで豊かな発想力と問題解決能力を持った人間を養成するというのは、本来の豊かで人間らしい生活をするためではなく、競争に打ち勝つような人間を養成するということに、知らず知らずのうちにすり替わっていたのです。ですから新しい教育というものは、それ以前の詰め込み教育に、新たに考え出された方法が付け加えられたものに過ぎませんでした。 そのため、実際は以前よりもはるかに管理的で抑圧的なものになっていたのです。もちろん自殺者が増えたという原因には、いまでこそ子供の成育には有害とされているバーチャルゲームが、その当時は無制限に行われていて、それが精神の成長を妨げたことも深く関わっていたようなんですが。 まあ、そういう訳で、結果として、子供たちの勉強時間も増えていきました。 一日に二十時間ぐらい勉強したという、その当時の記録もあります。 今、君たちはどの位勉強してますか?」
「僕は三時間ぐらい」
「私は二時間ぐらい」
「そうでしょうね。現在はそれくらいで充分なんですよ。
でも当時は、生きていくためには本当に勉強しなければならなかったんですよ。 それにはそうせざるを得ない状況におかれていたみたいですけどね。 なにせ、当時はいまと違って人間は住む地域によって話す言葉がちがっていましたから、競争に打ち勝つような人間として生きていくためには、最低でも二ヶ国語以上を話さなければならなかったみたいですよ。 それに、現在は、計算というものは、決して早くなくても、とにかく最終的には出来さえすればいいことになっていますが、当時は早く出来れば出来るほど、問題解決能力があると看做されていましたから、そのような能力を養成する教育が、ますます盛んになって行ったようです。 でも、やがて、こんな教育ではだめだということに多くに人が気づくようになりました。 そしてようやく真剣に、人間生きていくためには、何が必要か、そのためにはどんな教育が必要か、ということが考えられ始めたのです。 そして、本当の意味で人間的な教育が考え出され、行われ始めたのです。 では、その人間的な教育というのは、 まずは、子供が生まれつき持っている個性を最大限に伸ばすこと、 それから、その本人の生きる力を養成するということでした。 まず個性を伸ばすことですが。それまでとちがって、徹底した子供に合わせるものでした。
れはそうでしょうね。人間は人によって感じ方も考え方も違いますからね。具体的には、子供の好きなことを子供のやりたいことをやらせることでした。 そして、そのためには教育者は徹底して裏方にまわって手助けをするということでした。 まさに現代の教育の原型となったのですが、現在はさらに進化して、子供の嫌なことはやらないでもいい、とにかく好きなことだけををやれば良い、ということになっていますが。そして、これは何よりも、私たちの社会が当時よりも進化発展して、より多様な社会になったおかげなんですが。 それがどんなに自由にのびのびと健康的に子供たちを成長させるという、本当の意味での人間的な教育ということが判ったのです。でも、それだけでは従来の教育方法の延長線上にあるだけです。 たちが色んなことを学ぶのは、私たちの人生の目標や夢を実現するためですが。 その目標や夢を生み出すのは、まさに私たちの生きる力なのです。 そこで、本人の生きる力を養成するということが、子供たちの教育に取り入れられることになったのです。
ではその生きる力とはどういうものでしょうか。 イサム、なんだと思いますか」
「、、、、、」
「ちょっと、むずかしかったかな。 生きる力というのは、基本的にはまず何かを好きになったり誰かを愛したりすることから生まれてきます。 その愛することには大きく分けて二種類あります。 まずは自分を愛するということ。では、自分を愛することが出来るようになるためには、自分が身近にいる誰かに愛されることが必要です。 自分が愛されるに値する人間と思うことが出来るからです。 それから社会が好きであるということ。 社会が好きであるためには、家族であり人の集まりでもある身近に居る人たちが、まずは愛し合っている必要があります。 そうすれば、それよりも大きい人の集まりである社会は好きになるでしょうから。もし身近に居る人たちが憎み会っていたなら、その人間にとって社会は好ましいものとはならないでしょう。 むしろ興味のないもの不愉快なもの否定すべきものとなるだけでしょう。そんな社会のもとでは誰も生きたいとは思わなくなるでしょう。 それではそんな社会は衰亡するだけです。 人間は長いあいだ豊かで、便利で、快適で何の問題もないような生活が幸せな生活と考え、それを求め実現してきました。 そして、そんな幸せな生活から、生きる力が要請されてくると考えていましたが、それはとんでもない誤解だったのです。むしろその逆で、不便さや不快さや貧しさや逆境や抑圧や差別から、そして失敗や挫折から生まれて来ることに、だんだんとに気づき始めたのです。つまり、そのように悪い環境にあっても、それを跳ね返すような深い愛情のもとで育てられていれば、どんな条件下でも生きられるようなたくましい人間に育つということが判ったのです。そんなわけで詰め込みでもない、生きる能力をテストで計るのでもない実践的な愛情関係に支えられた教育が始まったのです。そして、それをふまえた上でさらに職業体験というものが重要な柱として付け加えられるようになりました。以前のそれは教育的にお膳立てされたもので、半分遊びのようなものでしたが、新しく始まった職業体験というは、実際に、大人に交じって働きながら、その仕事の難しさや大変さを実感して、将来その仕事に就くためには、これからどのようにことを勉強したらいいかを本人が実践的に学ぶものでした。ほどなく、このような教育によって、それまで理想とされていたことが達成されるようになったということです。それは、人間は自分の好きなことをやっていれば、それでもう充分に人間らしく生きられるということです。 もちろん子供たちが自由になったぶん、それまで好ましくないとされていたことも認められるようになりました。 たとえば、子供のときの暴力的な喧嘩やイジメなどが子供の成長には必要不可欠なこと、それは排除されるべきものでは決してなく、乗り越えられるべきものとなり、出来るだけ自然な形で教育の場に組み込まれるようになりました。
でも、ここまで来るまでにはかなり紆余曲折があったようです。というのも、今とはまったく逆の考え方が盛んにもてはやされ、実践されていた時期があったからです。それは、その原因がよく判らないような心の病があらゆる世代で出始めた頃、なぜそうなるかを考えた学者や専門家たちは、その原因は、子供の頃の喧嘩やイジメ、そして、そのほかの数限りない悲しいことや辛いことが原因だと考えるようになり、子供たちを、そういうことを経験しないような環境で育てれば、きっと将来にわたって心の病にかかることはないだろうという考えです。でも、その実践の結果、どういうわけか、皮肉としか言いようがないのでが、まるでアリ地獄に陥ったように、その病気発症の数が減少するどころかますます増えて行ったそうです。まあ、これもそのうちのひとつなんでしょうけどね、よくしようとして返って悪くなったという話しが、歴史上たくさんありますからね。たとえば、この世から悪をなくそうとして良いことだけををしようという運動しているあいだは、決して犯罪はなくならなかったとか、世界が平和になることを目指して平和運動をしているあいだは、決して戦争がなくならなかったとかね。それからこれは似たようなことなんですが、その当時は教育費にお金をかけれはかけるほど良い教育が出来ると考えていたようです。それで、子供たちには勉強に必要なあらやる参考資料が与えられるだけでなく、設備の整った校舎で、良い食べ物や、良い衣服も与えられて勉強していたようです。ところが結果はまったく逆のようでした。それはあるところまでは真理なのですが、ある限度を越えると効果は下がり続けるばかりだったのです。これも、良くしようとして返って悪くなったという、代表的な例でしょうね。ちなみに、参考までにいっておきますが、隣町のセイハンでは学校の校舎はないそうですよ。だいたい二週間交替に生徒のうちに集まって勉強しているそうです。いや、それどころか、大陸の西の方のエーユでは公的な教育システムがないらしく、先生といわれる人もいないそうです。ええと、では話は元に戻りましょう、でも結局は、現在行われている教育方法に落ち着いたわけなんですがね。そのおかげで人間は精神的に衰弱することもなく、より健康的に、そしてより創造的に生きられるようになったというわけです。」
「はい、素朴な質問なんですが、どうして昔は、そんな子供たちを苦しめるような、それに後になって何の役にも立たないような詰め込み教育を良いと思っていたんですか。」
「たぶん、それは人間の知恵は頭から生まれると思っていたからなんでしょうね。だからその知恵の元となる知識を頭に詰め込めば、知恵のある人間になると考えたのでしょうね。ほんとうの大昔はそうでもなかったみたいですが。それで、そういう教育が相当長い期間なされていたみたいです。でも、先程も話したように、それが原因で精神的な障害と思われるようなことが頻繁に起こってきたわけですから、とにかく昔は人間の知恵に対する根本的な誤解があったみたいですね。誤解といえば、豊かな発想力という言葉に対しても誤解があったようです。当時は豊かな発想力を考える力と思っていたようです。そして、その考える力は、読書と作文によって身につくと考えられていたようです。今から考えればとんでもない間違いです。考える力はそんな既成概念的な知識や、形式論理的な方法からは決して身につくことないのです。人間の本当の考える力とは、後で詳しく話しますが、私たちを取り囲むこの複雑で不可解な混沌とした世界と、私たちの生きる力が衝突するときに生まれてくるものなのです。まずは私たちの健全な生きる力が在ってこそ、私たちの健全な考える力が養成されてくるのです。ましてや私たちの豊かな発想力というものは、生きる力だけではなく、より個性的であったり、より好奇心が旺盛で在ったりするところから生まれてくるものなのですから。それで、考える力ということに対するこのような間違った認識は、豊かな発想力を持った人間を養成する、という現在のような教育方針に転換しようとしたときには、少なからず障碍となったようです。いったいいつ頃からこんな勘違いがはびこったのか判りませんが、とにかく相当長い間続いたようです。ところがです、そんな時代が長く続いているうちに、
『知恵は肉体に宿る』
とか、
『生まれたときにすでに宿っている』
なんていう者が現れてきて、初めは誰も、そんなタワゴトと思って相手にしなかったのですが、どうもそれは真実らしいということに皆が気づいてきて、だんだん社会に受け入れられるようになったのです。私には、その
『知恵は肉体に宿る』
とか、
『生まれたときにすでに宿っている』
ということの正確な意味は、あまり文学的すぎてよく判らないのですが、君たちが判るように科学的に言うなら、
『知恵は肉体を通して』
つまり、
『経験を通して身につく』
という意味のようです。それから、
『生まれたときに既に宿っている』
というのは、つまり、こういうことのようです。
私たちを取り囲む宇宙というのは、予測のつかないような複雑な変化をしながら進化発展してきました。
そして数え切れないほどの多様な植物や動物を生み出しながらも、未だに計り知れないような無限の可能性を満ちている混沌とした世界のようです。
だから、そこでですね、その進化の過程の最終段階に位置する人間も同じような構造を持っているに違いなく、つまり、複雑で多様な、その混沌とした世界に対応しながら、その色んな才能を発揮できる人間の無限の可能性のことを知恵と見て、人間はみな誰でも生まれたときにはすでにその無限の可能性を秘めているということを言っているようです。問題なのは、その無限の可能性でもあり、そして人間が生まれたときにすでに持っている知恵を、環境や教育によってどのように具体的に表現させるかのようです。それを昔の人は間違った考えに支配されていたために、無理やりに決まりきった枠に押し込めようとして、いじりすぎたために、かえって子供たちを抑圧して萎縮させる結果となり、本来なら当然のごとく進むべきものをこじらせ、その発達を妨げたために、その知恵の具現化にことごとく失敗したというわけのようです。ということからすると人間は知恵的には、今も昔もあまり変っていないようなのですね。このことを裏付けるかのように、こんなことを言った大昔の哲学者がいます。
『人類は、歴史が始まる前にすでに完成していた。』
ということをね。
このように知恵というものは肉体そのものだということですが、それに比べて知識というのは、そのような混沌とした世界を私たちの頭で抽象し分析して得られたものに過ぎず、それは世界を都合の良いように単純化して認識する方法に過ぎないというのです。なるほど、それなら、頭を通して知恵から生まれた知識を再び頭に返しても知恵は生まれないということだから、詰め込み教育が人間が生きていくためにはほとんで役立たないわけだ。
いわば、知識は人間が人間として生きていく上では基本的なものであり、また多少は必要ではあるようなんですが、決して絶対的なものでも、またすべてでもないようですね。当初は、知識の詰め込みが大切だと考える学力主義派と、知恵、つまり、まずは子供たちを愛情の元で育てながら、生きる力を養成しようとする生きる力派との間で激しい論争が行われたそうですが、最終的には生きる力派勝利を収めたようです。その勝利の最大のの要因は、学力というのは個人差がありますが、生きる力というものはそれほど個人差はなく、生まれたときから誰にもみな平等に備わっているために、ほとんどの人には生きる力派の主張が受け入れ安かったからのようです。最初は、学力主義派が支持されていたんですが、次第に生きる力派が優位を閉めるようになり、最終的には、生きる力派が完全に勝利を収めたようです。その決定的要因は追跡調査でした。それまでは詰め込み教育で優秀な成績を収めていたものが、その後社会に出てどうなったか、つまり、実社会でどんな活躍をしたかが判らなかったのですが、その追跡調査によってはっきりと判ったのでした。それによると、学力が高く優秀とされていたものと、その後社会で活躍したものとの間には何の相関関係もなかったということでした。その結果は衝撃的なものだったようです。でも、もっと衝撃的だったのは、学力が高かったものと、自殺者との間には正の相関関係があったことでした。では、そのことは何を意味するかというと、そのような詰め込み教育が、良くも悪くも人間の精神の発達や形成にどのくらい影響を及ぼすかは、人によって違うだけでなく、その典型的な悪影響とされている心の病、つまり精神病として発症する時期も人によってまちまちなのです。肉体の病気で言えば潜伏期間ですが、それが違うということです。若い内に発症する人もいれば、壮年になって精神的ストレスかなんかのちょっとしたきっかけで発症する人もいるのです。若い人は原因も単純でなんとか治療できるのですが、壮年の人の原因は色んなことが複雑に絡み合っていて治りづらいそうです。その場合は自殺につながる割合がかなり高かったようです。いずれにせよ、詰め込み教育というのは競争の結果をテストで計ろうとするものですから、いつ発病するかもわからないように精神の病に感染させたり、そのうえ不必要な劣等感だけではなく、ゆがんだ優越感も植え付けたことは確かなようです。そのようなわけで、もう誰も学力主義派の言うことは信じなくなったのでした。そしてその結果、その後は、まずは子供たちを愛情の元で育て、そして生きる力を養成しようとすることを基本にすえた教育が積極的に取り入られるようになっていったのです。もう君たちたちはすでに経験していると思います。君たちは色んな教育プログラムや、遊びや、スポーツや活動を通して、そこで次から次へと起こるさまざまなトラブルや障害を解決しながら、先に進んで行くためには、何をすればいいかを体験的に学習しているはずです。その過程で、君たちは悲しい思いや、辛い思いや、悔しい思いをしてきたと思いますが、それが、君たちを精神的に鍛えるとともに、大人になって人間として生きていくために必要な知恵や勇気をもまた育んで来たのです。それには昔のような知識が必要でないこともないんですが、それほど絶対的なものではなく、必要に応じてそのつど覚えればいいものなのです。しかもそれは、生涯にわたって覚えればいいものなのですから、子供のある期間にだけ限って覚えるという詰め込み教育は廃れるわけです。知識の不足は後で補えるが、愛情の不足は決して後で補うことは出来ないということのようです。というわけで、結局、今日のような教育制度に落ち着いたわけですが、では、この制度はどういうものかというと、つまり原始のころ人間が文字や数式などを用いないで子供を育ていたころの教育環境に戻ったということなのです。このことを昔の教育学者は、私たちの肉体に生まれつき備わっている知恵を利用する、と言っています。さっきもいってように、知識を詰め込む能力は個人によって大きく差があります。でも、生きようとする能力は個人差はほとんどありません。では、なぜ幾たびも、人間はその教育方法を間違えたかというと、教育というものは徹頭徹尾個人の問題であるにもかかわらず、まず、先生というものがいて、その先生が複数の子供たちに何かを教える、というシステムが最もベストと考えられたからなのです。では、なぜそういう結論になったかというと、それは子供を教育するには、どういう方法がが最善かということが徹底して考えられた結果ではなく、経済的なな制約、つまり、教育的には、できるだけ先生の数を多くして子供の数に近づけるということは、もっとも望ましいことなんですが、でも、それではあまりにもお金が掛かりすぎて経済的には不合理と考えられたからなんですね。現在お金がある人は先生を個人的に雇っていますが、ほとんどの子供たちは決してベストではないがベストに近い現在の教育制度もことで育てられています。私だけではなく今日の多くの人は、人間教育はマンツウマンが最善だと考えています。でも、今後、現在の教育制度がどうなるかは、それを支える経済的問題の解決しだいだと思います。」
そういい終わるとセイダは大きく息を吐いた。
このとき校内を涼しい風が通り過ぎていった。
セイダは、それまでの真剣そうな表情を満足そうな笑顔に変えて、再び話し始めた。
「ふう、どうやらやっと、私のささやかな夢が叶ったようです。今までは教育とはどういうものかについて、君たちに話したことはなかったのですが、今日、ようやくそれが出来ました。私も少しは先生らしく、君たちの為になることを言おうと思ってですね、何ヶ月前から勉強したんですよ。昔の本や資料を読んだりして。どうでしたか、少しは参考になったでしょうか。さて、そろそろ最後になりました。今日で君たちはこの学校を卒業して、ほとんどは今までさ育てられた親元を離れて、みんなそれぞれの道に歩むわけですが、これまではあくまでも、これから君たちが大人となって社会に出て行くための準備期間であり猶予期間なのです。だからここで君たちが学んだり経験したことは、専門家によって前もって考え出されたプログラムに基づいていますから、ある意味擬似体験のようなものであり、けっして真実ではありません。でも、これからは本当の意味で君たちの努力や忍耐が必要とされるようになるでしょう。そして本当の意味で悔しいことや辛いことや悲しいことを経験していくでしょう。でも心配入りません。君たちはそのために、この学校で学んできたのです。もう君たちには生きる力が備わっています。自信を持ってください。むやみに不安がってはいけません。それでは最後に、皆さんがこれから何をやるか、将来何になりたいか訊きたいと思います。では、ケルスから」
「将来、僕は科学者になって、まだ誰も見たことがない”宇宙の果て”について研究したいと思います。できれば、宇宙船でその場所に行って写真に撮ってみたいです。」
「宇宙物理学者だね。」
「それでは、カラムは?」
「将来、私は発明家になります。そして反重力を利用して今よりも効率のよいエアカーを作ります。それからもっと人間に近いロボットを作りたいです。でも本当は、まだ誰も成功してないタイムマシンを作りたいと思います。」
「夢は出来るだけ大きいほうが良いからね。セキルは?」
「私は医者になります。人間の心を守る医者になります。でも、学校にも、尊敬できる人のところにも行きません。そんな人いませんから。昔の本をたくさん読んで独学で勉強します」
「精神科学者だね。肉体の病気は、今はほとんどコンピューターと機械で診断し処置してくれるから、それはもう解決されていると言っても良いくらいだからね。それに比べて、人間の心の問題は複雑すぎて、未だに解決されてないことがあるからね。」
「あのう、ちょっと違うんですが。科学者ではありません。私は人間の精神は科学では計れないと思っています。だから学校にも尊敬できる人のところにも行かないんです。とにかく私は独学で勉強します。そして、今までになかったような学説を打ち出したいと思います」
「うむん、すばらしいことだ。ではラクルは?」
「僕は植物について勉強します。そして森を耕して土で野菜とか穀物を作る人になります。」
「いまは、食べ物はほとんど工場で作っているけど、昔流でやりたいんだね。素晴らしい挑戦だ。いつの時代でも若者は何かに挑戦しなくてはね。私も若いときはそうだったから。大変だと思うど、決して失敗を恐れずに、もし、だめかなと思ったら、とにかく世界生存機構(注1)を頼るように。これだけは皆も絶対に忘れないでおくように。私も若いとき挫折しかかって駆け込んだことがあるから。それではジュンカ。」
「僕は建物を作る人になります。」
「建築家だね。」
「いや大工です。木材で家を建てる大工です。お父さんの知り合いに名人といわれている人が居ますから、その人について修行をします。」
「やりがいのある仕事を選んだんだね。とにかく決して諦めないことだ。次に、マシルは?」
「僕は、まだ、なりたいものがないです。どうしても何かに決めないといけないんです。」
「いけないことは無いんですが、判らない人は時間をかけて決めても良いんですよ。それで今興味のあることは」
「歴史、人間や地球の歴史」
「良いんですよ。それで。なんににも興味ないことは問題ですが。それで充分です。それをどんどん発展させてください。歴史家になりたいということですね。では、ヤホムは?」
「僕は特別になりたいものはありません。でもあえて言うなら、旅をしたいです。そして地球上の色んなものをこの眼で見たいです。それから後は、たぶん新しい町(注2)づくりに参加すると思います。」
「そうか、実はね、私も若いときに、その新しい町作りに参加したことがあるんだよ。北アフカの大昔砂漠だったところでね。良い経験になったよ。人間の真実に触れることが出来、精神的に鍛えられたからね。それでは、次にイサム。」
「僕は本当は海に出て魚を取る人になりたいのですが、でも両親が反対するので、まずは船に乗って海を研究する人になります。」
「海は私たち人類の源だからね。雄大ですばらしい夢だ。マホミは?」
「私は絵を描くのが好きですから、画家になりたい。でも、それがだめだったら何かデザインする人になりたい。」
「大丈夫、好きであれば何にでもなれるよ。現代は、仕事を選ぶに当たって最も大切なことは、とにかく、その仕事が好きであることだからね。ヘレスは?」
「僕も新しい町づくりに参加したいです。でもそのためにはまず政治や法律についてもっと勉強したいです。」
「人間や社会について役立ちたいんだね。大変だと思うけど、とにかく挫折や失敗を恐れないことだ。これは誰にも言えることだけれどね。
それではリセは?」
「私は話をするのが好きだから、人と話したり、相談に乗ったりする人になりたいです。」
「カウンセラーだね。どんなに世界が豊かになっても、悩める人はいるからね。これだけは永遠に不滅ですからね。それでは最後にライヤだね。どうぞ。」
「私は、本当は先生になりたいです。セイダ先生のように、でも、、、、」
「そうだね。それ以上は自分からは言いづらいかな。みんな聞いてくれ、実はライヤは、、、、これは大変喜ばしいことなんだけどね。人類の究極の夢が叶うんだからね。人間が他の星に移住するというのはね。つまり、そういうことでライヤは家族と共に、人類最初の宇宙移住者として、三日後、第153銀河のM23惑星に移住するために、宇宙船でバイカ基地を飛び立つことになっている。そうだよね。」
「、、、、」
「有史以来、私たち人類はこのときをどれほど待っていたんだろう。ついにそのときがやってきたんだね。ライヤおめでとう。さあ、みんなも祝福してあげて。」
「おめでとう。」
「ライヤおめでとう。」
「ほんとうにおめでとう。ライヤ、君は私たちのの希望、私たち人類の永遠の命の夢を実現してくれるヒロインだ。そんな凄い人がこんな身近にいたなんて、本当に驚きだよ。とにかくおめでとう。君たちも見送りにいける人はぜひ行くように。それでは最後に恒例となっていますから、卒業していく君たちにふさわしい言葉を送りたいと思います。その言葉としては”ボーイズビアンビシャス” とか、 ”青年は荒野を目指せ” とか、 ”夢をあきらめないで” とかということをよく聞きますが、私はちょっと変ったことを言います。それは最近、大昔の詩人の本を読んでいて偶然見つけたんですが、次のような言葉です、ちょっと謎めいていますが、”できるだけ大きな夢を見よ、肉体の見る夢に比べたら遠く及ばないから”まあ、そうはいっても、君たちが最終的に進路を決定する来年の春までには、まだ時間があるから、ご両親に相談したりして、じっくり考えて決定するように。もし春までに決められなかったら、それはそれでいいと思います。とにかく時間をかけてほんとうに自分のやりたいことを見つけてください。それでは健闘を祈る。なお、これから伝統的な卒業の儀式を行いますが、参加できる人はするように。」
マシルたち男の子七人は退屈な儀式を抜け出した。そして校舎を出て、まだわずかに枯葉を残している樹木に挟まれた坂道を下った。眼下にはいつもより煙った町の風景が見える。町は中心部を除いては高い建物はなく、その為か、遥か地平線を越えて広がっているようにも見える。そして、その上空を移動するエアカー(注7)が鳥のようにも見える。
都市から都市を高速で人や物を運搬するオレンジチューブ(注5)が太陽の光を受けて光沢を放ち町を流れる川のようにも見える。
マシルたちの住む町はウルカと呼ばれ、人口は約六十万、ほぼ千年前に新しい町から興った町だった。
学校から離れるにしたがって七人表情はだんだん悪戯っぽい少年の表情になっていった。
マシルなんとなく開放的な気分でで町に入った。入ってすぐになぜ町が煙っているのか判った。いたるところで落ち葉が燃やされていたからだ。
七人はいつものように多くの人々が集まる町の広場へと向かってむ歩きつづけた。
しばらくすると道路を走っているエアカーから声をかける者がいた。
「ラクル、卒業おめでとう。」
そのエアカーが通り過ぎると、ラクルが不満そうに言った。
「なんで大人たちはみんなあう言うんだろう。ちっともおめでたくはないんだけど。そうだろう。」
「そうだ、全然おめでたくはないよ、卒業したからって。」
なげやりなラクルの言葉に同調するかのようにマシルが言う。
「大人って何を考えているのかよく判んないよな。」
ジュンカも同調して言う。
「そうだよな。ラクル、さっきの人誰?」
「親戚の人。ちょっとうるさいんだ。」
やがて七人は広場に着いた。
広場は小さな子供から年寄りまで多くの人たちで溢れていた。広場にはエアカーの乗り入れはできないが、その周辺には生活に必要なあらゆる店からあらゆる公共機関があるからだ。
七人はもう完全にいたずらっぽい少年の表情になっていた。
「もうセイダ先生と会えないと思うと、寂しいというか、嬉しいというか、複雑だね。」
「先生は最後に理屈っぽくなったね。」
「大人はみんなそうさ。みんな理屈っぽくて、それに、、、、」
「嘘つきでね。」
ヘレスのその言葉で話が途切れたが、そのときケルスが広場にそびえたつ掲示塔を指差しながら叫ぶように言った。
「見ろよ。地球の人口が十億人を超えたんだ。やっぱりほんとうだったんだ。今朝から何度も耳にしていたから気になっていたんだ。すごいな、これからどうなるんだろう。」
その言葉にヘレスがただちに反応した。
「どうってことないさ、だって昔は百億人以上もいたんだよ。」
「うそ。」
「ほんとうだよ。」
「いままでそんなこと聞いたことないよ。ヘレスはどうしてそんなこと知ってるんだよ?」
「調べたんだよ。特別世界資料館で。」
「あれ、そこは子供はアクセスしてはいけないんじゃなかった。」
「そんなこと関係ないよ。大人の決めたことだよ。その気になれば簡単にアクセスできるんだよ。もう昔の色んなことが判ったよ。今日マシルが質問した太平洋の緑のシミについて、あのこと、セイダ先生は嘘ついている。先生はよく判らないといっているけど。大昔はあそこには人が住んでいたんだよ。でもあることが原因で人が住めなくなったんだよ。」
「あることって。」
「戦争だよ。チャナとメリカという国が戦争して、その二つの国のちょうど間にあったヤホという国が巻き添えを食って滅ぼされたんだよ。核分裂爆弾を使用した戦争だから、最初はその二つの国が共倒れと思っていたようなんだが、どういう訳か何の関係もないそのヤホという国が犠牲になることで、しかもその二つの国はまったくの無傷のままで、その戦争は終わったということなんだよ。そのヤホという国には二百発以上の核分裂爆弾が落とされたみたいだね。それでそこに住んでいた人間は全員死んでしまって、それで、それ以後は二度とそこに誰も住まないようにと、永久に立ち入り禁止地域にしたみたいなんだよ。」
ケルスが苦笑いを浮かべながら少し声を荒げていった。
「僕はそんなこと信じない。確かに昔は核分裂エネルギーを利用していたっていう話は聞いているけど、でも、人間を殺すために使っていたなんてありえないよ。フィクションか伝説だよ。」
ヘレスが頭を左右に振りながら答えた。
「本当の話だよ。」
「いや、僕は絶対に信じない。どうして人間同士が殺しあわなければならないのか、その理由がまったくは理解できないから。」
「戦争だからさ。」
「その戦争というのがよく判らない。」
「昔の地球は沢山の国に分かれていたって今日授業で習ったじゃない。その国同士が戦争していたんだよ。今と違って、その頃は、国ごとに肌の色も、話す言葉も、宗教も、全部違っていたんだよ。それで何かのきっかけで仲が悪くなるとすぐ戦争を、簡単に言うと国同士の喧嘩だね、それをやったんだよ。」
「その戦争のきっかけってどんなこと。」
「うん、よく判らない。まだ調べてないから。でもその殺し合いってそうとう激しかったみたいだね。何十万人も部屋に閉じ込めて毒ガスで殺したり、空から飛行機で爆弾を落として何十万人も住む町を焼き払ったり、大きな穴を掘ってそこに何十万人もの人を集めて銃で撃ち殺したり、それでも生きているものはそのまま生き埋めにしたりしたんだよ。」
そのときヤホムが割り込んできた。
「そんなことありえないよ。でたらめだよ、作り話だよ。昔いくら人間が野蛮だったとはいえ、そんな同じ人間に対して残酷なことをするわけないよ。」
イサムも割り込んできた。
「僕も信じられない。どんな理由があろうが人間同士がそんな殺し合いをするなんて理解できない。」
「でも真実さ。僕にもその理由がよく判らないけど、その頃はとにかく対立していたみたいだよ。なにせ国によっては同じ人間を、肌の色が違っていう理由で、足を鎖で縛って奴隷にして使っていたぐらいだからね。それでも最初の頃の戦争というのは、弓や刀を使っていたみたいだけど、そのうちに、銃や爆弾を使うようになって、そして最後のほうは大量に、しかも無差別に人を殺せる核分裂爆弾を使ったみたいだ。そうじゃなければ、百億人もいた人間が現在の十億人になるわけないじゃないか。」
ヤホムも割り込んできた。
「いや、そんなこと考えられない。人間の数が減ったのは、きっと他の理由だよ。たとえば病気とか、天候異変とか、災害とか、絶対そうだよ。」
すると真っ先にヤホムが反応した。
「地球の人口が減ったのは、女の人が子供を生まなくなったからじゃない。お父さんが言っていた、昔、男の人が子供を生んでいたときがあるって。それくらい深刻な問題だったって、ことじゃないの、昔、女の人が子供を生まなかったってことが。」
ヘレスが冷静に答えた。
「それはちがうよ。男の人が子供を生んでいたのは、女の人が子供を生まないからじゃないよ。女の人が子供を生むか生まないかを自分で決めて、しかも、誰の子供を生むかも、自分ひとりの意志で決めるようになって、その結果、ほとんどの女の人が流行のように優秀な男の子供だけを生むようになったので、それなら、男たちも自分で子供を生もうということになったみたいだよ。」
「それは神話の世界の話しじゃないの、男が子供生むなんて信じられない。どうやって。」
「科学の力でね。」
「まさか、、、、」
「本当みたいだよ。とにかく昔は色んなことがあったみたい。なにせ科学の力ですべてが解決できると思っていたみたいだから。」
「どこかで聞いたことがある、昔は同じ人間を何人も作っていたことがあるって。とくに社会の役に立つ優秀な人間をね。」
「本当かな、信じられないよ。」
「嘘さ、作り話さ。」
「なんとなく気味が悪いな。」
「フィクションさ、昔話さ。」
「アッ、そうだ。人口が少なくなったのは戦争だけとは限らないのじゃないかな。先生が言っていたように、昔は変な人がいっぱい居たから、それで殺しあったり、それから自殺する人もいっぱい居たみたいだから、それが原因じゃないかな。」
そのときヘレスが話をまとめるように言った。
「よし、今日帰ったらさっそく調べるよ。」
そしてケルスが話題を変えた。
「もう、その話は止めよう。なんか気持ちが暗くなる。ところで、みんなはライヤの見送りには行くの?」
「もちろん行くさ。」
「行くよ。」
「もちろん。」
「会ってさよならを言うんだ。」
このように、ケルスの言葉にすばやく反応するものや、うなづく者がほとんどだったが、マシルだけは興味なさそうにしていたので、ケルスは直接訊ねた。
「マシルは?」
「僕は行かない。」
「えっ、どうして?ライヤとよく話してたじゃない。親しそうに。」
「そんなことはない、ケルスこそ仲良さそうに、よく話していたじゃない。笑ったりふざけあったりしてさ。」
「それはそうだけど。クラスメイトだからさ。でも、僕はいつも感じていた。マシルと話すときのライヤと、僕と話すときのライヤは違うんじゃないかって。ときおり、なんかちょっと恥ずかしそうな表情をしたりしてさ。たぶんライヤはマシルのことが、、、、」
「なに言ってんだよ。気のせいだよ。みんなと変わりなく話していただけさ。」
「そうかな、寂しくは思わない?」
「突然だったから、よく判らない。」
「僕はとてもショックだった。カラムは?」
「もちろん大ショックだよ。いくら人類の永遠の命の夢を実現するためとは言ったってさ、もう会えなくなるんだよ、きっと永久に会えないんだよ。僕は絶対に泣いちゃうだろうな。だってライヤは特別だから。そうだよね。」
「最後になんて言えばいいんだろう。サヨナラかな、、、、でも変だな。サヨナラはまた会う人に言う言葉のような気がするけど。」
その言葉を聞いて男の子たち全員黙ってしまった。
そして、その後も会話は弾むことはなかった。
やがて七人は、いつものように軽くサヨナラを言って別れた。
なぜなら、誰もがそのうちに、また会えるような気がしていたから。
その夜マシルは、将来の夢をはっきりと言えるクラスメイトたちが羨ましいと思うながらも、自分の将来のことを思うと、眠れないほど不安になった。
本格的に進路を決定する来年の春までには、まだ充分に時間があるとはいえ、いまだに自分にはどういう才能があり、また自分にはどのような職業が合っているのかも、そして自分は本当は何が好きなのかも、まったく判らないにもかかわらず、今日学校では、皆がそれぞれに自分の夢を言うものだから、それに釣られて仕方なく、人類や地球の歴史を学びたい、などと、それ以来ずっとみんなに嘘を付いてしまったという良心の疚しさを感じるようなことを、つい言ってしまったのだが、実際は自分は何になりたいのか、まだなんにも決まっていなかったのだから。
マシルはこれからどうすれば良いのか本当に判らなかったのだ。だが、自分を眠れなくさせている不安の原因は本当にそれだけなのだろうかと思った。そこには、これから自分が大人になって生きていかなければならない人間社会そのものにもあるような気がした。
でも、それはどういうものなのかは具体的なものとしてはまだ頭に思い浮かんでは来なかった。
そこでマシルは、今まで、これから人間として生きていくために、これだけは最低限必要とされている知識だけではなく、自分から進んで色んなことも学んできたことが、はたして将来ほんとうに役立つのだろうかとますます不安になるだけだった。
そしてマシルは、生まれて初めて、これから生きていくためには、もっともっと沢山のことを知らなければならないだけでなく、未来は決して祝福されものでも、希望に満ちたものでもないような気がしてきた。
翌日、マシルとヘレスとカラムの三人は町の広場で会った。
昨日より人出が多かった。
カラムはマシルを見つけるなり真っ先に言った。
「これからヘレスと二人でセイハン(注7)に行くんだけど、マシルも行く?」
「何をしに?」
「春まで暇だから、それまでに色んなものを見ておこうと思って」
「見聞を広めるためなんだ」
「住んでいる人も、町並みも僕たちの町とだいぶ違うみたいなんだ。どうする?」
「またの機会にする。ちょっと気分が優れなくて」
「あれだな、この時期になると不安になったり気分が滅入ったりするという病気十一月病だな、重いのか?」
「よく判らない。みんなは?爽快?」
「まあまあかな。理由は何?」
「これからどうしてよいか判らないんだ。 とても不安で。 いままではそれを目標にして自分なりに必要と思われることを勉強してきたつもりなんだけど、でも僕は、本当に政治や法律のことを勉強したいのかなって。 勉強してその後どうするのかなって悩むんだ。 ヘレスもカラムも、自分の進路に迷うことはない?」
「そんなことないよ。 僕は宇宙物理学者になりたいと思って、小さい頃から勉強してきたけど、でもそれは半分以上はお父さんの影響なんだ。最近ときどき地球や人間を事故や災害から守る人になりたいと思うこともあるんだ。 でも僕はそれ以上深く考えない。 お母さんも、そんなに焦って自分の進路を決める必要はないって言ってるから」
「僕だって不安だよ。 僕は物を作るのが好きだから発明家になりたいといったけど、でも僕にその才能があるんだろうかって思うときもあるからね」
「そうなんだ。 ところで昨日の続きだけど、詳しく判った? やっぱりあれは本当だった?」
「アッ、あれ、だめだった。いつものように地球の歴史から始まり、地球に起こった大事件、そして、人間が犯した犯罪について調べているときだった。 アクセスできなかった。 突然警告を受けてアクセスできなくなった。 十八歳まではアクセスできないって。 後でお父さんからも言われた。不正アクセスは違法行為だからやめるようにって。 情報管理局から連絡があったみたいなんだ。どうして不正アクセスだと判ったんだろう? 意外と厳重だったな。 まあ、いずれ大人になればは判ることさ」
「結局僕たち子供は他にやることがあるってことなんだろうね」
「でもね、戦争の原因だけは判ったように気がする」
「なに、それは」
ええとね。 それは、この地球上には二種類の人間がいるからみたいなんだ。 うんと働いて食べ物とか着る物とか、生きていく上で必要にものを生み出す人間と、ちっとも働かないで、それを横取りしようとする人間がいるから見たいなんだ。 色んな理由をつけて近寄ってきてね、それで?」
「よく判らない、たとえばどんな人間のこと」
「たとえば、危険から守ってあげるといって近寄ってきたり、幸せにしてあげるといって近寄ってきたり、病気を治してあげるといって近寄ってきたり、揉め事を解決してあげるといって近寄ってきたり、悩み事から開放してあげるといって近寄ってきたりしてね」
「そんなことで昔の人が戦争したなんて信じられない。 みんな、今どこにでもある総合相談所(注6)でやっていることじゃない」
「そういうこと。 とにかく昔は色んなことで遅れていたみたいだね。 それじゃ急いでいるから僕たちはもう行くよ」
そういい終わると二人は屈託のない笑顔を見せながらマシルから走り去って行った。
翌日は、青空の広がるありふれた秋の日だった。
ライヤは家族とともに、人類史上初めての宇宙移住者として、地球を飛び立った。
その様子は華やかに、そして感動的に全世界に中継された。
だが、マシルは見なかった。
なぜなら、そのときマシルは町を離れ森を彷徨っていたから。
夕刻、家に帰ったマシルは一人になってライヤのことを考えた。
マシルはライヤのことを学校に入る前から知っていた。
ときおり町で見かけ、印象に残った。
その可愛さが際立っていたから。
それで学校に入って、ライヤと同じクラスと判ったときには、ドキッとした。
でも、なぜかマシルは、そのことを表に出さないようにした。
その後マシルはライヤにたいしては、意識して他の女の子と同じように接するように心がけた。
そのためずっとクラスメイトであったにもかかわらず、特別に親しくはならなかった。
そのあいだマシルは、他の男の子たちもライヤに魅了されているのがだんだんと判ってきた。
それはライヤに接するとき、他の女の子と違って、その言動がぎこちなくなったりするその態度ではっきりと判った。
でも、マシルはそんな様子を見ても、自分だけ今までどおりに接しようと心がけ、そして実際にも、そうすることが出来ていた。
最近になってマシルは、自分がライヤに惹かれる理由は、その顔かたちの美しさだけではないということが、なんとなく判ってきた。
でも、それは、他の女の子たちが持っていないような何か、と感じるだけで、それを言葉でどう表現してよいか判らなかった。
ちょうど二ヶ月前、こんなことがあった。
夏休みを利用して人類の歴史について勉強していたマシルは、遺物の写真や映像だけではなく、実際に自分の目で、それらを見たいと思い、町の歴史博物館に行った。
すると偶然にもそこに来ていたライヤと会った。
会館直後だったので人影は少なく、ほとんど広い館内で二人だけといってもいいくらいだった。
ライヤとは学校に入ってからはずっとクラスメイトだったが、実際いままでプライベートな話をしたことはなかった。
その願望をひそかに心の奥底に抱いていたのは確かだったが。
だが、そのときマシルはどうしても自分からライヤに話しかけることは出来なかった。
それまで経験したことがないようなときめきに不意打ちされたから。
そしてマシルはさらに、それまでにま経験したことがないような戸惑いを感じ混乱した。
それはまさに、今の、この二人っきりの状況こそが、そのチャンスと、強く意識したからでもあった。
だが、そのことは返ってマシルに、ライヤに気づかない振りをし続けることを選ばせてしまった。
せっかく博物館に行ったのに、なぜか何も目的を果たせなかったマシルは、次の日も歴史博物館に行った。
すると再びライヤと出会った。
マシルは昨日と同様に戸惑い混乱した。
さらに昨日以上に胸が高鳴るのを覚えた。
そしてマシルは、昨日のようにライヤに気づかない振りをした。
結局マシルは二日とも自分の目的を果たすことは出来なかった。
でも、その次の日、マシルは博物館に行くのを意識的に止めた。
なぜなら、またライヤに会いそうな気がしたから。
ライヤが旅立った翌日、マシルはラクルから呼び出された。
スポーツドームの裏で壁にもたれて待っていると、ラクルが手作り自転車(注1)に乗ってやってきた。
栗色の髪を手でなでながらマシルに近づくと、ポケットから白く四角い物を出して言った。
「これ手紙、ライヤから。 おととい君に渡してくれって頼まれたんだけど、ついうっかり忘れてた。 だいたい察しは付くんだけど、たぶん、、、、」
「手紙って?」
「紙に文字を書いて、相手に自分の考えや思いを伝える手段だよ。 大昔のコミュニケーションの方法だよ。
でも、それは、ひょっとするとラブレターかな、」
「ラブレターって?」
「好きな人に思いを告白する手紙だよ」
「ライヤが、僕に、まさか」
「ところで昨日はやっぱり来なかったけど、見た、ライヤたちが出発するところ」
「いや、見なかった」
「とても感動的だった。 なんか地球全体から喜びが湧き上がってくるような。 でも、その後、もう会えないんだなあと思うと、泣きたいくらい寂しくなったんだけどね」
「、、、、」
「ねえ、君はもう準備始めている」
「準備って?」
「これからのことさ」
「まだ、春までは、まだ時間があるから」
「君のお父さんはウルサク言わないんだ。 森を耕して食べ物を作る人になるっていうのはダメだって言うんだ。 本当の自然相手は大変だって言うんだ。 そんなものは機械や食料工場に任せれば良いというんだ。
どうしてもダメだと言うなら僕はうちを出る。 それでもしかしたら、しばらくはマシルや皆には会えないかもしれない。 たぶん親戚を頼って隣り町に行くと思うから。 マシルの将来の夢はなんだっけ」
「僕は、このあいだ学校では歴史についてもっと勉強した言ったけど、でも政治や法律について勉強して、新しい町づくりに参加もしてみたい、本当はよく判らない、とても迷っている」
「マシルのお父さんやお母さんは」
「なんにも言わない。僕に任せているみたい」
「いいな」
小さくそういいながら遠くに目をやるラクルに、マシルはラクルの瞳が皆と違って緑色であることに初めてのように気づいた。
そしてラクルの言葉を聞いてマシルはなんとなくホッとした気持ちになったが、でもラクルの固い決意を羨ましくも思った。
二人はそれ以上話を交わすことなく分かれた。
そのうちにまた会えるような気がしていたからだ。
家に帰るとマシルは、さっそく自室にこもりライヤからの手紙を広げた。
いつも待っていてくれたマシルへ
いま私は眠れないまま朝まで起きています。
そしてこの手紙を書いています。
今朝の朝焼けはとても綺麗です。
おそらくこれが最後になるのね。
そういえば昨日の青空も、とても綺麗だった。
マシル、私は今とても迷っています。
どうしたら良いのでしょう。
私はお父さんやお母さんと別れたくありません。
もちろん弟や妹とも。
でも、マシルや他のクラスメイトとも別れたくないのです。
会う人会う人、誰もが、おめでとう、おめでとう、と私たちに言ってくれます。
でも、本当におめでたいことなんでしょうか。
皆と別れなければならないというのに。
しかも、もう二度と、永遠に、みんなに会うことはできないと言うのに。
私にはそれは、とても悲しいことのように思えるのです。
ところが、お父さんもお母さんも、他の人たちのように、
“人類の夢とか”、
“人類の永遠の命のため”、
とか言うばかりで、ちっとも悲しいという感じはないのです。
むしろ、それは誇らしいこと、喜ばしいことのように思っているみたいです。
私には何が”人類の夢、人類の永遠の命のため”なのかちっとも判りません。
はっきりしていることは、私の命は永遠でもなければ、
マシルにも二度と永遠に会うことはないだろうと言うことです。
お父さんは目的の星に着くまでは長時間眠っているから、
その意味では地球に残っている人より長生きできると、笑顔で言うのです。
それでどのくらい眠っているのと訊くと、何年、いや何十年かな、
などとと言葉を濁して言います。
そしてすぐ人類の夢とか、人類の希望とかに話題を変えてしまうのです。
でも私が思うに、何十年でも、その目的の星に着くことは出来ないと思います。
たぶん何千年か、何万年か、そのくらいだと思います。
それに、私は生きているかもしれないが、マシルはそのときにはもう死んでしまっていて、
ふたたび会うことも、お話しをすることも出来ないということです。
それでは長生きをすることに、どんな意義があるのでしょう。
何万年後に目覚めたとき、私はそのことを思って、
きっと悲しくって泣いてしまっているでしょう。
でも、もっと不安なのは他の人は誰も目覚めないで、
私だけということになったら、ということです。
この宇宙には私だけ、地球に帰ることも出来ない。
仮に帰れたとしても、マシルたちは生きてはいない。
私は完全に独りぼっち。
おそらく私は生きていけないでしょう。
私たち宇宙移住者が、本当に人類の夢、
人類の永遠の命の夢をかなえることがてきるんでしょうか。
いずれ地球がなくなるんだから、
他の星に人間の子孫を繁栄させたいと言うのは願いなんでしょうが。
でも、それは人間の永遠の命ではないでしょう。
私はとても不安です。
果たして目的の星を近づいて眠ったときと同じような状態で
再び目覚めることが出来るんでしょか。
そんな技術が本当に完成されているんでしょうか。
もし目覚めなかったら。
でもそれならそれで良いかも。
だってマシルたちはそのときにはこの宇宙にはいないんだから、会って話をすることも、
会って学校のときのように何かをいっしょにやることも出来ないんだから。
私には大人たちが嘘を付いているようにしか思えません。
そこで私は思い切って移住局の偉い人に私の疑問をぶっつけてみました。
まずどのくらい眠っているのかと訊いたら、
『光速で移動する宇宙船にとっては、まだよく判っていない宇宙の影響を受けやすいから、
正確な時間は判らない。』
というのです。
次に、私たち人間が生きていくためには植物や動物も必要です、
それはどうなっているのですかと訊いたら、
『地球上に何万という植物や動物の種子や遺伝子や受精卵が積み込まれているから大丈夫だ。』
というのです。
それから、本当に眠ったときと同じように状態でふたたび目覚めることが出来るのか。
と聞いたら、
『それは間違いない。』
というのです。
『長い間実験と研究を重ねてきたので完璧だ。』
というのです。
だから私ひとりだけが目覚めて、
宇宙の果てで独りぼっちになることは絶対にありえないということです。
そしてこんなことも付け加えました。
『仮にそんな不手際が起こったとしても、心配はいらない、
なぜなら、植物や動物の種子や遺伝子や受精卵だけではなく、
人間の遺伝子や受精卵も、しかも、かつて地球上で活躍した人たちの物も積み込まれている。』
と言うのです。
たとえば、それは、天才的といわれた芸術家やスポーツ選手や学者に加えて、
あらゆる分野の人たちの物が。
でも、結局は、みんな判ったように判らないような答えばかりでした。
私は最近真剣に思うようになってきたんです。
本当の幸せっていうのは楽しそうに何かをやることだって。
私には
“人類の永遠の命の夢”
とかいう大げさなものには、ちっとも興味がありません。
私は生きている間にみんなとお話しをしたり歌を歌ったり、ダンスをしたり、
劇をやったり、花を見たり、動物と遊んだりしていたいのです。
私にはそんなちっちゃな夢で十分です。
それだけで十分幸福です。
私は本当は行きたくないです。
でも、それだと家族は悲しがるし説得する力もありません。
マシル私はどうしたら良いのでしょう。
移住局の人の話だと、本当にいやだったら、出発直前でも取りやめることが出来るそうです。
でもそのためには、家族を説得でき、私自身も納得できるような理由が、
何かきっかけが必要なのです。
マシル、どうして私とあなたはずっと同じクラスだったのでしょう。
たぶん偶然なのでしょうが。
その間は授業で会うだけで、特別に二人だけで話したこともなかったのに、楽しいことばかり。
(子供裁判のときは悲しくて涙を流したときもあるけど。
それに魚や蛙の解剖はとても気味が悪かったけど。)
それから、みんなで映画やニュースを作ったり、
何年もかけてバイオリンや自分でデザインした自転車を作ったり、
私たちだけに全部任せられて野菜を栽培したり。
最初はどれもみんな、女の子の私にも出来るのかなと思って不安だったけど、
でもなんとか皆出来ちゃったっけ。
とにかく男の子は誰もみんな親切で優しかったからね。
でもね、本当に私を元気付けてくれたり支えてくれたのは、
すべての男の子たちの優しさや励ましの言葉ではなかった。
工具がみんなに行き渡らないとき、マシルが自分で使わないで遅れている私のために、
先に使わせてくれたり、三年前の課外授業で、
どうしても定刻までに到着しなければならないと、
みんなイライラしながら歩いているとき、
私が立ち止まって夕日が綺麗といってみているときに、
マシルだけがいっしょに見てくれたことだった。
だから毎年の職業体験や課外授業を乗り越えられたのも、
とくに昨年の課外授業で、隣町まで野宿をしながら、
その途中に起こる問題をみんなで解決しながら、何日もかけて歩いていったとき、
最初はみんなの意見が対立して喧嘩になったりしてたりして、
最後までうまく行くかどうか不安で辛く苦しかったけど、
結局は、マシルが近くに居たおかげと思っています。
それで、最後の頃はみんな仲良しになって、とても忘れられない思い出です。
ここ数ヶ月、私は不思議なことに気づいていました。
学校で遊んでいるときや授業のときなどに、なんとなく視線を移動していると、
ふとマシルと眼が合うのです。
それも気になるくらい何度も。
他の男の子とはちっともそんなことないのに。
あれはどういうことだったのでしょう。
単なる偶然だったのでしょうか。
とても不思議な気持ちでした。そしてそんなとき、私はマシルと歴史博物館で会いました。
あれも単なる偶然だったのでしょうか。
あの頃私はお父さんから移住に話を聞かされて悩んでいた時期でした。
それでなんとなく静かな場所とか落ち着いた場所とかに行って
ゆっくりと考えたいと思うようになり、歴史博物館に行ったのでした。
するとマシルに会ったのです。
なぜ今こんなときに、こんなところで会うんだろうと思って、
私は心臓が止まるくらいに驚きました。
そこで私は思いました。
これは私の悩み事を相談して解決してもらうために、
何か未知の力が、私をマシルに引き合わせてくれたんだと。
でもなぜか私は、普段学校に居るときのような気持ちで、
気軽に話しかけることは出来ませんでした。
二日目にも行き会ったとき、今日こそは絶対に話そうと思った。
でもなぜか私には出来なかった。
それはマシルが私を見たとき、とても不機嫌そうな表情をしたからです。
それを見て私は、私はマシルから迷惑がられているような、
避けられているような気がしたからです。
そしてまるでマシルが別人のように感じて、とてもショックだったからです。
私は激しく落ち込みました。
そしてこれからどうすればいいのだろうと絶望的な気持ちになりました。
でも、あれはきっと私の見間違いに違いない、
本当のマシルはあんな冷たい人じゃない、と自分に言い聞かせて、
なんとかその日は持ちこたえました。
そして次の日も私は行きました。
今日こそは絶対に話しかけようと思って。
でも、マシルは来ていなかった。
私はいま移住局の人が最後に言ったことを再び思い出しています。
どうしても移住したくなかったら、出発直前でも取りやめることが出来る、ということを。
でも、決心がつかない、きっかけが欲しい。
マシル、あれは絶対に私の見まちがいですね。
私はあなたにさよならを言いたくない。
よく泣いていたライヤより
いつ自分がそんな不機嫌そうな表情をしたんだろうと不思議に思いながらも手紙を読み終えると、マシルは胸が締め付けられるような寂しさに襲われた。
ライヤが自分になにを伝えようとしたのかよく判らなかったが、
永遠に二度と会えないことだけははっきりと感じてることが出来たからだ。
そしてもう二度と再び読むことないだろうと思いながら手紙を折りたたんだ。
そしてマシルはもう永遠に会うことはないライヤを思い浮かべた。
それは歴史博物館で偶然あったときの、驚いたような途惑ったような笑みを湛えた表情だった。
そしてマシルは激しく後悔した。
もしあのとき勇気を持ってライヤに話しかけていたら、
ライヤは旅立つことはなかったと、そして、ライヤを失わずに済んだと。
————————————–
————————————–
————————————–