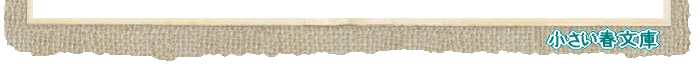真善美
* * * * * * * * * * * * * * *
その男は決して抜けてはいないのだが、物事に無頓着というか、ちょっとボォッとしている所為か、よく自分の周囲で起こっている変化に気づかないことがあった。
————————————
男が中学三年のとき学校で運動会があった。全員参加の二百メートル競争のとき、ほかのものはすべてスポーツ用のショートパンツをはいて走った。でもその男は下着のパンツで走った。新しい物ではあったが。
————————————
男が高校を卒業しようとしていた三月、ふと同級生たちの姿に目をやると、坊主頭は自分以外誰もいないことに気づいた。男は決して坊主頭に何か特別の意味をこめていたわけではなく、ただ子供のころからの習慣に従っているだけに過ぎなかったのに。
————————————
男が大学受験のための願書を出すとき、締切日のしかも、郵便局が今まさに閉まろうとするときに手続きをした。だから試験会場では一番最後だった。
————————————
男が大学に入学したとき、腕時計をもっていなかった。なくても不自由な思いをしたことがなかったから。でも男の母は不便に思ったらしく、べつに要求もしなかったのに新しい腕時計を買ってくれた。だが男は、それを三週間ほどで亡くしてしまった。
————————————
男が大学二年のとき学生寮に住んでいた。それは戦前からの古い二階建ての木造の建物で、野球場ほどの広さの敷地に三棟校舎のように建っていた。作りも間取りも簡素で、どこからでも出入りが出来るというぐあいに開放的で、周囲も成熟した樹木に囲まれ、社会からは隔離されているかのようにのんびりとしていて、いつも静かだった。古い建物の所為か、痛みや応急処置を施したような後が目立ったり、トビラがうまく閉まらなかったりというような不具合が至る所にあったが、概して住むにはそれほど不自由はなかった。その所為か、寮に入った頃は、建物の歴史に関するいろんな噂が飛び交った。たとえば、ドアが釘付けで封鎖されたトイレに関しては、学生にもてあそばれた女が中で首吊り自殺をしたとか、整備もされず荒れ放題の空き部屋は、空襲によって死んだ学生たちの死体安置所だったとか。そこで男はあるとき仲間四五人で興味半分にそのドアをこじ開けてみたりしたが、他と何にもかわらない個室だった。
夏休みになった。寮生たちはそれぞれの実家や故郷に帰り始めた。だが男はなかなか帰らなかった。お盆近くになると、時折どこかで歩く音が聞こえるくらいで、ほとんど静かだった。そんなあるとき、日が沈み暗くなったので男は部屋の電気をつけた。しばらくして男は部屋を出た。廊下から外を見ると真っ暗だった。どの方向を見てもどの建物を見ても電気ひとつ付いていなかった。男は耳を済ましてみた。物音ひとつしなかった。不気味なほど静かだった。男ははたと気づいた。この世間から隔離されたようなだだっ広い真っ暗な空間に存在しているのは自分独りだけだと。すると急に、トイレで自殺した女の話しとか、死体安置所とかの話が頭に浮かんできた。そしてその死体安置所というのが、実は壁ひとつ隔てた隣であったということに改めて気付かされた。
————————————
男が二十歳のとき、先輩と同級生の三人で大衆酒場に飲みに行った。その先輩は何事にも開放的で無頓着で、生活費のすべてを飲み代に使うような男だった。その先輩は、今日も仕送りのほとんどを飲んでしまったよと、酒場の主人に大声であっけらかんと話した。ところが、それ以降、三人から少し離れたところで飲んでいた十名ほどの労働者風の集団の何人かが、三人にちらちらと目を向けるようになった。男は、その男たちの視線の鋭さに不穏な気配を感じたので、なるべく彼らの居る方に目を向けないようにした。やがてその中の一人が、三人に話しかけるようになった。最初は普通の大人のように紳士的だったが、先輩の陽気な返答をきっかけに、急に乱暴になって行った。先輩の言動が、その男たちの気に触ったようだった。やがて男たちは語気荒く三人に因縁をつけ始めた。先輩は男たちに、学生の身分で少し調子に乗りすぎたことを謝ったが、その男たちは決して許そうとしなかった。そして、ある者の「お前ら、生意気なんだよ。」という発言をきっかけに、そこから四、五人の男が走り寄って来て、無抵抗な三人をポカポカと殴り始めた。男はもうだめかと思った。やがて、突然の嵐のような攻撃は終わった。先輩は男たちに自分の非礼をただひたすら謝り続けた。そして男たちは捨て台詞を残して去って行った。ところで男はふとあることに気づいた。乱暴な男たちがやってきたとき、もうだめかと思って、どうにでもなれと観念したのだったが、少しもだめではなかったのだ。確かに突然の嵐のような攻撃ではあったが、実際、男は誰にも殴られてはいなかったのだった。そう思って他の二人を見ると、それほどひどい目にも会っているようにも見えなかった。
————————————
男の学生時代は、マルクスの著作を読まない者は学生でないというような風潮があった。そこで男は読んだが、ボォッとしていたのか、頭が悪かったのか、よく判らなかった。だから学生運動にはハマらなかった。それは、男には馬鹿正直なところがあって、納得のできないことはどうしても行動に移せないという性分だったからだ。
————————————
男が大学四年になって就職しようとするとき、不況だった。周囲のものはなかなか就職できないといって焦っていた。でも掲示板には求人表がいっぱい張り出されてあったので男それほど焦らなかった。というより男は故郷の公務員になることを選んだ。このときも締切日に願書を送った。そしてどうにか学科試験は通った。周りのものはもう合格したようなものだといった。その根拠は男には判らなかったが。あるものが言った。「田舎の公務員は皆コネで受かるんだって。」と。男は思わず吹き出してしまった。こんな平等で民主主義の社会にあって、そんな不公平なことがまかり通るわけはない、と。男は面接で落ちた。後であるものからなぜコネを使わなかったのかと訝しがられた。「なぜ自分に言ってくれなかったのか」と地方の有力者から言われたと云うことも、男はあとで母親から聞いた。男はそのたびに思った。「そういえば面接のとき、面接官は、『あなたに県庁に勤めている親戚は居ますか。』と云うことを聞いたな。」と。でも、もう終わったこと、仕方がないことだと思った。それっきりだった。
————————————
男は就職が出来なかったので留年するつもりだった。でも単位を全部とってしまって卒業しなければならなくなった。卒業すると就職には絶対的に不利だということに気付かずに。
————————————
男が最後のテストに臨む前に異様な光景を目にした。すべての学生が公式を机の上に書いていたのである。カンニングをするために。男はそれまでそのようなことに全く気付いていなかった。正直言ってカンニングなどしたこともしようとしたことも一度もなかっただけに。でも男はそのとき心をいれかえた。そして最後の最後に生まれて始めて堂々とカンニングをした。しかも教科書を見ながら。
————————————
男は二十代の末に、昼下がりの電車に乗りながらふとあることに気づいた。生きるためには、卒業証明書も、年金証書も、失業保険も、健康保険も、住民票も、運転免許証も、資格証明書も、身分証明書も、住民票も、肩書きも、時計も、テレビも、新聞も必要ないということに。
————————————
男は実家を離れて暮らしてだいぶ経ったあるとき、久しぶりに母親の料理を食べてふと気づいた。母親は料理があまりうまくなかったと云うことに。それからどう見ても美人ではなかったということに。
————————————
男は三十を過ぎたころ、休暇でふるさとに帰ってきていた。そして退屈しのぎに、子供のころに親しんだ釣りを楽しむことにした。だが思わぬ誤算があった。子供のころには何ともなかったのだったが、いつのまにかにミミズに触れなくなっていたのだった。ミミズを引きちぎり、釣り針につけるのだったが、そのときミミズが抵抗して指を締め付けるように絡みつく、そのわずかな力でもなんとも気持ち悪く、失神してしまいかねないほどだった。勇気を振り絞って何度も試みたが結局失敗に終わった。だから最初は人につけてもらった釣り針のえさのミミズが食われてなくなっても、そのままにしてつりを続けている振りをしているだけだった。
————————————
男は三十の半ば頃、言葉が違う不法就労外国人といっしょに働いていた。仕事をしているときは気にならなかったが、休憩時間になると改めて言葉が通じないことに気づかされた。そしてどことなく不自由さを覚えた。言葉というものがむしろコミュニケーションを妨げているのではないかというぐあいに。
————————————
男は四十の半ばごろ、立ち退きで引越ししなければならなくなった。男は新しいは部屋はいつでも見つかると思い、ぎりぎりになるまで待っていた。そして三日前になってから探し始めた。だが、定職に着いていないということで誰も貸してくれなかった。ほとんどの不動産は門前払いのような形だった。 男は今までどのようにして部屋を借りていたかを思い返した。そして日本人である自分にさえ部屋を貸してくれないほど世界は変わったのだということに気づいた。男は思った。俺はいったい今まで何をしていたのだと。そして涙が出た。悔しいからではなく、これで本当の人生の意味を知ったような気がして、嬉しさのあまりに。
————————————
男は五十に近くなった頃、失業をしたが少し蓄えがあったので独りで暮らしていた。街中ではあったが友達も訪ねる者も居なかったのでずっと静かな生活だった。男はそんな生活を寂しいとか退屈だとかとは感じていなかった。むしろそれなりに充実感を覚えていた。それから十年後、男は町で人とすれ違いながら、はたと気づいた。そう言えばこの十年間人と話していなかったと。
————————————
男がテレビである司会者を見ていて、かつてはあんなに若かったのにこんなにも老けてしまったのかと思った。自分と同世代と気付かずに。男は鏡に映った白髪まじりの自分の姿を見た。そして、愕然とある事実に気づいた。自分は今の今までXXXXであったと。
————————————
男は五十を過ぎたあるとき、ふと気づいた。それまで自分は五人兄弟の末っ子ということで、誰よりも甘やかされ可愛がられ、少しは有利な立場で他のものより楽にいきてきたような気がしていた。でもよくよく考えてみると、親と過ごした時間は他の誰よりも少ないし、それどころか、普通に行けばすべての兄弟たちの死と向かい合い、一人残った自分が最も悲しい思いをしなければならないということに。
————————————
男はこの頃、ようやくインターネットを始めた。ところが始めてから気がついた。Eメールをやる相手が一人も居ないことに。そこで男は自分当てにEメールを送った。
————————————
男は天気の良い静かな日にふと気づいた。小さな子供のころから色んな生き物を殺してきたが、どのように殺したか決して忘れないものだということに。
————————————
男は五十代半ばのあるとき庭で草取りをしていた。そしてふとあることに気づいた。もはや突然出てくる虫やミミズに驚かなくなったということに。
————————————
男は五十年以上前の自分が生まれた年に死んだ姉の額縁に入った写真がほこりをかぶってよごれているのに気づいた。男はほこりをふき取って綺麗にしてやることにした。だが額縁がだいぶ痛んでいることが判った。そこで男は新しいのを買うことにした。額縁を買う前に銀行にお金を下ろしにいった。その預金通帳には四万円しかなかったので、男は前々から、残りを全部下ろしたら預金通帳は破って捨てることにしていた。男は暗証番号を打ち込もうとしたが、どういう訳か指がぎこちなくしか動かなかったので、意識的に集中して最初の四を強く押した。 だが、引き出し額が表示されて気づいた。四十四万になっていることに。どうやら四を二回押してしまったようだ。男は一瞬と惑ったが、どうせ残金はないのだから、出てくるわけはない、エラーとなってもう一度やり直しをさせられるだろうと思ってそのままにしておいた。 ところが、ATMは動き続け、四十四万円を出した。男は何が起こったのかとパニックになった。この金を手にするべきかどうか迷った。これは機械のミスに違いないから知らん振りして自分のものにしようかなとも一瞬思った。でも絶対にばれるに違いないとも思った。男は守衛を呼び、そこの銀行員を呼び事のいきさつを説明した。だが、解決はするまでには至らなかった。その銀行員の話しでは、何かの手違いがあったのだろうが、本銀行は契約銀行ではないのでこれ以上どうすることもできないということだった。 結局、男はその金を手にして家に戻った。そして二時間以上あれやこれやと考えた末、男が預金している銀行に電話をかけた。 ところが、男を興奮させ惑わせたミステリー劇はあっけなく幕切れとなった。その手違いで出てきたと思っていた金はもともとは男のもので、男の定期預金からのものだった。男はうっかりしていてと言うか、文字通りポォッとしていて、そのことをすっかり忘れていたのだった。その金は、男がその後三、四年生き延びるのに十分な額だった。 神も仏も奇跡も超常現象も信じない男は、これはきっと死んだ姉ちゃんからのプレゼントに違いないと心の底から思った。 もし、額縁を綺麗にしようと思わなかったならば、間違って四を二度押すこともなく、残金のない通帳は破られ、ゴミとなって捨てられていたのだから。
————————————
その男は小さい頃から本当にボォッとしていて、将来自分がなりたいものを頭に思い浮かべたことはなかった。そのことは青年になっても大人になってもずっと続いていた。だから、五十半ばを過ぎて、ようやく自分は何者にもなっていないことに気づくのだった。
————————————
その男は、ずっと最後までボォッとしていて、今まさに意識がなくなりかけようとしていたとき、ようやく自分が子供の頃から本当になりたかった者になっていたことに気づいた。
————————————
————————————
————————————