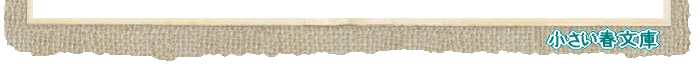はだい悠
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ボクは今、繁華街の中華料理屋でコック見習いとして働いている。
ボクが従業員として初めてこの店に来たのは、確か七年前、厨房に新しく入ってきて人たちが集まったとき、その雰囲気がなんとなく変だなということにすぐ気づいたっけ。
ボクの存在がとても場違いな感じがしたから。
そしてだんだんと気が滅入って行き、そのうちに、この店をバイト先に選んだことを後悔するようになっていたっけ。
ハローワークの人の話だと、市内の中華料理屋の厨房での、掃除や皿洗いなどの簡単な手伝いのようなものということだったが、実際に来て見たら違っていたから。
でもそのとき、実際に募集されていたのは、厨房で料理を作る人だったみたい。
面接に来たのは五人で、ボク以外はみな料理経験者だった。しかも二人は実際に中華料理店で働いていた人、他の二人も料理学校の卒業生だった。
どうやらボクは、ハローワークの人にこの店を紹介されたとき、ボクは料理は出来ないと言ったにもかかわらず、その人は、今のところそれは、別に構わないんじゃないか、と平気な顔で言ったので、たぶんそれは、皿洗いなんかのバイトだな、それでお金をもらい、そのうえ昼飯と夕飯がつくなら儲けもん、と勝手に判断していたみたいだった。
そのときの後悔っていうのは、主に、ボクが料理について、なんにも知らないことが皆にバレたら、きっと恥をかくだろうなという恐れから来るものだったが、そのうちに、
「それはボクの所為ではないんだ、バレたときはバレたとき、」
と開き直ると、多少の肩身の狭さを感じてはいたが、それほど後悔もしなくなり、だんだん気分もよくなっていったっけ。
でもラッキーなことに、初日は、集合に始まり、お互いの自己紹介の後、昼食として遅めのまかない食を食べて、午後には掃除や皿洗いなどで終わり、本格的に働くのは翌日からということになり、ボクがなんにも出来ないことが、その日に皆にバレることはなかったっけ。
でも、
「そのうちにきっとバレるんだろうな、」
という恐れから来る不安は小さかったけどずっと感じていたっけ。
それでも翌日も来ることにしたのは、たぶん、賄い食が美味しかったからだろうか。
この店で働く前、ボクは大学受験に失敗し予備校に通っていた。
て言うか、ときどき通っていた。
というのも、両親は三流大学でも学費は払ってくれるというが、あまり勉強が得意でなかったボクは、それほど大学に行くことには乗り気でなく、かといってそれほど働く気にもなれず、なんとなく親のすねをかじって、ブラブラしているのが楽だなあってコッソリ感じていたからなのだ。
でも、そのうちになぜか、このままでボクは良いんだろうかと、ちょっと疾しさを感じるようになったっけ。
それは予備校をサボっていることが親にばれたり、そのことで何か小言めいたことを言われたからではなかった。というより、逆にそのことでなんにも言われなかったからかもしれない。
いや、そもそも両親はボクがサボっていることには気づいていなかったかもしれない。だって、ボクの両親は、ボクの将来にそれほど関心を持っているとは思えないからだ。
大学受験に失敗した時だって、浪人しても良い、働くのも良い、どっちだも良いよって、普通の顔で他人事のように言っただけだったから。そう言えば小さいときからそうだった。
勉強しろとか、手伝えとか、ほとんど言われたことがない。二人とも外で働いているからあまり子供のことに構っていられないのだろうけど。でも、はっきり言ってなにを考えているのか判らない。ボクが大学をあきらめて中華料理のコックになるといったとき、
「それじゃ頑張ってね、」
と面倒くさそうに言ったぐらいだから。
親から期待されるのもプレッシャーだが、なんにも期待されないのも、とっても拍子抜けがする。
両親のことはさておき、居心地が悪くなったボクは、そこでバイトしようと思ったわけだが、はっきり言って、遊ぶ金がほしかったのだ。そしてお金がもらえた上に、大好きな中華料理が食べられるとなれば、これほど美味しいバイトはないと考えるのも当然だったわけで。
だが実際に店が募集していたのは料理人、早とちりしたボクも悪いが、適当に紹介したのハローワーク人間も悪いさ。
結局ボクは、バイト料と賄い食に釣られて、翌日も行ったのだったが。またもやラッキーなことに、ボクはどんな素人でもやれるような店の内外の掃除、皿洗い、そしてその他の雑用が言い付けられた。
他の四人はさっそく店に出す料理を任されていたが、ボクは正直言って、そんな雑用仕事でも少しも苦にならなかった。むしろ気楽でとっても楽しかった。
ボクはなんにも考えずに、いや、賄い食のことだけを考えながら働くことができたからだ。そしてボクは、ボクを指導してくれる色んな人の言うことを素直な気持ちというか、まったく信頼して聞くことができ、その人の言うようにすることが出来たっけ。
それはたぶん、ボクが料理について何の先入観も持っていなかったからなのだろうが。
いや、本当はボクを指導してくれたあの人のお陰かもしれない。その人は、普段はあまり店には出てこないのだが、みんなから、オヤジとか大将とか呼ばれ、若いときにこの店を始め、流行らせ、そして大きくし有名にした人だった。
どうやらこの店で一番力がある人のようだったのけれど、そのころボクは、その大将がとても穏やかな話し方をするので、そんなに偉い人とは思えず、どこにでもいるような普通の年寄りのように思っていた。でも、ボクはその人は前に居ると不思議と素直な気持ちになれたっけ。
バイトを始めて半月ほどたったある日のことだった。
いつものようにボクは昼食を済ませ、店の裏で午後の休憩をしていた。ちょうどそこへ、料理学校を卒業した二人が出てきた。そして、いつものように、ボクからちょっと離れたところに行き、木製の箱に座り、何やら話し始めた。
それまでボクは、同じ年頃でもあるにもかかわらず、なんとなく距離を感じて、仕事の上でもプライベートでも全くといって良いほど、彼らに話し掛けたことはなかった。それには彼らのほうからボクに声を掛けなかった所為もあるのだが。
しばらくすると彼らの話していることがはっきりと聞こえるようになって来た。
「あれは使い物にならないな。今日も注意されてたよ。皿の裏の汚れがちゃんと取れてないって。何度目だろう。本当になにを考えているんだろうね。」
「あのメガネ豚のこと。」
「本当だな、ぶくぶく太っちゃってさ。たいした仕事も出来ないくせに、食うことだけが楽しみって感じだよな。このあいだ大将に言われていたよ。『お前は食べるのが大好きなんだね。』って。そしたら奴は、うれしそうに答えてたよ。『はい。』って。イヤミで言っているのも判らないでよ。」
「奴は本当によく食べるよな。あいつぐらいだろう、昼も夜もおかわりするのは。」
ボクは最初、誰のことを言っているのかなと思って聞いていたが、この辺まで来てようやくボクのことを言っているんだなって気がついた。ボクは確かにメガネをかけているし太ってもいる、それに絶対におかわりもする。話しはさらに続いた。
「奴は何しに来てるんだろう。料理作る気あるんだろうか。」
「ないないない。あるわけないよ。作る気あるなら、もうちょっと自分から進んで何かやってるよ。言われたことしかやらないじゃない。今まで雑用しかやってないじゃない。」
「暇さえあれば鍋を磨いているばっかしじゃない。ぜんぜん意欲感じられないな。なんかボォッとしている感じでさ。料理にはイマジネーションが必要だって、学校の先生が言ってたけど、奴にはそんなもんはないだろう。」
「いいんでないの。ずっと雑用係やってれば。これからアイツのこと、ナベミガキと呼ぼう。」
「アイツ、もしかしたらアブナイ奴じゃないのか。」
「だったら、あまり変なこと言わないほうが良いぞ。やつら本気で怒るからな。フッ、フッ、フッ。」
「奴ら怒るとほんとに怖いからな。クッ、クッ、クッ。」
かすかな笑い声を最後に二人の会話は聞こえなくなった。二人は、ボクが傍にいるのが判っているはずだから、わざとボクに聞こえるように話しているなって、そのときボクは思ったが、でも、少しも腹を立てる気にはならなかったっけ。だってあの頃のボクは、たしかに彼らの言うとおりだったから。
ボクは何も彼らに気を使うことはなかったのだったが、でも彼等に気づかれぬように、そっとその場へ去ったっけ。なんか変な気持ちだったけど。そして厨房に戻ると何事もなかったかのように再び皿洗いを始めたっけ。
ボクは今も太っているが、その当時はもっと太っていた。ボクはとにかく小さいころからずっと食べるのは大好きだったからね。
だから彼らの言い分を全部認めたわけではなかったが、少なくとも当たらずとも遠からずで、ほとんどは納得しながら冷静に聞くことができたんだね。
いや、それはむしろボクとは違う世界に住む人間の言い分のように感じたのかもしれない。
なぜなら、そもそもボクには最初から、料理に対する意欲やイマジネーションがあるとは全く思ってなかったから、中華料理のコックになるなんて夢にも思ってなかったというわけで。
掃除や皿洗いや後片付けが何とかできるようになったころ、ボクは野菜切りをするように言われた。
大将から、包丁の持ち方から、色んな野菜の切り方を教わった。最初はとても遅かったり、失敗ばかりしていた。それできつく言われたり、何度もやり直しさせられたりした。
それまでボクはスポーツは得意でなかったが、それほど不器用だとは思ってなかった。でも、そのとき、他人が感じるように、外見どおりの不器用な人間であることに思い知らされた。
でもそんなには落ち込まなかった。だって料理人を目指していたわけではなかったので。むしろ時間が経つにつれて、苦にならなくなったというか、楽しくなって行ったっけ。
失敗をくりかえすたびに大将から指導され、そのうちにだんだんと早くなり上手になっていったからだ。今から思えば、なれない仕事で大変だったに違いないのだが、なぜか自分でもよく判らないが、そのとき辛いと思った記憶がまったくないんだ。そのうちにいつのまにかボクは、野菜切り全体が任せられるようになっていったっけ。
それまでボクは自分についてほとんど考えたことはなかった。
メガネを掛け太っていてスポーツはほとんど苦手だったが、だからといって生活していくうえで困ったことはなかったからだ。勉強も得意でなかったが、両親に厳しく言われたこともなければ、成績もそれほど悪いわけでもなかったので、進学でそれほど悩むこともなかったからだ。
それに特別に才能があったり目立ったわけでもなく、学校でイジめられたこともなかったからだ。
オタクのようになにか特別に好きなものがあったわけでもなく、世間で流行っているものには人並みに興味を示すといった程度のものだった。友達の必要性をそれほど感じたこともなかったので、高校のときにはほとんどいなかった。もちろんクラブ活動もやっていなかった。
でも、それほど孤独感は感じなかった。そのおかげで人間関係で悩んだり、トラブルに巻き込まれたりすることはほとんどなかった。
かといって、ヒキコモリが自分に合っているとも思っていない。適当に家にいて適当に外に出た。
それだからなのか、いま思うと、それまでは自分は、どういう性格をしていて、どういうことが自分に合っているのかもほとんど判らなかった。そして自分が怠け者なのか、それとも頑張り屋なのかも。それに自分勝手な人間なのか、それとも思いやりのある人間なのかも判らなかったのだ。
でも、本当の原因は、家庭っていうか、両親にあるような気がする。
人並みに平凡で人並みに仕事が大好きな両親にはボクはなんの不満はないのだが、もう少し人並みにって言うか、真剣に勉強や将来のことについて言ってくれたら、もう少しシャキッとした人間になっていたのかもしれない。
ようするに真面目だが子供には無関心な平和ボケしたような両親の元で、これといって衣食住に困ることなく育てられてきたので、余計なことを考えなくても生きてこれたと、いったほうが良いかも知れない。それで自分がどういう人間かも、将来自分が何になりたいかも考える必要がまったくなかったことのようだ。
それからしばらくしてボクが野菜切りに自信が持てるようになっていたころ、料理長が同期の五人を集めて次のように言った。
「来週の休みの次の日に、この店の売りであるチャーハンの特別実習、ていうか、テストだな、それを行うから、心の準備をしておくように。これは全員だ。オマエもだぞ。今日から先輩たちのやることをよく見ていて、出来るようになっているように。料理は盗んで覚えるように。」
料理長は最後はボクのほうを見て言ったので、それはボクも料理を作れるようになれということだと判った。はっきり言ってボクは驚いた。玉子を割ったこともないボクが、チャーハンなど作れるわけないと。そしてなんてムチャクチャなこと言うんだろうと少しだけ反発を覚えた。
でもどうしたらいいんだろう、できるわけないだろう、あと三日しかないのに、と悩み始めた。
それはたぶん、せっかくの料理長の期待になんとか応えたいと思い始めたから違いない。
それで、そのときからボクは、自分の仕事を続けながら、その料理テストの日に備えて、その手順や調味料の量を覚えるために、チャーハンを作る先輩たちの様子を注意して見るようになった。そして記憶したことをこっそりとメモしておいた。
テストの前の日は店は休みだったのでボクは家にいた。そしてメモに目をやりながら、はたしてボクに出来るんだろうかと、ちょっと不安な気持ちでぼんやりとしていた。ところがふと思いついた。せっかくレシピーがあるんだから、今、家で練習してみようと。ラッキーなことに父も母も仕事でいなかったのだから、ちょうど都合がよかった。
ボクはさっそく調味料や材料を用意して、メモの手順通りに作り始めた。最初はもちろん失敗だった。店で食べるのと雲泥の差があった。絶望的な気持ちになった。でも最初は、こんなもんだろうと半分やけ気味に開き直ってまた作り始めた。もちろんまたうまく行かなかった。油ぽくって食べられたものではなかった。そこでボクはその点に注意をしてまた挑戦した。でも今度は他のことで失敗した。その後もベチャベチャしていたり、塊が出来てたり、焦げ臭かったり、味が濃かったりと、新たな問題がやるたびに出た。
そんな失敗と修正を何度かくり返したころ、ボクは絶望的な気持ちになり、それ以上作ることを止めてしまったっけ。どうしても店の味には程遠かったからだ。でも、しばらくするとボクは、どうしても諦めることができずに、その原因を考え始めていたっけ。
だが、その結果は、
「手順どおりにやっているのにどうして失敗するんだろう。」
と思うだけだった。
「やっぱりオレには無理なんだろうか。」
と、本当に諦めかけていると、ふと、あることに気がついた。時間の掛け過ぎだと。ボクは先輩たちより三倍ぐらいかけていることに。
そこでボクはできるだけ素早く作るようにした。そして、確かに時間は短縮した。でも、それほどできばえが良くなっているとは思えなかった。そしてボクは、いまボクに出来ることは、このぐらいだろうと認めるしなかったっけ。
そのボクは何度か練習をした。そしてそれほど上達したとは思えなかったが、そのおかげで判ったこともあった。味付けを忘れたからといって、食べるときに塩を掛ければ良いと言うものではないことや、鍋に入れた油は出来るだけ温めたほうが良いこと。それにご飯は熱過ぎても、また冷た過ぎてもいけないということに。
翌日は、朝早くにみんなが集まり、店を開ける前にテストが行われることになった。
そしてボクは自分の実力が判っていたので動揺することもなければ気負うこともなくテストに臨むことが出来るはずだったのだが、ところが、ボクは普段のように厨房に入ってあるとんでもないことに気がついた。それはボクの家のガスコンロと店のガスコンロは火力が何倍も違うということだった。ボクは、せっかく良い所を見せようとして練習までしてきたのに、これじゃ何の役にも立たないじゃないか、これでは、絶対に失敗すると思うと、ものすごくがっかりした。
でも、すぐに何の心配もないことがわかった。それは、それは火力の強いガスコンロは四台しかなく、そこで、どういう訳か、たぶんボクがまったくの未経験者だからなのだろうけど、ボクが、携帯用のコンロで料理をすることになった。
もしかしたらそれは、ボクにとってものすごくラッキーなことかもしれなかったが、でもよく判らない。
五人いっせいに料理が始まり、ボクのチャーハンが皆のより少し遅れて出来上がった。そしてそれらはテーブルに並べられ、対象や料理長、そして他の従業員で試食が行われ、評価された。
ボクは、絶対に最下位かなと思っていたが、意外と評判がよく、料理学校の卒業生を抜いて三位に入った。確かそのとき、料理長はこういって褒めてくれたっけ
。
「いや、意外といいね、香りの出し方はまだまだだけれど、うん、まあ、しょうがないか、火力が違うからな。ふうん、なかなかやるじゃない。」
って。そのとき皆がいっせいに驚いたような顔をしてボクのほうを見たような気がした。たぶん、みんなはボクが料理が出来るなんて信じられなかったのだろう。
本来なら、そんな皆の態度はボクの自尊心を傷つけるものだったろう。でも、それよりはボクは、料理長から褒められて喜びが体全体から沸き起こってくるのを感じていた。
人から褒められることがこんなにも嬉しいことだとは思わなかった。そういえばボクが他人から褒められたのはあのときが生まれて初めてかもしれない。
それだからなのだ。
あの日からボクは、それほど肩身の狭さを感じなくなっただけでなく、失敗することも以前ほど恥ずかしいことだと思わなくなり、今まで出来なかったことに自分から進んで挑戦するのがほんとに楽しく感じるようになったっけ。
それから数日後、二人の料理学校卒業生が突然来なくなった。その理由は判らなかった。というより、ボクは彼らにあまり良い印象を持っていなかったので、彼らがどうなろうと関心なく、その理由を知ろうと思わなかったのが本音のようだ。
その後ボクは、少しづつではあるが何度も失敗を繰り返しながらも、仕込みや色んな料理作りにが関われるようになっていった。
でも、お客に出せるほど任せられていた訳ではなく、まだまだ先輩たちの補助的な、そして相変わらずの雑用仕事だった。
それにしても不思議だ。どうして両親はボクになんにも言わないのだろう。
ボクが将来どうなろうと関心がないのだろうか。
普通よその親だったら子供に期待したり、子供の将来を心配したりするもんだが。
そもそも他の親のようにはボクに対して愛情がないのだろうか。愛情がなければ心配も期待もしないだろうが。そうも見えない。それとも伸び伸びと自由放任に育てていたのだろうか。二人とも深い考えを持って生きているようには見えないが。よく判らない。
でも、社会では親の愛情が少なかったり、または逆に親が子供に干渉しすぎたりして問題になっているのだから、少しも不満を言うべきことではないのかもしれない。
真面目に仕事をして、裕福でも貧乏でもなく普通に生活しているだけだ。でも、ボクからみるにあまりにも平凡だし、あまりにも変化がなさ過ぎる。
ボクには、両親は地味であるがとにかく生きていければそれで充分と思っている、としか思えない。だから、今まで、家を建てるときに小額の詐欺に会ったくらいで、その後もたいしたトラブルや事件に巻き込まれることもなくやってきたに違いない。
それでいいのかもしれない。ボクは感謝すべきかも。
でも、もう少し期待してくれていたら、ボクは少しは積極的な人間になっていたかもしれない。
だが結局は、そのころのボクにとっては興味あることはとにかく料理しかなかったので、だいぶ遅くはあったが次から次へと料理を覚えるようになっていった。そしていつかは両親を店に招待してご馳走したいと思うようになっていた。それが大きな励みにもなっていたから。
その頃になってボクは、周りからシンゾウと名前で呼ばれるようになった、そしてボクも他の人を名前で呼べるようになった。つまりそれはボクがようやく一人前として認められ始めたということのようだった。同期の料理経験者の二人とも料理のことでなんとか話が出来るようになった。それまではまったく無視されたような感じだったのだが。二人ともボクより十歳ぐらい上で、独身で、千さんと友さんといった。千さんは、料理長を除いて他の誰よりも調理が早かったが、ボクが失敗したりすると不機嫌な顔になり何も言わなくなるので、ボクはなんとなく話しづらかった。その点では、友さんは感情を顔に出してハッキリ指摘するので、ちょっと怖いところもあったが、むしろその方がボクにとっては気が楽で、ほとんど苦手な感じはしなかった。それで友さんとは料理以外でもよく話をするようになった。そんなあるとき、友さんが、ボクの皿洗いを手伝いながら話しかけてきた。
「シンゾウは頑張るね。」
「普通ですよ。」
「言われたことはなんでも、ハイ、ハイってやるからね。えらいな。」
「いえ、ボクにはその位しか出来ませんから。」
「少しも嫌だとは思わないんだ。」
「はい。」
「どうしてそんな頑張れるんだろう。」
「判らないです。」
「大物だな。」
「まさか、そんなことは、まだ、なんにもわからないですから。」
「初めて見たときはすぐ逃げ出すと思ったんだけどね。人は見かけによらないもんだね。どう将来はコックになるの。」
「いや、まだわからないです。覚えも悪いし、仕事も遅いし、、、、」
「まあ、早けりゃいいってもんじゃないけどね。給料、どの位もらっているの。」
「いや、ほとんど、修業の身ですから。ボクはまかない食が食べられればそれで十分ですよ。」
「千が俺よりも給料が高いの知っている。」
「いえ。」
「入ったのも同じ、仕事内容もそんなに違うとは思わないんだけどな、でも違うんだよな。確かに奴は早いよ。でも、俺から言わせりゃあ、教科書通りって言う感じもするけどな。休みの日はどこで遊んでるの。」
「いや、あんまり遊ばないです。」
「修行も大切だけど、男なら、若いとき多少は遊んだほうが良いよ。大丈夫だよ。シンゾウは名コックになれるよ。いいか、とにかく腕を上げろよ。腕さえよければ、どこでも高い給料で雇ってくれるから。」
たぶんともさんはボクを褒めているんだろうけど、でもそんなことは遠い遠い未来のことにように思うだけだった。
その後ボクは、なんとか餃子やシュウマイが作れるようになった。そしてそれまで友さんが受け持っていた賄い食としてのチャーハンを任せられるようになった。最初はことごとく失敗し、毎日のように注意をされ、指摘を受けた。油の入れすぎ、火力の弱すぎ、香りが出てない、時間の掛けすぎ、などなどと。結局みんなから合格点をもらうまで、三ヶ月かかったけ。
それからしばらくして、友さんが休みがちになり、そして来なくなった。それは気がつくと知らぬ間に居なくなっていたという感じだった。理由らしい理由としては、お客係の女性たちが、今度自分の店を始めるために辞めるらしい、と話していたのを聞いただけで。たぶんそのころのボクは、ようやく自分の作ったチャーハンがお客に出せるようになっていたので、絶対に失敗してはいけないと、そのことだけに掛かりきりだったからだろう。
ボクは覚えも悪く、遅かった。先輩たちと比べてもそれはハッキリしていた。とくに千さんの手際のよさに追いつくにはどんなに努力しても不可能のように思われた。そのたびに自分の不器用さを思い知らされるのだったが、でも、他の仕事に移ろうというような気持ちにはならなかった。いつかは自分も出来るようになるだろうという淡い希望にすがりながら、不思議とへこたれることなく修行を続けることが出来た。そして時間を掛けながらスープ作りから調味料作りまで、基本的なことを身に付けて行った。そんなボクを見て、先輩たちはよく「ナットク君。」とか、「オマエは不器用裕福だな。」とか「オマエは鈍間なスッポンみたいだな。」と笑いながら話しかけてくれるほどだった。「ナットク君。」とは、ボクが何でも納得するまでやり続けるということを言ってるみたいだが、「オマエは不器用裕福だな。」と「オマエは鈍間なスッポンみたいだな。」については、ボクはその意味がよく判らなかった。でも、決してバカにされているようには感じなかった。
やがてボクは賄い食として、マーボー豆腐もレパートリーとして加えることになった。周囲の予想したとおり、最初は失敗の連続であった。でも三ヵ月後には、すべての人から合格点をもらえるまでになっていた。
その後のボクは、それまでと変わりなく、すべての雑用から賄い食を受け持ちながら、自分なりに忙しく動きまわっていた。
それでもまだ、ボクがお客に出すことを許されていたのは、餃子とチャーハンと簡単なラーメンだけだった。
そんなある日、店で地元商工会の食事会が行われた。人数は五十名ほどだった。短いあいだにたくさんの料理を出さなければいけなかったので、なかなか間に合わず、ボクは千さんのマーボー豆腐つくりを手伝った。食事会が無事終了し、みんなで後片付けをしているとき、料理長が、ボクのところにきて言った。
「豆腐を塩ゆでしなかったろう。味がしみていなかったよ。忙しいからといって、絶対に手を抜いてはいけないよ。」
ボクは思い出すようにゆっくりと答えた。
「いや、茹でましたけど、、、、」
「そうか、水っぽくってな。それから、仕上げにちゃんと火を入れるの忘れなかった。とろみがなくなっていたよ。」
「いや、それもちゃんとやりました、、、、」
「そうか、変だな。気のせいだったのかな。」
料理長のその言葉にみんなは手を休めて聞いていたが、すぐもとのあわただしさに戻った。ボクも、単なる料理長も思い違いじゃないかと思ったので、ほとんど気にならなかった。
それはたぶん何の疚しさも感じなかったからであろう。豆腐を塩ゆですることも、仕上げとして水溶き片栗粉を入れたとき強めに火を入れることも、三ヶ月かけて完璧にその作りかたを覚える間に、大将がひそかに教えてくれたものである。ボクは、確かに覚えが悪く調理も遅い、でも時間をかけて身につけたことを忘れたり、時間がないからといって、手を抜いたりすることは絶対にないと言える自信があるからだ。というより、手を抜いたりするのは器用な人間にしか出来ないような気がするからだ。それから手順を忘れることも考えられない。なぜなら、ボクには料理の手順を覚えているという自覚がないからだ。
よく家族にチャーハンをおいしく作るコツを教えてと言われても、すごく途惑ってしまう。完成するまでに何度も失敗に失敗を繰り返したことは覚えているが、いざその作る手順を思い浮かべようとするとなんにも浮かんでこないからだ。そこでなんとなく面倒くさく感じて、ボクが作っているのを見れば判るよと、いつも答えるだけだったから。ボクは本当に不器用なようだ。
千さんが辞めて行ったときのことはよく覚えていない。だから、今でもその理由は判らない。よその店ではよく従業員同士でトラブルがあるらしいが、ボクはいまだに見たことはないから、そんなことが原因でもなさそうだ。
千さんはボクと違って、痩せて格好よく、不得意なものがないくらいに手際よくなんでも出来たので、皆からは頼られる存在だった。それでボクはきっと次の料理長になる人だなとずっと思っていたぐらいだ。
でも正直言って、ボクはちょっと近づきがたかったので、ほとんど話したことがなかったけど。
たぶんあれほど仕事が出来た千さんが辞めて行ったのには、ボクなどには計り知れないような理由があったとしか思えない。それに、そのころはボクは自分のことで、いっぱいいっぱいだったのだろう。とにかく料理を作ることがとても楽しくなっていたから、そんなことを気にする余裕がなかったのだろう。
そして今日久しぶりに新しく人が入ってきた。久しぶりと思ったのは、ボクが入ってきてから、まだ誰も後輩が入ってきていないから。いや正確に言うと、入ってきても残っていなかったと言うべきかも知らない。実際にボクの後にも何人かは入ってきた。でもみんな人それぞれの理由で辞めていった。その理由に最初の頃は気になっていたが、今はもう気になっていない。それだけじゃない、新しく入ってくる人が経験者であるかないかも、いまはもう気にならなくなっている。おそらくボクはいま修行していることが楽しくてしょうがないのだろう。
それよりも今日とんでもないことに気がついた。新人が掃除をしたり皿洗いをやっているときに、そのぎこちない仕草や振る舞いから、まだ料理のことが、かつてのボクのようになんにも知らないことが判ったのだ。
そしてボクは衝撃を受けたように、あることを悟った。あのときも、ボクがどんなに取り繕うが、大将に、そしてみんなにも、ボクがまったくのど素人であることが。だからボクが二日目から皿洗いを負かされるようになったのだ。
これは技を見抜くことが出来る大将のの配慮だったのだ。大将にはすべてが判っていたのだ。判っていてボクを指導してくれたのだ。
ボクが見抜くことが出来るようになったのは経験によるものだ。わずか数年でこれほどのことが判るなら、ボクよりも何倍も経験のある大将には計り知れない力があるに違いない。大将は達人なのだ。大将こそ本当の料理の達人だ。
ボクがここまでこれたのは本当にみんなのおかげだ。本当にラッキーだった。よく不器用で覚えの悪いものは先輩たちに苛められたりすることが、他の店では良くあるというのを聞くが、この店にいそんな先輩たちは居なかった。みんな親切だった。意地悪そうな顔をしてボクに話しかけてくるのをほとんど見たことはなかった。いつも不思議なほど笑顔だった。ときには、面白いことを言ってないのに、笑われることもあった。それも従業員のほとんどの人に。だから真剣に相手にされていないように感じるときもあったが、でも決して悪い気はしなかった。
大将が、
「この仕事が任せられるようになるには、普通は六七年掛かるが、シンゾウははその倍掛かるだろうな。」
と笑顔で言うときも、ボクは決して自分の才能のなさにがっかりすることはなかった。むしろそれは
「ボクもみんなのように料理人になれるんだ。」
と思わせて希望の光のようにボクを励ましてくれるものだった。だから冗談にもみんなが、
「よう、未来の達人。」
とかって言ってくれると、ボクは本当に嬉しくなって、どんな仕事でも苦にならなくなる。
ボクはようやく自分がどういう人間であるか判りかけて来た。たとえば、周囲が思うほどには、無気力でもボォッともしていないこと。人並みに忍耐力もあり、好奇心も旺盛であるということ、どんな些細なことでも納得するまでやり続けるということ、それから、、、、
いやそんなことはもうどうでも良いのだ。とにかく今は、もっともっと修行をして、早く大将や料理長のように何でも出来るようになりたい。